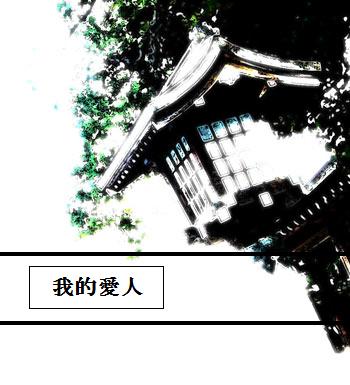
我的愛人 ─顕㺭和婉容─
男装の麗人・川島芳子と悲劇の皇后・婉容の出逢いと別れ。
シリアス歴史ストーリー。ほんのりGLです。
単発で読んでもお楽しみいただけますが、今後連載予定のタイトル同一連作「─我的愛人─」「─何日君再来─」「涙あれども語り得ず」も併せてお読みいただくとさらに楽しめます。
日中戦争・満洲国を背景に妄想全開で突っ走りたいと思います。
タイトル「我的愛人」は「私の愛する人・最愛の人」、サブタイトル「顕㺭和婉容」は「顕㺭と婉容」という意味です。
この話は完全にフィクションです。
登場する人物・関係性・建造物などは実在のものとは一切関係がありません。すべては作者の想像・妄想の産物となります。ご了承ください。
序 章
満州国
1932年から1945年の間、満州(現在の中国東北部)に存在した国家。帝政移行後は「大満州帝国(大滿洲帝國)」或いは「満州帝国」などとも呼ばれていた。
川島 芳子
清朝の皇族粛親王の第十四王女である。
粛親王の顧問だった川島浪速の養女となり日本で教育を受けた。日本軍の工作員として諜報活動に従事し、第一次上海事変を勃発させたといわれているがその実態は謎に包まれている。
戦後間もなく中華民国政府によって漢奸として逮捕され、銃殺刑となったが、日中双方での根強い人気を反映して現在でも生存説が流布されている。
婉容
清朝及び満州国の皇后。17歳の時、清朝の廃帝宣統帝(愛新覚羅溥儀)に皇后として迎えられた。しかし、夫婦仲は次第に冷めていく。鬱屈した気分を晴らそうとした婉容はアヘンに手を出し、重度の中毒に陥った。
日本の敗戦後、吉林省延吉の監獄内でアヘン中毒の禁断症状と栄養失調のため、孤独の内に死亡したといわれる。
~各wikipediaより~
第一章
辛亥革命によって紫禁城を追われた清朝最後の皇帝、愛新覚羅溥儀とその皇后婉容(ワンロン)が日本の保護の下、日本公使館を経て天津の日本租界にある「張園」からさらに「静園」へと移り住むこととなったのは1929年。
さらにその二年後の1931年9月18日、奉天郊外の柳条湖において、関東軍が南満洲鉄道の線路を中国側の仕業として爆破した事件に端を発した満洲事変が勃発。これが長きに渡る日中戦争の幕開けであった。以後関東軍は中国東北部「満洲」の制圧と侵略を推し進めてゆくが、国際世論の批判を避けるため、満洲全土の領土化ではなく、日本の保護下における独立政権──いわゆる傀儡政権の樹立へと方向転換することとなった。
関東軍奉天特務機関長・土肥原賢二大佐は、「静園」にて軟禁生活を送っていた愛新覚羅溥儀に日本軍への協力を要請。溥儀は満洲民族の国家である清王朝の復興を条件に、新国家の元首となることに同意したのだった。
11月10日、溥儀は天津を脱出し、その後営口を経て旅順へと移り、関東軍の保護の下、約束の地である満洲で着々と機会を窺っていた。
残された婉容は「静園」で落ち着かない日々を過ごしていた。名ばかりの夫たる溥儀が何処に脱出したのか? 自分に対し箝口令が敷かれているのだろう、周囲の者に訊いても知らぬ存ぜぬを繰り返すばかり。孤独はさらに深まり、陰謀と策略の影に怯えながら、身動きが取れずに彼女はただひたすら待つことしかできなかった。不安で押し潰されそうな、それでいて無限に続くかと思われる単調な生活は苦痛以外の何物でもない。日本領事館からも国民党からも秘かに監視を受けている以上、自由を望むなどもってのほか。
何を「待って」いればいいのか? 何時まで「待って」いればいいのか? 問うても帰ってこない答えを虚しく待ち続けて、彼女は無為に日々を送らざるを得なかった。
しかしその籠の鳥の婉容の生活に突然終止符が打たれたのは12月初旬のとある日の夕刻であった。日本の将校が面会に来ていると告げられて、怪訝な表情を浮かべて応接間へ下りて行くと、礼を正して直立不動のまま彼女の出現を待つ一人の人物がそこにいた。
上背のある均整のとれた体躯に軍服が良く似合う。俯き加減の深く被った軍帽から覗く白い顎、引き締まった頬。それらが匂い立つような若さを感じさせる。そしてその涼やかな唇から零れる流暢な北京官話の低い声に、婉容は思わずうっとりと聞き惚れた。
「慕鴻(ムーホン)皇后陛下にはご機嫌麗しく存じます。関東軍の命により、貴方様を宣統帝の許へお連れすべく本日参上致しました」
将校はゆっくりと顔を上げると双眸を真っ直ぐ婉容に据える。
切れ長の眼光鋭いそれはきつく婉容の視線を捕え離さない。対する婉容も、その煌めきを潜ませた大きな黒瞳で臆することなくそれをしかと受けとめる。二人のぶつかり合う視線は虚空で火花が散ったように閃き、もつれ、そして引き寄せ合うように絡み合う。そしてその固く絡まった視線の結び目をなかなか解くことが出来ずに、互いに見つめ合ったまま時が流れた。
「金璧輝、命を賭けて皇后陛下を護衛致します」
「中国人なのね」
驚く婉容に、璧輝は静かに頷いた。
「清朝復辟(ふくへき)という大義の為に今は関東軍の下で活動しております。本日皇后陛下をお迎えに上がったのも、すべてはその為」
復辟とは退位した君主が再び位に就くことである。清朝復辟とはすなわち清朝の再興との意だ。
満洲事変以降から、婉容の身辺でうっすらとかかった靄のように囁かれてきたこの清朝復辟という言葉。ここ「静園」にせわしなく出入りするあまたの日本の将校。それらが溥儀が脱出したことと何かしら関係があろうことは、婉容もいくらかは察知していた。けれどその言葉を彼女が具体的に現実として体感したのは、この時が初めてであった。
「そんなまた突然に……どうしても今日出立しなければいけないのかしら?」
「そうです。事態は急を要しております。そして宣統帝も皇后陛下の一刻も早い御到着を望んでおられます」
「一体これから何が起ころうとしているの?」
「それはまだ申し上げられません」
聞き飽きた言葉に苛立ちがこみ上げてくる。
「では、貴方が国民党の密偵ではないという証拠は? 皇上の名をかたって私を拉致するという可能性だってあり得るはずよ」
婉容の大きな瞳が探るように相手を睨む。
「全くもって仰せの通りでございます」
璧輝は彼女の予想外の返答に少なからず面食らった様子で暫く押し黙ったままでいた。するとおもむろに軍服の懐から不気味に黒光りする小型の回転式拳銃を差し出した。
「では、もし皇后陛下が私の行動に少しでも不審をお感じになったのなら容赦なくそれをお使い下さい」
今度は婉容が絶句する番であった。
受けとめる両手が小刻みに震えている。小型ながらずっしりと重い、初めて触れる拳銃に婉容は畏怖の念を抱いた。
「使い方が分からないわ」
「簡単です。引き金に指を掛けて……」
婉容は恐る恐る拳銃を握りしめ、人さし指を引き金に掛けた。
「そのまま狙いを定めて……」
そう言って璧輝は拳銃の銃口を掴んで、自分の左胸にぐっと押し当てた。
「そして引き金を引いて下さい。ダブルアクションなので操作は容易ですが、力一杯引き金を引かないと弾が発射されないのでご承知おき下さい」
「わかったわ」
婉容は力が抜けたようにだらりと拳銃を持つ手を下ろした。
「どうかご安心を。私は皇后陛下を裏切るような事は決していたしません」
「それはまだわからないことよ。貴方は私の問いに答えてくれないばかりか、初対面の……日本人なのか、本当に中国人なのか分からない、見知らぬ人物を到底信じるわけにはいかないわ。そうでしょう?」
「ごもっともであります。けれど今から私の命は皇后陛下の掌中にありますゆえ、どうか早くお支度を」
「では何処へ行くのかだけでも教えて頂きたいわ」
璧輝はほんの数秒躊躇った後に言葉を繋いだ。
「私は大連までお供させて頂きます」
「大連? 満洲の地へ?」
璧輝は頷いた。
第二章
まだ日付の変わらないその日の夜更け、璧輝の運転する車が音も無く滑るように埠頭に到着した。先に素早く車から降りて婉容の為にドアを開ける。夜の冷たい外気が無数の矢となって容赦なくその青白い頬を突き刺してゆく。婉容は帽子を目深に被り、オーバーコートのファーに顔を埋めた。震えが止まらないのは寒さのせいだけではない。着のみ着のまま、手にした荷物はハンドバック唯一つ。それを固く握りしめて、彼女は前を行く璧輝の防寒外套を纏った後姿をじっと見つめながら無言でついてゆく。
するとその璧輝の前方に同じく外套姿の三人の日本兵が、まるで亡霊のように闇から浮かび上がった。そのうちの一人は璧輝から車のキーを受け取ると、そのまま二人が乗ってきた車に乗り込んで、来た道を速やかに引き返していった。
「手筈は?」声を潜めて璧輝が問う。
「すべて整っております」
残された二人はおそらく護衛なのだろう、踵を返すとやはり無言で歩き始めた。
埠頭は墨をこぼしたような深い闇にすっぽりと覆われて、海と陸の判別がつかないほどだ。気の遠くなるような、重くずっしりとのしかかる静寂。それがよけいに神経を張り詰めさせる。無機質な靴音が敷き詰められた石だたみに打ち付けられ跳ね返り、さらに大きく埠頭に響き渡る。緊迫した空気の中、暫く歩くと明かりを消した一艘の小型の汽船が闇から不気味に姿を現した。全員無言で素早くそれに乗り込むと、すぐに船は岸壁を離れ、同時に船室内に灯りが点いた。
狭い船室に押し込められた婉容はまんじりともせずに中を見廻して、すぐにそれが旅客船ではなく輸送船であることに気づいた。ドアの両側には二人の日本兵が立ち、辺りには薄汚れたいくつかの土嚢と壊れかけた木箱の残骸が散乱していた。
「ご不自由でしょうが、暫くの辛抱です。どうぞおかけ下さい」
婉容は璧輝に促され備え付けの椅子に腰かけた。
丸い小さな窓を覗くとおそらくあれが陸地の外郭であろう、縁取られた細かな星のような幾つもの街の明かりがゆっくりと遠ざかってゆく。
押しつぶされそうな恐怖と僅かな好奇心とが入り混じった、複雑なこの気持ちを、確か以前にも味わったことがある。それは間違い無く、全くあの時と同じだった。
まだ自分が少女の頃、前時代の遺物とも言うべき清王朝という未知の世界へ、顔さえ見たことの無い皇帝溥儀の許へと輿入れした、あの時と同じ気持ちを今また味わっているのだ。
婉容は相変わらず漆黒の外界をぼんやりと眺めている。
自分の人生はまるでこの古びた船のようだと、今更ながらつくづく思う。自らの意思とは遠くかけ離れた所で、運命という暗く広大な海の上を、当ても無く人に操られながら彷徨っている。
きっと天津には二度と戻ることはないだろう。自分の生れ育った懐かしい街。紫禁城を追われ、皇后という身分を忘れ、自由な束の間の幸せな時間を過ごした街に二度と決して戻ることは無い。そんな哀しい確信が、紙に滲む漆黒のインクのように胸の奥にじわじわと滲みてゆく。
一体自分は何処に行き着くことになるのだろう。
今となっては何故か総てが遠い昔の事のように思われて、次第に離れ行く陸地を、婉容は名残惜しむかのようにいつまでも食い入るように見つめていた。
「ご心配には及びません。皇后陛下が向かわれている満洲の地もきっとお気に召すはずです」
まるで心を見透かしたように、隣に座っている璧輝が静かに声をかけた。婉容は驚いて璧輝を見つめた。そして投げかけられた璧輝の言葉に何も応えぬまま無言で冷ややかな一瞥だけを投げると、視線を再び窓の外へと戻した。
沈黙という重い荷を乗せたまま、どのくらい船は進んだろうか。突然岸の方から停船を迫る中国語の怒鳴り声が聞こえた。
璧輝は素早く席を離れ、ドアの両側に立っていた日本兵と血相を変えて何やら早口の日本語で話し始めた。すると二人の日本兵は慌てて甲板へと飛び出してゆく。三人の話の内容は分からなかったけれど、その状況、慌て具合、緊迫した表情からしてここは中国軍の勢力下なのだろうと婉容は理解した。
冷たい窓に顔を当てて見ると、船は速度を落として岸壁に近づいて行ったかと思うと同時に灯りが消え、突然岸から激しい銃声が轟いた。
第三章
婉容の身体に戦慄が走る。ここで中国軍に捕らえられたら一体どうなってしまうのだろう? 不安と恐怖が突然心臓を鷲掴みにする。そして追い打ちをかけるように、船上からも応戦の銃声が立て続けにわき起こる。刹那、船体がバランスを崩して大きくぐらりと揺れ、婉容の身体は椅子から勢いよく投げ出されてしまった。
「皇后陛下!」
床に叩きつけられる! そう思って固く瞳を閉じた瞬間、その身体は璧輝にしっかりと抱きとめられた。
暗闇の中鳴りやまぬ銃声、飛び交う怒号。
婉容の身体は小刻みに震え、ぐっと璧輝の胸に顔を埋める。
「捕まってしまうの?」
心臓が押し潰されそうなほどの激しい動悸に息が苦しく、喘ぎながら問いかける。それに応えるかのように、恐怖に慄く婉容を抱き締める璧輝の両腕にさらに力がこもる。
「そんなことはありません。ご心配なさらずに」
優しい声音が、頬に降りかかる吐息が、外套から伝わるぬくもりが婉容に軽い眩暈を起こさせる。早鐘のように打つ胸の鼓動は決して恐怖だけのものではない。暗闇の中、固く抱き合ったまま恐怖と甘美が入り混じったような切ない陶酔の時間がどれくらい経ったのだろう? 突如機関がうなりをあげ、船は猛スピードで岸から離れてゆく。遠ざかる銃声と怒号。再び訪れる静寂。船は中国軍をかろうじて振り切ったらしい。船室内に灯りが点き、婉容は漸く瞳を開けた。
「もう大丈夫です」
耳元で囁く声にはっと我に返った婉容がゆっくりと顔を上げると、そこには自分を心配そうに覗き込む璧輝の優しい眼差しがあった。間近で見るそのきめ細やかな白い肌、微かに憂いを潜ませ、それでいて涼やかな目元は溥儀とはまるで違う。この世には男性でもこんなに美しい人がいるのかと、婉容は心の中で息を飲んだ。
「お怪我はありませんか?」
形の良い唇から洩れた低い声に彼女は咄嗟に俯いて無言で首を横に振る。すると璧輝は優しく婉容を抱き起こして再び椅子に座らせた。
「驚かせてしまいましたね。皇后陛下はお疲れです。どうかしばらくの間お休み下さい」
そう言うと璧輝は自分の外套を脱いでそっと婉容に掛けてやった。ふわりと鼻孔をくすぐる璧輝の香り。
頬が赤く染まってゆくのが悟られないだろうか? この胸の高鳴りが聞こえてしまわないだろうか?
必死に平静を保とうと婉容は再び窓の外に視線を移した。外は陸も海も空も境界の無い一面の闇の世界。未だ頬に残る璧輝の吐息の感触を感じながら、婉容はいつの間にか心地よい眠りへと落ちていった。
汽船の大きな揺れにぎくりとして目を覚ました。気が張っていたのだろう眠りは浅く、その揺れにまたも中国軍との銃撃戦かと思ったのだ。
「お目覚めですか? ちょうど良かった。もうすぐ大連です」
不安はその一言であっさりと取り払われた。船内はかなり冷え込んでいて、オーバーコートの上に外套を掛けられてもなお、うすら寒い。一晩中軍服でいた璧輝はもっと寒いだろうと、婉容は外套を脱ぐと「ありがとう」と低く呟いて璧輝に差し出した。
「下船したら外はもっと冷え込みます」
璧輝はそう言って今度は婉容の肩にすっぽりとそれを羽織らせた。
「でも貴方が……」
「心配ご無用。さあ、到着です」
璧輝に手を引かれ、甲板に上がる。待ち構えていた二人の日本兵が璧輝と婉容の後に続く。夜はすっかり明け、空を厚く覆う灰色の雲の切れ間からほんの微かな陽光が降り注ぎ、べたつく冷たい海風がまるでよそ者を嘲笑うかのように容赦なく
吹きすさぶ。婉容は唯一の荷物であるハンドバックを縋るように片手で抱きかかえた。
──これが満洲の玄関と謳われた大連なのね……。
埠頭にはあまたの大型船が停泊していた。立ち並ぶ倉庫群、何台かのクレーンがその鋼鉄の長い首をせわしなく動かして船からの積荷を移動させている。正午近く、汽船は活気づいた埠頭へゆっくりと船体を近づけてゆく。
完全に中国の支配権を離れた日本の租借地、大連。どんよりと重く気の滅入るようなくすんだ都市。それが今日生まれて初めて足を踏み入れる、この地に対する婉容の第一印象であった。
「出迎えが来ております」
そう呟く璧輝の視線の先を追うと、岸壁に佇む日本兵五・六人の人影が見えた。
「中央の小柄な男が元憲兵大尉の甘粕正彦。ここから先は彼が皇后陛下をお護りいたします」
一際異彩を放つ丸眼鏡をかけた人物が、後ろ手を組んでこちらを凝視している。
「では貴方とはここで……」
「お別れです」
汽船は小さく揺れて埠頭に着岸した。
「お足もとにお気をつけ下さい」
そう言って再度差し延べられた白い手袋をはめた璧輝の手。婉容は躊躇う事無くその掌を固く握りしめた。
「川島、御苦労だった」
陸で迎える甘粕とその部下達。後方にはエンジンのかかったままの車が二台控えている。
「皇后陛下、長旅でさぞお疲れでしょう。この先は私甘粕正彦がお供させて頂きます」
小柄な体型とは裏腹に、全身から滲み出る強烈な威圧感。流暢な中国語を駆使して律儀に頭を下げる彼の、自分に対して投げられた一瞥に、僅かな睥睨を含んでいるのを婉容は見逃さなかった。彼女は甘粕の挨拶に応えること無く、璧輝に手を引かれ押し黙ったまま下船した。
そして婉容はいよいよ大連の地へと一歩足を踏み入れた。
「動くな」
甘粕率いる部下の中の一人が凄んだ中国語と共に、おもむろに頭を上げた甘粕の後頭部にぴたりと銃口を当てていた。
「武器を捨てろ! さもないとこの男の命は無いぞ!」
そしてもう一人の部下が他の日本兵に向けて銃を構えて威嚇する。
国民党の密偵が二人も自分の配下に紛れていたこと、それに全く気付かなかった自分の迂闊さに、甘粕はうろたえ、そして苦々しく臍を噛んだ。
「早く皇后を連れて逃げろ!」
叫ぶ甘粕。
「お前達日本人が満洲で何を企んでいるのか知らんが……そこの女、慕鴻皇后を渡してもらおうか」
男は尚も甘粕の後頭部に銃口をぐいぐいと押しつける。
「溥儀もお前達の手に渡った。そして今度はその女。旧清朝の廃帝と皇后を拉致して一体何をしようといている?」
「やかましい! この支那人め!」
一人の日本兵が腰から軍刀を引き抜き、甘粕に銃を向けている男の背後から勢いよく振りかかった。が、気配を感じて振り返った男の銃口から容赦なく銃弾が発射され、日本兵は呻き声一つ立てず即座に地面に沈む。その隙に甘粕は男から逃れ、素早く自分の拳銃を抜き、そして野太い声で璧輝に向かって叫んだ。
「あの車でヤマトホテルへ行け!」
「走ります」
璧輝は乱暴に婉容の手首を掴むと全速力で走り出した。銃口は執拗に二人を狙い、甘粕はその後を追いかける。
「どうかあと少し頑張って下さい。あの車まで……あれに乗るまでもう少し……!」
分かっている。分かっているけれども息が苦しく足がもつれ、とても璧輝に追い付けない。首を横に振りながら婉容はあえなくその場に崩れ落ちた。
「皇后陛下!」
後ろを振り返る璧輝の視界の端に過ったのは、今まさに引き金を引こうとしている男の姿。
そして一発の銃弾が瞬時に空間を切り裂いて、咄嗟に婉容に覆いかぶさった璧輝の肩を、灼熱の激痛と共に鋭く抉っていった。
第四章
「金璧輝!」
自分の身体の上からずるりと滑り落ち、微かな呻き声を上げて地面に崩れた璧輝を見て、婉容の喉の奥から自分でも信じられない程の絶叫が迸り出た。冷たい地面に沈んだ軍服の右肩がじわじわと赤黒く醜く滲みてゆく。
「しっかりして! ごめんなさい……私が走っていれば……転んだりしなければ……貴方がこんなことにならなくて済んだのに!」
璧輝は自分を庇って撃たれたのだ。
婉容は震える手で投げ飛ばされた自分のハンドバックを手繰り寄せる。追手は? あの中国人は? 痙攣の如く全身ががくがくと震え、体内を流れる血液が一滴残らず凍りついてしまったかのように流れを止める。後方であの甘粕が璧輝を撃った男に飛びかかり押さえつけようと必死に乱闘している。しかし彼の銃はあっけなく弾き飛ばされ、それでもかろうじて男を組み敷いているものの、ふいを衝かれて形勢逆転。今度は男が甘粕の上に跨ると、その銃で何度も何度も彼の頭を殴りつけた。
「くたばれ日本人! ここから、満洲から出ていけ!」
甘粕の眼鏡が吹っ飛び、こめかみから出血しているのがここからでも分かる。彼はおそらく失神してしまったのだろう。男は彼が抵抗できないと悟ると銃口をぴたりと左胸に押し当てた。その形相はまるで悪鬼の如く。殺人と暴力の衝動に憑かれた異様な笑みを浮かべて引き金に指をかける。
「皇后陛下……はやく……車へ……!」
腰から軍刀を引き抜いてゆらりと立ち上がった璧輝は、悠然と婉容に背を向けて立ち上がった。
「いやよ! そんな身体で……お願いやめて!」
璧輝の背中に向かって婉容は力の限り叫ぶ。
「甘粕を見捨てるわけにはいきません……だから今のうちに行って下さい、早く!」
強く荒い語気に婉容は思わず怯む。
璧輝の軍刀を構える右手に力がこもる。それと同時に、紅い血液が灰色の地面に滴り落ちた。
銃と軍刀──勝負は火を見るより明らかであった。
璧輝は男に向かって走り出し、甘粕から気を引く為にその身体に向かって斬りつける。案の定、男は璧輝の攻撃を避けるために銃を盾にしてその軍刀の切っ先を受けると、素早く甘粕から離れ、今度は璧輝に襲いかかる。抵抗し、腕に力を込める度に傷口から大量の血液が流れ出る。どちらが上になり下になり、組み敷き組み敷かれ、そしてとうとう男が勝利の笑みを浮かべて璧輝に跨り、手にした軍刀を振り払って、その銃口を憎き眼前の敵の眉間に押しつけた。
「去死!」
璧輝は最期の刻を知って固く眸を閉じた。
そして三度目の銃声が、重く灰色の雲に覆われた大連埠頭に響き渡った。
すべての時が止まったような数秒間。
璧輝はゆっくりと眸を開けた。と同時に男が銃の引き金に指をかけたまま、白眼を剥いてどさりと地に崩れた。
何が起こったのか分からぬまま、璧輝は肩を押さえて身体を起こす。顔を上げたその双眸に飛び込んできたのは、震える両手で自分の渡した拳銃を握り締め、自失呆然と立ちすくむ婉容の姿。
「……まさか貴女が?」
彼女の放った銃弾は男の脳天を見事に撃ち抜き、頭蓋骨と脳味噌を粉砕していった。
「川島! 騒ぎになる前に早く皇后を!」
追いついた別の日本兵の叫び声で我に返った璧輝は慌てて婉容の許に駆け寄る。
「お怪我はありませんか?」
言いながら震える彼女の両手からそっと拳銃を取り上げた。
婉容は璧輝の問いに答えるどころか、ショックのあまり目の焦点が合わず、まるで発作を起したように全身がぶるぶると震えている。璧輝は彼女の足元に落ちている自分の外套を素早く拾い上げ羽織ると、抱きかかえるようにして彼女を車まで連れて助手席へと押し込んだ。素早く運転席に座りハンドルを握って漆黒の車を走らせる。自分達を襲った二人の中国人密偵が既に冷たい亡骸となって、日本兵によって、まるで積荷のように無造作にもう一台の車に押し込まれているのが、走る車窓の片隅に見えた。哀れ、彼等にしても国への忠誠心にかけては自分と同じであろうに。
同じ中国人同士でありながら皇后陛下まで巻き込んで何故こんなことを? 自分の行動は正しいのか? このまま日本人の言いなりになっていいのか?
自問する璧輝に、己に潜むもう一人の自分が答える。
迷うな。すべては清朝復辟のため。その大願の前にあらゆる小事は犠牲にせねばならない。一介の国民党の密偵の命も、そして今隣に座っている何も知らない皇后とて同じ事。彼女の意思にかかわらず、何としてもこの方を満洲国執政夫人に祭り上げなければならない。たとえ今どんなに慙愧の念に苛まれようとも、後の壮大な勝利を思えばこそ、自分は日本人に協力し、関東軍から与えられた任務を遂行しなければならないのだ。
璧輝は青白く血の気の失せた唇を噛み締め、アクセルをさらに踏み込んだ。
車は猛スピードで大連ヤマトホテルを目指してゆく。
第五章
「甘粕の名で部屋が取ってあるはずだが」
フロントでそう告げると貴賓室の鍵を渡された。すべて秘密裏に甘粕が手配したらしく、「最上階は封鎖されております。利用客はございません」と、フロントマンが小声で耳打ちした。
早急に婉容を落ち着かせねばならない、璧輝はフロントマンの案内を断るとホテル内の人ごみをかき分け婉容の手を固く握ってエレベーターに乗り込んだ。
「あの人……どうなったのかしら? 私、人を撃ってしまったのだわ……殺してしまったのだわ……」
俯いてじっとエレベーターの床を見つめたままぶつぶつと呟き続ける婉容。
「あの者は皇后陛下のお命を狙った不逞の輩。撃たれて当然です。どうかもうそのことはお忘れ下さい」
「嫌よ……忘れるなんてそんなことできないわ……いや……お願い、私を天津へ返して! 私は人を撃ったのよ……! 人殺しなのだわ!」
頭を両手で押さえ首を激しく振り、金切り声をあげてがくがくと膝を震わせる。殺人というおよそ耐えがたい衝撃に半狂乱になっているのだった。
無理もないと、璧輝は思う。満洲旗人の家柄に生まれ、天津のフランス租界に育った上流階級の令嬢だったという。既に滅亡した清王朝に輿入れしなければ、今こうやって人を殺めることも無く、もっと違う人生を歩んでいただろうに──。
今にも崩れ落ちそうになる婉容の身体を璧輝は抱きとめ、叫び声を抑えるためにその顔をぐっと自分の外套の胸に押し当てた。
エレベーターが四階に到着し扉が開く。待ち構えていたかのように扉の両脇で守備をしていた二人の日本兵が抜き身の軍刀を向けた。
「甘粕の代わりに来た川島だ。慕鴻皇后陛下をお連れした。部屋に案内しろ」
抱きかかえた婉容が確固たる通行証となったらしい。日本兵は軍刀を下ろすと二人を貴賓室の前まで案内した。
「御苦労。甘粕以外の人間は一切ここに入れるな」
言い捨てて璧輝は室内に入った。
大連一の格式を誇る、ここヤマトホテル。その貴賓室は通常の客室の三倍はあろうか。主寝室・客間・リビングとそれぞれゆとりの広さを設けてあり、バス・トイレも充実した設備を備えていた。璧輝は部屋に鍵をかけると、暴れる婉容をまずリビングのソファに座らせようとした。
「放して! ここにいたくないわ……私は人殺しなの……嫌よ……満洲に来たからこんなことになったのだわ……お願い! 誰か私を天津に連れて行って!」
絶叫し、この華奢な身体のどこからそんな力が出てくるのかと呆れるほど抵抗する婉容。事情を知らない他人が見たらきっと軽い乱闘騒ぎと思うであろう。何とかして落ち着かせようと、彼女を押さえつける腕に力を込めるたび、創口からの出血と痛みはひどくなる。羽織っていた外套は床に滑り落ち、璧輝は貧血でその場に卒倒しそうになるのを気力で必死に持ち堪える。両手にはめていた血で汚れた手袋を取って床に投げつけ、婉容をソファまで引きずるようにして連れてくると、満身の力を込めて彼女を抱き締めた。
「皇后陛下は私の命の恩人でございます!」
掠れた声が確実に婉容の心に届き、璧輝の放ったこの言葉が彼女の自制心をやっと取り戻させた。婉容の興奮は治まり、嘘のようにぴたりと静かになった。
「あの時皇后陛下にお助け頂かなければ……今私はここにいることが……」
けれど最後まで言葉を繋ぐことが出来ずに、力尽きた璧輝は婉容の身体をすり抜け、どさりとソファの上に崩れ落ちた。
「金璧輝!」
必死に持ち堪えていたがその身体はとうに限界を超え、多量の出血のために軍服の上着右半分が鮮血で染まっていた。
「お願いしっかりして……一体どうしたらいいの?」
「バスルームに行ってタオルを……」
「え?」
「止血するので……お手数ですが……皇后陛下……」
「わかったわ、少しお待ちになって」
婉容は慌ててバスルームに駆け込んで、あるだけのタオルを抱えて戻って来た。
「身体を起こせる?」
璧輝は頷くが、どうにも力が入らない。婉容は見かねてその身体に手を掛け、ゆっくりと引き起こした。ソファの背もたれに上体を預けさせ、婉容は背後から血で汚れた軍服とベストを脱がせてやる。
「汚いことをさせて……すみません……」
「こんなときにそんなこと気にしないで。それにしてもすごい出血!」
おそらく発熱しているのだろう、激痛に歪めた蒼白の横顔に玉の汗がびっしりと噴き出ている。婉容はタオルでその汗をかいがいしく拭き、血と汗にまみれたワイシャツを脱がせた瞬間、あっと息を呑んだ。
第六章
「……貴方……女だったの?」
露わにされた背中の線は男のものとはまるで違い、滑らかで柔らかく艶めかしい。白い素肌、細い両肩、乱れた断髪……妖しくも倒錯した魅力を放つ璧輝に婉容は戸惑いを隠せなかった。
「お気づきになりませんでしたか?」
激痛で喘ぐ璧輝の口許が微かに緩んだ。
婉容の心の奥底を見透かしていたようなその笑み。
「……さあ、右手を上げて。痛いかも知れないけれど、我慢してね」
銃弾で抉られ、痛々しい赤黒い無残な創を残している璧輝の右肩を、婉容はまるで心の迷いを吹っ切るように力を込めてタオルで縛りあげた。そして彼女はすかさずきれいなタオルを手にして再びバスルームへ行くと、それを熱い湯で濡らして固く絞り、足早に戻って来て血まみれの璧輝の半身を優しく拭き始めた。
婉容のしなやかな指がそっと背中に触れたとき、璧輝の身体に甘い電流が走った。
「もったいないことを……」
「黙って」
婉容は自分の今のこの行動が信じられなかった。皇后として紫禁城に居住していた時はもちろんのこと、天津にいた時も常に人に傅かれ、自分は人形のように何もせずに、何も考えずに周りの者がすべて事を運んでくれていた。その自分が今は他人の為に自らの意志で動いている。それは彼女が今まで享受したことの無い新鮮な感動であった。
創を負い、それを介抱する。二人の間を阻んでいた警戒という薄い氷の壁は、今少しずつ溶け始めていた。
「私貴方を信じるわ」
「皇后陛下……」
「だって貴方の言葉に嘘は無かったもの。同じ女の身でありながら私を護って下さったもの」
自分の肌を滑る婉容の甘美な手の動きと囁くような声音が最良の治療薬だった。璧輝は酔わされるように痛みを忘れ、夢見るようにいつしか深い眠りへと落ちていった。婉容は璧輝が眠ってしまったのを確認すると、ソファに上体をうつ伏せたまま静かに寝かせ、自分が着ていたオーバーコートを掛けてやった。
「甘粕だ。川島、ここを開けてくれ」
ほっと一息つく暇も無く、聞き覚えのある声がドアの向こうから聞こえた。『アマカス』という日本語だけ理解できた婉容は恐る恐るドアに近づいてゆく。
「医者を連れて来ました。慕鴻皇后どうかここをお開け下さい」
創を負った璧輝の代わりに婉容がこのドアを開けることを甘粕は計算に入れていたのだろう、今度は流暢な中国語で語りかけた。医者と聞いて婉容はすぐさまドアを開けた。
「ありがとうございます。」
軽くおざなりの一礼をすると、額を包帯で巻いた甘粕が一人の年老いた軍医を従えてずかずかと室内に入ってきた。
「川島はどこです?」
新しい丸眼鏡をかけたその表情から自分を睥睨しているのがはっきりと読み取れた。この甘粕という男は「静園」にいた頃出入りしていた沢山の粗野な日本人将校と同じ種類の人間だと、婉容は鋭く感じ取った。丁寧な物言いの裏にあからさまに見え隠れする、日本人絶対の差別意識。
「あちらで今寝ているところよ。早く手当てしてあげて」
婉容が案内するまでもなく、軍医は大きな黒革の鞄を下げて勝手にリビングへと向かった。
「皇后陛下」
甘粕が全身から発する威圧感をさらに増幅させて婉容を見据えた。
「部屋を別に用意してありますので、そちらにお移り頂き、明日の朝大連を出立いたします」
自分の部下に密偵が紛れていたという失態を詫びもせず、何ごとも無かったかのように淡々と用件のみを伝えてくる。
「金璧輝はどうなるの?」
「そのようなことは皇后陛下がご心配なさることではありません」
「私はここから何処へ行くの?」
「とりあえず旅順に行っていただきます。そこで宣統帝と落ち合うことになるでしょう」
「とりあえず……なのね。私が訊いているのはそういうことではないの。最終的に私と皇上はどこに行き着くことになって、どういう役割を貴方がた日本人から承るのかしら?」
婉容の大きな二つの瞳がじっと甘粕を見つめた。彼がどう言い逃れをするのか試すように。
「それも今はお知りになる必要はございません」
子供扱いにも程があると彼女は唇を噛んだ。同じ自分を連れ出すにしても璧輝には最低の礼儀があった。皇后として自分を敬う心が感じられた。だからこそここまでやって来たのだ。けれど眼前にいるこの失礼極まりない日本人はどうだ? 人の意志などをまるで意に介さず、事務的に処理しようとするこの横暴な日本人は?
「嫌です。私貴方と旅順など行きたくありません」
「それは困ります。皇后陛下が最終的にどこに行かれるのかは、宣統帝からお話があるはずです」
自分の言い方が婉容を頑なにさせてしまったかと、甘粕はやんわりと言い方を変えてみる。
「そんな見え透いた嘘をおっしゃっても無駄ですわ。皇上は貴方がた日本人のいいなり。いっそ貴方が私に直接お話してくださったほうが早いのではなくて?」
「皇后陛下、どうしても嫌だというのなら、手荒な真似をしてでも私は陛下を宣統帝の許へお連れしなければなりません」
低く凄んだ声で甘粕は脅しともとれる言葉を吐き、対峙する婉容と甘粕、お互い一歩も引かずに睨み合った。
第七章
「……条件があるの」
しばらくして婉容が呟いた。
「貴方ではなく、金璧輝となら旅順に行くわ」
「それはなりません。川島はあの通り皇后陛下を護衛できる状態ではありません」
「わかっていてよ、そんなこと。ですから、彼女が全快してからの話ですわ。そして、その間私が彼女の面倒を見る。これが条件よ。どうかしら? もし、それも駄目だというのなら……」
婉容は素早くリビングへと走り、窓を開けるとバルコニーへと躍り出た。
「ここから飛び降りてしまうことよ」
皇后然とした凄絶な笑みを浮かべて、後から追ってきた甘粕を振り返った。
「そうすれば貴方が先刻おっしゃったように、『手荒な真似をしてでも皇上の許へ連れて行く』ことはできないわね? さあ、どうするの?」
甘粕の能面のような顔に初めて苦渋の表情が現われた。中国人密偵を拳銃で撃ち殺したこの皇后なら自殺することなど平気でやりかねない、そう彼は思ったのだ。
甘粕は──関東軍はどうしても重要な手持ちの駒を必要としていた。新国家建設に不可欠な二つの駒。一つは溥儀。そしてもう一つはこの婉容。今ここで無用ないざこざを起こしてその駒の一つをフイにするわけにはいかないのだ。
「わかりました。すべて皇后陛下のおっしゃるままに致します」
「そう。わかって頂けて嬉しいわ。それでは彼女の手当が済んだらすぐに出て行って下さらないかしら?」
甘粕は黙って頷いた。そして当座の間必要な物を届けさせるというような事を言い残し、暫くして治療が済んだ軍医と共に ──軍医は婉容に毎日の手当ての仕方を教えて──二人は部屋を後にした。
婉容は即座に鍵をかけた。そしてほっと胸をなでおろすと、軍医がソファでは治療がやりにくいと移動させたのだろう、璧輝の寝ている客間へと急いだ。
──私を庇ってこんなことに……。
顔を反対側に向けたままうつ伏せで熟睡している璧輝を見下ろして、婉容は静かにベッドに腰かけた。
甘粕と渡り合った時の胸の鼓動が今でも鳴りやまない。正直、怖かったのだ。甘粕は、本当に婉容を力ずくで旅順に連れて行きかねない勢いだったから。婉容があんなに強い意志を持って人と対したのはもちろん初めての事であり、あんなハッタリが自らの口から出てきたことに彼女自身が一番驚いていた。
それもこれもすべてはここに安らかに眠っている金璧輝のため。知らぬ間に成長してしまった、自分でも理解し難いこの感情が、婉容をそこまで強くしたのだ。
手が小刻みに震えている。自分でもよくやったと褒めてやりたい。自然と笑みが零れてくるのを抑えられず、婉容は震える手を差し伸べて、安らかに眠る璧輝の乱れた髪を何度も優しく撫でつけた。
第八章
お母様、顕㺭は日本になど行きたくありません!
そんな事を言っては駄目よ。今日からあなたは日本の子、川島芳子となるのだから。
いやだあ! 日本に行くのはいやだあ!
ほらほら、泣いて駄々をこねてはいけません。せっかくの白いリボンが台無しですよ。いい子ね、顕㺭。私の可愛い顕㺭……どうか日本に行っても元気でね……!
母の温かい手がいつまでも泣きじゃくる自分の頭を優しく撫でてくれる。優しくいつまでもいつまでも……。
璧輝はふと目を覚ました。
いつも見るあの夢の、いつも同じ所で目が覚める。とうの昔記憶の彼方に押しやった思い出が夢という形となってふいに現れる。今でも確実に思い出すことができる、あの日の母の涙に濡れた顔と懐かしい手のぬくもり……。
その母の掌が今自分の髪に触れたような気がした。
朦朧とした意識の中、自分が今どういう状況下にいるのか、璧輝は一瞬理解出来ずに必死に記憶を手繰り寄せる。割れるように痛む頭、灼熱の重くてだるい身体。撃たれて、必死に皇后陛下をここに連れてきて、半狂乱になったあの方を鎮めてそして……自分の背中を滑る細い指の優しい感触……。
──そうだ皇后陛下!
慌ててベッドから飛び起きようとしたその時、肩に鋭い激痛が走った。
「駄目よ、じっとしていて」
そんな璧輝を制するように温かい手が背中に触れた。閉じられたカーテンから幾筋もの陽の光が射しこんでいる。浅い眠りだったのかとゆっくりと顔を反対側に向けると、視界に入ってきたのは心配そうに自分を覗きこむ婉容の顔。
「もう大丈夫。お医者様が手当をして下さったわ。お疲れだったのね、貴方ほぼ丸一日眠っていらしたのよ」
「丸一日! その間ずっと皇后陛下がお傍に?」
「そうよ」
「申し訳ございません。私の為に……」
「あらそんなこと当然だわ。だって貴方は私を庇ってこんな大怪我をしたのですもの」
「甘粕は?」
「来たけれど、追い返してしまったの」
「何故? 皇后陛下の御身はこれから彼がお護りすると……」
唖然とする璧輝を余所に婉容は静かに、けれど毅然として頭を振った。
「金璧輝、私は貴方でなければ嫌よ。あの日本人、今すぐにでも私をここから連れ出そうとしたけれど、貴方を見捨てていけるわけがないでしょう?」
「私の事など構わず、皇后陛下は一刻も早く宣統帝の許に行かなければ……」
「いいえ。私あの失礼極まりない日本人に条件を付けて言ってやったの。貴方が完治して私を旅順へ連れて行ってくれるのなら……それなら私は言う事をきくわ、と」
婉容は熱の引かない璧輝の額の汗をタオルでそっと拭い、再び髪を優しく撫でつける。
「貴方が治るまで私がずっと傍にいてさしあげてよ。それと……」
撫でていた手を離し両手を自分の膝の上に重ねると、婉容は子供のようにちょっと困ったような顔をして小さく頭を下げた。
「昨日は取り乱したりして悪かったわ」
「もったいないことを……どうか顔をお上げください」
璧輝はまたも傷を負っていることを忘れ、慌てて身体を起こそうとする。
「ほらほら駄目よ、急に起き上がったりしては傷が開いてしまうわ」
婉容は優しくたしなめ、ゆっくりと立ち上がると、璧輝の上半身を抱きかかえて枕をクッション代わりに背中に挟んで寄り掛からせる。璧輝の血と汗で汚れた衣服はきちんと取り替えられていて、その代わりに清潔なバスローブを身につけていた。
「着替えも皇后陛下が?」
「そうよ。だってあのままでいさせるわけにはいかないし……かなり手こずったけれど、女同士だから別に構わないでしょう? さあ、包帯を交換するわね」
婉容は璧輝の背後に回り込んでバスローブを右肩だけ脱がせ、固く巻かれた包帯を慎重に解き始めた。
「痛いけど、我慢してね」
包帯を総て解き、創口にあてがわれていた血で赤黒く滲んだガーゼも取り除く。軍医が婉容の為に置いて行った、手当の道具一式の中からピンセットに真綿を挟んで消毒薬を染み込ませると、恐る恐る璧輝の銃創に当てた。
激痛に耐える璧輝の身体が瞬時に緊張で強張り、細いうなじと白い肩が小刻みに震えている。血はまだ完全には止まっておらず、その創口はじくじくと生乾きの醜い様相を曝している。婉容は璧輝の痛みを少しでも軽くさせようと手早く消毒を終えて、真新しい清潔なガーゼを当てる。軍医の施した包帯の巻き方を記憶の中で組み立て再現しようとしているその表情は真剣そのもの。額にうっすら汗をかいて解けないようにと、包帯を巻く両手に力を込める。
「緩いところがあったら言って頂戴」
「平気です。皇后陛下は意外と力がおありになるのですね」
「そんな憎まれ口を叩くのだったら、もう大丈夫」
背後の婉容が小さく笑った。
そして流れる沈黙。
手当に必死な婉容とは裏腹に、璧輝は自分を襲う、痺れるような感覚に驚きと困惑を感じていた。全身を貫く激痛と相まって、自分の肌を強く優しく自在に滑る婉容の細い指、言葉を発する度に素肌に降りかかる熱い吐息。
そしてあの夢の中の涙に濡れる母の顔と今ここにいる婉容の顔が瞬間一つに重なった。
「さあこれで大丈夫なはずよ。そうだわ、ちょっとお待ちになって」
婉容は弾かれたようにベッドから立ち上がり客間を後にすると、大きな水差しとガラスのコップ、白く薄い紙袋を乗せた銀のお盆を持って戻ってきた。
「お薬よ、飲める?」
そう言ってお盆をサイドテーブルに置き、紙袋の中から小さな包みを開けて渡す。白い粉末を口にして、璧輝は手渡されたコップの水を一気に飲み干した。
「もっと?」
熱砂に滲み込む水のように、熱に浮かされた璧輝の身体は水分を欲して止まない。立て続けに二杯の水を飲んでぐったりと枕に寄り掛かった。
「少し唇の色が良くなったみたい。さっきまでまるで死人のように真っ青だったもの」
ベッドの上に静かに腰を下ろして、美しく整った婉容の顔が穏やかにほころんだ。じっと璧輝を見つめる神秘な強い光を秘めた円らな二つの黒瞳、艶やかな深紅の唇。
「やっと笑顔になりましたね……」
璧輝はその微笑に見惚れずにはいられなかった。
「お美しいと評判の皇后陛下……貴方様の護衛を仰せつかった時……正直に申し上げますが、お逢い出来ることを私は心中秘かに喜んでおりました」
「あら、随分お上手ね。でも実際逢ってみて幻滅なさったのではなくて? 気難しいし、暴れるし、高慢で我儘で……」
「想像通りの……いや、それ以上のお方でした。お美しいだけではなく、意志が強くお優しい。そして何より私の命の恩……」
突然、璧輝の唇を婉容の人さし指が塞いだ。
戸惑って言葉を失う璧輝に上目遣いの悪戯な眼差しを向け、その反応を楽しむかのように童女のようにくすくすと笑う。
「顔が赤いわ」
「きっと熱のせいです」
「さあ、もう余計なお喋りは身体に障るからお終いにしましょう」
そんな無邪気な彼女を見て、秘しておくのが辛くなったのか、璧輝の口から思わぬ言葉が滑り出た。
「満洲国」
「え?」
「最終的に皇后陛下の行き着く場所は此処、満洲の地に新たに建国される満洲国。その首都新京でございます」
「……」
「宣統帝と皇后陛下には満洲国の執政閣下とその令夫人となって頂くことになるでしょう」
満洲国・新京・執政閣下──。
初めて聞く言葉の羅列に婉容は戸惑いを隠せない。彼女の笑顔は瞬く間に萎んでしまった。
「漢・満・蒙・日・朝の五族協和、王道楽土を理念とした新しい国家の建設。その頂点に立つことを宣統帝は既に了承済みです」
──ああ、またもそうなのだ。
婉容は心の奥底で絶望にも似た深いため息をついた。
運命は自分を、その希望とは真逆の方へと否応なく押し流してゆく。今となっては虚しい、名ばかりの清朝皇后とてなりたくてなったわけではない。ましてや得体の知れない『執政』夫人などもってのほか。
「執政夫人となれば、皇后陛下の未来は思うがまま。今までのような隠れた軟禁生活を送らずとも、我等が祖先の約束の地、この満洲で新しい希望に満ち溢れた国家を、清王朝を復活させるのです」
「我等が祖先の約束の地」
璧輝の発したこの一言を婉容は聞き逃さなかった。
「金璧輝、貴方は一体何者なの? あのアマカスは確か貴方をカワシマと呼んでいたわね? 貴方は本当に中国人? 漢人なの? ここ満洲は私達満洲族の故郷なのよ……?」
大きな黒耀の双瞳がじろりと璧輝を見据えた。
第九章
言わずと知れた満洲は女真族──後の満洲族の長となった太祖ヌルハチが、中国全土を手中に収め打ち立てた清王朝発祥の地。満人にとって心の故郷であるこの土地を、今や中国の人口の殆どを占める漢人がよもや間違ってもそのような言葉を発するはずがないのだ。況や日本人をや。
「貴方は誰?」
婉容は璧輝を問い詰めるようににじり寄った。
「皇后陛下はなんて鋭い」
璧輝は髪をかきあげ、少し照れるように苦く笑った。
「……隠していたつもりは無かったのですが……私は五歳の時に日本人に引き取られまして、普段は日本人として生活しております。日本名は川島芳子」
「だから日本に手を貸しているのね? それならそうと最初からそちらの名前を仰っていただければ、国民党の密偵だなんて疑わなかったのに……」
「申し訳ありません。皇后陛下は日本人がお嫌いと聞いておりましたので敢えて日本名を使いませんでした」
「そうだったの……」
「金璧輝という名は漢人風の名で、兄に倣って使っています。中国国内で活動する時はこの名の方が動きやすいので……そして……」
「そして?」
心の奥底をじっと見つめるような婉容の視線に耐えられなくなった璧輝はそっと眸を伏せた。
「私の本当の名は愛新覚羅顕㺭(シャンツー)」
「愛新覚羅……皇上と同じ王族なのね?」
婉容は低く呟いた。
「そうです、郭布羅婉容様。私は貴方様と同じ満洲族の人間。清朝王族粛親王の第十四王女として生まれました。宣統帝とは遠い従兄同士。その縁あって関東軍から今回の護衛の命を受けました」
婉容は信じられないというように頭を振った。
「そんな……由緒正しい清王朝の王女が何故男のなりをして、日本人に加担しているの?」
訊いた直後に婉容は自らの愚問を恥じた。返ってくる答えは分かり切っているはずなのだ。
「総ては復辟の為でございます」
寝具を固く握りしめた婉容の手を、璧輝の燃えるように熱い両手が包みこんだ。
「私は亡き実父粛親王、並びに養父川島浪花の清朝復辟という悲願を幼い頃から一身に受け、私もそれが二人から託された自らの使命なのだと信じて生きて参りました。今回の満洲国の建国も、復辟への単なる布石として、関東軍に請われるまま工作活動をしているにすぎません。何故なら復辟の為には日本人の力が必要不可欠であり、大いに利用するべきだからです。」
そして眸に確固たる熱い光を宿して璧輝は婉容を見つめる。
「我々清朝王族の宿願のためにも皇后陛下には是非とも国家元首夫人に就いて頂く必要がございます。そしてその先には必ずや復辟が成り、再び清王朝の皇后となられ、余りある自由と幸福を享受して頂きたいと、私は心から願っております」
婉容は言葉を失っていた。
一体、自分を新国家とやらに据える為にどのくらいの人間の血が流されそして死んでいったのだろう? 大連の埠頭で撃ち殺してしまったあの男。乱闘で命を落とした日本の兵士と中国人密偵。そして現に眼前にいる璧輝でさえ、自分の為に血を流し、大怪我をしているではないか。婉容はそんな彼女を目の前にしてとても言えなかった。自分は執政夫人などという役目はまっぴら御免、私の望む幸せは別にあると。普通の一女性として静かに穏やかにひっそりと暮らしてゆきたいと。
璧輝は実父と養父によって刷り込まれた妄想と幻影の虜となって、ここまで全速力で駆け抜けて来たのだろう。そしてこれからも見えない最終目標に向かって虚しく走り続けるに違いない。
婉容にとって塵ほどの重みを持たない清朝復辟というものが、眼前の男装の王女にとっては生涯を賭けた、為さねばならない重大な偉業なのだ。あまりにも一途で健気で危うい彼女。男装は自身の弱さと真の心を強固に護る盾なのだ。
自分に注がれる璧輝の篤い献身に、婉容は正直戸惑いと憐れみを覚えずにはいられない。目的の為には自身の生命をも厭わず、身体を張って護ってくれた璧輝に対して、婉容が報いることのできる術は唯一つ。
「わかったわ……私は満洲国の執政夫人となるわ」
「皇后陛下……」
「日本が私に課す役割としてではなく、貴方が私に心からそう望むのであるなら」
「もちろんです!」
「……本当に其処には自由と幸福が待っているのね?」
「はい。争いの無い地上の楽園を目指すのです。清王朝の栄光を今再び宣統帝と皇后陛下、そして我々と共に!」
「貴方はまた私を護ってくださる?」
「お仕えできる時はいついかなる時も。たとえこの身がお傍に無くとも、私の心は常に皇后陛下のお傍に在ります」
熱を持った璧輝の手がさらに熱くなってゆく。
「貴方をなんてお呼びしたらいいのかしら?」
「どうぞお好きな名前で」
婉容は迷わず一つの名を選んだ。
そしてこの昏い妄信に憑かれた彼女の心にどうか届くようにと、婉容は自らの気持ちを祈るように言葉にのせた。
「顕㺭は実の父上や義理の父上の望みを果たす為に存在しているのではないわ。もちろん、私の為でもない。人の命を奪ってしまった私が言うことではないけれど……どうか顕㺭、命を粗末にしないで。ご自分を大切にして。貴方は誰かの為にではなく、自分自身の為に在るのだから」
顕㺭はじっと婉容をみつめる。
今まで誰からも聞いたことの無かったその言葉。それが初めて婉容から放たれて圧倒的な力を持って顕㺭の胸に迫る。暫く無言で押し黙った後、彼女は自分に言い聞かせるように小さく呟いた。
「私は私自身の為に在る……」
「そうよ。たくさんの顔と名前を持つ不思議な顕㺭……でも私の前では、日本人の川島芳子でもなく漢人を装う金璧輝でもない、偽りのない本当の貴方……愛新覚羅顕㺭でいてね」
婉容の紡ぎだすさらなる言葉が、まるで天からの啓示のように、閉ざされた闇の中を疾走する顕㺭の心の裡──その遥か遠くに射すほんの微かな光となって瞬いた。
第十章
一週間余が瞬く間に過ぎ、顕㺭の銃創は完治とまではいかないまでも、熱も引いてかなり自由に身体を動かせる状態まで回復していた。ホテルの部屋から一歩も出ることが出来なくても、二人はそれで良かった。いや、却ってその方が良かったのだ。誰にも邪魔されずに絆を深めることが出来たから。
「僕が男装している理由? それはたとえ婉容でも教えられないな」
顕㺭の一人称が、改まった『私』から普段使っている『僕』へと変化していることでも分かる。寝食を共にして二人の親密度は日を追う毎に増していた。
「まあ、意地悪ね。私ったらその日本の軍服にすっかり騙されてしまって……」
「ちょっとまって、よく見て婉容。これは僕特製の軍服だよ。間違っても関東軍と一緒にしないで欲しいな」
妙な所にこだわりを持つ顕㺭の意外な一面を見た気がして婉容は思わず笑ってしまう。
「あら……それは失礼。でもどちらにしてもとてもよくお似合いよ。でも旗袍を着た顕㺭もきっと素敵だと思うわ」
「それはどうも」
穏やかな午後。リビングでルームサービスのコーヒーを飲みながら微笑みを交わし合う、束の間の平和なひととき。
「甘粕だ」
それを突然打ち砕く、荒々しくドアを叩く音。二人は咄嗟に顔を見合わせる。不安気な顔で応対に出ようとする婉容を顕㺭は片手で制して代わりにドアを開けた。
「診察に来た。中に入れてもらう」
横柄な態度は相変わらず。軍医と共にずかずかと室内に入ると、リビングで険しい顔をしてこちらを見ている婉容に会釈をする。
「ご機嫌はいかがでしょうか? 皇后陛下」
「最低よ」
吐き捨てると、そそくさと診察の為に客間に行く軍医と顕㺭の後を追った。
無言でその後ろ姿を見送る甘粕。しばらくしてテーブルの上の二客の飲みかけのコーヒーの入ったカップに気付くと、彼はそれをじっと見つめていた。
15分程で手当が済み軍医を先に部屋から退出させると、甘粕は婉容に顕㺭と二人きりで話がしたいと申し出た。顕㺭もそれに同意するので、彼女は仕方なく独りリビングでやきもきしながら二人が客間から出てくるのを待つしかなかった。
「具合はどうだ?」
「順調この上ない。医者が言うには普通の生活をしても構わないそうだ」
客間のソファに向かい合って座り、甘粕の問いに顕㺭は答える。
「そうか……それでは出立は明日の朝。もうこれ以上は待てん。それより、流石は川島。あの高慢な皇后に上手く取り入ったようだな。俺はすっかり嫌われたらしい」
苦笑する丸眼鏡が窓から射す西陽を反射してきらりと光る。
「取り入ったなどと……ただ正直に言っただけだ。満洲国の執政夫人になるのだと」
顕㺭は脚を組み換え、鼻で小さく笑った。
「あの日本人嫌いの皇后のことだから、面倒な事になると思って事後報告で済ますつもりでいたのだが……抵抗されなかったか? 自殺するとか外国に亡命するとか」
「いや、特に」
「皇后の身辺警護と護送役、これが今回の君の任務。その上説得まで無難にこなすとは、やはり軍の人選は確かだな。それはそうと、その身体で運転はできるか?」
「ああ……多分」
「では手筈通り、旅順の粛親王府へお連れしてくれ」
「わかった」
「そして君はその足で上海へ行き、次の計画を実行するのだ」
「了解」
「では成功を祈る」
立ち上がり客間のドアに手をかけた時、甘粕は背を向けたまま小声でぼそりと呟いた。
「川島、大連港では助かった。礼を言うぞ」
言い残して、足早に部屋を出て行った。
わざわざ礼を言うなど彼らしい、と顕㺭は思った。数多く見知った日本人の中でも甘粕は彼女にとって唯一信頼のおける存在であった。清朝の王族という自分を、何かと利用しようとする関東軍の中にあって、彼ほど性差や人種を超えて利害抜きに対等に接してくれる者はいないからだ。
「今度は何時逢えるか……」
顕㺭は甘粕の出て行ったドアを見つめて独り呟いた。
顕㺭が客間から出てくると、待ちきれなかったとばかりに不安気な表情を浮かべて婉容が駆け寄ってきた。
「彼は何と言っていて?」
一時凌ぎの嘘を並べ立てたとしても、この鋭い婉容には見抜かれてしまうだろう。そして何より隠し立てなどもう二人の間に必要が無いのだ。顕㺭はありのままを伝えた。
「明日の朝ここを発つ、と」
「……」
「旅順の……僕が幼い頃、日本に行くまで住んでいた家で宣統帝がお待ちかねだよ」
「そう……わかったわ」
婉容の反応は意外にもあっさりとしたものだった。
「では今宵が最後の晩餐というわけね」
婉容は努めて笑顔で言ったつもりであったが……あまりにも健気で痛々しいその微笑に顕㺭は応える術を持たなかった。
その数時間後。夜も更け、バスルームから出てきた婉容は部屋の中がすっかり冷え込んでいるのに気づいた。ナイトガウンを羽織った火照る身体が一気に冷えてゆく。
「顕㺭、いるの?」
返事は無い。婉容は怪訝に思いながら明かりの落とされたリビングへと向かう。するとすぐに部屋に充満する冷気の原因が判明した。寒風をはらんで大きく翻る白いカーテン。顕㺭がリビングの窓を全開にしてバルコニーに出ていたのだ。
「気は確かなのかしら?」
婉容は呆れ顔でそっと近づいてゆく。これから真冬にかけて満洲の寒さは恐らくアジア一なのではないだろうか? ましてや深更。厳寒をものともせずに顕㺭は軍服姿のまま、バルコニーの手すりに片手で頬杖をついて遠く夜空を見つめていた。
吹きすさぶ風に低い歌声が紛れて聞こえてくる。
顕㺭が、あの顕㺭が歌を歌っている……?
蒙古の言葉なのか、それとも自分ですらとうに忘れ果ててしまった満洲の言葉なのか。
婉容の知らない言語で歌われるその歌は、顕㺭の表情と同様に、もの哀しくやるせない。降り注ぐ銀色の月影に濡れ浮かぶ白い横顔。風に靡く黒い断髪、揺れる睫毛。男装などしていなければ、王女然とした相当に美しい姿であろうはずなのに。
するとふいに歌が途切れ、その代りに唇から押し殺したような呟きが洩れた。
──家あれども帰り得ず
涙あれども語り得ず……。
そしてその何処か遠くを見据える眸から頬を伝って一筋の煌めく涙が零れ、吹きすさぶ風に無数の小さな珠となって千切れ飛んだ。
婉容はその姿をじっと見つめたまま、まるで金縛りにあったように身動きができなかった。
……やはり彼女も同じなのだ。
戻る場所もなく、共に涙を分かち合える相手もいない。自分と同じ、果てしなく恐ろしいまでの孤独に囚われている!
こうして人知れず涙を流す顕㺭の暗い孤独の片鱗を垣間見て、固く閉ざされた心の盾の隙間を覗いてしまった瞬間、婉容の今まで無理やり心の奥底に閉じ込めていた感情が、顕㺭の涙に共鳴したかのように堰を切って溢れ出した。
「顕㺭!」
婉容は堪らず走り寄って、力任せにその軍服の背中に思い切り縋りついた。
第十一章
「婉容……?」
驚いた顕㺭は慌てて涙を拭い、身体を捩って婉容を背中から引き剥がす。そして両手でその小さな顔をそっと挟んで上を向かせると、二つの黒瞳は溢れる涙で濡れていた。
「一体どうした? 身体がこんなに冷たくなって……」
顕㺭は自分の軍服の上着を脱いで婉容に掛けてやり、肩を抱いてバルコニーから部屋の中へ戻ると、窓にしっかりと鍵をかけた。
「御免よ、窓開け放していて寒かったろ? シャワーを浴びたばかりなのに風邪をひいてしまう」
主寝室に行き、未だ泣き濡れる婉容をベッドに座らせる。顕㺭は隣に腰を下ろして婉容の冷たくなった両手を握りしめた。
「……よ」
俯く婉容が必死に言葉を紡ぐ。
「顕㺭と別れるなんて……嫌よ……」
「婉容……」
「ごめんなさい……偉そうにあんなこと言ったくせに……本当は執政夫人なんてなりたくないの! 清朝復辟なんて……皇后なんて……満洲国なんて……そんなものいらないわ! 顕㺭、貴方がいればそれでいい……ねえ……二人で何処か遠くに行きましょう! 私……私……初めて逢った時から顕㺭のこと……」
婉容の唇を今度は璧輝の人さし指が塞いだ。
思わぬ告白に顕㺭は戸惑いを隠せない。何故なら秘めたる想いは自分も同じ。婉容のその懇願の眼差しから一転して、驚いたようにじっと自分を見つめる童女のようなあどけない表情。伏せた濡れる睫毛、ほんのり紅い頬、震える細い肩、指に降りかかる微かな吐息……一挙手一投足総てがどうしてこんなにも美しいのかと、ため息が出るほどだ。
「僕にそれができるならとうにそうしていたさ! 僕が君を幸せにできるなら……だけど……僕は女で、日本人に踊らされる、しがない忘却の王朝の名ばかりの王女に過ぎない」
最初の邂逅の一瞥から自分の心をあっさりとわし掴んで攫ってしまった貴女。身体の深奥から込み上げ、日ごと膨れ上がっていった、未だ嘗て感じたことの無いこの許されざる想いを抑えられずに、顕㺭は任務を忘れ、その華奢な身体を思わず抱き締めていた。
「顕㺭といればそれだけで幸せなのに」
「……そんな幸福は束の間の幻。婉容にはその手で確かに掴み取れる現実の幸福がある。一国の元首夫人となれるその身分をみすみす捨てることは無い。僕のことなんて忘れて新国家へ自由に羽ばたくんだ!」
顕㺭の胸の中で婉容はただ首を横に振るばかり。
「顕㺭を忘れるなんて……そんなこと出来ないわ」
「婉容、よく聞いて。輝かしい未来の前で僕なんかに躓いたら駄目だ。君は確実に幸せになれる。僕は心からそれを願うよ。君の幸せが僕の幸せとなるのだから」
「私が満洲国の執政夫人になれば顕㺭も幸せになれるのね?」
「そうだよ、だから……」
婉容はぴたりと泣きやんだ。
彼女は知らないのだ……満洲国という新しい鳥籠を用意された自分は、決して幸福にはなれないということを。自分の望む幸せは既にそこには無いのだから。羽ばたくことなど出来ない。羽をむしり取られた飛べない鳥は、ただ単に清王朝から満洲国という得体の知れない鳥籠に移されるだけだ。
苦く何度も噛み締めた諦観の念を脳裏で反芻する。
定められた運命には逆らえない。
多少の荒波や逆風があったとしても所詮自分の人生は人に操られる古びた船なのだ。
「……明日は早いのでしょう? もう休むことにするわ」
上着を顕㺭に返し、ナイトガウンを脱いでベッドに入る婉容。
「とても寒いの……顕㺭、貴方のせいよ」
ブランケットを掛けようとしていた顕㺭の手を婉容はしっかりと握りしめて言った。
「温めてくれなければ嫌よ」
ベッドの中から哀願にも似たその黒耀の瞳でじっと見つめられたら最後、顕㺭は抗うことなど決して出来ない。黙って婉容の隣に滑り込むと、しっかりとその身体を抱き締めた。
まるで氷の塊のように冷え切った、華奢な身体をすっぽりと両腕に包んで、誰にも奪われぬようこの熱い想いで融かしてしまえたらどんなにいいか!
「我儘を言ってごめんなさい……私は顕㺭を信じているのだもの、貴方の言うとおりにするわ」
暫くして、顕㺭の胸に顔を埋めた婉容の耳に先刻のあの歌が聞こえてきた。
「その歌は……?」
「子供の頃母さんがよく歌ってくれた子守歌。もうずいぶん前のことなのに不思議と覚えているのさ」
「顕㺭はとても温かいのね」
「そう?」
「お願い。もう一度……いいえ私が眠るまでその子守唄聴かせてくださる?」
「いいよ……婉容」
顕㺭の手が優しく婉容の背中を滑る。
そのぬくもりを確かに感じながら、婉容は固く目を閉じて心の中で何度も何度も自分に強く言い聞かせた。
……貴方の幸せの為なら未知の世界にも懼れず生きていける。
たとえこの身が二つの国に操られ翻弄されようとも。
果てしない孤独が待っていようとも。
ああ、貴方を想えばきっと……。
第十二章
大連から旅順までは正味一時間。白玉山の西方の丘の上にある旧ロシアのホテルが粛親王府であった。
顕㺭が運転する、甘粕が手配してくれた車の中で二人は終始無言だった。何故ならすぐ傍まで来ている別れに怯えて。
「あの赤レンガの洋館がそうだよ。きっと僕の異母姉、顕珊が迎えに出ているはずだ」
森の中ひたすら車を走らせて次第に近づく壮麗な建物。顕㺭はそこから少し離れた所で車を止めた。王府の玄関前に一人の女性が出迎えに現れているのが、ここから小さく見えた。
「着いたよ」
顕㺭は俯いて助手席に座る婉容に声をかける。
「顕㺭……いろいろとどうもありがとう。これを見て私を想い出して欲しいの。受け取って頂ける?」
そう言って婉容は耳から翡翠のイヤリングを外し始めた。顕㺭は慌ててそれを制する。
「僕は他にもっと欲しいものがあるんだ」
え? と婉容は驚いた眼差しを顕㺭に向けた。
「何かしら? 私、他にさし上げられる物なんて何も持っていないの」
顕㺭は首を振って婉容の両手を握り締めた。
「君のとびきりの笑顔を。ずっとこの眸に焼き付けておきたいから」
「気障な顕㺭! そんなことよく恥ずかしげもなく言えるわね?」
吹きだして婉容は微笑んだ。
「君のこと決して忘れない」
「私もよ」
顕㺭の言葉がたとえ慰めであっても構わない。これを限りに二度と逢えなくとも、自分の事を忘れ去ってしまってもいい。今この時、この地で、この顕㺭と巡り合わせてくれた運命というものに、婉容は初めて心から感謝した。
未来の満洲国執政夫人婉容の、その美しい顔に大輪の笑顔が咲き誇る。惹きつけられてやまない深い漆黒の瞳、紅く艶やかな唇から零れる皓い歯。自分の為だけに向けられる、蕩けるばかりの絢爛の笑顔に顕㺭は束の間酔いしれた。
「もう行くわ。独りで大丈夫だから」
別れの言葉はどちらからとも切り出すことは無かった。出来ることなら、またいつかきっと逢いたいと、逢えると信じていたいから。
婉容は自ら車を降りて歩き始めた。その毅然とした後ろ姿を顕㺭は、まるで半身を引き裂かれるような思いで見送る。
いいのか、顕㺭? 彼女の真意は分かっているはずだ。彼女はお前の為に不本意ながらも歩いてゆく。敢えて困難で複雑な道を。
黙れ、璧輝! 他にどうしろと? 自分に何ができる? 困難か複雑かは分からない。祝福と輝きに満ち溢れた華やかな道かもしれないじゃないか!
己の中でこんな葛藤を幾度となく繰り返してここまで彷徨い続けてきた。この先自分はどうなるのか? どこに行き着くことになるのか?
決まっているさ、そんなこと! 芳子、お前に残された道は唯一つ。清朝復辟、唯此れのみ! 一つの任務は完了した。さあ、行け、上海へ。思い悩んでいる暇は無い。次の仕事が待っている。
遠くなる婉容。
千々に乱れる思いを完全に断ち切った彼女は唯の一度も振り返らなかった。そして顕珊に導かれるまま、あっけなく巨大な粛親王邸に吸い込まれていった。
最初は任務のはずだった。
けれど今感じるこの抉るような生々しい胸の痛みは一体何だというのか?
事は着実に進んでいる。もう後戻りは出来ない。
顕㺭は再び車を走らせる。
私の前では、日本人の川島芳子でもなく漢人を装う金璧輝でもない、偽りのない本当の貴方……愛新覚羅顕㺭でいてね。
縋るように婉容のあの微笑みを脳裏に思い浮かべながら。
自分に放った彼女の言葉を噛み締める。
そして1932年1月、上海事変勃発。
1932年3月1日、満洲国建国。
我的愛人 ─顕㺭和婉容─
完結です。
次シリーズ「我的愛人」に続きます。
お読みくださりましてありがとうございました。


