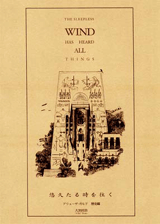
悠久たる時を往く
これに示すアリューザ・ガルド世界の歴史は、“次元の狭間”にある“イャオエコの図書館”の数多ある蔵書の中から抜粋、要約したものである。
永久にも等しい時間の中において、起こった出来事はそれこそ数限りない。ここではそれらの出来事について簡単に説明を行いつつ、歴史の流れをひもといていく。
この書の編纂を行いながら私は、自身が悠久たる時の流れを往く旅人であるかのような感覚を覚えた。川の流れが高きところから低きところへと向かうのと同じく、時は遡ることなく流れゆく。名も知れぬ数多の人間が、“時代”という名の流れに乗り、運命を切り開いてきた。そしてこれからも――。
こうして歴史書の編纂を終えた今、この書は図書館の蔵書として書架のいずこかに置かれる。いつの日か、この地を訪れた人間がこの書を読むまで。
過去に起こった事象が、紡がれゆく未来に何らかの指標となることを願って
司書長、“真理の鍵を携えし者”マルディリーン 記す
目次
<創造の世>
一. ミルド・ルアン紀
二. タインドゥーム紀
三. 色織りの紀
四. 大暗黒紀
<分かたれた大陸の世>
五. 扉の時代
六. 劫火の時代
七. 忘却の時代
八. 統一王国の時代
九. 黒き災厄の時代
十. 魔導の時代
十一. 諸国の時代
一. ミルド・ルアン紀
すべてのはじまり。
すべてのはじまりには、ただミルド・ルアンのみがあった。
超存在ミルド・ルアン――“自我なき源”――は、まったき空虚の中で身じろぎもせず、また考えることもせずに、永遠にも近い時の流れの中にて、ただ存在していた。
しかしながら永きに渡る停滞にも、ついに変化が訪れた。
ミルド・ルアンに自我が生まれ、そして死んだのである。また、それまでとどまっていた時間が、これを期に動きはじめた。
超存在の死によって、その身体からは三なるものが誕生した。
まずは一つ目として、大地が象られた。
広大な陸地と、それを取り囲む海が形成されたのだ。そしてこれこそが、のちにアリューザ・ガルドとなるべき世界の、はじまりの姿である。
この世界は、原初世界もしくはタインドゥーム世界と称される。
また二つ目であるが、ミルド・ルアンの放つ声によって、幾重もの“音”と、“思念”が放たれた。
これらは魂のもととなるべきものである。
“音”と“思念”のなかには、そのまま遠くに飛び去ってしまったものもあるが、大地にとどまったものもあった。
大地にとどまった“音”と“思念”はお互いに絡み合い、やがて大いなる生命となった。
これこそが古神。すなわちタインドゥームをはじめとした、原初の世界の支配者達である。
(飛び去ってしまったものが、のちにアリュゼル神族となって、タインドゥーム世界へ帰還するのだ)
そして三つ目。
大いなる力すなわち“始源の力”が世界を取り囲み、たゆたうようになった。
(“始源の力”によって、ミルド・ルアンは自我に目覚め、かつこれによって死んだ。しかしこれらの力は、外的に形成された事象ではなく、ミルド・ルアンが自ら形成していたらしい。
――この事項については神々の思惑よりもはるかに複雑であり、我々では推し量ることが出来ないので割愛させていただく)
これら、三なるものによって、原初の世界が創造されていくのである。
二. タインドゥーム紀
原初世界と古神の支配。そして始源の力の氾濫。
原初世界には、いっさいの“色”という概念がなかった。そこにあるのは暗黒と、漠然とした白のただ二つのみであると伝えられている。
海と空が白くなるときには大地は黒に染まり、また海と空が黒くなるときには大地は白く光ったとされる。これらは周期的に入れ替わった。時の流れにおいて、色の入れ替わりがひとつの大きな節目となった。これが一年という単位のはじまりである。
さて、色無き世界に降り立った神々の中で、最も気高きものは自らをタインドゥーム(“至上なるもの”の意とされる)と名乗り、他の神々を束ねていった。
古神達はそれぞれ気の向くままに世界を闊歩し、大地の大きさを把握したところで世界の中心部へと集まった。その場所で彼らは“タス”という名の聖宮を築き上げると、幾千もの時を平穏に過ごした。
やがて、古神達は自ら住まう世界に飽いた。彼らは自らの力を奮い、山や木々といった自然を生み出した。しかしこの時代の自然とは、あくまで石のように無機であり、荒涼たる大地しか知らない神々の鑑賞物であった。現在の世界のような、潤いをもたらす存在とはほど遠い存在であったとされている。
一方で、古神達にとってすら脅威となる存在があった。“始源の力”である。
“始源の力”は世界の果てを取り囲むようにしてたゆたっていたが、時折、力同士がぶつかり合うのだ。その度に大地は余波を受け、大きく揺らいだ。また、力同士の争いが激しいときには、敗れて行き場を失った力が大津波のごとく大地に襲いかかった。力の襲来によって神々にも犠牲が出るようになったのだ。
神々は力の襲来を防ぐため、世界の果てに防壁を築くことにした。だが世界の果てに赴いた際に力の襲撃に遭い、死んでしまうことを恐れた神々は、下僕を創造してこれに建造を従事させることにした。
魂のもととなるべき音と思念は、霧のようになってうっすらと宙に浮かんでいた。古神達はそれらを大地に取り込むと、人のかたちを作りあげた。
これが原初の人間、のちにディトゥアと称されるようになる者達である。
人間は船を造り、海を渡って世界の果てに赴いた。数知れぬほどの人間が力の犠牲に遭い命を落としたが、感情という概念を一切持たない人間達にとって、死は臆するものではなかった。彼らはあくまで、神々の忠実な下僕に過ぎないのだ。
多くの歳月と犠牲を払い、ついに人間達は世界の果てに防壁となる山々を築き上げた。これが後に言う“果ての山々”である。
生き残った人間達は大地に帰還するが、神の下僕たる彼らに安息の日は訪れることはなかった。彼らは奴隷のように酷使される一方、神々の戯れのためだけに人間同士の血を流して戦うこともあった。
神々は明らかに増長していたのだ。
そしてここから古神達にとっての終末が始まる。
“果ての山々”という防壁によって、永きに渡り“始源の力”の襲来は阻まれてきた。しかし、神々が安穏と暮らすうちにも、“始源の力”は変貌を遂げていたのだ。“混沌”と呼ばれる力は、他の力を飲み込み膨らんで、とうとう始源の力のすべてとなった。この“混沌”の力というものはあまりに強大であり、ついには抑制を失って力の暴走が始まってしまったのだ。
“混沌”はいともたやすく果ての防壁を乗り越え、巨大な津波のように大地に襲いかかり、すべてを洗い流した。その後に“混沌”は忽然と世界から姿を消した。理由は知れないものの、“始源の力”は突如として消え失せたのだ。
しかし、“始源の力の氾濫”によって、栄華を誇った古神達の時代は終焉を迎えようとしていた。タインドゥームは、“混沌”に飲まれて息絶えた。また、多くの神々や人間も死んでしまった。栄華を誇ったタスは跡形もなく崩壊してしまったのだ。
そして――突如として空が割れた。
裂け目からは今まで見たこともない新たな力が流入してきたのだ。
それはアリュゼル神族と、“色”の帯。
ミルド・ルアンのまたひとつの分身であるアリュゼル神族は、永きに及ぶ諸次元の彷徨の末、ついにもといた世界に帰還したのだ。
そして、色の帯の流入。これこそが魔力を帯びた“原初の色”である。
古神達は新たなる力、すなわち“色”を頑なに拒絶した。また、アリュゼル神族の討伐を人間達に命ずるが、彼らは従わなかった。色の流入を受け入れ、色ある存在となった彼らに感情が芽生えたのだ。人間達は逆に暴君たる古神達に矛先を向けるようになった。
ついに、古神とアリュゼル神族は直接戦うこととなった。だが衰えた神々に抗うだけの力はもはやなく、程なく古神達は暗黒の果てへと追放されてしまうのである。約二万年に及ぶ古神達の支配はここに終わりを告げた。
世界中に“原初の色”が流入していくさなか、アリュゼル神族の大いなる方、天帝ヴァルドデューンはおっしゃった。
「この世界こそが我らと、そして我らの子らが永久に栄える世界である。この世界は“アリューザ・ガルド”である」
ここにおいて、アリューザ・ガルドの歴史が始まっていくのだ。
三. 色織りの紀
原初世界と古神の支配。そして始源の力の氾濫。
[織り混ざる色と、太陽の誕生]
世界に流入した“原初の色”の帯は、互いに絡み合い、無数の色を作りあげていった。それまで色という概念が存在し得なかった世界は、美しく彩られるようになっていく。
また、色は魔力そのものを内包していたので、彩られた世界は大いなる魔力にも包まれることとなった。
“原初の色”が万物に内包されるようになると、物質は独自の色を放つようになった。これこそ我々が普段目の当たりにする色に他ならない。
そして万物に溶け込まずに、最後まで空に残った“原初の色”もあった。これらはやがて天高く上りゆき、偉大なるひとつの色を形成した。
それこそが“太陽”と呼ばれる、大いなる光である。
太陽は天球を巡るように運行を始め、世界に昼と夜の区別が生まれた。同時に、一日という概念もここから始まることになった。
創造されて間もない頃の太陽は、ある一定の日時ごとに(正しくは二十八日ごとに)その色あいを変えていたとされる。
(ただし、色織りの紀の終わり頃までには、“光”という一色に定まるようになった)
太陽の色は金色からはじまり、白、黄、緑、紅、紫、黒、紫紺、蒼、橙、光、銀となりふたたび金色に戻る。これら十二色の変化の周期はちょうど一年に相当した。また、色の期間ごとにひと月という概念が生まれた。
[ディトゥア神族への昇華]
さて、アリューザ・ガルドと名の付いた美しい地上は、アリュゼル神族の住まう大地となった。かつて古神達が住み、そして廃墟と化したタスを浄化したアリュゼルの神々は、その大地に新たに“フォルタス《光満つる宮》”という荘厳な宮殿を築きあげた。
一方で、始源の力の氾濫と、神々の戦いによって滅びかけた人間達は、新しいアリューザの神々からは遠ざかり、辺境で細々と暮らしていた。
かつては古神達に隷従していた人々だが、感情が芽生えてからは過去の悲しみと神々への恐怖にとらわれてしまったのだ。やがて人間達は自身の存在自体すらも悲しむようになり、滅びの一途をたどるようになった。
天帝ヴァルドデューンの后フルーウェンはこのことを大変悲しみ、神々と人間達が共栄できないものか、天帝に進言した。古神達を追放できたのは人間達の力があったればこそ、と考えていたヴァルドデューンは、人間達の長を呼び寄せ、話し合いを行うことにした。
それに対し、「アリューザ・ガルドとは神々のみが住まう地である」として、人間達を拒む神もいた。ヴァルドデューンの弟、ザビュールである。
ヴァルドデューンはザビュールをなだめたうえで、人間達の長をフォルタスに招いた。
人間の長はまだ若くはあったが、一族をうまく束ねていた。ひと月に及ぶ話し合いの結果、人間の長は神々の意思に深い感銘を受け、アリュゼル神族に対して心からの忠誠を誓った。
そして人間の長は、すべての人間をフォルタスに呼び寄せた。すべての神々とすべての人間達の前で、ヴァルドデューンと人間の長は宣誓を行った。これこそがはじめての誓いにして、永遠に朽ちることのない、“ディトゥアの誓い”である。
宣誓の後にはひと月に渡って宴が催されたという。歌や音楽、酒などが、この時はじめて世に出たとされている。
神々は各々の内包する色と魂を、一部ずつ人間に分け与えた。これにより人間は神族へと昇華することになった。
“護るもの”ディトゥア神族の誕生である。彼らの長は、ヴァルドデューン直々に名を頂いた。その名こそがイシールキア、すなわち“並びうる者のない導き手”である。
ディトゥア神族はこうして、アリューザ・ガルドを守護する神として存在することとなるのだ。
[神々の繁栄と、ドゥール・サウベレーンの顕現]
アリューザ・ガルドでは神々の加護のもと、生命と自然とが創造されていった。アリュゼル神族が歩いた地は肥沃な大地となった。また神々の歌声は朗々と世界中に響き渡り、それは空気すらも感銘させ、雨や雪を降らせて大地を潤すのであった。
こうしてアリュゼル神族は世界を美しく彩らせながら、数多の生命達の理想郷を築き上げていった。
アリュゼルの住まう荘厳なる“フォルタス”は天空高く昇って全世界を見渡せる位置につき、世界の存在意義を紡ぎ続ける。一方で、ディトゥアは地上の館“エヴウェル”にてさまざまな事象を束ねていった。
ある時、アリューザ・ガルドの南西部の山々から大きな火柱が天高く上った。その炎はディトゥア達をたやすく寄せ付けず、三ヶ月に渡って燃え続けた。やがて炎が消えたとき、そこから異形の生命が姿を現した。
ドゥール・サウベレーン《龍》である。
最初のドゥール・サウベレーンは、名をイリリエンと称した。この深紅の龍王は次元を乗り越えるという禁忌を破ってまでして、アリューザ・ガルドに現れたのだ。そしてそれゆえにイリリエンは深く傷ついた。龍王はアリュゼル神族のひとり、レオウフィックによって介抱され、やがては互いに心を通わせるようになった。
美しい深紅の龍は、その身体が十分に癒えると、神々に申し立てた。
『“次元の扉”を解き放たれよ。さすれば事象界は地上と近しい存在となり、火が、水が、大地が、そして風が、この地にさらなる祝福と癒しをもたらすのだ』
“次元の扉”とは、世界の裂け目。アリュゼル神族がこの世界に進入してきた場所であるが、古神や混沌の流入を恐れて、それ以降固く閉ざされていた。
だが、それから幾千もの年を経て、アリューザ・ガルドの摂理は確定した。もはや太古の勢力が侵入できる余地などない。ヴァルドデューンとザビュールは互いに承諾し、レオウフィックに命じて“次元の扉”を開け放った。
火・水・土・風の事象界はアリューザ・ガルドと繋がり、イリリエンの言葉通り、世界はさらに美しく彩られていくのであった。火の世界はイリリエンが守護し、その他の事象界はディトゥア達によって護られていくこととなる。
また、“次元の扉”の開放によって、“次元の狭間”という名の、物体を伴わない幻想的な世界が誕生した。
夜になると星々が全天を覆うようになったのもこの頃からである。星々は、アリューザ・ガルドとは異なる次元世界の放つ煌めきである。
[人間の創造]
こうしてアリューザ・ガルドの運行が整ったので、アリュゼル神族は世界の守護をディトゥア神族に託し、自分達は天の彼方にて永遠に見守ろうと決意した。創造の最後にあたり、アリュゼル神族は人間を創造した。これにおいて意外にもザビュールが他の神々の導き手となり、幾多の生命が誕生していく。
最初に創造したのはエシアルル。彼らは水の事象界に属するものであるが、人間は水の中では生きていけないため、地上で最も水と近しい存在である森の加護を受ける存在となった。
次いで風の加護を受けるアイバーフィン、そして地の加護を受けるセルアンディルが創造された。火については既にドゥール・サウベレーンが守護していたので、新たな種族の創造はなされなかった。
こうしてアリューザ・ガルドは、神と人との理想郷となり、一万年にも渡って至福の時代を送ることとなる。
この後、アリューザ・ガルドが限りなく深い絶望によって支配されるなど、天帝ヴァルドデューンでさえ予想だにしなかったであろう。
四. 大暗黒紀
ザビュールの反乱。神々の戦い。
神々と人が住むアリューザ・ガルドのなかにあって、孤高の存在であったドゥール・サウベレーンの中に、人間になりたいと願う者が現れるようになった。
龍は自分達の持つ知識と力をもって、人化のすべを形成するに至ったのだ。これは龍の英知がいかに神々に近しいものかを物語っている。
龍王イリリエンは難色を示したが、人化を切望する龍達の願いを受け、最後には理解するようになり、ヴァルドデューンに申し立てた。
ヴァルドデューンは、龍の意外な申し出に驚きはしたものの、人化を承諾した。
かくして、炎の加護を受ける龍人、ドゥロームが誕生した。
人間達は、各々の種族によって言語が異なっていた。
当初は何ら問題が起きなかったが、各種族が交流を始めるに従い、言語の違いは大きな妨げとなる。
“力”を統括するアリュゼル神であるトゥファールは、人間達に新たな言葉をもたらした。ラズ・デンと呼ばれるこの言語は、アリュゼル神族の言葉であるタス・アルデスを人間が発音可能なように簡素化したものである。
アリュゼルの子らである人間達には馴染みのある言葉であったため、ラズ・デンはすぐにもアリューザ・ガルドの共通語となった。
だが、ラズ・デンには大きな欠点があった。もともとが神の言葉であるゆえに、発する言葉自体が大きな力を持ってしまっている点である。
[フォーユ・ネェルンの大禍]
かくして、フォーユ・ネェルンの大禍は起こるべくして起きてしまった。
人間達の言葉の裏に潜む負の感情――妬みや悲しみ、怒りなど――がアリューザ・ガルドに蔓延していき、世界は重苦しい雰囲気に包まれた。
やがて空気は障気を帯び、水は毒となっていく。
そして――蓄積された負の障気は、ついに弾けた。
“滅びのことば”によって、である。
その言葉はラズ・デンの中でも最も短い単語群によって形成されており、それまでにも祈りや呪いのために日常的に使われていたものらしい。
その言葉が突如、とてつもない力を発揮したのだ。
世界はかたち無き力の暴走によって壊滅の危機に瀕する。その有様は、のちの“魔導の時代”における魔導の暴走に酷似するものであったが、被害ははるかに甚大であった。
アリュゼル神族は地上に降臨し、ついに暴走をくい止めた。
しかし、世界に平和は訪れなかった。人間達は言語を取り上げられてしまったのだ。
神々の降臨の折に、ザビュールが人間達の言葉を封じたのである。これにより人間達は話すべき言葉を失い、彼らはひどく混乱した。
――人間達を野放図にした挙げ句の果て、世界は破滅にさらされることになったのだ。人間達に自主性など与えてはならない。あくまで、アリュゼル神族が主体となってアリューザ・ガルドをはぐくむべきだった。しかし、アリュゼル神族も腑抜けてしまった。もはや兄に天帝たる資格などない――
もともと他のアリュゼル神族とは考えを異にしていたザビュールは、そう考えるに至った。そして、自分こそが至高の神たらんと、兄ヴァルドデューンに対して反旗を翻したのだ。
[冥王ザビュール]
ザビュールは単独でヴァルドデューンの宮居に攻め入った。しかしヴァルドデューンの姿はなく、ザビュールのこの企ては失敗に終わる。
アリューザ・ガルドの西の果てにある裁きの塔にてザビュールは裁かれた。すべてのアリュゼル神族を前にして、ザビュールは深く頭を下げ、改心したかに見えた。
しかし、これまでの行動はすべて、ザビュールの策略であった。法廷が終わる直前になり、ザビュールは己が持つ強大な力をはじめて世にあらわしたのである。
内包するあまりにも膨大な、“まったき黒き色”を、憎悪の衣と化して身にまとったザビュールは、その場で七柱ものアリュゼル神を殺した。それら死んだアリュゼル神の魂を自らの魔力と還元し、ザビュールはその魔力をさらに膨張させて、次元をひとつ、新たに創りあげてしまったのだ。
魔界“サビュラヘム”の創造である。
ザビュールは、魔界の唯一の神、“冥王”として君臨することを明らかにした。さらに、アリューザ・ガルドを永遠に冥王の支配下に置くことをヴァルドデューンに対して宣言すると、邪悪な笑いと共に魔界へと消え去った。
魔界へとつながる次元の扉は、アリューザ・ガルドの東部域にすでに出来上がっていた。ザビュールは、自ら創造した魔物を魔界からアリューザ・ガルドへと解き放った。
神々が手をこまぬいていると、ディトゥア神族や人間達、龍の中にザビュールに魅せられた者が出てくるようになった。深く絶望したこれらの者達は、アリュゼル神族の説く理想は脆く儚いものであると考え、すべてを凌駕するザビュールの超常的な力に魅せられたのだ。
ザビュールはこれらの者達、特にディトゥア神族を受け入れることがなかった。原初の民であるディトゥア神族こそ、アリューザ・ガルドにとって邪魔な存在だと冥王は考えていたからである。
それでも必死にすがるディトゥア達に対し、ザビュールは、彼らの肉体を異形のものに変化させてしまった。
「余は貴様らの姿をこのように変えることができるのだ。それでも、この冥王に仕えるか?」との問いに、ディトゥア達はひれ伏し、心からの忠誠を誓ったのだ。
ザビュールは彼らを忠実なる下僕であると認め、ディトゥア達を天魔、人間達を魔族、龍達を漆黒なる冥底の眷族とした。
かくして魔界の勢力は地に満ち、アリューザ・ガルドは千年以上に渡って、恐ろしい暗黒のなかに閉ざされることとなる。
[神々の戦い]
千年もの間、神々や人間はザビュールの暴虐をただ傍観していたわけではない。彼らは時折、機が熟したと見たときに魔界サビュラヘムにうって出たのだ。しかし、その結果はいつの時代も悲惨なものとなっていた。どれくらい多くのディトゥアや人間の血が流れたのか定かではない。
アリュゼル神族はついに、ザビュールを滅ぼすために天空の宮殿フォルタスをあとにし、再度アリューザ・ガルドに降臨した。神々は持てる力をすべて顕現させてまで冥王を滅ぼすことにしたのだ。
だが人間達にとっては、神々の超絶的な力に耐えることができない。そのためアリュゼル神族は、神々の戦いに終止符が打たれるまで、人間達を眠りにつかせることとした。
ついに神々同士の戦いが始まった。アリュゼル神族が地に降臨すると同時に、冥王を初めとした魔界の軍勢もアリューザ・ガルドに出現した。
神々の戦いは熾烈を極めた。
戦いのさなか、唯ひとつの大陸はふたつに分断された。多くの大地が海に沈み、また海底が隆起して新たな大地となった。
山は割れ、雷は全天に轟き、地震と洪水が大地を襲う――世界中に天変地異が襲い来る中、神々と冥王の軍勢は一進一退を繰り返していた。
だが、一人のデトゥン・セッツァルの裏切りによって戦局は終局に向けて大きく動いた。
ディトゥア神族としての本来の責務を思い起こしたこの天魔は、魔界へと通じる門を固く閉ざしたのだ。
退路を断たれた魔界の軍勢は浮き足たち、アリュゼル神族やディトゥア神族によって次々に打破されていった。ヴァルドデューンはついに、ザビュールと戦いを始めた。あとがないザビュールは、戦いのさなか逃亡を図った。
アリュゼル神族は、冥王を討ち滅ぼすことは叶わなかったものの、神々の力によって、逃げ行く冥王を暗黒の宙に幽閉した。
アリューザ・ガルド大破壊の果てに、神々の戦いは終焉を迎えたのだった。
[アリュゼル神族の離別]
冥王を封じたとはいえ、もはやアリューザ・ガルドは荒廃し、かつての楽園の姿を留めるものではなくなってしまった。
アリュゼル神族も自ら危惧していたように、神々の力はアリューザ・ガルドで行使するべきものではなかった。神々の力とは、世界の摂理をはるかに超越するものであった。
結果、大陸は分断され、神々と人間の理想郷であるはずの世界は、永遠に失われたのだ。
アリュゼル神族は、アリューザ・ガルドから離れる決意をする。自分達は遙か天の彼方、“アルグアント”という名の天界の次元に移り、そこから世界の存在意義を与えるように、見守り続けることにした。
アリューザ・ガルドの運行を任されるのは、ディトゥア神族である。
ヴァルドデューンは、ディトゥア神族の長であるイシールキアに力を託した。これによりイシールキアは、アリュゼル神族に等しい力を持つようになった。
またイシールキアは、四匹の聖獣を授かった。すなわち、東方の守護イゼルナーヴ、西方の守護ファーベルノゥ、南方の守護エウゼンレーム、北方の守護ビスウェルタウザルである。
戦いを終局に導いたデトゥン・セッツァルは改心し、イシールキアのもとを訪れた。この天魔すなわち浄化の乙女ニーメルナフは、ヴァルドデューンの后フルーウェンの祝福を受けてディトゥア神族となった。ニーメルナフはのちにイシールキアの妻となる。
ヴァルドデューンらアリュゼル神族が去った後、イシールキアは聖獣達を四方に飛ばし、全土に重くのしかかっている灰色の雲を引きちぎらせた。雲の合間を縫うようにして光の筋が次々と差し込み、千年ぶりに太陽が姿を現した。
それとともに、眠りについていた人間達が目覚めることとなる。
ディトゥア神族のアヴィトは、言葉を失ったままの人間に新たな言語を授けた。この言語はハフトといい、ディトゥア神族の言語テウェン語から派生したものであり、ラズ・デンのような力は持ち得ない。
こうしてアリュゼル神族の時代は去り、アリューザ・ガルドの歴史は人間によって紡がれていくことになる。
五. 扉の時代
諸種族の交流と争い。ハウグィードの戒め。
“大暗黒紀”を経て、アリューザ・ガルドは地核の大変動が起こった。
唯一の大地は二つに分断され、神殿エヴウェルを核とする世界の中心部、それと南西部の神殿都市ラディキアは海深く没した。
今ではラディキア高山系の頂が、海上に頭を出しているのみであり、これをラディキア群島と呼ぶ。
また北方では大地が隆起し、カダックザード、アリエスの高山地帯を形成した。
長きに渡る眠りから目覚めた人間達には過去の記憶が薄れていたものの、壮麗な神殿エヴウェルが世界から失われたのを悲しみ、大陸を“エヴェルク大陸”と名付けた。
この時代においては東方大陸であるユードフェンリル大陸の存在は人間には知られていない。“統一王国の時代”における種族移動により、はじめて明らかになるのだ。
ディトゥア神族は、アリューザ・ガルドにとどまる決意を固めた者、次元の狭間にて世界の運行を見守る者との二者に分かれた。前者は“宵闇の公子”レオズスや、“エシアルル王”ファルダインが知られ、後者はイシールキア、“慧眼の”ディッセといった面々が知られている。
[人間達の勢力]
目覚めた人間達はそれぞれの勢力を繁栄させていった。
また、アヴィトにより与えられたハフト語は、次第に各種族ごとに微細な差違が生じるようになり、やがて各種族ごとの言語と化した。共通語であったはずのハフトは次第に廃れ、世界共通語はアズニール語が登場してくる千年後まで待つこととなる。
セルアンディルは、イルザーニ地方を中心とした肥沃な平野を拠点とし、大いに栄えた。後にいさかいが起こるものの、“扉の時代”の大部分の時期においてセルアンディル達は平和な時代を送り、町を作りあげるのであった。やがていくつかの町は統合され、共同都市となる。
エシアルルはあまり外界と交わらず、ウォリビア及びアブロットの大森林にてひっそりと暮らしていくこととなる。彼らの生活は現在に至るまで変わらない。
ウォリビアの森林には巨大な木が生えていた。その太い幹は銀色であり、葉は落ちることなく常に青々と茂っている。エシアルルはこの大樹を神聖視し、“世界樹”と呼んだ。またディトゥア神族のファルダインが、この世界樹を住処としたことから、ファルダインはいつしかエシアルル王と称されるようになった。
しかしこの時代において、もっとも栄えたのはアイバーフィンとドゥロームである。
彼らは共に翼を有し、またそれぞれ風と火という武器を持っていた。なにより、その勢力範囲が隣接していたことが、彼らに戦いの道を歩ませることになった。
[天空の会戦]
アイバーフィンとドゥロームの間で、小競り合いはしばしば起こっていたが、とうとう戦いの火蓋が切って落とされた。翼を持つ者としての尊厳にかけて、大空の領有を巡る戦いが始まったのだ。
第一次会戦は一年間繰り広げられたが、突如世界を襲った大寒波のため、休戦を余儀なくされた。二年の異常気象の後、戦いはもはや起こらないとも思われた。しかし実際には両種族ともに戦力がまとめるための準備を行っていたのだ。
三年後、再度戦いは幕を開けた。第二次会戦は実に五年にも渡り、熾烈を極めるものとなった。これはアリューザ・ガルドにおいて、最初で最後の空中戦争である。
空を飛び交う両種族は、おのの持てる力を存分に発揮した。ドゥロームの放つ炎が大地を焼き、アイバーフィンの起こす嵐が草木を根こそぎ奪い取った。
地上に住む種族は嘆き悲しんだが、アイバーフィンとドゥロームは常に空にあったので、地上の様子に関心を示すことなく、戦いはさらに激化していった。
そしてついに戦いは最終局面を迎える。
エシアルルの嵐とドゥロームの炎が激しくぶつかり、両軍ともに多大な犠牲者を出した。のみならず――風と火との融合された力が大地を襲ったのである。
ラデルセーン地方は一瞬にして火の海と化した。アイバーフィンとドゥロームの多くが大火のために死んでいった。
嵐を伴う大火はラデルセーン地方のみならず、北上していく。この凄惨な様子は、世界樹からも見て取れた。ファルダインは朱に染まる夜空を見て、イシールキアに上奏する決意を固めた。
突如、天高くから滝のごとくに水がなだれ落ち、火の勢いが止まった。イシールキアの四匹の聖獣は海の水を巻き上げた後にひとところに集い、これを落としたのだ。
火の勢いが止まると共に、アイバーフィン、ドゥロームの両軍は申し合わせたかのように兵を退いた。
戦いはここに終結した。
[土の扉の占拠]
時を同じくして、セルアンディルの小都市においてもいさかいが起こっていた。
それまで商業において健全に競争を続けていた諸都市群であるが、世界を襲った大寒波により財政は破綻した。ようやく気象が正常に戻ったあとも経済情勢が好転することはなかった。やがて各都市はお互いの利益を巡って衝突、時には武力を伴った戦いまで起こるようになった。
そのような中、共同都市ウヴァイルは、イルザーニ地方の聖地、“テュエンの扉”を占拠してしまう。扉を介してアリューザ・ガルドに現前する土の力、龍脈の利権を得たウヴァイルは、共同都市群の頂点に立つ。
ディトゥア神族の忠告をも聞かず、彼らは利権の専横を続行するのであった。
[ハウグィードの戒め]
裁きを司るディトゥア神族の“天秤の測り手”ハウグィードは、人間達の尊大な態度を改めさせるべく、ヴァルドデューンとイシールキアの名の下に戒めを与えた。
アイバーフィン、ドゥロームからは翼を奪い取った。これ以降、彼らは各々の事象界に赴き、試練を受けない限りは、本来の力が発揮できなくなった。
またセルアンディルからは“テュエンの扉”の所在を隠し、容易には土の世界の恩恵を受けられないようにした。
これにより、翼を持つ民達が空を占有することは不可能になり、セルアンディルが地上の主権を得るようになる。翼を持つ民は、再び小さな社会においての生活に戻り、先の増長を戒めとして、再び野望を抱くことはなくなった。彼らは焦土と化したラデルセーン地方をあとにし、安住の地を求めて移動を開始した。
エシアルルは、大森林の中でひっそりと隠者のごとくに営みを続けており、このような事態に無関心であった。アリューザ・ガルドと“慧眼のディッセの野”を行き来する彼らは、精神体としての側面が強く、アリューザ・ガルドのみに固執することがなかったのだ。
地上の一大勢力となったセルアンディルであるが、ハウグィードの戒めによって土の恩恵を受けられなくなった痛手はやはり大きく、彼らはセルアンディルとしての力を急速に失っていくのである。やがて彼らは土の加護を自ら放棄し、“結束せし力”バイラルとなっていくのだ。
バイラルは驚くべき結束力を持ってして共同体をまとめあげ、アリューザ・ガルドにはじめて、人間の王国を興すのである。
六. 劫火の時代
王国アル・フェイロス。魔法体系の誕生。帝国主義的膨張と瓦解。
アイバーフィン及びドゥロームの両種族は、先の“天空の会戦”によって一面の焦土となり、生活が不可能となったラデルセーン地方から移住を開始することとなった。天空より大地を見下ろしていた時分に、彼らの住まうべき場所を既に見つけていたのだ。
アイバーフィンは、北方のアリエス地方を目指して大移動を始めた。当然ながら移動の途中には、エシアルルの領域であるアブロット地方とウォリビア地方を通過することになったが、両種族ともお互いに不干渉の態度をとり、いさかいごとなどの無いまま、さらに北上を続けようとした。
一方、ドゥロームは海の向こうに安住の地を求めるようになった。彼らはラデルセーン地方にとどまりながら航海術を独自に編み出していく。とりあえずの目的地は、ラデルセーン東方に位置するラディキア群島であるが、ドゥローム達は遙か東方へ思いを馳せていた。すなわち、ユードフェンリル大陸への移住である。
しかし、彼ら両種族の思いどおりには歴史は動かなかった。バイラルの興した王国、アル・フェイロス。その軍隊の侵攻により、とどまることを余儀なくされたのである。
[アル・フェイロス王国の建国]
“ハウグィードの戒め”により、セルアンディル達は土の事象界“テュエン”へとたどり着く道を失った。ここで彼らはむやみに道を探すことをしなかった。時間の浪費であると考えるに至ったセルアンディルは、むしろ自ら進んで土の力の加護を放棄したのである。
そのため、彼らが本来持ち得ていたセルアンディルの癒しの力は損なわれ、また寿命も短いものとなってしまったが、彼らにはそれらの弱点を補えるだけの資質を持ち得ていた。ここ一番というときの結束力の高さは、他の種族を圧倒するのである。彼らはやがて“結束せしもの”を意味するバイラルを名乗り、共同体同士の小競り合いを短期間でおさめたのだ。
最大の勢力を誇った共同都市は、なおもウヴァイルであったが、“ハウグィードの戒め”以前の威圧的な態度は影を潜めていた。聖地イルザーニを専横したがために神々の怒りを買ったことは彼ら自身一番痛感するところであったためである。
ここにおいて共同都市ウヴァイルは、都市同士の結束を強くする仲介者の役割を果たすこととなる。いくつにも分かれていた勢力は次第に固まり、ひとつの大きな勢力を築くこととなった。これがバイラルの興した人類はじめての王国、アル・フェイロスである。フィレイク地方のティン・フィレイカを王都においた。
王国と名が付いているものの、後の歴史に現れるイクリークやアズニールのような中央集権君主制国家ではなかった。アル・フェイロスの王の在位期間はおよそ十年ほどであり、国王は各都市の長から選出される。そのため、共和制の色が濃厚であった。国民の多くはホルスびとであった。
建国の年より歴史書が編纂され、また暦法が世に広まる。アル・フェイロス暦である。
[新たなる力、魔法]
アル・フェイロス国内は文化的美術的にも繁栄したが、いっぽうで人間にとって大きな発見があった。それこそ魔法の力である。
土の加護を無くしたセルアンディル、すなわちバイラルにとって、土の力に取って代わる新たな力を得ることこそが夢であった。いくらバイラルが人間の中で最大の勢力を持っているとはいえ、どう猛な竜達“ゾアヴァンゲル”や魔物に対しては無力であるからだ。
力の覚醒は突然に起きた。今までの常識では考えられない超常の力を使える者が現れたのだ。彼らこそ魔法使いの始祖である。魔の力を持った異端の民として、当初は蔑まれた彼らであるが、その力は脅威である。
アル・フェイロスは懐柔策として、うまく彼らを社会の上層部に組み入れた。魔法使いは最良の環境で自信の持つ力の研究を存分に行うことが出来るようになったのだ。
[アル・フェイロス軍による制圧]
アル・フェイロス王国の固い結束力は揺るぐことがなかった。それゆえ、諸都市の統一では飽きたらず、バイラル達はさらに勢力を拡大し始める。フィレイク地方からイルザーニ地方への拡大はたやすかった。このイルザーニ地方はセルアンディルにとっての聖地であるがゆえに争いは避けられ、アル・フェイロスは無血でイルザーニを版図に加えることができた。
その後、南方のシャルパ地方とドゥータル地方に進軍するが、既にこの地にて徒党を組んでいたベルドニースびと、ラクーマットびとと激しく対立する。しかしながら魔法の助力もあり、五年の時を経てこの地を制圧する。
これによりアル・フェイロスの建国から僅か二十年足らずで、すべてのバイラルがアル・フェイロスの名の下にひとつとなったのである。
[大森林を焼く劫火“ルアラン”]
征服意欲に駆られるアル・フェイロス王国はさらに版図を拡大していくことになる。アル・フェイロス最後の王となったルヴォネルドは、アリューザ・ガルド全土を制覇することを宣誓、まずはウォリビア地方の制圧に取りかかった。
平穏を望むエシアルルの意思を汲んだファルダインは和解を申し出るが、ルヴォネードはこれを無視、魔法の火をもってウォリビアの大森林を焼いていった。
北部へ向けて移動中のアイバーフィンの中で風の力に長けた者達が逆風を吹かせてアル・フェイロス軍に一矢報いるものの、アル・フェイロスはさらに強大な魔法の劫火“ルアラン”を発動させた。これにより、アイバーフィンにも多大な被害が及び、風を操る翼の民にもなすすべが無くなった。
一方、ようやくラディキア群島へ移住していたドゥローム達もこの争いを止めるべく、龍達“ドゥール・サウベレーン”と結託し、ティン・フィレイカへの海からの攻撃を試みた。しかしながらドゥロームがアル・フェイロスに至ることはなかった。シャルパ地方の東岸にたどり着こうとしたその時、すべての船は一瞬にして海の藻屑と化し、また空を行く龍達も翼を打たれて海に落下していったのだ。これはアル・フェイロス軍の力ではなく、何かしら超常の力の発動ゆえである。以来、この地域は“忌まわしの海”アガンディッケと呼ばれ、今なお何人たりとも寄りつこうとしない。
[ルヴォネードの謝罪]
さて、魔法の劫火をもって大森林は次々に焼かれていった。
だが、エシアルル王ファルダインは、ついにディトゥア神族としての力を行使することとなる。ファルダインの力は強大な呪いとなり、アル・フェイロス国内の穀物や水を毒に変えてしまったのだ。
冬の季節に至り、ついにアル・フェイロス王国の財政が破綻してしまった。ルヴォネードはすべての軍隊をウォリビア地方から退かせ、単身で世界樹に赴いた。その地には、事態の重さゆえにディトゥアの長イシールキアまでもが姿を見せていたのだ。彼はイシールキアの名に誓い、ファルダイン及びエシアルルに非を詫びた。
これが世に言う“世界樹の宣誓”である。
以降、バイラルが他種族に対し攻撃を行うことは禁じられたのだ。
エシアルルは再び、静謐なままに森を護り、アイバーフィンは移動を再開、ついにアリエス地方にたどり着くこととなる。
[王国の没落、忘却の時代へ]
国力が疲弊しきったアル・フェイロスには、軍事面でも文化面でも、もはやかつての勢いが無くなっていた。五十年足らずで急激に膨張した王国は、早くも没落の時代を迎えてしまったのだ。
世界樹の宣誓から五年を待たずして、アル・フェイロス王国は瓦解した。
そして――音もなく、“忘却の時代”が訪れる。
全く謎の空白期間が。
七. 忘却の時代
歴史書は言うに及ばず、神々の記憶にすら残っていない空白期。
“忘却の時代”とは、“劫火の時代”が過ぎ去ったあとに訪れた、全くの空白の時代である。
この間、歴史書は一切存在せず、ながきを生きるエシアルル達の記憶はおろか、神々の記憶からも消え失せているのだ。
アリューザ・ガルドにおける最大の謎とも言える。
確かなことは、この忘却の時代そのものが六百年に及んだこと。そして、過ぎ去ったあとには、ティン・フィレイカを中心としたアル・フェイロスの中央都市は崩壊し、その痕跡すら判別がつきがたいほどに遺跡化していたこと。魔法の研究に歯止めがかかり、その大部分が失われてしまい、術やまじないのみが細々と残るに過ぎなくなったこと。またすでにユードフェンリル大陸への人間達の移住が行われていた、ということである。
では、なぜこのような歴史の空白が訪れ、また去っていったのだろうか? しかしながらその質問に対する答えは存在しない。すべては謎の中である。
自然の大災害、アリュゼル神族の怒り、魔導の暴走、混沌の支配、冥王ザビュールの復活――過去から現在に至るまで、さまざまな説が賢人やさらにはディトゥア神族のなかでも持ち上がるが、いずれも確固たる証拠がない。
八. 統一王国の時代
イクリークの繁栄。不死の探求と大きすぎる代償。
“忘却の時代”という、歴史の大断絶が過ぎ去ったあと、世界状勢は大きく変貌を遂げていた。
エシアルル達の領域は全く変化していない。
アイバーフィン達は北方アリエス地方へ移り住み、冷涼な山岳地帯であるこの地域を安住の地とした。
ドゥローム達は、ごく一部の者が“天空の会戦”で荒れ果ててしまったラデルセーン地方を元通りにするために残ったようだが、ほとんどの者はラディキア群島や、ユードフェンリル大陸のオルジェス地方に移り住んでいた。
バイラル達はこの時代、戦乱に明け暮れていたようである。諸勢力がしのぎを削っていたのであった。
また、アル・フェイロス遺跡の中心部は“禁断の地”とされ、石壁で囲まれて立ち入りが固く禁じられるようになっていた。
[バイラル達の勢力争い]
エヴェルク大陸ではソルセイア帝国と前アズニール王国が領土争いを繰り広げていた。おそらくソルセイア帝国は、以前は広大な領土を占めていたものと想定されるが、この時代にあっては凋落していたようである。
勢いに乗る前アズニール王国であったが、帝国と争うためには後方の憂いが存在していた。ひとつは、メルリアの攻撃である。禁断の地の守護者と称するメルリアという勢力が幅を利かせるようになり、たびたび局地的な攻撃を受けていた。もうひとつは、海上貿易の要衝であるカイスマック島の領有を巡って、ユードフェンリル大陸の前イクリーク王国と対立していたことである。
ユードフェンリル大陸においては四つの新興勢力があった。そのなかで最も力を伸ばしたのが前イクリーク王国である。王国は早々にソルセイア帝国領を掌握、リウォンルクやライオフに対しても睨みをきかせていた。
時のアズニール王ウォード・アズニールは、イクリーク王フウェンディン・アントスと会談を行い、相互不可侵の条約を締結した。カイスマック島の領有権はイクリークのものとなったが、後方の憂いを断ち切ったアズニールは、メルリアとも和解し、いよいよソルセイア帝国との争いに総力を結集することにした。
二十年に及ぶ戦いの末、アズニールはエヴェルク大陸における主権を確立した。
一方のイクリークは次々と対抗勢力を併合、アズニールより十五年先んじてユードフェンリル大陸の宗主となった。
イクリークとアズニールは敵対関係に陥るかと懸念されたが、アズニール王はイクリーク王の、人間による統一王国建国という意思に感銘を示し、アズニールはイクリークと併合することとなった。歴史上名高い“慈悲のもとの無血譲渡”である。
王権を自らの意思で譲渡した事例は古今例がない。(ただし、アズニール王朝建国の際、レツィア・イナッシュによりアズニール家に王座が譲渡されている。これについては“黒き災厄の時代”にて著述する)以降、アズニール家はイクリーク王朝の執政家となる。
若き国王ジェナーグ・アントスは開かれた王朝を主張し、他種族との接触も積極的に行った。そのため、アイバーフィンやドゥロームもイクリーク領内に多く居住するようになる。ここに人類の統一王国、イクリーク王朝が誕生したのである。
王都はユードフェンリル大陸のガレン・デュイルである。
暦法については、すでにアル・フェイロス暦が使われなくなり、各勢力が独自の暦を用いていたが、ここに至ってアル・フェイロスの暦法が復活、若干の訂正を伴ったそれはイクリーク暦法となり、イクリーク統一の年をイクリーク暦元年と定めた。
以降、約六百年に渡り、この平穏なイクリークの時代は続くことになる。
[イクリーク王朝の繁栄]
イクリーク王朝は、それまで一部の商業目的を除いて一般の利用が禁じられていた渡航を解禁した。さらに航海術についてもひろく公開したため、この時代は船舶が海洋を行き交う大航海時代となった。
商業は大いに栄え、またそれに伴い人々の生活圏も拡大し、イクリークの版図も広がっていった。ドゥロームやアイバーフィンも、イクリーク統治の恩恵を十分に受けた。こうして多少のいさかいを除いて、きわめて平和な時代が過ぎ去っていった。
イクリーク王朝没落のきっかけは、“色のくすみ”であった。
世界のありとあらゆる事物の色が薄れていったのである。
みずみずしい若木の緑はもやがかかったように不鮮明になった。朝夕の太陽の赤は弱々しく、紺碧の海は重たい灰色と化した。
世界は終わりを迎えようとしているのではないか?
“魔導の時代”を経た現在でこそ、色のくすみの原因が「万象の内部を流れゆく原初の色が、何らかのためにせき止められてしまったため」と理論的に説明できる。
しかしながらこの時代においてはまだ魔導が存在しなかったため、人々はただ畏れるだけであった。やがて厭世の空気が世界を覆い尽くし、終末の退廃した雰囲気に満ちていった。
王政も同様である。イクリーク暦600年が経過した頃には建国時の気高い志は消え去り、人心はとうに離れていた。また王朝も民草に関心を示さず、ただただ緩慢な厭世の空気の中で腐敗していった。
[不死の探求、そして]
国王タイディア・アントスは陰鬱な野心に燃えていた。
彼はひそかに禁断の地に足を運び、そこからアル・フェイロス王国時代の魔術に関わる書物を入手していたのだ。
その中で特に彼の心を惹き付けたのは魔術の異端書である。これには不死の探求が記述されていたのだ。
それからというものタイディアは徐々に常軌を逸するようになり、忌まわしい儀式に日夜を費やすようになった。
そして、ついに彼は禁断の領域に足を踏み入れてしまった。
酸鼻きわまりない儀式の果てに、国王の体は異形のものと化した。あたかも魔族のような体に。
時を同じくして禁断の地では大きな亀裂が走り、数限りない魔界の住民が姿を現したのだ。
空は一面の暗黒に包まれる。
もはや色のくすみごときを嘆いている場合でないことに人々が気付いたときにはすでに遅かった。
冥王ザビュールがついに神々の呪縛から解き放たれ、暗黒の宙から降臨してしまったのである。
九. 黒き災厄の時代
冥王ザビュールの降臨と暗黒の支配。イナッシュの勲。
[世界を包む絶望]
冥王の復活により、アリューザ・ガルドのすべての色は飲まれた。
色の調和を失った太陽は黒に染まり、寒々しくなった世界からは季節が消え失せた。そのために農作物は枯れ果て、ドゥローム達の操る炎を用いた、新たな栽培法が確立するまでの五年間、飢饉に見舞われたのである。夜空を照らすはずの月は、夜の暗がりの中でも特に暗い色を放つようになり、暗黒の忌まわしさを際だたせた。
かくしてアリューザ・ガルドは闇の中に閉ざされた。
暗黒の宙の封印から放たれたザビュールはしかし、アリューザ・ガルドに姿を現すことなく魔界へと姿を消した。冥王といえども、千年以上に渡り幽閉されていたために力は衰えており、本来持つ力を癒すのには相当の時間を要するのだった。
こうしてザビュール本人は、降臨したとはいえ決してアリューザ・ガルドに姿をみせることなく、タイディアをはじめとした魔族に統治を委ねた。
禁忌の扉を開けてしまった張本人であるイクリーク王タイディアは、身も心も魔族と化しており、彼は居並ぶかつての臣下に対して、ザビュールの言葉を告げた。
冥王こそが世界に関わるすべての事象の支配者たることを認識すること。
冥王を畏れ崇めること。
禁断の地に生じた亀裂を深く掘り下げ、魔族のための大要塞を建築すること。
ザビュールはかろうじて人間の生存を認めたが、三箇条に従わぬ者、反逆する者に対しては容赦がなかった。そもそも彼は人間の自主性を認めておらず、神の絶対性の前には人間など矮小な存在の極みであるというのが持論だったのだから。
タイディアがイクリークの諸卿によって暗殺された折の復讐はあまりに有名である。麗しき王都だったガレン・デュイルは、火山が直下で爆発したかのように一瞬にして吹き飛び、すぐさま襲来した魔の眷族によって地獄絵さながらの大殺戮が行われたのだ。流域のヘイネデュオン河は血のために真っ赤に染まり、見せしめのために杭で貫かれた死体は、廃墟と化したガレン・デュイルを取り囲むほどの数に至った。
タイディアの後継には天魔のアルツァルディムが就いた。タイディアを屠ったところで、人間にとって状況が好転することなど無かった。
世界の守護者であるディトゥア神族にもなすすべが無く、人間は三箇条を受け入れざるを得なくなった。
こうして人間達にとって三百年にも渡る、絶望の歴史が幕を開けたのである。
[冥王を崇める者]
人間の中にもザビュールに心底傾倒する者もいた。
彼らに言わせると、ザビュールの支配が絶望であると感じるのは旧来からの慣習や倫理から抜け出せないためである、という。
ザビュールが構築しようとしているのは新たなる世界であり、秩序なのだ。人間が感じている苦しみを乗り越え捨て去ってこそ、真の安定――闇という力による安らぎが訪れる、というのが彼らの信条であった。
秩序と摂理の破棄と再構築という、この常軌を逸した信念はやがて信仰となっていく。神々が人間に近しい位置にいたために、それまでアリューザ・ガルドには宗教という概念が存在しなかったが、ここにはじめて唯一の宗教が――ザビュールを崇める暗黒の信仰が誕生したのだ。
冥王が封じられて以降、この信仰は固く禁じられているが、今なお世界のいずこかに確実に息づいているのだ。ザビュールの復活を待ち望んで。
[ドゥール・サウベレーンの戦い]
ザビュールの復活に対して、まず行動を起こしたのは龍達であった。平和な世にあっては事物などに関心を示さない龍達であったが、時ここにいたって彼らは魔族を追放すべく攻撃を繰り返した。
龍達の攻撃により、確かに多くの魔族はうち倒されたが、地の底から際限なく次の魔族が出現していく。龍達の中には魔界を目指して禁断の地の亀裂から深淵へと立ち入る者も現れたが、その多くは二度と大地に帰ることがなかった。
また、なかには冥王に魅入られ、黒龍と化した龍も少なくなかった。イズディル・シェインはかつての同胞に対して戦いを始めた。
ドゥール・サウベレーンはどうにかしてイズディル・シェインを魔界に追いやったものの、力を使い果たしてしまい、以来龍達は永きに渡る眠りについてしまったのである。彼らは“魔導の時代”の中期に至るまで目覚めることがなかった。
[聖剣の誕生]
一方でディトゥア神族は、アリュゼル神族の降臨を願い、幾度となく上奏するが、アルグアントに住むアリュゼル神族は動く気配をみせなかった。
イシールキアはすべてのディトゥアを招集し、冥王に抗う対策を講じた。この会談は魔の者の目をかいくぐるようにして、何度か密やかに行われた。
結論は、冥王その人をうち倒すほか無かった。この難題を乗り切る唯一の手段こそ、聖剣である。
ディトゥアの神々の力を一つの拠り所に結集、さらに鍛え抜くことにより超常の力を持つに至る剣、それが聖剣と呼ばれる大いなる力の道具である。しかし鉄や銅などといった自然の鉱物では聖剣を精製できない。
八本腕を持つ土の世界“テュエン”の王、ルイアートスは、自ら一つの腕を切り落とし、そこに大地の力を注ぎ込んで他にはない鉱物を創り上げた。この鉱物には大地をはじめとした各事象界の守護の力が内包していたほか、絶対の力すなわち光すらも秘めていた。
神々はルイアートスに力を委ね、この土の王のもとでついに聖剣が誕生した。これこそが冥王を倒しうる唯一の力、“ルイアートスの腕”ガザ・ルイアートである。
しかしながら超常の存在、聖剣を鍛え抜いたためにルイアートスの力は失われ、ついに彼は魔族に殺されてしまう。
そんな中、ルイアートスの遺志を継ぎ、彼からガザ・ルイアートを受け取ったのは“宵闇の公子”レオズスであった。
[レオズスの役割]
レオズスはディトゥア神族のなかでも闇を司る神である。その属性ゆえに、かつての大暗黒紀においてザビュール側につくのではないかと疑念がもたれたのだが、レオズスは結局のところ魔の一族になることはなかった。
闇を絶対とするザビュールに対して、レオズスは光あってこそ闇が成り立つと考え、あくまでもアリューザ・ガルド世界の現状維持を望んでいるのだ。ザビュールに屈することのない気高い意思により、イシールキアはもとよりアリュゼル神族からの信頼を得るに至った。
しかしながら、レオズスには大きな制約がある。レオズス本人は、まったき黒き色を宿す冥王その人を倒すことが出来ないということだ。また、光を秘める聖剣も、闇を司るレオズスの手にあっては本来の力を発揮することが出来ないのだ。
(逆に言えば、聖剣の持つ絶対的な力を抑え込むことが出来る唯一の存在がレオズスである、という事である)
レオズスは、この剣が最大限の力を発揮するのは、人間が聖剣を握るときであることを知った。
彼はアリューザ・ガルドを放浪し、腕の立ちそうな人間を見つけたが、その者は聖剣を持った途端に心をうち砕かれてしまった。聖剣自身にも何らかの意志が存在し、所有者たる資格を持つかどうか試練を与えるということをレオズスは知った。そして聖剣を持つに値する者を捜す旅が困難を極めることも。
しかしやがてレオズスは、ついに望んでいた人物を見いだす。その者こそイクリーク王朝の血統を持つ、レツィア・イナッシュであった。
[イナッシュの勲]
レツィア・イナッシュはアントス家の一族、イナッシュ家の末裔であった。この時代のイクリーク王朝は傀儡と成り下がっていた。しかしレツィアは国王となるとすぐに、魔族に抗うべく、ひそかにエシアルル王ファルダインやドゥローム、アイバーフィンの長達、さらには地下に潜む反乱同盟(冥王に従うことを良しとしない者達の集まり)にまで連絡を取り合い、現状の打破を目論んだのだ。だがこの目論見はザビュールを恐れる者達によって露見してしまい、イナッシュは王座を失い、流浪の身となったのだ。
後ろ盾をなくしたイナッシュを殺すべく、刺客が数多く送られるが、イナッシュはこれをすべてうち破った。しばらくはイナッシュの消息は知れないものとなった。
それから二年後、彼の名は再び世に伝わるようになる。冥王の代行者であり、大要塞タス・ケルティンクスの王ともなったアルツァルディムを倒したのだ。イナッシュの力はディトゥア神族にも匹敵するほど、人の持ちうる力を超越していたとされる。そうでなければ天魔を、すなわちもとディトゥア神族を倒せるはずがないのだ。
その彼のもとに現れたのがレオズスである。レオズスはイナッシュに聖剣を渡そうとした。すると聖剣はするりと、イナッシュの手に収まり、まばゆく光り輝いたのだ。ガザ・ルイアートはイナッシュを所有者と認め、彼にさらなる力と、土の民セルアンディルとしての能力をもたらした。
イナッシュはレオズスと共に、タス・ケルティンクスの深淵に降り、ついに魔界の領域にたどり着いた。
光り輝く聖剣を手に、イナッシュとレオズスは魔界の深層部にて、冥王と対峙することとなった。
冥王の力がいまだ癒されていないとはいえ、その存在感は圧倒的なものであった。彼の姿は神々しいまでに美しいが、その美しさは人間の想像をはるかに超越したものであり、ひとめ見ただけで魂までも消去される。また、冥王の一挙一動すらも畏怖に値し、人間の体は容易にうち砕かれる。彼の話す一言は、強大な魔法となって襲いかかるであろう。
ザビュールとの戦いはどのような言葉をもってしても語ることが出来ないほど、事象を超越したものであり、かつ熾烈なものであったが、ついにイナッシュはザビュールの胸元に聖剣を突き立て、冥王をうち倒したのだ。
かくして、人間の手によって冥王は倒された。しかし完全に滅ぼすことは出来ず、イナッシュとレオズスは聖剣を用いて封印を施した。これによりガザ・ルイアートは持ち得る力を使い果たし、以来、失われた大地の帰還に至る千年余に渡り、所在が知れなくなる。
[イクリーク王朝の終焉]
アリューザ・ガルドからは魔族が消え去っていき、空を覆う暗黒がうち払われた。同時に、太陽と月と、くすんでいた色ももとに戻り、ようやく世界はあるべき姿を取り戻したのだ。
タス・ケルティンクスを封じ、地上に戻ったイナッシュは再び王座に座るが、数ヶ月して彼は自ら王座を降りた。イクリーク王朝に幕を下ろす時が来たと考えたイナッシュは、執政家のアズニール家に王権を譲渡し、自らは隠遁することとしたのだ。この後のイナッシュについては定かではないが、レオズスと再会し、彼と共に世界を巡ったとされている。
これ以来、“イナッシュの勲”として吟遊詩人が彼の武勲を語り継ぎ、今日に至るまで世界の至るところでうたわれている。
新王でありイナッシュの信頼が厚かったオーウィナク・アズニールは、没落していた王朝の体制をまとめあげ、イクリーク王朝の正統な後継として、アズニール王朝を興すのである。
十. 魔導の時代
古代魔法の発掘と、研究の深耕化。魔導王国ラミシス。
[アズニール王朝の長期安定]
アズニール王朝がイクリーク王朝の後継となり、暦法の名が変更された。アズニール遷都の年を「アズニール暦元年」としたのだ。
アズニール王朝の王都は、エヴェルク大陸のイルザーニ地方、ラティムへと正式に移った。ここは“統一王国の時代”に至るまでの間、前アズニール王国の本拠地であったのだ。
また、かつてのイクリークの王都ガレン・デュイルは、さきの“黒き災厄の時代”に、魔族による大殺戮によって、見るも無惨な廃墟と化してしまっていた。それ以来、歴代のイクリーク王はガレン・デュイル郊外の古城ハウェイジェンにて国政を執っていたのだが、この城をアズニールの王都にするには不適当とされた。華やかさがなかった上、老朽化が進みすぎていたためである。それ以上に、ザビュール支配の面影を払拭するという理由が大きかった。
遷都が行われてからも、ザビュール配下の魔物や妖魔の残党などがしばしば国内を荒らすなど、アリューザ・ガルドはまだ混乱のさなかにあった。また、恐怖に覆われた人々の心を癒すには、多大な時間を費やす必要があった。
アズニール初代王オーウィナクは、諸種族やディトゥア神族との交流を深め、国内情勢の安定化に尽力した。歴史の表舞台から姿を消したイナッシュもひそかに国王に助力していたと伝えられている。その甲斐あり、五十年余を経てアリューザ・ガルドはようやく本来の平和を取り戻した。
オーウィナクはそれから程なくして崩御するが、死に臨むその顔は安らぎに満ちていたと言われている。
以来、アズニール王朝は長期に渡りアリューザ・ガルドの大部分を統治していくことになる。
“黒き災厄の時代”末期までに全世界に広まっていた言語は、アズニール語と呼ばれるようになり、ここにはじめて汎世界共通語が誕生した。アズニール語の伝播により、各種族ごとの言語は次第に使われなくなっていく。
かつての統一王国全盛期を彷彿とさせるような潤いを取り戻した世界は、とりたてて大きな事件もなく、二百年の月日を数えていった。
[古代魔術の発掘、魔法学のはじまり]
アズニール暦も200年代に入ったころ、ひとりの古代史研究家が、以降のアリューザ・ガルドの歴史に多大な影響を及ぼすことになる。彼の名はノスクウェン・ルビス。“忘却の時代”の謎を追ううちに、彼は不死についての文献を見いだす。かつてのイクリーク王、タイディア・アントスは自身の不死を欲し、結果として破滅をもたらしたわけであるが、ルビスはあくまで研究対象として、この不死の文献を読んでいった。
けっきょく不死についての研究は頓挫してしまうのだが、ルビスは大きな功績を後の世に残した。不死についての文献をさらに求めるべく、ルビスはアル・フェイロス遺跡群を探索するのだが、この時二冊の本を見つけた。一冊目は、ラズ・デンやハフトといった、今となっては失われた言語についての本であった。そして二冊目は、アル・フェイロスの魔法貴族によって記された魔法書であったのだ。
ルビスは、親友の術使いクェルターグ・ラミシスと共に魔法書の判読に没頭していき、失われた魔法の体系を復活させた。ここに魔法学が誕生し、魔法そのものの研究に加えて、世界の事象、とりわけ原初の色との因果関係を含め、大規模な研究が進められる。
術の素養を持つ者達がルビスらのもとを訪れるようになり、ルビスの住むヘイルワッドの町は、やがて魔法研究の中枢として大いに発展していくことになるのだ。
アル・フェイロスの魔法体系は、クェルターグの息子ミュレギアの代にほぼ復元され、完成の域に到達した。さらにはミュレギアの息子ジェネーア・ラミシスによって、原初の色を交えての魔法研究が深耕化されていくが、ジェネーアはその過程で錯乱状態に陥り、自ら発動した魔術によっていずこかに行方をくらました。
学長ラミシス失踪により、魔法都市ヘイルワッドはしばしの間混乱に陥るが、新学長としてレクティル・ファトゥゼールが就くと、やがてその混乱も収まっていき、ラミシスの名は忘れ去られようとしていた。しかしながらこの時、ルビスの遺していた、不死についての文献が消え失せていたことに気付く者はいなかった。
[魔導王国ラミシス]
アズニール暦300年代の初頭、ラミシスの名は突如、歴史の表舞台に現れる。
ジェネーア・ラミシスは失踪後、魔法の禁断の領域である不死を追求しはじめた。ジェネーアのもとに集った魔法使いのうち、最も才覚を現した者こそがスガルトであった。不死の研究の過程において、ジェネーアは自らの体を滅ぼし、魂をスガルトに宿らせたという。
スガルトは“漆黒の導師”を名乗り、ユードフェンリル大陸南部の島に、ラミシス王国を興した。彼のもとには有能な魔法使いが招集され、国を挙げての魔法の研究をはじめたのだ。
その伸びはめざましく、数年を経ずして魔法研究においてヘイルワッドに比肩するまでに至ったが、この魔導王国の目的は不死性を求めること。魔法という大いなる力を究極まで肥大化させることによって神々の領域に近づくことをその目的としていたのだ。
かつての歴史において、不死を追い求めた結果ザビュールを降臨させてしまった。そのためにアズニール王朝は、不死を研究するラミシスの存在を危険であると見なした。
事実、ザビュールの気配を濃厚に残すと伝えられる“黒き大地”において、闇の力が増したとも言われており、ザビュール崇拝者達はラミシスを訪れるようになっていき、関係を密にしていくこととなる。
ついにラミシス打倒の勢力が決起した。その筆頭は魔導師シング・ディール。彼はスガルトの血族であるが、漆黒の魔導師の狂気から逃れるために離縁していた。ディールはアズニール諸卿より助力を受け、軍勢を引き連れてラミシスに攻め入る。
しかし、大陸とラミシスを隔てるスフフォイル海を渡る際、強力な魔力障壁に阻まれて戦力は壊滅、ディールは敗走することになる。
[ヒュールリットの攻防]
ディールを助けたのはドゥール・サウベレーンのヒュールリットだった。この龍つまり“朱色のヒュールリット”は、もともとドゥロームであったのだが、龍化の資格を得たために龍となったのだ。ヒュールリットは、“黒き災厄の時代”以来、未だ目を覚まさない龍達を呼び起こした。
龍達はディールと共に行動を起こした。ディールとその軍勢は龍に乗り、ラミシスの魔法障壁を打破してついに魔導王国へと至った。
ラミシス上陸にあたり、ラミシスの魔導師達と龍達の戦いが繰り広げられるが、この熾烈な戦いは“ヒュールリットの攻防”として歴史上名高い。
戦いをくぐり抜けたディールはヒュールリットと共に、王城オーヴ・ディンデの玉座の間に降り立った。魔法を極めた王スガルトも、龍と魔導師の力には敵わず、ディールの鍛えた剣、漆黒の雄飛“レヒン・ティルル”によって葬り去られた。
王を失ったラミシスは浮き足立ち、アズニール軍と龍達によってあっけなく滅びた。
こののち魔法学は、ラミシスから持ち帰った資料を加えて、さらなる発展を遂げていくことになる。最も高みに位置する魔法――いわゆる“魔導”の研究が始まっていくのだ。
魔導師達の時代。魔導の暴走。レオズスの支配。
[原始の色と魔導]
忌々しい儀式に塗り固められていたとはいえ、ジェネーア・ラミシス、そして漆黒の導師スガルトが遺した魔導の資料は膨大であり、また魔法の研究を大きく前進させるものであった。
シング・ディールらヘイルワッドの魔法使い達は、世界を彩る“原初の色”と、魔法との相関関係を明らかにした。すなわち、魔法とは世界に存在する“原初の色”を抽出してはじめて行使が可能であるということである。その考えに基づき、とうとう魔法体系の頂点である魔導が確立した。
それまでの魔法は、あくまで術者本人の魔力(つまり術者に宿る原初の色)のみを魔法の触媒としていたのだが、魔導は世界に存在する原初の色からも魔力を抽出し、発動させるのだ。しかしその高度な発動原理ゆえ、世界の理を把握していないものには行使すら不能である。
シング・ディールは魔導師を名乗っていたが、この称号はやがて魔法を行使する者にとっての最高の誉れとなり、その位を手に入れるために魔法使い達は競って魔導の研究を始めた。
300年代も終わりに近づく頃になると、魔導の向かうべき究極の姿が明らかにされる。
このアリューザ・ガルドに存在するすべての色を交わらせた究極の色、“光”を生み出すことこそが魔法の究極なのだ。
より強力な魔導を求める魔導師達は、術を行使する色の力場に複雑な紋様を織り込むことで魔導が強化されるのを発見した。これを呪紋といい、呪紋を含んだ魔導を使いこなす者を特に“呪紋使い”と呼んだ。
また、原初の色を増強するために世界の四カ所に魔導塔が建造された。四つの魔導塔が交差する線上にある地域こそ、かつてのアル・フェイロス王国の王都であり今は遺跡と化したティン・フィレイカであった。
アズニール暦400年代は、魔導の研究の最盛期である。この時代には多くの有能な魔導師達が世に出たが、その中にユクツェルノイレとウェインディルの名がある。
ラクーマットびとのユクツェルノイレ・セーマ・デイムヴィンは若くして魔導を極めた者として有名である。彼は魔導を学びはじめた当初から頭角を現し、僅か六年目、年齢にして十九歳の時に魔導師となったのだ。彼の二つ名は“まったき聖数を刻む導師”である。
魔導師の位に就くのは、体内に宿る原始の力を最大限に活用できるバイラルのみであると思われていたが、ウェインディル・ハシュオンは例外であった。エシアルルの彼は、水の事象界へと連なる原初の色を差し引いてもなお膨大な魔力を有していたのだ。彼はユクツェルノイレに師事した。ウェインディルは多くの魔導師の中でも群を抜いた魔力と知識を持っており、“礎の操者”や“最も聡き呪紋使い”の二つ名で知られるようになる。
この二名の魔導師は、後述するレオズス支配を阻んだものとして広く知られるようになるのだ。
[魔導の暴走]
光という究極を追い求める魔導師達は、いつしか魔導の本質を見失ってしまっていた。結果として、人の手に余る力はついに氾濫してしまったのだ。
アズニール暦425年。四つの魔導塔からは極限まで高められた魔力が放出され、魔導師達にすらくい止めることが叶わなかった。
この悲劇こそが“魔導の暴走”である。かたち無き力は世界中に波及し、各地に壊滅的打撃をもたらしてしまった。
ユクツェルノイレやウェインディルを筆頭とした魔導師達が対策を講じるも、解決策は見いだせなかった。根本的な解決法は、魔導塔に凝縮された“原初の色”を、アリューザ・ガルド外の世界に封じ込めることと、魔導そのものを行使不能なように封印することであった。後者はともかくとして、前者は人の力ではどうにも出来ないのだ。
しかし428年、魔導の暴走は突如収まった。自然消滅したものと当初は思われていたが、実際には、事態を重くみたディトゥア神族のレオズスが四つの魔導塔に入り、“原初の色”を消し去っていたのだ。
だが人間達の喜びもつかの間であった。
あろうことかレオズスは“混沌”の欠片をアリューザ・ガルドに呼び寄せていたのだ。さしもの彼をもってしても自身のみでは魔導の強大な力をくい止めることは出来なかったため、彼は苦肉の策として、“混沌”の力を借りることで暴走を抑えたのだ。
しかしながらレオズスは“混沌”に魅入られてしまい、この太古の力の手先となってしまった。そして宵闇の公子は、アズニール王朝ひいては人間に対して隷従を強いたのである。
[混沌に魅入られたレオズス]
宵闇の公子は、北方エルディンレキ島の魔導塔を自らの居城とした。人間にとって、かつての冥王君臨にも似た暗黒の時代が訪れることとなるのだが、レオズスは冥王とは異なり、配下をいっさい持たなかった。その代わりに彼には禁忌の力、“混沌”があったのだ。
レオズスに刃向かう者に対しては“混沌”の力をけしかけ、存在そのものを抹消してしまった。また、レオズスはエルディンレキ島周辺に“混沌”による結界を作りあげ、例えディトゥア神族であってもこれを越えることは叶わなかった。
しかし、このレオズスの君臨を阻んだのは三人の人間であった。
431年、ウェインディルは預幻師クシュンラーナ・クイル・アムオレイ、剣士デルネアとともにレオズスの封印を、この世ならざる剣“名も無き剣”をもって打破した。そして居城に乗り込み、壮絶な戦いの果てに宵闇の公子をうち破ったのである。
深く傷ついたレオズスは、イシールキアをはじめとしたディトゥア神族によって裁かれた。レオズスは神族より追放され、以来その姿を見ることはなくなった。
事の発端となった魔導の知識は封印されることになり、魔導の行使は不可能となった。また、魔導の塔に残存していた魔力の源は、魔導師達によって厳重に封じ込まれた後、アリューザ・ガルドから離れた次元へと持ち去られたという。
[アズニール王朝の崩壊と失われた大地]
魔導の暴走が消え去り、レオズスの支配から脱却したとはいえ、アズニール王朝の体制はレオズスに対する隷従のために弱体化しており、かつての栄華を取り戻すことなくアズニール王朝は崩壊してしまった。
それまでも独立の動きを見せていた諸侯は一斉に挙兵し、アズニールの広大な領土は割かれた。乱立する小国同士は互いに争い、アリューザ・ガルドは戦乱の時代を迎えることになってしまった。
災禍が過ぎ去ったというのに訪れることのない平和。レオズスを打倒した三人の英雄は、その状勢を憂えた。
当時彼らはイルザーニ地方にて手厚い待遇を受けていたのだが、433年にひそかにその地を離れ、カダックザード地方へと移った。
以来彼らの消息は絶たれるが、437年のカダックザード西部消失事件そのものに関わっていた事がその後明らかになる。
この消失事件とは、カダックザード地方の西部がある日、光に包まれて忽然と無くなってしまったことをいう。
後に残ったのは、まるで地面を根こそぎえぐり取ったような大断崖。その南方に存在していたであろう大地はいつしか、“失われた大地”と呼ばれるようになった。
“失われた大地”がどこに消え去ったのか知る者はなく、やがて事件そのものも忘れ去られていった。
十一. 諸国の時代
諸勢力の勃興と、安定。“失われた大地”の帰還。
アズニール王朝崩壊後から現在に至るまでの“諸国の時代”は、バイラルの各氏族・諸侯が勢力を争っていた時代である。幸いにも魔物の動向については、いちおう沈静化しているようだ。
[アズニール暦400年代後半~500年代]
アズニール王朝崩壊により、王朝の有力諸侯は挙兵し、互いの勢力を伸ばすための戦いが繰り広げられた。
初期の段階では、二つの大きな派閥に分かれての争いであった。“魔導の暴走”をもたらした原因が魔導師であるとする旧アズニール王朝派と、魔法使いや魔法貴族を擁護する新興勢力との戦いである。
魔導の力が封印されたこの時代において、魔法使いにはかつての力はなく、彼らの多くは上記のような争いに巻き込まれるのを嫌い、歴史の表舞台からひっそりと消え去った。
(魔法使いを擁護する、という主張は、権力志向の強い貴族達による形骸化した大義名分でしかなかった)
五十年近くの攻防の果てに、エヴェルク大陸の諸勢力は次頁のとおりの六大勢力に取り込まれ、しばし膠着状態となる。
戦乱を逃れる人々はカダックザード地方へと移り、ティレス王国を建国。このティレスは、広大な領有地域に相反して国力はさほどでもないが、建国以来六百年の歴史を、血なまぐさい争いとはほぼ無縁に送ることになり、いつしか平和の象徴とも呼称されるようになる。
旧アズニール王朝勢力は戦乱の果てにかつての王都ラティムから撤退、ドゥータル地方を中心とした地域に拠点を移さざるを得なくなった。
エヴェルク大陸中央部において最も勢力を誇ったのはクウェアルディンであるが、王都ラティムや聖地イルザーニ地方の占有を巡って、サルドゥエイルやズウェイアといった有力勢力とにらみ合い、時には剣を交えていた。
ユードフェンリル大陸においては、アントス家の末裔と称するアイズウェン・アントスがいち早く諸勢力を抑え、廃墟と化したガレン・デュイルを復興し東方イクリーク皇国を建国。これによりユードフェンリル大陸は統一され、戦乱のさなかにあるエヴェルク大陸と対照的に、しばし平和な時代が到来した。
[600年代~800年代]
この時期は、イクリーク皇国の繁栄と没落の歴史ともいえる。
582年のユードフェンリル大陸統一後五十年ほど、東方イクリーク皇国は国内の安定化に努めた。国内の情勢が安定すると、ユードフェンリル大陸東部の未開地域を開拓。この地に住まう悪鬼や怪物などに悩まされながらも、版図を拡大させた。
次に皇国は、エヴェルク大陸へ軍を進める。相も変わらずにらみ合いを続けていたエヴェルク諸勢力は一時休戦し、皇国に抗戦することになる。
しかしながら皇国の国力は圧倒しており、655年にクウェアルディンが皇国のもと剣をおさめると、リギンも同調した。
なおも反発するサルドゥエイルはズウェイアと“強い意志のもと”結託、旧王都ラティムとイルザーニ地方の守護という名目でイクリーク皇国に対抗した。
サルドゥエイルにすら反発する一部のズウェイア勢力は、シャルパ地方にファグディワイスを興した。この地域はそれまで、正統アズニール王朝が占有していたため、当然ながらファグディワイスとアズニールとの間に戦いが勃発することになる。
800年代に至るまで、アリューザ・ガルド主地域を治めたイクリーク皇国であるが、800年代にはその繁栄にも翳りがみえはじめた。エヴェルク大陸側ではサルドゥエイルの侵攻が再度活発となっていた。さらにユードフェンリル大陸側においては国力が分断。アントス皇とマイロウル皇の分割統治となり、国内情勢は混乱を迎えた。
乗じて、イクリーク国内でも反発勢力が兵を挙げ、皇国は二つの大陸双方に敵を有するかたちとなった。
さらにイクリーク皇国に追い打ちをかけるように、“黒き災厄の時代”以来、ナルデボン地方の地下で眠っていた魔族ゲハンクェムが覚醒した。皇国はこれを倒すために戦力を割かざるを得なくなり、結果として対抗勢力が大きくなるのを黙認するかたちとなってしまった。
[900年代~1000年代]
最初にイクリーク皇国の勢力を削いだのは、エヴェルク大陸のサルドゥエイルであった。910年、フィレイク地方に侵攻したサルドゥエイルはこの地にフィレイク王国を興し、イクリーク勢力を一掃した。フィレイク王国の王都は海に面したファウベル・ノーエである。
エヴェルク大陸の他勢力についても変化があった。
908年、ファグディワイスは“ディラクネルの海戦”にて正統アズニール王朝をうち破り、エヴェルク大陸南部域において宗主国となった。ファグディワイスの王都は、ドゥータル地方のヒェルティンレヴに遷都された。
ファグディワイスとフィレイクは不可侵の同盟を結び、各々の国家において商業を繁栄させていくことになる。また、フィレイクはサルドゥエイル時代に占拠していたイルザーニ地方から撤退、セルアンディルにとってのこの聖地を“いかなるものにも属すことのない開かれた地”とした。イルザーニ地方はその後エヴェルク大陸陸路の貿易要衝となり、大都市カルバミアンは大いに栄えることになる。
ティレスはこの時期、国内の勢力が二つに割れていたが、強硬派のサイジェム将軍によりイイシュリアが建国された。強兵を誇るイイシュリアにティレスは手をこまぬき、隣接するフィレイクは国境に兵を置いて警戒を強めた。
ラデルセーン地方においては、小勢力がまとまり、エニルグ王国をつくりあげていた。
フィレイク軍によるエヴェルク大陸からのイクリーク撤退を受け、910年にユードフェンリル大陸ではとうとう内戦が勃発、長いこと統一されていたユードフェンリル大陸は諸勢力による戦乱の時期を迎えた。
1000年代初頭には勢力図は安定化し、マイロウル朝を継ぐアルトツァーン王国と、都市共同体が集約したメケドルキュア王国の二つが興された。アルトツァーンの王都はガレン・デュイル、メケドルキュアの王都はイストゴーアである。
マイロウルの長子カストルウェンと、イストゴーア市長の息子レオウドゥールは旧来より親交が篤く、二人の少年期にはユードフェンリル大陸南部のラミシス遺跡やエヴェルク大陸の世界樹を訪れるなどの冒険行を重ねていた。
そのため二つの王国はとりたてて互いに反目することなく、平和のうちに境界線が定められた。
こうして諸勢力が安定化しようとしていたとき、大きな事件が起こる。
それこそが魔導の時代の末期“失われた大地”となったカダックザード地方南部の“還元”である。
1056年の夏のこと。その日、にわかに空には暗雲たれ込め、大地震と、天を轟く雷がアリューザ・ガルド全土を襲った。
その地異が過ぎ去った後、忽然と姿を現した島こそがフェル・アルム島であったのだ。
“還元”に際して多くのことが起きたが、ここではそれら一つ一つを言明しない。『フェル・アルム刻記』をご参照いただきたい。
(けして忘れてならないのは、フェル・アルム還元の際、太古の“混沌”の欠片がほんの一時であるもののアリューザ・ガルドに現前したという事実である。それまで存在そのものに疑念がもたれていた“混沌”が実在することが明らかになったのだ)
当初、魔物の棲む島として敬遠されていたものの、独自に王国が築かれているのが判明すると、ティレスはフェル・アルムと国交を結んだ。一方でイイシュリアは1058年、フェル・アルムの制圧に乗り出すが、フェル・アルム女王サイファ・ワインリヴ指揮のもと、かの国の精鋭騎士団“烈火”により退けられる。
この戦いの後イイシュリアは国内外からの反発を買い、1059年にはティレスに併合されることになる。
フェル・アルムから大陸に渡る者も多くいたが、その中で著名な人物にテルタージが挙げられる。彼ら夫婦は冒険家としてアリューザ・ガルドを巡り、とくに著書『天を彷徨う城キュルウェルセ』にある冒険行は、広く世に知られることになる。
[現在]
時に1100年代となった現在、アリューザ・ガルドは安定化しており、特に大きな変動はない。ひとまずアリューザ・ガルド史の編纂を締めくくることとする。
【追記】
ディトゥアの同胞たるマルディリーンがこの書を書き上げてから、人の世では早くも二百年の歳月が流れた。もちろんその間、この本には記されていない多くの出来事があった。
例えば今私が眺めている魔導塔にしてもそうだ。魔法は再びアリューザ・ガルドに復活したのだ。
それに諸国家の情勢にも変化が生じた。
アリューザ・ガルドの趨勢は、とどまるところがない。だからなのだ。私がマルディリーンに請うて、彼女の記した書の写本を手にし、ここアリューザ・ガルドにいるのは。
運命を切り開くのが人間の担う役割であればなおのこと、歴史はできるだけ多くの人間が知るべきだ。私は旅を続けながらこの写本を各地に残していくつもりだ。歴史は世の終わりまで完結することがない。これからも多くの歴史家が諸事を書き連ね、吟遊詩人が詠っていくことだろう。
そして私もまた楽器をつま弾き詠おう。少しの酒をともにして。
――休まぬ風は、全ての事象を聞いてきた――
魔導塔の全貌が見渡せる丘にて 宵闇の公子 レオズス
【悠久たる時を往く・了】
悠久たる時を往く

