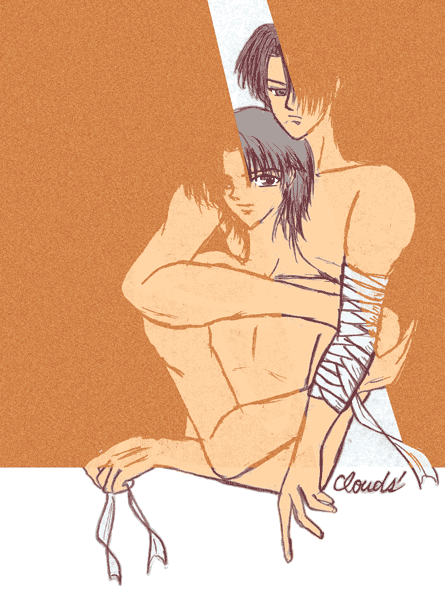
フルーツバスケット版権小説「残り香(紫呉×はとり)」(全年齢対象BL・無料)
【再掲時コメント】
アニメ「フルーツバスケット」の前半+妄想設定で、2004年ごろに書いてWebサイトにUPしていた作品の再掲です。紫呉×はとりで、性的交渉場面を書く気はないけど、その前後のなんとなく気だるそうな雰囲気を書こうとしたもの。「僕から、僕を」に続くBL2作目。
【人物紹介】
(「フルーツバスケット」を知らない人が小説を読むのに必要だと思われる、設定の抜粋です。一部、著者なりに解釈したところがあります。)
草摩はとり(そうまはとり):草摩家の主治医として働いている。体が弱ったり、異性と抱きついたりした場合、タツノオトシゴに変身してしまう、という十二支の呪いにかかっている。いつも真面目で冷静で、感情の起伏が少ないのではないかと思われがちである。
草摩紫呉(そうましぐれ):結構売れっ子の小説家。はとりと同じく、体が弱ったり、異性と抱きついたりした場合、犬に変身してしまう、という十二支の呪いにかかっている。このため、犬の声が聞き分けられたり、ちょっとした会話ができたりする。人に「さざ波」「クラゲ」と称されるなど、ひょうひょうとしたつかみ所のない人物。
「今日はもう、帰らなきゃ」
そう言って紫呉が布団を出たのは、一体どれくらい前のことだったのだろうか。
彼が去ったのは、数秒前のことにも、数時間前のことにも思われる。彼が衣を直す音がまだ耳元に残っている気がするし、それよりなにより、彼の残り香が、確かにまだあった。体臭と交じり合い、彼自身をあらわすほどに特徴的な、煙草の香。
家まで送ってやる、と言ったのだが、やんわりと断られた。慣れない営みで、まだ体が痛む。紫呉はそんなはとりの体を察したのだろうか。
確かに、起き上がり、体を拭き、着替えることを考えると、かなり億劫ではある。とは言え、こうして独りで家に残されることを考えると、いくら辛かろうとも、一分一秒でも紫呉のそばにいればよかった、とはとりは思った。
眠る気はしないが、起きる気にはならず、仰向けの姿勢のまま、両手を天井のほうに向かって伸ばす。こうしていると、この腕に誰かを抱いていたなんて、すべて嘘のように思える。しばらくそうしてみたが、掴まるものがない両手は、疲れる前に結局布団へと落ちた。はた、という乾いた音と、腕への少しの衝撃は、まるで他人事だ。
窓から入ってくるかすかな明かりが、顔の上に舞い落ちてくる埃を照らす。そのまま目を閉じると、少し暖かく、少し湿ったような布団の感触が、どうにも気持ち悪かった。
誰かが居た感触。このまま腕を左に伸ばすと、まだその誰かを味わえるのではないか、という気にさせられる。自分のにおいで包まれた自分だけの布団が、今日はまるで別の世界だ。想いを振り払うように目を開けてみたが、まだ朝が来ない夜の重みに、今にも押しつぶされそうだった。
「残り香、か」
言い聞かせるように、そしてそれを振り払うように、はとりはそっと呟いた。春は過ぎたが、まだ夏には遠く、すこしまだ冷たいものを含んだ夜風が、そっと彼の頬を撫でる。その柔らかな感触が、またもや彼に、去っていった男の存在を思い起こさせる。
もう一度無理やり目を閉じてみたが、一つの感覚を遮断すると、触覚、そして嗅覚が、きしむ音を立てかねない勢いで活動を始める。そうなると、もう今しばらくは到底寝られそうにはない。
はとりは静かに起き上がり、部屋の端につってあるスーツの胸元に手を伸ばした。その冷たいような生暖かいような感触に、ふと思い出す。
今日は、雨に降られた。結構酷い雨だった。どうせすぐ近くに車を止めているのだから、と病院を出てから走ったのだが、予想以上の距離は、はとりのスーツを、そして体を、完全に濡らしてしまった。
胸ポケットに入れていた煙草も然りである。良くここまで濡れたものだ、と小さくため息をつき、もう吸えそうにもない煙草の箱を、ゴミ箱のあるあたりに放り投げた。スーツは先に女中に渡しておくべきだっただろう。明日は着られそうにない。
ただちょっと煙草がほしかっただけなのに、濡れた布の感触に、妙に現実に引き戻された気がした。
かすかに窓からもれてくる明かりに照らされる、乱れた布団も、なんとか肩からぶら下がるようにまとわり着いている寝間着も。すべて、ただ、夢の象徴。暗い闇の中、自分はいつだって独りだったのだ。今更、何を求めるというのだろう。
吸えない、と思えば、無性に吸いたくなるのが、煙草である。はとりは決してヘビースモーカーではなく、最近では思い出したように一日一、二本吸うだけだ。それでも、体と頭がニコチンに侵されていることには代わりない。確かこのあたりに、と、はとりは薄くもれてくる明かりの中で、近くの書棚を探り始めた。
「たしか、このあたりに……」
どこかの引き出しで、いつか見たような気がする。そんなかすかな記憶を元に物を探そうと思っても、そう見つかるものではない。本当に探す気があるのならば電気をつけて本腰入れて探せばいいものだが、そこまでするつもりはなかった。そもそも、存在をあいまいにしか覚えていないほどの古い煙草を見つけられたとしたって、どうせしけっていて、吸えやしないのだ。
ほんの少し、時間が潰せたらいい。結局、理由はそれだけだ。煙草を探しているのではなく、ただあちらこちらの引き出しをかき混ぜているだけの自分に気がつき、はとりは唇を少しゆがめた。
煙草は見つからなかったが、はとりはそれに似たものを見つけた。細長く、煙が出るもの。香である。
いつ誰がこんなところに入れたのかわからないが、真っ白な和紙をまとった箱に、紫色の細い棒が行儀良く寄り集まってできた筒。薄いセロファンの包み紙を開けると、かすかな匂いが鼻をついた。
香なんて焚いた記憶はないので、香立てを探しても無駄だろう。はとりは筒を一つ手に取り、手近なライターで火をつけ、吸殻入れに山となっていた煙草の間に立てた。
香の香りというものは、すっと自然に空気になじむのかと思っていたはとりの考えとはまるで違い、結構な匂いが出る。匂いが出るというより、香の束は、はとりの目の前でもくもくと燃え、これは少々おかしいのではないかとはとりがなんとなく思い始めたときには、もうすでに部屋は白い煙で満たされていた。
目の前を手ではらってもはらっても、煙はどんどん部屋を染めていく。何とかしなければ、と焦る気持ちが心のどこかにあるのに、思考が追いつかない。濃密な煙は、渦となってはとりを襲う。
はとりはその中で何事もなかったかのようにぺたっと布団の上に倒れ、天井を眺めた。かすかに外から入ってくる風で煙が少し乱れ、広がり、また一つになる。ゆっくりと下へ下へと降りてきて、舐めるように体を包んでいく。目を閉じると本来感じられるはずのない煙の粒子が、彼の体を撫でて、過ぎ去った快感を思い起こさせた。
「しぐれ……」
はとりは思わず声を出す。自分にこんな感覚を味合わせてくれるのは、彼だけだから。ゆっくりと目を開けると、煙は徐々に人の形を取っていくように思えた。心なしか、着流しの男のように。そして、はとりが良く知る人物のように。
「まさか、な」
幻か。夢か。夜の隙間を縫って、悪魔でも舞い降りてきたというのだろうか。
目の前を覆い尽くす香の煙をすべて取り払ったら、その姿がゆっくり見えるだろうか、とは思ったが、今もし手を動かすと、すべてが消えてしまいそうな気がした。
どうせ夢なら、いっそ覚めるな。魂でも何でもとっていけばいい。今晩一晩でも逢えない辛さと添い寝するくらいならば、いっそそのほうが幸せだ。
「……はーさん」
幻が言葉をつむぐ。煙をかき分けつつ、そっとしゃがむ。
はとりはその姿にゆっくりと手を伸ばし、触れた。
「夢のはずなのに……」
指を幻の頬に触れさせると、ゆったりとした生暖かさが伝わってくる。
「触れられるよ」
幻は、声まで似せることができるのか。
はとりがゆっくりと動かした手は、柔らかな細い感触の中にもぐりこむ。その手はやさしくつかまれ、生暖かく濡れたなにかが指先をすべる。
「何やってるの、はーさん」
「紫呉……」
はとりは近づかない幻がもどかしく、もう片方の手も伸ばした。目の前にある顔をぐっと掴み、自分の胸に押し当てる。突然の行為に紫呉はバランスを崩し、はとりの上に覆いかぶさった。
「紫呉、行くな」
「どうして?」
「……そばに、いてほしいからだ」
「どうして?」
「幻のくせに、それ以上しつこく聞くな」
腕の中でごそごそと動く感覚は、夢としては少々現実味がありすぎ、はとりはかたまって一つの方向に流れ出している白煙の中、ようやく現実の紫呉の存在を知った。少々冷たい夜風も流れ込んできて、頭が徐々にはっきりとしていく。
「何を莫迦なことやってるの、はーさんは」
紫呉はしがみつくように押さえ込んでくるはとりの手からすりぬけ、白煙の元となっている香と灰皿とを自分が入ってきた障子から外に出し、さらに障子を一杯まで開け放った。
「僕が来なければ、煙に巻かれて死んでたよ」
煙はほとんど外へ出たが、まだ濃い香りだけはしっかりと残り、はとりはまだ夢の世界に居るような気がした。布団をはたき、なんとか香りまでも外に出そうとしている紫呉の白い首元に、はとりはそっと手を伸ばす。
「夢じゃないのか?」
「もちろんだよ。まったく、はーさんってば香のたき方も知らないの?」
「うるさい」
「こんなにいっぺんに火をつけて、きっちり部屋を閉めきって。ちょっと戻ってきたから良かったようなものの」
まくし立てる紫呉に、はとりは「だまれ」と一言告げるのももどかしく、唇を唇に寄せ、次の言葉を吸い取った。紫呉は普段とは違う煙の味に眉をしかめつつも、はとりの求めに応じて自分の舌を自由にさせてやる。
「妙に積極的だよね。普段はされるがままなのに」
一息ついて目を伏せ、つい顔を背けるはとりを見て、紫呉は満足げな笑みを浮かべた。
「はーさんって、肝心なことは何も言わないんだから」
「何がだ」
怒っていいのか照れたらいいのか分からず、はとりは紫呉に背を向ける。
「言いたいことがあるなら、はっきり言えばいいのに」
「別にお前に言いたいことなどない」
「ほら、さっきまでのあんなに素直だったはーさんは、どこに行ったのかなぁ」
紫呉は、背中では何も語ろうとしないはとりに横から抱きつき、乱れた布団に押し倒す。可愛いくらいの些細な反抗はさっさと押さえつけ、そっと首筋を舐め上げ、雄弁な反応に満足する。
「素直に、行くなって言えばいいのに」
「誰が、そんなことを」
紫呉の手の動きとともに、はとりの語尾が乱れ、息が上がりだす。
「言わないならいいけど」
紫呉は手を止めて、体を上げた。快感を止められ、はとりも物足りなさげに顔を上げる。紫呉はそばに転がっていた香の箱から一束を取り出し、一本だけ抜き取り、すっと火をつけた。
「この香のいわれ、知ってる?」
「香に興味などない」
「だろうね。知ってるなら、こんな夜には焚かないよ」
すっと立ち上る一筋の煙は、さほど登らぬうちに外からの風ですぐに乱れてしまう。先ほどはとりが焚いた大量の香のにおいがまだぼんやりと残っている中、その一本の香はまた違った印象を部屋に与えた。
二人はしばらく立ち上る煙を見ながらじっとしていたが、はとりはその穏やかな沈黙が絶えられなくなり、紫呉の肩に手を伸ばした。振り向いた紫呉の瞳がちらっと光る。
紫呉ははとりの膝に頭をあずけ、左手でじっくりとはとりの体を下からなぞっていく。
「もし、僕に永遠に逢えなくなったら、どうする?」
「嫌な質問だな」
「ねぇ。どうする? こんな夜に、僕はもうはーさんのところへ戻ってこれないかもしれない」
「それなら、この手を離さずにいる」
はとりは紫呉の手を捕まえて、そっと口づけた。
「するっと抜けるかもしれないよ」
「大丈夫だ。ずっと、見ている」
「じゃぁ……」
もう言うなと言わんばかりに、はとりは紫呉の両肩を捉え、布団に押し付けた。そのまま自分も倒れこみ、紫呉の首筋に、普段良く彼が自分にするように、舌を這わしてみる。
もどかしい動きがくすぐったく、紫呉は身をよじった。別に逃れようとする理由はない。たまにはされるがままになるのもいいか、と紫呉はそのまま体をあずけた。
香の名は、へツリモユメ。どこかの国の言葉がなまって、日本語の意味と混じったらしい。分かりやすく書くと、「別離モ夢」
現世で別れた者たちが、せめてあの世でまためぐり合えるように、常に二人の間に道を作る。煙でできた、細い、一筋の道。ちょっとした風ですぐに揺れては掻き消え、またしばらくすると、形を変えつつも、また道を作る。
この香をいったい何本燃やせば、あなたに逢えるのだろうか。どのくらい時を過ごせば、再び巡り逢えるのだろうか。
想いを途切れさせないように、ひたすら燃やし続ける。
どこの国の伝統かまではもう忘れてしまったが、愛する者と死に別れた者は、毎晩必ず一本だけこの香を焚くという習慣があるということを、紫呉は聞いたことがあった。
なぜ、一本なのだろう。あの世との道筋を作り、絶やさないように、香を焚くというのに。
しかもこの香は、かなり短い。仏壇用の香の半分もないほどだ。現に今も、紫呉がこうして身をゆだねているうちに、いつの間にかとっくに燃え尽きてしまっていた。
こんなもので、どうして現世とあの世とが結べるのだろう。
これではむしろ、さっさと忘れてしまえと言ったほうが正しいほどである。一本焚いて、少し涙して、そしてそのまま寝てえとでも言うのか。また次の日には一本焚いて、そして、次の日にままた一本。そのうち、涙も出なくなるだろうか。
人の感情なんて、この煙よりうつろいやすいものなのだ。
だが。
もし自分が、本当に大切な人を失ってしまったら。
自分はいったい、どうするのだろう。
この香には、人の神経を麻痺させる何かが含まれているとも聞いたことがあった。実際、たいした量の煙でもないのに、はとりは既に意識を失いかけていたし、今だって、なかなか冷静さを崩さず、常に受身な普段の様子を微塵にも感じさせないほど、積極的に攻めてくる。
この香を一本ずつでも毎日焚き続けたら、次第に神経が蝕まれていくのかもしれない。妄想の世界でのみ生きて、思い出の中でのみ息を吸って。煙に巻かれて夢を見て。そして、自分に本来与えられた命をほとんど全うしないまま、死ぬ。その者の人生は、体半分を失った時点で、既に終わっているのかもしれないが。
どうしてこんな香がはとりの手元にあったのかはまったく分からないが、はとりをこんなにも狂わせてしまったのは、自分だ。
そう思ってみると、なんだかひどく背徳的で、ひどく楽しかった。
「はーさん、好きだよ」
紫呉は、胸に秘めたさまざまな感情を、ありきたりの言葉に押し込めた。
フルーツバスケット版権小説「残り香(紫呉×はとり)」(全年齢対象BL・無料)
以下、冒頭部分を初めてネットに公開したときにつけていたコメント。
「残り香」なんてなんともありきたりなコードネームをつけてしまった小説。かなり短いものに仕上げるつもり。
ふっと風呂場で思いついた小説案。そういえば、昔研究室の後輩が海外旅行でお土産に買ってきてくれたお香のセット、どこいったんだろう、なんて思い出して。引越しのときに発見し、確かにこっちに持ってきているはずなんだけど。どこいったんだろう。先日友人と街をふらついたとき「こういうの好き?」とお香やアロマテラピーなどのセットを指され、そういえば、あったなぁ、と。そのもらったお香とか、衝動買いしてしまったにおい付きキャンドルとかいろいろあったけど、結局使ってない。だって、前の家、家の下が消火器屋さんなんだもん! ……ろうそくたいて、その煙でいろいろと発動なんてしちゃったら、もうとんでもないことに……?
今回の話は、直接的に性的交渉場面を書く気はないけど、その前後のなんとなく気だるそうな雰囲気あたりならなんとかなるのではないか、と思ってみたり。……どうもなぁ、なんて気はするけど。何書いてるんだか。
自分の布団には、確かに自分のにおいがする。太陽の下で一日干さないと、消えない。確かに自分のものだ、という妙な安心感がそこにはある。他人がもし自分の布団にいた場合、一体どれくらいにおいが残るのだろう。また、他人がいつも使っている布団って、どれくらい違和感があるのだろう。
……微妙に色気があるようなないような話だが、抱き枕の「なごぺん」と背中合わせで寝つつ、もしこのペンギンが魚くさかったら、大変だろうなぁ、なんて思ってみた時の話。もし何らかのにおいがした場合、一日中布団の周囲にいるわけだから、私より、なごペンのにおいのほうが、布団にはべっとりついているはずだ。彼を布団から離した場合、魚くささはどれくらい残るのだろう。
……毎晩のように、魚や海の夢ばかり見る羽目になりそう。はふ。
-------------------
以下、書きあがったときにつけたコメント。
久しぶりの版権小説。紫呉×はとり。はとり受けです。はとりは紫呉を好きで好きでしょうがないが、紫呉は結構冷めていたりもする。はとりの反応が楽しく、いろいろと意地悪しているが、心の中ではほんとは好き。失ってはいけないものだと気がついている。
これ、お香をネタにはとり紫呉小説を書こうと思ってから冒頭部分を書き、実際に完成するまで、半年以上放っておいてしまった。ほんとはリツが数年前の修学旅行に買ってきたもので……とかいろいろと裏ネタを考えつつちょっと軽いオチありものにするつもりだったのだが、なんとなくそういう気分にはなれず、そうとは言って、とことん重いものにする気もなかったので、妙に中途半端なものになった気がする。
タイトルは、一番初めにつけた「残り香」のまま。書き終わって再び考えたが、あまりいいのも思いつかず。香の名前をつけるのもいまいちだし。香の名前や由来は唐突に思いつき、唐突に入れた。実在するかなんて知らないし、香というものにそもそもいわれや由来があるのかすら、知らない。でも香の歴史って結構深そうだし、多分あるものはあると思うんだよね。
二人主人公が居る三人称小説って、どうもつい視点が行ったりきたりしてしまう。本当は一人に焦点をあてて書くべきなのだろうが、どうしても一人が知っていて一人が知らないことや想いを入れようとなると、つい視点が動いてしまう。どうやったらそのあたりがうまく行くのだろうか。なかなか悩みどころ。
(2004.4.27)


