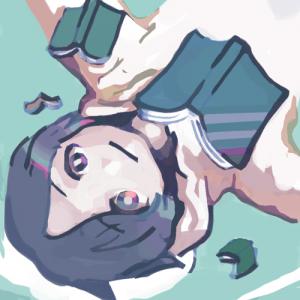雪に灰煙
2014年(確か)の秋のコミティアにてSometime Dropというサークルで出した最初の本の一編です。
「僕は少しは大人になったかな。それか、少しは大人になれるかな」
歩いているだけで疲労が蓄積されていくような容赦のない熱帯夜だった。
いつもなら空を仰げば散らばっているちっぽけな星の明かりも分厚い雲に阻まれ、唯一月だけが濁った池に落とした黄色いビー玉みたいに存在していた。
両手の指で足りる程の回数だけ曲がり角を折れると、すぐに世間から忘れられたように人気のない道に入ることができる。
シャツの胸ポケットから煙草を一本取り出してジッポライターで火を付け、喫って、吐く。もわっとした煙がこのぬめりを含んだような熱気にはお似合いだった。
そのまま煙草を喫いながら歩いて行く。角を曲がり、更に奥へ、深く誰の息もない場所へ。
数えるのも億劫になる(元から数える気もないけれど)程の角を曲がると、一人の少女がいた。
僕はその場で足を止め、三~四種類ほどその少女の存在する理由を考えてみるが、その中から導き出された自分の取るべき行動を実行する前に少女に先手を取られた。
「これ、どーぞ」
見た目からして十歳とちょっとに見えるその少女は、僕に怯えることなく近所の隣人に接するかのように近づいて来て、一枚の白い紙を渡してきた。
迷いは少なからずあったけれど、取り敢えず僕は煙草の灰を片手で地面に落としながらその紙を受け取った。
「これはなんだい」
内容も確かめずに少女に訊く。
「おねがい」
何が? と思ったけれどそれは渡された紙に書いてあった。
おとなをさがしてください。
一般的に使われる印刷用紙に手書きでそう書いてあった。
おとな。
大人?
両親じゃなくて?
「えーと、取り敢えず聞くけど、君、迷子か何か? それとも家出?」
「おじさんは誰?」
質問を質問で返された。しかも純粋に人の話を聞いていないタイプの返し方だ。
しかしおじさんか。まだお兄さんの歳の筈だけれど。まぁこの年頃の子供からしたら僕みたいなのは皆おじさんか。
「おじさんはおじさんだよ。それと、君は迷子でいいのかな。家出でいいのかな」
「もしかしてけーさつ?」
少女のその言葉には不安は見えないが経験が見えた。
「違うよ」
「じゃあ誰?」
「当ててごらん」
僕は煙草を口に咥えた。
少女は腕を組んで頭を傾げ、典型的な考えるポーズを取った。
少女が僕に渡してきた紙はその一枚だけで、その他には何も持っていなかった。配り終わったのか、それとも配るものではなかったのか。
「あ、分かった!」
少女の表情がぱっと明るくなる。典型的な閃いた表情だった。
僕は彼女の遙か頭上に煙を吐いた。
「おじさん、たんてーでしょ」
僕は人生で初めて、最近の子供の考える事って分からないな、と思った。
ため息を吐いた。含まれた水分が凍結していく。まるで僕の体に溜まっていた理由のない疲れがそのまま形を成して出てきたみたいだ。
雨に比べたら焦れったいほどゆっくりと地面に落ちる雪は、世界中のノイズをその一粒一粒の結晶に閉じ込めたかのように静かだった。
横断歩道を前だけを見て横断し、今出てきたアパートの向かい側にある自動販売機に歩を進める。
こんな時間帯だから車の一つも通る気配がない。
今までの経験上、街は二つに分類される。
眠る街と眠らない街。
どうやら、なんて言うまでもなくこの街は完全に今、睡眠に落ちている。
ポツリポツリと光の道標になっている街灯は、今日も誰も来ないコンビニの夜勤だ。
そんな街灯や、今僕の目の前にある自動販売機の意義を今考えた所で、それはつまり僕の存在意義を再認識しなくてはならないとても面倒くさい作業なので、財布の中の小銭を数えることに頭を向けた。
ラインナップの一番端に追いやられた味気ないデザインのあったか~いブラックコーヒーのボタンを押すと、愛想のない店員の渡す釣り銭のような態度で缶コーヒーが落ちてきた。容赦はないが最低限の良識は知っているフリをしているガゴンという音が響く。まったく、下にクッションでも敷けば良いのに。
ため息をもう一度吐いてしゃがみ、少しぬるい気がする小さな缶を取り出した。
煙草に火を点けて細い煙を吐くと、雪を通り抜けて拡散する灰色のその向こうから少女が見えた。
「たんてーは夜が好きだね」
少女はダッフルコートの袖に両手を隠しながら僕の隣に座った。
「起きてたのかい、ワトソン君」
「起きたんだよ」
少女の吐く息は僕とは違って白く綺麗なものだった。
「子供はとっくに寝る時間だよ」
「たんてーだって子供のくせに」
僕はそれを否定もせず、かと言って肯定もせずに煙草を喫った。
成人していようがいまいが、彼女にはそんなこと関係ないらしい。
僕は少女の顔を横目で見る。陶器で作られた林檎みたいな表情を空に向けていた。
「お正月からは少し経ったけど、夜ってこんなに静かなんだね」
少女は無数に落ちてくる雪の一つ一つを数えるように黒い空を見ながら言った。
「ここには神社がないからね」
「そいういうものなの?」
少女が僕の顔を見る。
「さぁ。子供の僕にはわからないな」
僕は少女の代わりに空を見上げて言った。
そして煙草の灰を地面に落とした。
僕は少女のことを「ワトソン君」と呼んでいる。
それまでは「君」とか「ちょっと」とか「あのさ」とか、年頃の息子が使う母親の呼び名のようなものを使っていたが(君はないか)、ある日突然彼女が僕の部屋に置いてあったシャーロック・ホームズを読んでいた時に「これからはわたしのこと、ワトソン君って呼んで」と頼んできたのだ。
探偵の助手、ということだろう。
「たんてーはさ」
僕がパソコンとにらめっこしていると、ワトソン君は文庫本から目を離さずに呟いた。
「大人ってなんだと思う?」
「どういう意味での質問かな」
「社会的な意味での質問だよ」
「難しい言葉で難しい質問を言うようになったね」
ワトソン君は僕のアパートに住み着いて以来、部屋に居る時間、食事やお風呂に入る時以外はもっぱら室内に点々となんの基準もなしに積み上がっている本の塔を崩しては片っ端から活字に目を通し、崩れた塔の構成物質を全て読破したらまた同じように積み木の要領で積み上げていった。
彼女と出会ってからもう三ヶ月以上になるが、日に日にワトソン君の知識は豊富になり、言葉遣いもそれに準じたものになっていった。
おそらく、彼女は本の「読み方」を覚えたんだろう。
「たんてーはどう思う?」
ワトソン君は活字から目を背けずに言った。
僕はパソコンから目を離し、テーブルの上に置いてある煙草の箱を取って残りの本数を数えながら考えた。
窓からは暖かな日差しが差し込んでいて、部屋の一部を陽溜りとして占拠していた。ワトソン君はその陽溜りに両足を突っ込んで文庫本を広げている。
「よく分からないな。まずなにが分からないって、基準が分からない。何をしたから大人とか、どういう心構えを持てるようになったら大人とか、そういう基準が僕には分からないな」
「子供と大人の間に基準なんてないよ」
「そういうものかね」
「そういうものかもね。まずたんてーはまだまだ子供だよ」
「なんでそう思うんだい」
「子供のくせして大人ぶって煙草喫ってるところが子供」
「なるほど」
僕は煙草の灰を灰皿にトンと落として、そのまま小さな丸い溝に置いた。
限りなく儚く薄い透明な煙が、一つのとても細い布の様に天井へと向かっていく。
「君が探してるって言う、君が思う「おとな」っていうのは、どういう人のことなんだい?」
僕はワトソン君の方を見て言った。
「なんでも出来る人のことだよ。でもなんにもしない人。全部を知ってる上で全部は知らないでいる人」
「もうちょっと具体的には?」
「自分を捨てて社会に適合して、貢献出来る人。かな」
「それってつまりロボットってことかい?」
僕は灰皿から煙草を摘んで口に咥える。
「でも笑うことが出来るの。たんてーとは違って」
なるほどね。
なんとなくだけれど、彼女の言う「おとな」ってやつの輪郭がかいま見えた気がした。
「しかし、最近良く思うんだけどね」
僕は煙を天井に向かって吐き出しながら言った。
「ワトソン君。君って本を読んでいる時、かなりテンション低いよね」
僕の言葉が彼女に届いたのかは分からないが、その言葉がきっかけになったようにワトソン君は文庫本をパタンと閉じた。栞も何も挟んではいなかった。
「たんてー。お腹空いたー。なにか作って」
「おーけー。ワトソン君は何が食べたい」
少女は大きな目を開いて楽しそうに大きな声で言う。
「ハンバーグ」
「ごめん。面倒くさい」
仕事を失った生活になれると、どうも昼夜が逆転するらしい。
僕は朝日と入れ替わるように布団に潜り込み、夕日が沈む頃に目を覚ます。
夜は大抵アパートを空けて、しんとした空気の中をコートに身を包んで徘徊する。
「たんてー」
長い階段の、その一番下の段の雪を足で払って椅子代わりにし、喫煙しているとワトソン君が呟いた。
ワトソン君は階段を下った場所で、未だ誰にも足あとの残されていない場所を見つけては遠慮もなしにベコベコと踏みつけていた。
「今年もやっと雪が降ったね」
「なんだかんだ言ってね」
僕は煙を細く吐き出した。
「去年は初詣に行ったけど、今年は行かなかったね」
「僕は人混みってやつが嫌いだし、去年の冬はまだ少し暖かった」
「それと」
ワトソン君は新雪を踏み荒らしながら話を強引に続ける。
「雪が降るとあんまり寒くないね」
そして少しの間、僕は煙草を喫って時間を置いた。
ある程度の範囲の雪に足あとは刻み終わったらしく、ワトソン君は振り続ける雪の中の、その一つを手で掴もうと空に手を伸ばしている。
「そう思えるのはワトソン君が子供だからだよ」
彼女は片手に僕が渡した傘をぶら下げながら、上空に差し出した手をそのままにこちらを向いた。
「たんてーは少しは大人になれた?」
「そうだね。どうだろう。まだ自覚というようなものは見当たらないかな」
「そんなもんだよ」
「そんなもんかね」
それからは暫く少女は雪を掴み取る作業に戻り、僕は無言で煙草を喫い続けた。
今日もこの街は規則正しく眠っていて、かと言ってその眠りを邪魔している僕らを邪険には扱わなかった。
この街は優しくて、寂しかった。
しかし、寂しいからこそ、嬉しさもあった。
朝日を拝んで布団に入る時、季節に関係なく暖かな日差しを部屋の中に送り込んでくれるこの街の太陽が僕は結構気に入っていたし、深夜にこうやって少女と出歩く時には目に見える全ての風景が身じろぎもせずに無言で歓迎してくれた。
「あ、見て見てたんてー」
ワトソン君が僕の方に小走りで近付いて来て、ほら、と手を広げた。
しかしその中には水滴がぽつりと残っていただけで、それがなんだかなんとも言えない気持ちにさせた。
「雪を掴んだの。地面に降り積もる前に。私の手で」
彼女が求めていた結果は目的の延長線上で、結果がどうあれ過程に楽しみを感じていたらしい。
僕は浅く積もった雪に煙草を押し付けて携帯灰皿に入れ、次の煙草を咥えて言った。
「ワトソン君、逆に訊いてみようか」
「なになに」
ワトソン君は大きな両目をこちらに向けた。
「僕は少しは大人になったかな。それか、少しは大人になれるかな」
少女は手に持った傘を手首に引っ掛け、腕を組んで頭を傾げた。典型的な考えるポーズだ。
遙か上空の雲から零れた雪が音もなく地面に吸い込まれるくらいの間、沈黙が出来上がる。
そしてワトソン君は腕を組んだまま切なくなる程の笑顔で口を開いた。
「まだまだ子供だよ、たんてーは」
「何処らへんがだい」
「だってハンバーグ、作れないもん」
僕は苦笑しながら灰色の煙を吐いた。
その灰煙は多分、僕の身体からにじみ出たため息の色なんだろう。
「お腹は空かないかい、ワトソン君」
「空いたー。でも子供にはハンバーグは作れないから、ハンバーガーでいいよ」
難易度が上がっている気がするが、まぁいいだろう。今日のところは我慢してもらって、明日の朝にでもファーストフード店に行こう。
上から下へ。
降り積もる雪には音がなく。
下から上へ。
空まで届くことのない煙草の煙にも、当然音なんてなかった。
雪に灰煙
Sometime Dropの時に書いた原稿をそのまま写しました。書きなおしてもいいのですけれど、個人的に最初の出した掌編集はいつか全部書き直してやりたいので、やっぱり今は書きなおさないでおきます。
数少ない、この掌編が載っている僕の本を買ってくれた人には申し訳ないですが、この一編だけ、投稿させてください。
それはそうと、幼女を初めて書きましたが、僕ってこんな幼女しか書けないのかもしれません。