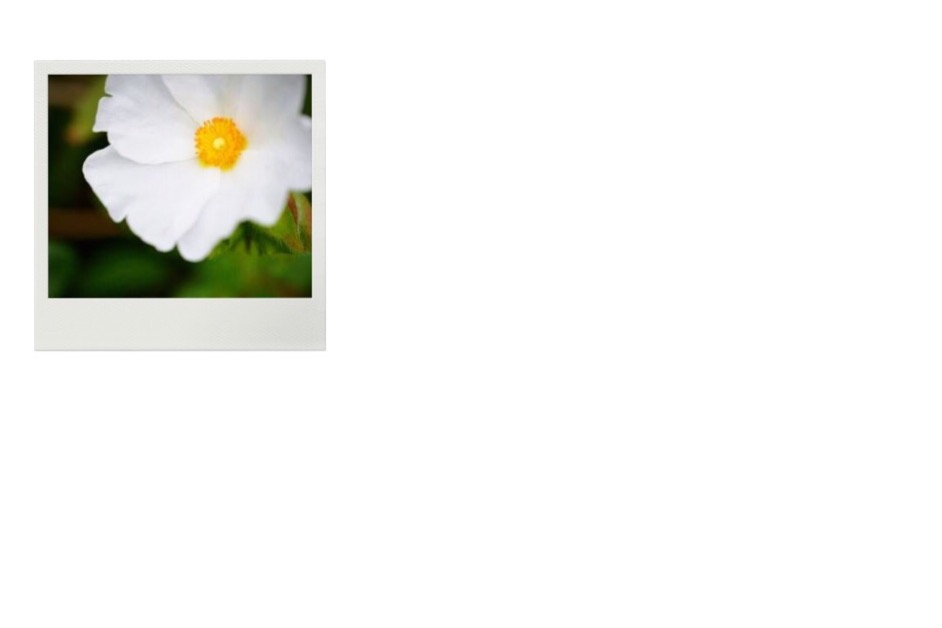
White-leaved rockrose
「やほー!元気?」
南風がそよぐ窓から見知った声のする方に首を回すと、五歳年下の妹・夏海が、ドアから顔を覗かせた。
『昨日と変わりないよ。
っていうか、昨日も来たじゃないか。』
夏海は、そうだったかなぁなんて呑気な声を出しながら、窓台に荷物を置いた。
『ずいぶんと大荷物だな。』
「そんなことないよ。
半分はお兄ちゃんの着替えで、もう半分はね…」
笑みを浮かべて両手に持ったものを、僕の前に差し出した。
「じゃーん!今日はね、梨と桃、持ってきたんだー!」
夏海の両手には、その名の通りの色をした綺麗な桃と、手に余るほど大きな梨があった。
『どうしたんだ、それ。』
「福島のおじいちゃんとおばあちゃんが送ってきてくれたんだよ。
すごく美味しいから、お兄ちゃんにも食べて欲しくて。』
もうそんな時期なのかと、季節の変わり目を実感する。
ここ最近窓から入ってくる頬をなでるような爽やかな風は、季節が移ろいでいた証拠だった。
『どうして制服なんだ?』
「今日ね、夏休み明けの文化祭の準備で少しだけ学校に行ったの。
明けてすぐだから、準備がなかなか進まなくて、夏休み返上で準備してるんだ。」
スカートのプリーツを翻し、引き出しからナイフを取り出すと、器用に剥き始めた。
『…手、切るなよ。』
「酷いなぁ。私そんなに不器用じゃないもん。
昨日だって、私がお父さんに剥いてあげたんだから。」
『昔は皮は食べちゃえばいいとか言って、そのまま食べてたよな。』
両手で抱えながら一生懸命に果物を頬張る幼い頃の夏海が頭に浮かんで、自然と口元が緩む。
「それいつの話よー!ちゃんと剥けるんだから邪魔しないでよっ」
眉間にしわを寄せながら、僕の注意を受け入れてくれたのか、手元をしっかりと見ながら皮を剥いていた。
その瞬間、心臓の鼓動が少しだけ早くなる。
大きく波打つ鼓動に、息が苦しくなる。
夏海に気づかれない様にゆっくりと深呼吸をすると、なんとか落ち着きを取り戻した。
窓の外に目を向けると、青い海と空の境界線が分からないほど透き通っていた。
白い砂浜には小さい子を連れた家族が、砂浜で水遊びをしているようだった。
鼻歌を歌いながら慣れた手付きで軽快に皮を剥いていく夏海の横顔が、少しだけ母さんに似ていた。
僕たちの母さんは、夏海が一歳の時に病気で亡くなった。
今日みたいな爽やかな風が吹いていた日だった。
もともと体の弱かった母は、夏海を産む前から調子を崩していた。
医者からは堕胎を進められていたほどだったが、母は断固として首を縦に振らなかった。
何とか持ちこたえた身体は、出産の負担で既にボロボロだった。
それでも母は父の介護と入退院を繰り返し、夏海の誕生日を迎えた翌日、自宅のベッドの上で息を引き取った。
僕は母が息を引き取ったとき、夏海と別室にいた。
『子供達には、笑ってた顔だけ覚えてて欲しいから』という母の意見優先したからだ。
安らかな寝顔だったと、父は穏やかな声で僕たちに話してくれたことがあった。
そしてその母を苦しめた病気は、僕の体を少しずつ蝕んでいった。
今から二年前の秋、突然教室で倒れた僕は、病院に運ばれて体の隅々まで検査を受けた。
その結果、遺伝していた病気が発症しているとの診断を受けた。
その翌日から僕の入院生活が始まった。
繰り返される診察と精密検査、お世辞にも美味しいとは言えない病院食、病院外の外出や、激しい運動も禁止されていた。
最初はお見舞いに来てくれていたクラスメイトも、だんだん距離を置くようになっていた。
「お兄ちゃん剥けたよ!」
皿に盛られた果物は、いくつずつ剥いたのだろうか、皿に白と桃色の山ができていた。
『こんなに剥いて食べれるのか?』
「大丈夫だよー!本当に美味しいから、ぺろりと食べられちゃうよ。」
桃を爪楊枝で刺して口に運ぶと、ひんやりとした身は舌の上に丁度いい甘さと甘い香りが鼻から抜ける。
『美味しいよ。』
「でしょ?お兄ちゃんに食べさせたかったの。」
笑顔で次から次へと口へ運ぶ夏海を見て、つい笑ってしまうと、への字口で対抗されてしまった。
あれほどあった果物を二人で平らげ、お腹も程良く満たされた。
「あ!」
夏海が突然、窓の外を見て大きな声をあげた。
『どうした?』
「先週まで咲いてた海辺の向日葵、もう種になってるの。」
夏海が少し興奮気味で指差した方に視線を向けると、花弁が落ちて真っ黒な種が詰まって首がうな垂れていた。
『後で種とってきて、来年埋めようっと』
楽しみだね、と元気な声とは裏腹に、太陽に照らされた夏海の横顔が、夏の終わりを告げる景色に少しだけ悲しそうに見えた。
『そういえば、夏海、もうすぐ誕生日だよな。』
「そうだよ。よく覚えてたね。」
風に吹かれるロングヘアを抑えながら、近くに置いてある椅子に腰掛けた。
『何か欲しいものあるか?』
「そんなこと気にしないで、お兄ちゃんは早く病気を治して。」
目を細めた微笑、色素の薄い長い髪、歳を重ねるごとに母に似ていく夏海に少しだけ鼓動が早くなる。
『…ありがとう。』
「気にしないで?その代わり、退院したらいーっぱい買ってもらうから」
『…このまま病院に居ようかな。』
「もー!お兄ちゃんてば!」
ハリネズミの様に頬を膨らませる夏海の顔を見て吹き出した僕につられる様に、夏海も声を出して笑った。
「それじゃあ、私、そろそろ行くね。
今日夕ご飯作る当番だから、買い物して帰らなくちゃ。」
そういうと夏海は立ち上がり、スカートの裾を直した。
時計は正午過ぎを指してた。
『夏海、』
「どうしたの、お兄ちゃん」
『これ、』
ベッドの横の棚上にあった袋を夏海に差し出した。
「うわー、綺麗な花だね。なんていうの?」
袋から取り出すと、株を覆う様に五枚の白い花弁が満開に咲き誇っていた。
『キスツス・アルビドゥス、っていうんだ。』
「きすつ、なに?」
『キスツス・アルビドゥス。
和名はゴジアオイっていうんだ。』
「ゴジアオイ、不思議な名前だね。」
夏海が首を傾げた。
『今の時間が、一番綺麗に咲くんだ。
花が葵に似て、正午頃に咲くから、午時葵っていうらしい。
一日だけ咲いて、その日のうちに枯れてしまう一日花なんだ。』
「こんなに綺麗なのにね、」
眉尻を下げて、白い花弁を慈しむ様に指先で触れる。
『まぁ、今日一日だけでもこんなに綺麗に咲いたんだ、きっとこの花も悔いはないさ。』
「…そうだね。また、きっと咲くもんね。」
『夏海にやるから、大事にしろよ。』
「本当に?ありがとう。」
昔から花が好きで、花の図鑑をボロボロにするまで読み込んでいたほどで、そんなところも、虫が苦手なのにガーデニングが好きだった母さんによく似ていた。
「じゃあ、お兄ちゃん、また来るね。」
落ち着いたはずの心臓が、また激しく動き出す。
『…っ、あぁ、気を付けて帰れよ。』
「大丈夫だよ。お兄ちゃんこそ、無理しないで早く治して、文化祭来てよね。」
扉を開けて振り返った夏海は、屈託のない笑顔で鉢植えを持っていた。
『…そうだな。』
じゃあね、と扉の閉まる音がすると、夏海のローファーの音が遠ざかっていく。
「…はぁっ、はぁっ、」
きっと夏海は気付いていないだろう。
そのほうがいい、夏海の悲しむ顔は見たくないから。
最後に、夏海の笑顔を目に焼き付けられて良かった。
心臓を服の上から掻き毟る様に抑え、朦朧とする意識の中、片手で精一杯ナースコールを押した。
キスツス・アルビドゥス(ゴジアオイ)の花言葉
『I 'll die tomorrow.(私は明日死ぬだろう)』
White-leaved rockrose
White-leaved rockrose(キスツス・アルビドゥス)
葵に似た花を正午過ぎに一日だけ咲かせる一日花のため、和名を午時葵(ゴジアオイ)という。
35〜50°Cの気温になると、茎から揮発性の油を出して自動発火し、周囲の植物もろとも自らを焼き払って生息地を広げるのだそう。


