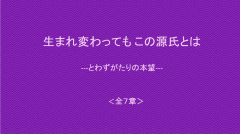
生まれ変わっても この源氏とは
『源氏物語』 <全7話>
源氏の問わずがたり
1 十かそこらの
(1)
--- 面ざし通う
紫のゆかり
なかりせば
あの日
あのとき
私が貴女に
目を留めることは
なかったろうか?
病得て
鬱々過ごした
山里で
偶然見かけた
十ほどの
幼い貴女が
かの人の
面かげ宿す
血続きの姪と
物好きな
詮索高じて
知ることなくば
私が貴女を
見初めることは
なかったろうか? ---
急ぐ気もない
答えはいつも
うやむやのまま
うっちゃっていた
若かりし日の
気負った自問
私を置いて
黄泉路へ発った
貴女を腕に
抱いて今
止まらぬ涙に
往生しながら
その
穏やかな
永遠の寝顔に
否としか
悔しいほど
否としか
その一言しか
浮かばぬ答え
貴女が
貴女で
あればこそ
誰彼の
ゆかりを問わず
私は貴女の
虜になった
手弱女ながら
気丈夫で
賢いがゆえに
馬鹿にもなれて
凛としてかつ
従順な
貴女が
貴女で
あるかぎり
またいつの世に
いずこで
逢おうと
性懲りもなく
私は必ず
貴女の虜に
なるだろう
(2)
この世の中で
誰より先に
誰より深く
貴女に懸想
した者として
いや
今もなお
逝った貴女に
懸想を止めぬ
者として
最大限の
思慕と
敬意と
吃驚の
念を込めて
敢えて
“くせに”と
戯れて言うのを
赦されよ
あの山里で
あの日
あのとき
貴女はほんの
十かそこらの
幼女の“くせに”
愛くるしくて
無邪気で
素直で
それでいてなお
芯があり
筋を通して
おいそれと引かぬ
意地があり
貴女はほんの
十かそこらの
幼女の“くせに”
源氏と呼ばれた
この私をして
遅疑や
躊躇の
猶予も与えず
たちどころに
恋い狂わせた
五年のち
十年のちの
貴女を
誰より
間近で見たくて
あまつさえ
他の男に
やりたくなくて
未来の貴女を
妻に娶ると
即刻
その場で
心に誓った
晩春の
日も落ちかかった
山里で
小柴の垣の
隙間から
偶然目にした
十かそこらの
幼な児の
夫になると
十八の
私は固く
心に決めた
2 今は鬼とも蛇とも呼べ
(1)
母亡き貴女を
一身に
庇護しつづけた
祖母の宮が
他界されたと
聞いた私が
悠長に
座視など
どうして
していられよう
一刻の
猶予とてない
生まれてこの方
疎遠つづきの
父宮が
遠からず
貴女を手元に
引き取るだろう
そうなっては
すべてご破算
その前に
私が貴女を
引き受ける
二条の院へ
私の邸へ
迎え取る
衣食住など
言うに及ばず
一人前の
礼儀作法や
上流社会に
伍し得る教養
人後に落ちない
気品と雅に
至るまで
その全てに
私が貴女の
世話役となる
決して貴女に
失望させない
世話役となる
とはいえ
それは
私の理屈
頑是ない
寝ぼけ眼の
貴女を
夜中に
抱き上げて
車で邸に
連れ帰るなど
卑劣な狼藉
無法きわまる
かどわかし
それどころか
貴女の歳など
知る由もない
世間が聞いたら
言うだろう
地位と金とに
物を言わせた
色好み
ここに極まれりと
それでもいいと
納得ずくの
蛮行だった
変事と悟った
貴女の抗議の
泣き声を
抱き上げた
懐の中で
耳にしながら
表の車に
乗るが乗るまで
女房どもの
狂わんばかりの
制止や悲鳴を
前後左右に
耳にしながら
それでもいいと
今は
鬼とも蛇とも
呼べと
気がすむまで
私を
悪者呼ばわりしろと
納得ずくの
蛮行だった
父宮に
先んじられては
万事休す
たとえ
血筋の
家族であろうと
他人に貴女を
取られたくない
他人が育てた
貴女など
見たくはない
貴女は
私が育てたい
父になり
母になり
兄にも
師にも
友にもなって
生いゆく
貴女を
眺めたい
蕾がやがて
花とほころぶ
変化の妙に
目を細めたい
その一念の
蛮行だった
(2)
それにしても
幼きことは
ありがたきこと
あっという間に
貴女は
馴染んで下さった
二条の院にも
この私にも
邸に帰った
私を迎えに
いの一番に
走り出て来て
広げた私の
懐に
真っすぐ
笑顔で
飛び込んできて
下さった
無垢で
利発で
鷹揚で
気が利いて
大人顔負けに
勘は鋭く
かと思えば
頬を赤らめ
みるみるはにかむ
日々の
貴女の
一挙一動
祖母宮を悼む
喪服の色の
痛々しさを
補ってなお
余りある
魅力があった
掌中の
玉だった
幼い貴女の
生い先を
我が手元でと
もくろんだ身で
支離滅裂な
繰り言なれど
願わくは
あの頃のまま
時が止まって
いてくれたなら
願わくは
貴女をずっと
十かそこらの
幼女のままで
神が
とどめ給うたなら
貴女と私は
永遠に
父娘として
兄妹として
穏やかな日々を
過ごせたろうに
愚かな私が
今日ここまで
犯した数多の
罪業に
罪なき貴女が
妻たるがゆえに
苦しむことも
なかったろうに
3 三日夜の餅
栴檀は
双葉より
何とやら
笛に筝
絵や書や和歌に
至るまで
教える端から
のみ込みが早く
その上達は
日々目覚ましく
師として
まことに
鼻高々の
末頼もしい
自慢の弟子も
ほんの一日
二条の院から
足遠のいて
戻ってみれば
私の不在を
すねて
うつむく
あどけなさ
罪の意識と
笑顔見たさに
浮気を繕う
情夫さながら
機嫌取り々々
貴女をあやして
数日は
外に出かける
気も失せた
そうかと言って
男女の情理
妹背の契り
謎をかけても
ふざけてみても
気が抜けるほど
とんと解さぬ
おぼこの貴女の
天真爛漫
世話役は
お手上げで
打つ手もなくて
ただ苦笑した
貴女が邸に
来て四年
もう決して
早すぎるとは
思わなかった
純粋無垢な
掌中の玉の
貴女ではもう
飽き足らなくて
これ以上
待てなくて
待つ気も
なくて
ある晩
貴女と
枕を交わした
おいでと呼べば
いつも変わらず
喜々として
我が懐に
飛び込んでくる
初心な貴女に
おいでと呼んで
ほろ苦い
切ない夜を
味わわせた
昨日まで
父だ
兄だと
任じた輩が
ある日突然
男という目で
貴女を女と
眺めれば
裏切り者の
烙印押されて
恨まれるのは
必定なれど
それでもいいと
覚悟した
いつかはと
決めていたから
貴女を娶ると
決めていたから
貴女の
最初で
最後の夫に
私がなると
決めていたから
それが
たまたま
あの晩だった
それだけのこと
さはさりながら
恥じらいと
怒りと
不信で
口も利かない
新妻が
初めて目にする
“後朝の文”を
何と見るやら
閨を去るのも
気が気ではなく
“三日夜の餅”の
いわれを貴女に
説く夜は
さすがの私も
照れくさかった
童女(わらわめ)が
たおやかな
女性(にょしょう)に変ずる
不思議を見ながら
貴女のすべてに
ぞっこんだった
4 鄙で見た夢
(1)
放縦の
科を負わんと
自ら望んだ
都落ち
期限を定めぬ
遠国蟄居
贖罪は
この身ひとつで
果たそうと
貴女を残して
独りで発った
鄙の地で
私はひとつ
罪を重ねた
明石の鄙で
ひとつ
儚い夢を見て
見たままを
とつおいつ
逡巡の果てに
貴女に宛てて
文にした
ある日突然
遠流の地から
“側室”という
摩訶不思議を
文一通で
突きつけて
いぶかる貴女に
問答無用で
“嫉妬”なる
奇怪な念まで
教授した
何から何まで
唐突で
あまりにも
得手勝手な罪
無事の帰りを
待つだけの身が
悲しいと
遠い都で
涙ながらに
案じてくれた
罪なき貴女に
終生負わせた
懊悩の
あれが始まり
今日まで重ねた
私の数多の
罪業のうち
まちがいなく
一二を争う
残酷な罪
それでも
貴女は
黙って耐えた
嫉妬なる
異な魔物さえ
貴女は
見事に
牛耳って
罵るでも
泣き叫ぶでも
生霊となって
呪うでもなく
隠しおおせぬ
恨めしさを
ごくごくたまに
やんわりと
歌の半句で
ほのめかしては
そっぽを向いて
束の間すねた
せいぜいそれが
妻として
私に見せた
貴女の焼きもち
その慎ましさが
可愛くて
その度ごとに
機嫌をとっては
なだめたけれど
「焼きもちなど
似合わないから
貴女は焼くな」と
笑う私の
理不尽や
比翼連理と
誓った愛に
信じて賭けた
虚しさに
呆れて
やがて
諦めて
誇り高く
慎み深く
他を慮る
貴女はいつしか
焼きもちを焼く
素振りすら
見せては
下さらなくなった
(2)
明石に
生まれた
姫母子が
優しい貴女の
心の鉄鎖と
ならなかった
はずがない
身ごもることの
ついぞなかった
我が身の
不運を
かこつどころか
産みの母さえ
手を合わせるほど
姫を我が子と
慈しみ
姫をして
生涯慈母と
慕わしめた
底知れぬ
貴女の献身
のみならず
件の姫の
母親を
ゆかしい女性と
褒めて微笑み
仲睦まじく
行き来を重ねた
貴女の
度量の
無限の広さ
それらすべては
健気な貴女が
自分自身の
自尊心すら
投げ打って
贖いつづけた
犠牲の賜物
女性にょしょうとして
ときに
どれほど
悔しかったか
女性にょしょうとして
ときに
どれほど
妬ましかったか
察して余る
その苦しさを
ちらとも表に
出すことなく
姫母子を
包んだ
貴女のまなざしは
私には
大きな呵責
未来永劫
消えない呵責
紫よ
貴女を
母に
してやりたかった
腹を痛めた
我が子を抱いた
貴女を
ひと目
見てみたかった
母たる貴女を
見てみたかった
5 衣選びは
年甲斐もなく
昔 浮名を
流した相手が
忘れられずに
ちょっかい出して
---互いに恋は
不似合いな歳---と
にべもなく
釘を刺されて
冷汗三斗
またあるときは
亡くした
昔の恋人の
忘れ形見を
養女に迎えて
父親以上に
世話を焼き
嫁がせてなお
恋々とした
そしてとどめは
もう若くない
この歳にして
娶った正室
貴女と二人
穏やかな
余生を共にと
千回万回
願ったはずが
兄の望みを
無下にもできず
親子ほどにも
歳のはなれた
内親王を
妻と迎えた
次から次へと
きりもない
私の醜態
滑稽な
痴態の数々
貴女は
嫌でも
目にし
耳にし
いいかげん
嘆く気力も
失せたろう
目も耳も
いっそ
塞ぎたかったろう
その頃だったか
「新年に贈る
衣選びは
くれぐれも
各々方の
ご器量に
似合いのものを」と
ある年の暮れ
貴女は言った
言い方が
言い方ならば
夫の多情を
痛罵する
鼻持ちならない
当てこすり
多少とも
身に覚えのある
夫なら
二の句も継げない
嫌味な皮肉
しかるに
貴女の一言は
悪意の
あの字も
ないどころか
温かく
仁恕にあふれ
もしも私が
女でも
到底真似は
できないと
いつもながらに
舌を巻き
そして内心
恩に着た
貴女は
終生
堪忍袋の
緒を切らすことの
ない人だった
終生
貴女の
堪忍袋の
緒はどこまでも
しなやかで
その
しなやかさを
いいことに
私は
とことん
好き放題
いつのまにか
その陰で
膨らみすぎた
堪忍袋に
ほかならぬ
貴女自身が
押しつぶされて
喘いでいたのも
気づかなかった
かけがえのない
貴女の命の
灯を縮めても
気づかない
鈍い阿呆が
夫たる
この私
6 我が子ではない我が子を抱いて
(1)
この子の父は
私でないと
私自身が
知っていながら
妻をねぎらい
待望の子を
我が腕に抱く
この皮肉
この子の
真の父親が
誰であるかも
疑う余地なく
知っていながら
懐に抱いた
小さな寝顔に
せめて涙は
落とすまいと
人知れず
天を仰いで
祝福の声に
笑顔で応える
この皮肉
これこそが
遠い昔の
あの我が罪の
見事な流転
神仏が
私に負えと
今なお命ずる
峻厳な罰
(2)
---源氏よ
そなたも
ここへ来て見よ
歳の離れた
この弟は
そなたに
たいそう
よく似ている---と
その昔
生まれたばかりの
赤子を抱いて
両の目に
限りない
笑みをたたえて
我が父は
桐壺帝は
朝な夕な
飽かず眺めた
小さな命は
愛おしいと
頬ずりしては
飽かず眺めた
あるいは
あのとき
父上もまた
知っていたのでは
あるまいか
口にするさえ
まがまがしい
不肖の息子の
大罪 即ち
今は亡き
藤壺の宮と
この私が
秘かに通じた
不貞の罪を
のみならず
会う人ごとに
祝われて抱く
その赤子こそ
二人の
堕罪の
忌まわしき
証なのだと
知っていたのでは
あるまいか
知っていてなお
一切を
自分ひとりの
胸におさめて
最期の日まで
何一つ
知らぬ素振りを
貫いて
下さったのでは
あるまいか
時は下って
今や
あの日の
不肖の息子が
我が子ではない
我が子を抱いて
あの日の父の
無限の慈悲に
ただひたすらに
頭を垂れる
犯した罪への
恐懼と
悔悟と
慙愧の念に
おののきながら
仮借なき
罪の報いに
羞じてただ
頭を垂れる
(3)
紫よ
貴女と
夫婦に
なってのち
本音も
見栄も
行きずりの
恋の遍歴も
如何に私が
余すことなく
貴女に晒して
きたとはいえ
口の端に
上せるだに
今なお疼いて
狂おしい
遠い昔の
あの罪だけは
到底
貴女に
告げ得なかった
この先も
よもや
告げ得まい
さればこそ
悪因悪果の
この罰だけは
弱音を吐いて
貴女にすがる
図々しさも
度胸もない
父でない
父に抱かれて
我が懐で
眠る罪なき
この幼子は
この私が
生ある限り
己独りで
背負うべき罰
さればこそ
せめて私は
死ぬその日まで
何ひとつ
知らぬ素振りで
この子の父で
あらねばなるまい
7 私に出逢うことなかれ
(1)
温かみは
とうに失せても
抱きしめた
貴女が死んだ
気がしない
閉じた瞼が
二度と見開く
ことはなくても
貴女が死んだと
思いきれない
血の気の失せた
その唇から
軽妙洒脱な
相槌も
袖に隠した
忍び笑いも
もう二度と
返ってこないと
判っていながら
物言わぬ
貴女に向かって
話しかけずに
いられない
貴女を弔う
野辺送り
急かして
止まない
周りの声は
耳塞いでも
聞こえてくるのに
死ぬほど
聞きたい
貴女の声は
もう二度と
聞こえてこない
(2)
---愛した者が
満たされる---
そのことを以って
良しとするなら
私の懸想は
満願成就
大いに叶った
不足はない
さりながら
---愛された者が
満ち足りる---
そのことなくして
懸想の成就と
言わぬとあらば
私の懸想は
何ひとつ
誇れる実など
結ばなかった
紫よ
貴女を
見出だし
守り
育てた
それが私の
自負だったのに
いつの間にやら
貴女は私を
追い越して
遠くはるかに
大人におなりで
いつの間にやら
私の方が
貴女を慕い
貴女を頼り
貴女に狎れて
貴女に甘えた
それでも貴女は
倦むことを知らず
私を憐れみ
気遣い
赦し
挙げ句の果てに
精も根も
尽き果てて
あまりに不憫と
見るに見かねた
仏の御許に
召されて逝った
仏が貴女を
召されるのなら
人の私は
拒めまい
貴女を返せと
泣き叫んだとて
叶うまい
かといって
貴女を失くした
この身など
どの道長くは
持つまいから
それならむしろ
遠からず
私の命が
尽きるまで
貴女のいない
侘しいこの世に
のたうち回って
その日を待とう
貴女のいない
この寂寥の
業火に焼かれて
その日を待とう
紫よ
もし万が一
万々が一
この先互いに
同じ世界に
いつか再び
生を享けても
もしも貴女が
満ち足りた
平穏な日々を
望むなら
二度と
私に
逢うなかれ
---互いに
満たし
満たされてこそ---
そんな懸想の
イロハのイすら
わきまえぬ身で
貴女を愛した
不埒な阿呆に
逢うことなかれ
いつの世に
どう生まれたとて
逢えば再び
性懲りもなく
貴女に焦がれ
虜にならずに
いられない
この私とは
決して
出逢うことなかれ
<完>
生まれ変わっても この源氏とは
最後までお読みいただき、ありがとうございました。 懐拳


