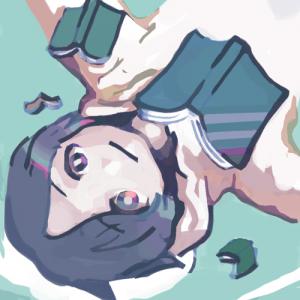雨が降る日に死体がみっつ
雨の描写をするのは好きです。
というより、雨が降っているという状況を屋内で感じる描写をするのが好きです。
現役の殺し屋を一日で二人見るとは、どんな感想を抱いて良いのかわからなかった。
「カオル君、申し訳ないんだけれど、先に部屋に戻っていてください」
ホテルの中にあるレストランで朝食をとったあと、部屋に戻ろうとエレベーターの到着を待っていると、隣に立っているユージがそう言った。僕の目の前には橙色のエレベーターの扉があって、その横にある回数を表示する数字が八から七にかわったときだった。
「どうして?」、僕はユージに言った。
「用事が出来たんですよ」
ユージは首を傾げるようにして僕に顔を近づけると、比較的小さい声でそう言った。
「用事ってなにさ」、僕は右隣に立っているユージの顔を見上げた。彼は僕よりもうんと背が高いから、その表情を見るためには首を曲げなければならない。
「野暮用ですよ」
ユージは笑っていた。僕はそれを見て、なんとなく安心した。だけど、同時に不安も立ちのぼった。彼の笑い方が「相手を安心させるために作った表情」だということが分かっているからだ。
「もうちょっと、具体的に教えてよ」
「野暮な用ですよ」
「ちっとも具体的になってない」、それに、と僕は続ける。「野暮な用なんだったら、職務怠慢じゃないか。いや、職務放棄だ」
「別にいいじゃないですか」
ユージは、はははと軽く何かを吹くように笑うと、背後にあるレストランの出入口をちらりと見た。確認した、と言っても間違ってはなさそうだった。
「一人で部屋に戻れますよね?」
「馬鹿にしないでよ」
話が次のステップに進んでいる。どうやら僕の質問には、明確な回答をくれないようだった。だけど僕も深く追求する理由はないので、建前は建前のままで終わらせた。
ユージがポケットから部屋の鍵を取り出すのと、レストランの出入口から一人の女声が出て来たのはほとんど同時だった。スタッフからの丁寧な礼を受けても見えていないかのような動作で歩く女性。いかにも高級そうな服装で身を飾り、背中の真ん中あたりまで伸びた黒髪を一枚の布のように優雅に揺らしている。女性は僕達と同じエレベーターには乗らないのか、そのままエントランスの方へ進んでいく。
確か、こことエントランスを挟んだ向こう側にも同じようにエレベーターがあった。客室は二つの棟に分かれていて、その構造上、エレベーターも二箇所に分けられているのだ。
女性の進む方向とは逆の角から、広い間を置いて、白い手袋を嵌めた両手で台車を押す男性従業員が見えた。
ユージはその光景を合図と受け取ったように、それじゃあとだけ言って重たい鍵を僕に渡し、男性従業員の後ろに気付かれないように付いて行った。どうやら本当に野暮な用だったらしい。
幅広く間を空けた三人一列が、女性を先頭にして順番に角を曲がって消えていくのを見ていると、僕の後ろでエレベーターの到着を知らせる上品な音が鳴った。振り向くと、中は空っぽで誰もいなかった。僕はドアが勝手に閉まってしまう前にと、心持ち急いで中に入った。
閑寂な空気が漂うエレベーターから降りても、一人ぼっちな状況が織り成す雰囲気に変化はなかった。
進む廊下の先には誰もいない。気配もない。
ただまっすぐに伸びた天井に等間隔で輝く明かりだけが、金色の光で薄暗さを演出している。屋内独特の静けさは、昨夜から振り続く雨の存在を際立たせるには充分だった。耳を澄まさなくとも、雨滴が外のすべてを濡らす音が遠くから聞こえて来る。僕は廊下に敷かれた絨毯を、必要以上の大きな足音を響かせながら進んだ。
〈五◯六〉と記されたドアの前で足を止める。右隣は五◯五号室。左隣は角を折った廊下になっていて、その先は階段へと続く。
ユージから渡された鍵を使って部屋に入ると、ベッドのシーツが綺麗に敷き直されていた。二度寝をしようかと考えていた僕だったけれど、まるで展示品のように流麗なベッドを見ると、早速よごすのも勿体無い気がした。なので部屋の隅にまとめられた荷物から文庫本をひとつ取り出して、反対側の隅にある一人掛け用のソファに腰を降ろした。
正方形のテーブルの上に文庫本を置いて、一息ついた。
薄いカーテンから透きとおって差し込む光は、淀んだ天気によって灰色に濡れている。部屋の中は雨の音に包まれていた。
僕は窓から差す明かりをライト代わりに、文庫本の栞が挟まれたページを開いた。
◆◇◆
男の目の前には、顔があった。
表情はこの上なく苦悶を訴え、赤紫色に染まっている。大きく開かれた二つの目からは、ぽろりと落ちてしまいそうな丸い眼球が、どちらも焦点をあわさずに黒目を上へ向けている。あくびを途中で止めたようにだらしなく開いた口からは、泡だった涎が滴っていた。
目の前で今にも事切れそうに身体を痙攣させている人間の首を、渾身の力で締め上げながら、男は「なんだっけな。どっかで見たんだよな」と思考の断片を口から零すように呟いていた。機械的に力を緩めずに相手を死に追いやっている両手は、男の意思とは別に、独立して動いているかのように見えないこともない。
男が殺人を実行している部屋はシングルルームであり、殺している相手はその部屋に宿泊している客人だった。
部屋の中を漂う音は、首を締め上げられた人間のカエルの様なうめき声と、男の淡々とした呟きと、窓から聞こえる雨音と、部屋の壁際に置かれたテレビに移る女性ニュースキャスターの味気ない声で構成されていた。なかでも場の空気を一切読まないテレビが発する音声が、室内の雰囲気を強引に彩っていた。
「うるさいな」と呟いて男は音声元の方へ目をやった。テレビ画面に映った女性ニュースキャスターの隣に、今朝のニュースが一覧になって表示されている。男は次にリモコンを探す為に視線を動かそうとするが、二つの目は画面に映ったひとつのニュースを見たままで固定された。とある大きな会社が、他社との合併を正式に発表したという内容だった。
「これだ。思い出した」
そう呟いた男は、両手に込めた力をすっと抜いて立ち上がった。ようやく解放された相手は、声ひとつ発することなく、糸の切れた人形のように床に崩れ落ちた。
男は納得した表情でリモコンを手にとってテレビを消すと、丁度自分を見上げる形で仰向けに倒れている死体を足でゴロリと横に転がし、服の縒れた箇所を直してから部屋の外へ出た。
男が廊下へ出ると、長身の男がこちらへ歩いて来るのが見えた。男は姿勢を正して一歩下がり、長身の男にひとつ礼をした。相手はどうも、とだけ言って手を挙げると、そのまま目の前を通りすぎて行った。それを見届けてから男は長身の男とは逆の方向、つまりエレベーターへと向かった。
◆◇◆
ノックの音が静寂の中に転がった。
ページをめくる手を止めてから、僕はドアの方を見た。勿論ドアは透けることもないので、来訪者が誰なのかはわからない。
でも予想は絞ることができる。おそらくユージだろう。早々にあの女性に拒絶されて戻ってきたのかもしれない。もしそうだとしたら、彼は右と左のどちらの頬を赤く腫らしているだろうか。そんなことを適当に考えながら二度目のノックに返事をしてドアを開ける。
しかしノックを響かせたのはユージではなかった。
薄い橙色のジャケットと白い手袋が特徴の男が、目の前に立っていた。つまりホテルの従業員が立っていた。
「ルームサービスです」と従業員の男は言った。
「……え?」、言葉にならない声が落ちた。
僕はルームサービスを頼んでいない。だから彼が僕の部屋を尋ねる理由はないはずだった。ユージが気をきかせてくれたのだろうかと瞬時に考えてみるけれど、それも期待するには心もとない予想であったし、なにより目の前に立っている男は手ぶらだった。そして極めつけには、彼の表情はホテルマンらしからぬものだった。礼儀や節度をないがしろにした、嘲笑に近いものが口元に浮かんでいる。
「頼んだ覚えはないんだけれど」、どう対応すべきなのかがわからないけれど、取り敢えず僕はそう言った。僕にそう言われた男は、剥がれかけた化けの皮を自ら脱ぎ捨てるように、態度と表情を崩した。
「ルームサービスって……、確かにそれは無茶があるか」、自分の言葉の違和感を楽しむように男は笑う。「さっきの女も、おんなじ反応してた」
さっきの女が誰なのかは知らないけれど、こっちの男も誰なのか僕にはわからないので、貴方は誰ですかと正直に、率直に訊いてみた。
「客観的に見れば、ホテルマン」、そして男は笑う。軽快で、風に吹かれればどこまでも広がりそうな笑い声だ。
「そんなのわかってますよ」
わかってるならいいじゃないか、と言いながら、男は首と目だけを動かして左右を見た。そして次に、早く中に入れてくれよと言った。
「……なんで?」、正直な感想だった。
「立ったまま話をするのもアレだしさ」
「なんで?」
「……なんでもいいだろ」と男は微塵の苛立ちを含めて言う。
よほど僕の顔に浮かんだ疑問と混乱が強かったんだろう。
それからいくらかの問答を繰り返したけれど、男は意見を曲げることを知らないばかりか、僕の意見を曲げることしか知らないらしく、最終的には「部屋に入れないと殺す」と脅迫まがいの台詞を言いながら、半ば強制的に部屋の中へ入り込んだ。ツインルームってやっぱり広いんだな、と男は無遠慮に一人掛け用のソファに腰を降ろす。僕はドアを閉めて鍵も回したあと、男の向かい側のソファに座った。男は勝手にテーブルの上に置いてあった文庫本を手に取りページをぱらぱらとめくっていた。
「つまんないもの読んでるな」、男はページを操りながら言った。
「つまらないものだってわかるの?」
「わかるさ」、そして文庫本をテーブルの上へ置いた。「文章なんてつまらないさ。文章なんて書くくらいなら、文章なんて読むくらいなら、実際に行動した方が面白い」
僕は何かしら言い返そうとしたけれど、何を言ったとしても彼には通用しないだろうと思い直し、ムキになることなんてないと自分に言い聞かせた。そして代わりに「何しに来たの?」と彼に訊いた。発言した後で、こっちが本題だということに気付いた。
「ああ、そうだった」と男は白い手袋に包まれた指で頭を掻いた。「それが肝心だ」
無意識の内に、自然な流れで年上であるだろう男に対して敬語を使い忘れていたことに気付いたが、そのことについて彼は咎める気はないようだった。
「カオル君。っていったっけ」、男は僕の顔を見て言った。
「え? うん」
「カオル君さ、お父さんって大きな会社の社長さんだよね」
「うん」
「ああ、やっぱり」
彼が僕の名前を知っていることも、僕の父親が社長職に就いているのを知っていることも不思議だったけれど、それを質問する権利は与えてくれないようだった。
「いきなり本題に入りたいところなんだけれど、その前に自己紹介だけさせてくれ」、男は一旦間を置いて、両手を広げながら続けた。「俺さ、殺し屋なんだ」
室内が、一瞬だけ雨音に支配された。
「う、うん」
「反応薄いね」、不満そうな顔をする男。
疑問に思うことと混乱するべきことが多すぎて、まともなリアクションが出来ない状況だった。こんな場合、まともなリアクションというのがあるのかどうかは知らないけれど、流石に僕の反応が男の期待はずれだったことは理解出来た。
「まぁ、いいか。びっくり仰天されても、それはそれで困る」と男は広げた両手を軽く握った。「騒がれるのが一番嫌いなんだ」
現役の殺し屋を実際に見るのは、初めてだった。だけどその存在は父親とユージに幾度と無く聞かされていたので、突拍子も無い出来事というわけでもなかった。しかしそうなると、先程の「部屋に入れないと殺す」という発言は、脅迫まがいではなくて本当の脅迫だったということになる。僕は知らぬ間に、命の危機を回避していた。
「今朝、レストランの前でカオル君を偶然みつけてさ。どっかで見たことある顔だなぁって思ってた。それがずっと頭にひっかかってて、もやもやとしてたんだけれど、さっきテレビでニュースを見て、それで思い出したんだ」
「テレビ?」、僕は部屋に置いてあるテレビを横目で見た。
「そう、テレビ。カオル君のお父さんが経営してる会社が、他の会社と合併するっていうニュースをやってたんだ」
それは僕も知っていた。
僕の父親は絵に描いたような傍若無人な性格で、自分の会社を大きくすることしか考えていない、そういう類の人間だった。そのための一環ならば、社員を切り捨てることもなんとも思わない。だから父親は色々な人に恨まれていることも知っていた。それによって僕に及ぶ可能性のある被害も、ユージから聞かされていた。
僕は承知している。
「じゃあ、つまり」、僕は慎重に言葉を探して頭の中を冷静にする。「僕を殺しに来たってこと?」
即答するだろうと思っていたけれど、意外にも彼はうーんと腕を組んでうなった。
「カオル君を尋ねたのは、仕事じゃないんだな」と男は言った。
「どういうこと?」
「仕事はもう終わってるんだ」、男は組んだ腕をほどいて見せた。「今さっき、一人だけ殺して来た。今日はもうオフ」
さらりとした衝撃的な告白だったけれど、彼にしてみれば普通のことらしい。
今このホテルでは人が一人死んでいる。なのに建物内は至ってその静けさを依然崩そうとしない。簡単には見つからないようにしているのか。そこらへんのことについては、考えるのは無駄だし興味もなかった。だけどそれを聞いて、僕は安堵に似た感覚を味わった。両肩に走っていた微弱な緊張が緩む。
「さっきも言った通り、カオル君をみつけたのは偶然でさ、学校帰りにちょっと寄った駄菓子屋さんみたいなもん。財布持ってないくせに、みたいなさ」
殺し屋の男はよく分からない比喩を使って、背中を伸ばしながらソファに体を預けた。
「じゃあ、殺すつもりはないの?」と僕は訊いた。
「どうだろ」
あまりにも適当な答えだった。僕としては、直接的で直面的な死活問題なので、はっきりさせてほしいところだ。殺し屋には適当な男しかいないのだろうか。
「殺し屋って、もっとキチンとしてるのかと思ってた」と僕もより一層ソファに腰を沈めた。
「キチンとって、どんな?」、男は体勢を変えずに僕を見た。
「冷酷無比っていうか、もっとロボットみたいにさ、黒いスーツ着て、拳銃持って、さっさと撃ち殺してさっさと消えるような」、少なくとも殺し屋がルームサービスに化けて出てくるとは思わなかった。
目の前の殺し屋は、つまらない妄想だなぁ、と平べったい溜息を吐いた。
「でも確かに、そういう奴もいることにはいる。妙に職業的でさ、無駄に鉄仮面被って、あくまでも仕事だと割りきってやってるような奴」、男は後頭部あたりに両手をまわして組んだ。
「会ったことあるの?」
「あるよ」
男の口調は楽しそうではなかった。ここから話を広げるつもりはないらしく、横目に窓の外を眺め始めた。僕は質問する事項を見失った。
雨はまだ降っている。相も変わらずに、忘れてしまうくらい当然のように降り続いている。僕も男と同じ様に視線を横にずらし、窓をつたって流れ落ちる水滴を眺めた。一つの水滴がツツツと滑り、他の水滴とぶつかり混ざり合いながら加速して落ちていく。
その退屈な光景を見ながら、今日、目の前に座る彼に殺された誰かのことを想像してみた。探偵をするつもりはない。推理でもない、ただの暇つぶしとして。
ホテル内の何処で殺されたのだろうか。客室だろうか。
そういえば先程、男はさっきの女も同じ反応がどうとか言っていた。つまりそれは、僕を尋ねて来た時と同じ様に女性の部屋にルームサービスを名乗って現れたということで、ならば彼が殺したのは女性だと言う事になる。
そしてもう一つ。男がこの部屋に無遠慮に入り込んだ時、彼はツインルームは広いなと言っていた。つまり彼に殺されたのは女性で、殺された場所はシングルの客室内ということか。
そこまで思考を伸ばし、ひとつ気になる疑問を見つけた。それは疑いというよりかは、好奇心に偏ったものだった。
「どうやって殺したの?」、僕は窓から目線を戻して男に訊いた。
「あ?」と男は寝起きのような声を出して僕を見た。
「武器の話。拳銃とか、ナイフとかあるじゃん」
「ああ」、男は頭の後ろで組んでいた手をほどいて前にもってきた。「俺は武器は使わないんだ?」
「何も使わないの?」
「そう、素手。この両手で殺す」、そう言って白い手袋を嵌めた両手を力強く握った。「そもそも武器を使うと色々と面倒なんだ。銃を使えば弾が残るし、刃物を使えば切り傷が残る。それに対して素手なら証拠が残りにくい。特定がされにくい」
僕は声に出さずに感嘆し、表情だけで返事をした。意外と、色々と考えてるらしい。
「なにより素手で殺すのが一番楽しい。それが本音。別に楽しければ銃でもナイフでもバズーカでも日本刀でもなんでも良いんだ」
色々と考えている方向が違っていた。
「でも、素手だと大変じゃない?」
「別に大変なんかじゃない。首絞めれば死ぬし、頭をアホみたいに殴りまくっても死ぬ。両目を指で貫いたらショック死した奴もいたけど、あれはオススメはしないかな。手袋してても手が汚れる」
男は記憶の中にある情景を思い浮かべるように目を閉じた。オススメもなにも、僕は想像したくもなかった。それと、頭をアホみたいに殴りまくるのは大変なんじゃないだろうかと思ったけれど、質問してもまともな答えが返ってくるとは思えなかったので、口には出さずに飲み込んだ。
「そういえば」、目を閉じたまま、男は口を開いた。「もう一人は何処にいんの」
もう一人とは、ユージのことだろう。あれ以来、彼は姿を見せていない。
「今朝に野暮用が出来たとか言って、どっか行っちゃったきり」
「あれはなんだ。兄弟か?」
「友だち見たいなもの」
ふうんと納得したのかどうかわからないような返事をして、男はソファからゆっくりと立ち上がった。
「帰るの?」と僕は訊いた。
「どうしようかなぁ……」
男は室内をぐるぐるとまわり、ベッドに背中から倒れこんだ。展示品のようだったベッドが、一瞬にして整然さが崩壊した。しかしそこは僕のベッドじゃなかったので、怒りの感情は湧き上がらない。男の体は二度三度と小さくバウンドして――
室内に音が響いた。
まるで、水風船の破裂音を逆さまにしたようで、だけどなんとなく乾いた音。
それが三回リズムもなく響いて、ベッドの上の男の体も、一緒に揺れた。
殺し屋は何も言わずに驚きを混ぜた疑問符を顔に浮かべる。
そして血を吐いた。咳をするように、男の口から赤い血が飛び出す。さらに背中を中心としてベッドが赤く染まっていく。みるみるうちに血が広がり、清潔さを犯していく。
発言もできず、行動もできず、思考もできずにいる僕はただベッドを眺めているだけで、その視界に黒い影が出現したこともすぐに気付くことが出来なかった。
黒い影は、ベッドの下から出現した。這い出てくるように、ぬるりとすべり出て、立ち上がる。人だった。黒いスーツに包まれた男が、ベッドの下から登場した。革製の黒い手袋を嵌め、右手には拳銃を握っている。銃口には細い煙突のようなものがついている。サプレッサーだ。あの奇妙な音は、消音器付きの銃の発泡音だった。
最長記録だ、と黒スーツの男は言った。ベッドに倒れた殺し屋は、幾度か体を痙攣させていたけれど、まもなく動かなくなった。
「ベッドの下で隠れてた時間」、黒スーツの男は僕を見て言った。「最長記録だ」
「う、うん」
「反応薄いな」
よく分からないことに関して取り敢えず相槌をしてしまうのは、僕の癖だ。
「朝食も食べずにベッドの下に忍びこんで、今までずっとだ。いつまで経ってもお前の付き人は来ないし、代わりに来たのは他の殺し屋とは。流石に驚いた。先を越されるかと危惧したが、こいつはお前を殺すつもりはなかったんだな」
黒スーツの男は溜まったなにかをここぞとばかりに吐き出すように、一人でにしゃべりだした。
「分かっていると思うが、俺も殺し屋だ」
現役の殺し屋を一日で二人見るとは、どんな感想を抱いて良いのかわからなかった。だから僕は黙ったまま、沈黙で返事をした。
「さらに俺は、冷酷無比で、黒いスーツを着て拳銃を持って、さっさと殺してさっさと帰って寝る殺し屋だ」、そう言いながら黒スーツの男はあくびを無理やり噛み砕いた。
雨の音が聞こえる。
いつの間にか降りは強くなっていた。暴力的な雨滴が窓を叩く音が室内に充満している。
「まずは付き人を殺してからと思ってたが、不在なんだったら好都合だ」
黒スーツの男の拳銃が僕に向けられた。
光を吸い込むような黒い拳銃の銃口が僕をまっすぐ狙っている。今にも弾丸が飛び出して、僕の頭に直撃しそうな予感が持続的にまとわりつく。圧倒的で無慈悲な危機感が体の自由を奪う。
黒スーツの男の指が引き金を引くために関節を曲げる。
それと同時に、彼の首から銀色の刺が生えた。
続けてその根本から血が噴き出る。僕はそれをきっかけに、金縛りから解放されたように銃口から逃れた。黒スーツの男の体がうつ伏せに倒れる。うなじの辺りに一本、背中に三本、取っ手のようなものが生えている。ナイフだった。深々とナイフが突き刺さっていた。突然首から生えた刺はナイフの刃の先端だった。
「意外な展開でしたね」
バスルームから姿を表したユージが言った。そのまま黒スーツの男に近付き、刺さったナイフを丁寧に抜く。小さく血が吹き出た。ユージは抜き取ったナイフに付いた血を、手に持っていたタオルで丁寧に拭きとる。
「そのタオル、どうしたの?」、僕は額に浮かんだ汗をぬぐいながら、片方の手でタオルを指差す。
「バスルームから拝借しました」とユージは言った。
「出てくるのが遅いよ」
「しょうがないじゃないですか、状況がわからなかったんですよ。なんですかこの男は、何処から出てきたんですか」
「ベッドの下から」
「笑えますね」、ユージは口だけで笑った。
「笑えるんだ」
僕には笑う暇がなかった。
「殺し屋は彼一人だと思っていたんですが、予想外でした。彼がカオル君を殺す気がないなら、それはそれで見逃すつもりだったんです。だからカオル君とそこの男が楽しそうに会話しているのを聞いて、バスルームで安心していたんですけれど。まさか既にベッドの下に、もう一人の殺し屋がいたとは。しかもこっちが本命だったとは」
「殺し屋がホテル内にいるっていうのは知ってたの?」と僕は訊いた。
「それは知ってました。今朝、怪しさ満点のホテル従業員の格好をしたこの男を見かけて、こいつだと思っていたんですけれど、ハズレでしたね。彼のターゲットは女性でした。まぁ、高級なホテルですから、命を狙われる客は多いんでしょう」
僕の予想は当たっていたわけだ。
「だけれど、念の為に後を付けたらこの部屋に来たものですから、バレないようにバスルームに忍び込んだ訳です」
ルームサービスを名乗って一人目の殺し屋が部屋の中に入り込んだ時、その後からユージが姿を見せた。彼は部屋に入り込んだ男に気付かれないようにバスルームに隠れると、僕に鍵を閉めるようにと指示をした。そして今にいたるまで、ユージはバスルームの中で虎視眈々と殺し屋の命を狙っていたのだ。だけど殺し屋本人は僕を殺す気はなかったらしく、そのまま退散しようとしていた。ユージはそれを察して彼を見送ろうとした。けれど彼はベッドの下に隠れていた黒スーツの男に撃ち殺された。黒スーツの男が、僕の命を狙う殺し屋だった。
僕は自分の命が狙われていることを、この時初めて知った。ユージはできるだけ僕に知らせないようにしていたのだ。
「それにしても、ギリギリじゃないか」と僕は言った。「あと一瞬遅れてたら、撃たれてたかもしれない」
「大丈夫ですよ。殺し屋ってのは皆、意外とお喋りなんです。今回のような状況は滅多にないものですから、自分が有利に立っていると、無意識に余裕が生じてしまうんですね」
「そういうものなのかな」
「そういうものなんですよ」、ユージはナイフを服にしまい、立ち上がりながら笑った。「僕も、元殺し屋だから、わかるんです」
やはり、殺し屋には適当な男しかいないらしい。
ユージは足元に倒れた死体と、ベッドに仰向けに寝ている死体を交互に見た。ベッドは既に赤く染まり、絨毯にも血溜まりが出来上がりつつあった。
二つの死体は何も言わずにただ人形のように黙然している。
その沈黙を覆うように、雨音は激しさを保っている。窓をつたう水滴は数を増やし速度をあげ、外の景色を歪ませる。
「さて」、溜息混じりにユージが口を開いた。「どうしますか」
僕はもう一度、改めて室内を見渡した。
酷い惨状だと思った。
「ユージに任すよ。殺し屋なんだから、こういうの慣れてるでしょ」
「元、殺し屋ですよ」
「元、なんだったら、適当な仕事はしないでね」
「承知しました」
雨はまだ、降り続けている。
雨が降る日に死体がみっつ
殺し屋という職業は、探偵という職業と同じくらい小説において魅力的な要素になりうると考えています。
治安の悪い国では殺し屋というのは日常に潜んでいるのかもしれませんが、こと日本、僕の住んでいる地域では殺し屋や探偵は未知の存在にかなり近く、だからこそ非日常を書くのが好きな僕にはうってつけの職業なのかもしれません。