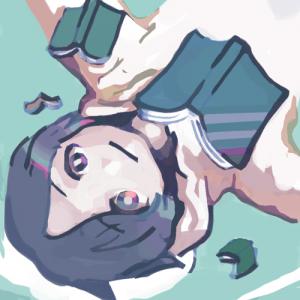兎
兎っていうのは、誰かを何処かへ連れて行ってくれる役なんですかね。
昔はボクだって、もっと黒い姿だったんだ。と兎は言った。
玄関に兎が立っていた。
二本の脚で立っている。
靴も履かず、背後にあるドアに施されたすりガラスから透きとおった夕日に静かにあてられている。
全身に白くふさふさとした毛をまとい、真っ赤なベストを着て、三つの大きな金色のボタンを前でとめている。首からは鈍く金色に光る、円盤のようなものをつり下げている。
場所も、状況も似つかわしくなかった。
兎の存在感は、まるで骨董品店に置かれた空気清浄機のように際立っている。
なにしてるの?
と兎が僕に尋ねた。血のように赤く、丸い二つの目が僕の顔をまっすぐに見ていた。
「いや……、台所に行こうと思って」僕は右手に持った白くなめらかに光るマグカップを見せた。
ふうん、と兎は退屈そうに、細い鼻息をもらした。なるべく早くしてね。そう言いながら左足に重心を傾け、右足で三和土を叩く。
タンタン、タンタン。
僕と同じだ。あれは他人を催促するときにする。やられた方は機嫌が悪くなる。それに僕が気付いたのはいつだったか。兎はそのことを知らないのか、はたまた承知の上なのか。
「なんで早くしないといけないの?」
出かけるんでしょう?
兎は首から下げた円盤を裏返して僕に見せた。懐中時計に見えた。だけど時針はなく、分針もなく、秒針だけが時計周りに音もなく動いている。真ん中に、デジタル数字の羅列が表示されていた。時刻ではない。一番右はしの数字が、正確に一秒を積み重ねている。兎の右足が刻むリズムとあわさる。
タンタン、一秒。タンタン、一秒。
「出かけないよ」僕は数字に目をあわせたまま言った。
どうして?
不思議そうな顔。
どうして出かけないの?
「行くところがないから」
なんで?
不満そうな顔。
なんで行くところがないの?
「どうでもいいじゃないか」僕は言う。「僕の勝手だろ。どこに行く予定もない」
予定がなくちゃいけないの?
「そうだろ」
違うね。
兎は言った。
嘘だね。
兎は笑った。口が横いっぱいに広がり、二本の白い歯がのぞいて見えた。
「なにが嘘なんだよ」
予定があっても、どこにも行かないくせに。予定があったって、どこにも行けないくせに。行きたくないくせに。自分から消したくせに。自分から逃げたくせに。
兎は抱えた時計を目の前に掲げた。
見てくれよ、この時計。もうこんなに進んでしまった。もうこんなに溜まってしまった。ボクは、もうこんなに遅刻してるんだ。早く止めてくれよ。君が止めてくれよ。君が止めないと、時間は進む一方だ。
タンタン、一秒。タンタン、一秒。
早くボクを連れていってくれよ。
兎は二本の耳を揺らした。
時計のデジタル数字が、一秒を一秒ごとに積み重ねていくのを、僕は黙って見つめていた。
折角ボクが迎えに来たんだぜ? ここまでやって来たんだ。こんなに時間がかかったし、みんなに反対されたけれど、やっとこうやって出迎えに来れたんだ。それは君だって知ってるだろ?
僕は理由もなくマグカップの中をのぞいた。
何も入っていない、空っぽだった。
虚しくて、哀しいだけの空っぽがあった。
底にはうっすらと影が溜まっている。
君は弱虫だね。
兎の声は、怒っているのか、荒だって響いた。
なんて弱虫なんだろうね。そうやって逃げ続けて、父さんと母さんからも逃げて、もうここは袋小路じゃないか。自分の部屋で時間が流れるのを眺めて。次はどこに逃げるっていうのさ。窓の外から飛び降りるかい?
「弱虫なんかじゃない」声が言葉になってから、ふるえていることに気付いた。「それに、逃げてなんかいない」
強がるのも弱虫の証拠だね。
兎は真っ赤な目を細めて言った。刻むリズムがもたらす一秒が、僕の頭の中に染みこんでくる。額の裏側が熱くなっていくのがわかった。
君が弱虫で、優柔不断だから僕が迎えに来たんじゃないか。自分一人で行動することも出来ずに、そのくせ他人にも頼らずに逃げてる。どこまでも臆病で、怖がりで、弱くて、弱くて弱くて弱くて弱くて――
「うるさい」
響いた自分の声に驚いた。曖昧で、だけど確かな怒りがこもった言葉が、ひとりでに飛び出した。
兎は両目をパッと大きく開いて、次にしゅんと悲しそうな表情を見せた。
ごめんよ。ごめんよ。悪かったよ。もう言わないよ。
そう言う兎の二本の耳が、ゆっくりと垂れ下がっていく。足の動きもピタリと止まった。
しばらくの間。どこからか聞こえてくるひぐらしの鳴き声だけが、沈黙を遮ってくれた。
僕は奥歯を強く噛み締めた。連動するように、自然と両手にも力が入った。すりガラスを通った夕日にあてられて、影を差した兎を見る。すっかり垂れ下がってしまった耳が顔を隠していた。
肌、と兎は呟いた。肌、白くなったね。真っ白だね。
顔を隠す二つの耳の隙間から赤い目がのぞいている。
「君に言われたくなんかない」僕は兎を指さした。
昔はボクだって、もっと黒い姿だったんだ。と兎は言った。知ってるだろう?
だって、ボクは、僕なんだから。
だって、僕は、ボクなんだから。
「……そんなの」重たい口を開く。「そんなの、思い出したくない」
言葉とは裏腹に、頭の中に水のように流れる景色が見えた。
眩しい太陽の光を受けて、黒く焼けた腕と足を思い出した。
額に浮かぶ汗と、それを拭い前を見る楽しさを思い出した。
それはボクの記憶だった。
もう叶うことない夢の跡。
望んだのに、目を背けた。
……そうだよね。
うつむきかけた顔を少しだけ上げて、吹けば消えてしまいそうな声で応えた兎は、また右足を動かし始める。永遠に一秒を刻み続ける淡々とした無慈悲なリズムが響く。僕はその音から逃げるように踵を返して台所へ向かった。
もうすぐ両親が帰ってきてしまう。
早く自分の部屋に戻らないと、出くわしてしまう。顔をあわせてしまう。
タンタン、一秒。タンタン、一秒。
兎
不思議の国へ連れて行ってくれる兎ですが、誰もが不思議の国に行きたいと思っているわけではないんですね。