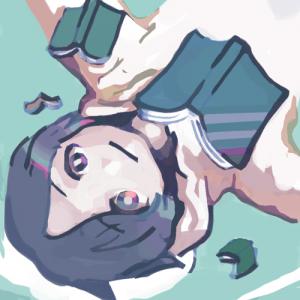三流死神
自分が初めて書いた掌編小説です。
社会に押しつぶされた男が出会ったのは自称死神。死を与えてくれるという彼についていくと……。
「……死にたい」
最終電車の中。男が無意識的に口から零した言葉は、行動には移せなくとも、限りなく本心に近かった。
男の年齢は三十代の後半といったところで、随分と年期の入ったヨレヨレのスーツを着ている。十人ほどが座れる広さの座席の一番端に腰を下ろし、傍らには黒い鞄を無用心に置いていた。
車両の中には男以外には誰も居なかった。長方形の空間の中には、電車の規則的な音が響き、不規則で微弱な振動が隙間なく伝わって来て睡魔を際立たせる。
男は前のめりに背中を曲げ、拝むように組んだ両手の上に頭を乗せて溜息を吐き出す。男が吐き出した溜息には、安堵ではなく絶望が混じりこんでいた。
「死にたい」
男は吐き出した溜息をもう一度吸込み、言葉としてまた吐き出した。
車内に流れるアナウンスが停車する駅名を告げていた。
男の日常は毎日が同じことの繰り返しだった。平日だろうと休日だろうと男の日常に変化は訪れず、同じビデオを何度もリピートして見ているような、そんな味気の無い日常。
朝早くに起床し、満員電車に体を押しこみ出勤する。出社をすれば、年下の上司に理不尽な仕事を不条理に押し付けられ、処理が出来ずに怒鳴られる。定時に帰ることは許されず、帰りの電車が無くなってしまうという理由で、帰宅することを許された。他の社員達は定時に帰る為、男は社内の自分のデスクに一人で仕事をするはめになる。
無人の最終電車に揺られて自宅に帰ると、六畳一間の四角い部屋が男を迎えてくれた。部屋の中は殺風景で、目立つ物といえば、常に畳の上に広がっている布団に小さな木製の机くらいだった。だが、帰ってきたら糸が切れたように布団の上に倒れる男にとって、それ以外の家具は必要なかった。
こんな日常が始まってから、もう何年になるだろうか。最初の時期は元気もまだ余っていて、自分の不遇について他の社員に愚痴を零したり、帰り道で電信柱を意味もなく蹴飛ばしたりもしていた。が、今となってはもうそんな気力は残っていない。愚痴を吐いたり物に当たったり等の無駄なことはせず、自分の身体に出来るだけ負担を掛けずに、次の日のリピートに備える。
だが今日、そんな男の日常に変化が起きた。
照りつける太陽が背中を焦がすような暑い日の昼間。男は取引先の会社へと行き、取引を終えて大金の入ったアタッシュケースを持って会社へと戻るだけだ。時間にも余裕がある為、男はアタッシュケースと黒い鞄を持ったままファーストフード店へと寄った。帰ったとしても部長に次の仕事を押し付けられるのだ。会社の外に出た際は、男はいつも余った時間を利用してこのファーストフード店で休憩をとっていた。
店内は外とは別世界のように涼しかった。男は外で消費した水分を取り戻すために水を大量に飲む。連日まともな物を食べていない空の胃袋に冷たい水が流れこむと、少しだけ気持ち悪い気分になった。
事件が起きたのは、その時の事だった。
男が少しの間トイレへと行き、戻ってきたら、取引先の会社から持ってきた大金の入ったアタッシュケースが無くなっていた。男は慌てて辺りを探すが、それらしきものは見当たらない。周りの客に声を掛けてみるが、皆揃って首を横に振るだけだった。
男は店内を隈無く探し回ったが、それでもアタッシュケースは見つからない。時間もそろそろ会社へと戻らなくてはいけない時刻へと近付いている。部長の事だ。一分でも遅れたらまた怒鳴り散らかすだろう。
男は勘定を済まして店を出る。店の入口にあるレジを担当している店員に「アタッシュケースを持って出てった奴はいなかったか」と聞いたが、わからないとまた首を横に振られた。
容赦なく照りつける太陽の光に目がくらみ、一瞬だけ世界の色が反転する。頭の中でぐちゃぐちゃと色々なことが混ざり合って隙間なく埋め尽くしていく。
邪魔な雑念を追い払い、考える。男の持っていた黒い鞄は盗まれていない事からして、アタッシュケースを盗んだ犯人は、あの中に大金が入っていることを知っている人物だろう。中身を確認しようにも、あのアタッシュケースには鍵がかかっていて、四桁の暗証番号を正確に合わせないと開かないようになっている。その暗証番号を知っているのは、自分と、取引先の会社の社員だけだ。
男は目眩にふらつく両足をなんとか動かし、すぐさま先程まで居た取引先の会社へと舞い戻った。取引の件で話をしていた社員に問い詰めたが、なんのことだかわからない、と困惑した表情をされた。
時計を見ると、もうすぐにでも会社に戻らなくてはいけない時間を示していた。
結局男は、大金の入ったアタッシュケースを見つけること無く会社へと戻り、上司にこれ以上ない程に怒鳴られ、そして殴られた。必死に訳を話したが、突然アタッシュケースだけが無くなるなんていう突拍子も無い話を信じられることは無かった。
「もしその馬鹿げた作り話が本当だとしても、お前が無くしたも同然だろう。取引先から受け取った金はお前が全額払うんだな」
上司はそう怒鳴りつけ、次の仕事に関する資料の束を男に投げつけた。
なんとか会社をクビになることは避けられたが、男はこの事件のせいでコツコツと長年稼いできた金も残り少なかった上司からの信頼も全て失うことになってしまった。
「お困りのようですね」
自分以外居ない筈の車内の中に声が響いた。感情という色が一切混じっていない、無色透明の声だった。
男が俯いていた顔を上げると、丁度自分の正面に位置する座席に、一人の青年が座っていた。年齢は詳しくはわからないが、二十代の半ばといったところだろうか。服装、人相と共に、特徴といったものが見つからず、目を逸らしたら存在を忘れてしまうような存在感の薄さを身に纏っている。
いつの間に乗り込んで来たのだろうか。次の停車駅を表示するパネルを見上げると、まだ男の住むアパートまでは半分近く残っていた。
「お困りのようですね」
青年はもう一度同じ言葉を言った。自分と、その青年しか車内には存在しないのでおそらく自分に向けた言葉なんだろう。言葉の意味が良く分かりかねるが、適当に相槌を打つ。
「良かった。人違いだったらどうしようかと」
「えっと。すいません。何方でしたっけ」
青年に対してさえ、敬語を使う自分が嫌になった。年下の上司を思い出す。
男は青年に見覚えがない。逆に青年は男のことを知っているかのように話しかけてきた。そして、何を判断材料にしたのかは分からないが、青年は男を見て人違いではないと判断したらしい。
「死神。といえば、分かりますかね。僕には他と区別するための呼称が無いので。とりあえずは、死神と名乗らせてもらいます」
「は、はぁ」
意味が分からない。呼称が無い。つまり名前が無いということだろうか。それに死神とはなんだ。
青年の言っていることは、文章にしてしまえば冗談にしか見えない。だが、それをこの青年が言葉として発することによって、妙な信憑性を男は感じた。
「死神と言っても、元は人間ですし。混乱されてもこちらとしては困りますので、あまり気になさらなくても結構です」
「は、はぁ」
「ところで、貴方にとっては突然になりますが、僕が貴方を殺して差しあげましょうか?」
「は、はぁ……は?」
「あ、ごめんなさい間違えました。具体的には、僕が直接貴方を殺すのではなく、貴方を死に導いて差し上げましょうか。という意味です」
聞き逃すほどの小さな舌打ちが聞こえた。
突然何を言っているのだろう。殺すとか死に導くとか。なにやら物騒なことを言っているのは分かるが、青年の目的が不明瞭だ。殺し屋、ということだろうか。いや、自分では殺さないと言っている。ならば、殺し屋と目標(つまり自分)を繋ぐ中継役ということだろうか。落ち着いて考えれば冗談にしか聞こえないが、何故か青年の言葉には、上手く受け流せない雰囲気があった。ひっかかり、というのだろうか、頭に纏わりついて離れない。染み付いて、離れない。
「多分、頭の中で色々な考えが飛び交っていると思いますが、難しいことではないです。言葉そのままの意味をシンプルに受け取ってもらって結構です」
青年の無色透明の声は、疑念が湧いている男の頭の中になんなく染み渡る。まるで耳を経由せずに、直接頭へと入ってくるようだった。
「つまり、僕は死にたがっている貴方に、死を呼ぶことがでる。それが僕の仕事です」
「仕事、ですか」
「そう。仕事です。貴方はその仕事のせいで、お困りではないですか?」
男は今日の事を思い出す。仕事。無くなったアタッシュケースと大金。借金。男を不幸に導くキーワードが、頭の中に浮かんでくる。明日からの事を考えると、胃の辺りが気持ち悪くなる。どうすればいいのだろう。どうすることもできないのだろう。何も出来なくなる。今まではコツコツと薄給を貯めて生活できていたが、それもすぐに苦しくなる。今回の件で無くした大金を払い終わったら、おそらくクビになるだろう。そうなったらもう終わりだ。
「どうですか? このまま生きて不幸を永遠に味わうより、いっそ死んでしまってこの絶望から逃げ出してしまいたい。そう考えていたのではないですか?」
青年が男の背中を押すように、死の運命を促してくる。
何故だろうか。死、という言葉に対する抵抗は無かった。混乱している頭の中の隅で、妙に落ち着いている箇所がある。死。死ぬことが出来たなら、この苦しみから開放されるのだろうか。この理不尽で不条理な、不幸に塗れた世界から開放されるのだろうか。
男の中の天秤は、このままこの世界で生きて経験した不幸、そしてこの先経験するであろうさらなる不幸に耐えることが出来なかった。
青年は男の表情を見て、僅かに口の端を吊り上げた。
「料金とかは、払ったりするんですか?」
「必要ないですよ。人間じゃないんですから。貴方が死んでもらえれば、それで充分です」
青年が自分を見る目はとても黒く、その目で見られるだけで、崖の淵へ後押しされている気分になる。抵抗はない。むしろ心地いいくらいだ。
「それでは、そうですね……次の駅で降りましょう。少しだけ歩くことになりますが、よろしいですよね?」
青年は停車駅を示すパネルを見上げながら言った。
男は最後の迷いを振り払った。
もう後戻りは出来ない。する気もない。自分はやっと、この不幸な世界から開放されるんだ。ある種の清々しさがある。日頃、暇さえあれば自殺の方法を考えてはいたが、まさか死神に殺されることになるとは。不幸に魅入られた自分には、これ以上なくお似合いなのかもしれない。
死神の青年と男が駅の改札を抜けた街は、真っ黒に染まった空とは違い、明るいネオンに包まれていた。深夜の時間帯にも関わらず、歩道では歩行者とすれ違うことが少なくなく、車道では停止を告げる赤信号の下に車が何台か詰まっている。
男と青年は、薄いパステルカラーのタイルが綺麗に敷き詰められた道を並んで歩いていた。ホテルから出てきた男女や、コンビニの前で屯っている若者が、視界の端に見えては消えていく。駅から出てからからは青年との会話は無く、外灯や光るお店の看板に照らされながら歩き始めて、十数分が経過している。
何処を目的として歩いているのだろう。青年の歩き方は、目的地を決めてそこに向かっているというよりは、気まぐれや散歩のように街を徘徊しているように思えた。
「どこまで歩くんですか?」
無言で男の斜め前を少しだけ先行して歩き続ける青年に、たまらず聞いた。
「そうですね。この道を進むと、建設中のビルがあります。そのビルの先を進んだところにバーがあるので、とりあえずそこまで歩きましょう」
男からの質問を予測していたのか、青年は教科書を音読するように感情が入っていない口調で答えた。
青年が使ったとりあえずという言葉に違和感を覚えながらも、男は後に続く。知らない夜の街を歩き続けた為に、ここで帰ると言い出しても道がわからない。彼の言葉に従って歩くしかないのだろう。
さらに数分歩くと、青年の言った通り、白い囲いに囲まれた建設途中のビルが見えてきた。ビルの上では、クレーン車が一台、夜空へと首を伸ばして佇んでいた。街の灯りもそこまでは届かないのか、遠目からだとクレーン車が複雑なモニュメントに見えないこともない。
「見えてきましたね」
青年の歩幅が、僅かに広がったような気がした。急いでいるのだろうか。置いてかれないように、男も歩幅を広げる。
ビルのすぐ横を通る道、男は真上を見上げる。強く、冷たい風が男の首に巻きつく。ビルの上の方では、さらに強い風が吹いているのか、鉄骨に被さった灰色のシートがバタバタと音を立てて暴れていた。
曲げていた首が疲れたために、男が頭を下げた時、上空から猛獣のイビキのような音が聞こえた。否、鉄が曲がった音だった。何事かとすぐにまた空を見上げると、電信柱以上はある真っ黒な鉄骨が、渦巻く風を貫きながら落ちて来る。
「う、うわっ!」
男は自分めがけて落ちてくる鉄骨を反射的に避けようと足を前へと踏み出す。が、走りだそうとした瞬間、前へと出した足が何かに引っかかった。何もかもがスローモーションに感じる一瞬の間、足元へと視線を移すと、誰かの靴が自分の前へと出した足を止めていた。青年の足だった。男は躓いて、その場に倒れる。
うつ伏せに倒れた男の下半身に鉄骨が直撃した。右足を潰し、骨を砕き、腰を抉り、左足も潰す。そのまま鉄骨は、敷き詰められたタイルを抉り飛ばし、凄まじい轟音を響かせながら何度かバウンドして転がり、止まった。
「た、助けてくれ……誰か」
男の抉れた身体から、真っ赤な血液が蛇口を閉め忘れたホースから漏れ出たようにドボドボと流れ出る。瞬く間に血溜まりが完成した。
男は混乱して自分の身体の状態に気づいていないようだった。両手を醜くバタつかせて助けを求める。突然響いた轟音を聞いて、大勢の人間が集まって来る。
「死にたがっていた癖に、いざ死ぬとなると生きたがる。本当に醜い」
男の傍らで、青年が誰に問いかけることもなく、独り言を呟く。
「即死とまではいかないか。死ぬことには変りないけれど、これじゃあ意味が無い」
青年は身体の半分が潰れた男を一瞥し、背を向けて歩き出す。次々と集まって来る人ごみをすり抜けるように進む。青年の肩が何人かの人間に当たったが、誰も青年の存在に気づいていなかった。
両脇を高いビルに囲まれた道を歩いていると、二つの建物の間に溜まっている闇から声が聞こえた。
「また失敗かよ。しかもよりによってあんなに醜い殺し方とはね」
「うるさい。街を歩きまわっても、あのビルからしか死を呼べる気配が無かったんだよ」
「それはお前が未熟だからだろ。暗示もまだまだ弱い。俺ならあんな男、自分から飛び降りさせてやるさ。あんな中途半端な暗示だから、あの男も最後には死から逃げやがったんじゃねえか」
「……」
「お前はそんなんだから――」
「うるさい」
誰もいない無人の公園のブランコで、死神が一人、項垂れていた。空は真っ黒に染まり、その中で穴が開いたように真っ白な月が静かに輝いている。
死神は拝むように組んだ手に載せていた頭を上げ、夜空に向かって白い溜息を吐く。
「また失敗した。これで何度目だ。畜生、せっかくアタッシュケースを盗んだっていうのに。これだから僕は、三流死神なんて言われるんだ」
輝く月が照らす無人の公園で、三流死神は一人でブランコを揺らす。
三流死神
これを書いたのは中学生くらいの時ですが、黒歴史は黒歴史として添削しないで載せてしまおうという魂胆で(本当は書きなおすのがめんどくさかった)そのまま載せてみました。