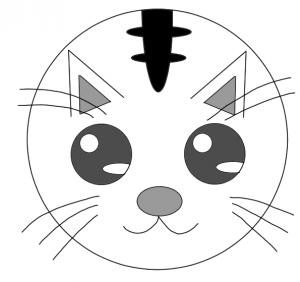ある日の僕のモノクロームな世界
三題話
お題
「謝罪」
「パステル」
「画家」
いつもと同じような朝。いつもと同じような空。
いつもと同じような、それでいていつもと少しだけ異なる、今日の僕。
ぐるぐると回る時計の針はいつまでも同じ場所を行ったり来たり。
決まった領域内でしか動けないのが人間なのだと理解しつつ、僕はそれを歯がゆく思っている。
…
「今回も素敵な絵ですね。題材はタンポポですか?」
そう、キャンバスの前に座る僕の斜め後ろにいる少女は笑顔で話し掛けてきた。
「ん、あ、ああ」
その問いに対して、僕は曖昧に頷くことしか出来なかった。
まだ色の塗られていないデッサンであるし、そもそも僕の絵には題材なんて高尚なものは存在しない。
見方によってはタンポポに視えるのだろうか。もしかしたら何かの花のように見えるのかもしれない。
でもそれは彼女の感性が生み出した幻想であり、そんなものに意味は無い。
「まだ絵は完成していないのに、どうして素敵だと言える?」
「それは……先生の作品だからですよ。例え点の一つ、線の一本であろうとも先生が描くものは全て私の心に響いてきます。それが何なのか、うまく言葉にすることは出来ませんが、何かを感じるのです」
そう力強く言って、彼女は笑った。
そのきらきらとした笑顔が、僕は苦手だ。
描きかけのデッサンへ目を向けると、白いキャンバスに黒炭の線。僕の内面を描いたそれは、彼女には全く別のものに見えているようだ。
いつものように目を閉じて、感覚を遮断する。
視界は真っ暗、周りは静寂。
ここでは独りだ。
僕の心は渦潮のように、ぐるぐると永遠に沈みこんでゆく。
無限に続く螺旋。始点と終点がはっきりとしない。
前回よりももっと深く深く。自身を求めて下ってゆく。
どこまで行こうと、一向に底が見えない。それどころかここでは何も見えない。
闇の中。静寂。何も無い空間。
ああ、まただめか。
今回も何も得られないまま、僕はゆっくりと両目を開いた。
「これで、デッサンは完成ですか?」
キャンバスの前に座る僕の斜め後ろにいる少女は、静かに口を開いた。
「ん、あ、ああ」
その問いに対して、僕は曖昧に頷くことしか出来なかった。
「あとは色を塗るだけですね?」
「そう、だな」
僕はそのモノクロームを見て、胸にずきりと痛みを感じた。
これから色付けされるであろうその絵は、僕の心の一部分だ。
モノクロの僕を、パステルカラーに染め上げる。
そうすればいつか僕自身が普通の人間になれると思うから。
淡い色彩が美しい、僕の斜め後ろにいる少女のように――。
振り返ると、彼女は申し訳無さそうな表情を浮かべた。
「あ……すみません。私がいたら邪魔ですよね。では、そろそろ帰ります」
彼女は長い髪を揺らしながら一礼をして、静かに部屋から出て行った。
微かに残った甘い香りが僕の鼻腔をくすぐる。
モノクロームな世界が少しだけ色付いて見えた。
…
夜になれば眠りに付いて、朝になれば目を覚ます。
当たり前の生活。当たり前の日常。
そして今日もいつもと同じような一日が始まる。
ある日の僕のモノクロームな世界