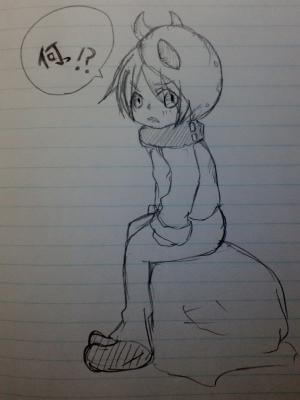いぬかぶり 第3話
3話を出すことになりました。ここまで付き合ってくれている人ありがとうございます。
今回もこんな稚拙なお話に付き合ってくださると大変うれしいです。
では、お楽しみください。
「いらっしゃいませ。」
佐藤は家と駅を結んだ最短距離の道のりを一本外れた道を歩いた。
普段は…というか、今住んでいるところに来てから一度しか進んだことのなかった道だ。
その道を進んでゆき、住宅街を抜けている最中に小さな喫茶店を見つけた。佐藤は何となくその店に入った。
その店は、普通の家の一階に作られている感じだ。入って左側にテーブル席、右側にカウンター席そのカウンター席にキッチンがある。その向こうに見えるカーテンは、きっと住居と店を仕切るものだろう。かすかに聞こえてくるFMラジオが落ち着く感じだ。
「あれ?初めて見る顔だ。」
店に入った時にカウンターには短い茶髪の女性が立っていた。
佐藤が無言で入口に立っていると、さらに彼女は声をかけてきた。
「どうしたの?ボーっと立ってて。早くこっち来て、すわりなよ!」
「あ…はい。」
普通の喫茶店とはちょっと違うようだ。こんなに店員さんが話しかけてくる店に行ったことはなかった。
「何する?これ、メニューね。」
「あ。はい。」
手元には、手書きのメニュー。字はかわいいかんじだ。
佐藤は少し悩んだ後に注文をだす。
「…パン・オ・ショコラと、カフェオレ。」
「オッケー。」
そういうと、店員はキッチンでいろいろ作業を始めた。
鼻歌混じりなところはものすごく楽しそうだ。
「あら?お客さん?」
カウンターの後ろのカーテンをめくって、40代頃の女性が出てきた。髪はものすごく短く、黒いままだった。
「はい。お母さん。初めて来た人です。」
「あらそお…。名前を伺ってもいいかしら?」
「え…佐藤と申します。」
「へえ…佐藤さんね…。」
少し顔を覗いた後で
「あなた、今日何か嫌なことあったんじゃないかしら?」
小さく質問をする。
「え。分かるんですか?」
「えぇ、まぁ。話してくださると何か楽になるかもしれませんわ。」
「そうですか、じゃあ…。」
「パン・オ・ショコラとカフェオレです。」
佐藤は、カウンターによりかかるような状態で話していた。
「って言うことで、無職の状態です。」
「あらあら。」
お母さんと呼ばれた人は、眉をハの字にした。
「一つ提案があるわ。そこの、テーブルの端でパソコンを広げている彼。彼はいろんな会社や事業とパイプを持っているわ。だから、彼に再就職先を探してもらいましょうよ!」
「いいね!それ!」
カウンターの向こうから、バンダナをした状態で最初の女の人が出てきた。
「あ、佐藤さん。これ、うちが作ったパン・オ・ショコラなんやけど、味はどう?」
佐藤はパンを一口かじる。焼き立てのため、クロワッサン生地がパリパリしていて、かつ中のチョコはとろとろになっていた。
親指をピッと立てる佐藤。
うれしそうに手をたたく女性店員。はにかんだ顔がとてもかわいい。力こぶを作り、二の腕のところをぽんぽんと叩いてガッツリドヤ顔。
「あ、うちね、加賀美巳緒っていうん。佐藤さん、これからよろしくね。」
「は…はい。よろしくお願いします。」
「巳緒ちゃん、佐藤さんの仕事の話はどうするつもりなの?」
お母さんはカウンターの向こうの椅子に座って、巳緒をみる。
「あ…そうだよね。どうする?佐藤さん、あの端っこの彼を使ってみる?」
「あぁ?」
端っこの彼…色白に黒縁メガネがよく似合う顔。少し長めの黒髪が特徴的。
テーブル席の入り口から最も離れた一角を占領している。テーブルの上にはパソコンと何が入っているか分からないジュラルミンケースが足元にある。パソコンを見つめたまま、カウンターの方をじっと見つめる。
「まったく、俺をなんだと思ってんの?俺は就職情報誌じゃないんだけど。」
「朝開店直後に店にやってきて、それでいてまっすぐ店の電源を使いまくっている男が何言ってんの?」
お母さんがカウンターの向こう側から呟く。何か頼みなさいよ。せめて、コーヒーぐらい。
「今月の使った分の電気代は払うって言ったじゃん。今朝。」
「え、お母さんそんなこと話してたん?」
「巳緒ちゃーん、聞いてよ。お母さん、毎朝『電気代~。電気代~。』って、言ってくるんだよ~。」
佐藤は、黙って座っているだけ。巳緒は男の呼びかけを半分無視する。
「佐藤さん。この人、多田恭太って言う人。今は、国の何かの機構に所属しているらしいんだけど、いろいろ言って職場には行ってないんよ。ただめんどくさがっているだけね。要するにひきこもり一歩手前な人。ここにしか、普段からいないんだから。三食すべてここで食べているから、家は睡眠と入浴とかにしか使っていないのよね。」
巳緒はよくわからない顔をして座っている佐藤に話しかける。佐藤は多田の座っている方に体を向ける。
「こんにちは。佐藤って言います。」
「おう。おれは多田な。で、巳緒ちゃんの言っていた話は半分事実で半分真っ赤なウソな。俺は確かに一日の大半をここで過ごしている。でも、それは仕事場に出るのが面倒なんだからなんかじゃないんだって。俺は、あの職場にいると仕事の能率が大きく下がるの。だから、職場に行かないでここでいろいろやってるわけ。分かった?」
「は…はい。」
「でだ。佐藤君、君は僕のパイプを使うのかい?」
佐藤は考える。再就職をしたい佐藤にとってこの話はおいしいものだ。しかし、佐藤はこの多田という男にであってまだ一日もたっていない。それなのに、この男に自分のこれからの人生をかけるのか?
「多田さん。僕に少し時間をくれませんか?僕はまだお金をもらえる身なんです。だから、考える時間をください。それでもいいですか?」
「いいよ。その判断は君の自由だからな。」
「これからよろしくお願いします。」
「へぇ、じゃあ加賀美さんはここでバイトしているんですね。」
「そうよー。佐藤さん、うちのこと巳緒って呼んでいいんよ。気を使わなくていいんだから。この店ではね、みんな家族のようにするんよ。一応お客さん、やけどね。何回も来る人は家族決定!」
「珍しいですね。このあたりでこんな感じの店ってありませんよ。僕、この近くに住んでいるんですけど、ここを見つけてよかったかもしれません。見つけなかったら今のこの状況を相談する人はいなかったので。」
「そうだよね。佐藤さんはここの人じゃないもんね。おまけに両親はここに居ないし。」
佐藤は気づいたら店に2時間はいた。一応精神的ダメージを受けた佐藤にとってはなぜか居心地の良いところだった。みんな自分のことを受け入れてくれるのだ。巳緒が“家族”と表現したのも納得がいった。
ふと佐藤は後ろを振り返った。多田は椅子でひっくり返っていた。
「多田さん、どうしました?」
「…んや?なんでもない。上手く仕事が進んでないだけ。」
ドアベルが鳴る。ドアを開けて入ってきたのは、一人の男。
「あら、高波さんやん!こんにちは!」
「高波さん、いらっしゃい。」
「おう。」
高波と呼ばれた男は、この店を長いこと利用しているらしく店員二人と親しげだった。
高波という男は、背丈は少し高めだが、肩幅が広いせいか大きくみえる。すこし長めの濃い茶色の髪にパーマをかけていた。佐藤はまっすぐこの男をカッコいいと感じた。そのカッコよさは、きれいとかそのようなものではなく男らしさが強かった。
「うん?初めて見る顔がいるな。」
佐藤は彼の低い声に少し驚いた。
「そう!彼は佐藤さん。今日初めて来たん!」
「よろしくお願いします。」
「ん。よろしくな。俺は高波敬吾。今は、近くでちょっとした仕事をしている。あと、どうしようもない年上のはずの男たちの面倒を見ている。あ、巳緒さん。あいつらはたぶん6時を過ぎたぐらいに来ると思う。」
「そう。にぎやかになるね。」
「おい、多田。」
「はい。なんですか、高波さん。今度はどんな悪ふざけの話ですか?」
「なんで俺を見ると悪ふざけの話を連想するんだ。」
「だって、高波さんの話は大体、そんな話じゃないですか。」
「…なんだよ。それ。今回はちょっと仕事関係の話だ。いいか?」
「なんだよ。珍しいな。」
いぬかぶり 第3話
このあいだ、ふと自分の受験のことを思い出しました。
大学受験ですよ。
今は教育学部でお勉強していますが、他に受けたのは某女子大学の数学科と某有名私立大学の機械工学科。
今考えれば、何をしたかったのか不明ですね。
機械工学科を受けたときの話。
機械工学科だけあって、女の子はほとんどいません。
教室内に2人だけでした。
そんな状況下でのおひるごはん。
家からお弁当を持ってきました。
開けます。
箸を見ます。
絶句
長さの異なる木製の箸とプラスチック製の箸が出てきました。
一人で爆笑…したかったのですが、周りはみんな見知らぬ男性。
女子高だったこともあり、恐怖感倍増。
誰にもなにも言わずに黙々と食べましたとも。
めげなかったぜ、私。
どんな冷たい視線にも耐えちゃうんだぜ。
まあ、だれも見てなかったのだろうけど。
なんて考えながら、3話をたたみましょう。
次回も読んでくださるとうれしいです。
それでは、また。