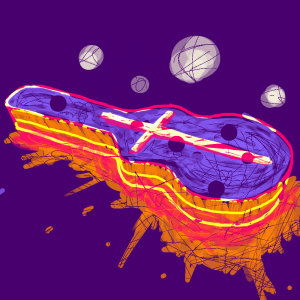だんもやいやい
ダンモ員の日々を記すゾ、全ての活動日分を記すのはキツいからとびとびに描いていくゾ
4月8日 午前
面白いことをしでかしたかもしれない。
まずいことになったかもしれない。
気合で内申をオール5にしたら、偏差値69の高校に入ることを、許されてしまった。
この町で一番かしこい、東京都立サルビア高校。
自由と博愛の精神を持つ、本物志向の高校の、入学式がもう始まっている。
「本年度は…240人……新入生…おめでとうございます …県立…相境中等教育……提携で……新入生のうち80………ここへ…入学することになりました…… さあ…全ての新しい友達………大切にしてください。…これからの学び………起点は……全て出会いの中にあります
…みなさん…豊か………成長を…祈ります」
校長先生の話が、講堂の天井に融和して、飽和して、私の耳に入る前に消えた。私は、講堂という空間に驚いていた。綺麗で大きくて、拍手の音にリバーブがついてくる。ここにパイプオルガンを建てたらさぞかし荘厳だろう、合唱をしたら天にも敬虔に聴こゆだろう、と考えているうちに、生徒呼名の儀がやってきた。
「…本原古町!」
「はい。」
返事と共に立った。
私は目だけで辺りを見渡した。知り合いが見つけられない。どういうこと?三中がいくら頭の悪い中学だからとはいえ、少しはここに入学した三中生もいるはず。美化委員の金森先輩みたいに。
何かを思い出した。金森先輩からLINEで頼まれていることがあった。たしか、ダンモというところに仮入部しろということだった。ダンモって何だろう?私は知らない。“そうだ!部活はダンモに来てねー、毎週火水金でやってるよ!”というLINEの(それだけの)文面が、仰々しく頭をよぎった。詳しいことを聞いておけばよかった、と今更思った。
リバーブを伴った「A組、着席」という声がした。A組の私は座った。
「──木曽濃々香!」
「はい!」
私はその声を、条件反射で内耳のうずまき管へ通した。ののか!きそののかじゃんよ。アホのお前も受かってたべか。さすがは幼稚園からずっと一緒にいる同志だ。三中では卓球部の仲間だった。部内で女子たったの2人、仲良くラリーをしてはドライブを外していたことは忘れない。
生温い安堵に肩が降りたのも束の間、まさか知り合いはこいつだけじゃなかろうな、座った状態で、また辺りを見回し始めた。視界が狭い。どうにかして目が人を探している。
否、これではどうしようもないなと思った須臾、私の右目が立ってふらつく少年の姿を捉えた。
東玉川学くんだ!
中3で同じクラスだった東玉川くんだ。頭の冴える少年の東玉川くんだ。学年中の女子からモテていたのに、私はモテる理由が最後まで分からなかった、ガリガリのまなぶくんだ───
安堵の温度が上がったのか、ふと私の目が大人しくなった。他の三中の友達はとうとう見つからなかった。
4月8日 午後
1年A組の、サルビア高校に来て初めてのホームルームが終わろうとしている。相境中等から上がってきた人たちがクラスに12人ぐらいいて、その子たちはヒソヒソ話している。後はみんな緊張で息が死んでいる。教室のドア向こうにも、たくさんの先輩が息を殺してべったり貼っついているのが見える。
出待ちだ。
ホームルームが終われば部活見学が待っている。これからあらゆる先輩が、私らをあらゆる手で自分たちの部活へ釣り上げるのだろう。私すらも狙われている魚の一匹であった。ほら、そこに金森先輩がいる。体のゴツゴツした野球部の兄ちゃんらに挟まれて顔を覗かせている。
「それでは君たち!気を付け、礼!」
「さようなら!」
先生と生徒の挨拶と同時にドアが勢い良く開いた。ドッと先輩が押し寄せる。教室の人口が一気に2倍ぐらいに増えた。周りでは、顔も知らないクラスメイトが顔も知らない先輩に捕まって、ヘラヘラと疲れた笑いを掲げている。緊張感のあったホームルームの時とは打って変わって、教室内がものすごく騒々しい。
背後から猛烈に肩を叩かれた。
「こまちゃん!お久しぶり、元気?息してる?」
「金森先輩!お久しぶりです。元気にしています!高校でもよろしくお願いします!」
「はーい!ところでこまちゃん、あのねー…」
金森先輩が、痴漢みたいなキッチュな笑いをしてこっちの目を見ている。私は捕まったんだ。私は、先輩の口から“ダンモ”という言葉が出るのを確信しながら、それを待っていた。
「ダンモに来ない?」
瞬間、先輩が私の手を引いて教室を駆け出た。もっとゆっくり走ってください、と言おうとした、だが、肝心と口が酸素の補給に使われていて、虚しくぱくぱくするだけだ。
先輩が走る。私も走らされている。人気の無い階段を一気に降りて、校舎の出口を求めて走ってゆく。校舎を出る。グラウンドを横に見ながら、L字型の校舎の側をL字に曲がる。講堂横を通り過ぎる。目の前の茂みを抜ける。どこをどう曲がったか、もう覚えていない。
「ほら、ここが部室だよ」
小さいレンガ造りの建物が、突然姿を表した。ここってどこ?というぐらい、現在地が分からない。学校の敷地じゃないみたいだ。それもそのはず、茂みと木々で囲まれた中にある部室だからである。
「元々はボイラー室だったんだけど、6年前、校舎を改築する時に、いらなくなったからスタジオにしたんだってさ。サ高で一番歴史のある建物、サルビアスタジオだよ」
「サ高って略すんですか?」
「うん」
金森先輩がスタジオのスライド式の扉を開けた。錆びて重い、鋼鉄の扉だった。
4月8日 放課後
「おじゃましまーす…」
スタジオの玄関口で上履きを脱いで、床に上がった。カーペットの敷かれた床である。壁からレンガ肌が点々と見えている。広さは教室の1.5倍ぐらいだろうか。1階建てらしく見えるれど天井は高くて、まるで小さい体育館みたいだ。エアコンらしきものが天井についている。部屋の奥の方に、確か小学校でしか見たことの無い旧式の石油ストーブが見えた。
室内にはドラムセットやらギターやらが数台ある。大きなバイオリンみたいな楽器もある、何て言うんだっけ、そうだコントラバスだ。壁際のラック式の棚に、色々な大きさの黒い容れ物が乗っかっている。その両隣に、グランドピアノとアップライトピアノが鎮座している。
「あの、ダンモって、音楽をする部活なんですか?」
私は恐る恐る金森先輩に訊いてみた。
「あれ、こまちゃん聞いてなかったっけ?説明してなくてごめんね。ダンモっていうのは、モダンをひっくり返した言葉。正式にはモダンジャズ研究部というの。あたしたち、ジャズやってるんだよ」
ジャズ。
音楽に無縁の私にとって、ますます無縁の音楽だ。私が好きな音楽といえば、Jポップ、の中のジョニーズプライマリの曲ぐらいだ。楽器も、リコーダーぐらいしか吹けない。無縁の音楽を演奏するなんて、とんでもない話である。
「誰そいつ」
「お前の後輩?」
「のんもおっくーもいたんだ~!隠れてないでちゃんとお出迎えしてあげてよ。この子はあたしの後輩。中学校の美化委員で一緒だった子。もとはら…」
「ほんばらです」
「そう。ほんばら古町。こまちゃん、あそこにいる金髪がドラムとピアノの能ヶ谷で、そこの目付き怖い人がギターとベースの大蔵。どっちも悪い人じゃないよ」
グランドピアノの裏に隠れていた男の先輩が2人、姿を表した。ドラムだという先輩はなんとなくヤンキーみたいで近づきにくいし、ギターだという先輩は目がものすごく怖くて、怨霊が学ランを着てるみたいだ。
「そいで、あたしがアルトサックスね。そういや、こまちゃんは音楽経験ある?」
「ゼロです。」
「こまちゃん、楽譜は…」
「読めません。」
真顔で金森先輩の質問にすぐ応えた。男の先輩2人がただ怖いので、このスタジオを出たくなってきた。別にこのジャズをやる部活に入る気もしない。
ふと、ゴリゴリと扉の開く音がした。
「失礼しまーす!ダンモの部室で間違い無いですか?」
「ののか!!!!!!!!!!」
ののかだ。ののかが部室に入ってきた。
「ののか!?!!?!??」
「こまちなんで!?!!なんでここにいるの??」
「お前こそなしてここにいるよ???」
「うち、ドラムやるの!!!ここで!!!!ドラム習ってるし!!!!!!」
そういえばそうだった。ののかは小5からドラムを習っていたのだ。でも、ドラムをやりたいだけなら軽音部に入ればいいものを、
「ののか、軽音部には入らないの?」
「だってこの高校軽音無いもん、だからダンモ入る」
「そうそう、サ高は音楽やる部活少なくてさ、合唱とダンモしかないの。このスタジオは週3でダンモ、週2で合唱が使ってる」
能ヶ谷先輩が軽く補足をつけてきた。軽くて気前の良さそうな声だ。
「ところでこまちは何やるの?」
「それあたしも聞こうと思ってた」
「んうぐ」
「…こまちどうしたの?」
ものすごく焦った。ジャズで使う楽器すらはっきり知らないのだから、何をやったらいいか分からない。私は、金森先輩の導きだけでここへ来てしまった哀れな人間だ。何ら音楽への矜持も無い。
「だってそいつ器楽演奏の経験無いでしょ、そりゃ迷うに決まってる」
大蔵先輩が流し目で私の方を見て言った。生きててすいません、といった文字列が私の頭を満たした。
「サックスやらせれば?」
能ヶ谷先輩が軽い声で提案した。金森先輩の目がぱっと開かれて、私を見た。
「サックス!いいね。あたしが教えてあげられるしね。こまちゃん、サックスやろうよ。指の動かし方なんてリコーダーと一緒だよ、やろう?あたしも高校から始めたけど、1年で結構吹けるようになったし。やろう!」
「強引だなお前」
大蔵先輩は、床にうつ伏せに寝っ転がって話している。
私は遠く、アップライトピアノの隣に置かれている、サックス立ての上のサックスを見た。よく見てみると、ものすごくごちゃごちゃしている。これを私が吹くんだろうか。吹けるんだろうか。
「まあ、やってみろよ。1ヶ月もすればFブルースが吹けるようになる」
能ヶ谷先輩の声はいつだって軽い。能ヶ谷先輩の声を聞くと、エフ=ブルースとは何なのか、サックスとはどんな楽器なのか、無性に知りたくなってくる気がした。
「それでこまち、入部はするの?」
「ののかが入部するなら、する」
「やった~~~~!!部員2人ゲット!」
私と、ののかと、3人の先輩が、同時に笑い出した。広いスタジオ一杯に、リバーブを伴った私らの声が飽和して、響いた。
4月10日 新入生歓迎ライブ
ダンモが、放課後、講堂で小1時間ほどライブをやるという。廊下の窓に貼ってあったポスターに、そう書いてあった。私はののかと2人でさっさと講堂にやって来た。
しかし、講堂に入ると、中はがらんどうであった。ステージの上に、ただグランドピアノが1台と、コントラバスが1台置いてあった。
私らはステージの真ん前の真ん中の椅子に座った。2人で座る講堂はたいへん広い。
講堂の後ろの方で、ドアの開く音がした。女の子が2人入ってきた。女の子たちはこちらの方へやってきて、私らの右の方に座った。4人で座っても、まだまだ講堂は広い。
講堂の前方にあるドアが開いて、人がまた5人、6人と入ってきた。どうやら先輩に見えた。彼らは私らのちょうど2列ほど後ろに座った。それでもやはり講堂が狭くなることは無い。
ふと、講堂にいた人々が姿を消した。3分ほどして、彼らは知り合いを連れて戻ってきた。隣に目をやると、ののかがいない。きっと彼女も誰かを呼んでくるのだろうと思った。
人が人を呼んで、講堂に点々続々と人がやってきた。それでもって講堂には、ざっと50人ほどの人が集まっていた。でも、どうしても講堂は広かった。
3分経った。ののかが帰ってきた。
「イケメンの知り合いいたから、持ってきたよ」
ののかの手には、しっかりと東玉川くんの手首が握られていた。連れてきて大丈夫なのかと尋ねると、ののかは、これぐらい普通だよ、それにまなぶは音楽に造詣が深いタイプの人間だから、と笑ってごまかした。
ついにステージに人が現れた。つい一昨日話した、金森先輩と能ヶ谷先輩と大蔵先輩である。それでもって私は奇妙な疑問に覆われていた。ダンモの部員は3人しかいないのだろうか、3人でジャズは成立するのか、と考えているうちにもう辺りから拍手の音がしていた。先輩たちが楽器を構えておじぎをした。
能ヶ谷先輩がピアノで軽く序奏をつけると、大蔵先輩が応えるようにコントラバスで拍を返し、それに合わせて金森先輩がサックスを吹き出した。曲が始まった。
なるほどこれはジャズであるというメロディであったし、どこかで聴いたことがあるようでもあった。ドラムがいないので弦の低音がリズムを作っているが、これはこれで支障の無いものであった。
ふと、東玉川くんは小声で、
「これはモーニンという曲じゃないかな。ライブの幕開けにはよく使う曲だね。でも面白いね。ドラムレスでやるだなんて」
「どこが面白いの?」
私とののかは息を合わせてそう尋ねたが、説明が面倒だと言って流されてしまった。そのうちにモーニンという曲が終わった。
私は観察をした。
先輩らは、一つの曲を演奏している間に楽譜を一切めくっていない、ということに私は気付いた。そのことを東玉川くんに話した。
「そりゃあ、そうだろうね。モダンジャズっていうのは、楽譜に書いてある和音の流れを延々と繰り返してアドリブを取るものなんだよ。だから楽譜の体裁自体は1ページぐらいなんだ」
「繰り返す?」
「注意して聴いてみなよ」
曲の半ばに出てくる意味不明で端麗な旋律やらは、全てアドリブで吹かれていたということを、私は今知った。聴けば、なんとなく伴奏あたりが同じことを繰り返しているような気がした。あくまで気である。
「たぶんこれは、僕の記憶が正しければ、帰ってくればいいのにというミュージカル由来の曲かな」
「どこでそういう知識は湧いてくるの?」
「母親がジャズ好きなんだよね、家にもレコードが粗大ゴミみたいに転がってるし。僕のお気に入りのレコードは………」
東玉川くんの粗大ゴミの話を聞き流すうちに、ミュージカル由来の某という曲が終わった。
先輩たちは、短い曲をいくつか演奏した。その間に、東玉川くんはいろいろなことを断片的に話した。
ソロが終わったら観客はソリストに向けて拍手をするということ。
ジャズは裏拍が強いので音頭とは真反対であること。
主題はテーマ、序奏や後奏はイントロ・アウトロと呼ぶこと。
ああして合奏することはセッションと呼ぶこと。
ブルースは12小節単位の曲の総称であること。
「それでは!私たちの最後の曲です!」
金森先輩が叫んだ。すぐにピアノでイントロが入った。サックスはそれを追うようにして、テーマ?を吹いた。
それは、新歓ライブの中で、最もテンポが速く、最も音の密度が高い曲だった。
強烈でシニカルで、ものすごく早いフレーズが吹かれた。大蔵先輩は、額から汗を流しながら、太い弦を素早く指で弾いている。
そのまま先輩たちはソロに突入した。3人の先輩が次々に、駆け抜けるようにしてソロを取った。熱い旋律だった。私らは目と耳を釘付けにして聴いた。
あっという間に曲が終わってしまった。拍手をせずにはいられなかった。人々の拍手が、広い講堂をどんどん満たしていくのを感じた。
「ダンモには、2年生が3人しかいません!このままだと廃部になります!ぜひ入部してね!」
私とののかは顔を合わせ、なるほどね、と言った。東玉川くんは興奮冷めやらぬ様子で震えて言うに、
「あのベースの人は、すごい。あんなに派手にアドリブが取れるなんて、高校生じゃありえない。ダンモ入ろうかな」
とのことだったので、
「マジ?」
とののかは訊いた。
「おいでよまなぶ!あんた中学で軽音部でギターだったでしょ?ギターやってみなよ!」
「え、あの先輩ベースだったしベースやりたい」
「大蔵先輩はギターもベースもできるすごい先輩だよ」
私が斯く言うと、ののかと東玉川くんが一様に私の方を向いた。
「ギターやります。」
眼を見開いて東玉川くんが言った。
4月13日 放課後
「このリードをね、これをこうして、ネジを締めるでしょ?そう!ここの間隔は髪1本ぐらい、リードはまっすぐにしてね。で、吹くんだけど…」
「マウスピースだけでも音は出るんですか?」
「出る出る!プーってやってみ?下唇をちょっと歯の上に巻く感じで。口の力は抜いていいよ」
私がサックスのマウスピースを吹こうとしている。ののかが遠くからこっちを見ている。東玉川くんはコード表というものを見て、大蔵先輩から伴奏のやり方を教わっている。
下唇を歯の上に置いて、リードに直接触れないようにして、口全体から力を抜いて、頬は膨らまさないようにして、お腹で息を吸う。金森先輩から教わったことだ。
私が息を吹き込もうとしたその時、
部室の外から金切り声のような異音が聴こえた。
「外で、誰かが、マッピ吹いてる。しかも高い音。ソプサクかな」
先輩たちが、互いに神妙な顔を見合わせている。私らも同じように顔を見合わせた。
「吹部の知り合いかもしれない。俺、様子見てくるよ」
ふいに能ヶ谷先輩が立ち上がり、部室を出て行った。
ほどなくして、部室の外で歓声が興った。女の子の黄色い声だ。
クラリネットと曲がっていないサックスみたいな楽器とをそれぞれ持った女の子が2人、能ヶ谷先輩と一緒に、部室に転がり込んできた。顔貌のよく似た女の子だった。
クラリネットを持った方が、
「はじめまして!妹の蓮野つくしです!ソプラノサックスとクラリネットを吹きます!」と言うと、
続いてもう一方が、
「はじめまして!姉の蓮野やくしです!ソプラノサックスとクラリネットを吹きます!」と同じような情報を言った。
「「入部します!よろしくおねがいします!」」
部室の人は彼女らを取り囲むようにして集まった。
「いやぁ~マジでビビったよ。こいつら桑畑中の吹部の双子の後輩でさ、部で一番上手い2人だったわけ!これでダンモは安泰でしょお」
「いやいや、のん先輩もカッコいいドラマーです!!」
「てへへぇ…」
「そのクラとソプサク、双子共用?」
大蔵先輩が頬杖をついて、三白眼で双子の方を見ながら訊くので、怯えたつくしがやくしの陰に隠れるようにして逃げた。今度はやくしがつくしの後ろに移動した。2人がこれを繰り返すので、どちらがつくしでどちらがやくしか分からなくなってしまった。
「…はい、双子共用、です……マッピは別ですけど」
震えている双子の片方が答えた。
「おいおいそんな怖がらせんなよ~、無害な女の子だぜ?」
と能ヶ谷先輩が大蔵先輩の肩を掴みながら言った。大蔵先輩は、肩を持っている能ヶ谷先輩の手に自分の手を添えて、殺人鬼ばりの阿漕な笑いを湛えると、
「蓮野は無害、お前は有害。てへへぇじゃねえんだよ、オカマか?」
と小声で囁いた。
「ヒエーこわいこわい」
金森先輩が棒読みで茶々を入れたので、緊張が解けてみんなで一斉に笑った。
「ヨッ!五代目!大蔵権之助!」
部室の戸の外の方から、歌舞伎大向うのような掛け声がする。
「五代目でもないし権之助でもないんだけど」
大蔵先輩は、ぶつぶつ文句を呟きながら扉に向かい、ガラッと大きな音を立てて扉を開けた。
仁王立ちの女の子がいた。
「おっくーここで何してんの?デジモン?ファンモン?」
「俺はポケモンしかしねえよ。帰れ」
とまあ芸問答のような洒落た挨拶を交わし、“帰れ”の命令をかわし、私らの方を見て、
「わし、おおやみなみです。おおたにじゃなくておおやです。みなみは南に美しいと書くって噂です。相境中等から進学してきた1年生です。おっくーとは中等から行きずりのどうしようもない関係です。よろしく」
と適当な自己紹介をした。
大谷南美は部室の玄関できちんと靴を揃え、部室につかつかと入ってきた。南美のショートボブの鋭い切っ先が揺れる。書道の半紙5枚ぐらいなら簡単に切れそうだった。
「皆さん、練習、しないんですか?」
南美が軽く伺った。
「いや、さっきまでは練習してたんだけど、お前みたいな新入りの部員が来たから自己紹介してた」
「“お前みたいな新入り”ってすごいな。よくわしが入部するって分かったね」
「入部しようとしなかったら普通はここに来ねえだろ」
「え、ほら、おっくーに会いに来るためだけに来たっていう可能性も…あるべ?」
「ねえよ」
「ないか。さすがにキモいな」
「それ俺が言うべき事なんじゃないかな…」
「わかり哲也!」
大蔵先輩と南美の会話は、さながらマシンガンの撃ち合いのようで、私らは銃弾の雨に打たれているようで、興味深そうに聞くより他は無かった。東玉川くんは、私に耳打ちで「すごい」「映画みたいだ」と言ってきた。
「結局、お前入部するの?」
「するよ」
「楽器はどうするの?」
「今ダンモに何が足りないかで決める」
「ピアノとベースが今いないね」
「小学生の頃で辞めちゃったけどピアノやっていい?」
「お前ができるなら。能ヶ谷困らせるなよ」
「ギョイーン」
大蔵先輩と南美の会話が解散すると、自然にその場から拍手が起きた。大蔵先輩は不思議そうな顔をしていた。南美は腕を組んで笑っていた。
「はーい解散!各位、練習!」
金森先輩の声で私らは解散し、練習に戻った。
私のそばに、ソプラノサックスを抱えた双子の片方が近づいてきた。
「双子の見分け方なんだけど、おでこにほくろがあるのがやくし、無いのがつくしだからね。よろしくね。」
おでこを見た。ほくろがあった。私はやくしと握手をした。やくしと一緒にマウスピースを吹いた。
4月18日 放課後
私らの部室、サルビアスタジオからは必ず音がする。中に人がいる時なら、必ず。管楽器の音、ドラムの音、地団駄を踏む足の音。でも、そういう音はたいてい、厚いレンガの壁に遮られて聴こえなくなってしまう。
だから、部室に人がいるか知りたい時は、レンガじゃないもの(つまりは扉)に耳を押し付けてみる。
何の物音もしない。
先輩も、同輩も、みーんないないと思ったので、私は覚えたばっかりの校歌を歌いながら、扉を開けて入った。
歌を歌いながら靴を脱ぎ捨てて、スタジオにあがると、予想に反してひとりの知らない男の子がいた。肌色は生白くて、割と背の高い男の子だった。
スタンドに立て掛けられたコントラバス────おととい大蔵先輩から教わった言葉で言うなら、ウッドベース────その方をじっと見ている。
私は、邪魔しちゃあいけないと思って、彼の様子を見ながら、黙って部室の隅の棚からサックスを持ってきて、静かに組み立てた。
男の子が、ベースの4本の弦を、低い方から順番に弾いていった。
私はマウスピースに湿らせたリードを入れて、そしてネック管にはめて、それを本体にはめて、一通り吹いた。図太くてプーっと怒鳴る音が、弦が鳴るのを掻き削ってしまった。なんだか申し訳無いと思った。それで私は口からマウスピースを放してしまった。
静かになって30秒ぐらいした。
男の子がこっちを向いた。眉毛が太かった。
「あの、今日ってジャズ研やってるんですか?入部届け出したんで、来てみたんですけど」
男の子が喋った。早口だった。
「たぶん……2年生の先輩が今日、ちょっとした実力テストみたいなものをやってて、だから、人がいないだけだと思います」
先輩が来ない一通りのことを喋りながら、今度は同輩が来ない理由を考えていた。1年生の秘密の学年集会があるのかもしれない。重大な説明会をすっぽかしているのかもしれない。私は何かを忘れているかもしれない。それだから、私は死にかけの鯖みたいに口をぱくぱくしてしまった。
「あれ、アンタ1年生?」
男の子がこっちを見て話してきた。睫毛が長くて丸い目を、ぱちぱちさせて私を見ていた。私は口をぱくぱくするのを止めてうなずいた。
「俺も1年」
このとき、(どうして同じであることを確かめる必要があったのか知らないが、どうしても安心してしまって、次の瞬間に肺が)「同じだね」と叫んでしまっていた。「同じだね」と男の子も言った。
私はマウスピースにふたをした。
男の子は息継ぎをして、続けて言うには、
「あのね───俺、中学のとき軽音でベースやってたのよ」
大して恰好良くもなく、都会っぽくもない感じの男の子が、軽音でベースを弾いていたという事実。ダサい話なので、
「へぇ、そうなんだ。」
と、そっけない相槌を返してしまった。
「ウッドをこんなに近くで見るのは初めてだから、まあ、わくわくしてる。後々この楽器を弾かされるんだろうけどさ、どぉーなんだろ、ゼッタイ指痛いって」
彼は早口で話している間、ずっとニッコリの顔で笑っていた。一種の、完成された、幸せそうな笑顔である。何を考えているのか、よく分からない。
彼の右手首、そして右手が、甚だ変な形相で胸元に留まっている。何かの病に侵されているみたいに。
私は反射で彼を気持ち悪いと思ってしまって、それでまた彼に申し訳無くなってしまった。
ふと、部室の扉が開いて、南美が入ってきた。
「ハナ?」
南美は部室の玄関で、私たちのいる空間に大きく問うた。
「うん。その通り」
男の子が南美の方を見て、笑って返した。
「…ハナっていうんですか、名前」
「うん。俺、名前はハナスケ。…ダサいでしょ」
「いえ、そんな…」
私は口ではそんなことを言いながら、その名前、絶対にダサい、と確信してしまった。私が申し訳無くなるのを制止するように、南美が、
「わしハナと同じクラスなんだけどさ。漢字は明らかに“ひでほ”としか読めないっぽいのに、ハナスケって読むんだよ。多分日本中探しても、こいつと同じ名前の人はいない」
南美が私に、1年E組の名簿表を差し出した。というより、投げつけた。名簿表をたどると、出席番号9番のところに、
図師 英甫
と印されている。
エーっと叫んで、これはわからないと思った。な、わからないだろ、と南美が呼んでいる。
「私、図師ハナスケくんのこと…なんて呼べばいいかな」
「いいよ、図師で」
図師は即答した。彼はきっと、変かもしれないけど、私よりずっとサッパリした人物なのだ。
南美がこちらへ走ってきて、私たちのもとでへたり込んだ。
「ハナはいい奴だよ。こまちと同じくらい」
「あれ、この子が、話題の、本原こまち?」
「私、話題になってたの?!」
「いんや、わしが勝手に話題にしただけ」
「ちょっと、驚かせないでよー!」
図師が甲高い裏声でそう叫んだ。
「それ私のセリフだよね?」
「「すごい!よく分かったね、えらいね!」」
図師と南美がそろってそう言った。
南美もきっと、私よりずっと変だけど、私よりずっとシンプルな生き方をしているんじゃないか、そう思った。
「図師くんと、南美って、なんだか似てるね」
「え、そう?」
図師と南美は、顔を見合わせていた。
4月23日 放課後
今日のサルビアスタジオは、部員がみんな来ているし、わいわいして練習している。ののかは「タム回し」というものが上手くいかないらしいので、延々とそのおさらいをしている。東玉川くんは一人で、ノートに色々書きながら、アドリブの取り方を考えている。
私もサックスを練習している。ロングトーンがうまくいくようになって、綺麗な音が出てきた。音階は、ドレミファソラシドに加えて、半音をようやく早く吹き繋げるようになってきた。金森先輩は私のことを、器用だと言っている。
私は最近、毎朝(あるいはダンモの無い放課後)校舎の屋上で、サックスを練習している。だから、できるのはむしろ当然なのである。このことを他人には黙っていた。なんだか恰好悪いから。
「セッションするか?」
楽器の音に負けないくらいに、能ヶ谷先輩が大きな声で叫んだ。
「ウォームアップに、ストラッティンでもやろう」
「ストラッティン?」
金森先輩が私の方へサッとスコア本を広げ、「昔、日本でだけ超流行ったFブルースなんだってさ、あたしはよく分かんないけど」とぼやきながら、
Cool Struttin'
とタイトルに書かれたページを見せた。初見の曲だった。
「フロントは、じゃあクラでつくしとアルトで本原。ギターはまなぶよろしく。ベースは大蔵、お前で頼む。ピアノ、大谷お願ーい。ドラムにののかちゃん!4バースよろしくね。俺はサボって見てるよ」
「のん先輩から指名受けちゃった!がんばる!」
ののかは張り切ってドラム椅子を座り直した。
指名を受けた部員が、各自でテーマのメロディを軽く練習し出した。
私も、初めて能ヶ谷先輩から指名を受けたかもしれない。そしておそらく、今回のセッションで私は入部初のアドリブを取る。緊張して言葉が出ない。金森先輩から教えてもらった、ブルーノートスケールという旋法を、今一度指で押さえ直してみる。
「じゃあみんな、位置について~」
能ヶ谷先輩が軽くセッションの場を仕切る。
「用意はいい?じゃあののかちゃん、テンポはこれくらいだからね。カウントで始めて」
金森先輩の指示に従って、ののかが、スティックを打ち鳴らす。
「ワーン、ツーッ、ワン、ツー、」
スリーを言い切らないうちに、私らは管に息を吹き込んだ。
テーマのラからドへ上がって伸びるのがすごく心地良い。
12小節、繰り返してもう12小節、過ぎると、つくしがアドリブに入った。
さすが、中学から吹部にいる人間は、しっかりしている。2年生の金森先輩と比較すれば劣るかもしれないけれど、指の動きも音量も、自信がある。強いメロディが作られている。
呆然として見ていると、たちまちアイコンタクトが飛んできた。私はつくしからの合図を確かに受け取った。つくしへの拍手が起きていた。
出だしを若干突っかえた気がしたが、体勢を立て直す。ピアノのバッキングの音が聴こえるので、それに応答するようにスケールの一部を吹き流してみる。半拍だけ間を置いて、また吹く。高いレから下へ、やや勢いをつけて音を流し、止めて、中音域を漁る。
レミラという音型を違うリズムパターンで5回ぐらい繰り返すと、大蔵先輩が目だけでこっちを見て、でかしたという風に笑った。
そうしていると、もうコーラスを3周ほどしてしまったので、東玉川くんの方に目をやった。東玉川くんもまたこちらを見たので、私はソロを明け渡した。部員らに拍手をされた。
「こまち!すごいじゃん!」
私が頭を真っ白にして突っ立っているところに、つくしがハイタッチをしてきた。
「本当にかっこいいべ!どうやった?」
「金森先輩に、言われた通りにやってみた、だけ…」
どんなアドリブを吹いたか、もう既に記憶が無い。それでも私はつくしと共に、一入分の喜びを噛み締めていた。
しばらくして、セッションを見ている全員が、急に真剣な顔になった。みんなどこを見ているんだろうと視線の先を探ると、アドリブを取る南美がいる。
南美の作るフレーズを聴いて、私もつくしもギョッとしていた。さっきまで頬杖をついて寝転がっていた能ヶ谷先輩も、飛び起きて南美を見ている。
南美は、私ら普通の1年生とは、全然違う。
指に迷いが一切無い。甘えも無い。雑な思い付きではない、仕込まれたようなメロディをひっきりなしに作る。スケール外の音もたまに踏んでいくけれど、決して違和感を作ることが無い。
南美のソロが終わった。大きな拍手が起きた。
つくしが耳打ちで、
「みなみヤバいね。きっと次期部長になる」
と言うので、私は何回も何回もうなずいた。
能ヶ谷先輩はまだポカンとして、南美の方を見ていた。
ベースでアドリブをしていた大蔵先輩がつくしに目をやったので、つくしがハンドサインを挙げた。4バースを示す、指4本である。
私らは4小節ずつ、ドラムと交互に、アドリブを回していった。ののかは極めて楽しそうに上のタムを叩いた。
テーマに戻ってきた。私は主旋律を吹く。つくしは茶々を入れてくれた。繰り返して24小節。初めてアドリブを取ったセッションがようやく終わった。
人々が口々に「お疲れ様」とか「良かった」とかの言葉を発した。大蔵先輩と能ヶ谷先輩が南美を取り囲んで何かぶつくさ言っている間に、私とつくしは金森先輩に頭を撫でてもらっていた。やくしがつくしの肩を組んで笑った。
「よしよし。良い感じだね。みなみちゃんがすごすぎて二人とも尻込みしてるかもしれないけど、あれを追い越す勢いで、どんどん頑張っていこう!」
「南美も、初セッションなんですか?」
「らしい、けど、本当にそうなのかなあ…あたしは信じない」
金森先輩は、首を傾げていた。
ウォームアップのセッションが終わったばかりながら、ダンモはすでに奇妙な喜びと喧騒に満ちていた。
部室の隅のアップライトピアノの陰から、図師の首が覗いて、東玉川くんを呼び止めた。東玉川くんは図師の方へ近寄って、ひそひそと会話した。能ヶ谷先輩が「俺もピアノ真面目にやるか…」と言うのが聞こえる。南美はグランドピアノの鍵盤に伏して、よく分からない独り言を言ったり、携帯を触ったりした。
私は南美の肩を叩いた。
「なに」
「どうやったら、アドリブって上手に取れるようになると思う?」
「わしは知らんよそんなこと。おっくーから言われた通りにしてるだけ」
南美はピアノの蓋を閉めて、そこに伏して、仮眠を取ってしまった。
4月27日 放課後
「「おいしいもん食べよう?郷田で!」」
部活が無いし、ののかはドラム教室なので、私はサ高の最寄り駅である郷田駅にて蓮野姉妹と遊ぶことになった。双子に両手を引かれながら進むのも中々骨の折れる移動方法である。
「もしかしてこまちは郷田初心者?郷田駅前で遊んだこと、無いの?」
「うん。だって、家に帰るバス路線のバス停が、学校の真裏にあるじゃん?どっちかっていうと、郷田から反対方向に進むよね」
「え、サルビア高校前ってバス停!あの、塀挟んでスタジオの隣にある?」
「そうだよ。郷田の魔境、谷銅団地行き。ののかも同じ」
「魔境、わかるー!だってあそこ鉄道駅無くない?」
「無いけど、その代わり、横浜急行バスのどでかいツインライナーが郷田まで送ってくれるんだー」
「あの?駅前ターミナルにいるでっかい青いバス?」
「「いいな~」」
私たちは、一緒に帰宅をさぼって遊べるのだから、きっと友達になりつつあるのだと思う。それはきっとののかも同じで、例えば私が習字教室に行っている毎週月曜日の放課後は、ののかは双子たちと郷田へ行っているのかもしれない。
このまま仲良くなれば、土日にダンモの女の子たちと、郷田だけじゃなくてもっと色々なところにも行けるかもしれない。
ぬるま湯のような期待に包まれていると、やくしが、
「こんどデュドニーシー行こう!ダンモの女の子で」
と言う。
「こまちと、ののかと、ふたごの4人!」
「あれ、一人足りなくない?」
すると、つくしが性格の悪そうな目つきをして、
「大谷南美は女の子じゃないから。」
と、吐くように言った。
「いじめの根源を感じるって、それ~!」
と、やくしが笑い半分に注意した。
「悪意を持って言ってるわけじゃないんよ。南美は、本当の意味で女の子じゃない。デュドニーシーに行っても、キャラグリなんかに見向きもしないはず。むしろ、火山エリアのふもとに生えている植物とか、生態系を見てそう」
つくしは真顔で持論を述べた。南美がどんな感じの人間か、確実にシミュレーションができている。つくしは人間観察が上手いのかもしれない。
つくしの話で若干会話の空気が濁ってしまったので、私は、
「あの子さ、一人称がわしだよね」
と話題を展開させた。
「あーそれ!わしって言う!本人は………自分のことを私とかうちとか呼んで、女の子みたいに表すのが、生理的に無理、なんだってさ。スカートも全然折らないから膝下丈だし、…………聴く曲だって、ふたごのパパが聴いてる音楽と趣味が同じ。変だよね」
やくしが追伸のように付け加えた後の文章が、私に一つの疑問を呈した。
「つくしとやくしが使ってる“ふたご”って言葉は、人称代名詞か何かなの?」
「あたり!やくしが発明した1.5人称だよ。すごくない?」
「すごい。“わし”に勝るとも劣らない希少性だよ」
「「アハハ!!」」
双子が揃って笑う。一卵性の、そっくりな笑いだ。
双子につられて笑いながら歩くと、小さな商店街の入り口にたどり着いていた。商店街の路地は細くて、天井も割と低く、中は薄暗い。向こうの出口が光を放って見える。
「この中に、クレープ屋と焼き鳥屋があるよ。お店がちょうど向かい合わせにあるの」
私は手を引かれて歩いた。商店街は小さな店で溢れている。相当狭いハンバーガー屋、古着屋、東南アジアの雑貨屋、パソコンの修理店、怪しいお香を売る店、占い。そこに、にんじん亭という名のクレープ屋と、ドリームハウスという名の焼き鳥の店が、向かい合わせに建っていた。私らはそこで立ち止まった。
「ここの塩いちごクレープがおいしいの!」
「ここのねぎまをタレで頂くと最高だよ!」
双子が、同時に喋って、私の腕を双方に引っ張る。両方買うから焦るなと言って、私は二人の腕をほどいた。それでもって双子に言われた通り、塩いちごクレープとねぎまのタレを買った。
「右手はJK、左手はサラリーマン、って感じだねー!あ、そうだ!50円払うからクレープ2口食べていい?」
ハツとレバーの串を左手に持ったつくしがそう言って、瞬く間に私のクレープを2口かじり、私の制服のポケットに50円を突っ込んだ。
「ごちそうさま!」
いちごの部分は、半分ほど食べられてしまった。それでもおいしいクレープだった。
双子はしばらく夢中で食べていたので静かだったが、食べ終わったところでつくしがいきなり口を開いた。
「東玉川くんさ、イケメンじゃない?頭も良さそうだし。狙ってみようかな」
瞬間、やくしがつくしの方を横目に睨んで、低い声で「取らないでよ」とだけ言って、普通の笑顔に戻った。つくしはやくしと目を合わせないようにして、「はいはい分かってる分かってる、大丈夫だから」と応えて、やくしの肩をぽんぽん叩いた。
「───双子の間の、恋愛事情って、どうなの?」
「実はさ、中2の時に、つくしがやくしの彼氏取っちゃって。ふたごで大喧嘩して、協定を結んだの。ふたごが両方とも好きになった男の子とは、両方とも付き合っちゃいけないって」
「なんかそれ、悲しくない?」
「殴り合って血まみれになるより絶対安全だよ!それにさ、友達以上恋人未満の状態で、ふたごで男の子を取り囲んじゃえば、逆らわれることが無い。2対1だもん」
「東玉川くんにも、そうするつもりなのね」
「まあ、増上寺に行くぐらいのデートは、したいよね」
「ほんと、二人とも、しょうもない小悪魔だね」
そんな風に適当にコメントをすると、双子がお互いに目を見合わせて、にんまりと笑った。
「こまちは東玉川くんのこと、イケメンだとは思わないの?」
「うーん。ガリガリでちょっと弱そう。強い人がいい」
「大蔵先輩も痩せてるよね、苦手だったりする?」
「その通り。能ヶ谷先輩はその点、筋肉しっかり付いてて、素敵な先輩かなって思う。チャラいけど」
「でしょー!でも、のん先輩は渡さないからね!吹部時代からずーっと、のん先輩はふたごのものだよ!」
「「ねー!」」
双子は仲睦まじく手を繋いで笑っている。その姿だけ見てみれば、やっぱり蓮野姉妹は、私が思い浮かべる双子というものの理想像のようであった。
5月1日 朝
皐月の爽やかな休日に部活が入った。
知ってる誰かにいつか訊きたい何かがあって、何だったっけ、と思いながら噛んでいたガムを飲み込んでみる。
ダンモの人々は、先輩も同輩もおおよそ暢気な生活をしている。部活開始時刻9時というものが来てしまってもそんなに気にしないだろう。だから私は校門に着くと、すぐさま用務員さんを呼びに行く。部室の鍵を開けてもらうために。9時2分。私も遅刻している。
「あら、スタジオならさっき開けたよ?」
尋ねた用務員さんはきょとんとして応えた。
誰がそんなに時間ぴったりに来るものなんだろうと考えながら、私は部室まで歩いて来た。
扉を横に押し流すようにして開けると、玄関に人の外靴が1足ある。誰の靴かは、分からない。部室に上がって中を見回っても、1人の人は見つからない。
でも確かに、人が1人ここにいるはずである。
ふと部室を見回すと、玄関横の壁に梯子がついていて、梯子の先の天井には、出口の扉が付いていた。日頃は玄関は靴を脱ぐだけの空間であるだけに、気付かなかった梯子である。
一段、また一段、その梯子を繰ってみる。扉に手を掛けられる位置まで昇った。取っ手を下へ引くと、扉は案外簡単に開いた。私は先を昇った。
ロフトのような空間が姿を表した。天井がやや低い、けれど屋根裏部屋にしては広めだった。壁と天井には配管が、SFドラマを彷彿とさせる形相で巡る。ボイラー室時代の遺跡なのだろう。
部屋の中央にはギター入れがいっぱいに散乱して、積もるようにして重なっていた。ベースケースもある。ウッドベース入れも、3、4つはある。
積まれたギター入れが、緩やかにうごめくのを見た。この中にきっと、任意の人間がいる。
私がそのケースをどかそうとするより先に、人の頭がひょっこり出てきて姿を現した。
図師の頭である。
図師はその頭を、非幾何学的な方向へ幾度か回すと、こちらを見て言った。
「アンタも、来たんだね。LINE見た?今日午前は部活無くなったの。部員の半分が寝坊したから。俺ァね、先輩の頼みで、今からここでケース整理するの」
確かに私はダンモのLINEを見忘れていた。見ると、部活中止の連絡が出ている。
「私、手伝わないから」
「えっ」
図師の目が少し泳いだ。私はいきなり口から申し訳の無い言葉が出てしまったことに気付いて、慌てて口を押さえて、手と首を左右に振った。図師が暢気にニッコリ笑って、
「言い間違えたのね。焦らないで」
とフォローをした。
私はいつも無意識に、図師のことを避けてしまう。それでも図師は私に優しくする。それが苦しい。それも偽善者めいた親切ではなくて、もっと透明で淡白な慈悲だ。彼は人間全てに対してこんな態度なのかもしれない。
「そんなに気を遣われると、私、ハートがアレ」
首だけ見えていた図師が、袋の山から立ち上がった。
「えェー、じゃあ気ィ遣わない方向で行っちゃうよ。これ、ギターケースとベースケースに分けて、別々に積むの手伝って」
言われるままに、私は無造作なケースの山を漁って整理した。短い方がギターケース、長い方がベースケース。きっと私は今、図師にまんまと使われているのかもしれないけれど、嫌な感じはしなくて、むしろこれが「当然」じゃないかという気がしていた。私の中で、図師が奇妙な慈悲を放つ妖精という位置付けになり出した時、
今朝ずっと考えていた「知ってる誰かにいつか訊きたい何か」というものを思い出した。
それは先日、双子と郷田に行った際のことだった。は
「ひでぽんのことは、どう思ってるの?」
あの道中、確かやくしが私にそう尋ねてきたのだ。ひでぽんとは図師のことである。名前の漢字の読みが明らかにひでほだから、双子は陰でそう呼んでいるのだそうだ。図師には何となく近寄れないと答えると、
「やっぱり、こまちもそう思うんだね、薄気味悪いよね… ───あのさ、即天模試、あったじゃん?高校受験模試。ひでぽん、模試結果と一緒に配られるランキング表にいっつも名前が載ってたの。いっつも!5位から上のところに!」
「開啓高とかにでも行きゃよかったのにさ、どうしてわざわざ都立のサ高に来たんだろう?」
みたいなことを双子が言っていたのである。
「──ねえ、図師くんはどうして、サ高に来たの?頭良いんでしょ。私国立とかでもっと良い高校、あるのに」
私はそう作業をしながら尋ねると、図師は不意に感情の無い顔をして、
「俺ね、」
と言って、息を吸った。
「貧乏だから私立行けない。………俺は………埼玉県境あたりの都民だった………だけど…まあ…色々あって………」
訊いちゃあいけないことを訊いてしまったと思って、私はとてつもなく焦った。図師は天井のパイプを見て、ぽつぽつと言葉を繋いでいる。私はぎゅっと目を閉じた。
「埼玉あたりから一番行きにくそうな都立高校をね…」
目を開けると、図師は笑顔に戻っていた。私は何とか喋ろうとして、口を開けたり閉じたりした。空気だけを虚しく吸っているうちに、ケースが大方整理されていった。
ひと仕事した私と図師は、それぞれロフトの壁に寄りかかった。
「────────ごめん」
「心配しないで。俺、そこまで人間に期待もしてないし、絶望もしてないもの」
図師が私の方を見て、ニッコリ笑っている。私にはその笑顔が、いつもと違う、何かを投げ出した時の表情にも見えた。
扉が開く音がした。人の声もした。
「先輩、靴が2足あるんですけど、人は…」
「たぶん上のロフトだ。おーい図師ちゃーん!ありがてえ!降りてきなよ、セッションしよう!」
東玉川くんと能ヶ谷先輩の声だ。
図師は床の入口に首だけ突っ込んで応答した。
「部活、無くなったんじゃなかったんですかー?」
「俺が来た時間が部活の時間だー!セッションしよーぜ!あと、もう1人の子は誰だ?」
「本原です!」
「サックスかー!よーし、ドラムレス1管だ!セッションするよ!降りてきなー!」
能ヶ谷先輩が私らを呼んでいる。図師は首を戻して、振り向いて、
「アンタさ、そんな、誰にも愛されてないみたいな顔しなくてもいいじゃないの。愛されてるんだから。ほら、降りよ」
と言う。
誰にも愛されてないみたいな顔って、どういう顔なんだ?
私はそれを考えながら、梯子から滑り落ちるように降りていった。10時47分。お腹がゆるやかに減るのを感じた。
5月6日 放課後
セーラー服に、青いリボン。白い鍵盤、金の真鍮、茶色のレンガ、緑のリード箱、隅で倒れたエレキギターの灼ける赤。
そういうものを見て、10数えて、スタジオの灰色の天井を眺める。すると、さっき見た色の補色がくっきり浮かぶ。この遊びを延々と繰り返している。
無意味な遊びを繰り返していたら、入学して初めての中間テストがものすごい速度で近づいてくるのは分かっている。けれど、(これはいつも思っていることなのだが、)ここまで余裕じみた時間を過ごすことができるのは、今しかないと反抗してしまう。理由の無い反抗である。
自覚の効く範囲でゆっくりしなければ。
エンデの著したとある物語が、たぶんそういう話題を述べていた気がする。今ゆっくりしなければ、きっと永遠に私らは、せわしなく、荒く敷かれたコンクリートの地べたを這いずり回るより他は無いのだ。我々は、遊ぶ時も勉強する時も、いつでも余裕を持って為さなければならないはずなのである。ほら、もう10分経っている。
横を見ると、東玉川くんが、スケールを仰山書いた紙とにらめっこしている。黄色いイヤホンが彼の耳にずっと刺さっている。あるいは、音を聴き逃さないようにか、そのイヤホンをずっと彼の両手が押さえている。
ふと東玉川くんがイヤホンを外して、こっちを向いた。
「そういえば本原はさ、このダンモで、ライバルだと思える相手、見つけた?」
東玉川くんが問うてきた。
「わからない。管の女の子でつくしとやくしはいるけど、まだすごく遠い存在に感じるの。私、まだまだサックスで綺麗な音出ないし、あの子たちみたいに初見の曲でアドリブも取れない」
「そうかあ」
東玉川くんが私を見ている。私というより、私が手にしているサックスかもしれない。
「僕…ね、本原が一番、競争できる相手になるかな、って思ってる」
「楽器違うじゃん、なんで?」
「共感しやすいんだよ。いつも迷いながら弾いて、弾きながら迷ってる感じがさ。木曽はどことなく頭が足りない。蓮野たちは、他人の演奏を追うことに鈍い。図師と大谷は何考えてるか分からない。結局、本原が一番分かりやすいし、割と応援したくなるし、競争したくなるなって」
「うるさい」
私は持っていたサックスをサックス立てに置いた。
分かりやすい人間と言われると、意味が分からないと言われるのと同じくらい──いや、それ以上腹が立つのは何故なんだろう。自分の存在が他人によって浪費されていくような気、あくまで気がするのである。
やがて、自分が持っているものを、自分ではない誰かが浪費している時が一番不快であるという結論が見えてきた。それはきっと「もの」を「時間」に置き換えても同値の結論が見えて、自分の時間を自分が浪費していくことが最も安心する行為になりうるのかもしれない。そして、理由の無い反抗の理由の気配を感じて、おもむろに私の目が閉じていった。
目を閉じていると東玉川くんの声がしたので、仕方無く目を開いた。
「それにしてもずいぶん余裕そうだね。それで1ヶ月後のセッション会に間に合うと思ってるの?」
「セッション会?」
「知らないの?咸城女学館ジャズ研との交流会だよ」
ミナキの女学館だって?
根っからの田舎の公立育ちでお嬢様学校群とは無縁の私でさえ、学館の名や梨の形をした校章を知っている。ミナキは私の憧れの学校だ。それは、小袖と紅の袴の制服を持つ神道系の女子校である。気高く、それでいて慎ましい生徒たちの姿は、まさに大和撫子そのものだという。
私は口を押さえたが、ヒョッという変な声が出るのを抑えることはできなかった。
「えっ、それは、知らない情報だった」
「だろうね。実際すごくないか?モダンジャズをやる高校って、東京だとここと咸城しか無いんだってさ。」
「世間の高校はビッグバンドだしね、珍しい部活だよ」
金森先輩が腕を組みながら会話に現れ、そう言った。
「あたしね、去年の6月ぐらいに初めて咸城にセッション行った時、すっごい上手いアルトの子に会ったの。名前はたまちゃん…えーっと、思い出した、たまみだ」
たまみ、と言うと、金森先輩は自分の頬を突っついた。
「三沢たまみだ。しかも同い年で、サックスも高等部から始めたっていうから…あたし初対面でおったまげたの!そんで、絶対に追いつくって決めたから、ずっと練習してさ。今年の1月にもセッション会あったんだけど、そこでどうにかして追いついたかなーって」
三沢先輩のことを話す金森先輩はいつもより興奮していた。
「三沢先輩って、どれだけ上手いんですか?」
怪訝な顔をした東玉川くんが訊く。
「たまちゃんはすごいの!フレーズ回しがもう完璧。速いテンポでもミス無く吹けるしさ、リズム隊を煽るのも上手いし、チェイスもチェイスできてるし、最高だよ!」
金森先輩が自信ありげに言い、ふとその場を立って、機嫌良さげにどこかへ去っていった。
「面白そうだよね」
ギターの指板を抑えて、東玉川くんがこっちを向いた。
「ライバル。何もしなくても女学生がやってきて、勝手にライバルができてしまう。退屈じゃないかな?」
「何も考えなくても、何も焦らなくても」
「うん。それはそれでエキサイトなのかもしれないけど。僕らは今巨大な歩く歩道に乗っている」
「動く歩道でしょそれ」
「そうそれ、動く歩道だ。動く歩道に乗った状態で歩いていけば、相当の速さで動ける。でも面倒だから立ち止まってしまう」
「わかるなあ…」
「えーっ咸城にもダンモがあるの!マジ!?」
叫び声を上げながら、ののかが部室に駆け込んできた。周りを見ることも振り向くこともせず、玄関に靴を脱ぎ捨て、私らのもとへスライディングして来た。
「うち今知ったよ!!知ってるんなら教えてくれてもいいじゃん、もーう!!!」
モモ。
ふいにエンデの物語の名前を思い出した時、同時に「誰も聴きもしない音楽」という作中の言葉も思い出した。何かのインスピレーションが鳴った気がして頭を叩いたが、それ以上は何も出てこなかった。
5月10日 放課後
大蔵先輩が部室の窓を丁寧に拭いている。
「今日は中間前最後の部活日だかんね!うちは絶対にセッションし尽くしてやるんだ」
ののかは興奮で顔を真っ赤にして言う。
「だって、明日からテスト1週間前だから部活できないべ!それに、中間期間中も最終日までもちろん部活できないから、実質1週間半!部活、できない!」
私も、全くもって1週間半の部活禁止は認められないと思っている。高校生の領分においては、勉強と部活の両立こそが最も魅力的なのだし、部活止めはテスト3日前ぐらいからで良いと思っていた。
しかしながら、それを順序立てて叫ぶことでののかに賛同するスタミナが足りなかった。今日6限の山崎先生の現代文の内容がべらぼうに濃くて、それで身が疲れてしまったのだ。
「曲、何やるの?」
部室のカーペットにへたり込んだ図師が、ののかの方を向いて言う。南美がブリックパックの野菜ジュースを紙の髄まで吸う音をさせながらグランドピアノに頬杖をついている。東玉川くんはその様子を怪訝な顔で眺めている。
扉の外で仲良く管を吹いていたつくしとやくしが、部室に入ってきた。
「のん先輩も金森先輩も来てないの?」
「来てないの?」
双子が場に質問を投げると、
「どっちも来てねえよ。あいつらどうせ一週間前から勉強しないと追いつかねえんだろ、馬鹿だから。LINEで俺にスタジオの清掃頼んできたあたり、2人とも最低だよね。今後の人生大丈夫なのかな」
と大蔵先輩が笑って答えた。
「本当は最低だとは思ってないから、そういうこと言えるんだよね」
とブリックパックを丁寧にたたんだ南美が笑って返した。
「曲、何やるの?」
部室のカーペットにへたり込んでいる図師が、ののかの方を向いて再度言う。大蔵先輩が窓をあらかた拭き終わり、自分のギターを抱えて、床にころりと転がった。
「みんな、やりたい曲、ある?」
とののかが訊いたところ、
「帰っていけたらいいのに。You'd be so nice to come home to。今のお前らにはちょうどいい」
と大蔵先輩がつぶやいた。
「え、その邦題、帰ってくれたらうれしいわ、じゃないんですか?」
と東玉川くんが質問した。
「良い質問だね。“帰ってくれたらうれしいわ”というのは、大橋巨泉が若いころにしでかした誤訳なんだ。あなたの元へ帰っていけたらどれだけ素敵なことだろう、というのが正しい訳なんだよ。話し先じゃなくて話し手が帰るんだよね」
大蔵先輩が流暢な日本語で返すので、私らは口を揃えてへえと言った。
「曲、それやるの?」
部室のカーペットで大の字になって寝ている図師が、ののかの方を向いて言った。南美が図師を見てうなずいた。
「トーラーの188ページにあるよ、開いて」
南美が言う。スコア本の188ページを開くと、You'd be so nice to come home toと書いてある。
「軽く練習したらセッションするね」
と大蔵先輩が言った。譜面台や楽器を抱えた。蓮野姉妹はスタジオの外へ出て、図師は屋根裏へ登り、南美はグランドピアノのふたを開けた。
20分ぐらいが経った。
後ろから、「セッションするぞ」という大蔵先輩の声がした。
私がスタジオの扉を開けて、「セッションするよ」と言うと、つくしとやくしが中へ入ってきた。
ちょうどその時校内放送がして、
「1A 本原さん 国語研究室まで」
という情報が流れた。
何者かに呼び出されたのだ。すぐ終わる用事ではないと薄々思った。今からのセッションは半ば諦めたが、ラストテーマぐらいは吹きたいと頭の末端で考えていた。サックスをどこかに置く暇も無く、抱えたままスタジオを出た。
スタジオから校舎本館までが遠い。走っていると、「本原さん、国語研究室まで」という2回目の放送がした。南館を通って本館へ入って階段を4階まで駆け上がり、ようやくのことで研究室まで辿り着くと、扉の前に今日の現代文の先生が立っていた。頭が真っ白な髪で覆われた、中年で痩せて中背の先生である。
「時間と空間には殊に相剋が発生するものです。 安心をしてください、これはただの新入生への面談であります。 わたくし山崎忠雄は、現代文の教師かつダンモの顧問です。 どうぞ室内へ」
言われるがまま中へ入ると、国語教師が幾人かいて、それぞれ仕事をしていた。奥の方にソファがあり、そこへ向かい合って座った。
「あなただけ面談の連絡がつけられず、仕方無いので呼び出しました。 申し訳の無いことです。 あなたはアルトサックスを持っていますね。 楽器はアルトサックスですか?」
山崎先生は相当ゆっくり喋っている。ラストテーマへの希望は次第に失われていた。
「そしてあなたは今練習をしていたところですか?」
「そうです」
「好きな演奏者や曲、アルバムはありますか?」
「ペッパーは聴いています」
「アート・ペッパー。 飄々とした白人のサックスの方ですね、良い演奏者として有名ですね。 ところで、入部の動機は何ですか?」
「金森先輩に誘われたので」
山崎先生はゆっくり腕を組んで微笑んだ。
「金森さんは優秀な人です。 彼女から盗めるものはたくさんあるはずです、よく学んでください。 それでは面談を終わります。」
山崎先生はゆっくり喋るが、面談は案外早く終わった。
私は全速力でスタジオに駆け戻った。
部室前に着くと、中からエンディングか何かでシンバルが鳴っている音がした。中間前最後のセッションは死んだ。悲しくなった。シンバルが鳴り止んでから扉を開けると、そこにいた部員が一斉に振り向いた。
「山崎との面談?」
大蔵先輩が尋ねる。私がはいと応える。
「山崎はまあ、おっとりしてるけどジャズに詳しいから頼っときなよ。それにしても運とタイミングが悪いね、もう1曲やるか?お前ワンホーンで」
「えっ、いいんですか!」
「いいよ。Fのブルースを回す。テーマはナウズでもストレートでも何でも吹け」
私は謂れも無く、サックスを抱えてジャンプした。
5月21日 放課後
金森先輩が部室のど真ん中にうつ伏せで寝ている。
「音みたいにさ、一度手を離れてしまった答案も、空中に行って、もう二度と戻ってこないといいんだけどね…」
「死ね。」
「は?死ぬのはおっくーだから」
大蔵先輩もベースの横で猫みたいにうずくまっている。私とののかは金森先輩の近くで正座している。
ノート提出を済ませたであろう図師が勢いをつけて部室に入ってきた。ドアを開けっぱなしにしている。夏に近い匂いがする風が、スタジオに入ってくる。
いきなり金森先輩が起き上がって、ののかの肩をつかんで、
「この時期、最悪じゃない?進級して最初のテストが返却されるし、一週間後には運動会も控えてるんだよ」
と不服を申し立てた。
「そもそもダンモの人間は運動ができない」
と金森先輩が言うと、
「太鼓の馬鹿以外は」
と大蔵先輩が付け加えた。
ちょうどその時、開いたままのドアに能ヶ谷先輩が入ってきた。
「テスト終わウィーーーーーーーーー!!!!!!!」
スタジオが能ヶ谷先輩の叫び声で満たされた。
「うるせえ太鼓の馬鹿、今ちょうどお前が馬鹿って話してたんだ」
足を伸ばして座った図師が、指を鼠蹊部の前で組んで、首を傾けて気兼ね無く笑っている。
「運動会!!俺色対抗リレーのセミアンカー!!!今日決まったの、すごくない?」
ドンキーコングみたいに唇を突き出して能ヶ谷先輩が言及するので、ののかは堪えることができず笑った。隣で金森先輩も笑っている。
「来たのね」
ぽつりと図師が言う。私は図師の方を見た。南美が隣にいた。いつの間にここへ来たのか知らないけれど、南美はあたかも“ずっと前からここにいた”ような表情で座っていた。
「おい、セッションはしないのか?ここにちょうどピアノも、ベースも、ドラムもいてオーボエもいるだろうに」
と南美が言った。
「オーボエはいないよ。南美、1年生だけでセッションしてみたいの?」
「うん、先輩みんなテストで死んでるっぽいし。世界史?」
「会話バリバリ聞こえてるぞ、それと俺は世界史はそんなに苦手じゃないから」
うずくまったままの大蔵先輩が応えた。
セッションしよう?サックス1管であんまし派手なことはできないから、Beautiful Loveでもゆったりやろう。ドラムもブラシにしてさ。わしらさ、スローテンポでセッションする機会がそこまで無いし。
南美の声が夏の近い風に融けて、歌、あるいは現代ジャズのテーマのように聴こえる。
よっこらせ、とののかが起き上がりながら言って、ドラムの方へ行って、ドラム椅子に腰を下ろした。
「のん先輩、部所有のブラシってこれですかー?」
ののかが手持ち花火みたいな棒を振っている。能ヶ谷先輩がそれを見て、ああそうだよと言う。
ふと顔を上げるとみんな楽器の準備が大体できていて、私も慌ててサックスを組んで構えた。マウスピースを口に咥える前から南美が緩やかなイントロを弾き出した。
思えば、テーマの最初のシドレファというメロディに、Beautiful Loveという言葉がぴったり入るのかもしれない。その心地でシドレファを吹いてみると、些かセンチメンタルな響きができた気がした。
遅いテンポだと、アドリブを取るのが転た難しいと感じる。8分音符のライン上に音を載せるだけではまだ無意味な休符があって、何か音を作らなければと思うのだが、発想が乏しくて次が出てこない。1コーラス目でだいたいの諦めがついて、南美のピアノにアドリブを譲った。
南美はやっぱり上手だった。吹くことは容易にできるだろうが、聴いていて最高に心地良い音の並びをいくつも出してくる。南美の脳はちょうど性能の良いマシンガンのようになっているのだろう。一つのフレーズを出しきる前から、次にぴったりはまるフレーズが用意できている。その場しのぎではない、つながりのある即興。それにしても、脳のどこから、はまる旋律が沸いてくるのだろう?
図師がベースのソロを取らないということで、南美のソロから直接テーマに戻ってきて締めた。
「おつかれさまー!ダンモ初ブラシ楽しかった!いつものことだけど、南美すごい!どうやって練習してるの?」
ののかが間抜けな声色で南美に訊いた。
「第二音楽室」と南美が述懐した。
「え、第二音楽室、あの誰も来ない廃墟みたいな部屋?」
「そこにもウッドベースとピアノがあって、ハナと昼休みにデュオやってる」
図師がうなずいた。
「デュオ、いいよ、自分の音と100%向き合わなきゃいけなくなるから練習に合う」
と図師が言う。
ののかが私の近くに寄ってきて、「あの二人絶対できてる」と耳打ちしてきた。
私が小さくうなずいていると、図師が空目遣いでこっちの方を見て、
「アンタたち、さっきから何の会議してるの?」
と小声で言う。
私は別に何でもない素振りで首を振って、ののかは呑気にむくれた。
しばらくの会話の余白の後で、
「同じ会話とか、同じフレーズって二度と思いつけないじゃん?でも、似た文言、似た余白構成なら思いつける気がして、鍵盤を触ってみるんだけど、どうしても…戻ってこない」
と南美がピアノに向かって独り言を言った。
「だからジャズは楽しい、…油そば」
寝ている大蔵先輩が寝言を言った。能ヶ谷先輩がそれを見て笑った。
When you hear music, After it's over,
It's gone in the air, You can never capture it again.
Eric Dolphy
だんもやいやい