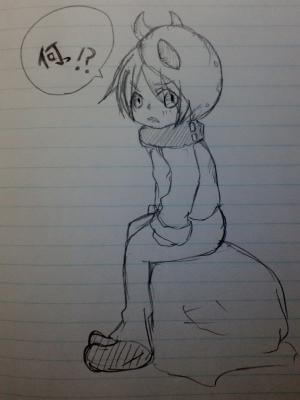いぬかぶり 第1話
はじめての投稿になります。
まだまだ未熟者で、文章が乱雑になると思いますが、よろしくお願いします。
地元の風景をもとに書き上げました。
そのうち、どこか分かるようになってくれるとうれしいなと考えていたり…。
お願いします。
どうしてこうなっちゃたんだっけ?
公園のベンチに一人で腰かけている自分。家を飛び出した時は重かったカバンは、今は軽い。
「もういいです。わたしなんて、この会社に必要ないんでしょ?いい加減はっきり言ったらどうですか?もうみなさんいい大人なんでしょ?この会社は、チームワークを売りにしてるんでしょ?だから、私みたいに何かが合わない人はいてほしくないんでしょ?」
そうやって小さな事務所の小さな社長のデスクに向かって叫んだのが1時間ちょっと前。四角い…昔、某料理人が国営放送のアナウンサーに向かっていった「焼き豆腐みたいな顔」…そんな表現がぴったり合いそうな顔の社長は驚いた顔をしていた。少し社長は固まった後、すぐに態勢を整えた。
「佐藤君、急にそんな大声を出したら他のみんなの邪魔になるじゃないか。そのくらい君は考えられないのかね。そして、君は急にそんな文句を言い始めるのかね。普段はおとなしい顔をして言うことを聞いているのだがな。まったくだ。」
社長は少し目線をずらして、他の社員に目線を送った。社員は、自然な動きで佐藤が使っていたデスクを片づけ始めた。
「…え!?社長…これは一体…。」
もともと、強気な性格でないことが災いして言いたいことが完全には出てこない。手を強く握りしめることで精一杯だった。社長はニコニコしながら佐藤の方を見上げた。
「クビだよ。当たり前じゃないか。…まぁ、ストレスを与え続けたガラスのコップがとうとう割れちゃったってとこかな?君も君で便利だったがな…。まさか、こんな風に思っていた、だなんてね。」
膝の力が抜けることが分かる。この会社は、複数人で依頼人の警備を行うことを主な職務にしていた。佐藤も、仕事に関わることは何度かあった。しかし、現場の社員との関係が上手くいかず、最後の方は仕事に支障をきたすほどになっていた。大きな会社だと、配属転換を願えただろう。この会社は、警固を行っているメンバーを除いた社員は、社長とその秘書だけ、という小さな会社だった。そのため、佐藤は願いを乞う場所がなかったのだ。
このような状況だけだったら、佐藤は社長に文句をいうことなんてなかったのだろう。彼もいい大人だった。多少の人間関係の不具合だったら対処できる自信があった。しかし、これ以降彼の記憶から永遠に消されるであろう、ある事件をきっかけに彼はこの会社に居続ける自信がなくなったのだ。その事件は警察沙汰にはならなかったし、社長の方に届くこともなかった。知っているのは、事件の張本人の佐藤と関係者だけだった。佐藤はこの事件で一瞬、死を覚悟した。もしくは、死ぬことはなくともこれから彼の一生に残るであろう傷を負うことになるところだった。現在の彼は、この事件のことは完全に忘れている…と思われる。
佐藤…佐藤晴彦…これが彼の本名でこの話の主人公に躍り出る男である。中肉中背に優しそうな目、物腰は柔らかく決して攻撃的とは言えない雰囲気の持ち主。少し長めの黒髪の持ち主である。性格は確かにやさしめで強く自分の言いたいことは言えないと自己分析をしている。兄弟はおらず、両親は佐藤が独立してから急に田舎に行きたいと言い出して東北の方へ行ってしまった。彼の通っていた高校・大学は現在住んでいるところから離れたところにあった。そのため、彼には仕事について気楽に相談する相手もいなかった。仕事は時間が不定で急に夜中に仕事が入ってくることもあった。この職業のせいか、彼がここに出てきてから新しい友人を見つけることもなかった。
時間は、彼がその会社に文句を言っている頃に戻る。
社長はニコニコしながら佐藤を見ていた。
「そもそも、君のことは誰が入社を認めたのかねっていう話になっていたんだよ。私も、多くの社員も君のことは心から仲間だとは認めていないんだよ。だから、君がこの会社を去ることは私たちからしたら歓迎なんだよ。だってそうだろ?一方的に具体的な理由なしでこの会社を去ってくださいなんて言えないじゃないか。君から言ってくれたならば、私たちは、それはそれで歓迎するよ。…安心してくれ。今のこの経済状況だ。1年分ぐらいだったら、君の生活費を出すよ。だったら、文句はないよな?」
佐藤は一方的に話す社長を見る。少しは、引き留めてくれると期待していた自分が馬鹿だったと思った。(そうだ。無駄な期待はするべきものではないのだ。この社会は。)
「…だったら、この会社を出ます。これ以上自分の身を危険な場所に置いておきたくありませんし。生活費を出してくれるのであれば、私も納得します。」
これが佐藤にとって、一番のこの会社への嫌がらせだった。いくら仲が良くなかったとはいえ、彼もいくつか仕事を請け負っていたからだ。(自分が出てゆけば、このひどい仕事場の人間たちに迷惑をかけることができる。そう、自分が仕事を辞めるといった前に自分の机を片づけ始めたこの人たち。体つきから言ったら、自分の何倍かはあるだろう。なぐり合ったら、体重の関係で勝ち目はない。一つの攻撃の重さが違いすぎるのだ。)いろいろ考えながら、佐藤は社長の机の前で立ち尽くしていた。これが、もしかしたら彼の本音なのかもしれない。
「おい、佐藤。いつまでそこに立っているつもりだ。君はこの会社ではもう用事はないのだ。早く帰ってくれ。私たちはこれから、君が残していった仕事を片づけなければならないからね。幸いなことに、君は私物をここに残していなかったみたいだね。机の整理がしやすかったよ。」
「…社長。ありがとうございました。」
佐藤は頭を下げて、事務所から出て行った。
ランドセルを背負った小学生が向こうに見える道を行き来し始めた。手元の時計を見る。午後3時半を示していた。もう、1時間は座っているのか。我ながら感心ものだ。この公園は駅の近く…目の前といった方が正確…にあって、かつ近くには小学校と中学校が合わせて4つは存在している。だからか、下校時刻になると小学生の数が半端ない。昔はあんな感じだったんだろうな…なんて、しみじみと考えてしまう。
佐藤はふと考える。(そう、ここに座りっぱなしなのもよくないんじゃないか?次の職を探すには立ち上がって、何か行動を始めないと。そうだ、たまには回り道をして帰るのも名案だ。何か見つかるかもしれない。)
「よし。頑張れ、俺。」
膝を叩く乾いた音がなる。
いぬかぶり 第1話
はじめて、自分が書いた物語を他人に読んでもらったのは小学校5年の時。
元気いっぱいの女の子の物語だった気がします。
いかんせん5年生の作った物語。
ストーリーのつながりが薄かった気がします。
そんな女の子が成長して、不特定多数の人に見られる作品を書くようになりました。
これからもよろしくお願いします。