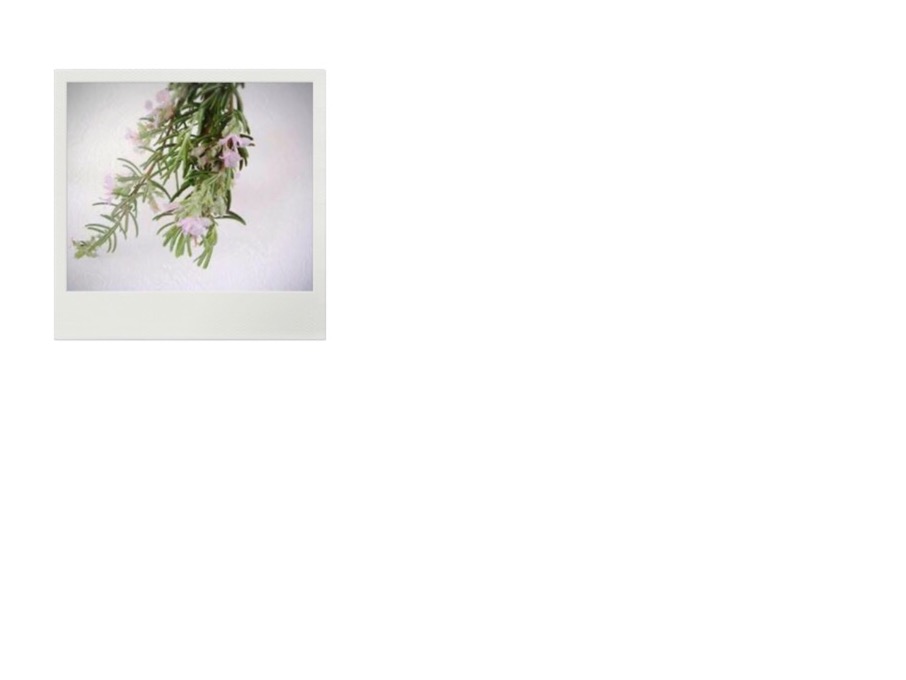
Rosemary ( 中 )
二人でバーを出ると、小雨がぱらついていた。
先週梅雨に入ったと風のうわさで聞いたが、特有の肌に張り付くような湿気と夜のひんやりした風が、アルコールで火照った体には心地よかった。
『この近くにデリがあるから、何か買って行こう』
「はい」
月明かりが所々に雲に覆われてぼんやりとしていた。
彼からあの言葉を言われたとき、私の手は彼の腕を掴んでいた。
「……っ!、すみませっ、」
思わず離そうとした手は、彼の大きな手に遮られて同時に重なった。
彼の瞳が、私を捕らえていた。
私の身体は見えない彼の視線に囚われ、縛り付けられたように動けなかった。
『……同じ気持ちだと、思ってもいい、?』
私は彼の瞳を見て、深く頷いた。
酔っていたのかもしれない、でも、もう少しだけ、彼の側にいたかった。
これが、最期ならーーーーー
『うわ、』
空からとめどなく降り注ぐ大粒の雫に、彼が隣で声を上げた。
デリで適当な買い物を済ませて店先へ出ると、先程までの小雨は土砂降りに変わっていた。
『ここから走ればすぐなんだけど、さすがにこの雨じゃなぁ、』
困ったように空を見上げる彼を脇をすり抜け、軒先から二、三歩踏み出した。
頭上を打ち付ける雨が、淡いワンピースを徐々に濃く染めていく。
『えっ、?!、ちょっと待って、風邪を引くよ!』
「一度やってみたかったの!
すごく気持ちいいよ」
見上げた空は一面の灰色だけど、今の私の心の中は雫に流されて浄化されたような清々しい気持ちでいっぱいだった。
「きゃっ、」
急に視界が真っ暗になり、彼のジャケットが頭からかけられたと同時に右手を引かれ、そのまま駆け出した。
『そのまま走って!』
先程まで私を呆然と見ていた彼が、私の手を引いてぐんぐん前へと進んでいく。
彼の体温を指先から感じながら、足がもつれそうになるのも構わず、ワイシャツが張り付く彼の背中を追いかけた。
彼の部屋の扉を開ける頃には、二人とも息が上がって、肩で会話をしていた。
全身で至るところが雨を吸い込み、ワンピースと髪は身体に張り付き、雫が地面へと吸い込まれていく。
呼吸が正常に戻ると、二人で見合って笑った。
『君は不思議な人だね。あんな大胆なことするなんて』
「私だって、こんなこと初めてよ、?」
『はは、でもおかげで全身びしょ濡れだ』
笑いながらかきあげた黒い髪から滴る雫が、ワイシャツの襟からつたって首筋を流れていく。
程よく引き締まった細い体のラインに魅入ってしまう。
視線が交わり、急に羞恥心におそわれ凝視していた目線をそらした瞬間、唇から柔らかな熱を感じた。
かろうじて肩に引っかかっていたジャケットが玄関の床に吸い込まれていくように落ちていく。
一瞬だったのか、数分経っていたのか、それすらも分からないほど、唇から伝わる彼の体温に浮かされていた。
両手は彼の指先と絡まって、唇からは彼の熱が伝染し、じわじわと彼という雄に染められていく。
「んっ、……ふっ、ぁ……」
徐々に深くなる口づけの端から漏れる聞いたこともない自分の卑猥な声に、体の芯から羞恥心が溢れ出す。
唇を離すとそのまま私を抱き上げ、部屋のドアを開けて二人でベッドへ身を沈めた。
『…ごめん、』
謝る彼に、私は熱に侵された頭を左右に振り、目の前の彼を見た。
「…謝らないで。ここまで来たのは私の意志よ。
だから、お願い、」
女という生き物は、どうして妙に勘がいいのだろうか。
彼の気持ちが、手に取るように分かる。
瞳の色が後悔の念を抱いていることに気付いていたが、私は見て見ぬふりをした。
自ら手を伸ばし彼の首に腕を回すと、彼に口づけをする。
先程のキスよりも、ゆっくり、奥深くまで探り当てるように。
私は自ら彼の引き金を引いた。
そこから先はベッドのスプリングが軋む音と、彼の全てに酔いしれた。
――――――――――――――――――
―――――――――――――
―――――――――
『君が弊社に入社したければ、その地味な身なりを何とかして、ここにいる我々を説得させる何かをしてごらんよ。
そうしたら、少しは考えてやってもいいがね?』
そう言った面接官を筆頭に、薄ら笑う声が静かな面接室に響いた。
頭の先から足先まで黒で統一した清潔感のみをそろえた身なりは、厭らしい視線で足元を見ていた重役たちにはお気に召さなかったのだろう。
大学三年生、初春のことだった。
数社受けた中で強く志願していた会社の圧迫面接は、心をえぐられたような気持だった。
もともと地味な顔立ちなのは自覚していたが、他人に指摘されるのは辛いものがあった。
面接を終え、何とか会社の外に出ると先ほどのビルが見えなくなるまで勢いよく走った。
立ち止まって肩で息をするのと同時に、大粒の涙が頬を伝っていく。
次から次へと伝う雫は、止まる気配すらなかった。
悔しくて、悲しくて、何も言い返せなかった自分に余計に腹が立ち、流れる涙を少しでも止めようと自然と眉間に力が入る。
目元をこすると、マスカラの黒い繊維がいくつか手についてしまい、咄嗟に鞄からハンカチを取り出すと、手の震えが止まらなくて手を離してしまった。
地面に落ちたハンカチを拾おうと手を伸ばすと、寸前のところで自分よりも大きな手がハンカチを包み込んだ。
『大丈夫?』
かけられた声にはっと顔を上げると、大きな瞳と視線が合う。
その瞬間に感じた心臓が握られるような、不思議な感覚は、頬を伝う涙のあとによってすぐに消え去った。
「ありがとうございます。」
思わず泣き顔を隠しながら、ハンカチを受け取った。
きっとメイクもボロボロで酷い顔をしているだろう顔を見られてしまい、気恥ずかしくなった。
『ねぇ、これから時間ある?』
「……へ?」
聞き間違いかと思った誘いの言葉に、気の抜けた返事をしてしまった。
『この近くにケーキが美味しいカフェがあるんだ。よかったらどうかな?』
彼に連れられて入ったお店は、夜はバーになって珍しいお酒も飲めるというあのお店だった。
窓から射し込む太陽の光は、重厚感のあるブラウンで統一されたカフェを明るく優しく包んでいた。
『マスターの作るシフォンケーキは本当に美味しいんだ。』
カウンターに並んで座り、シフォンケーキと紅茶のセットを注文した。
彼の声色は傷ついた心をなだめるかのように落ち着いていて、時々見せる少年のような無邪気な笑顔に、心が落ち着かなかった。
『圧迫面接、か。それは酷い会社だったね。』
「志望していた会社だったので、やっぱり辛いですね。」
思い出すだけで涙腺が緩み、目の前の光景が段々とぼやけていく。
彼の視線を感じ、必死に堪えようと眉間に力を入れ、無理矢理に笑顔を作った。
その瞬間、身体が彼の腕に引き寄せられた。
彼の温かい左胸に、心臓の奥がじんわりと安堵感に包まれる。
『無理に笑わなくていいよ。難しいかもしれないけど、泣いて泣いて、自分を吐き出すのも大事だよ。君なら大丈夫だよ』
大きく波打つ心臓は、彼の言葉で洗われるかのように落ち着きを取り戻し、私の目から大きな雫が溢れる。
『冷めないうちに紅茶を頂こう。きっと気に入ると思うんだ。』
暖かい紅茶から立ち昇る茶葉の甘さが、泣き疲れた体に染み込んでいった。
彼の柔らかい髪をゆっくりと指で梳く。
熟睡している彼は無防備で少年のように穏やかな顔をしていた。
先刻までの私を奪い尽くすような雄の部分は微塵も感じない。
初めて出会ったあの日、数時間話しただけの彼にこんなにも惹かれてしまう自分がいるなんて、自分の心の中にこんなに激しく誰かを想う感情があるなんて知らなくて、そして彼とこんな風になるなんて夢にも思っていなくて、今が夢のようで、このまま覚めなければいいなんて本気で思ってしまう。
『ん、…』
彼が体を捩り慌てて手を離と、指先を掴まれる。
「……っ」
『…ん、』
そのまま口元だけもごもごと動かし、私の手を離そうとしない彼に自然と口元が緩む。
このまま、このまま彼のそばにいたい。
ずっと、彼をいちばん近くで見ていたい。
このまま・・・ーーーー
彼の手を少し強く握り返した瞬間、ふわりと風が吹いて、カーテンを揺らした。
--- 約束の時間よ。
声のするほうへ視線をはなつと、彼女が窓枠に座っていた。
後ろに写る灰色の雲に覆われていた空はいつの間にか、紺碧のキャンバスに染められ星が散りばめられていた。
Rosemary ( 中 )


