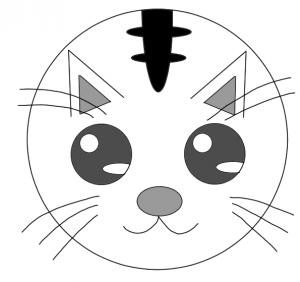海月、その後
三題話
お題
「騒がしい」
「心にもない」
「サクランボ」
この日は家でだらだらと過ごしていた。
学校が休みの日はたいてい家で過ごす。それは海月も同じで、ずっと俺の部屋のベッドに寝転んで漫画を読んでいる。
「何か飲み物でも買いに行ってくるわ。海月は何か欲しいものあるか?」
「あ、お兄ちゃん、それなら僕も一緒に行くよ」
海月は読みかけの脇に漫画を置いてから、笑顔で身体を起こした。
こうした不意に見せる笑顔がとてもかわいい、なんて、この前あんな変な夢を見てしまったからなのかそんなことを思ってしまう。
ずっとパジャマで過ごしていた俺達は、外着に着替えてから外へ出た。
昼下がりの、日差しで幾分かは暖かな時間帯。
春はもう少し先なのかもしれない。
…
「お兄ちゃん、もうすぐ春休み終わっちゃうね」
「ああ、そうだな」
俺はこの春から大学生となる。海月だって来年は高校受験なんだから、忙しくなるだろう。
こうして二人でゆっくり過ごすことも少なくなるかもしれない。
「やっぱり大学って忙しいのかなぁ?」
「どうだろうな。バイトもしたいし、忙しくなるだろうな」
「……寂しくなるね」
海月はぽつりとそんなことを言った。
「え?」
聞き返した俺に海月は笑顔で、なんでもないよ、と小さな声で答えた。
この言葉に対して俺は何と返せばいいのだろう。
他意は無いのだろうけど、ついつい変に意識してしまう。
「はあ」
「どうしたの? 溜息なんて吐いて」
そうして自宅から五分ほど歩いて、コンビニに到着した。
自動ドアを通り抜けると、いらっしゃいませー、とだらしなく間延びした店員の挨拶が耳に届く。
真っ直ぐに奥のドリンクコーナーへ向かうと、海月は迷わず一つの商品を手に取って俺に手渡した。
「お前、相変わらず豆乳好きだな」
「うん、好きー」
海月が選んだのは豆乳リンゴジュース。
いつも豆乳飲料を飲んでいるが、俺はそんなにおいしいものではないと思う。好きか嫌いかで言えば、嫌いの部類だ。
「お兄ちゃんも豆乳にすればいいのに」
「いや、俺はこっちにするよ」
俺はいつものように適当に炭酸が入っているものを手に取ってレジへ向かった。
ついでに肉まんを二つ買って、行きと同じ道を辿って家へ戻る。
また俺の部屋に二人で入り、ベッドに腰掛けた。
「ほら、海月の」
「ありがとー」
海月に肉まんを手渡すと、おいしそうに笑顔で頬張った。あっという間に食べ終わり、豆乳リンゴジュースを飲む。
肉まんには合わなさそうだけど気にならないようだ。
俺も肉まんを食べながら炭酸を飲んでいると、横から海月の手が伸びてきた。
「お兄ちゃん、少し飲ませて」
「お、おう」
海月にペットボトルを手渡すと、くぴりと一口飲んで、苦い表情を浮かべた。
「べー、炭酸はやっぱり苦手」
「相変わらずだな」
海月は炭酸が苦手で飲むことが出来ない。こうやって俺が飲んでいるやつを一口飲んでみるが、なかなか慣れないらしく毎回苦い表情を浮かべている。
俺は海月から返してもらったボトルを見て、少し考える。
これって、間接キスか……?
何を考えてるんだ俺は。家族間で気にするようなことじゃないだろ。
「ん? どうしたの?」
「いや、なんでもない」
この瞬間は海月の顔をまともに見ることが出来なかった。
騒がしいほどに心臓がバクバクと鳴り響いている。海月に聞こえてしまうかも、と思ってしまうほどに。
海月は俺を見つめ、俺は海月を見つめている。
さくらんぼのようにぷっくりとして瑞々しい唇が、俺の目の前にある。
食べてしまいたい。そんな衝動に駆られて、俺は思わず海月の唇を奪っていた。
「ふあっ――」
海月が身体を引いて、二人の唇は離れ離れになる。
「あ……」
そこで俺はひどく後悔することとなった。まさか兄弟でこんなことをしてしまうなんて。
あの夢を見て以来、海月が愛おしく思えてしまったのは否定しないが、それにしても……。
そこで俺は顔を背けた。海月を見ることが出来ないし、逆に顔を見られたくなかった。
どれくらい沈黙が続いただろうか。
初めに口を開いたのは、海月のほうだった。
「ね、ねえ、さっきのは……」
「ごめん。そんなつもりじゃなかったんだ。忘れてほしい」
顔は背けたまま、感情を込めずにそっけなく答えることしか出来なかった。
「あのさ、お兄ちゃん。僕のこと……好きなの?」
忘れてほしいと頼んだのに、海月は会話を続けてくる。その質問には答えられないというのに。
「…………」
「僕は、お兄ちゃんのこと好きだよ。でもこういうのは、ちょっと違うかな。ううん、お兄ちゃんとなら……いいかも」
「…………」
俺は何も言えなかった。動けなかった。
海月は何にも分かっていない。俺が、夢の中とはいえ、海月に何をしたのかということを。
心にもないことは夢に見ない。
だから俺は、黙っている。
左肩に重みを感じても、顔を右側に背けたまま。
「ねえ、お兄ちゃん」
海月の両腕が俺の身体を包み込む。海月の吐息が耳にかかってくすぐったい。
俺が海月に顔を向けると、今度は海月のほうから唇を合わせてきた。
ちゅ、と静かな音を立てて、海月は俺から離れた。
「これでおあいこだよね。だから、お兄ちゃんが気にする必要はないんだよ」
そのときの海月の笑顔は、天使のように輝いていた。
海月、その後