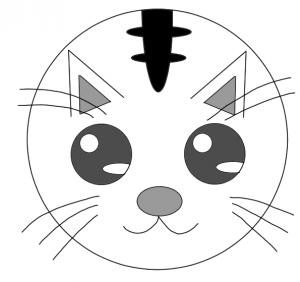ヤミの形
三題話
お題
「いいことを教えてあげよう」
「茫然自失」
「カステラ」
夜、私は独りで公園にいた。
誰もいない夜の公園。そこのベンチに座っている。
私は両手で顔を覆い、声を押し殺す。
まさか誕生日に彼氏から別れを告げられるなんて……。
喧嘩別れではない。他に好きな人が出来たから、らしい。
今日は夕方に待ち合わせをして、食事をして、プレゼントを貰って、その後はどうするのかと思っていたところで、突然別れ話を切り出された。
初めは理解出来なくて、混乱した。私のことが嫌いになったわけではないが、好きなのかどうか分からなくなったという。いきなりのことで私は頭の中の整理が出来なかったのだろう。そうなんだ、という一語しか口にできなかった。
そしてその場から逃げるように、じゃあね、と言って彼に背を向けた。最後に見た、彼の申し訳無さそうな顔が頭から離れない。
家へ帰る途中で通り掛かった公園のベンチに座り、一息吐くと、急に両目から涙が溢れ出て、私の顔を醜く濡らした。ここまで来てようやく、私は現実を理解することができた。
大好きだった彼に振られたという事実が突如として私に襲い掛かる。
それはとても悲しくて、苦しい出来事。
どうしてその場で何も言えなかったのか。
別れたくない、と。貴方を愛している、と。
私は今更のように後悔していた。
ザリ、という音に顔を覆っている両手を退けると、人の足が見えた。
いつの間にか目の前に人が立っている。
こんな姿を見られてしまい、私は恥ずかしくなり身体を縮める。
「おお、どうしたんだい?」
その人は私の隣に腰掛け、顔を寄せてきた。
「女の子は泣かせちゃあいかん。大切にしないと」
嫌なにおいのする息が顔にかかり、気分が悪くなる。
横目で隣の男を窺うと、多分両親より年上だと思われる年配の男だった。よれよれのスーツを着て、赤ら顔で眼は充血していて酒臭い息と合わせて明らかに酔っ払いであると判断出来る。
その男は気持ち悪い笑みを浮かべながら、私の肩へ腕を回してきた。
じっとりとした右手が私の右肩へ置かれた瞬間、それを振り払って飛び退いた。
「おお、びっくりさせちゃったかな。ごめんよお」
男は立ち上がって私の正面に立つと、懲りずにまた手を伸ばしてきた。
でもその手が私の身体へ届く前に、男は変な声を上げて地面に倒れ込んでしまった。
その後ろには、別の男が立っていた。
背は私とほとんど変わらないから、男性としては小柄なほうだろう。体格は大きめのパーカーを羽織っているせいでよく分からないが、太ってはいない。野球帽を目深に被っていて、なおかつ俯き加減で目鼻は窺えないが、口元だけはよく見える。
口角を上げ、笑っているように見えた。
「危ないよ。こんな時間に独りでこんな場所にいたら」
その男にしては高い声で、この辺りは夜になると酔っ払いや変質者が増えるんだ、と補足した。
もしかしたら少年なのかもしれない。
「あ、あの……」
私は一応お礼を言おうとして、だけどそれは少年の言葉に遮られてしまう。
「でも安心して。君のことは僕が守るから」
こちらへ伸ばしてきた左手。私はそれから逃れるために背を向けて走り出していた。
一刻も早くこの場から離れようと、私は懸命に両脚を動かす。
だけど少年は笑顔のまま佇んでいて、私の後を追い掛けてくることはなかった。
◇
その日は二人で夜の繁華街を歩いていた。
「それにしてもヒドイ男だな、そいつ。なにもそんな日に振らなくたって」
「彼のことを悪く言うのはやめて。良い思い出だけを残しておきたいの」
私がそう言うと、それ以上は何も言ってこなかった。単に呆れているだけかもしれない。
そのまましばらくは無言で歩き、私達は公園の中へ入った。
この公園を抜けて行けば少しだけ近道になる。でも明かりが少なくて周りの道路からは木々に視界を遮られるため、変質者の出現を警戒しているのか夜にここを通る女性は少ない。
私は警戒心が足りないのか夜に独りでもこの近道を利用するが、特に被害を受けたことはない。
今のところは。
「そういえばこの公園だっけか。ホームレスが殺されたのは」
「うん、そうだよ。事件があってからここは通らないようにしてたの」
「もうすぐ一ヶ月になるのにまだ犯人は逮捕されてないんだろ。警察は何をやってるんだ」
そこで私は無意識に、彼の手を握っていた。
「なんだか、怖いね」
「俺がいるから大丈夫だって。それにヤバそうだったら走って逃げればすぐに人通りのあるところへ出られるし」
私を安心させるためか、軽い口調で彼は言った。
立ち止まり、優しい笑顔を私に向けて、空いている手で頬を撫でてきた。
その彼の優しさに、心地良さと心苦しさを覚える。
ガサリ、と近くの草むらから音が聞こえて、二人でそちらを見たが何もなかった。
「ここで待ってろ」
そう言って彼は音がした方へ近付いてゆく。
ザリ、ザリ、という彼の足音だけが響く。
こちら側は明るいけれど、向こう側は暗くて視界が悪い。
待ってろと言われたのに私は歩き出していた。
彼が植木を飛び越えて奥へ進み、そして鈍い音と呻き声とともに視界から消えてしまった。
私は駆け寄り植木の先を覗き込むと、彼は後ろ向きに倒れて動かなくなっていた。
彼の向こう側にはあの時の野球帽とパーカーの少年が立っている。ふわりと柔らかな動作で植木を飛び越えて、私に向けて両腕を広げた。
「ほら、今日もまた君の望み通りだよ」
倒れている彼の顔は赤く染まり、形が歪んでいる。
それには目もくれず、少年はこちらへ歩いてくる。
「今日は君が好物だと言っていたカステラを買って来たんだ」
がさり、と私に向けてビニール袋を掲げた。その袋には私が好きな店のロゴが印刷されている。
あの日と同じ笑顔のまま。
あの日と同じ場所で。
だけど、今回は私の身体は動いてくれなかった。
ザリ。私は両腕で自身の身体を抱いた。
ザリ。少年は真っ直ぐ近付いてくる。
ザリ。そして私の目の前で立ち止まった。
私は俯いて少年の顔を見ないようにした。
その行為に何の意味があるのか、私にも分からなかった。
薄汚れたスニーカーが視界に入る。右足、そして左足。
少年は私へ左手を伸ばした。私は身体を震わせる。
肩へ手が触れた瞬間、私はようやく脚を動かすことができるようになって、全力でその場から離れていった。
しかし今回も少年は後を追い掛けてこなかった。
ヤミの形