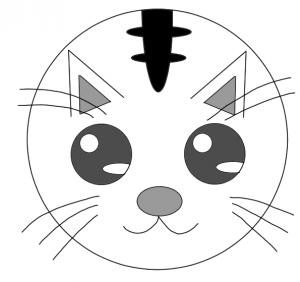幼馴染チョコ
三題話
お題
「手作り」
「チョコ」
「失敗なのか成功なのか」
ようやく大学の試験が終わって、試験結果が出るまで勉強に関することは完全にオフとする。
一夜漬けで疲れ切った脳みそはオーバーヒートぎみでパンク寸前。
帰りに缶ビールやお菓子を買い込み、一人暮らしをしている大学近くのアパートで来客を待つ。
ビールを冷蔵庫へ入れ終わりようやく座ったところで、インターホンが鳴った。
俺はすぐに立ち上がり玄関へ向かう。
「よう、早かったな」
「同じアパートなんだから当たり前でしょ。カバンを置いてきただけだし」
同じ大学に通い同じサークルに所属する、そして偶然にも同じアパートに住んでいるカナミを部屋へ招き入れる。
部屋に女の子を招き入れるなんていろいろなことを期待したくなるが、カナミと俺は幼馴染。
保育園からずっと一緒だったりする。
だから部屋に二人きりでも甘い展開はないし、同性の友達となんら変わらない関係だ。
「さて、さっそく飲みますかね」
俺は冷蔵庫から缶ビールを二本取り出して、一本をカナミに手渡した。
「まだ昼間だよ。それに、私達はまだ未成年なのに」
「そんな細かいこと気にすんなって。来年には成人式だろ」
「もう。しょうがないなあ」
そう言いながらも缶を開けて、俺と乾杯をする。
「かんぱーい」
「かんぱい」
こうして俺達二人は午後三時から飲み会を始めた。
…
「なあカナミ、バレンタインデーってあるじゃん?」
「ん、それがどうかしたの?」
午後七時を回ったところで、夕食とお酒の買い足しに外へ出た。二人ともアルコールには強い体質で、缶ビールを三本飲んだくらいではまだほろ酔い気分だ。
二月に入って更に寒さが増した夜の空気は、一気に酔いが覚めてしまうほどにキリリとしている。
「あれってさ、男も女もめんどくさいよね」
「そ、そうかな?」
「そうだよ。だってそもそもの始まりがチョコを売るための企業の策略だろ? 特に義理チョコなんてさ、気を遣ってかなんだか知らないけどくれてもお返しに困るだけだし」
「で、でも、女の子にとっては特別な日なんだよ。きっと」
「ははは。お前も一応女の子だったか」
「あ、ひどーい」
ぽすぽすとカナミの頭を叩きながら近所のスーパーへ入る。店内は賑やかで暖かな空気に包まれていた。
二人で笑い合いながら買い物を済ませて、結局明け方まで飲み会を続けることとなった。
◇
二月十四日。バレンタインデー。
特に何かがあるわけでもなく、俺は朝から夜までバイトをしていた。ここでのバイトは、もうすぐ一年になるか。
午後十時を過ぎて、ようやくバイトから解放されて帰宅する。
くたくたになって歩く暗い帰り道。外の冷たい風が火照った身体を冷やしてゆく。
すぐに寒くなって、カバンからマフラーと手袋を取り出して身に付けた。早足でアパートまで辿り着くと俺の部屋の前に人が立っていた。
「あっ……」
その人物は俺の姿に気が付くと、白い息を吐きながらこちらを見た。鼻の頭が赤くなっているところを見るとけっこうな時間ここにいたのではないだろうか。
「カナミ、そんなところに立ってたら風邪引くぞ」
「今来たばかりだから大丈夫。そろそろ帰ってくる頃かと思って」
カナミは笑顔で俺を迎え、手には小さな紙袋があった。
バイトのシフトについては話していないから、いつ帰ってくるかなんて分からなかったと思うけれど。
「はい、これ。受け取ってくれる?」
「もちろん。ありがたく受け取りますよ」
俺はわざとらしく両手で丁寧に受け取ってお辞儀をする。
その仕草にカナミは小さく笑った。
「えっと、ごめんね」
「ん、何が?」
「ううん。何でもない」
「せっかくだから中に入れよ。これ、一緒に食べようぜ」
ドアを開け、紙袋を掲げてカナミを誘う。どうせ中身はチョコだろう。
保育園の頃から毎年欠かさず皆勤賞。幼馴染だからとはいえ素直にありがたいと思う。
「ごめん。今日は疲れちゃって、もう眠いから帰るよ」
「そっか。じゃ、また今度な」
「うん。お休みなさい」
お互いに手を振って俺達は別れた。
ドアを閉めたところで一息吐くと、疲れがどっと押し寄せてきた。
「うわ、俺も今日は早めに寝るかな」
荷物を置いて風呂場へ向かおうとするが、部屋へ入ったことで強烈な眠気が襲い掛かってきた。
今日は自分で思っている以上に疲れているらしい。朝から夜までバイトするのは久し振りだったからなのか。
俺は寝巻きに着替えるとすぐに布団へ潜り込んでそのまま眠りに付いた。
…
朝、目が覚めて時計を見ると、正午を過ぎていた。
自分でも驚くほどの爆睡ぶりに、思わず笑ってしまった。
もう朝じゃない。
洗面所に行って顔を洗って、昨日帰ってきてそのまま寝てしまったことを思い出してシャワーを浴びた。
部屋へ戻ってきて、布団を畳んでからテレビをつける。ケータイを見るが、メールなどは入っていない。
そういえば、と昨日カナミからもらったチョコのことを思い出した。紙袋を引き寄せて中を見ると、四角い箱と手紙が入っていた。
箱の中身は、俺が好きなトリュフチョコ。いつものようにカナミの手作りだろう。
一つ摘んで口に放り入れ、俺は手紙を手に取った。
毎年小さなメッセージカードに一言添えてあったが、こうして手紙が入っていたのは初めてだ。
ハート型のシールで留めてある封を解き、中から折りたたまれた便箋を取り出す。広げると、かわいらしい模様の便箋には小さな丸文字がたくさん並んでいた。
『チョコを受け取ってくれてありがとう。迷惑かな、と思ったけど渡しちゃいました』
どうしてそんなことで気を遣うのか、と疑問に思ったとき、俺はこの前の自分の発言を思い出していた。
わざわざ義理チョコをくれても、お返しがめんどくさい。
たぶんその事を気にしているのだろう。俺とカナミの仲ならそんなことは気にする必要はないのに。
『こうやって手紙を添えるのは初めてだね。もしよければ、最後まで読んでください』
妙に丁寧なのは、手紙だからだろうか。今日は何の予定も入ってないから、俺は続きを読むことにした。
読み終わるまでそんなに時間は掛からなかった。
でも、なかなか手紙を手放せずにいた。
カナミの気持ちが綴られた、この手紙を。
その時ケータイの着信音が部屋に鳴り響き、俺は驚いて少し飛び上がった。
着信の相手は、幼馴染のカナミ。
まるでこちらの様子を見ていたかのようなタイミングの良さに、俺は苦笑いを浮かべた。
「おう、カナミ」
ものすごく緊張していたけれど、俺は精一杯冷静に振舞う。
一言目から俺の声は裏返っていた。
幼馴染チョコ