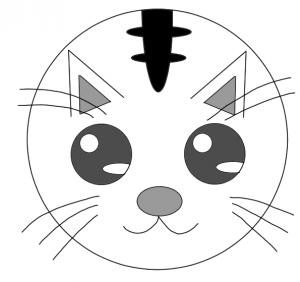最期の悟り
三題話
お題
「二人だけの」
「最期の望み」
「笑って死のう」
「なあ、どうする?」
彼は開かない扉を見つめながら、呟くように口を開いた。
「そんなこと聞かれてもわかんないよ……」
暗く閉ざされた密室に二人きり。
いつからこうしているのだろう。焦りより不安が強くなってきて、二人とも口数が少なくなってゆく。
もうこのままずっと、ここにいるしかないのだろうか。
「あー、お腹空いたー」
静寂の中、ぐう、と情けない音が響く。
「そうだね。わたしもお腹空いてるかも」
ぐう、と二人のお腹の音が重なった。
それがおかしくて、二人で笑い合う。けれどそれも一瞬のことで、すぐに沈黙が訪れる。
だんだん、不安から恐怖へと遷移してゆく。
「ねえ、修太くん」
「……なんだよ」
「このまま誰も来てくれないのかなあ」
「……わかんね。だけど、明日にはなんとかなるだろ……たぶん」
どちらからともなく肩を寄せ合って、お互いにもたれるようにして座る。
ぶるりと身体が震えたのは、寒いからではなくて。
「わたし、トイレに行きたくなっちゃった」
「え、えっと……え?」
きょろきょろと視線を泳がせて、だけどわたしのことを心配して、大丈夫か、なんて声をかけてくれる優しい人。
でもどうしよう。もちろんここにはトイレなんてないし。
「まだ大丈夫だけど、結構やばいかも」
わたしは乾いた笑顔を彼に向けた。意識すればするほど波が押し寄せてくる。
すると彼は立ち上がり、開かない扉をドンドンと強く叩き始めた。
「おーい! 誰かいないかー!」
ドンドン、ドンドンドン。
叩き終わった後に訪れるのは、今までと変わらない虚しい静寂。
近くには誰もいないようだ。
「なあ、大丈夫か?」
「う、うん」
かろうじて見える彼の表情は、わたしのことをかなり心配しているよう。わたしのほうはだんだんと息が荒くなり、明らかに余裕がなくなってきている。そう、もう諦めてしまいそうな。
「ほら、これ使えよ」
彼から手渡されたのは、ポリバケツ。
「えっと……」
「俺は出来るだけ離れてるから。何も見ないし、何も聞かない」
それだけ言ってわたしから離れていった。といっても限られたスペースの中。離れる距離にも限界がある。
もしかしたらもうすぐ外へ出られるかもしれない。出られないかもしれない。
迷っている間にも限界が近付いてくる。どちらが恥ずかしいかなんて、それはあまりにも明白で。
「…………」
わたしは意を決して、バケツを跨いでしゃがみこむ。
もう死にたくなるほど恥ずかしいが仕方がない。自分でも目を閉じて、耳を塞いで、心を無にして力を抜いた。
…
彼の肩をとんとんと叩く。
本当にわたしには背を向けて耳を塞いでいてくれたみたい。
振り返った彼の顔は、気恥ずかしそうに赤くなっている。たぶんわたしの顔はもっと赤くなっている。
「あ、ありがとね」
そんな気持ちは振り払って、わたしは小さな声で俯きながらお礼を言った。
「……ああ」
彼は視線を逸らしながら、そっけない返事をした。
わたしはそのまま彼の隣に腰を下ろし、再び沈黙が訪れた。
どうしてこんなことになってしまったのだろう。
早く帰りたい。なのに誰も来てくれる気配がない。
「もう、このまま死んじゃうのかな」
ぽつりと、呟いた。
「それは大げさだろ。大丈夫だって」
彼は軽く笑い、わたしの言葉を否定する。
でもわたしはだんだん怖くなって、思考がマイナスの方向へ向かってゆく。
「修太くん、あのね」
「ん、どうした?」
「わたし、修太くんのこと……好き」
「ん……えっ?」
「だから、このまま二人で死んじゃっても、いいかも」
「いや、その、死なないって」
「死ぬのは嫌だけど、修太くんとずっと一緒にいられるのなら、嬉しいかも」
「不安なのはわかるけど、とりあえず落ち着けよ。お前、さっきからおかしいぞ」
「二人で天国に行って、二人きりで過ごして……だから、悲しくない」
「…………」
わたしは思わず、彼に抱きついてしまった。
「怖いけど、わたし、笑えるよ。だって修太くんと一緒なんだもん」
そのとき、扉の向こう側が急に騒がしくなった。
「あっ、誰か来たんじゃね」
彼はわたしを押し退けて、扉の前に立ってドンドンと叩いた。
「おーい! ここだー!」
ばたばたという足音と、大人達の声が聞こえてくる。
すぐに鍵を開けるからな、という頼もしい声が返ってきた。
「やったな。外に出られるぞ」
「……う、うん」
彼は笑顔だけど、わたしは内心複雑だった。
つい先程のことを思うと、とても気まずい。どうしてあんなことを言ってしまったのだろう。
がちゃがちゃと鍵を開ける音がして、続いてわたし達を閉じ込めていた重たい扉がゆっくりと開け放たれた。
…
午後九時過ぎ。場所は学校の体育館の奥にある倉庫。
中に閉じ込められていた時間は、約三時間といったところ。
外のひんやりとした空気が汗ばんだ身体には心地良かったが、わたしの心は深く沈んでいた。
最期の悟り