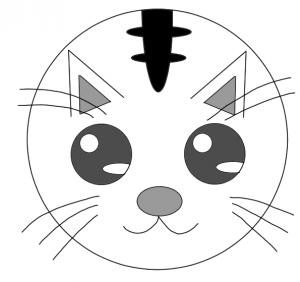雪が降る夜の彼と私
三題話
お題
「熱々の」
「かまぼこ板」
「スノー」
高校時代に同級生であった私達は、付き合い始めてもうすぐ七年になる。
大学は別々だったけれど気持ちは離れることなく、今までずっと関係が続いている。
お互いに社会人二年目。バタバタとあっという間に過ぎていった一年目と比べて、いくらかは心に余裕を持てるようになってきたかな。
彼は割と実家近くのところに就職したようで、車で通勤はしているが、実家で家族と共に暮らしている。
私は大学を卒業して独り暮らしを始めて、週末に彼が泊まりに来ることもある。
…
冬が近付きだんだんと寒さが厳しくなってきたある日。いつものように私が独り暮らしをしているアパートへ泊まりに来たときのこと。
彼が急に「夕飯は俺が作る」と言い出した。いつもは私が作っていて、彼が作ってくれたことなんて一度もなかったのに。それに、彼が料理をすることが出来るのかは不明だ。
「よし、出来た」
テレビを観ながらのんびりしていた私は、配膳くらいは手伝ってもいいだろうと思って立ち上がり、台所へと向かった。
…
「味はどうだ?」
「う、うん。おいしいよ」
「そうかそうか。それは良かった」
「でも……」
「ん、どうした?」
炊き込みご飯はレトルトを使ったみたいだけど、かまぼこは自分で追加したようだ。
コンソメスープの具はキャベツと玉ねぎとかまぼこ。
野菜炒めにはピーマン、キャベツ、そしてかまぼこ。
更にそのままのかまぼこもある。刺身のつもりなのか、小皿にワサビ醤油が用意してある。
「全部にかまぼこが使ってあるね」
「まあ、かまぼこ好きだからな、俺」
「そんなこと初めて聞いたけど」
少し変わった彼の手料理。
これが伏線だったのだ。
◇
それからしばらく経って、私の誕生日がやってきた。彼と普段より少しオシャレなディナーを堪能して、帰りは並んで歩いて私のアパートを目指している。
明日は日曜日だから、今夜は二人きりで過ごす。
とても寒い夜だった。厚いコートに身を包み、吐く息は白く染まっている。
「やっぱり車で行けばよかった」
「だな。この時期、夜に外を歩くのはつらいな」
両手はコートのポケットに隠し、彼に寄りかかるようにして歩く。
露出している顔は、外気に晒されて冷たくなっている。
「お、自販機だ」
彼はそう言って、自販機に五百円玉を入れた。
「何が飲みたい?」
「んー、それじゃあココア」
「了解しました」
私はココア、彼はカフェオレを、近くの公園のベンチに座って飲んでいる。
その時、目の前にふわりふわりと白いものが舞った。
朝に天気予報で言っていた通り。
「雪だ」
彼のその言葉は、とても優しい響きだった。
…
「あの時も、雪が降ってたよな」
「……うん」
彼の呟きに、私もあの時のことを思い出していた。
それは私の十七歳の誕生日。
高校二年だった私達が、付き合い始めたあの日。
あの時も、雪が降っていた。
「あれから七年か」
「……うん」
そして彼は真剣な表情で私を見た。
「お前に、言いたいことがあるんだ」
…
「これを受け取ってほしい」
「うん。開けていいの?」
「もちろんだ」
彼から受け取った小さな箱。紙の包みを開くと、木箱が出てきた。
木箱はどうやら手作りのようで、その材料はどこかで見覚えがあるような。そういえば彼はこういう工作が好きだったな。
「これって……」
蓋を開けると、そこには小さな宝石が付いた指輪があった。
顔を上げて、彼と目が合う。
彼がいつも以上にかっこよく見えた。
「俺と、ずっと一緒にいてください」
「……は、はい」
私の声は震えて、頬に一筋の涙が流れた。
「そ、それと、これ」
そう言って彼が出したのは、一枚の板。彼の苗字が彫られている。
「えっと、それは表札?」
「そう。俺の手作り」
私はそこでようやく、木箱の材料が何であるのかがわかった。
「ああ、だからこの前はかまぼこ料理だったんだ」
その日は珍しくゴミを持ち帰ったから、不思議に思っていたんだよね。
雪が降る夜の彼と私