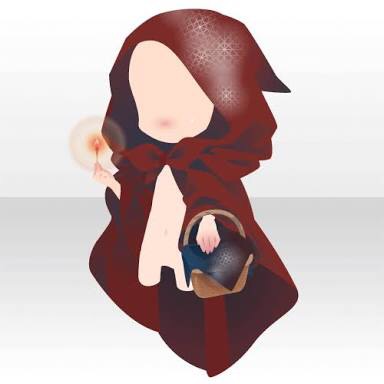
マッチが売れた少女
マッチ売りの少女は、商売がうまくいかず嘆き、マッチを捨てて夜の街で現実逃避をおこす。しかし一人の女の子と出会う事によって、少女は女の子の狂気に恐れながらも危険な好奇心が勝利し女の子の家へと足を延ばす事になる。意外な展開から少女のマッチは高価な値打ちで売れる事になるが…
マッチが売れた
「マッチ、マッチはいりませんか?」
雪がシャンシャンと降り、青白い街灯がぼうっと淡く光る。
街の中は人、人、人、しかし人が通り過ぎる雑音の中で小さな女の子の声は打ち消される。
そして通行人の一人である、人相の悪い男が「チッ」と舌打ちをし、邪魔そうに少女に雪を蹴りつけた。
硬い塩の様な雪が少女の顔にかかる。
それでも、少女はマッチを売り続けた。
「マッチ、マッチはいりませんか?」
が、結果は変わらず人は目の前には止まらない。
「あーーーーーーッ!もう、いいわよ!」
そう言い放つと少女は黒い空に向かって投げた。
当然、マッチは雪の間に潰されてパラパラ落ちてくる。
「あんのクソ親父、今時、マッチが売れるわけがないじゃ無い!」
そうぶつぶつと不貞腐れ、少女は糸がほつれたポケットの中に震える手を放り込んで、歩いた。
と、「ーーーッドッ!」
生暖かい空気にぶつかり、少女は尻を厚い雪の上に沈めた。
「いったい、わねー!」
決して目の前を見ないで歩いていなかった訳ではない、少女の身体よりも線が細い女の子が少女の目には入らなかっのだ。
「だ、だいじょうぶ?」
チリんとした声に目を向ける。
小さな女の子であった。
自分よりもひと回り小さい女の子が、足元まであるスカートの雪を払ってペコペコとお辞儀している。
「ごめんなさい、ごめんなさい」
透き通る白い肌に反して黒い髪が対比して輝いて見える。
少女は一瞬「大丈夫よ!あなたの方こそ怪我はない?」と口を反応させようとしたが、唇を噛んだ。
そう、少女は売れ筋が悪いマッチが頭の中で拭いきれてはなかったのだ。
そして少女は大声で赤い斑点に向かって指をさす。
「たっく!あんたの所為でマッチがバラバラに飛び散ったじゃないの!」
自ら捨てたマッチはコックリと首を下に伏せている。
「あ、あ、あ、ごめんなさい、い、いまから拾います」
小さな口をパクパクさせる女の子は直ぐにでもマッチを拾うとするが
「バッカねー、地面に落ちたマッチを人様に商品として出せる訳がないじゃない!」
「え、え、そんなぁ」
たじたじする女の子に少女は勢い良く叫ぶ。
「全部、弁償しなさい!」
その理不尽な音は残響し、急いで道を進む人の身体にも響き渡った。
「で、でも、わたし今お金をもっていないんです」
寒さなのか、それとも、恐いのか分からないが女の子は震えている。
「は?ふざけないでよ!!お金がないなら警察に連れて行くわよ!」
「そ、そんな、それはやめてください!お願いです!」
と慌てる女の子には身体には合わないバスケットを大事そうに持っている事に少女は今更ながらに気付いた。
「ふーん、そうね、お金がないなら、そのバスケットの中身で許してあげてもいいわよ」
少女は冷たく微笑み、バスケットを撫でた。
「そ、そ、それはこまります」
女の子の額からはゆっくりと汗が垂れる。
「困るで済む訳がないでしょー?」
女の子は必死になって口を開く。
「このバスケットは、おばあちゃんに届けにいくのです!!」
「君たち!」
少女、女の子、共に声のした方向に首が自然と動く。
見ると、二人の騒ぎに誰かが通報したのか、スラリと身長の高く偉そうな警察官が少女と女の子の後ろに立っていた。
警察官は目を細め、深く被っている濡れた帽子を親指でクイッと上げて質問する。
「今、少しばかりだが、ちょっといいかな?」
もしかして、私捕まるの?
少女はビクッと身体を振動させて、神経の中で電気が弾けて停止した。やがてしぼんだ肺はやがて膨らみ、穴の開いた舌は緊張しつつも柔らかく運動した。
「な、なんでしょう?いやはや、お疲れ様ですわ」
「うむ、実は君たち二人が口論し、道で騒いでいると言った連絡が入ってね」
警察官は二人を軽く見つめて話す
「署まで来てくれないかな?」
「そ、そんな事をいわれても、って、あなた少しくらいは何か言いなさいよ」
少女はそう言うと女の子に目を移す。
みると少女は女の子から違和感を感じた。
ギシ、ギシと石と石を研磨する様な音がするのだ。
とても動揺しているのか、黒く大きい瞳はギョロ、ギョロ、見えない空気の泡を追いかけている。また、白い乳歯の奥歯を噛み締め顎を動かしている。
歯ぎしりだった。
この光景に少女は街灯に映る、少女のボンヤリと落ちている影にも嫌悪感を感じた。
突然、女の子は丸い目ん玉をデメキンよりも開いて喋り出す。
「じゅん、じゅん、じゅん、じゅん、じゅ、じゅ、じゅ、じゅん、じゅんさだぁああ!!」
女の子は手に持っていた大きなバスケットから赤い頭巾を取り出して、勢い良く被り、冷たい空気を切り裂いて薄暗い路地裏に物凄いスピードで走り、走り進んだ。
その出来事に少女は口をポッカリ開き、警察官も理解できずに立っていたが、我に返り叫ぶ。
「お、おい!どうしたって言うのだ!」
少女も正気に戻り、警察官に早口で説明する。
「ははは!彼女は相当な人見知りなんです!!ほら、あれですよ、今流行りの思春期とかそんな感じなんです!」
なんとも適当な理由を警察官に投げつけ、少女は女の子の後を追う。後ろで警察官が呼び止める声は数秒で消え去り、辺りは一層、街灯に植え付けられたランプの光が眩しく感じ始めていた。
少女は真っ直ぐ歩く中、雪のジュウタンに立つ女の子をとらえた。
女の子には真上から淡い火が零され、赤い頭巾がとりわけ燃えて映っていた。
少女は凍える温度の中で駆け巡ったので体温は熱く、またその影響か脳みそも熱く溶けそうになっている。
少女は憤りを混ぜて声を発した。
「あなた!何、警察官から逃げてるのよ!」
少女はハァハァと息を切らし、文句を言った。
女の子はニコリと笑って返答する。
「ごめんなさい、わたし、とってもじゅんさが苦手なのです」
「あなたがいきなり走って逃げるから、とってもビックリしたじゃない!」
それにしても、女の子は汗ひとつ垂れていない、いや、そもそも髪さえも乱れてはいない。
と、少女は女の子の頭に気付いた。
「あなた、凄い原色の赤色を被ってるわね」
女の子は少し悲しそうな表情を浮かべる。
「ごめんなさい、最初から被っとけば良かったですね、この頭巾」
「おかぁさんの言う事をちゃんと聴いてればなぁー」
女の子はため息を吐く
「あぁー、顔を見られたかもしれない」
と、ジロリと目玉だけを移し、少女の顔を見てニッコリと微笑む。
その視線に少女も背中から大きな玉の汗が伝わるのが分かる。
と、女の子は、奥の見えない路地裏をスタスタと歩き始め、少女もその後を追いかけてしまう。
少女は単刀直入に質問した。
「あなた、何かやましい事でもしているの?」
その質問に対して女の子は答える。
「違いますよ、わたしは、おかぁさんにオオカミさんには、気を付けろって教えられているんです」
少女はもちろん、その答えに疑問を感じる。
そこで、質問を別の物に変えた。
「その、バスケット、おばあさんに届けるって言ってたけど、何が入ってるわけ?」
「そうですね、お姉さんには助けて貰ったので、教えてあげても良いですよ」
少女は決して助けた訳ではないと思いながら、黙って女の子の言葉に耳を傾ける。
女の子は優しく笑う。
「お姉さんのお仕事ってなんです?」
と、急に尋ねる。
少女は適当に答える。
「何それ」
「一応、仕事っていう、仕事は別にやってはいないけど」
弾む声が少女の鼓膜を叩いた。
「爆弾」
「は?」
少女は女の子の言った単語におまわず単発の発音をした。
「実はわたし、こうみえても、爆弾を作る事を家業でやってるんですよ!!」
天使の様に微笑む女の子、それに加え凛々と輝く目からは到底考えられない状況が今まさに、そこには存在した。
「爆弾」
少女は今でも面白くない冗談を言っていると考えていた。
「嘘をつかないでよ、そんな事があるわけないでしょ」
まるで、その言葉を待っていましたと言わんばかりに、女の子は頬っぺたをツルツル光らせて喋る。
「では、これを見てください!!」
そう言って少女はバスケットから茶色い粘土の様な物を取り出す。
「これは建築物など、限定された対象を爆破するために造られたいわゆる、プラスチック爆弾です!!」
「は?はぁあ!!」
女の子は少女の反応に関係なく話し続ける。
「あ、ごめんなさい説明不足ですよね」
「このプラスチック爆弾は従来の性能の約6倍で軽量に成功しました。見て下さい!!ここの赤いボタンとダイヤルを回すと人の熱を感知して…」
少女は目の前で楽しそうにペラペラ語る女の子に恐怖を感じ始めていた。
「いや、いや、いや、まって頂戴!何を言っているの?」
「そうですよね!!そんな事より、値段ですよね!」
「今なら、180000デロンでー」
「買わないわよ!って、高すぎるわ!」
「確かに高いと思うかも知れません、しかし、この性能にしてこの値段は…」
少女は本気で思った、この女の子はおかしいと
「あたしはそんなの、欲しくないわ!!」
「なら、これならどうですか?」
そう言うと今度は手紙の様な封筒を出してきた。
「いわゆるこれは、手紙を貰った開封者が開くと、ドカンッ!!」
「と、爆破する設計です!これもですね、従来のものより10倍薄、しかも曲げても折れないにくく、また!金属の様な感触がまったくしないのです。それに加えて、探知機にも反応しないと言ったーー」
少女は青ざめていく血液を自から感じながら、つまった唾を吐く。
「あ、あなたは、一体何者なの…」
女の子は笑みを見せ微笑む。
「何者って、ただ家業が爆弾専門店なだけの人です」
と、いつの間にか暖かい光が漏れる、木造の家屋の玄関の前に立っていた。
「どうぞ、どうぞ、おばぁちゃんの家です。お茶でも飲んで行って下さい」
女の子は青銅のノブを回し、木製の扉を開けた。
中からは橙色の眩しい色が少女たちを照らし、それと共に女の子は縮こんでいる少女の冷たい手をゆっくり握る。
少女は断りたくても、断れない、見えない恐怖と一緒に進んだ。
狭い、キシ、キシとかすれた廊下を歩く。
また、木製の建具を女の子は引いて、ドアをあけた。微かに甘いケーキの匂いと火薬の匂いが少女の鼻腔を触る。部屋は思ったりよりも広く、隅にある暖炉にはマキが燃えていたらしく、白い煙だけがモクモクと上がっている。
「あの、どうぞ、この椅子に座っていて下さい」
革が張られ、焼きたてのパンの様な光沢感がある椅子を引きながら言った。
少女は黙って浅く座る。
そして目をテーブルに移す。
テーブルの真ん中には白いケーキが寂しくぽつんとあった。
アリの行進を待っている。
少女は甘い香りに胃が膨らんだ。
「ごめんなさい、おばぁちゃんは寝ている様です。なので、わたしの取っておきの爆弾を見せたいと思います」
と、女の子は大きな木箱をテーブルの上にドカンと置いた。
「何なの?何なの、それ?」
少女は不安の念を感じ、その重そうな箱を見た。
「これは、わたしの一番のオススメで、わたしの力作なんです」
女の子は誇らしげに言葉を発した後。
その女の子は華奢な身体にありえない力で、重装な鋼の蓋をゆっくりと持ち上げた。
「あぁ」少女は小さく言葉が漏れた。
中にはキラキラとしたガラスの様な器で造られおり、銀や銅、光る石で生ける花々を彫刻していた。まさに一つの作品であった。少女はその美しさに見惚れてしまい、隣にいる赤い頭巾を被った女の子に聞いてしまう。
「こんなに綺麗な物も爆弾っていうの!」
「そうです!これは見ての通り、ガラス細工で出来ていますが、オルゴールでもあるんです!!」
「オルゴール?」
「そうです、オルゴールなのです」
赤い頭巾から飛び出た髪の毛が跳ねる。
「一つの音色を奏でた後に爆発する、まさに最後の最後に強大な一点の音色、これはステキではないですか?」
女の子のビー玉の様なクリクリした目は、少女をつかむ。が、少女は視線をそらし唇を犬歯で噛み。
少女は批判した。
「そんなもの、ステキでもなんでもないわ」
「どうして?」
「あなたの言う、音色は心を打たないからよ」
女の子は疑問に眉をひそめる。
「それなないと思います。聞く人々を熟したトマトみたいに種と水分を撒き散らして、炎天下の熱と氷の濁流の涙の粒が心を震わすんです!」
「それは、きっと最高のロマンチックがあると思います」
女の子の無邪気な笑顔と反して、少女は後ずさりをした。
その瞬間である。
バタン!!
「やっと、見つけたぞ!爆弾魔!!」
と、さっきの警察官がおばぁちゃんの部屋から飛び出して来た。
「赤い頭巾、怪しいと思ったのだ」
「君たちについて来て、先に潜り込み、お前の祖母は逮捕したぞ!さぁ、観念しろ!お前も逮捕だ!」
意気揚々とした警察官は赤い頭巾を被った少女の前に仁王立ちをして、勝利の笑みを浮かべた。
バタン!!
今度は玄関の方から力強く扉が開いた。
「よう!今日入手したっていう、新商品を買いに来たぜ」
明らかに人相の悪い男が入ってきた。
「な、なんだ、貴様!」
警察官は驚いている。
人相の悪い男も驚き声をあげる。
「な、なに!警察官がいるだと!約束を破ったな!」
人相の悪い男は女の子をギロリと睨みつける。
女の子はアワアワと慌てるが
「大変な事になりました。そうだ!二人共、降参しなければ今ここで、この爆弾を爆発させますよ!」
女の子は何処から取り出したか分からないが、黒い玉の様な爆弾を右手に持って見せつける。
しかし警察官はニヤリと笑う。
「フハハ!そう思って、そこらじゅうにある着火する物と火元は全て捨ててあるぞ!」
その一言に女の子と、人相の悪い男はサッと青ざめる。
「堪忍したまえ!」
警察官は人相の悪い男を縛ろうとする。
ところが、人相の悪い男は何かに気付いた様に瞳孔が開いた。
「お、お前え!」
人相の悪い男は、少女に向かって叫ぶ。
「お前、そう言えば、さっき道でマッチを売っていた少女だな?」
少女はそう聞かれて、ただ「売ってましたけど」と返事をした。
その返事を聞くと人相の悪い男は明るい表情になり少女に懇願した。
「そのマッチ、俺に売ってくれ!」
少女はこの状況からの言葉が理解できずにいたが、警察官は何かに気付いたようで、少女に大声で話しかける。
「おい!絶対にマッチを渡すな!この男は、爆弾に火を着けるつもりだぞ!」
警察官の慌てる声を遮り人相の悪い男は少女に自分の声を叩きつけた。
「そのマッチ、10000デロンで買うぞ!」
「な、なんですって!!」
少女はその価格に驚いた、なぜなら10000デロンという値段は少女の5年の年収に相当したからだ。
「どうだ?売る気になったか、ならマッチを渡して貰おうか」
と、甲高い声が響き渡った。
「まって!そのマッチ、私なら20000デロンで買います!」
「何だと!」
「ふざけるな!」
二人の男の声が部屋でこだまする。
赤い頭巾を被った女の子は少女に手を出しマッチを受け取ろうと仕草をした。
「まてまて、なら私は25000デロン出すぞ!」
警察官が手を上げて話しかける。
「俺が先に言ったんだぞ!分かった、30000デロン、俺はこれを出す!」
人相の悪い男が両手を広げて叫ぶ。
人相の悪い男は勝利を誇った顔つきになった。
しかし
赤い頭巾を被り、ニコニコと微笑む女の子は蜜の様な声を唇から振動させた。
「お姉さん、わたしは10000000デロンを差し上げます」
少女は軽く小さな箱を握り締めた。
ボロボロで今にも破れそうな薄いポケットの中に入った、一本の首の長いマッチが、まさかこんな高価な値段で売れるとは。
これで、お父さんに怒られなくてすむ
マッチが売れた少女
少女と女の子の後半のやりとりを上手く描写するのは難しいです。


