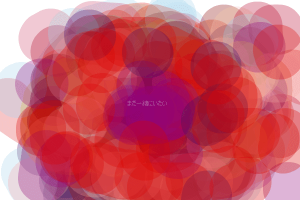ticket -手に入れた空虚-
低いステージと隙間の空いたフロアであの人はギターをかき鳴らす。それを恍惚の表情で見つめるのはわたし。
あの人はわたしを妹のように大切な存在だと言う。それがどれほど残酷なことか、わたし以外誰も知らない。
あの人と一緒にいるために、わたしは好きでもない「あなた」と夜を重ねていく。
「あの人」が「あなた」になった日
アボカド色のギターから鳴るのはいつも劈くような低い音。擬音にするなら、ゴリゴリ。
両手を広げたり、首を左右に振るあなたのまねをしたり、それもほどほどにいつのまにか深くなった夜。
泥酔した友人が蹲る右のトイレ、自分の酔いをおさえて介抱を尽くしているうちに0時も20分を過ぎた。もう帰る術がないのは知っていた。
「・・・酔っぱらちゃったかな、うまく歩けない、それに、帰りたくない。」
硬いコートに顔をうずめたまま、もごもごと発した言葉。あなたはきっと困った顔をしていた。
だめだ、とか
大事だから、とか
そんな言葉が何度も聞こえて、それでも顔を上げないわたしは、まるで駄々をこねる子どものようで。
このまま一緒にいたら、もたないんだ。
そう言ったのを最後に、行き交う通勤者たちを無視して唇をあわせたのは朝5時をすぎた頃だった。
手を引かれ入ったコンビニ、店員と談笑しながらコーヒーを買ったあなたはもう1度わたしの手を握って馴染みの階段を下りてゆく。
重い扉を開け、真っ暗の中手探りでたどり着いたそこは、一言でいうと『良い段差』
少しずつ身に纏うものを失ったふたりは空がオレンジに染まるのと変わらない速度で繋がってゆく。
あなたの低い声が耳の真横でいつまでも聞こえ、泣きながら、鳴きながら、圧に耐えるために握りしめたわたしの手を、あなたが優しく掴んだ。
なかったことに、しようか ?
疲れきったあなたの頭が肩の上で揺れたのは、わたしが必死に首を横に振るせいだった。
指の一本ずつを絡ませたあなたの左手とわたしの右手は確かに触れているのに、胸の奥は冷えきって、まるでひとりぼっちの冬の夜のようで、口を開く体力さえ使い切ってしまったわたしは、あなたの
もう帰ろうか の低い声にただ頷くしかなかった。
あなたが赤い自転車を押して、わたしがその横を歩く。それからまもなくふたりは駅前で立ち止まる。
改札の前であなたは、
じゃあまた、今日。と浅い笑みを浮かべた。
「寝坊しないようにね。」
わたしは振り返らないように改札を通り、電車に乗り込んだ。
あなただけを見つめ、あなたの声だけを聞き、あなたの言葉を信じたわたしがあなたと繋がることによって掴んだのはからっぽで意味の無いものだった。
歩く度に痛む両脚を無理やり交互に動かし、虚しさで広がった心の穴を摩るようにゆっくりと息をした。
梅の花がきれいに咲き誇る頃だった。
昼過ぎに目覚めたわたしはまた、あなたに会いに行く。
愛は言葉でも体でもなかった。
ticket -手に入れた空虚-