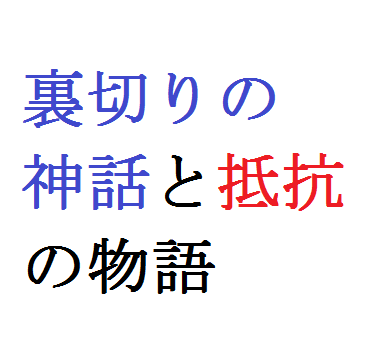
裏切りの神話と抵抗の物語 後編
「裏切りの神話と抵抗の物語 中編」の続編です。
第四章 新たなる志と神
静かな明朝、冷ややかな風。タレファルナ山脈は真っ白な絹を麓まで纏って居た。イグリュータ川は変わらず穏やかに流れて行く。何ら変わらない自然。変わったのは人間の心。
***
あの日から既に二年という月日が流れていた。地獄の様だった世界は急速に復興を遂げ、元ラプタス国は今と成ってはベスタルク一の都市へと様変わりして居た。神々の恵みを享受する豊かな土地は瞬く間に賑わい、今はベスタルクと三国に開かれて居る。彼等は先の聖戦等忘れて仕舞ったかの様に至福の時を活きていた。其処にラプタス人の姿は無かった。
***
繁栄を遂げた旧ラプタス国の郊外にベスタルクが建設した監獄が在った。其処には凶悪犯罪の罪人や聖戦の捕虜、戦犯が収容されており、町からは隔離されて居た。
其の監獄にオルヴァスは戦争犯罪人として収監されて居た。バルタで指揮を執ったシャレールを収容する事が叶わずベスタルク側がオルヴァスを指揮官として捕縛したのだ。バルタでの激戦は全て彼の先導が原因とされ、多くの罪を着せられた。極悪非道な犯罪者として扱われ、死罪が言い渡されて居た。彼は独り牢の中で、処刑を待つ身と成って仕舞った。
「ほら、狡猾なラプタス人め、出ろ。今日は貴様の処刑が取り行われるぞ。」
闇に包まれた薄汚い牢には、見る影も無く変わり果てたオルヴァスが座り込んで居た。髪は無造作に伸び、ろくに食事も与えられて居ない為かすっかり痩せ細り、かつて華の騎士団で色男の名を賜って居たとは思えない変わり様であった。
「……此の日をどれだけ待ち侘びたか……。人殺しめ、民衆の面前に其の無様な姿をくれて遣るわ。」
ベスタルクの牢番はオルヴァスをそう罵った。しかしオルヴァスは何も言わない。俯いたままで立ち上がろうともしない其の姿に、牢番は苛立たし気に彼に近づき、脇腹に強く蹴りを入れる。
「早く立て、死に損ないがっ。…漸く貴様も死ねるのだ…。嬉しいだろう?仲間を失っても死ねず、捕虜達が殺されても死ねず……。貴様だけが生き残った。此の世界の恨みを一身に浴びて…。」
「……。」
オルヴァスは尚も黙って居た。唯、少し上げた顔と髪の隙から覗き込んだ眼は絶望感に満ちており、死んで居る様に冷たかった。其れは彼の全てを映し出して居る様で、溢れんばかりの悔いや自責、恨みや怒りが混ざり合い、激しく揺らいで居た。今にも消えそうな命の灯が其処には在った。
「行くぞ…大罪人。着いて来い。」
オルヴァスは黙って立ち上がり、生気無く牢番の後に続いた。今から自分は死ぬのだ。しかし、ちっとも嬉しくは無かった。あの世へ行ったとしても自分には仲間達に見せる顔が無い。無様に生き残った男を見て、仲間達は嘲笑するだろう。とは言え此の世に留まる故も無い。何せ自分は世界の恨みを背負って居る。自分が処刑されれば、幸せになる者や救われる者も居るのだ。生きる価値も無いのだから。
今更色々な考えを巡らせる。何時、何処で道を違えて仕舞ったのだろうか。あの日、あの時、騎士団入隊していなければ此の様な事には成らなかったのだろうか。
途方もない事を思案しながら、処刑台へと連れて行かれる。何だか騒がしい。如何やら処刑は公開で取り行われる様だ。致し方あるまい。多大な犠牲を出したあの聖戦の戦犯が処刑されるのだ、民衆達は公開処刑でなくとも必ず集うだろう。
「隠微なラプタス人め……死んで恥を知れ。」
「其の名に陶酔し、傲慢にも神を独占しよう等、卑怯な真似をするからだ。」
「最強の名も地に落ちたな……敗軍の将よ、神の賊よ、死んで我等に詫びたまえ。」
屈辱的であった。此れほど迄に罵声を浴びせられるとは思いもしなかった。
後ろ手に縛られたオルヴァスは、其の鋭い目を乱れた髪で隠す様にして民衆を見据えた。皆、怒り憎しんで居た。其の場に居る誰もが自分の死を待ち望んで止まないのだ、と感じた。
しかし恐れは感じなかった。今更、怖れる事等何もない。もう、何も失う事等出来ない程に全てを失ったのだから。
そう思うと狂気の民衆が放つ怒号も、処刑人の喧騒も、何も気にならなくなった。久しく穏やかな心で、青く透き通る空を仰ぐ。雲が解けた様な空は人間の醜い争い等、気にも留めず風という名の大河を穏やかに行く。其の姿は正に自由其の物で、終ぞ自分には縁が無かったと悲しくすら成って来る。
(…此れで全てが終わる……。)
オルヴァスは瞳を閉じて静かに覚悟を決めた。
民衆が処刑人を固唾を飲んで見守る中、遠方まで続く人だかりの中から荒ぶる様な叫びが聞こえて来た。
其の場の者は皆、騒ぎの方を何事かと見遣った。其処には遠方から一人の男が馬に乗り此方へ向かう姿が在った。何かを必死に叫んでおり、人だかり等蹴散らす様な怒涛の勢いで迫ってくる男の妙な気迫に民衆達は呆気に取られた。
やがて其の男の叫びが処刑場まで聞こえて来ると、オルヴァスは弾かれた様に顔を上げた。
「……オルヴァスっ。」
彼には自分の名を呼ぶ声に聞こえた。もう数年呼ばれて居ない其の名等、此の場に知る者等居ない筈であるが、何だか嬉しかった。懐かしくて、途轍もなく悲しかった。
気のせいに違いない。此れは神が最期に聴かせた幻。唯、神に弄ばれたのだろう。
「……オルヴァスっ、オルヴァス、未だ死ぬな。」
其の声は確かにそう言った。次は幻等では無い。強い叫びが刑場に響き渡った。
思わず目を凝らして見ると、其処には褐色の髪を振り乱した男が一騎で民衆を突き飛ばして行く姿が在った。気のせいではない。男は確かにアジィール其の人であった。
「オルヴァス、良く此処まで生き延びたな。……もう良い、良く頑張った、帰ろう。」
刑場に滑り込んだアジィールはオルヴァスに手を差し延べた。あまりにも突然の出来事に処刑人も硬直しきって居た。
「…アジィールさん……如何して此処に……。」
「そんな事は後だ。俺の手を取れ、此処から逃げるぞ。」
そう言ってアジィールは拘束されたオルヴァスを馬に乗せ、再び民衆達を掻き分ける様に走り抜ける。
漸く状況を飲み込んだ民衆は怒りの声を上げながら、大罪人を逃すまいと必死の形相で追って来る。
「やっと見付けたんだ、そう簡単に殺されて堪るかよ。」
吐き捨ててアジィールは馬に強く鞭を入れる。すると付き纏っていた民衆達を振り払い、やがて開けた草原に出た。
オルヴァスは久々に風に当たり正気を取り戻したのか、先程よりも覇気のある表情で尋ねた。
「アジィールさん、如何して此処に?」
「町で戦争犯罪人が処刑される、と言う噂を聞き付けてな。バルタに出兵して居た戦犯と聞いてもしかしてと思って此処まで来てみたのさ。そうしたら此れだよ…。」
アジィールは得意げに笑った。オルヴァスは未だに納得の行かない表情を浮かべて居た。
「とは言っても、オルヴァスが生きててくれて本当に良かったよ……。」
アジィールが影のある横顔を向けて言った。彼もまた聖戦で心を疲弊させたのであろう。オルヴァスは其の表情から何となく様々なものを察した。
「……そうだ、君に伝えて置かねばならん事が有る。……聖戦の事は勿論だが、メルヴァントの事だ。」
オルヴァスは大きく目を見開いた。懐かしい友の名に郷愁すら感じる。
「彼は……生きて居る。俺達は今、メルヴァントが隠れ住んで居る小屋に向かって居るんだが……。」
オルヴァスは歓喜し、涙を流した。友が生きて居る、其の事実が何とも嬉しかった。監獄の中で考えていたのはメルヴァントが生きているか否かばかり。彼にだけは生きて居て欲しい、何度も神に祈った。自分が守り切れなかった国で親友を失ったのなら、悔やんでも悔やみ切れなかった。ずっと彼を案じていたのだ。
其れが今アジィールは、確かに彼は生きて居る、と言った。此れ程嬉しい事は有るだろうか。
「本当ですか。メルヴァントは生きて居るのですね。」
「あぁ。確かに生きて居るよ。」
オルヴァスは感慨無量で大きく息を吐いた。良かった、唯々良かったの一言に尽きる。彼が生きて居る、其れだけでオルヴァスは救われた様に思えた。
しかしオルヴァスの喜びに反してアジィールは複雑そうに笑った。オルヴァスに憐れむ様な目を向けて、
「唯、メルヴァントは先の聖戦で心身共にかなり疲労して仕舞ってな……。今は独りで悪魔崇拝に走っているよ……。でも、中身は何ら変わらないメルヴァントだ、如何か会っても目を反らさないで欲しい。」
懇願した。共に聖戦を戦ったアジィールであるからこそ分かるメルヴァントの心の傷の深さ、悲しみ、憎しみ。生き残って仕舞った事への後悔の念。彼なりに苦労して、藻搔いて二年と言う月日を過ごして来た事を分かって遣って欲しかったのだ。
メルヴァントにとってもアジィールにとっても、無論オルヴァスにとっても二年と言う月日は長すぎた。時の流れは戦乱の悲しみを癒す事無く、唯々無情に流れて行った。
「…例えどんなメルヴァントであっても私の大切な友、と言う事には変わり在りません。其れよりも生きて居てくれた事が嬉しい……。」
オルヴァスは涙が溢れそうになるのを堪えて笑った。久々に笑うせいか頬の筋肉の動きが妙にぎこちなく、違和感を感じてしまった。
***
アジィールは馬を走らせながら、オルヴァスに聖戦時の首都シャルティネの話をした。
バルタを破ったベスタルクが攻め行ったシャルティネの惨状は凄まじいものであった。ラプタス騎士団は壊滅し、半数以上が無残にも殺された。町は死に絶え、とても栄えていた都とは思えぬ酷い状況だったそうだ。
「……ヴァイゼン公は…如何されたのですか。」
アジィールは瞳を閉じて首を横に振った。
「国を混乱に陥れた責任を取って戦地で自刃したよ……。あの方は何も悪くは無かった。最後まで俺達に生きろ、と仰ってくれた。」
オルヴァスは初めてヴァイゼン公に出会った時の事を思い出して居た。公爵は父親の様に寛大で温かく、威厳の有る人だった。そんな公爵を彼は心から尊敬して居た。あの人の様な騎士に成りたい、憧れていたのはオルヴァスだけでは無いだろう。皆、公爵と言う人が好きだった。自害したとは思えない程、公爵の温もりはオルヴァスの心の中に溢れていた。
「皆、死んだよ。歴戦の猛者や若い騎士達も皆。生き残った奴らもな、差別と偏見に耐え兼ねて死んで仕舞ったよ……。もう、此の世界にラプタス人は殆ど居ない。周りはベスタルクか三国連合の奴等ばかりで、俺達の居場所なんて何処にも無いさ。」
アジィールは嘆く様に言った。其の言葉が生き残った彼の苦しみの様で何とも辛かった。数々の言われも無い罪を着せられ、罵られ、蔑まれた者の実感の籠った嘆きであった。
「……アジィールさんは、今は一体如何されて居るのですか。」
オルヴァスが遠慮がちに尋ねた。
「…此の世界ではラプタスの人間が生きて行く場所なんて無いからな……。俺は生き残ったラプタスの奴をこうして探して居るんだ。一人でも同郷の奴が生きててくれたら、嬉しいだろ。」
そう言うアジィールの背は悲しかった。何時でも自分達を包み込んでくれた太陽の様な明るさは無く、孤独な男の悲壮感が其処には在った。
「…でも本当は其れだけじゃない。……シャレールを探して居るんだ。」
其の一言にオルヴァスは胸を抉られた様な思いがした。
「ミグルで俺達は誓い合ったんだ。絶対に死んだりはしない、って。彼奴は普段は冷たいけどさ、約束は破ったりしないんだ。正直で生真面目な男だからさ、何年経っても何時かは帰って来てくれる、って俺は信じてる。」
オルヴァスは益々辛くなった。アジィールはシャレールが生きて居ると信じて居る。しかし、実際はそうではない。如何しても事実を言えなかった。アジィールが余りにも強く信じ込んで居るから。裏切るような事は言いたくは無かった。だが隠す事も出来そうにも無い。こんなにも純粋にシャレールを信じるアジィールが辛かった。嘘等、到底吐けなかった。
「あの、アジィールさん……。」
アジィールの実直さにシャレールの死を隠す自分の醜い心が映し出されそうで、耐えられなかった。だから正直に話そうと決意したのだ。
しかし其の決意に反して、アジィールはオルヴァスの言葉を遮る様に話を被せた。
「オルヴァス、言うな……。信じさせてくれ、彼奴の事を。こんなどうしようもない絶望感の中で唯一の希望なんだ。……彼奴を信じる事を止めて仕舞ったら、俺にはもう生きる意味等無く成って仕舞う。だから、良いんだ。俺はシャレールを探す。もし死んで居たとしても、彼奴の屍を見るまでは、ずっと探し続ける……。其れが、俺が彼奴にして遣れる事なんだ。」
アジィールは作り笑いを浮かべた。其れはオルヴァスにも嘘偽りだと分かって仕舞う程の不器用な表情で、悲しくなった。あれ程、自分達を照らしてくれた笑顔を奪ったのは誰だろう。
***
広大な草原を駆け抜けると閑静な木々の茂みの中、古ぼけた小屋が一軒在った。風雨を凌げる程度の貧相な小屋であったが、此処にメルヴァントは居ると言う。
「俺は此処で別れよう。オルヴァスはメルヴァントと二人で積もる話もあるだろう、二人でゆっくり語り合うと良い。」
アジィールが目を細めて笑った。後輩の念願の対面を見届けて遣りたいが、そうすれば別れ難く成って仕舞うだろう。其れではいけない。自分がシャレールを見つけて遣らねば一体誰が見つけると言うのだろうか。
「…でも、アジィールさんは如何するのですか。」
「さっきも言っただろう。俺はシャレールを探しに行く。だから御前達とは此処で御別れだ。」
「そんな……。待って下さい。私は貴方に未だ何の恩返しも出来て居ない…。」
颯爽と外套を翻すアジィールの背中にオルヴァスは叫んだ。
しかしアジィールは振り返る事無く、軽やかに笑って、
「何を言ってるんだ。御前達が生きててくれただけで俺には十分だよ。……オルヴァス、其の命を大切にしろよ。」
何時かラプタスの者が幸せに暮らせる様に成ったなら、其の時又会おう。
そんな思いを込めてアジィールは告げた。後輩の悲しむ顔が目に浮かぶ様であったが、オルヴァスに必要なのは自分では無い。無論、メルヴァントにとってもだ。
オルヴァスはアジィールの大きな背中を唯呆然と見送るしか無かった。もっとアジィールと過ごしたかった。勿論メルヴァントとシャレールも共に。聖戦前の穏やかな日々、あの頃が思い出されて何とも懐かしかった。毎日が笑いに満ちて居て、楽しかった。もしあの戦乱が無ければ、今も昔も変わらず四人で笑って居たのだろうか。
必然の様に感じられる出会いと別れの中で、翻弄される自分の無力さに絶望すら感じられた。
オルヴァスは気を取り直して小屋に向き直った。そっと近づき、中の気配を探る。
「……メルヴァント…。」
呟く様に名を呼んでみる。しかし何の反応も無い。其れが返って良かったのかオルヴァスは大きな声で友の名を呼んだ。
小屋の中から何やら物音がする。
「……アジィールさんですか、今日は全く何処をほっつき歩いて来たのです?」
其れは確かに友の声であった。呆れた様な溜め息交じりの声が小屋の中から聞こえる。
何やら呟きながら小屋の壊れかかった扉を開くメルヴァント。其の瞳に映ったのはアジィールではなかった。しかし考えなくても目の前の男が誰なのかは直ぐに分かった。
乱れた髪、薄汚れた身体。傷だらけの四肢は其れまでの苦労を物語って居るかの様に酷く、無様に痩せ細った男。だが髪は長くとも変わらず綺麗な赤毛で、綺羅とした濃緑の瞳は彼以外には有るまい。
「……オルヴァス。」
久しい再会にメルヴァントの声は、手は震えた。まさか生きて居るとは思っても居なかった。あれから二年もの時が立って居たのだから。
「メルヴァント…生きて居てくれて、有難う……。」
二人は邂逅の喜びに思わず抱き合った。其の手に、身体に、肌に生命の温もりを感じる。生きて居る事を改めて実感させられる様で心が妙に休まった。
「…オルヴァス……。終ぞ帰って来てくれなかった、と思って居た。…良かった。あれが最後の別れに成ら無くて…本当に良かった。」
メルヴァントは涙を流した。オルヴァスが自分の前に現れる頃はもう二度と無い、と思って居たのだ。そう心に決め、生きて行こうと決意した彼の悲しみや悔しさは一体誰が分かるだろうか。
メルヴァントとオルヴァスは互いをじっくりと見合った。二年の月日は二人の様相こそ変えて仕舞って居たが、互いの目に映る友としての念情だけは揺らぐ事無く、其処に在った。
オルヴァスの姿も確かに変わって居たが、メルヴァントはオルヴァスの想像を絶する変貌ぶりであった。美しく、流れる様な金髪は相変わらずであるが、白い両頬には漆黒の紋様が描かれて居る。規則的に並び描かれた其れは一種の不気味さを醸し出して居た。肌の白い肉付きが良かった右腕は義手に、身体を覆う外套は底無しの闇の様に吸い込まれそうな黒色をして居た。彼が纏う雰囲気は全体的に妖艶かつ不気味で、メルヴァントと言う人柄を知らなければ何とも近寄り難い、そんな姿に成って居た。
(此れがアジィールさんが言って居た、悪魔崇拝か……。)
「オルヴァス、こんな所では何だから中へ。狭いけれど、二人位だと返って丁度良いかも知れない。」
オルヴァスは、メルヴァントに招かれる様に狭い小屋の中に足を踏み入れる。中は深夜の様に暗かった。目を凝らして見ると如何やら壁一面に黒い布が張り巡らされて居る様で、外の光の一切は遮断されて居た。唯一、室内を照らすのは弱々しい燭台の光。無造作に置かれた寝台には見知らぬ言葉で書かれた呪符の様なものが散乱している。
オルヴァスは時が来た時に其れ等の一切に触れる事にした。
「……懐かしいな。二年も会って居ないと、いざ何か話そうと思っても中々…何から話始めたら良いのか分から無いものだな。」
メルヴァントが俯きがちに言った。二人は向き合いながらも何だかぎこちなかった。
「…オルヴァスは一体今まで如何して居た?二年も姿を見せなかったから、私はもう……。」
「ベスタルクの監獄に収監されて居た。聖戦の首謀者として処刑される所を今日、アジィールさんに助けて貰ったのだよ。」
「そうか…。二年もずっと監獄の中だったのだな。……私はシャルティネでラプタスが敗戦を喫して後、アジィールさんと共に戦場を離れた。仲間は皆死んで仕舞って、生き残る事も辛かったが、ベスタルクの捕虜に成る事だけは何としも避けたかった。……奴らは、自国の者以外を人だとは思って居ないからな。」
メルヴァントとオルヴァスは凄まじき聖戦を語り合った。互いに違う戦場で戦って居た為、あの日国内で何が起こって居たのか興味深かった。唯、二人共決してあの日の傷は癒える事は無かった。話して楽になるものでも無い。地獄で見た光景は、其れは其れは彼等の若き心に鮮烈に焼き付いて、離れる事はしない。未来永劫背負って行かねばならない責務の様な苦しみや憎しみ、怒りの重荷であった。
メルヴァントが戦場で見たものはアジィールが見たものとは又違い、酷く凄まじかった。
「どれだけの月日が流れてもあの日の光景を忘れる事は無いよ。…今でさえ夢に見るのだから。……オルヴァス、シャルティネにはあの日神が消えた。君が居なくて良かったと思う程、酷かったのだよ。言葉ではとても言い尽くせないけれど……。私はあの日、沢山の命が失われていくのを見た。中には私の父や兄達が命を落とす姿もあった……。気が狂うようだったよ。」
メルヴァントは遠くを見つめる様な目をして言った。青く美しい瞳に暗雲の影が差す。
「私とて、メルヴァントにあの日のバルタは見せられない。女性達が嬲る様に殺される……あれ程趣味の悪い、薄気味悪いものは見るべきでは無いよ。ベスタルクは本当に冷酷無比だった。バルタの男達も、女子供から老人まで、構わず殺された。何の罪も無い者達が、一瞬にして有象無象の屍に成った。」
如何して人間と言うものは此の様な残酷な事が成せるのであろうか。
「メルヴァント……私は君に言わなくてはならない事がある。」
オルヴァスが意を決して切り出した。メルヴァントはオルヴァスの唐突な言葉に目を見開いたが、直ぐに何時もの穏やかな表情に戻って、耳を傾けた。
「バルタで私は…シャルティネの貴婦人達を助ける事が出来なかった。騎士は女性を守るべき立場であるにも拘らず、私は……出来なかった。其の中に、アズリータ嬢も居た。私はあの人が死んで逝く姿を前に何も出来なかったのだ。唯、怒りに任せて敵を斬る事位で、ろくにアズリータさんを救う事なんて……。」
メルヴァントは衝撃を受ける様子も無く、淡々として居た。一方のオルヴァスは耐え兼ねて、涙を流しながら続けた。
「……其れだけではない。私はシャレールさんを見殺しにして仕舞った。…シャレールさんは私を助ける為に一人で戦場に残って……其れなのに私は…私は、何の感謝の言葉も言えず、シャレールさんが死んで逝くのを無様にも見ている事しか出来なかった。……挙句の果てには助けに来た下さったアジィールさんにさえシャレールさんの事を話せなかった。……私はあの人達から騎士たる者として学んだ事の一つも成せなかった……。」
オルヴァスの悲しみがメルヴァントの心に沁み込んで来る様であった。激しく泣き叫ぶオルヴァスにメルヴァントは背を撫でながら、
「…いいや、君は何も悪くはないさ。辛かっただろう、二年も独りで抱えて来たのだな…。」
優しく言った。傷つき合った者同士が傷を舐めあう様な妙な心地良さ。しかしオルヴァスは首を横に振りながら否定する。
「……私は騎士として何も成せなかった。自分の郷国の惨事に戸惑ってばかりで、何も……何も出来なかったのだ。……私がアズリータ嬢とシャレールさんを殺したのだ。」
「其れは違う。君は自分を責める必要なんてない。悪いのは神々だ。」
メルヴァントは七種神の信者とは思えぬような一言を発した。オルヴァスは驚いて顔上げ、メルヴァントをじっと見遣る。
「……神々が、悪い…?」
信じられないとでも言いたげな表情であった。敬虔な信者らしからぬ神を冒涜する様な言葉にオルヴァスは終始、驚きを隠せなかった。事も在ろうに貴族社会で神々に忠誠を誓って来たメルヴァントらしくは無かった。
「アジィールさんには物凄く怒られて仕舞ったよ。ラプタス人は誰よりも何よりも神に誠実で、敬虔でなければならない、と。だけれど、私は聖戦から自らが其れまで信じて来た神を捨てたのだよ。私は知って仕舞ったのだ。どれだけ神々に対する信仰心が強くとも、祈りを捧げても、神は時として我等を救ってはくれないのだ、という事に。」
オルヴァスはメルヴァントが如何にして悪魔崇拝者と成って仕舞ったのかが目に見える様であった。
彼は果ての無い戦乱で多くの死に遭遇して、深く傷付いて仕舞ったのだ。神に強く祈っても救われない状況に絶望を感じた彼の其の時の心情を鑑みると、辛くて堪らなかった。絶対の真理として生まれてから其れまで信じて来たものに裏切られた悲しみは想像を絶するものだったに違いない。
「……例えラプタス人の恥だと言われても構わない。七種神の厚い信者としての誇りを捨てても構わない。私はもう、此の真理に気づいてしまった心を偽って神を信ずる事等出来ないのだ。」
「メルヴァント……君がそんなにも深く傷付いて、悩み苦しんで居たのに、傍に居られなくて…御免。」
「もう、良いんだ。オルヴァスが謝る事では無い。此れは私が私の意志で決めた事なのだから……。其れに後悔はしていない。だって、信じて強く祈っても顧みてくれない神なんて、必要ないじゃあないか。……弱い者を助ける事が出来ない、救ってもくれない神なんて、此の世界に要らない。」
其れはメルヴァントの固い決意の様でもあった。夢から覚めた様な鋭い目は既に神を求めてはいなかった。
「……矢張り、私に責任がある。メルヴァントを此処まで傷つけ、変えて仕舞ったのだから…。私等、あの時アジィールさんに助けられず、刑に処されて仕舞えば良かったのだっ。」
相変わらず強く自分を叱責するオルヴァス。メルヴァントの変貌ぶりが彼の自責に拍車を掛けた。
「こんな事なら…死んで置けば良かった。……私等、生きる価値すら……ない。」
俯き頭を両手で抱え込む様にして呟くオルヴァス。其の目には自分に対する酷い自責と悔しさ、怒りが溢れんばかりの滴と成って滴って居る。
メルヴァントは無言のまま立ち上がり、オルヴァスに歩み寄った。
「……。」
弾ける様な音が小屋に響き渡った。
オルヴァスは思い掛けない事に頬を押さえる。メルヴァントに打たれた頬は真っ赤に染まり、痛々しかった。
「馬鹿っ。」
メルヴァントは滅多に出さない様な怒気を孕んだ声で叫んだ。
「…私は、君は死んだものと思って居た。幾ら探しても君を見つけられなくて、悔しかった。だけど、一年も半分を過ぎた辺りから、希望も諦めに変わった。……其の時の私の悔しさを君は分かるかっ。…探しても探しても友を見つけられず、君が生きて居るかもしれない、と言う夢すら見られない程に切迫し、疲弊し切った此の心を、私はどれ程恨んだ事か……。」
メルヴァントはオルヴァスにつられて涙した。悔しかった。心からの友と漸く再会出来たと言うのに、生きる価値を見失ったオルヴァスを鼓舞する事も出来ない自分自身が。伝えたい思いが溢れてメルヴァントを何時に無く感情的にさせる。
「……嬉しかったのだ…偏に私は、嬉しかった。今日こうして君が私の元に来てくれた事、生きて居てくれた事……。」
頭を固く抱えるオルヴァスの両腕を取り、底深の緑色の瞳を見つめて言った。
「君が生きて居てくれるだけで私は幸せだ。……私が、君が生きて居る事を喜ぶだけでは、君の生きる意味には成らないか?」
メルヴァントの魂をぶつける一言であった。
オルヴァスは彼の言葉に感極まったのか、勢い良く流れる涙を必死に拭った。
「…オルヴァス、如何か私の生きる価値であってくれ。」
涙を流しながらも微笑むメルヴァントは温かかった。
君が側に居るだけで私は辛い事も、悲しい事も乗り越えられる、メルヴァントは言いながらオルヴァスの背を抱いた。
悲しみと喜びに小刻みに震えるオルヴァスの背は、小さく見えた。彼が経験した苦しみや悲しみ、様々な感情が収まり切らない程、彼の背は小さく見えた。手中に抱くのは唯、弱い一人の人間で、其の彼を抱く自分も又、少しの悲しみにも耐えられぬ程に脆弱な人間なのだと、実感した。
「…有難う……有難う、メルヴァント。」
オルヴァスは唯々そう言って、涙が枯れる程に泣いた。堪えていた何かが解き放たれた様に止めど無く流れては、留まる事を知らない。
オルヴァスはメルヴァントの暖かな腕の中で、彼が生きて居てくれた事への感謝を只管に感じて居た。
***
星々が煌めく静かな夜。深い、深い悲しみの闇が旧シャルティネの郊外を包む。
オルヴァスはメルヴァントとの再会の喜びと共に、其れまでの疲れが一度に押し寄せたのか直ぐに眠りに就いた。メルヴァントは寝具の呪符に何やら呪文の様なものを唱えていた。
部屋を照らし出す弱々しい燭台の光。揺らめいて室内を薄暗く照らす。
(私は、もう神を信じる事は無い……。全てを奪った神を…。)
其の目は既に此の世界の果てを見て居る様に冷たく、又神をも凌駕した様な強い輝きが在った。
「嗚呼、邪神よ、悪魔と呼ばれし神々よ。今こそ七種の神々の壮絶な裏切りに一矢報いる時です…。如何か私に力を、与えたまえ。」
此の世から嫌厭される邪神達。其の存在は神にも拘らず、邪悪で悪魔の様な存在とされて居る。誰もが忌み嫌って止まない神々達の存在は世界の秩序を奪い、混沌に貶めると言う。
誰も知らない神の国の真実。神話の本当の筋書きを世界は、人々は未だ知らない。非情な裏切りと醜い戦争。久遠の生命と偉大な名声。大いなる理不尽と裏切り。メルヴァントは其の果ての神々の物語すら知って居るのかもしれない。
***
二年の月日を越え再会した二人は小屋で数日過ごし、此の場所を去る事にした。其れは同時に懐かしの首都シャルティネを捨て、生まれ故郷を捨て、そしてかつて栄華を誇ったラプタスをも捨てる、と言う事を意味して居た。聖戦で死に損なったラプタス人が生きて行くには此のベスタルクの統括する世界は余りにも窮屈で、冷酷であった。其処に神の恩恵を受ける豊かな国は無かった。
身を隠して居ても何時かはベスタルクの者に知れて仕舞う事に成る。其の前に一刻も早く此の国を去りたかった。だが意を決してみたものの、此の先郷土を失った彼等に行く宛など無い。知り合いも、頼れる者も居ない。ましてや今まで自分達に剣を教え、面倒を見てくれた先輩達はもう此の世に居ない。此れからは二人だけで生き抜かねば成らないのだ。
「初めてラプタスに来た日が懐かしい。目に映る何もかもが新鮮で、新しくて大層感動した。」
荷造りを終え、何も無くなった小さな空間を見渡してオルヴァスが言った。
「知らない町へ独りで出て来た時の期待と不安、今でも鮮明に覚えている。故郷で見繕って貰った服は大きくて、馬を走らせるには向いて居なかった。私は家族に感謝もせずに、文句を言って仕舞って……。」
全てが初めての経験で、何だか物寂しかったあの頃。生きる事と死ぬ事、戦う事の栄光、残酷さ。未だ何も知らず希望と夢に満ちた若き志。
今日の旅立ちは、あの頃を彷彿とさせる様であった。但し、持ち合わせているのは純粋に夢見る心では無く、生死への悲しみと深い傷。
「私も思い出したよ。優秀な兄達に激しく劣等感を抱いて居た私は、父上や母上に懇願して騎士団入隊の許しを乞うた。目眩む様な忙しない毎日だったよ。」
そう語るメルヴァントの表情は何時に無く穏やかであった。
小屋を後にし何処までも広がる草原の中、空を見上げた。白い雲が果て無い大空を悠々と飛んで居る。大きく息を吸い込むと何だか胸が苦しい様だった。何も知ら無い様な純粋な空が辛酸を舐めた心に、酷く浸みたのかもしれない。
懐かしい思い出を回顧しながら草原を行く。踏み締めた土の、草の柔らかな感触が何とも久しぶりで、新鮮であった。
「メルヴァント…私達は此れから何処へ向かえば良いのだろうか。」
オルヴァスの問い掛けにメルヴァントは沈黙し俯いた。
「……ベスタルクも三国も、戦乱も無い……神々の居ない所……。」
其の呟きはオルヴァスの耳に聞こえるか否か程の小ささであった。しかし此れは確かに彼の苦しみを投影した心の叫びでもあった。
ラプタスを割り、仲間や家族、大切な人達の命を奪ったベスタルクと三国連合は無論、途轍もなく憎い。アジィールとシャレール、オルヴァスと共に過ごして来た心休まる様な一時、此れからも続いて行く筈だった安らかな時を奪った聖戦も憎い。だが何よりも神々の方が憎かった。
生まれてからずっと七種の神を信じて生きて来た。祈りを捧げ、忠誠を誓い、心の拠り所として今迄、其れは其れは律儀に、実直に一縷の疑いも抱かずに神を信じて来た。あの日地獄の様なシャルティネでもメルヴァントは只管に神に祈って居た。必ず救われる、苦しみを味わえば何時かは神が救いを御与え下さる、そう信じて。
しかし、どれ程強く祈った所でラプタスが救われる事は無かった。敗戦に敗戦を重ね、誰よりも敬虔な七種神の信者であったラプタス人は虐殺された。今迄、何の為に祈って来たのだろう。真に救いを求める者に、神は慈愛の手を差し延べるのでは無かったのか。此れでは余りにも残酷では無かろうか、激戦のシャルティネでメルヴァントは強く感じた。そして知って仕舞ったのだ。神が万人に平等では無い、と言う事。弱者が必ずや救われる訳では無い、と言う事。此れ等を理解した瞬間、彼は大いなる絶望感に苛まれた。
であるからこそ、神など居ない世界に生きたい。自らの力で、努力で、理不尽な状況を何とでも変える事が出来る、そんな世界が在るのならば、行きたいと願って止まないのである。
だが其の願いをオルヴァスに強要する事は出来なかった。神に絶望して仕舞い、邪神の信仰に昼夜を費やす自分は、酷い自責の念を抱き、生きる価値を見出せず葛藤して居るオルヴァスとは違うのである。メルヴァントはオルヴァスにだけは希望を持って生きて居て欲しいと思って居る。神を信じる事が出来るのならば、其の心を何時までも大切に、忘れずに居て欲しいのだ。自分が選んだ悪道非道の運命に態々巻き込まれる事は無い。
「…否……兎に角、町に出よう。旅に出るなら食料が必要だし、町に出ればきっとベスタルクを出る手段が見つかると思うから。」
「うん。……そうだね。」
メルヴァントの心の闇等つゆ知らず、オルヴァスは穏やかな笑みを湛えて頷いた。其れはメルヴァントと共に過ごす今此の瞬間に強い喜びを感じて居る様で、至福の表情であった。
メルヴァントは胸が痛かった。何時しか友の此の美しい微笑みを裏切り、志を違えて歩む日が来るのだろう。そう思うと何とも寂しく感じられた。聖戦が終わった此の世界ではもう、メルヴァントとオルヴァスが見ているものは違って居るのだ。あの時の様によもや過去を笑い、神を信じて生きる事は出来ないのである。
オルヴァスには彼の生きる道がある。彼の悲しみを、怒りを、そして其れ等との強い葛藤を知って尚、彼を巻き添えにする事等誰が出来ようか。
***
ベスタルクの露店街は大いに賑わって居た。様々な身分の者達が人波を渡り歩く。
絢爛豪華な装束を身に纏った上流階級の者、中流の兵士達、商人や平民は大きな荷袋を背負い、街を忙しなく動き回る。少しでも気を緩めると、人波に揉まれ、流されて仕舞うだろう。賑わう反面、忙しない人々の動きは穏やかさの欠片も無かった。
「メルヴァント、私が何か見て来るから、君は此処で待って居てくれないか。」
「……有難う、オルヴァス。」
余りの人の多さに眩暈がして居たメルヴァントは、オルヴァスの好意に甘んじる事にした。
オルヴァスは軽く頷き、軽快な足取りで露店街に消えて行った。
メルヴァントは辺りを見渡し、少し離れた所に深く腰掛けた。其処からは犇めく露店と行き交う人々の様子が良く見えた。
威勢の良い商人の声、人々の喧騒からは聖戦の傷痕等、窺う事は出来ない。皆、自分達とは違い生気に溢れている。しかしそんな姿を見ても今は恨みも、憎しみも感じる事は無い。唯、死んで逝った仲間達が、多くを失った自分が、何だか情けなく感じた。抱いた感情は唯、其れだけであった。
「おい、御前はそんな事も出来ないのか。……役立たずめ。」
そんな罵声が聞こえて来た。メルヴァントが露店街をふと見遣ると、如何にも性根の悪そうな中流階級の男が側に従えて居た奴隷を叱責する姿が在った。道行く人々は男から距離を置く様にして眉を顰め、陰口を叩いて居る。ベスタルクの者達にとっても男の印象は悪い様だった。
「奴隷の分際で、主人の言う事も聞けぬのか。……誰が御前を助けて遣ったと思って居る。あの場所に帰りたいのか?」
周囲は騒然とした。男の声だけが露店街に響き渡る。
周囲の冷徹な目等気にも留めず、男は奴隷に向かって片手を振り上げた。痩せ細った少年奴隷は思わず目を閉じる。
鞭打つ様な痛々しい音が聞こえる。少年が倒れ込んでも尚、男は怒り任せに叩きのめした。
「……いっ、痛……い。」
少年はか細く鳴いた。幾ら圧倒的に身分が下の存在であっても余りに酷い仕打ちを受ける少年に、人々は同情した。しかし誰も彼に助けを差し延べる事はしない。他人の所有物である奴隷に手を貸す事は犯罪であった。下手に首を突っ込めば、重い刑罰が科せられる。誰も少年を助ける事は出来なかった。
同様に遠目で男と奴隷の遣り取りを見て居たメルヴァントは小刻みに震えていた。妙な事に、手の発汗が止まらず、背には悪寒が走る。視界が大きく歪み、吐気すら催して居る。気分の悪さに頭を抱え込んだ。
メルヴァントの脳裏に聖戦の記憶が蘇る。
無残に殺された仲間達。襲いかかるベスタルクの軍勢は皆、不気味な笑みを湛え、人を人とは思わぬ様な極悪非道な手段で騎士達を死へと追い遣る。希望すら爆ぜる様な其の光景は、正に地獄。
打たれる少年奴隷の姿に、殺された仲間達を、無残な捕虜達を、残酷な聖戦の光景を思い出したのだ。
「…メルヴァント…気分が悪いのか?確りしてくれ。」
過呼吸をし、苦しそうに表情を歪めながら座り込むメルヴァントが目に入り、オルヴァスが駆け寄って来た。
「オルヴァス……もう…此処を、離れよう。……気分が悪い。」
苦し紛れに言いつつ、オルヴァスの腕を取る。メルヴァントの肩に手を回し、抱え込む様にしてオルヴァスは露店街を離れた。
「メルヴァント…大丈夫…?其処に座って……。」
オルヴァスは持参して来た水入れでメルヴァントに水を飲ませた。
冷えた水を嚥下するとメルヴァントの顔色は幾分か良く成った。先程までは顔面蒼白で頗る調子が悪そうであったのだが。
「さっき露店の主人に聞いたのだけれど、此の先に港が在って、渡航の船も幾らか出ているらしい。だから、早く其処に行って此の国を出よう。……私は君が苦しむ姿を見たくは無い。」
オルヴァスは露店で手に入れた食料をメルヴァントに僅かに与えて言った。
「此処はもう、私達が住まう事の出来る場所では無い。だから、逃げよう。何処までも。私は君と一緒ならば何も怖くは無い。恐れる事は何一つ無い。何時までも君と共に、君の側に居続けるから……。」
オルヴァスの言葉にメルヴァントは胸を打たれる様であった。自分と共に在ろうとしてくれる友の存在が何とも喜ばしかった。しかし同時に自らの罪深さを実感させられる様でもあった。
自分が無茶を言おうとオルヴァスであれば付いて来てくれるだろう。例え地獄の様な世界でも、死の淵であったとしても。自分自身に添い遂げる事で彼の人生をも狂わして仕舞う、そんな自分の存在が深い罪の様に思われた。神を捨て、信仰を捨て、国を捨てた自分と運命を共にする事で、非情な運命に束縛されるであろう友が何とも哀れに思われて成らなかった。
「……有難う、オルヴァス。君の心優しい其の気持ちだけで、私は十分に生きて行ける。」
メルヴァントは笑った。歓喜の表情を湛えて。しかし其れは心からの微笑みでは無かった。何時の日から自分は心を許した友にまで作り笑いをする様に成ったのだろうか。
***
潮風を浴びながらクォルド海を行く帆船。其の真っ白な帆は日の光に照らされて、眩いばかりに堂々と風を切って居る。
メルヴァントとオルヴァスは新天地を求めてベスタルクを後にし、広大なクォルド海へと航海に出た。船は立派な帆船で、渡航と交易の二つの役割を同時に果たし大海原を走るのであった。
過ぎ行くベスタルクの街並みを見詰めながらメルヴァントは物思いに耽る。此れより新たな地へ移ると成ればある程度の身の振り方は決めて置かねばならない。
オルヴァスは何も言わなければ自分に付いて来るに違いない。しかし彼には彼の一生がある。自分の醜い野望の為に尊い時間を犠牲にする事は無い。何せ自分はもう何も知ら無かったあの頃の様では居られないのだから。神々の真実も、悪魔と称えられる邪神達の悲劇も知って仕舞った今では。
「……御前は私と良く似ている。」
甲板に立って居たメルヴァントの耳にそんな囁きが聞こえた。聞き慣れない声に衝動的に振り返るが、其処には誰もいない。では今の声は幻聴であろうか。そんな事を考えていると、再び同じ声がした。
「自ら呼び起こして置きながら……人間と言うのはどうしようもないものだ。」
呆れ果てた声と共に重みのある低い女の声が淡々と話を始める。
「我が名はエレシー。かつて神々の国で冥府を束ねた神。…今と成っては邪神の扱いを受けて居るが。」
そんな申し出にメルヴァントは耳を疑った。声の主は邪神だと言う。しかし其の様な事、信じられる筈も無かった。神の言葉が聞こえる等、有り得ない事である。神が遣わせた使徒でも無い限り、神の御告げが聞こえる事等無いのだ。つまりは神の声を聞く事は、通常あっては成ら無い事なのである。
「未だ理解して居ない様だな。まぁ良い、いずれ分かるだろう。……私は御前に其の様な詰まらぬ話をしに来たのでは無い。御前自身の闇、心中に秘めたる生々しい野望、其れ其の物に興味を持ったのだ。何せ、御前は私、私は御前。不運にも酷似して居るのだから。」
邪神と名乗る女の声が告げた事は余りにも理解し難いものだった。
しかしメルヴァントの心中など構わずエレシーは話を進めて行く。
「御前は私好みの野望を抱いて居る。神の存在しない世界の創造、私は深く感じ入った。しかし御前の軟弱さでは望む世界は手に入らないぞ。全てを覆す様な大いなる力を持ち合わせて居なければなるまい。」
此のエレシーの言葉にメルヴァントの理解は漸く追い着いた。
聖戦で自らの神を捨て早、二年。其の間毎日欠かさず悪魔崇拝を続けて来た。弱者を救う事の出来ない神に抗う為に。そして何時か必ずや祈りや努力が報われる国を造る、新たなる志の為に。
厚く邪神に縋り付くと共に彼の脳裏にはかつての神々の世界が浮かぶ様に成って居た。其の時彼は七種神以外の神の存在を知り、神話に隠された悲しき冥府の物語をも知って仕舞ったのである。其れ以来彼は自らの志を果たす為にも邪神達に大いなる力を求める様に成った。
そして今、邪神が目には見えない声として現れ、自分の野望に興味を抱いて居る。此れは好機に違いない、メルヴァントはそう解釈した。
「私は御前と同じくかつての世界で裏切りに遭った。大切な仲間が裏切られ、憤怒した我等は抗った。だからこそ御前の心中を慮る事は容易だ。力を欲する所以も納得が行く。私とて此の世界に仇成す為、邪神へと身を変化させ執念の化身と成って浮世に舞い降りたのだから。」
「力を求めよ、異端の心を持つ者よ。私を其の脆弱な体に受け入れれば、御前は絶大な力を手に入れる事が出来よう。さあ、目を覚ませ、選ばれし者よ。御主の野望の為に。」
メルヴァントの目には覚醒したかの様に邪神エレシーの姿が見えた。闇の様に深い漆黒の衣装に身を包み、意地悪くしかも艶めかしく笑う姿は正しく、執念を帯びて此の世界に舞い降りた邪神其の物であった。
彼女の切れ長の瞳がメルヴァントの心を射抜く様に鋭く成った。
「七種の神を此の世界から消し去りたい、と望むのだろう?……成らば私を受け入れろ。」
迷いは無かった。メルヴァントの前に彼女の申し出を断る理由等何処にも存在しなかった。
理不尽な、神という概念を此の世界から消し去る。そして人間の実力や努力が実を結び、救いを求める者の元に慈悲の手が差し延べられる世界を作り上げる。
其の壮大な夢の実現の為にも、力は欲しい。何せ此れはかつて誰も無し得なかった事であり、世界の摂理や概念を覆す大事なのだから。
「君は私の心が分かって居たのだな……。神を捨てたにも拘らず、邪神を崇める矛盾を犯す私の心の内を……。願って止まない世界への果て無き欲望すらも……。」
メルヴァントはエレシーの前に跪き、差し出された白い手を柔らかく取った。
「如何か私に貴女の力を御貸し下さい。」
まるで貴人を扱うかの様な手付きにエレシーは満足げに頷き、微笑んだ。何かを目論む様な愉快な調子で。
メルヴァントはエレシーを抱く様に其の身体の中に宿した。
此の日彼はかつての神々にさえ恐れられた女神と禁忌の契約を果たしたのだった。
***
大海原はやがて曇天の空に覆われた。其れは此れからの風雲の事態を予期して居るかの様であった。
帆船は嵐に煽られ、蛇行を繰り返しやがて難破した。広いクォルド海に投げ出された帆船の乗客は、深く冷たい海に散り散りに成った。
無論メルヴァントとオルヴァスも海へと投げ出されて仕舞った。しかし海洋の大きな流れに乗せられる内に、他の乗客と共にやがて小さな島に漂着した。
暗闇の中何処かから鈍い音が聞こえて来る。
「……。」
濡れた衣服を身に纏ったオルヴァスはゆっくりと起き上った。如何やら自分は意識を失って居た様だ。だが何故意識を失って居たのかを思い出す事は容易では無かった。島に漂着した、と理解するまでにはかなりの時間を要した。
「……メルヴァント…?」
荒れた海に閉ざされた島を一見すると其処には信じ難い光景が広がって居た。
「ははっ……ハハハハハハッ。」
オルヴァスの眼前には不気味な高笑いを上げるメルヴァントの姿が在った。手には血の滴った剣を提げ、装束は妙に紅を帯びて居る。
「…オルヴァスか。漸く目覚めたのだな。」
「何を悠長な事を言って居る。此れは一体どういう事だ。」
オルヴァスは苛立たし気に辺りの光景を指差しながら言った。
其処には血みどろで無残に嬲り殺されたであろう屍が点在して居た。其の死に様は異様で単に斬り殺しただけでは有り得ない程、酷いものであった。
此れ等を見る限りメルヴァントの所業に相違無いのだがオルヴァスには彼が此の様な非情な事をする様には思えなかった。其れに彼が他人を淫らに殺める動機が無い。
「私が意識を失っている内に何があったのか、教えてくれないか。」
メルヴァントはかつてオルヴァスが目にした事の無い不気味な笑みを湛えて此れに応じた。
「彼等が私の目の前で七種神への祈りを捧げ始めたから、罰を与え、裁きを行った。偽りの神への奉仕は過ちだ。其れを正した、単に其れだけの事だ。」
「単に其れだけ?……メルヴァント、君は間違って居る。君が遣った事は正義でも何でも無い。単なる欺瞞だ。自分と考え方が違う人間を殺す必要は何処にも無い。人に罪を与え、裁きを下す等、私達が行って良い事では無い。……其れは神の一存で行われる事だ。人間が手を出しても良い領域では決して無い。」
険しい顔付きで言うオルヴァスにメルヴァントは瞳孔の開いた興奮した目で、彼の襟首を鷲掴みにし叫んだ。
「オルヴァス…君までもが私が間違って居ると言うのか。……あぁそうか、君は何時だって従順な七種神の信者であるものな。」
呆れた様に言うメルヴァントの表情は何処か哀し気で、寂し気であった。
「違う、そうではない。ただ私は考え方が違うだけで人を殺める事は可笑しい、と言って居るのだ。」
「考え方が違うだけ……?君にはかつての世界の真実が見えないのか。神々の世界で起こった悲劇を知ら無いから其の様な事が言えるのか。」
メルヴァントは心底驚いた様であった。
一方のオルヴァスもメルヴァントの思い掛けない言葉に驚きを隠せないで居た。神の世界があった事すらも今、初めて知ったにも拘らず悲劇が如何の等知る由も無かった。
「メルヴァント、神の世界なるものを私は知ら無い。其れが何か教えてはくれないか。」
「もう良い。所詮、私が可笑しいのだ。……昔からそうだった。自分にとって正しいと思う事は間違って居て、間違って居ると思って居る事は大抵正当だった。」
オルヴァスに背を向けたメルヴァントに絶望と諦めの色が滲み出た。
「君だけは私を受け入れてくれる、と思って居た。しかし其れも単なる私の思い込みだったのだな……。」
至極無念、とでも言いたげなメルヴァントにオルヴァスは距離を詰め、不貞腐れて居る彼の頬を平手で打ち付けた。
「私は君が可笑しい等と一度も思った事は無い。私達は友では無かったのか…同志では無かったのか。」
怒り任せに言うことばの端々にメルヴァントへの感謝が込み上げて、途轍もなく辛かった。此処でメルヴァントを失望させてはいけない。自分が繋ぎ留めなければこんな世界で誰が彼を繋ぎ留められようか。
「君が私に、君が生きて居る事を喜ぶだけでは、君の生きる意味には成らないか?と言ってくれた時、本当に嬉しかった。あの時に私は決めたのだ。此れより先は何があっても君に添い遂げよう、と。メルヴァントの生きる意味に成る為に、もう一度立ち上がろうと思ったのだ。だから、話してくれ。君に何があったのかを。」
一か八かであった。どんな言葉を並べようとも、彼の閉ざされた心が開くとは思わない。下手をすれば彼の心は離れていくばかりである。しかし自分には彼を引き止め、悪を正す責務がある。彼の友なのだから。
「……君と私とは生きて居る世界が違ったのだ。もう、構わないでくれ。」
言い残し踵を返そうとするメルヴァントにオルヴァスは語りかける様に言った。
「そうして、逃げるのか。……逃げて何になる?」
「……五月蝿い。君にはもう関わりの無い話だ。」
「君が私を友と言ったのだろう?……第一君は唐突なんだ。此処数日の間に一体何があったのか教えてくれなければ分から無いだろう?君の考えも、理想も……。私の考えだって君は知ら無いじゃないか。」
早足に其の場を去ろうとして居たメルヴァントは立ち止まった。
「伝え合わなければ、歩み寄ら無ければ、何も分から無い。……私達は全知全能じゃあないから。」
オルヴァスはメルヴァントと共に此れから先も、ずっと一緒に歩んで行くつもりだった。何があっても。例えメルヴァントが神を捨てても、自分を裏切っても、世界中を敵に回したとしても。ずっと彼の傍で、彼の味方であるつもりであった。共に辛く、悲しい聖戦を乗り越えて来た唯一の友として。
オルヴァスにとっては彼との繋がりが、唯友であるという事、其れだけで十分であった。其れさえ在れば何時、何処で、何があろうとも彼を信じて行ける。
「私は何時までも君と生きて行くよ。偶然にも二人一緒にこんな世界で生き残って仕舞ったのだから。……私は君が拒絶しようと、敵対しようと執念深く君の側に居続けるから。」
「……私が世界を敵に回し、神を殺してでも?」
背を向けた儘のメルヴァントが諦め半分に尋ねた。
「無論。私と君は此の世界でたった二人だけの友なのだから。」
オルヴァスは何時しかの様に慈悲のある美しい表情で笑った。其の暖かな眼差しに孤独が差して居たメルヴァントの心はどれ程癒えただろう。そして心根の優しい友の存在に感謝し、自らの軽率な行動や愚かな考えを深く恥じた。
***
二人だけに成った無人島でメルヴァントはかつての神々の聖なる世界、所謂、聖界について、そして二年もの間其の身に抱いて来た野望をオルヴァスに話して聞かせた。
「…そんな事があったのか。済まないメルヴァント、君が辛い時に気付いて遣れなくて……。そんな事を知って仕舞ったら誰しも一人では抱えきれないよ………。本当に御免……。」
メルヴァントの話の全てを耳にしたオルヴァスは己を深く恥じた。メルヴァントの苦しみは相当のものであったに違いない。にも拘らず、自分の事ばかりでメルヴァントが思い悩んで居るとはつゆ知らず、彼には苦境を強いて来た様に思えたのだ。
聖戦の経験が彼の心の深い傷となり、今でもあの地獄の日々を夢に見る事。其れまで強く信じ、崇めて来た神々を信じる事が出来なくなり、悪魔崇拝者になり下がった時の屈辱感。果てには此の世界の誰も知る由も無い神々の世界が見える様に成り、世界の摂理と信仰の矛盾を目の当たりにした時の絶望感。
全てが波の様にオルヴァスの胸の中に流れ込んで来る様だった。メルヴァントの苦悩が自らの胸に、脳裏に渦巻く。倦怠感や閉塞感を覚える、此の胸の痛みに独りきりで耐えて来たのかと思うと、何とも辛かった。友を理由に此の苦しみを吐き出させた自分への嫌悪感に襲われる。友であるならもっと早く気付いて遣るべきだったに違いない。
「私はあの日、あの戦場で一切の希望を捨てた。そして神を捨て努力が、祈りの心が救われる世界を夢見て来た。望んでも、望んでも手に入らなかったものが漸く手に入れられる時が来た。邪神と呼ばれる女神と盟約を交わし、大いなる力を得た今、もう後戻りは出来ない。」
「…君の言う、神の存在しない人間の世界が君の正義だと思うのだね。」
「あぁ、神の意志に委ねられた詰まらない一生を送る意義は何処にも無い。我等の運命は我らで決める。其処に誰の意も介さない。祈りを捧げても救われない、理不尽を見てみぬふりをして嘆願の声にも耳を貸さない神に我等の運命を、世界を定める義理は無い。」
メルヴァントは恨めし気な表情で語った。其処には友想いのメルヴァントは何処にも居なかった。唯、地の果てでも執念で其の命の炎を燃やし続けるであろう程に、自らの野望に執着している一人の人間の姿が在った。
オルヴァスは死も恐れぬ狂信的な何かを感じたに違いなかった。
「分かった。君が其処まで言うのなら、僕は君の正義を信じて君の為であり続けるよ。……君がどんな道を選んだとしても唯君の目指すものの為に此の力を振るおう。」
其れが彼なりの贖罪である様な気がした。彼の志に共感し、彼に自分の力を貸す事。其れがメルヴァントの苦しみに逸早く気付き、対処して遣れなかった自分が出来る罪滅ぼしであった。
彼の正義が間違ったものであったとしても、自分にはもう彼は止められない。決して止める事は無い。例え滅びの道へと邁進したとしても其の運命と共にするつもりであった。自分には彼を正す権利は無い。彼の決死の足掻きすら悟る事は出来なかったのだから。
「君ならそう言ってくれると思って居たよ。……有難う、オルヴァス。」
全てを見透かして居たかの様な口ぶりと共にほくそ笑むメルヴァント。其の表情が自信に満ち溢れた上流社会の者らしく、メルヴァントには良く似合って居た。
そんな彼の様子に一息吐くと共にオルヴァスは何だか悲しくなった。もう昔の様に心優しいメルヴァントは居ない。世界に抗う事を選んだ彼は自分の知って居る友では無かった。何だか二人の間に天地程の距離を感じる。メルヴァントは此れから彼自身の望みの為に躍進するだろう。そして何時かは自分の手の届かない所へ行ってしまうのではなかろうか。手を伸ばしても、追っても決して追い着く事は出来ない。そう思うと此れまでの比に成ら無い程の悲哀を感じた。
「礼を言われる事は何もないよ。唯、私の意志で君に付いて行くと決めたのだから。」
そう此れは最後の我儘であった。自分が彼を見守って置かねば成らないと言う、身勝手かつ傲慢な貪欲も甚だしい。何と醜い心だろうか。
メルヴァントに何気なく微笑みかけた様に見せたオルヴァスの本心は嘘で、彼とはもう二度と心から笑い合えないであろう未来さえ悲しんで居るかの様だった。
「ならば、私と共に行こう。世界の高みへ。」
悪魔の悪巧みを彷彿とさせるメルヴァントの態度。神をも恐れぬ堂々たる姿、神懸かった様な自信に満ち溢れた風格に、畏れ入ったオルヴァスは思わず跪いた。
「……はい。何時までも、何処までも御一緒致します、メルヴァント様。」
二人の間に友や同志とは違う、主従関係が生まれた瞬間であった。
***
世界の創始を知ろうと試みれば、神々の世界に辿り着く。其処は永遠の名の元に生きる不死の神々の世界。様々な世界を生み出す神々が集い歴史を、生物を、感情を紡ぎ出す場所、聖界。
其処には隔たれた冥界と、其処に君臨する冥府の神々が差別を受けながらも存在して居た。
悲しき神々の抗争。世界の創造以前に繰り広げられた醜い争いの真実は誰も知ら無い。七種神が絶対的な信仰神とされて居る此の世界で、悪魔と称される邪神の大義、冥府の深い憎しみと恨み等誰も知る筈が無かった。
世界でたった一人神話の道に導かれ、悲しき神話の真の話を知って仕舞った少年は何を志し、どの様に世界を導くのだろうか。
将又、其れは本当に彼の意志なのであろうか。
第五章 約束の少年
南半球の様子は、ラプタス国が勢力を振るって居た頃に比べ様変わりして居た。
ベスタルクは大陸一の軍事国家として名を馳せ漸次、版図の拡大を図っている。其処に三国連合が力を添え、屈強な集団として南半球を統括して居た。しかし彼らに不満を抱く者も少なくは無く、新たなる戦乱の契機が漂い一触即発の緊張状態が続く。結局他国に侵攻し搾取した者達は、また別の国に侵攻され、やがては滅んで行くのであった。栄枯盛衰の人間の儚い定めである。
変貌を遂げた南半球の中でも最も変化著しかったのは、ベスタルクの東に広がるクォルド海の南西諸島群であった。此処は無人島が数多く点在しており、また航海の際に座礁の危険性を生み出す事から誰もが好んで近寄らない、暗黒の地帯と成って居た。
しかし其処に突如として強大な力を持ち、世界を混沌に貶めようと企む漆黒の組織が現れたのだ。言わずもがな、其の組織とはメルヴァントとオルヴァスの率いる抵抗組織であった。彼等は世界から七種神を排除し、人間が望む未来へと努力をする心こそが何よりも尊く、神に導かれるままでは無く自分の手で運命を切り開く事が出来る世界を創造しようとして居た。
驚く事に此の志に感銘を受け、自らメルヴァントやオルヴァスの元にやって来る若者も多く居た。其の為今ではすっかり一大組織として、他国も見逃しては置けない勢力として彼等の動向を窺って居る。
更に厄介なのは彼等の誰もが世界を総べるのは王や皇帝でも、神々でも無く、自分の求めるものの為に努力を重ねた真に強い者であると信じて居る事である。一見正しい事では有るが、戦乱溢れる此の時代、指導者としての理想は強者であったが、実際の所は遥か昔に手柄を上げた者の子孫や、かつての英雄の末裔が権力を笠に着て国家を形成して居るに過ぎないのである。
要するに周辺国家からすれば、正論を正義に掲げる彼等は目障りな存在であった。彼らの志に賛同した者達が国家転覆を図る危険性を孕んで居るからだ。
そんな周辺国家の懸念を他所にメルヴァント達は着実に力を得て行った。其れを最も良く表して居るのが、かつてメルヴァントとオルヴァスの二人が漂着した無人島に建ち並んだ、漆黒で異様な様相を呈した塔の群立である。此れ等は彼等の組織の活動拠点で、組織の者以外は安易に近寄れない要塞の役割も果たして居る。天まで聳える様な其れ等の群立が現れ始めた時、南半球の人々は恐れを感じたに違いない。其れ程此の塔は圧倒的な存在感を誇示して居たのだった。
「……オルヴァス様、北方の遠征部隊から要請です。」
丁寧な口調でオルヴァスを敬う様に跪くのは、彼の付き人であり部下の若者であった。闇夜の様な色味を帯びた外套を羽織り、幾何学模様の呪文の類を頬に描き、組織にすっかり魅せられて居る様だ。
今では大規模な組織集団を束ね、其の頂点に君臨するメルヴァントの側近として雑事を熟すオルヴァスには彼自身が育て上げた部下を幾人か抱えて居る。
此の従順そうな少年も其の一人であった。彼は此の組織の志に感化され、進んで組織に遣って来た。そんな彼の視線は陶酔し切った様に常にオルヴァスに向けられて居る。
世間知らずの自分を育て上げ、側に仕える様に計らったオルヴァスに感謝と尊敬の念を抱いて居たのである。
「私が直接、北方に出向く事にしよう。メルヴァント様に報告して置いてくれ。」
そう頼まれると彼の瞳は星屑の様に煌めく。オルヴァスの為に働く事が嬉しくて成らないのだ。
「はい。承知致しました。北方に出向かれる為の準備を早急に進めて置きます。」
自らの役割に誇りと自信を持ちながら早速準備をして置こう、と立ち上がる。オルヴァスの前で恭しく一礼し身を翻した途端、オルヴァスに呼び止められる。
「御前は一体、誰の為に任務に当たって居る?」
「……無論、オルヴァス様の為であります。」
明朗快活な返答をすると、恐るべき形相を浮かべたオルヴァスが少年リタ=マレアティスに近づき、
「愚か者め…我等が組織の頂点の座は一体誰の者と心得て居る。」
激怒してリタを蹴り飛ばした。余りに容赦ない一撃にリタの身体は一瞬宙へ舞いながらオルヴァスから遠ざかる。
「勘違いをするな。我等が崇め奉るのはメルヴァント様であって、私では無い。」
オルヴァスは自分に向けられたリタの羨望にも似た眼差しに気が付いて居た。付き人として従順なのは構わない。寧ろ主人に従順な位の方が使役をする、という面では都合が良い。しかし、其れが組織の任務に当たる者の心得と成っては又、訳が違うのだ。
組織と言う集団が何か一つの事を成し遂げるには、組織を構成する一人一人の人間が同じ方向を向いて事に当たる必要がある。志や考え方、信仰の対象、誰に命を捧げ、誰の為に死ぬのか、其れが皆一様で無い組織の未来は破滅在るのみ。
であるからこそオルヴァスは此の組織を率いるのはメルヴァントであり、彼の命令ならば命を賭してでも果たさねば成らないと心得ている。無論、部下達には日頃から此れ等の旨を口煩く言い聞かせて居る。此れは組織の存続に繋がる問題であるからだ。
其の昔、憧れて止まなかった先輩騎士達が自分達にしてくれた様に。
***
メルヴァントが組織の頂点に君臨し、オルヴァスが組織内部を統括する此の闇の組織は現在、勢力拡大を図って大陸に進出して居た。
中でも戦乱で混乱期にある北半球は醜い争いに傷つき、新たなる世界を志して止まない、絶望した若者も多い事だろう。オルヴァス達はそんな希望を失った若者達を求めていた。世界を変えたい、と言う純粋な心と果敢で恐れを知らず、愚直なまでに志を果たそうとする若者の力が必要不可欠だった。
七種神の信仰という概念を奪い、努力を積み重ねた真に強い者が統べる世界の創造。世界中を敵に回す志を抱えて暗躍して居るのだから。
オルヴァスは要請を受けて急ぎ北半球の陣営へ出立した。
「…オルヴァス様、ようこそ御出で下さいました。」
「礼は無用。……其れより、一体何があった。見る限り、特別何か起こった様でも無いようだが…。」
北半球に派遣して居た組織の者達がオルヴァスを手厚く迎える。彼等の上場に別段困惑の色は窺えない。
オルヴァスが組織の陣に目を遣ると、一見変わった事等無く、彼等が敷設した組織の陣営と天幕の仰々しい群れが砂漠一帯に広がって居るだけである。
取り越し苦労であろうか、と思って居ると陣営の隅の方で組織の者の困り果てた、嘆くような声が聞こえた。
「そうは言っても我々は人助けを生業にしているのでは無い。…もう、帰れ。」
「…如何か御願です。せめて何方か貴方方の組織を纏める御方に会わせて頂きたいの。」
「…しつこい女だな。帰れと言ったら帰れ。言葉の意味が分から無いのか?」
オルヴァスが駆け寄ると其処には、組織の者二人を前に額を砂地に付け平伏して必死に何かを嘆願する女性の姿が在った。
「御前達、如何した。」
請う様に突っ伏して居る女性を厄介払いして蹴りかかった若者に、オルヴァスは割って入った。女性を囲んで居た二人はオルヴァスを見るなり驚いて目を見開いた。まさか組織の二番手で実質組織を束ねて居る彼が、辺鄙な派遣地の小部隊に遣って来る等とは夢にも思って居なかったのだ。
「お、オルヴァス様、失礼致しました。」
「貴方とも在ろう御方が此の様な場所にいらっしゃるとは、つゆ知らず……。」
狼狽して敬意を示す二人の青年を煩わしく思いながら、何が在ったのかを再度問い質した。
「此の女が毎日此処に、何やら嘆願をしにくるのです。其れがもうずっと続いておりまして、追い払おうにも帰らないのです。」
「…挙句の果てには組織の統率者を出せ、とまで要求する様に成り正直手を焼いて下ります。」
オルヴァスは心底不快な表情を浮かべ、大きく息を吐いた。
北半球に進出すべく派遣した部隊が態々、要請を出すのだから、大事が起こったに違いない。そう予見し、至急馬を走らせ遣って来た自分が馬鹿々々しかった。
屈強そうな此の地の輩なら未だしも如何にも華奢な女を相手にする等、気力の欠片も出なかった。
「…おい、其処の女。我々は便利屋でも何でも無い。頼み事ならば、他所を当たってくれ。此処は女の来る所じゃあ無い。」
地面に這い蹲る様に先程から只菅に頼み込んで居る女性に、オルヴァスは気怠げに言い放った。
女性は今迄自分を追い返してきた男達とは違う声に反射的に顔を上げる。
女性は如何にも貧しく、もう何日も同じ衣装を身に付けて居るのだろう。小汚い格好で、不安に歪んだ表情はオルヴァスを最後の頼みとばかりに縋る様な目を向けて居た。
「……貴方は此方の御偉い方ですか。…もしそうであるのなら、私の話を聞いて下さいませ。如何か、如何かっ。御願い致します。」
オルヴァスの衣装の裾を強引に引っ張り懇願する女性。其の狂おしい程に必死な姿が何とも無様だ、オルヴァスはそう思った。人と言うものは自分の願いの為ならば此処まで恥を捨てられるのだな、と嘲笑しながらも同情する様に女性を見下ろした。
其処で今度はオルヴァスが衝撃を受ける番であった。
「……貴女は…もしや…。」
信じられない光景であった。其れまで卑しいと相手にもして居なかった女性の祈るような表情に、目が覚めた様であった。何とも弱々しい其の顔が彼の女性と瓜二つであった。
其れは正に、不意打ちであった。此の世に、あれ程恋い焦がれ失っては絶望した愛しき女性を彷彿とさせる面影の持ち主が居るとは思いもしなかった。
「私に叶える事が出来る願いかどうかは分かりませんが、もし良ければ貴女の願いを御聞き致しましょう。」
そして、まさか自分が此の時分に至って騎士時代の様な丁寧で、尊重を含んだ言葉の紡ぎ方をする羽目に成ろうとは思ってもみなかった。しかし此の言葉は意識的に出たものでは決してなく、無意識の内に彼のアズリータに向けて居た好意が呼び覚まされた形であった。
女性は初めて自分を一人の女として扱い、手を差し延べる男の姿に感慨深く涙を流した。
「有難う御座います、有難う御座います。」
喜びに打ち震える女性に手を貸して立ち上がらせた。其の身体つき、雰囲気、目の前の女性の姿の全てに親近感が湧く。
一方の女性はオルヴァスを頼みの綱の様に見遣り、早口に語り始めた。
「私は、故郷の東国で死罪を言い渡された者です。不貞の罪を着せられ、無実であるにも拘らず、私は処刑されるのです。」
女性の故郷である東国は小国にして兼ねてより皇帝を頂いて居る。しかし栄華を誇った時代も過ぎ去り、現在は廃れ治安は最悪であった。
又、古くからの身分制度が人々を支配しており、階級によって職業や居住地を制限される等、厳しい風習が根強い。其処に付け込んだ特権階級の豪族達が愚鈍な皇帝に変わって領地を支配して居る。
そんな情勢から誰も豪族に反発する者は居ない。ましてや、やましい事が在れば豪族達に告げ口する者すら現れ、幾ら無実の罪であっても一度疑惑を持たれた者は其の土地に留まる事すらままならなかった。
此の女性も濡れ衣を着せられながら、自らの無実を糾弾出来ずに居るのだ。
「……しかし、そんな事は私にとって何でもありません。其れよりも案じられて成らないのは、私のたった一人の家族である弟の事です。」
黙って女性の話に耳を傾けて居た青年二人は、身内の話を始めた女性に掴み掛ろうと身を乗り出した。組織は此の女の家族の手助けの為に存在して居るのでは無い。そんな妙な自尊心が彼等を駆り立てる。
しかしオルヴァスは平然と彼等を制し、女性に話の続きを促した。唯、自分にはそんな意識等は無く身体が操られたかの様に動くだけであった。
「私の弟は生まれて間も無く両親を亡くし、私だけがあの子の家族でした。私が刑に処されれば弟は天涯孤独と成るでしょう。其れに弟は未だ幼く、世間を知りません。一人では生きて行く事も困難でしょう。其れだけならば、私は故郷から態々此処には参りません。私は貴方方が私の様な小汚い者を相手に、頼みを聞き入れて下さる組織では無い事は十分に承知して下ります。……其れでも私は貴方方に頼らねば成ら無かったのです。」
女性の郷土である東国は正しく名も無い小国であった。しかし近年の北半球に迫り来る戦乱の影響に揉まれ、混乱が広がる国々の一国であった。誰もが戦火から逃れる為、自分の命惜しさに人を利用し、裏切る世界。そんな世界の何処にも彼女が助けを求める事等出来なかった。自分は罪人の身。其れに貧しさを生き抜く為に身を売って生計を立てて来た身の上。誰も自分を人間として扱う事等無い。其れは生まれた時から嫌と言う程思い知らされて来た。
何処かに最後の望み、弟の身を託して置ける場所は無かろうか。処刑の日が迫り来る中、女性は必死に探し求めた。其の果てに有ったのが、メルヴァントが統べる組織の小部隊であった。
女性は兼ねてから此の組織の噂は男衆から耳にはして居た。七種の神を崇めず、努力が世界を救い、世界の頂点には実力の勝る者が君臨すべきだ、と言う無謀とも言える志を掲げる其の組織が彼女に取って此の世界で唯一、信用出来る様な気がした。
「私の弟は唯の人間では御座いません。こんな風に言うのも可笑しな話ではありますが、妙な親心でも何でも有りません。弟は神の名を持って生まれた来たので御座います。」
彼女は自分の弟が神の名を持って此の世に降り立った、七種神の使徒だと言う。
其れまでオルヴァスに制止され、黙って居た青年二人が耐え兼ねて言った。
「神の使徒だと?…馬鹿を言うな。そんな者は此の世に存在しない。」
「そうだ、そもそも神を忌み嫌い、神をも恐れぬ我等に其の様な話が信じられるとでも思ったのか。」
女性を罵る青年を横目で睨み据えたオルヴァスは、彼等でさえ見た事の無い穏やかな表情で、
「聞いた事が有ります。七種の神が此の世に救いを与えるために遣わせた七人の使徒。其の者達は生まれながらに神の名を持ち、使命を帯びて居る…。南では上流社会の者は大抵知って居ます。」
聖戦で亡くしたシャレールを思い出して居た。地獄の様な騒乱前の舞踏会、其処でシャレールは自分を信頼して秘密を打ち明け、教えてくれた。
重要な隠し事を共有した、あの何も知ら無い頃が無性に懐かしく感じられた。
「貴方は御分りに成るのですね……。そうです、神々が遣わせた神聖な名を持つ者、其れが使徒であり、私の弟なのです。」
彼女は又しても救われた様な希望を感じ、一息に話した。
「今迄は私があの子を守って来ました。ですが、もう私は死にます。あの子は自覚の無い儘に使徒としての力に目覚めるでしょう。……そうなればあの子は殺されて仕舞います。もしくは戦乱に兵器として利用される事でしょう。……私の故郷では未だ差別や偏見が根強いですから。」
女性は涙を流しながら再び砂地に額を付けて懇願した。
「無理な頼みとは承知の上です。如何か、私の弟を助けて遣って下さい。特別な温厚を与えて貰わなくとも構いません。他の組織の皆さんと同等に扱って頂いても構いませんから、如何かあの子を生かして遣って下さい。……あの子は未だ幸せと言うものが何なのか、喜びと言うものが何なのか知ら無いのです。其れを知らずに死んで仕舞っては、あの子が此の世界に生を受けた事が余りに残酷に思えてなりません。」
女性は自身の死に対する恐怖等、微塵も感じて居ない様に見えた。否、余りに必死な姿が其れを感じさせなかっただけかもしれない。其れ程までに彼女は自身の死より最愛の弟の未来を案じて居た。
オルヴァスは母性の様な温かく、しかし鬼気迫る様な女性の想いを肌で感じて居た。否と言わせぬ女性の気迫に其れまでの苦労と弟への慈悲深さ、そして組織を頼らざるを得なかった時の苦渋の決心が目で、肌で、感じた。其処には女性でも姉でも無く、一人の母親の姿が在った。
「一つ御聞きしたいのですが。……我々が彼一人を抱えたとして、彼に組織を繁栄させる活躍を期待する事は出来ますか。」
其れはオルヴァスが組織を束ねる立場として如何しても聞かねば成らない事であった。
彼は女性から無慈悲だと罵声を浴びせられる事は覚悟して居た。
女性の願いを聞き入れたい気持ちは山々であった。しかし彼は今、世界の理不尽な摂理を覆し、此の世界の神々に仇名す組織の頂点、メルヴァントの側近と言う立場である。例えどれ程女性の弟を救って遣りたい、と思った所で組織の役に立たねば助ける意味は無い。
単に助けたいと自らの慈悲だけで動くのならば役に立つか否かは問題では無い。しかしオルヴァスはメルヴァントと命を共にすると心に決めており、一人の少年を救うと言う正義の為だけに其の固い契りを違えるつもりもない。其れに、家庭も持たず組織を束ねる事に奔走して居る一人身男の元より、組織内部で利用する方が余程安心である。
「……はい。あの子はきっと貴方方の御役に立てると思います。」
強い語調でそう言った女性は数日の間に処刑される身とは思えない程、強く気高かった。どれ程の苦境であっても、人としての尊厳だけは忘れてはいない。そんな女性の姿がアズリータを思い出させたのかもしれない。
「……では貴女の願いを聞き入れましょう。」
「…っ、オルヴァス様。私は納得出来ません。」
「そうです。神の存在しない世界の創造を志す我等に神々の使徒等、矛盾ではありませんか。」
其れまで口を挟む事無く女性とオルヴァスの話を黙って聞いて居た組織の青年達は、オルヴァスの方針に強く反対した。
「君達の言い分も分かって居る。だから彼を私の従者として扱った上で、彼に何の見込みも無いと判断すれば、煮るなり焼くなり君達の好きにすれば良い。」
組織の二人は黙らざるを得なかった。オルヴァスが女性ばかりでは無く、自分達の言い分を分かった上で彼女の願いを受け入れた事に、何の不満も抱かなかった。否、抱けぬ程に彼は後先を良く考えて居たのだった。
「…あっ、有難う御座います。…有難う御座います。」
女性は頭を垂れ、泣きながら礼を言った。此れでもう何も思い残す事は無い。自分が処刑されて此の世から居なく成った後も、弟は十分に生きて活ける。其の事実だけで十分であった。
思い返せば弟には何時でも苦労を強いて来た。貧しい平民の身分では一日を生き抜くも必死である。彼女は何とか幼い弟を養う為に、自分の身を売って生計を立てて来た。其の為、家を空ける事が多く、弟は独り孤独に耐えて居たに違いない。あるいは忍び難い空腹感、無力感にも襲われた事だろう。
しかしそんな日々にも漸く終わりが訪れるのだ。弟の我慢の対価にも成らないだろうが、最期に家族として自分が成すべき事を果たせる。其の事実が在れば彼女は何も苦しくは無かった。
「本当に、有難う御座いました。」
深々と一礼した女性は此の世に何の執着も無い、晴れやかな面持ちをして居た。其れは今際の際の人間の美しい姿であった。
***
女性の姿は幾重にも連なった砂山の向こう側へと消えて行く。オルヴァスが其の揺らめく陽炎を見つめて居ると、優美で可憐なアズリータの姿が彼の脳裏を掠めた。
斜陽に煌めく粉塵が儚げに舞い散る。其の先のアズリータの影に手を伸ばしても、其の手が彼女の艶やかな髪に、柔らかな肌に触れる事は無い。甘美な彼女の微笑が幻影にすぎない事を思い知らされる様で、胸が軋む。
先刻、自分の前で必死に成って懇願して居た女性の姿がふと思い出された。其れだけでは無い。恭しく、興覚めする様な過剰の敬意を向ける部下や組織の者達、自分が歩くだけで平伏し、機嫌を取り、媚び諂う者達の人相が漸次、鮮明に浮かんで来た。
そして彼は無性に孤独感に襲われた。変わって仕舞った悲しみ。否、変わったが故に知った寂寥。オルヴァスは騎士として一心不乱に剣を振るって居た頃が妙に懐かしく成った。あの頃は皆が皆、神の為に戦う事が使命と信じ、必死に鍛錬を重ねて居た。父親の様なヴァイゼン公に、頼もしい兄の様なアジィールにシャレール。清らなアズリータは何時でも騎士達の元に来て、献身的に自分達を支えてくれた。そんな光景。当たり前に、何時までも続いて行くと思って居た日常には、息苦しく成る様な敬意や尊敬、恐怖に恐れおののき譲歩する人間の姿は無かった。皆、其れなりの幸せを精一杯噛み締め、幸せに満ちて居た。
しかし今、自分の居る環境にそんなものは欠片も無い。新たな世界の為に、のた打ち回って来たが結局の所、得られたものは地位や名声。何時かは揺らぐ儚いものばかりであった。其の何処にも幸せは無い。喜びや歓喜、仲間や安心感等はとうの昔に失って仕舞って居た。そんな事にたった今気付いたのである。
自分は決して偉くはない。世界の命運を覆せる程力も、友の過ちを正す勇気すら持ち合わせて居ない。世界の中の小さな存在でしかないのだ。其れを今の今迄忘れて居た。何かに成り代わろうとして、自分こそが世界を変えられると血眼に成って迷走して、沢山殺した。数えきれない程の尊い命を其の手で殺めた。そして取り返しが突かない程落ちぶれた今、そんな単純な事に気づいたのである。
オルヴァスは広大な砂漠を遠い目で見つめた儘、自分自身を嘲笑した。如何して此れ程、簡単な事に気付かなかったのだろうかと思うと、自分の其れまでの行為が馬鹿々々しかった。
一頻、自分を嘲笑うと胸が清々しく成る所か、再び虚しさに苛まれる。自分が気づかぬ内に何よりも自分が変わり果てて居た。もう昔には戻れない。唯、自分が誤って選択した道しか彼の前には残されてはいなかった。誰も止められない程の力を手に入れ、自分と同じく傲慢になり下がったメルヴァントと共に、衰退の運命を共にする事。彼にはその道を選ぶ事しか残されていない様に感じられた。
神と言うものは案外、実在するものなのかもしれない、オルヴァスは何気なく感じた。偶然とも言い難い女性との出会い、そして約束。自分の傲慢さに神が罰を与えたとしか思い様がなかった。
しかし自分も自分である。何故あの女性の個人的な願い聞き入れたものか。と自分に呆れる一方で彼は確かに気付いて居た。女性の雰囲気が身を焦がす程に熱く、消えかかりそうな蝋燭の火の様に繊細で、燃え盛る様な恋心を抱いたアズリータに似ていたから。たった其れだけで自分は彼女の途方も無い願いを叶えて遣ろうと思ったのである。全く自分は馬鹿である。恋は盲目とは正しく其の通りで、熱い想いは時として人を狂わせるのだ。其れは悪夢の様であり又、麗しき夢の様な出来事であった。
***
今日、彼を訪ねた女性ヘリエル。気品に満ち、妖艶な彼女の姿は雰囲気だけでは無く、其の見た目もアズリータと瓜二つであった。彼女との出会いはオルヴァスに、アズリータへの恋情と彼女の犯した罪の様な死に様を思い出させる。そして此の出会いは、彼の聖戦以後の行いを律する様に、時々脳裏に現れて彼自身を苦しめる事に成るのであった。
***
名も無い砂漠地帯の陣営から組織の本拠地に帰還したオルヴァスは、彼の地での顛末をメルヴァントに上奏した。無論、ヘリエルの弟を自らの従者として組織で受け入れる旨も含めて。
「……と言う訳で御座います故、どうぞ御見知り置きを。」
軽く膝を折って頭を垂れたオルヴァスをメルヴァントは疎ましく見つめた。
「…くだらない。能も無い愚図ばかり集めて、貴様は一体何をして居るのだ。役にも立たぬ少年の命等誰も惜しくは無い。我等に必要なのは唯一つの世界、神々の居ない楽園だ。」
メルヴァントは大袈裟に息を吐き、
「我等は此の地から世界を変えるのだ。偽りの神話の元に造られし世界の摂理を正す。其の為に私は強大な力を振るう。恨んでも恨み切れないあの日の復讐を果たす為に。」
物々と呟く彼の表情には影が射し、彫りの深い彼の横顔は悪魔を思わせる様な異形さを漂わせて居た。頬に描かれた幾何学の紋様が其の顔を醜形なものへと変化させる。其の姿は正に邪悪其の物であった。
オルヴァスは遠慮がちにメルヴァントを見遣り、絶望する。彼の目に映ったのはあの慈悲深く、友想いの優しいメルヴァントでは無かった。殺気に満ち溢れ、疑り深く、人を殺める事も厭わない、傲慢な悪魔。其れが今のメルヴァントであった。否、此の悪の指導者はメルヴァントでは無い。彼が狂酔した邪神が彼の身体に乗り移って居るのだ。
其れは確かにオルヴァスの目の前で起こった。
***
ベスタルクを出て大海原を帆船で駆けて居た日々は、長い長い旅路に時間を持て余して居た。
新たな旅への期待と不安、故郷への愛着に後ろ髪を引かれる思いで何とも言えずもどかしかったあの頃。もう少し毎日を丁寧に生きて居たならば今の様には成ら無かったのかも知れない。オルヴァスは近頃、後に組織の拠点と成る島に出会ったあの頃を思い出してはそんな事を思って居る。
ふと目を閉じれば今まで生きて来た数々の瞬間が鮮明に思い出される。あれは確かとても日差しの強い、暑い季節の出来事であった。
クォルド海は其の美しい水面に日の光を享受して、光り輝く絨毯の様に煌めいて居た。真っ白な帆を持つ帆船が潮風を勢い良く斬って、大海原を滑って行く。
甲板で潮風を浴びながら辺りを見渡すと、其処は一面の海で島の一つも見当たら無い。青い空と青い海は眩いばかりに輝いて、目が眩みそうに成る。海上では毎日風に当たって何も考えず唯只管、海を眺めて居るのが日課であった。澱みの無い透き通った水が聖戦で傷付いた心を洗練して行く様で、何とも心地良かった。
其の日もオルヴァスは何時も通り甲板に出て風を全身で感じて居た。彼の故郷では感じられない潮の独特な匂いが至極気に入って居たのだ。
「……。」
直ぐ側でメルヴァントの声が聞こえた様な気がしたが、帆船には他にも乗客が在った為オルヴァスはさして気にも留めなかった。しかし次の瞬間、
「力を求めよ、異端の心を持つ者よ。私を其の脆弱な体に受け入れれば、御前は絶大な力を手に入れる事が出来よう……。」
常軌を逸する大きな声と異常な内容に彼は思わず声のした方を見遣った。
しかし其処にはメルヴァントがたった一人甲板に立って居るだけで、他の者の姿は何処にも無い。だがメルヴァントの様子は妙に可笑しい。誰も居ない方向を向きながら難しい表情で何やら呟いて居るのだ。其れに先程の声はメルヴァントのものとはかけ離れて居た。
不可解な状況にオルヴァスは益々興味を惹かれる、林立する帆柱の影に身を隠し、メルヴァントの様子を垣間見た。
「君は私の心が分かって居たのだな……。神を捨てたにも拘らず、邪神を崇める矛盾を犯す私の心の内を……。願って止まない世界への果て無き欲望すらも……。」
オルヴァスの居た場所からは波の音に掻き消され、メルヴァントの声は届かない。しかしながら彼の憑き物の取れた様な晴れやかな表情は聖戦以後、オルヴァスは目にした事が無かった。
其の狂信的な悪魔崇拝ぶりからも窺い知れる様にメルヴァントの心は聖戦ですっかり疲弊し切って居た。貴族階級の気品と才智に満ちた知的な風格は枯れ果て、今と成っては神経質で、窶れて目の据わった暗い雰囲気が彼の人相を作って居る程であるから其の深い負の感情を推し量る事は出来ない。
しかしオルヴァスが見た彼は何か良い事でもあった様な悟り切った清々しい顔をして居た。其の表情は澄み切った空も相まって美しく儚げであった。
彼に何があったのかは定かでなかったが、友の久しく穏やかな面持ちにオルヴァスは嬉しく成った。だが嬉しい筈の出来事に、素直に喜ぶ事が出来ない自分が居る事も確かであった。
彼の澄み切った様な美しい表情にオルヴァスは何処と無くメルヴァントとの距離を感じて居た。其れは全てを許し、恨みや怒りの感情を捨てた様に見えるメルヴァントと未だに聖戦で大切な人を失った、と言う絶望的な感情を胸に宿し、消化し切れて居ないオルヴァスの心の距離であった。
何を志し、何を夢見てもあの日の地獄の様な光景が彼の脳裏から離れる事は無かった。生まれ育った郷里を失い、慕って居た者達を失い、愛する人を失って、そして国すら守る事が出来なかった無念。騎士としての誇りと人間としての尊厳を奪われ、自分自身を軽蔑する日々。奈落の底に突き落とされた様な状況で一縷の希望すら抱く事を知ら無い。戦乱とは、人間とは、国家、文明、歴史、そして神々とは一体何であろうか。其のどれもに永遠など決して無い事を悟った時、彼の生命の灯は消えかかりそうな程に小さく萎んで仕舞った。在りもしない恒久の為に何かを成す事等、愚かで馬鹿々々しく思えた。
そしてそんな死人にも似た感情を抱いた自分自身に絶望を感じて居た。だからこそ心の何処かで常に、メルヴァントと決して交わる事の無い運命の流れの様なものを感じて居たのだろう。メルヴァントの様に悪魔崇拝を行う事で、聖戦で痛んだ心に施しを与え、何処かで諦めを付ける事等出来なかったのだ。自分自身への対応の差異が彼の心底に澱んで居たのだ。
「如何か私に貴女の力を御貸し下さい。」
甲板からは恭しいメルヴァントの声がオルヴァスの心中を思い遣る事無く聞こえて来る。
独りでに跪き、宙に手を差し出す。其の様子はまるで貴婦人に愛を誓う騎士の様であった。優雅な彼の所作が姿形の無い女性の姿を描き出す。魅了され潤んだ瞳でメルヴァントを見遣る婦人の表情が目に見える様だった。
メルヴァントの長い睫毛が縁取る瞳が潤みながら揺れ動いた時、彼の身体が目映いばかりの白光に包み込まれた。余りに主張の強い光は彼の姿を隠して行く。
突然の出来事にオルヴァスは目を見張った。思わず目を細めて仕舞う程に眩しい光の巻起こす事象を彼は既に知って居た。其れはバルタでシャレールが其の身を犠牲にして自分を戦地から遠ざけた直後の出来事だった。シャレール自らが愛する全てのものの為に、其の尊い命を賭して神々の使徒としての能力を発揮させたあの時と同じ類の光であったのだ。
神秘的で全知全能、此の世の果てまでを見据えて居るかの様な鋭くかつ包容力のある光。誰もが己の無知を恥じ、決して抗う事の出来ない運命を知る様な輝き。其れは確かに神懸かった何かを感じさせた。
メルヴァントを包み込んだ光は急速に弱まり、やがて彼の胸の辺りに吸い込まれて行く。
弾かれた彼の身体には呪符の様な物が全身に張り巡らされて居た。其の奇妙たる事、思わず目を背けたく成る様な異常さが漂って居る。其れだけでは無い。あれ程までに美しかった彼の金色(こんじき)の髪は光すら享受しない無機質な硬質で漆黒の物に。瞳の奥はありとあらゆる怨念の籠った様な曇天の様相で、一切の光を映し出す事をしない。また色の白い肌も何処と無く痩せ細り、不健康そうな青白い顔色へと様変わりして居る。其の為もあってか彼の表情は全体的に暗く、其処に先程までの美しい微笑を湛えた彼の姿は何処にも無かった。唯、其処に木偶人形の様な、慈愛や優しさと言う人間の感情を失った冷たいものが存在して居た。
其処に居たのはメルヴァントでは無かった。彼の身体をした悪魔、とでも言うべきだろうか。狂気の眼差しで白い歯を見せ、気味の悪い笑いを浮かべる彼は邪悪な何かが其の身に宿った様だった。
オルヴァスは背に気持ちの悪い汗が流れて行くのを感じた。と同時に友の美しい心の全てが眼前の悪魔によって食い散らされた事に強い怒りの感情を覚えた。しかし自分に何が出来るのだろうかと考えた所で彼には自分が成す術も無い事を良く理解して居た。友の過ちを正す事すら出来ず、寧ろ鼓舞する様に誤った方向に導いて行くのは何時でも自分であった。そんな自分への贖罪、其れが彼と運命を共にする事。例え其れが明らかな破滅への道であったとしても、彼は止めない。止める勇気も、強さも持ち合わせて居ない自分が唯一出来る選択、其れが彼の全てを受け入れる事であった。仮に世界中を敵に回そうとも。
雲一つ無い晴れ渡った空の元、オルヴァスが下した決意であった。
***
其の背に有象無象の怨みと復讐の念を背負い、妙な貫禄のあるメルヴァントを遠い目で見つめた。もう彼は永遠に自分を友と呼ぶ事は無い。あの溌剌とした青春の光も、恋に焦がれて寝られぬ夜も二人で過ごした輝かしい日々は遠く彼方へ消え去って行く。其の悲しき情景が目に見える様で、御互いに離れて行く心を暗示して居る様でもあった。
メルヴァントは如何して悪魔の様に成って仕舞ったのだろうか。また何時、人としての喜びや悲しみを失って仕舞ったのだろうか。
自分は一体何時から親友をそんな目で見つめる様に成って仕舞ったのだろうか。
***
美しい薄桃色の花が太い幹に満開に成って人々を見下ろして居る。月明かりに照らされた小さな其れは微かな風にも儚げに散り、優雅にそして清らに宙を舞う。
弱々しい光を宿した燈篭に、石造りの階段に、小さな花の花弁が積もって小ぢんまりとした山が出来上がって居る。咲く花の頼りない可憐さに溜め息を吐いて仕舞う程美しい。触れるだけで壊れて仕舞そうな花の大木に其の身を開く姿は圧巻であった。
誰もが愛でる其の花の淡い光に包まれてオルヴァスは唯一人、佇んで居た。
今宵はヘリエルの処刑の日。刑場一帯には温かな時候の麗しい花が、憎たらしい程に美しく咲き誇って居た。
其の姿はまるでヘリエルを映し出して居る様で、彼女の一生とが儚さによって花と結び付けられる。彼女の為に用意された様な鎮魂の華の様であった。
オルヴァスが見た事も無い美しき花に目を奪われて居る側で、清らかな花を天蓋にして狩る宴が催されて居る。如何やら名も無き東国の者達は此の花に執心し切っており、其の愛で様は狂信的でもあった。しかしながらオルヴァスには何と無く彼等が此の花を愛しんで止まない訳が理解出来る様な気がした。其れ程までの美しさと魅力を感じさせ、見る者の心を奪う巧妙さすら感じさせるのだった。
しかし此の宴が単なる花を愛でるだけのものでは無い事は直ぐに明らかと成った。何故なら此の広場には仰々しい程に朱色に塗られた断頭台が闇に聳えて居るからだ。罪人に裁きを下すには華美が過ぎる程の装飾が施され、直接人の首を掻っ切る鋭利な刃は松明の光に照らし出され、恐ろしい程に煌めく。そんな場所で人々は談笑しながら祝杯を上げて居た。今年も美しい花が咲き誇った事への喜びと、大罪人への処刑を祝して。
此の大罪人とは無論ヘリエルの事である。
「漸くあの悪女が刑に処される。今日此の日をどれ程までに待ち侘びた事か。」
「…あの女の悪事を鑑みれば断首は生ぬるい気もするが…まあ良いだろう。いずれにせよ此の世界から消えて無く成るのだ其れだけで十分だろう。」
口々にヘリエルの言われもしない罪を罵り、愚弄し、嘲笑う者達の姿は大層醜かった。眉を顰め、大袈裟に毛嫌いした表情を作り、陰口を叩く其の口は醜い程に歪んで居た。
オルヴァスはそんな者達を視界の片隅に捕えながら、処刑台をじっと見つめて居た。世界から取り残された様な侘しさを感じながら、愛する人と瓜二つの女性の最期を見届けようとして居る。何時だって自分には何も出来ない。そんな風に感じると今まで目の前で失って来た命が無間地獄の様に彼に追い打ちを掛けて行くのであった。
「…出たぞっ。」
何処からか大きな叫び声が上がった。と同時に処刑台の傍にヘリエルが現れる。処刑人に連れ添われ弱々しい足取りで断頭台へ歩みを進める彼女は、悲しい位に痩せ細り、美しかった面影など微塵も無い。別人の様に成って居た。
此れにはオルヴァスも愕然とした。彼女の姿からは日々の酷い拷問の跡が窺い知れる。言われも無い罪に此処まで歪められて仕舞う等、どれ程までに悲しく辛かった事であろうか。以前監獄に収容されて居たオルヴァスには彼女の苦しみが少しばかり理解出来る様な気がした。
処刑人に導かれて殺気漂う刃の前に連れられるヘリエル。其の表情は暗闇に紛れて良く見えない。無論オルヴァスの居た場所からは距離があって彼女の影の差した顔等、見る事が出来なかったが、何となく銀色の雫が花弁の如く散っている様に感じられた。
「…早く刑を執行しろ。」
そんな怒号を合図にヘリエルは断頭台に其の細く白い首を掛けた。人を喰う刃が彼女の首目掛けて一直線に走る。
「……。」
其の刃が確実に彼女の首を捕えた時、刑場は静寂に包まれた。燈篭の灯は霞み、風さえも其の瞬間だけは止んだ。全ての動きが停止して一瞬が永遠の如く長く感じられた。
「…あれを見ろっ……。」
重々しい何かが地面に落ちる音と共に、そんな声が静寂を裂いた。直後、民衆の大歓声が巻き起こる。
無慈悲な刃物からは淡々と血が滴って居る。人を殺める事に長け、戸惑う事もせず其の刃は確かにヘリエルの首を貫き、一瞬で其の命を奪った。
紅く美しい花が妖艶に散った。其の美しさを誰からも認められる事は無く、唯ひっそりと。一輪の花が処刑台の足元に花開いた。
オルヴァスは唯、其の無情なる光景を呆然と見つめて居た。幾千もの木々の下で彼の頬は静かに濡れて行く。今し方降り始めた雨のせいであろうか。否、其れは確かに彼が数年間其の存在すら忘れて居た、悲しみの雫。溢れ出す感情の形跡。
彼は思いがけず溢れた涙に戸惑いを隠しきれず、無常を感じさせる木の下で静かに泣いた。愛する人を失ったあの日の様に。
***
オルヴァスは刑場を黙って去った。其れ以上其の場に留まって居ると、溢れ出した感情が自分を乱して仕舞う。そんな何時も詰まら無い事で虚勢を張る。
感傷的な気分で暫く其の場に立ち竦んで辺りを見渡すと、彼方の暗闇に小さな塊が蹲って居る。其の正体が妙に気になり、歩み寄ってみると、其処には未だ年端も行かない少年が小さな身体に顔を埋めて居た。
少年は激しく嗚咽を漏らし、豊かな銀色の髪を乱して居る。深い悲しみが此方にも伝わって来る様だった。途方もなく悲しい、そんな感情が黙って見て居たオルヴァスにも込み上げる。
オルヴァスは自然に少年の元へと歩みを進めて居た。見なかった事には出来ない雰囲気が少年からは漂っており、少年とオルヴァスが此処で出会うのは必然であったかの様だ。
突然、月明りの美しい空から涙の様な雨が点々と降り始めた。其の小さな滴は泣きじゃくる少年の身体を少しずつ濡らして行く。光り輝く銀髪は雨に打たれて一層の輝きを放ち、神秘的な様相を呈して居る。
オルヴァスは此の悲しみに暮れる少年こそがヘリエルの弟である事を無意識の内に悟って居た。其の上で予め定められて居た運命の強大さに絶望感を抱いた。
少年の背には言い尽くし難い程の悲しみが伸し掛かって居た。オルヴァスは彼の姿に聖戦で全てを失った自分との境遇を重ね合わせて居た。そうして居ると其の少年が無性に可哀想に思われた。同情など好きでは無い。しかし其れ以上にどんな言葉も見当たら無かった。唯一の家族である姉を失い、刑場での地獄と人間の心の醜さを目の当たりにした少年の人生がまるで自分の歩んで来た道、其の物の様であったのだ。自分と同じ運命を辿らざるを得なかった少年が至極可哀想であった。
オルヴァスもまた唯、雨に打たれながら少年の傍に佇む。悲しむ少年に何もして遣れぬ儘、呆然として居る。否、彼自身数年、慈愛の心を忘れて居た為に泣き叫ぶ少年に何と声を掛けて良いのやら分から無かったのだ。
「…少年。」
やっとの思いでそう言葉を発すると、膝を抱えて泣いて居た少年は大きく身震いした。恐ろしく暗い男が一人雨に打たれる姿と、其の重々しい声に驚いたのだ。
「…君は、神は弱い者を救わない……そう思うか?」
思い掛けない一言に少年は泣く事も忘れてオルヴァスを見つめた。
少年の頬には涙の跡が幾重にも見受けられる。暗闇の中に燦然と輝く瞳は此の世の穢れを知ら無い純粋さを持ち、色白の肌が照り雨の中で美しい輪郭を描き出して居た。
其の顔にオルヴァスは驚愕した。余りの驚きに自分の目を疑った程である。何時かヘリエルに出会った時と同様の衝撃が彼の全身を駆け巡った。
「君は…。」
思わず言葉を失う。オルヴァスは唯、口を力無く上下に開閉し、其れ以上言葉を紡ぐ事が出来ずに居た。
其の悲哀の少年の透き通る様な銀髪、潤った瞳の純粋無垢な輝き、其のどれもがまるでシャレールの様な風貌だった。衣装は東国の成りをして居るものの、雪の様な純白さを秘めた肌や何処と無く華奢な四肢はシャレールから取って借りた様であった。
オルヴァスは異様な既視体験に身震いした。そして運命や必然的な何かに恐れを抱くと共に、此の不可思議な出来事の数々は自分への罰の様に感じられた。他人の命を奪う事を厭わ無い無慈悲な心に、此の世界の絶対的な摂理とも言うべき神々を冒涜した自分自身に、神罰が下って居ると直感的に感じた。其れまで神など人類が創り出した空虚な妄想だと思い畏れもしなかったが、案外神と言う存在は安易には覆す事も叶わぬ強大な所謂、創造者なのかもしれ無い。
何とも言え無い無力感の中、彼を現実に引き戻したのは言うまでも無く件の少年であった。
「……僕は…化物では無いよ。ちゃんと人間だから……だから…っ。」
オルヴァスに縋り付いた少年は絶望と恐怖に満ちた眼を向けた。
アネモスの名を賜る美しき風体の少年はオルヴァスより遥かに不条理な人生を送って来た様だった。
其れは彼の恐怖に戦く瞳から見て取れる。人間と言うものに怯える憐れな表情は、彼が其れまで受けて来た数多の暴力と軽蔑や差別の日々を物語っていた。
「…僕はね、悪い子じゃないんだよ…悪魔でも化物でも何でも無い。御願い…僕を信じて……。」
少年の慟哭が不自然な程静かな辺り一帯に響き渡る。癇癪を起こした様に激しく、同じ言葉を繰り返す彼の身体を絶望が包んで居た。
オルヴァスは唐突に泣き出した少年を黙って見ていたが何を思ったのか、やがて彼の小さな背中を撫で始めた。其の手つきはまるで赤子をあやす母親の様に優しく、温かい。
泣き喚いて居た少年はオルヴァスの思いがけない行動に次第に穏やかさを取り戻す。
そして彼に直感的に何か通じる所を感じたのか少年は静かに語り始めた。
「…今日は姉さんが殺されました。僕が可笑しな子供だったから……。姉さんは何一つ悪い事なんてして居ないのに。僕が弟だったせいで、姉さんは…姉さんは……。」
少年はオルヴァスが故在って彼の元に居る事等知ら無い。況してや此の無愛想な男が姉の差し向けた者である事等、知る由も無い。
拙い言葉が其れまでの深い悲しみの出来事を精一杯に伝える。オルヴァスは何とも言えない気持ちに成った。
赤貧の生活、命の危険に晒される日々、階級による支配が理不尽な境遇を生む毎日。何も救い等無かった。其れは全て自分が妙な名を持って生まれたが為。少年は心の何処かで自分を責めて居た。
一日を生きる為に姉が其の美しい髪を売って居た事、何処の者とも分からぬ輩に身体を売って居た事。姉は何も言わ無かったが彼には全部分かって居た。子供の勘と言うものは存外鋭いもので、少年は姉が自分の為に酷く辛い境遇を耐え忍んで来た事位、見透かして居た。
分かって居たからこそ苦しかった。郷里でも稀に見る美しい風貌の姉が窶れて、みすぼらしい、見るに耐え無い姿に成って行くのが見て居て辛かった。
生きる意味すら見失いかけて居た彼に唯一の家族が残したのは、酷く辛く、苦しい時は神が見守って下さって居て、何時か必ず救いを与えられる、と言う言葉だった。毎日其の言葉だけを信じて生きて居た。どんなに惨めでも、理不尽であっても此の言葉があれば何とかやって行かれた。
しかし実際の所、現実はそう甘くは無かった。どれだけ神を崇めて日々を精一杯生きようとも、救いは愚か、ますます窮地に立たされて行く。少年の中で姉の言葉に対する不信感が少しずつ芽生えて行った。そうして居る内に、ヘリエルは豪族達から恨みを買って無実の罪を着せられ、刑に処された。彼女が神に救われる瞬間など一度も無かった。共に生きて来た彼は少なくともそう思って居る。
「…もし君が此の世界の理不尽に泣くならば、其の小さな手で救いを求める者達が等しく救われる世界を創ってはみないか?」
少年の話を聞き終えたオルヴァスは唐突に言葉を発した。骨の髄にまで響く様な重々しい声が反響する。
「神など存在しない、誰もが幸福を求められる世界…此の世の不条理に泣く者の居ない世界を共に創ろうではないか。……君の様に神を信じられ無く成って仕舞った者達の集う、我等の組織で。」
オルヴァスは少年に手を差し延べた。
小さなシャレールは青い宝石の様な瞳を大きく見開いた。此の世界に自分に助けの手を差し延べる者が居る事等、生まれて初めて知ったのだ。小柄な身体は大いに動揺した。しかし迷う事無く静かにオルヴァスの手を取った。
絹の様な肌触りの美しい手が歴戦の厚い手に触れる。少年は偉大な温かさを感じた。心の休まる安息、穏やかな眼差し、其のどれもが初めての事で少年は唯々嬉しかった。
「…誰かに慈悲を受けたのは貴方が初めてです。」
立ち上がった少年の頬を今度は嬉し涙が濡らした。曖昧ではあったが確かに心が融かされて行く感覚があった。今まで感じた事の無い温もりが左胸の奥に宿る。そんな不思議な感覚が何だか物凄く嬉しかった。初めて人間として認められて様なそんな気分だった。
「…そうか。……だが私は決して心優しくは無いぞ。其れでも付いて来られるか。」
「……はいっ。」
曇天の空を晴らす様な勢いで軽快な声を上げた。もう何も怖いもの等無かった。オルヴァスの不器用なまでの優しさがあれば。
「君、名は……?」
「……リマイアーと言います。」
オルヴァスは了解した意を伝える為だけに深く頷いた。
「そうか…。良い名だな。」
其の表情が何処か穏やかで満足げだったのは夜闇のまやかしだったのかもしれない。
***
澄み切った空は何時に無く穏やかな海を映し出して居るかの如く青々と輝いて居る。所々に白波の様な千切れ雲が点在し、風に乗って揺れ動く。
あれから更に数年の時が経った。
メルヴァントの君臨する此の組織は今ではすっかり世界中に其の名を馳せて居る。至る所に組織の者達を介入させ、幾つかの国々すらも支配下に置き、着々と勢力を拡大して居た。一方、オルヴァスが引き取ったリマイアーは其れは其れは聡明な少年に育ち、又あらゆる剣術や武術の才を認められ若くして組織の幹部に取り立てられた。
しかしながら刻一刻と移り変わる世の情勢の中、外界に広がる自然だけは唯、悠然と佇んで居る。此の世界に元より存在して居たものには永久不変の呪いでも掛けられて居るかの如く、穏やかな時間が流れる。
建物の装飾によって切り取られた無機質な空を呆然と眺めながら、オルヴァスはそんな事を思って居た。
彼はメルヴァントの鎮座する玉座の傍へ跪いて居る。先刻遣って来た何処かの国の領主が貢物を持って、富と名声と権力に溺れた厭らしい表情でメルヴァントに媚びを売って居る。彼等の遣り取り等オルヴァスには興味が無かった。在るのは何とも言えない空虚感や寂寥。
夢と希望を胸一杯に宿してシャルティネの町へ遣って来た時から十年も経っていない。其れにも拘らずオルヴァスの心はまるで老人の様であった。酷く心と身体が重い。時に妙に昔の時分が懐かしく思えて、眩い光に満ちたあの日の事を思い出しては、物思いに耽る日々の連続である。一方のメルヴァントは不死の薬でも飲んだのかと疑う程に若々しく活力に溢れて居た。其の風体もオルヴァスが出会った当初と大きな変化は無い。違うのは異形の仮面や怪しげな衣装を纏い、剣を遣った右腕が欠如して居る位だろうか。
果たして何故こんなにも違って居るのだろうか。オルヴァスは疲れ切った思考でそう思った。騎士に成る事を志して共に切磋琢磨し、波乱の時代も片時も離れず乗り越えて来た友にも拘らず、如何してこんなにも違いが生まれたのだろうか。何時までも変わらず若々しいメルヴァントに少しの羨望を抱きながら、何時自分が道を違えて仕舞ったのかを只管に回想して居た。
しかし思い当たる節等無い。どんな状況であっても日々を精一杯生きて来たつもりである。仮にそんな彼の人生に一つだけ誤りを見出すのならば、メルヴァントの傲慢な企みを止める事が出来なかったあの日。あの瞬間には少なからず間違いはあっただろう。彼の心の弱さには若干の非がある。しかし其れを今更後悔した所で如何にか出来る筈も無く、途方に暮れる他無かった。
オルヴァスは焦点の合わない眼で呆然と、メルヴァントと領主との気色の悪い笑みを眺めて居た。絶え間無く動いて行く世界の中で歯車の止まった人形の様に、此の世界から隔離された様なもの寂しさが胸を包んだ。
***
メルヴァントから数刻の暇を出され、組織の塔の中を行く宛も無く彷徨う。
「…オルヴァスさんっ。」
金管楽器の様な軽やかで華やぎのある声が彼方から聞こえる。静寂に包まれた石造りの空間に其の声が反響する。
オルヴァスが徐に振り返ると其処には案の定リマイアーが此方に駆けて来る姿が在った。
振り返ったオルヴァスの姿を眼に見留めると、リマイアーの瞳が慕わし気な人への眼差しに変わり、数多の光を享受して輝きを放った。
そんな眼に見える素直な反応を示す健気な姿が微笑ましかった。部下の教育には言葉の鞭と暴力を欠かさなかった彼が唯一其れ等を一切用いなかったのがこのリマイアーである。其れだけ彼を大切に思って居たのである。アズリータと瓜二つのヘリエルに生前任されたシャレールの様な風貌の少年だからであろうか。もしそうならば何と身勝手な理由であろう。しかし彼は何だか満足して居た。失ってばかりの彼が手に入れた一縷の希望、其れがリマイアーであったが故に。
彼の将来は有望であろうとオルヴァスは直感的に感じて居た。少なくとも自分の様に道を違える事は無い。彼には其れだけで十分だった。誰かが自らと同じ過ちを繰り返す事を望んでは居ない。
しかしながら少年も後に此の世界の抗えぬ神話の道に巻き込まれて行くのであった。
***
世界は途轍もなく無慈悲である。
オルヴァスの途方もない悲しみも、メルヴァントの見た真実も、リマイアーに待ち受ける試練も、広過ぎる世界では知る者等誰も居ない。唯、無情な世界は続いて行く。
大河や雲は素知らぬ顔で悠然と風に乗って流れ行く。
歴史は繰り返され、栄枯盛衰を重ねて流転して行く。
例え世界が狂い、人間達が醜い欲望の為に争い合ったとしても、此の世は決して終末を迎える事等無い。
***
世界は時に穏やかに、そして時に残酷に我々に微笑み掛けるのであった。
完
裏切りの神話と抵抗の物語 後編
遂に完結致しました。
お付き合い頂き、ありがとうございました。
この物語は次作へのバトンともなるので、そちらの方もご覧頂けるとより一層両作の深みが増す事と思います。


