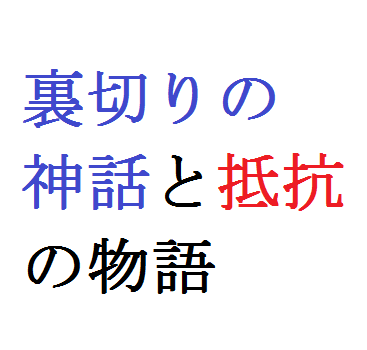
裏切りの神話と抵抗の物語 中編
「裏切りの神話と抵抗の物語 前編」の続編です。
第三章 大乱の果てに
南半球最大の戦乱が幕を開けた。舞台はラプタス南端ミグル地方。此処は険しい断崖に囲まれ、死の砂漠と呼ばれる動植物が一切生息しない大地が広がっている。自然の色合いが欠如したミグルは褐色の世界が唯広がっているのだ。
そんな特殊な土地にラプタスの騎士団は首都シャルティネから十日間馬を走らせやって来た。大勢の騎士を率いるラプタス軍が枯れた砂漠を駆けると、視界には砂埃が一面に舞う。敵の姿は全く見えない。無論敵からも見る事が出来ないのだから、地形を上手く利用すれば敵軍を誘き出す事も出来る。やはり自分達の領内だけあって、此の地方の地理については皆其れなりに詳しかった。
ラプタスの者にとり、此のミグル地方は絶好の戦場であった。
「あぁ、我らが神よ。」
黙々と隊列を成していた騎士の中からそんな声が聞こえた。騎士達は各々剣を抜き大空に向かって突き付け、唯一つの声に呼応する様に叫んだ。
「大海原を生み、大地を生み、そして我らを生みたもうた神々よ。」
「タレファルナの山に宿る七種の神々達よ。」
「いざ戦わんとする我らに大いなる御恵みと御加護を。」
「そして偉大なる神々の御導きが在らん事を。」
大地がうねる様な雄々しい鬨の声が岸壁に木霊する。若者達の熱い思いが神の祈りに込められ、何処からとも無く熱気がラプタスの軍勢を包み込む。タレファルナ山脈とイグリュータ川を描いた軍旗が音を立てて翻った。
「さぁ若人よ、剣を取って立ち上がれっ。」
一軍を率いていたヴァイゼン公の声がミグル一帯に響き渡り、開戦の合図が告げられた。
騎乗の騎士達は馬を巧みに操り四方八方に出撃して行く。怒号にも似た雄叫びを纏って。
猛烈な速さで砂埃を裂く様に進むと、やがて敵の軍隊が見えて来た。噂に由れば小国テノンとオキュロス、タルビーテの三国連合軍はラプタス軍の 三分の一程度の僅かな軍勢で参戦していると言う。大陸全土に其の名を轟かせたラプタス軍の相手にも成るまい。誰もがそう思っていた。
しかし一部の者だけは負け戦にも成り兼ねない圧倒的な戦力さに疑問を抱いていた。何か裏が在るのではないか、と思うのだがラプタスが誇る諜報技術では何も察知して居ない為、如何にも腑に落ちない様であった。其れでも疑う者の中には件の三国の急速な発展と大国の関与を指摘する者も居り、議論は平行線を辿っていた。
三国連合の六芒星の旗印とラプタス軍が激突する。奇襲攻撃を食らう形となった連合軍は狼狽しつつ、必死の攻防戦を繰り広げた。
「ははっ、御前達なんて俺の剣の錆にしてくれるわ。」
得意げに馬上で大剣を振るうアジィールはラシャの平原育ちなだけあって流石に大層強かった。筋肉質な肉体と豪快さが敵を圧倒する。重量感のある大剣を軽々と振り回し敵軍を次々に突破する様子は、誰も近寄り難い迫力を醸し出していた。
「……貴様女か?やけに華奢だな。」
馬鹿にした様な目つきの兵士がシャレールに向かって来る。
シャレールは軽蔑する様な冷たい眼差しを向けながら静かに剣を引き抜く。身軽な彼が敵の背後に回り込み鋭い切先を敵の首筋に向ける。
「油断して居ると痛い目を見るぞ。」
言い終えるか否かの刹那、まるで舞踏を披露するかの様な軽やかな動きで敵を斬った。
飛び散る血飛沫に彼の白い肌が紅に染まる。残酷な眺めではあるのだが、其の姿は艶やかで美しかった。
大剣を肩に乗せ烈風の如く駆け抜けるアジィール。自由に駆ける彼は野性的で、興奮した表情であった。紅の瞳は深い朱色に変化し、緋色に染まった外套が彼の戦果を語る様。
「三国の兵士達よ、此の俺に掛かって来いっっ。」
獅子の様に叫ぶ彼の髪は狂乱し、真っ白い歯が好戦的な彼の表情を一層情熱的に魅せた。
果敢に斬りかかって来る兵士を馬上から圧倒し、容赦なく薙倒していく。
聖戦に参戦し武勲を挙げる、其れは彼が幼い頃より胸に秘めたる夢。砂塵吹き荒ぶラシャの広大な平原で純粋な少年は、彼のアセラ=バスクの英雄譚に何度心踊らされた事か。
ラシャの者は皆、口を揃えて言う。所詮先の短い人生ならば思う存分楽しもうではないか、と。アジィールも其の如く、好きに酒を飲んでは好きに女性と戯れる。其れが儚き平原の猛者達の性なのである。であるからこそ、あの多感な時期に強い羨望を感じ、大切に守って来た幼き日の夢を今、叶えようとして居るのかもしれない。
「勝利は常に我等、ラプタスの騎士団と共にある。」
負ける筈が無いのである。何せ南半球最強の名を賜っているのだから。神は何時でもラプタスの者に勝利を齎し、栄光の道へと誘う。絶対的な真理。 揺ぎ無い神への信仰心は、理論では説明できない感情論に現実味を与える。根拠も無い言い伝えを皆が皆心から信用して止まないのである。
アジィールとシャレールが配属された先鋒隊は流石、選りすぐりの精鋭揃いなだけあって怒涛の勢いで三国連合軍を打ち破って行く。
しかしメルヴァントとオルヴァスが所属している後方支援部隊も勝るとも劣らない実力の持ち主ばかりが揃い踏みしている。主に新入りの騎士達で構成された其の部隊は初々しい爽やかな風を纏い、敵陣中を突破して行くのである。純粋な戦闘心が又、恐ろしい程彼等を強くしている。初めて味わう殺戮の妙な高揚感に若干の狂気を感じるものの、此れこそが神の為に命を投げ出す栄光なのだ、と若人達の胸には素直に受け入れられた。其処に潜む狂信ぶりには未だ誰も気付いて居なかった。寧ろ此の道こそが絶対の真理なのだと信じて止まなかった。
騎乗のメルヴァントは其れは貴族の品性と高潔さを放っており、戦場で敵味方の隔てなく誰も彼の行く手を阻む事等しない。一人ミグルの砂漠を悠々と駆けていく。まるで広大な砂の大地を旅しているかの様。
砂塵の彼方から現れた敵を彼の持つ、先端の鋭利な剣が吸い込んで行く。其れは正しく魔術の様。
メルヴァントの繊細で身軽さを利用した軽やかな立ち回りは、豪快な剣裁きからは想像も付かない程秀麗であった。所作の隅々に渡って貴族らしさが及んでおり、美しかった。
一方のオルヴァスはバルタ剣術を礎として様々な剣を遣った。数多の剣術を状況に由って使い分ける彼は正しく、我流を極めていた。新人騎士の中でも一番の腕前、と名高い。
オルヴァスは戦場で嵐の如く駆け回った。敵の目に突然現れては、油断も隙も無い細やかで几帳面な剣を振るい、早々に敵を倒しては規則性も無く別の敵の群衆に特攻していくのだ。此れがあのヴァイゼン公を唸らせた自由で何にも囚われない彼の剣である。
メルヴァントとオルヴァスの剣術は騎士団に入隊した当初と比べ随分変わった。繊細で貴族の剣を律義にそして丁寧に修業して来たメルヴァントは、アジィールに憧れて大胆な剣を遣う様になっていた。オルヴァスは誰に憧れて、というのは無いのだが以前の田舎育ちらしい豪快かつ獰猛な剣から逸脱した、風流で芸術的な剣術をするのであった。二人の剣遣いは彼らが出会った当初とは入れ替わる様な形で変化していった。
***
普段は平穏かつ無慈悲なミグル一帯は金属の触れ合う鋭い音と、馬が砂漠を駆ける怒号にも似た鈍い音とが混ざり合い、混沌の様相を呈していた。
ラプタスの騎乗騎士達は砂丘を隊列を成しながら越えて行く。閃光の様な斜陽が粉塵に乱反射して微かにぼやけた光を演出している。
血生臭い戦場には三国連合軍の兵士とラプタス騎士の屍が無残にも横たわっている。其の凄惨な光景には似つかわしく無い砂塵の煌めき。其れはまるで神々の鎮魂歌の様で何とも無情であった。
「ラプタス騎士団先鋒隊、今宵は此処に陣営を敷く。明日も激戦に成ろう。今日はじっくりと体を休めなさい。」
先頭を切っていたヴァイゼン公が敵軍の伏兵の有無を確認して、そう告げた。日々厳しい修行に当たっている騎士達とは言え、実戦ともなると疲労の色も窺い知れた。
多くの精鋭騎士が馬を降り、一斉に野宿の支度を始める。
「おおい、シャレール。無事だったか…。」
白馬の影に隠れる様にして体を休めていたシャレールを見つけたアジィールは揚々と声を掛けた。
「なっ、おい、シャレール、其の傷大丈夫なのか。」
彼の白い頬に薄っすらと細い切傷を見たアジィールは柄にも無く狼狽えた。彼は普段は其処まで意識していないのだが、自分が知らない内にこうして傷ついて居る姿を見ると何だか無性に胸が騒めくのである。
「敵の切先が少し掠めただけだ。心配要らない。」
「其れなら良いんだが……。なぁ、シャレール。」
アジィールは腑に落ちない表情を浮かべながら、普段は見せない真剣な面持ちで、
「……俺が居ない所で死ぬなよ。」
言うのであった。シャレールは呆れた様に笑う。まるで今にも自分が死ぬかの様に途轍もなく悲しげな表情をするアジィールが可笑しかった。要らぬ心配をするものだ、と思った。
「…馬鹿だなぁ。私は君が思っているより強いから、そう易々と死んだりはしないよ。其れに、私が死んだら君のふしだらな素行を止める人が居なくなるじゃないか。」
アジィールの心配とは裏腹に何時にも増してきつい冗談を言うシャレールは本当に楽しげであった。
「あはは、そうだな。其れは困る。シャレールが居ないと誰も俺の女遊びと大酒飲みを止めてくれる奴なんていないな。……うむ、此れは深刻だ。」
大袈裟に笑って見せた。実はシャレールを心から頼りにして居る等と素直でない彼が言える筈も無かった。
「本当に、君の尻拭いをする身にも成って欲しいものだ。こんなにもどうしようもない事は無い。」
激戦の緊張から解放され暫し談笑の一時を過ごす二人。明日の苦しみも今日の比に成らない事は分かっている。しかし掛け替えの無い此の一時を無心で過ごしたい、と願って止まないのであった。
***
今朝ミグル地方で幕を開けた聖戦はラプタス軍の優勢で今宵は一時終焉を迎えた。
地の利を生かして戦うラプタスの圧倒的優位な形勢はそう覆らないだろうと誰もが見ている。実際ラプタスの騎士達の士気は上々で未来の勝利を約束する様であった。
アジィールとシャレールの先鋒隊が陣を張った後、後を追う様にして後方支援部隊が陣営に到着した。隊の半数が新入りの騎士で編成されている為か騎乗の騎士達に其れ程の疲労困憊は見えず、血気盛んな若者達が凱旋の如く笑顔を湛えている。
メルヴァントとオルヴァスも何か大事を成し遂げた様な清々しい表情であった。ヴァイゼン公はそんな二人を激励し、早めの休息を促した。
「今日は何だかひたすら駆け回っていた様な気がするな。」
「うん、やっぱり日頃の鍛錬と戦場は違うし、騎乗ともなると慣れない事ばかりで……。」
指定された場所に張られた天幕へと向かいながら、今日の出来事を互いに回想する様に振り返る。
「でも此処でしか経験出来ない事ばかりで、新鮮な気がするよ。」
オルヴァスは躍動する心を落ち着かせる様に大きく息を吐きながら言った。聖戦が貴重な体験である事はメルヴァントとて同じ事であった。
貴族社会に呑まれる様に父親と兄達の威光を着せられて、彼には毎日が窮屈だった。今の自分にはオルヴァスと言う心からの友で同志の大切な存在がある。其れは何にも代え難く、自らの命を惜しんででも守りたいものと成っていた。
だからこそ二人で語り合う此の一時は心休まるものであった。此の儘、連勝を挙げ御互いに生きてシャルティネに帰還したい。ラプタスの今日の形勢に揺るぎは無いだろうとは思って居るのだが、僅かに芽生える不安が彼の心に影を落とすのであった。
「明日も我等に神の多大な御加護が有りますように。」
弱気な感情を紛らわせようと神に強く祈った。
***
聖戦は翌朝不意に始まった。三国連合軍が奇襲攻撃を仕掛けて来たのである。昨日の日没後、三国連合軍は広大な砂漠をラプタスの一軍を追って這う様に進行していたのだ。其れが今朝になり、頃合いを見計らって突撃して来たのである。狙いは軍の総崩れであった。圧倒的な兵力差を前に何としても内部からの崩壊を誘うしか無かったのである。しかし、一体何故そう迄して三国はラプタスに宣戦布告したのだろうか。
陣営を畳んでいた折からの突然の奇襲攻撃に、ラプタス軍は一瞬狼狽えたが各部隊の指揮官が歴戦の猛者達なだけあって其の場は大きな混乱には陥らなかった。
「精鋭部隊、進軍せよっ。」
例の如く鬨の声を上げ、砂埃を巻き上げながら力強く砂地を駆ける。隊列を乱す事無く、規則正しく距離を置いて行軍する姿は最強の名に相応しい。
静かなる砂漠で強靭なラプタス軍と高揚する三国連合軍が激突する。其れは肉弾戦を窺わせる様な激しさを伴う。神の意志でも、其の恩恵でも何でもない大きな力が動き出そうとしていた。
「後方支援部隊、いざ出陣。」
若人達は勇んで出て行った。恐れる事は無い唯、信じる道を前に進む其れだけの事である。
彼等の希望に満ち溢れた瞳を、其の表情をヴァイゼン公が忘れる事は無いだろう。
(明日を担う若者たちに如何か栄光あれ。)
公爵は祈った。彼だけではない。聖戦に参戦しているラプタスの騎士達や三国連合の兵士達、郷国で彼らを案じる者、恋人や家族、幼い子供達。七種神を信仰する人々が至る所で聖戦を案じ、戦場で戦う者達を想って祈った。深く深く、其れはもう強く自らを犠牲にしてでも彼らは祈念した。
祈りを捧げる彼等の誰一人にも心の内に不安があったのではない。聖戦とは光栄極まりないものだ。何せ神の為に命を投げ出して戦うのだから。けれども、彼等の心の奥底に妙な不信感を禁じ得なかった。其れが何故かは誰にも分から無いのだが。
***
ラプタス軍と三国連合軍の戦いは激しさを極めていた。形勢は圧倒的にラプタス側が有利なのだが、小規模の軍勢で押して来る連合軍は捨て身の戦法で必死の戦いを見せていた。其の為にラプタス軍も粘り強い戦線を強いられていたのだ。しかし最強と言う名に誇りを抱くラプタス軍は根気よく戦った。そして先鋒の精鋭部隊は三国の兵士達をラプタス国外へと追い込んだ。
早朝の陣営と言うラプタスには不利な状況を突いて奇襲攻撃を仕掛けたにも拘らず、一瞬で形成を覆された三国の司令官達は一気に混乱に陥った。其の場の兵士達の動向は乱れに乱れ、高まっていた士気は急速に下がって行った。
「おう、三国の輩が引いて行くぞ。」
逃げ惑う三国連合の兵士達を遠巻きに眺めながら、アジィールは大きく笑った。
「南半球最強は俺達だ。大陸の新参者がラプタスに手を出そうなんて百年早いわっ。」
強気に捨て台詞を吐く。撤退して行く三国の兵士達を見るのは何とも壮観であった。
神宿るラプタスの名は此の戦乱を期に確固たる物に成ろうとしていた。
「うわぁ、凄い。此の人達皆、私達と戦っていたのか。」
精鋭部隊に続いてやって来た後方支援のメルヴァントとオルヴァスも混沌たる戦場を見つめ、其々に思う所がある様だ。
「実際戦っていると目の前の敵に集中していて感じる事は無いけれど、いざこうして見ると私達はこんなにもの人達と戦っていたのだ、と……。」
圧巻であった。興奮と不安が渦巻いて一度に溢れ出す。其れが目には見えない感動となって眼前の光景に感涙を誘う。
砂の大地は相変わらず荒廃している。虚空を舞う砂が薄日に吸い込まれ、昇って行く。ミグル一帯は先程までの騒乱が嘘であったかの様に、再び静寂に包まれる。
「メルヴァントにオルヴァスも此処まで来ていたのか。」
彼方を見つめる二人の姿を見つけアジィールは騎乗の儘、無遠慮に声を掛ける。シャレールも彼の後からやって来た。
先輩二人の無事を知ったメルヴァントとオルヴァスは安堵した。二人に限って命を落とすと言う事も無いだろうが、やはり何処かで案じていたのだ。
「二人共、無事だったか?戦場で迂闊に斬られたりして無いだろうな。」
アジィールが傍らのシャレールを横目で見ながら言った。シャレールは恐ろしい程満面の笑みを浮かべて、
「二人共無事で良かったよ。君達なら何の心配も要らないとは思っていたが、何処かの誰かが夜通し君達を案じて寝られないで居たから……。」
爽やかに告げた。嫌味を感じさせない其の表情が返って嫌味たらしい。
アジィールはつくづくシャレールの恐ろしさを実感した。
「…ま、まぁそんな事より折角此処で会えたんだ、アステューク家の御子息君と色男君の戦果を御聞きしようじゃあないか。」
豪快に笑うアジィールを他所に三国連合を偵察していた者が息を切らして駆けて来た。
「申し上げますっ。ラプタス北方バルタ地方の国境沿いで隣国ベスタルクが国内に侵攻を開始しましたっ。」
衝撃の事実であった。其の場の騎士達は戦慄した。
今ラプタス国内の主要な軍力は此処南方のミグル地方に集結している。つまり首都シャルティネや北方のバルタをはじめとする諸々の地方は現在、警備が手薄と成っているのだ。隣国ベスタルクは其の僅かな隙を突いてバルタに攻め込んだのである。
「敵軍の総数は…如何様か。」
ヴァイゼン公が青ざめながら偵察の者に聞いた。
「そ、其れが……数万の大軍と。」
騎士達は愕然とした。数万と言えばベスタルクの軍力の総数に相当する。要するにラプタスを陥落させる為に本隊を動員して来たという事だ。
「何たる事態……。」
ヴァイゼン公は狼狽えた。其れも其の筈、ラプタスの諜報組織は数万と言う大群の動きを一切察知して居なかったのである。戦場の騎士や貴族が知る由も無かった。
ラプタスの騎士達の表情からは先程までの優越感は消え去り、絶望感にも似た負の感情が包み込んだ。
バルタの者達は強い。其れは騎士達も認める確かな事実である。しかし幾ら屈強なバルタの者とて数万の大軍には敵う筈も無かった。無論皆が皆、戦を知る者でも無い。バルタの陥落は明らかに見えている様なものだ。
ラプタスの要塞の役割を果たすバルタが墜ちれば、首都シャルティネがベスタルクに攻め込まれるのも時間の問題であった。ラプタス軍は撃沈した。シャルティネには騎士達の家族が居る。家庭がある。恋人や想い人が居り、友や恩師が居る。彼等が命の危険に晒されるのだ。大人しくして等居られなかった。
動揺した一部の騎士達は、途方も無く広い砂漠をシャルティネ目指して馬の手綱を取った。
「総員、戻れ。持ち場を離れるなっ。今此処で我らが分裂すれば、故郷の家族の命は救えぬぞっ。」
やっとの思いでヴァイゼン公は声を振り絞った。此処で混乱を避けねば、ラプタス軍は二度と戦えない。逸る気持ちは痛い程分かり辛かったが、指揮官としての使命を全うせねばならない。
(私が戸惑って居てはいけない。誰よりも冷静に状況を判断せねば。此の私がっ。)
自責にも似た強い思いであった。失敗は許されない。此の場の騎士達の命と国家の命運は全て彼に託されているのだ。
混乱の最中、騎士や貴族の中にも三国連合が無謀な戦乱を招いた真の目的に気付く者があった。ベスタルクはラプタス国内の軍力をバルタから撤退させる為に三国連合にミグルを攻めさせた、と言う事に。其の由に何とも強い恨みを抱かざるを得ない。
事実、ベスタルクと三国連合は一年程前から内密に手を結びラプタス陥落を計画して居たのである。ラプタスが誇る諜報技術が其の機微を掴めなかったのは、彼等がラプタス周辺の情報網を掻き乱して居た為だ。
シャレールやメルヴァントも此れに気づいた者の一人であった。
「オルヴァス……。」
メルヴァントは彼が案じられた。オルヴァスの故郷は言うまでも無い。家族の無事が心配で堪らないだろうと思った。今にも駆け出して家族を、故郷を守りたい、そう思っているに違いなかった。
「…大丈夫だよ、メルヴァント。バルタの者強い。暫くは持ち堪えてくれる筈……。」
心配を懸けない様、無理矢理に笑った其の目は潤んでいた。
メルヴァントは何とも言えない悔しさが込み上げて来た。友の大事に何の力にも成れない自分が情けなかった。何の為に今まで剣の腕前を磨いて来たのだろうか。
しかしオルヴァスはオルヴァスでメルヴァントの無念が其の表情から見て取れ、辛かった。様々な感情が一度に込み上げ、可笑しくなりそうだった。だが涙だけは流せなかった。友や先輩に心配を駆けたく無い思いと、何としても譲れない男としての自尊心が彼を泣かせなかった。
そんな後輩達の遣り取りを見たアジィールとシャレールは、此の世の無情さをつくづく実感した。とは言え自分達に出来る事も、今は無い。そう思って二人はメルヴァントとオルヴァスそっと見守った。
「此れより大至急シャルティネに向かう。」
オルヴァスの悲しみ等他所にヴァイゼン公が騎士団の指揮を執った。
其の時ふとシャレールがヴァイゼン公に歩み寄り、
「御言葉ですが……。」
珍しく声を張り上げた。
「全軍をシャルティネに向かわせては、バルタは誰が守ると言うのですか。」
「……うむ。其れも一理だな。さればシャレール、君は私に如何せよと。」
「貴方の兵と騎士を僅かばかり御貸し下さい。私が参ります。」
意志の強い目が煌めくと一陣の風が吹き抜けた。
稀に見るシャレールの強い意志表示にヴァイゼン公は応えてやりたかった。無論其れはオルヴァスの為でもある。しかし此処で判断を誤ってはなるまい。戦場では一縷の失敗も許されないのだ。様々な事象が彼の頭を悩ませた。
「…ヴァイゼン公、私に郷里を訪れる機会を御与え下さい。御願致します。」
オルヴァスはシャレールの傍らに立って懇願した。
必死に頭を下げるオルヴァスの姿がヴァイゼン公には辛かった。ラプタスの守護を考えれば彼等の願い出は断わらねばなるまい。しかしオルヴァスの気迫は例え自分が強く言い聞かせた所で、一人で飛び出して行くに違いない事を暗示している様だった。数年間、父親の様に彼を見守って来たヴァイゼン公なら其れ位の事はよく分かる。
「ラプタス騎士団を統括する身としては其の願い出を聞き入れる訳にはいかない。」
ヴァイゼン公の重々しい言葉にオルヴァスは落胆した様に息を吐いた。
「……だが私個人としては君の気持ちは痛い程良く分かる。其れにシャレールの言い分も最もだ。其処で君達には私の戦力を幾らか貸し出すから、バルタを、其処に住む民を守って来なさい。」
父親の様な寛大な優しさに、オルヴァスは大いに感謝した。其の表情は歓喜に満ちている。
シャレールも彼の喜ぶ姿に微笑みを漏らした。ヴァイゼン公への進言が彼を思っての事だとは、シャレールは決して口にはしないであろうが、彼は確かに満足げであった。
「但しオルヴァス、決して私情では動かない事、此れだけは約束してくれ。バルタでの指揮はシャレールに執らせる。彼の指示をよく聞いて、生きてシャルティネに帰還せよ。良いな?」
「はいっ、有難う御座います。」
改めて感謝の意を示し、深々と一礼したオルヴァスの元にメルヴァントとアジィールがやって来た。
「良かったな、オルヴァス。」
アジィールはオルヴァスの肩を力強く叩いた。メルヴァントはオルヴァスの正面に立ち、
「私とアジィールさんはシャルティネに向かう。だから首都の事は気にせず、バルタを確り守れ。私も首都を死守する。離れて居ても思いは何時も君の元にある。其れだけは忘れないでくれ。」
強く伝えた。他にも言いたい事は有る。此れが今生の別れに成るかもしれない。そう思うとあらゆる想いが溢れて言葉にするのも追いつかない程であった。
しかしメルヴァントは掴んでいたオルヴァスの腕をそっと離し、身を引いた。此れ以上傍らに居れば、弱気な事を言って仕舞うだろう。そんな情けない姿は見せたくはなかった。
「……有難う。きっと勝ってシャルティネに帰るよ。」
二人は凛々しい笑みを湛えながら、握手を交わした。
***
ヴァイゼン公の命を受けてオルヴァスとシャレールは即刻バルタへ向かった。公爵から借り入れた兵と騎士は本当に僅かであったが、屈強な者達ばかりであった。其れがオルヴァスには何とも心強かった。
ミグルからシャルティネまでは十日、其処から幾つかの町を経てバルタまでは七日。夜通し馬を走らせてもバルタに到着するのは二週間も先に成る。其れでは益々戦況が悪化するかもしれない。其処でシャレールは知り得る限りの短絡路を駆使しシャルティネに向かった。五日と言う驚異的な速さで首都に入った一行は其処からはオルヴァスの土地勘を頼りにバルタへ向かった。
戦地バルタへ着いたのはミグルを発って八日後の事であった。
戦場と化したバルタにオルヴァスは衝撃を受けた。其処には彼の故郷は無かった。強靭な男達の賑やかな笑い声も、逞しい女性の姿も、愛らしい子供達の姿も何処にも無かった。在るのは誰とも知れぬ屍のみ。
家屋の外壁や地面の至る所に凄絶な戦乱の後とも言える血飛沫が、バルタの町を紅に染め上げていた。遥か彼方には戦火の煙が立ち込め、辺りは恐ろしい程の静寂に包まれていた。
「此れは…一体……。」
オルヴァスは郷国のあまりの変貌ぶりに絶句した。視界に広がる光景が戦乱の凄まじさ物語って居る。
言葉を失ったのはオルヴァスだけではない。無論シャレールも眼前の異様な光景に終始目を見開いている。
(ベスタルクの侵攻とは言え、此処まで酷いとは……。)
彼の中に緊張が走った。偵察の者の焦燥具合から厳しい状況にある事は目に見えていたが、既にかなりの激戦を窺わせる光景に予想外の困惑を感じた。
とは言え何より気に掛かったのはオルヴァスの事であった。故郷の変わり果てた凄惨な姿を前に正気で戦えるとは思えなかった。
愕然として絶望に満ちた眼差しで佇むオルヴァスの元に、負傷したバルタの者が藻搔き苦しみながら擦り寄った。
「あぁ騎士様よ、私達を御助け下さい。此処は…左程酷くは無いですが……町はもう駄目です。」
途切れ途切れに話す負傷の男はオルヴァスに縋る様な目を向けた。
「ベスタルクが侵攻して既に二十日程ですが……バルタの者は皆散り散りに成って……此の辺りも時期に敵軍がやって来ます。」
男の目は半ば強要するかの様にオルヴァスに助けを求めた。其の強い視線にオルヴァスは一刻も先に町へ向かわねば、と気持ちがせった。
一連の遣り取りを見ていたシャレールの元にラプタス軍の紋章を着けた兵士が駆け寄った。彼は明らかに今まで激戦の中で白刃を潜り抜けたのであろう。其の衣装は返り血を浴びて赫々としている。
「ラプタス騎士団の方々、漸く援軍として来て下さったのですね。」
「援軍……?何の話だ。私達はミグルでバルタの窮地を耳にして、たった今やって来たのだ。首都で援軍の要請を受けたのではない。其れにベスタルクの侵攻と言う話を聞いたのも数日前の事だ。」
シャレールが兵士の言葉に驚いて返答すると、今度は兵士の方が困った顔付きに成った。
「其れは可笑しいですね……。我等は騎士の方々が発って直ぐにバルタへ出陣しました。此の件は貴方方も耳にしているものだと……。」
兵士の言う通り全く可笑しい。同じ国内で起こった出来事であるのに、手にしている情報に大きな差異が生じている。
シャレールは嫌な予感を感じた。
「私達が援軍としてやって来る、と言う情報は誰から得た?」
「ラプタスの諜報組織を名乗る者数名です。彼等はラプタスの紋章を身に付けていた為、情報の信憑性は高いものだ、と指揮官が判断しました。」
「そうか、実は私達が此の地の危機を知ったのも諜報組織の者からだった。……如何やら其の諜報組織の者の一部が国内の情報を撹乱させている様だな。」
シャレールは最悪の事態を想像していた。しかも此れが単なる空想では無く、如何も現実味を帯びて来て居る事が何とも恐ろしかった。
「君には未だ聞きたい事がある。其れに此方についても話して置かねばならない事が残っている。しかし私達は此処バルタを守る為にタレファルナを越えて来た。今は戦場に向かう事が先決だ。君に案内して貰いながら、御互いに握っている情報を交換しよう。」
そう言ってシャレールは兵士を馬に乗せた。率いて来た軍勢に前進を促す。
「オルヴァス、此れより戦場に入る。……行こう。」
負傷したバルタの者の解放をしていたオルヴァスはシャレールの声に駆け戻って来た。
「……故郷を如何か御助け下さいっ。」
彼が家屋の陰に連れた負傷者の声だった。見るに堪えない傷を負って居る、とは思えない程の明瞭な声が響き渡った。
オルヴァスは彼の外傷から先は長くない事を悟っていた。だからこそ死に際の人間の強い思いを感じ取り、思わず振り返った。
「此の命に代えてでも、きっと…守りますから。」
オルヴァスの目には薄っすら涙が浮かんで居た。男の様子が気に掛かったが、今はバルタを守り切る事に専念しよう、と涙を拭い勇んで馬に飛び乗った。
***
兵士に案内されバルタの市街地まで馬を進めると、其処は想像を遥かに絶する凄惨な光景が広がっていた。町中は至る所が血で染まり、バルタとベスタルクの者達の屍が乱雑している。中には若い女や赤子を抱いた母親とも思しき亡骸もあった。
士気高揚の為に掲げられたラプタス軍旗が無残にも踏み躙られている。賑わって居たであろう市街地の露店にはベスタルクの兵達が食料や金銭を搾取した跡があった。
オルヴァスが見た故郷は余りにも荒れ果てていた。彼の中に怒りが芽生える。郷国を此の様な死の世界へと変えたベスタルクが憎かった。軍隊が騎士や兵士と相対するのは構わない。彼が許せなかったのは何の罪も無いバルタの民達を惨殺し、町で略奪を働いている事だった。
(許せない……私が無念で死んで逝ったバルタの者達の仇を取る…。)
シャレールは道中、兵士と此れまでの顛末を一頻語り合った。
「ミグルで私達騎士団は三国連合軍と激突した。三国は幾ら盟約を交わしたとは言え、近年興った新興国だ。ラプタスに宣戦するのは余りにも無茶な事だろう。……しかし彼等には何としてでもラプタスに攻め込まねばならない訳があった……。」
シャレールは兵士にミグルで立てた考察を話して聞かせた。
「其れは……?」
「今此の国に蔓延している情報は其の大部分が嘘だろう。だからあくまでも私の推測ではあるが……。」
新興国の三国はラプタスに不信感を募らせていた。其れは他でも無い、彼等だけが神宿るシャルティネの恩恵を受けている、と考えていたからだ。だが幾ら不満を嘆いてもラプタスは南半球随一の軍力を誇る騎士団を抱えている。そんな相手に侵攻すれば多大な損害を請うむるに違いない。三国はラプタスに手を出せずにいた。
一方ベスタルクは兼ねてからラプタスと戦乱を繰り返しており、彼等の恨みは日増しに募っていた。何としてでもシャルティネに攻め込み、神の恩恵をラプタス一国に独占させたくはなかった。
そして三国連合とベスタルクは同盟を結んだ。無論ラプタスの首都シャルティネを奪う為に。
ベスタルクはバルタの国境沿いに位置している。何度も侵攻を試みるもののバルタの者は強い。其れに加えラプタスの兵士が町中を巡回しており、ベスタルクの動向は直ぐに読まれてしまう。
其処でベスタルクは南部に位置する三国連合にラプタスへの宣戦を促した。ラプタス国内の兵力をバルタや、シャルティネから遠ざける為に。
「……ラプタスの諜報技術は一気に形勢を逆転させる程の情報を齎す。だからこそ此の国の諜報組織はベスタルクや三国連合に介入された。…もしくは国内に敵軍の内通者が居るかもしれない。……私はこう考えた。」
シャレールの見立てに兵士は驚きの声を上げた。彼の言い分は的確で疑念を抱く余地も無い。
「貴方の仰ることは大方当たっているでしょう。…しかし此れが本当に起きているとすれば……。」
「…そう、国家転覆の危機だ。安易に口走ってはいけないだろう。……だが気づいてしまったからには此の国を死守しなくてはならない。」
シャレールは大きく深呼吸した。此処での指揮官は自分なのだ。覚悟を決め、腹を据えて戦わねばならない。例え身の危険に遭遇しても。
「…今からバルタを守る為、私達は戦う。何が遭ってもベスタルクをシャルティネに通さない様、徹底抗戦する。皆、決死の覚悟で戦ってくれ。」
彼はヴァイゼン公の痛みが分かった様な気がした。此の戦乱は明らかに勝ち目が無い。町の様子を見ればそんな事は一目瞭然だった。しかし戦わねばならない。国を守る為に。家族や恋人、シャルティネに待機するメルヴァントやアジィールの為に。神の為に命を投げ出さねばならないのだ。そんな彼等に死んでしまうかもしれない、等と弱気な事は言えなかった。目の前の仲間達は今から半数以上が死ぬだろう。だが鼓舞せねばならないのだ。例え偽りの仮面を被ってでも。
「オルヴァス、私と共に行こう。何としてでも戦うのだ。」
シャレールがオルヴァスに向けたのは日溜まりの様な微笑みであった。
オルヴァスは其の微笑に心が温まるのを感じた。怒りの心が一瞬薄らぎ平常心が戻る。戦場だと言うのに気分が興奮して居ないのは何だか不思議な気分であった。
***
バルタの市街地へ繰り出し、ベスタルク軍を斬って回った二人の目に飛び込んで来たのは信じられない光景であった。
「…此れは一体どういう事か……。」
市街地から少し離れた小さな教会。其処はベスタルクが占拠していたのだが、其の程度の事は驚きには値しない。衝撃だったのはベスタルクでは無い。
「シャレールさん、あの中にシャルティネの貴婦人達が……。」
シャレールは唯々頷いた。如何やら見間違いと言う訳では無いのだろう。
小さな教会の窓越しには確かに、シャルティネで騎士達の帰りを待って居る筈の貴婦人達が見えた。皆、疲れ切った表情をして居るのは外からでも窺えた。
しかし一体何故に彼女達は激戦地バルタに居るのだろうか。少なくともオルヴァスとシャレールは彼女達が此処に来ている、と言う話は耳にしていなかった。
「ラプタスの騎士団の方々ですか……。」
更なる不安と疑念が広がる中、弱々しい女性の声が聞こえた。
「貴方は……。」
シャレールが振り返って尋ねた。其処には小綺麗な薄手の衣装に細い腕を通した、見るからに貴族の夫人であろう女性が立って居た。彼女の瞳は絶望感に濁り、曇天の空の様な様相であった。
「……私はシャルティネに住まう貴族の……。騎士様、バルタは如何なって居るのですか。私達は此処が戦地だとは一言も聞かされて居ませんでした。……私は如何なって仕舞うのかしら。」
「状況を把握したいので少し落ち着きましょう。……貴女方は誰の命を受けて、何故此処にいらっしゃるのですか。」
シャレールは落ち着き放って尋ねた。一方オルヴァスの表情は、事態の深刻さに時を追うごとに険しくなって居た。
「私達は貴方方がミグルに発って直ぐに、シャルティネをベスタルクが襲撃すると言う噂を耳にしました。其れでラプタスの要塞と名高きバルタへ逃れる様にと、例えバルタで聖戦が起こっても彼等が守って下さるから、と避難の命が下ったと言う情報が……。」
又してもベスタルクによる虚偽の情報が仇となった。
「バルタは今ラプタスの中でも最も激しい戦地です。女性が此の様な所に居てはいけない。シャルティネには騎士団の本隊が待機しています。ですから其方へ逃げて下さい。」
「今からシャルティネに戻れ、と仰るのですか。」
「はい。其れが貴女の為です。此処も時期にベスタルクの魔の手が襲って来るでしょう。其の前に早く行って下さい。」
シャレールにしては珍しい強い口調で捲し立てる様に言った。其れだけ切迫した事態であると言う事だ。
女性はちらと背後の教会に目を遣った。幾ら危険だから、と言われても共に此処まで逃れて来た他の婦人達を残しては行けなかった。
「大丈夫です、御心配には及びませんよ。私達があの方々を助け出しますから。」
女性の迷いを察知したオルヴァスは胸を張って言った。決して其の様に明るく振る舞える様な状況では無かったが、彼が今出来る事は女性を安心させ、シャルティネに返す事であった。
「……必ずよ、必ず助けて差し上げて。」
小刻みに震えた女性は一礼して足早に去って行った。
オルヴァスとシャレールは改めて眼前の状況について話した。
「首都の婦人達が逃れて来ていると言う事は、アズリータ嬢も此の中に……。」
「であろうな。しかし此処は既にベスタルクの軍勢に占領されている。」
厳しい状況であった。此の様な所で無駄に思い悩んでいる暇はない。今此の瞬間も仲間達はベスタルクと戦って居るのだ。一刻も早く教会の中の貴婦人達を助け出し、彼らの元に馳せ参じねばならない。
「シャレールさん……。奇襲、ですか。」
「そうだな、彼方の数は多いが私達は二人だ。奇襲で一気に攻めるしか無いだろう。」
***
ベスタルクに包囲された教会に二人の騎乗騎士が奇襲を掛ける。敵軍を蹴散らすように駆け抜ける様は烈風のように激しく、周囲を圧倒させる様だった。
「敵襲っ。ラプタス騎士二名を捕えよっ。」
二頭の疾走する馬はベスタルク兵の怒号の様な声を潜り抜け、教会内部に滑り込んだ。
突然の出来事に、教会に居た女性達の甲高い悲鳴が上がる。
オルヴァスとシャレールが見た教会内部の光景は此れ又、信じられないものであった。石造りの広い床に女性達が幾人かに纏めて座らされ、手足を縄で拘束されている。其れだけではない。教会の中央では幾人かの女性の屍が横たわり、辺りには血の海が広がって居る。常軌を逸した酷い死臭が立ち込め、其処は地獄であった。
神に祈りを捧げる教会で、其れも神聖な神々の面前で此れ程までに酷い出来事があった等、断じて信じられなかった。否、信じたくは無かったのだろう。神々が此の様な惨事を黙認する事は決してない。敵には必ずや神の天罰が下るだろう。そう信じて置かなければ、見るに堪えない地獄の様な争いを、平常心を保ったまま戦う事等出来ないからだ。ましてや友や仲間、家族を失って尚も生きる事は出来ない。
「愚かなラプタスの騎士達よ、其の目に焼き付けるが良い。……大陸最強の名を持ってしても大切な者を守れなかった苦しみを死ぬまで味わえ。」
オルヴァスの翡翠の瞳の瞳孔が怒りで大きく開く。湧き上がる憎しみと恨み、自分の無力さに対する遣る瀬無さが彼を突き動かす。怒り任せに剣を抜き放ち、叫びを上げて斬りかかった。
「オルヴァスっ、行くなっ。」
シャレールの必死の叫びは彼には決して届かない。此れではオルヴァスまでもが死んでしまう。彼だけは死なせられない。シャレールは彼を助ける為に剣を抜いた。
剣は透き通る程美しく、磨き上げられた刀身は血塗られた景色を映し出して紅く輝いて居る。
「シャレール、どんな事があってもオルヴァスを死なせるなよ、俺達の可愛いい後輩なんだからな。」
出立前、アジィールはバルタ行きのシャレールに言った。彼は此の時アジィールと約束を交わした。必ずオルヴァスと共に生きて帰る、と。其の契りを違える訳にはいかない。シャレールはアジィールの一言を思い出して奮起した。此処で負ける訳にはいかない。何としてでも生きて帰らねば、何も始まらないではないか。
シャレールがベスタルクの兵を三名余り斬り倒した直後の事であった。オルヴァスの背後にベスタルク兵が回り込み、彼の背に斬りかかったのだ。
「…オルヴァスっ。」
聞いた事も無い様なシャレールの異常な声に思わず振り返る。瞬間、辺りの光景が緩やかに見えた。敵兵が自分の背後に襲い掛かって来て居る。距離は間近まで詰められ交わす事も出来ない。
(最早、此れまでか……。)
そう思うと瞬く間に様々な情景が脳裏に鮮明に蘇った。最後に友のメルヴァントの姿が浮かぶと、諦めた様に瞳を閉じた。
「……あぁっ。」
無念さからだろうか痛みは感じなかった。途轍もなく長い間、静寂が包んだ。
ふと顔を上げてみると、其処は先程とは何ら変わらない地獄が広がって居た。
何かが崩れ落ちる音と共に視界に映り込んだのは、
「…貴女は…あっ、……アズリータ嬢。」
腹部から流血したアズリータであった。全てを察したオルヴァスは、彼女を斬り付けたベスタルク兵を切り捨てるなり、アズリータに駆け寄った。
「アズリータさん……アズリータさんっ。」
苦しそうな表情を浮かべたアズリータを揺さぶる。オルヴァスは必死であった。
「…は、オルヴァス様。怪我はして居られませんか……。」
「私の事等、心配して居る場合では無いでしょう。……如何して…如何して私を庇ったのですかっ。貴女は女性です。私が守って差し上げねば成らないのに……。如何して…。」
アズリータは目を細めてオルヴァスを見た。其の表情が何処となく嬉しそうで、切なそうであった。
「私にはもう時間がありません。下らない事を御聞きに成らず、私の話を訊いて下さい。」
オルヴァスの目からは涙が流れた。信じられなかった。恋い焦がれた女性が自分を守って死ぬ等。又も自分の無力さを感じた。失いたくない人に対する溢れんばかりの恋心に涙を禁じ得なかった。
「…嬉しいの、最期に想い慕う人の御顔が見られて……。御免なさいね。……今日程貴方が愛しかった事は有りません。有難う……。」
「嫌です、貴女は未だ生きている。如何か御願です、そんな弱気な事は言わないで下さい。……帰りましょう二人で、首都に。…皆さん待って居ます。だから…だからっ。」
オルヴァスの涙はアズリータの頬に静かに落ちる。大粒の涙は煌めき、とても美しかった。
「有難う……私の為に貴方がこんなにも涙を流して下さるなんて……私、もう何も要らないわ。貴方が生きているだけ、其れだけで私は嬉しいの。……だからね、私の分も……生きて。」
輝くような微笑を浮かべるアズリータ。其の死に際の美しさに彼女が帰らぬ人と成って仕舞う事を実感したオルヴァスは、アズリータの前で見境無く泣き喚いた。其れは騎士らしくも男らしくも無い、所謂無様な姿であったが、彼にはそんな事は構わなかった。唯、偏に悲しいのだ。
アズリータはそんなオルヴァスを慕わしげな目で見つめ、彼の腕を自分の方に引き寄せた。
「……っ。」
オルヴァスの唇を奪ったアズリータは涙を流して歓喜した。彼の悲しみが口元を通して伝わる様だった。此の悲しみを、彼の癒えない傷を酷くさせたのは自分であろうか。
彼女は悲しくも嬉しくもあった。愛しい人に添い遂げられない事は悔やまれてならないが、自分の一番美しい姿を鮮明に彼の脳裏に焼き付ける事が出来たのは何とも言えず、満足であった。
「……永遠に御慕いして居ります。オルヴァス様……。」
魅了された様な可憐な表情を浮かべた儘、眠る様な静かさでアズリータは天に召された。
オルヴァスはひたすらアズリータの名を呼びながら彼女の体を揺すった。騎士見習いの頃から良く知る魅力的で優雅で、そして恋い焦がれた其の人が死んで仕舞ったと言う事実が彼には受け入れ難かった。其の名を強く呼べばきっと又、大きな瞳を開いて笑ってくれるに違いない。
彼は信じて居た。此処は教会、神宿る場所。だからきっとアズリータは息を吹き返すだろうと。
「……ヴァス、…オルヴァス。」
シャレールが駆け寄った。泣きじゃくるオルヴァスの背に手を添える。何と声を掛けて良いのか、どんな言葉を掛ければ良いのか分から無かった。唯、彼の背からは悲しみが溢れて可哀想な程だった。
「オルヴァス、君は彼女を連れて、行きなさい。」
其れが唯一、彼が言える言葉であった。此れ以上オルヴァスを苦しめてはいけない。そう判断したシャレールは彼をシャルティネに返す事にしたのだ。だが実の所はシャレールの方が、悲しむオルヴァスを見て居られなくなった、とでも言うべきか。
「……否、私は戦います。…故郷を奪われ、大切な人を殺され…此の儘ベスタルクと剣を交えぬ訳にはいきません。……此れでは騎士に成った意味がない。大切なものを守れ無い位なら……死んだ方が余程良い。」
オルヴァスは言い張って立ち上がり、剣を抜いた。
そんなオルヴァスを見たシャレールは俯いて首を横に振った。
(もう良い……もう良い、オルヴァス。君は十分戦った。故郷の惨状、人の死にも目を背けずに良く此処まで来た。……けれどもう、見ている私が辛いのだ。)
「オルヴァス、君は首都に帰りなさい。此れ以上の苦しみを私は君に強いたくは無い。」
「…苦しみではありません。今此処で戦わなくては、此の恨みや怒りを何処に吐き出せば良いのですか。……仇を取らなくてはならない。亡くなった人達の為にも……。其れに今此処から離脱すれば貴方は独りです、シャレールさん。」
シャレールは意地を張るオルヴァスの傍へ寄った。そして彼の背を思い切り突き飛ばす。
「首都へ戻れ、と言って居るのだ。君が戦うか否かを問うて居るのでは無い。……此れは指揮官命令だ。出立前にヴァイゼン公から御達しが在った筈だ。私情では動かない事、私の指示を聞く事、と。私は指示を聞けぬ騎士を後輩にしたつもりは無い。…首都へ帰れ。」
見た事も無い程に冷徹なシャレールはオルヴァスを睨み据えて言った。彼とて此の様な形で首都へ返したくは無い。何事も無い様に首都まで送り届けてやりたい。何せ素直で優しい、何にも代え難い大切な後輩なのだ。突き放すつもりは微塵も無い。唯、偏に彼が無事に生き残ってくれる様願って止まないのだ。
「…申し訳ありませんでした。貴方の命に従います。……しかしシャレールさんは一体如何するのですか。」
「…私は神の使徒だ。いざと言う事があれば其れを使う。……心配するな、私も後を追う。」
ほら、と隙を見てオルヴァスを教会の外へ出した。オルヴァスが振り返る前にシャレールは再び戦地に戻って行った。
其の背を唯、呆然と見る事しか出来なかったオルヴァスは自らの弱さが何とも悔しかった。
「ベスタルクの雄々しき兵達よ。憎きラプタスを殲滅せよ。」
教会内部ではそんな掛け声と共に、幾人ものベスタルク兵がシャレール目掛けて襲い掛かって来た。
「死んで自らを恥じ、大いに悔いれば良い。ラプタス人めっ。」
罵る声を聞きながらシャレールは笑って居た。肩の荷が下りた様な安らかな表情で剣も構えず、唯立ち尽くしている。
「幾人にも忌まれた此の命がもし役に立つのなら……神よ、如何か貴方の使徒に此の場を守るだけの力を与えたまえ……。」
静かに心落ち着かせて唱える。詩を吟じる様な透き通った声と共に、彼の身体は淡い光で包み込まれる。
「…アジィール、メルヴァントそして……オルヴァス、有難う。私は本当に楽しかった……。」
一筋の涙を流しながら、剣を振り上げる。斬り付けたのは敵では無く、自分自身の左腕であった。
瞬間、教会は眩い光に包み込まれる。誰もが動きを止め、何が起こったのか知る者は居なかった。唯、心に染み入る様な柔らかな光が体内に流れ込むようであり、其処には微風が吹いていた。
其の昔、神々の使徒達は不思議な力を体内に宿して居た。彼等が其の力を用いる時は、各々を遣わせた神々から受けた洗礼の様な光が辺りを照らし出し、世界の摂理を覆す程の力が彼等の中に呼び覚まされる。世界の危機は何時でも彼らが密かに其の力を持って救って来た。但し、使徒が其の力を発揮するのは神に身体の一部を捧げた時のみであり、同時に彼等の中に蓄積された自我は消え去る。強大な力を持つ事はつまり、彼等の死を意味して居た。
シャレールは禁忌とでも言うべき最後の手法でラプタスを救おうとしたのだ。
「…シャレールさん。」
教会の異変に気が付いたオルヴァスは引き返して来て、叫んだ。しかし其処にはシャレールは居ない。感情を失った様な無機質な人型が剣を振るって居るのみである。其の姿はもうシャレールでは無かった。
「…シャレールさん…御免なさい……御免なさい。」
突然の出来事に全てを悟ってしまったオルヴァスは泣きながら首都を目指して教会を後にした。せめてシャレールの命令を受け入れて首都に戻る、留まる事はシャレールが望んでいない。そう感じて走り去った。
彼の悲しみは其れまでの比には成らなかった。突然二人も大切な人を失ったのだ。シャレールに至っては余りに突然だった。先程までの自らを顧みては後悔の念しか浮かんで来なかった。彼を死に追い遣ったのは自分だと感じ、激しい自責の念に駆られた。
(結局、私は誰一人として守れなかった……。)
***
大陸史上最悪の聖戦はラプタス軍、三国ベスタルク連合軍共に多大な犠牲を出して幕を閉じた。
難攻不落と謳われたバルタはベスタルクの手に陥落し、流れ込んだ兵が首都シャルティネを占領した。
神宿るラプタスで繰り広げられた激戦は無情にもラプタスの敗戦で終わりを告げ、ラプタス一帯はバルタの領地に編入される事に成った。生き残ったラプタスの者達は牢に入れられ、又捕虜にされたりもした。ベスタルクに口汚く罵られ、軽蔑されたラプタスの者達はやがて誇りを失っていった。命を絶つ者が後を絶たず、生き残ったラプタス人は僅かと成って仕舞った。
神々は汝の為に命を投げ出す者達に無慈悲であった。あれ程までに信仰深く、敬虔な信者であったラプタスの者達が何故此れ程までに悲惨な目に遭ったのだろうか。
其れは誰も知らない。誰も知り得ない世界の摂理。無情にも降り掛かり、決して抗えぬ神々の神話。
神を失った者達は一体何を信じ、何に向かって生きるのだろうか。
裏切りの神話と抵抗の物語 中編
四章からは「裏切りの神話と抵抗の物語 後編」へ続きます。


