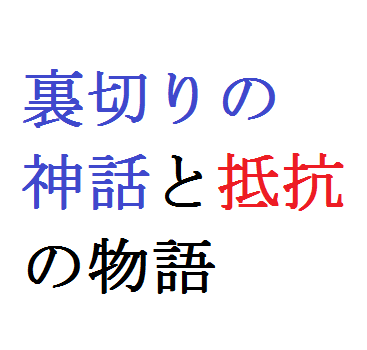
裏切りの神話と抵抗の物語 前編
今から数十年前__________。
未だ世界の均衡が保たれ、誰もが疑いもなく七種神を信仰していた頃、
神に仕える巫女や聖職者達は持て囃され、不思議な呪術を持つ者達はことごとく異端視され殺された。
神宿るタレファルナ山脈と天の恵み、イグリュータ川を頂く南半球の国、ラプタス。
そこには信心深き七種神の信徒達が秩序の元に国を統治していた。
七種の神はラプタスに集うと言い伝えられていた頃。
大陸揺るがす大乱に人々は何を見たのだろうか。
第一章 都の騎士と華の少女
遥か彼方に万年雪を纏い、大陸航路に横たわるタレファルナ山脈が見える。
片田舎のバルタ地方から七日馬を走らせ、首都シャルティネにやって来た少年、オルヴァス=ルシアネス。
彼は美しい赤毛を持ち、瞳は情熱的な輝きを放つ深緑。目を引く様な逞しく凛々しい顔立ちに、色白でその細さに似合わぬ剣を吊り下げていた。
ラプタスの首都シャルティネは今日も活気に溢れていた。色取り取りな衣装を纏った貴人、馬に馬車を引かせ、豪遊に浸る貴婦人。国が誇る騎士団の騎士達が町を行き来し、商人は様々な品を露店に並べ客引きをしている。
そんな光景に戸惑いながらもオルヴァスは騎士団に入隊するために、とある屋敷へと馬を進める。真横を通る貴族の馬車を見て思わず馬を降りると、体格の良い立派な馬に少年は頼りなく見えた。彼は未だ二十歳にも成っていないのだが、ラプタスの騎士団に憧れて、遠く離れた田舎からこのシャルティネまでやって来たのだ。
彼位の少年が騎士団に憧れて田舎から一人都へやって来る事は、珍しい事ではなかった。何せ世は聖戦が繰り広げられている時代。騎士団の活躍を親に聴かされて育った者も多い。オルヴァスもその一人である。
街道を抜け、静かな路地に入る。そこには石造りの館が重々しく腰を下ろしていた。オルヴァスの生まれ故郷、バルタにはそんな豪勢な建物など一つもない。溢れんばかりの好奇心と少しの不安を胸に宿しながら、建物の一つ一つを穴が開くほど見て回った。
「騎士団入隊を志願して此処までやって来ました。バルタ地方のオルヴァス=ルシアネスと申します。」
目的の場所、騎士団を取り仕切るヴァイゼン公の屋敷に着いた。厚い門の前の門番に緊張しながら伝えると、門番は無言で門を開いた。騎士団入隊の志願者は皆、屋敷に入れてもらえるのだろうか。
「…入れ。真っ直ぐ進んで、角を右に曲がる。そこが公爵様の御部屋だ。」
「くれぐれも失礼の無いように。」
二人の門番から口々に言われ、彼の頭は混乱した。だが、気を強く持ち、勇気を出して屋敷に足を踏み入れる。彼の愛馬は屋敷の外で大人しく、彼の背を見守っていた。
***
部屋の中から話し声が聞こえる。一つは低く、もう一つは若い感じの声だ。先客であろうか。もしそうなら、ここで待つべきだろうか。オルヴァスは戸惑いながらも、戸を叩いてみた。
「……どうぞ。」
明るく、しかし威厳のある声に、はいと小さく返事をして恐る恐る部屋に入った。
「あのっ、騎士団入隊を志願してバルタ地方から参りました、オルヴァス=ルシアネスです。」
部屋の中央にどしりと腰を下ろした中年の男がヴァイゼン公であった。公爵はオルヴァスを吟味する様にじっくりと顔を見た後、にっこりと微笑んだ。その暖かな表情にオルヴァスの緊張が幾分か解れた。
「よく来たな、歓迎しよう。」
そう言って、オルヴァスに歩み寄り右手を差し出した。オルヴァスは背筋を伸ばし恐れ多い、と言わんばかりの面持ちで握手を交わした。
「…早速だが、其処の彼と一戦交えてくれないかな?」
「……えっ。」
突然の申し出に振り返ってみると、そこには一人の少年が立っていた。歳は同じくらいで、整えられた金髪、青く澄んだ瞳に小奇麗な衣装を纏っている。あどけなさの残る彼の顔が不満げに揺らいだ。
「其処のメルヴァントも騎士団入隊を志願していてね。君たちの実力を見せて欲しい。」
とんでもない展開となった。オルヴァスは緊張に唾をゴクリと飲み、メルヴァントは溜め息を付いた。
***
オルヴァスとメルヴァントとの一戦は屋敷の中庭にて行われる事となった。
兎にも角にもメルヴァントは悔しかった。どうして自分がどこぞの田舎騎士と剣を交えねばならないのか。
自分には実力がある、メルヴァントはそう信じていた。実際、彼は先の聖戦で隣国ベスタルクを追いやった貴族騎士メトゥルノスの子息である。幼少の頃から剣術を叩きこまれ、都では随一の実力を持つ。そんな自分の実力を何故ヴァイゼン公は認めて下さらないのだろうか。
「君たちの全力を出して御覧。私は此処で何方が騎士に相応しいか見極めさせて貰おう。」
広々とした空間に二人の若人。互いの緊張感が空気を通して伝わりそうな、そんな静寂。
(あぁ、物凄く強そうな人だ…。)
オルヴァスは成る様になれ、と言わんばかりに大袈裟に剣を振り上げた。
「私の名前はオルヴァス=ルシアネス。私の剣を受けてみろっ。」
(なんて粗い太刀筋なんだ…。)
メルヴァントは呆れた。これだから田舎騎士は……と思った。
しかしヴァイゼン公はオルヴァスの姿に目を見開いた。彼の大雑把な剣裁きに反して、技は確かであり、剣を振るう姿もとても美しかった。
「私の名はメルヴァント=アステューク。御相手致そう。」
メルヴァントは流石、貴族の子息だけあり素晴らしく無駄のない剣裁きであった。
彼らの綿密でしなやかな剣裁きにヴァイゼン公は思わず大きく頷いた。
なかなか決着は着かなかった。メルヴァントの想像以上にオルヴァスは強く、今までの一対一の決闘でこんなにも苦戦した事は無い。その事実が彼に焦燥感を感じさせていた。
「ハァ、ハァ…。」
息が上がる。剣を握る手が、思うように動かない。メルヴァントは今までに無い位の焦りに襲われた。一方のオルヴァスは平然とした顔で淡々と剣を振るっている。その落ち着き払った瞳は真剣そのもので、底深の緑色の眼は鋭い光を飛ばしていた。
剣と剣が軽快に触れ、激しい金属音が屋敷一体に響き渡る。疲労の色が見え始めたメルヴァントにオルヴァスは距離を詰め、軽やかに彼の剣を刃先で流した。
「……ッ。」
「勝負ありっ。」
次の瞬間、メルヴァントは地面に倒れ込んだ。
(…まさか…まさか此の私が負けるなんて……。)
ヴァイゼン公は立ち上がり、拍手をしながら二人の元に歩み寄った。
「素晴らしい、本当に素晴らしかった。君たち双方、立派な騎士だ。…殊にオルヴァス、君の太刀筋は若々しさが有って良い。型に嵌らぬ姿…、君は大雑把な剣の振り方さえ直せば、今に素晴らしい騎士となろう。」
言って、オルヴァスと固く握手を交わした。
「ほっ、本当ですか?……有難うございます。」
微笑みながら頷き、ゆっくりとメルヴァントの元へ向かう。
「さて、メルヴァントはどうだったかな?私は君の剣の腕は買っているよ。御父上によく似て、果敢に剣を振るう、其の姿はとても良い。貴族の中でも、君の様なラプタス古来の剣術の使い手はいない。其処は十二分に分かっているよ。しかしね……。」
メルヴァントはヴァイゼン公を見上げた。何とも悔しげで、負けん気に満ちた表情だった。
「君には都一の実力は有る。しかし型に嵌り過ぎで、自由さが無い。戦場で戦う時、大切なのは生き抜く事だ。より多くの敵を倒し、上手く生き残るために剣を振るえ。さもなくば、君は戦場で死ぬことになろう。」
厳しく言い放ったが、やがて優しく笑いメルヴァントに手を差し延べた。その姿はまるで父親の様で、威厳は有りつつも片時も優しさを忘れないのだった。
「オルヴァスにメルヴァント、君たちを直属の騎士として迎え入れよう。私の元で沢山鍛錬を積み、立派なラプタスの騎士と成ってくれ。」
そのヴァイゼン公の申し出にメルヴァントは顔を上げた。
「しかし、公爵様は先程何方が騎士に相応しいか見極めると……。」
「何か不満でも?」
「いえ、ですが私は負けました。彼は本当に強い。それに比べ私は……。負けたにも拘らず、騎士として取り立てて頂いても宜しいのかと……。」
ヴァイゼン公は大きな声で笑いながら語りかける様に言った。
「そんな事を気にしていたのか。…メルヴァント、君の其の潔さが私は大変気に入っている。だが、私は今何と申した?騎士に成りたくないのであれば構わぬが……。」
「あっ、いえ決してそういう訳ではございません。あの、有難うございます。」
メルヴァントは喜びに震えながら礼儀正しく一礼した。
と共にオルヴァスも嬉しそうであった。彼自身、実力のあるメルヴァントに勝った事が信じられずにいた。此の人は騎士に成るべき強さを持った人だ、直感的にそう思っていたのである。だからこそメルヴァントも騎士として取り立ててもらえた事に喜びを感じたのである。
腕を組み、二人の新たな騎士を前にして満足げな表情を浮かべるヴァイゼン公の元に、従者らしき男がかけ寄って来た。男は神妙な面持ちで公爵に耳打ちする。
「分かった。直ぐに向かおう。……メルヴァントにオルヴァスや。」
何が起こったのかと不安げな表情を浮かべる二人に公爵は手短に伝えた。
「急な私用が出来てしまってね、すまないが暫く客人の間で待っていて貰えないだろうか。直ぐに戻るだろうから。」
何が遭ったのかは分からないが、二人は黙って頷いた。ヴァイゼン公はその反応を確かめると同時に、急いで屋敷を後にした。
屋敷に残されたメルヴァントとオルヴァスは客人の間に案内され、二人きりになると何方からともなく語り合った。
「改めて、私の名はメルヴァント=アステューク。此処シャルティネの貴族、メトゥルノス=アステュークの三男だ。先程の無礼な態度、申し訳なかった。」
こうして面と向かって話しをしてみると、メルヴァントという少年はとても誠実で、紳士的であった。自らの非礼を認め、素直に詫びる姿はまさに騎士そのものだった。
「いえ…私の方こそ御相手して頂いて…有難う御座います。……私はオルヴァス=ルシアネスです。タレファルナ山脈を隔てたバルタ地方から騎士に憧れて此処までやって来ました。」
オルヴァスの言葉にメルヴァントは大きく目を見開いた。
「バルタから来たのか、それは羨ましい。バルタとは彼の英雄アセラ=バスクの生まれ故郷であろう?」
「はいっ。バルタの者は皆、彼をラプタスの英雄と呼び尊敬しております。」
「なぁ、オルヴァス。私達は同志だ。だからそんな堅苦しい言葉遣い等せず、気楽に語り合おうではないか。」
突然の申し出にオルヴァスは驚いた。幾ら同志とは言え、メルヴァントは貴族の子息である。気楽に語り合えるような身分ではない。そもそも彼は幼い頃から両親に、貴族と騎士には決して無礼な態度を取らぬ様に、と言い聞かされて来たのだ。
「ですが、私とメルヴァント様とは身分が違います……そんな畏れ多い事など。」
「いや、貴族とは言え私には兄がいる。優秀な兄たちの後に継ぐもの等何もない。だからこうして呑気に騎士など目指す事にしたのだ。……畏れ多いと思う事は無い。御願だ、オルヴァス。君には対等に接して欲しい。」
彼の心からの願いであった。名門アステューク家の三男という立場上、周囲の期待も多くは無いものの、有能な二人の兄に囲まれて暮らして来た彼には自分自身に多少の劣等感を抱いていた。
兄たちとは違い剣術にしか能がない自分にとって、貴族として扱われる事が何とも苦痛であったのだ。
「私は身分の為に心から語り合える友を持ったことが無いのだ。学友たちは皆、互いの身分と顔色しか見ない……。けれど君は私に大切な事を気付かせてくれた。此れも神の御導きだろう。…だからどうか君だけは私の心からの友であって欲しい。」
所謂田舎者のオルヴァスには彼の苦労は理解し難い。だが貴族も貴族で何かと苦労も有るのだな、と妙な関心に浸るのだった。
暫くの沈黙の後、オルヴァスは爽やかに笑って、
「…うん。分かったよ。私と君は親友だ。」
と言った。その言葉にメルヴァントは大層喜んだ。生まれて初めて気を許し、対等に付き合える友が出来た事が喜ばしくてならなかった。彼の幼い顔が屈託のない笑顔を浮かべる。
「有難う、オルヴァス。此の日の事を私は決して忘れないだろう。」
今日此処に二人の少年の固き友情が生まれた。
***
それから彼らは思いのままに語り合った。町の事、家族の事、騎士を志したきっかけ…。中でも故郷の話は大いに盛り上がった。
「オルヴァス、君の故郷はバルタであろう?どうか私にバルタの話を聞かせてくれぬか。幼い頃からの憧れなのだ。」
メルヴァントが憧れを抱くバルタとは一体どの様な地であろうか。
ラプタスの最北バルタ。古くからタレファルナ山脈はラプタスの要塞、バルタはラプタスの剣、と謳われる剣術の町である。南にタレファルナ山脈を頂き、北は隣国と国境を接しているという特殊な地理上、古来よりバルタの者達は自らの手で町を守って来た。その歴史的背景からこの土地には独特の剣術が広まり、バルタの男は皆この剣術を嗜んでいる。南半球に最強の名を響かせるラプタスの騎士団でさえも彼らの腕には敵わないのであった。
それ程の強さを誇るバルタの男達の中から数十年程前、アセラ=バスクという豪傑が騎士団の一員として聖戦に参戦した。彼の活躍は凄まじく、一躍その名を大陸全土に轟かせた。それだけではない。彼は困窮を極める激戦地に援軍として駆けつけ、騎士団に勝利の軍旗を齎したのだ。それからと言うもの彼は英雄と呼ばれ、その武勇伝は語り継がれて少年たちの格好の憧れとなった。
メルヴァントやオルヴァスも彼の英雄譚を聞いて育った少年たちの一人である。アセラ=バスクのおかげでバルタ人は獰猛な田舎者、という汚名を払拭し又、騎士団には彼に憧れた少年たちが詰め寄った。
兎にも角にも、アセラ=バスクとはラプタスの者にとり、特別な存在であることは確かであった。
「羨ましい限りだ。私もオルヴァスの様にバルタに生まれたかった…。」
メルヴァントが溜め息交じりに呟いた。オルヴァスは笑って、
「私も貴族に憧れた事があった。貴族ならば騎士団に入隊せずとも腕を振るえただろうにと。……人生なかなか上手くは行かないな…。」
メルヴァントと同様に彼もまた溜め息を付いた。
「全くだ。」
二人は顔を見合わせて笑い合う。まるで十年来の友であるかのように。
「でも此の数奇な運命もきっと神の御導きなのだろうな。」
メルヴァントは天を見上げて言った。
***
斜陽がシャルティネの町を紅に染める夕暮れ。町は一層賑わい、人々は鼓動を刻むように行き交う。
屋敷へと戻って来たヴァイゼン公はメルヴァントとオルヴァスに、騎士団の心構え等を話した。
幾ら明日からヴァイゼン公直属の騎士とはいえ、正式には未だ見習いに過ぎない。見習いの騎士達は屋敷近くの宿舎にて毎日鍛錬の日々を送るのだ。そしてヴァイゼン公をはじめ、騎士団を統括する諸々の貴族に見出された者から順に正式に騎士と成る。一人前の騎士に成るには少なくとも三年は掛かる、というのが不文律であった。
「毎日、日が昇ると共に剣術の鍛錬に励み、日が沈むと共に床に着く、というのが宿舎の決まりだが…年長者に成れば成る程、決まりを守る者は少ない。しかし、きちんと決まりを守って健やかに生活をすれば、それだけ剣の腕前も上達するだろう。君たちが決まりを守るか否かは君たち次第だ。それに…。」
最強の名を響かせる騎士団の中にも乱暴を働く者が居ない訳ではない。
自らの名声に酔い痴れ、自堕落な生活を送る者、町の者から顰蹙を買う者…様々であるが、騎士たちの不名誉な噂を防ぐためにも、貴族たちは見習い騎士たちを厳しく教育しているのだ。
「決まりを守って朝日と共に起床すれば、宿舎から朝食が出される。夕食も同様だ。昼食については各々、町に出て済ませる事。町の様子を知る事も騎士にとって大切な事だ。町に出てみなければ経験出来ない事もある。先輩の見習い騎士に町を案内してもらっても良い。…メルヴァントはシャルティネの生まれであるから、オルヴァスはメルヴァントに連れて貰うのも良いだろうな。」
ヴァイゼン公自ら久々に選んだ新人に、あれも此れもと思いつく限りの話をした。何しろ近頃はこんな話をする事も少なくなってしまったのだから。
「後は…そう、宿舎についてだ。私の直属の騎士が集う宿舎は此処から程近い、ミヌア通りに有る。オルヴァスはメルヴァントに案内して貰うと良い。彼は其処に一室間借りしている故。あと此れは二人に私からの頼みなのだが……。」
ヴァイゼン公が言い難いと言わんばかりに、一瞬口籠った。
メルヴァントとオルヴァスが無邪気に首を傾げると、何とも言えず困り果てた顔を浮かべた公爵は言った。
「先の聖戦で騎士団は大いに活躍を見せた。其れ故、騎士団に入隊を希望するものが増え、今や何処の宿舎も見習いの騎士で溢れ返ってしまって居て、部屋の数が足りていない。すまないが、メルヴァントとオルヴァス二人で一室を使ってくれないか。」
致し方無い事情であった。騎士団への入隊すらも困難な此の御時世、騎士団を抱えるどの貴族にも余裕など無い。長引く聖戦に貴族は皆、大金を叩いているのが事実である。
「…私はメルヴァントが良ければ同室でも構いません。」
オルヴァスの快明な応えにヴァイゼン公は幾らか安心した様に、しかしメルヴァントが口を開くまでは慎重な面持ちであった。
「私もオルヴァスとなら同室でも構いません。我らは同志であります故。」
其の無垢な微笑みに、公爵はどれ程安心した事であろう。
二人の騎士見習いを前に、彼は何時か感じた様な不思議な惹かれ合う者の姿を見た。彼らはきっと大人物に成る、直感的にそう感じた。
***
日は既にタレファルナ山脈の彼方に消え、遠方には幾億の星々が瞬いている。
オルヴァスはメルヴァントに連れられて宿舎にやって来た。ひとしきり宿舎内を案内して貰うと、間もなく長旅の疲れが込み上げて来た。何しろ七日間ろくに睡眠を取っていないのだ。無理も無かろう。
「…明日、目が覚めると今日の全てが夢だった、なんて事になったら嫌だなぁ。」
床に着いたオルヴァスが誰に言う訳でも無く呟いた。
「其れは私とて同じだ。…だが夢等では無い、きっと。だって君との巡り合わせは神の御導きに違いないのだから。」
メルヴァントの一言が何とも温かかった。暗がりに包まれた部屋の中にメルヴァントの青い瞳が綺羅と輝いている。其の灯の様な輝きにオルヴァスは安心感を覚え、深い、深い眠りの淵に落ちて行った。
***
早朝、田舎育ちのオルヴァスは日が昇る前に目覚めた。
傍ではメルヴァントが小さく寝息を立てている。オルヴァスは肩を揺らして、彼を起こした。
「メルヴァント、朝が来る。そろそろ起きないと鍛錬の時間だ。」
目覚めが悪い性質なのか、薄らに開いた目を擦り大きな欠伸をした。そして部屋を見渡してから、はっとした様に立ち上がった。
「もう朝なのか……。」
「そうだ、もう直ぐ日が昇る。其の前に鍛錬に出て、他の騎士達の剣遣いを此の目で見ておきたい。」
「それが良いな。よし、行こう。」
二人は鍛錬が行われる宿舎の広場に走り出た。其処では数人の見習い騎士が各々剣を磨いたり、太刀筋を確認したりしている。誰もが強者顔をして居り、とても見習いの騎士とは思えない。
(あぁ…凄い。バルタにも強そうな人達は居たけれど、此処は何だか違う。風格や気品があって其れで居て、きっと実際強いのだろうな。)
オルヴァスは感動して震えあがった。此の世界は未だ知らない事で満ちている。そんな当たり前の世界の真理に触れ、改めて其れを感じた。
「オルヴァス、凄いな…私に分かるんだ、君は勿論分かるだろう?此の血潮が騒ぐ様な何とも言えない…高揚を感じるだろう。」
「あぁ、感じるよ。此処は私達が夢見て止まなかった本当の…ラプタスの騎士が集う場所。……何だかとても強く惹かれる。」
高鳴る鼓動に、希望を宿した彼らの瞳が何色にも爆ぜる。親元を離れ、初めて自らの意志で飛び込んだ世界に、彼らは興奮を覚えて止まなかった。
「君達…もしかして新入りかい?」
軽やかな声に振り返ってみると其処には、褐色の髪に夕焼けの様な赤赤とした瞳の騎士が立っていた。見るからに年上で、しかし気さくそうな人物である。
「貴方は……アジィールさんじゃないですか。」
メルヴァントがあっ、と声を上げた。アジィールと呼ばれた男は彼の反応に真っ白い歯を見せて笑った。
一方のオルヴァスは何が起こったのか理解出来ずに、首を傾げていた。
「此の人は…私を騎士見習いとしてヴァイゼン公に紹介して下さった、いわば恩人の様な人なんだ。」
やはり生まれが違えば育ちも違うもので、オルヴァスはメルヴァントの交友関係に恐れ入った。と同時に羨ましさも込み上げ、何だか複雑な心境である。
「ようやく騎士見習いとして認められたんだな。おめでとう、メルヴァント。…それで此方は君の友人かい?」
アジィールは俯くオルヴァスの方に目を向けて言った。メルヴァントが友であり、同志である旨を伝えるとオルヴァスは恥かしそうにした。
「私はオルヴァス=ルシアネスと言います。宜しくお願いします。」
「オルヴァス君か、宜しく。俺はアジィール=レファント。荒涼の平原、ラシャからやって来た騎士だ。」
彼の生まれであるラシャはラプタスの西方に広がる平原の総称である。此処は古くから旅人に牙を剝く、と言われる程に荒涼とした厳しい自然に閉ざされている。其の為、旅人は恐れ戦き人が余り立ち入らない地域となっている。しかし荒れ果てた平原に住まう者は皆、太く短く生きており独特の強さを持っているのであった。
「其れで、こっちが……。」
アジィールが側に居たもう一人の騎士を指した。
其処にはアジィールと同じ位の年頃で、色白の雪の様な清らかさを持つ男。朝日に映える銀髪を呈し、切れ長の瞳は海の様に鮮やかな青色、整った顔立ちは中性的であり何とも形容し難い高潔な雰囲気を醸し出している。アジィールとは正反対の落ち着き放った青年であった。
「シャレール=ミレビア。此奴はな、花柳の巷ラピシィアの生まれなんだぞ。」
と何故か自分の事のように自慢気なアジィールにシャレールは冷徹な目を向ける。
一方、メルヴァントとオルヴァスは花柳の巷と聞き、赤面した。何とも若々しい純粋な反応である。
「ラピシィアの者が皆、花柳界に関わっている訳ではない。我らは誰よりも固く貞潔を守る種族だ。君の様にふしだらではない。」
容姿に反して厳しい一言を放つシャレール。調子の変化が少ない彼の声がアジィールの胸を抉る。一見反りが合わない様に見える二人だが、本当の所は非常に仲が良いのだろう、とメルヴァントとオルヴァスは思った。彼ら二人の姿が羨ましくあったが、きっと此の二人の様に否、其れ以上に自分達は固い絆で結び付き合うのだろう、と直感的に感じる新入りの二人であった。
「……まぁ俺も此奴も癖はあるが、一応君達の先輩だ。分からない事、不安な事、無論剣の相手もしよう。気になる事があれば、何でも言ってくれ。」
父の様なヴァイゼン公に、兄の様なアジィールとシャレール。何とも人望に恵まれた二人であった。
***
暫く他愛もない話をしながら、剣を振ったり打合ったりした。
アジィールとシャレールの二人は流石先輩だけあって、しなやかな太刀筋と豪快な剣を使うのであった。美しい、其の一言に尽きる二人の剣裁きである。
広場には多くの騎士見習いたちが出て来て、鍛錬を始めている。此れが此の宿舎の朝の光景である。しかし一つだけ違うのが、今朝は何だか騒々しい所だ。宿舎の門の辺りから賑やかな声がするのだ。其の喧騒はどんどんと広場に近づいてきて、やがて止まった。
何事であろうかとアジィールが広場の中央を見ると、其処には女性が一人立っていた。其の周りを騎士や従者が囲み彼らが口々に女性に話しかけていたのだ。
「おい、シャレール。あれはアズリータ嬢じゃないか。」
「あぁ。そう見受けられる。気になるのなら、駆け寄って見て来れば良い。」
今にも駆け出さんとするアジィールに皮肉っぽく言った。
「あの…其の人は一体……。」
好奇心旺盛なメルヴァントが尋ねる。未だ緊張気味のオルヴァスも気になっていたのか、興味を示した。
「彼の有名な名門パラフィーネ家の子女、アズリータ=ベル=パラフィーネ嬢だよ。父親がヴァイゼン公と仲が良いらしく、其の関係で御嬢さん自身が此の宿舎によく来ていて……。容姿端麗で博識だから憧れる人が多いんだ。」
「其れに加え、君の初恋の人だろう?」
揶揄う様にシャレールが補足した。彼の嫌味が届かない程、アジィールは女性の方に夢中だった。
アズリータ嬢…彼女はラプタスの歴史と共に脈々と其の歴史を受け継ぐ、名門貴族ラセドラ=パラフィーネ公の娘である。気立てが良く、博学多才な事、見た目の美しさも相まって世の男に求婚されている。しかし本人はそういうものに疎く鈍いため、全く其の気は無い。唯、彼女も騎士の英雄譚に憧れを抱いた者の一人であり、少しでも彼等の役に立ちたい、と一心に願うのみであった。
其の彼女が何かに気が付いた様にメルヴァントとオルヴァスの元に歩み寄って来た。突然の出来事に、二人は顔を見合わせる。
間近に見るアズリータは大層美しかった。腰まで伸ばした長髪がゆるりと靡き、後頭部で結い上げられている。黄金色の髪飾りが綺羅綺羅と輝く。前髪に秘めたる大きな瞳は、長い睫毛が丁寧に縫い上げていた。
「貴方たちは新入りかしら。私はアズリータ=ベル=パラフィーネ。初めまして、宜しくね。」
「あっ、は、初めまして私はメルヴァント=アステュークです。宜しくお願いします。」
遠目から眺めて居るだけでも綺麗な彼女であったが、こんなにも近くに寄られると余りの美しさに緊張を感じる。上ずった声にメルヴァントが恥かしくなっていると、優しい声が彼を救った。
「貴方はアステューク家の三男でしょう。御父上から御話を伺っているわ。其れに昔、貴方が幼い頃に私と会った事があるのよ。あんなに可愛らしかった少年が大きくなって……。随分と逞しくなったわね。」
メルヴァントはアズリータの褒め言葉に此の上なく照れ上がる。白い頬が紅に染まり、目は少し潤んでいる様だった。
優しく微笑みかけたアズリータはメルヴァントの側に居た赤毛の少年に目を向けて、息を飲んだ。
「貴方はバルタの人ではなくて?」
「はい…バルタから来ました、オルヴァス=ルシアネスです。」
硬直して彼女の目を見る事が出来ず、独りでに狼狽しているとアズリータは嬉しそうにして、
「やっぱりそうなのね。…私を幼い頃から可愛がって下さった叔父上がバルタの人だったの。其の人はもう此の世には居ないのだけれど、貴方の様に美しい赤毛と濃緑の瞳をしていてね……あぁ懐かしいわ。もし良ければ今度貴方の祖国の話を聞かせて貰えないかしら?」
と突然申し出た。余りの事にオルヴァスは驚いたが、妙に落ち着いた面持ちで、
「はい、是非に。」
そう答えた。其の瞬間、鼓動が今までに感じた事の無い速さを刻んだ。体が熱を持ち、瞳孔が開く。目の前の女性に強い、強い憧れを抱いた。其れが淡い恋心であると気付いたのは後々の事である。
「其れでは二人共、頑張ってね。」
儚げな微笑に返事の言葉すら出なかった。
「アズリータ嬢っ。」
アジィールが名残惜しそうに呼び止める。振り返ったアズリータは、
「可愛らしい後輩を宜しくね。」
と嗜めて笑った。アジィールは美しい微笑みに胸を打たれ、又もや儚い恋に散るのだった。
宿舎を出るために彼らに背を向けたアズリータは、振り向き様にシャレールに一瞬微笑んだ。其の微笑が何を意味するのかは分からない。しかし、 シャレールは変わらず飄々としていたのだった。
***
再び静けさを取り戻した広場。喪失感に満ちた騎士達は、黙々と鍛錬を再開した。
アジィールが此の妙な雰囲気を変えようと話題を振る。
「オルヴァスはバルタの人間だったんだな……。」
「気づかなかったのか?こんなにも綺麗な赤毛なのに…。」
シャレールが今更、と呆れて呟いた。
しかしメルヴァントもオルヴァスもそんな二人の遣り取り等耳に入っていなかった。
オルヴァスは高鳴る鼓動からアズリータへの恋心に気づいてしまった様だった。身分違いの儚げな恋。気づかない方が幸せだったかもしれない。そんな後悔すら覚えた。
一方、オルヴァスは淡い、叶わぬ恋情には気づかずにいたが、初めて込み上げる感情に不思議な気分がしていた。唯、アズリータ嬢は自らの故郷の人とは又違う、独特の雰囲気を放った女性だと感じた。
***
神の国ラプタス、大いなる志、友情に尊敬、興奮と歓喜に、淡い恋。全てを巻き込んで神話という名の大河は、謳う様に流れていくのであった。
第二章 国家分裂の気配
国境付近で勃発した聖戦が激化し始めた年の暮れ。
メルヴァントとオルヴァスが騎士見習いと成ってから、おおよそ四年の月日が流れた。首都シャルティネは変わらず平凡で賑わいがあったが、激戦地から帰還した騎士達をよく見かけるようになった。
「ヴァイゼン公が君の剣の腕前を高く買っていてね。私の元に来てくれる事に成って嬉しい限りだよ。」
「いえ……そんな…御褒めに与り光栄で御座います。」
オルヴァスはパラフィーネ公に恭しく一礼した。彼はすっかり逞しくなり、上背もあるため如何にも一人前の男へと成長した。巷では色男と呼ばれる程中々良い男に成っていた。
今日は例のパラフィーネ家から直々に呼び出され公爵本人から御抱えの騎士に成らないか、と提案されていた。オルヴァスは現在ヴァイゼン公直属の見習い騎士である。一人前の騎士に成る為には、他の貴族に認められ雇って貰う必要があるのだ。今居る宿舎は言わば、騎士の養成所なのである。
「と言う訳で契約成立だ。明日から宜しく頼んだぞ。」
「はい、公爵様。」
***
オルヴァスがパラフィーネ家所属の騎士に任命された頃、メルヴァントも幾人かの貴族から騎士任命の話を承っていた。無論あれから四年の月日を経ているのだから、アジィールとシャレール等は既に一人前の騎士としてラプタスの国土を駆け回っている。騎士として多忙な日々を過ごす四人は顔を合わせる機会が減った、という事も無くむしろ今まで以上に交流を深めていった。
唯一つ変わった事と言えば、オルヴァスは以前と比べて彼のアズリータと会う機会が増えたという事だ。何しろパラフィーネ家の騎士に成ったのだから可笑しい事では無いのだが、当の彼女の方が幾らか彼を意識している様に見受けられた。
「いよいよ色男のオルヴァスも騎士か……。いやぁ、おめでとう。今日は俺からの祝福だ、遠慮せず飲んでくれ。」
「祝って頂き、有難うございます。」
アジィールが気前良く言った。オルヴァスよりも彼の方が遥かに嬉しそうだ。
今宵は例の四人で酒屋に来ていた。シャルティネの酒はとても美味しい。其れは美しきイグリュータ川から騎士達への恵みなのだろうか。
「アジィール、酔って人の肩に抱き着くの止めたらどうだ。」
オルヴァスの肩を馴れ馴れしく触る彼にシャレールが怪訝そうな顔を向ける。アジィールが煽るように一杯飲んで、
「うるせえ。俺は未だ酔ってないっ。」
言い張ったが既に辺りは空の杯で溢れ返っている。
メルヴァントはそんなアジィールを遠巻きに眺めながら、黙々と飲んでいた。目の辺りがほんのりと赤い。一人で飲む余り、うっかり飲み過ぎてしまった様だ。
「メルヴァント、飲み過ぎじゃないか?」
「うん……?」
オルヴァスが心配して尋ねた。メルヴァントが虚ろな目で笑う。
「大丈夫だって……。君より酒には強いんだ…。」
其れが引き金に成ったかの様にメルヴァントは何やら物々と呟き始めた。
「私だって、もっと早く…其れこそオルヴァスよりも早く、騎士に成れていたら……。其れはね、オルヴァスの方が剣の腕もありますけどね……でも彼だけパラフィーネ家の御抱え何て……狡いですよ。」
アズリータの事になると如何にも自棄酒に誘われる様だ。メルヴァントに悪気は無い。唯、酒という名の酩酊感が彼を饒舌にさせている、其れだけの事だ。
彼はアズリータへ恋心を抱いている。其れが彼の騎士道精神を燃え上がらせているのは事実ではあるが、物思いというのは何とも辛い。其れが身分違いの恋となると此れはもう焦がれてしまいそうになるのである。そんな悩みもあり、中々御目に掛かれない女性の屋敷に出入りするオルヴァスが羨ましくも恨めしくもあったのだ。
「あぁ、すっかり酔ってるな……。」
シャレールが呆れて呟いた。全くどうしようもない面々である。
「そうか…メルヴァント。俺には其の気持ち、分かるぞ。辛いよな……そうだ近くの遊郭にでも連れて行ってやろう。」
アジィールがメルヴァントと肩を組み、店から出ようと歩みを進める。
「おい、今日はオルヴァスの祝賀会じゃあなかったのか?俺からの祝福とか何とか言っていただろう?」
「そんなのは終いだ。今からは男の慰み合いをするんだよ。気に入らないなら帰ってろ。」
シャレールは溜め息を付いた。全く、本当に勝手気ままである。アジィールとは長い付き合いではあるが、こういう所は中々慣れない。しかしそんな彼の強引な所に惹かれない訳でも無い。其の実、彼はこうしてアジィールと行動を共にしているのだ。
「オルヴァス、すまない。奴は嗚呼見えて人情深い人間なんだ。言葉は上手くないけれど……。悪気は無いから許してやってくれ。」
まるで自分の失態の様に申し訳なさそうに謝るシャレールに、
「そんな、別に良いですよ。元より怒ったり何てしてないですし。…其れに私は誘って頂いた立場なので。」
オルヴァスは爽やかに微笑んで言った。
「でも、シャレールさんは優しい人ですね。アジィールさんの事を信頼していて、何だか羨ましいです。」
「否、私は決して優しくなんて無い。」
自嘲的な笑みを浮かべて呟く。
悲哀を帯びた様な憂える彼の表情がオルヴァスに何だかとても切ない思いをさせた。シャレールはどの様な人なのだろうか。今まで余り深く関わって来なかった為、シャレールの事をどうもよく知らなかった。何しろ、彼は普段から寡黙で中々人と関わりを持たないのである。二人で話す機会等そうなかった。
結局二人は早々に店を出た。四人分の酒代を払ったのはシャレールだった。其れを見たオルヴァスはやはり彼は優しい人だと思ったのだった。
***
其れから数日後のこと。メルヴァントも遂に騎士と成り、アステューク家の子息として大きく期待された。シャルティネ郊外のとある伯爵の所属となったが、抱いていた様な不満は伯爵の人柄に触れて一気に払拭されたのだった。
年の暮れも深まり、益々シャルティネの町は活気付いている。何とも濃密な宵の口の頃。パラフィーネ公の屋敷で貴族や騎士が大勢招かれる舞踏会が催された。其処には勿論、直属の騎士であるオルヴァスをはじめ、メルヴァント等も招待された。何とも大規模な集いである。
「まぁ何と逞しい御方でしょう。」
「あの方が彼の有名なパラフィーネ家直属の?」
「そうよ、オルヴァス=ルシアネス様。あの方はバルタの御人なのよ。」
屋敷の前で護衛をしているオルヴァスを見て、貴婦人達はそんな言葉を交わしてゆく。今、貴婦人たちの話題の中心は聖戦と夫である貴族の愚痴、そしてオルヴァスやメルヴァント等新たな騎士である。唯、騎士が強いか否かではなく、容姿や才覚、家柄等他愛も無いものばかりであった。
「オルヴァス、凄いな。君は本当に女性から人気があるなぁ。」
門扉の前で彼と会ったアジィールはやけに厭らしい目を向けながら言った。
「何しろ今日はアズリータ嬢も出席なさるんだ。気があるなら上手くやれよ。」
「…私はそう言うのでは無いですから。」
嘘ではない。確かに彼は未だ自らの心の内に眠る、淡くしかし激しい恋心には気づいていないのだ。
「ほら、そんな所で油を売ってないで行くぞ。」
聞き慣れた声に振り返ると、アジィールを見下げた様に見つめるシャレールが立っていた。
彼は今日も何処か悲哀を帯びていて、凛として動じないのだった。
「…シャ、シャレール。御前も招待されたのか。」
「当り前だろう。今夜の舞踏会はあらゆる貴族騎士が招待されている。寧ろ招待されていない者は騎士ではない、と言っても過言ではない。」
すっかり見慣れた遣り取りを交わしつつ、シャレールはアジィールをオルヴァスの前から連れ去って行った。
(アジィールさんもシャレールさんも手慣れたものだな。舞踏会なんて初めてだから如何して良いやら…)
「オルヴァス。」
彼是と思い悩んでいると友人のメルヴァントが微笑みを湛えながら、歩み寄って来た。
透き通るような金髪を風に靡かせる。あどけなかった顔立ちもすっかり大人の男の表情に変わり、青い瞳が何とも凛々しかった。
「メルヴァント……。」
「オルヴァス大丈夫か?舞踏会初めてだろう。何かあれば遠慮なく私に訊いてくれ。伊達に貴族の三男坊でも無いからな。」
優しく笑った。オルヴァスは彼の良く気が利くところを尊敬している。メルヴァント自身は意識しているのでは無いのだろうが、其の無意識の優しさが有り難いのだ。
「大丈夫…。若干緊張して疲れただけで、心配要らない。有難う。」
「其れなら良かったよ。……あ、そろそろ時間だからまた夜、宿舎でな。」
騎士と成った今でも、二人は何故かヴァイゼン公直属時代の宿舎で寝泊まりしていた。
「…言い忘れたけど……。」
メルヴァントがそう言いながら戻って来た。オルヴァスが不思議な顔をしていると、
「良い人、見つけろよ。」
アジィールの受け売りとも思しき一言を残して去って行った。オルヴァスは騎士に成る以前からよく、アジィールと町に出ていた。近頃は夜分遅くに酔って帰るのが日課とも成っている。そんなメルヴァントをオルヴァスは密かに心配しているのだった。
煌びやかな装飾、絢爛豪華な絵画や美術品が並び、壮大な音楽が奏でられる会場。其れに劣らぬ程着飾った貴婦人や貴族、騎士でさえも襟元などに 細やかな刺繍を入れる等していた。町でも目にした事の無い賑わいに圧倒される。
舞踏会が始まり、屋敷の門前を護衛していたオルヴァスも参加を促された。だが、余りの人の多さに困惑するのだった。周りは見知らぬ顔ぶれ。メルヴァント等の居場所など到底分かるはずもない。
(私は如何すれば良いのだろうか……。)
分からず、会場の隅に立ち竦んだ。目の前には酒を飲みながら語り合う貴族や、何とも美味しそうな色鮮やかな料理を頬張る夫人、貴婦人。彼方では男女が手を取り合って踊る。目の眩む様な光景だった。
慣れない為、少し歩いただけで疲れてしまった。水を一杯嚥下し、気分を落ち着かせる。溜め息をついた頃、見慣れた人影が前を横切った。風の様に颯爽と歩く其れは確かにシャレールで、驚く程足早に外へ向かっている様だった。追い駆けようと一歩踏み出した途端、同じ方向から数 人の貴婦人がシャレールの後を追う様に横切った。
「何処へ行かれたのかしら。シャレール様が舞踏会にいらっしゃるなんて。」
「此の様な場では余り御見掛けしない御方だから、一度は共に踊って頂きたいわ。」
口々に漏らした。彼は余り貴族の催す会合に出席する性質ではない。
アジィールはそんな彼を昔は良く誘ったものだが、今は無理に誘う事はしない。何となく彼の触れて欲しくない部分に触れた気がしたからである。
其の様な事情など貴婦人たちは知る由も無いのだが、何とも執念深い。確かに彼は其の見た目の為、女性から思い慕われている。しかし本人は恋、等というものに興味を示さないのだった。
オルヴァスは何となく気になって、シャレールを追って露台に出た。シャレールは確かに其方へ向かった筈だったが彼の姿は無く、唯会場よりも静かで夜空が美しいだけであった。
(見失ってしまった……。シャレールさんと少し御話してみたかったのに。)
「オルヴァス様?」
包み込まれる様に心地良い声と共に長髪の少女が隣に立った。
「……アズリータさん。」
一瞬気が付かなかった。何しろ今宵の彼女は美しい装束で、黄金の耳飾りや腕輪を纏い、一層美しかったのだ。細く白い腕を露出し、鎖骨の美しい筋が何とも妖艶である。
「こんな所でいらっしゃるなんて。…舞踏会は楽しんで頂けなかったかしら?」
「いえ…、慣れないもので御恥かしい事に、疲れて仕舞いまして。」
「初めは皆、如何して良いか分から無いものよ。此れから身に付けていけば良いのだから、気にしなくて良いわ。」
アズリータは柔らかく笑う。彼女からは何故か不思議と甘い雰囲気が流れている。其れが如何してかは分からないのだが。
「あとシャレールさんを御見掛けしたので御話しようと思っていたのですが、見失ってしまって。」
「あら、シャレールと?また逃げていたのね。あの人逃げ足速いでしょう?」
オルヴァスは困った様に頷いた。アズリータはふふふ、と笑ってオルヴァスの耳元で囁く。
「あの人のこと、知りたい?私なら教えてあげるわよ。」
耳の奥がくすぐったい。こんなにも至近距離で囁かれたこと等無く、至極緊張した。
「あっ、でもそんな…勝手に人の話を御聞きするのは……。」
本心は確かに気になっていた。しかし他人から聞き出すのは何だかシャレールに悪い気がする。誰しも触れられたく無い過去はあるものだ。
「では私の思い出話とでも思って聞いて頂戴。」
アズリータは懐かしそうに目を細めて語り始めた。
***
未だラプタスの騎士が大陸に名を轟かせる以前の事。アズリータは父パラフィーネ公爵の職務の都合でラピシィアに滞在していた。至る所に花柳街が広がり、美しい装飾を模した衣装、建物は豪華絢爛でありながらも、過剰ではなく大層素晴らしい町であった。
そんな地での滞在も最後となった日の夕暮れ。公爵が一人の少年を連れ帰った。意識が無く、酷い外傷を負っていた為に公爵が自ら抱きかかえて来たのだ。パラフィーネ公の話によれば、賑わう町の隅で数人の大人達に痛めつけられていたそうだ。可哀想に思った公爵が思わず連れて来てしまったのだった。
公爵は自らの領地に彼を連れ帰った。三日三晩意識を失ったままであった為、其の儘残して帰る訳にもいかなかったのだ。
目を覚ました少年は浮世離れした美しさで、此の世の者では無い神秘的な雰囲気を宿していた。其れはまるで産まれたばかりの赤子の様に清らかで、穢れの一筋も無い様な不思議さがあった。そんな優美な少年を公爵は大層気に入り、養子に迎える事にして屋敷に住まわせた。
少年は見る間に背の高い、しなやかで華奢な青年に成長した。屋敷の中で誰もが一目置き、易々と話しかける者など居なかった。
アズリータは其の頃の事を鮮明に覚えている。誰も寄せ付けぬ凛とした雰囲気の狭間で、何処か悲しげな青年の姿を。当時の彼女は彼が気に掛かり何度も声を掛けようと試みていた。しかし、いざ声を掛けた途端に瞳の煌めきは消え去り其れが又、彼の機嫌を損ねたのではないかと気に病んでしまうのだ。
何時の日からかそんな彼に笑って居て欲しくて、けれども絶望的な眼差しを向けられることが辛くて、声を掛ける事が出来なくなっていた。其れは彼女が初めて感じた恋心。もどかしくも辛い恋情を青年に抱いてしまったのである。
彼女が自分自身の奥深くに潜む恋心に気づき始めた頃、彼がラプタスの騎士団に入隊するという噂が流れた。
「貴方、此の屋敷を出るというのは本当なの?」
此の時ばかりは不安や恥ずかしさ等振り払って尋ねた。もし知らぬ内に彼が此の屋敷を出て言ってしまったなら、言葉を交わせなかった事を悔いるに違いない。其ればかりか、もう永遠に会えぬかもしれないのだ。其れならば、せめて別れの言葉を告げておきたい。
「…ヴァイゼン公の元に騎士見習いとして修業を積む。……何時までも此の屋敷に世話に成る訳にはいかない。」
「そんな…。貴方は此の家の、家族の一人よ。自立するまで養うのは当然だわ。其処に恩義や義理を感じる必要なんてないのよ。」
引き止めたかったのだ。恋い焦がれて止まない其の青年に、嘘でも此処に残る、と言って欲しかったのである。
「だからこそ、何時までも此の立場に甘んじていてはならないのだ。元は素性も分からぬ身寄りもない子供。そんな私を養子にして頂いただけでもあり難いのに、此処までして頂いた。」
「でも、御父様もきっと留まって欲しいと……。」
「私には使命がある。其れは公爵様にも分かって頂けた。思い残す事は何も無い。私は此処に、悠長に戯れに来たのでは無いのだ。」
アズリータは酷く落胆した。想い人が行ってしまう。此のもどかしい気持ちを伝える事も出来ずに。其ればかりか、彼には浮ついた恋心や浅ましい欲など微塵も無い。元より独り善がりの叶わぬ恋であったのだ。
「今まで世話に成った…有難う。」
其れが、彼が最初で最後に目と目を合わせて交わした言葉であった。
アズリータは其の日、一晩中泣き明かした。何故かは解らなかったのだが、瞳から涙がはらはらと零れて止まらなかった。
「……昔の話よ。今となっては懐かしい思い出だけれど。」
アズリータは滅多に見せない様な情けない顔をするのだった。けれども其の表情は一瞬の内に思い出を懐かしむ慈愛の色に変化した。
「唯一つ忘れられないのは、彼が父上に最後の挨拶をしていた時の事……。」
青年の旅立ちを未だ受け入れられず、快く送りだす為の言葉も何もかも口に出来なかったアズリータは、出立前の青年の姿を最後に目に焼き付けて置こうと公爵の部屋を密かに覗き込んでいた。
熱い視線の先には公爵と彼と同じ位の背丈の青年。彼の澄み渡った青い瞳は公爵唯一人に向けられ、二人は談笑している。
落ち着き放っているのは相変わらずだが、身を委ねる様な安心感に包まれた彼の微笑み。まるで想い人を見つめる様な慕わしげな瞳。
アズリータは彼のそんな表情を初めて見た。そして悟ったのだ。彼は本当に自分を何とも思って居なかったという事、初めから叶うはずも無い恋だったという事、そして何よりも父親である公爵を心から尊敬していて、父も彼を気に入っているのだという事。男同士の固い絆とでも言うべきか、其れには決して敵わないという事実。全てが一度に理解出来た。だからこそ本当に驚く程素直に、身を引こうと思えた。
「当時は辛かったのだけれど、今はシャレールに出会えて良かったと思っているわ。」
(神は私を何時でも良い方へ導いて下さるわね。)
アズリータは例の如く微笑んだ。
「聞いてくれて有難う。…今宵はゆっくり楽しんで頂戴。」
オルヴァスが礼を言う暇も無く、去ってしまったのだった。日頃は中々御目に掛かれぬアズリータ嬢に、兼ねてから関心のあるシャレールの話を聞けたのだ。人波に酔った疲れも何処へやら、此の上ない経験に満ち足りた気分であった。
***
華の去った露台に独り夜風を浴びる、オルヴァス。舞踏会に出席して居るというのに、未だ誰とも旋律の一時を過ごしていない。慣れない出来事に如何対処して良いのか分からないのだ。
「オルヴァス、人に酔ったのか?其れとも単に飲み過ぎたか?」
聞き慣れた声に振り返ると、穏やかな微笑みを湛えたシャレールが杯を手にして立っていた。
「あぁ、シャレールさん。……私は田舎育ち故、此の様な絢爛豪華な式典には不慣れなもので……。」
「そうか。私も同じだ。何時まで経ってもアジィールの様には振る舞えない。何しろ貴婦人と一時の踊りを嗜むという習慣が故郷には無い故。」
「ですが其の貴婦人が先程まで貴方を探して居ましたよ。」
オルヴァスが笑って言うとシャレールが困惑した表情で、
「やはりか。私は如何も女性の御相手をするのが下手なのだが、其れに反して貴婦人の方々は私に一興迫ってくる。本当に困ったものだ。」
今夜のシャレールは何時になく多弁である。其れが酔いから来るものか、又は別の訳があるのか、オルヴァスには分からなかった。だが、彼と話が出来る望んでもみない好機であったのは確かである。
「あの、先程アズリータさんが此処にいらして少し御話させて頂いたのですが……。」
シャレールが不思議そうに首を傾げて言葉の先を待つ。
オルヴァスはシャレールに如何してもアズリータから過去の話を聞いた事を伝えて置きたかった。尊敬する先輩騎士のシャレールに隠し事はしたく無かったのである。と言うよりは秘密を隠す胸の内が、彼に如何も見透かされてしまいそうだった。
事の全貌を聞いたシャレールはオルヴァスを叱責する事も無く、唯アズリータに対する呆れた溜め息を付いた。
「全く、あの御方は誰かれ構わず他人の事を話す。気を付けて頂きたいものだ、パラフィーネ家の品性に関わる。……しかしオルヴァス、私が其の様な過去が遭ったと隠していた事、責めるか?」
「いいえ、人は誰しも一つや二つ触れられたく無い過去を持っていると思います。だから責めたりはしませんよ、決して。」
敢然とした輝きを宿す瞳にシャレールは大きく目を見開いた。思い掛けない返答に内心嬉しかったのである。今迄生きて来た中でアジィールを除いて、皆が皆一様に自分に対して強い興味を示して来た。そして触れて欲しくない部分に遠慮も無く触れてくるのだ。其れが歯痒くてならなかった。何時でも不愉快だった。
「そう言ってくれたのはアジィールと君だけだ、有難う。」
感謝せずには居られなかった。オルヴァスにも自分自身を導いて下さる神々にも。
「御礼を言って貰う様な事では有りませんよ。……折角ですから少し御話しませんか。」
辛気臭くなった雰囲気に耐え切れずオルヴァスは提案した。
「私は以前からシャレールさんと御話してみたかったのです。」
「其れは嬉しい限りだ。」
微笑みと共に露台には穏やかな風が吹き抜けていった。
***
屋敷は舞踏の音楽と賑やかな歓声が包み、夜空の星は頭上を高く舞っている。
オルヴァスとシャレールの二人は滅多に無い機会を大いに楽しんだ。故郷の話やら他愛も無い世間話迄。音楽と共に女性と演舞していては味わう事の出来ない濃密な一時を過ごした。
「……オルヴァス、君は七種神の敬虔な信者だと思うが、神々が遣わせたと言う使徒の存在を信じるか。」
其れは唐突な問いかけであった。
天地を創造したと言う七神の話は此処ラプタスは勿論、人々の唯一の信仰神とされている為、知らぬ者など居ない。故に無論、残虐で終わりの無い戦乱が満ちていた過去、南半球に神々が遣わせた使徒の存在を知らぬはずは無かった。
しかし使徒の存在は、まやかしや悪魔崇拝者の虚偽妄想ではないかとも言われている。ある種此の話は神話の中の伝説と化していた。信じる者も信じ無い者も両者多数存在する。何せ大昔の話であるから、実際に使徒を見たと言う者も居ないのである。
そんな話を何故シャレールは唐突に切り出したのであろうか。
「私は神の御導きと言うものを信じて下りますし、実際ラプタスの地には神々が宿っていると感じる事も多くあります。美しい山、綺麗で美味しい水、此れ等を与えたもうた神々には深く感謝しています。…だから、其の存在が確かなものかは分かりませんが、必要と有らば神は使徒を遣わして我らをお導き下さるのだと、私は勝手ながらそう解釈しております。」
まるで全ての摂理を知った様な堂々とした態度に、シャレールは再び驚く羽目に成った。
此の世界は思いの外、神話に厳しい。少しでも神の御導きに相応しくない事があれば、其れ等を全て否定する傾向が強いのだ。だからこそ此処、神の宿る場所(ラプタス)では巫女や聖職者は重宝されるが、呪術師や使徒等は悉く異端視され、酷い差別に遭っている。
其れが此の世界の常とでも言うべきか。しかしオルヴァスは何とも対等で適切な洞察力を持っているのだろう。未だ見ぬものに恐怖や軽蔑等せず、寧ろ強い興味を持っているのであった。
「そうか。オルヴァス、其の清らな心を忘れてはならないぞ。」
「え…、あ、はい。…そう言うシャレールさんはどの様に御考えですか。」
予想通りの返答である。此の話題をすれば必ずそう返って来る事位、彼には容易に理解できたはずなのだが。如何した事か、つい自ら禁忌としている話を自分で始めてしまったのだ。其れはオルヴァスに今迄出会ったどの人とも違う何かを感じたからであろうか。
「そうだな……、私は話すと長く成ってしまうが、君さえ良ければ話をしよう。」
「……はい、是非に。」
其れは名も無い時代の小さな、小さな物語であった。
***
絶対の真理が七種の神に委ねられ、今よりずっと差別や偏見が強かった頃。端的に言えば、未だバルタが田舎の蛮人と呼ばれていた頃だ。
花柳の巷ラピシィアにシャレールは誕生した。神の愛に溢れた子供の誕生に、祝福の鐘が鈍く鳴らされる。皆が其の神の御導きに歓喜し、諸手を上げて感謝した。
何時の日も子供の誕生は心からの祝福を受けるべきであり、神は特別な寵愛を幼子たちに向ける。何ら変わらぬ光景、此れが日常。
しかし思い返してみれば、自分の誕生は其の様な祝福されたものでは無かった様に思う。
何故なら其れは自分には親から与えられた、もしくは神に導かれた名の他に、「生まれ持った名」があったからだ。其れは誕生した子供が唯の赤子ではない、もしくは特別な宿命を帯びた生命である事を意味していた。
そんな特殊な子供を持った両親は、やがて狂信的な七種神の信者によって殺された。同じ部屋にいた自分だけが無様にも生き残った。其れも此れも「生まれ持った名」が齎す災い。
幼くして両親を失ったシャレールは義理の兄の家族の元へ引き取られた。しかし間もなく煩わしく思った其の家の母親によって、遊郭へと売られた。花柳の巷と言われるだけあって、其処ら中至る所に遊郭があったのだ。勿論男色家向きの娼館も用意されている。
訳も分からず男娼と成った彼だが、客は一人も取らなかった。其の見た目から何度も言い寄られたが、一度も体を開いた事は無い。誇り高き貞潔の心だけは忘れないでいた。
酷い毎日だった。地獄を這うような日々、終わりの無い悪夢。何時しか楽しさや喜び、感動や恋情等忘れてしまった。古く色褪せた感情は今でもかの帳の中に置き去りに成っている。
「……ずっと孤独だった。」
彼方を見つめるシャレールの表情はとても悲しげであった。細く薄く今にも割れそうな儚げな横顔。綺麗であるが酷く冷たい、何とも言えぬ悲しみが其の表情から伝わってオルヴァスも無性に悲しくなった。
「震えそうな程に寂しくて、独り冷たい部屋の中。今でも思い出す。」
彼を孤高の風が包み込む。昔日の煌めきを纏う星々と月明かりの下で彼の白い肌が一層美しく映える。
「全ては私が、生まれ持った名の為。」
「……其れはどの様な名だったのですか。」
オルヴァスは興味と畏敬の念を宿しつつ遠慮がちに尋ねた。
「……アネモス。」
「其れは……。」
オルヴァスは衝撃の一言に慄然となった。
何故ならアネモスとは七種神の一神の名であるからだ。神から導かれた名というものは存在するが、神其のものの名を持つ者は神以外にあるまい。つまりはシャレールが他ならぬ特別な生命である事を示しているのだ。
「そう、アネモスとは此の世の静寂を司る神の名だ。生まれた時から私には此の名が与えられていた。特別な名と託された使命、其れを果たすために私は……。」
オルヴァスは終始驚きを隠せないで居たが、暫くしてゆっくりと口を開いた。
「そうなんですね、シャレールさん。貴方は神の使徒だと、そう言うのですね。」
シャレールは静かに頷いた。
「そうだ。冗談を言っている訳でも、嘘を吐いているのでも無い。信じられないかもしれないが、私は神に遣わされた使徒なのだ。」
確かに容易く信じられる話ではない。しかしオルヴァスは、自ら心を開き身の上話をしたシャレールが嘘を言っているとは到底思えなかった。其れに、彼が特殊な名を持って生まれたが故に幼くして両親を亡くした、と言うのであれば合点がいく。
決して驚かなかった訳では無い。だが普段から冷静沈着で寡黙なシャレールを誰が信じないだろうか。もしかすると彼は、自分の考え方を知った上で身の危険にも関わる重要な話を自分にしたのかもしれない。其れだけ信頼して貰っている、という事だ。其れ程嬉しい事は無い。何せオルヴァスが 憧れて止まないシャレールなのだから。
「信じていますよ、シャレールさん。貴方の事、嘘だとか変だとか思いません。だって、シャレールさんはシャレールさんではないですか。例え神からの密命を帯びて此の世に遣わされたのだとしても、私の目の前に居るのは凛々しくてけれども孤独な一人の人間です。」
俯きがちのシャレールは其の一言にふと顔を上げた。オルヴァスの暖かな一言が痛い程嬉しかった。
本当は話すべきではないだろう、幾度も思った。此の世界は温かいようで実は冷酷其の物なのだ。皆が皆自分の様な存在を受け入れるとは思わない。しかしオルヴァスの強く芯のある言葉に、此の人になら話しても良いのではないか、初めてそう思った。
今迄ずっと独りで抱え込んできた。誰にも言えない秘密。言えば最後、捨てられるに違いない。自分は他人と違うのだ、人は違うものを強く拒む。だから言えなかった。アジィールにさえも。怖かった。初めて心を許した親友に裏切るような真似はしたく無かった。怖くて、震えて、何時も逃げていた。
しかし今は違う。オルヴァスの一言が心に染み入った。今まで感じていた恐れは何処かへ消え去り、受け入れて貰えた喜びが強く込み上げる。
人には必ず違いというものがある。だが其れは、今まで自分が恐れてのた打ち回る様な歪んだものでも、隠して置かねばならないものばかりでも無い。存在していて当たり前なのである。生きているのだから。唯自らの秘密は此の世界では未だ風当たりが強いだけである。
そんな単純な事に今の今迄気が付かなかった。
「オルヴァス…有難う…。私は今迄ずっと苦しかった。独りで広い世界を彷徨っている様な気分で……。」
「シャレールさんは一人なんかじゃありませんよ。確かに以前はそうだったかもしれない。でも今は此処に私が居ます。メルヴァントが居ます。貴方の大切なアジィールさんやヴァイゼン公、パラフィーネ公にアズリータ嬢。こんなにも沢山居るじゃないですか。賑やかで困ってしまう位に。ちっとも寂しくなんてありませんよ。」
オルヴァスは意志の強い目でシャレールの両手を取った。強く強く握りしめる。独りではないと感じさせる様に。何とも一生懸命で健気であった。
シャレールの視界に映る赤毛が不意に歪む。一瞬で景色がぼやけて、揺らめく。大粒の雫がはらはらと零れ落ちた。止まる気配は全く無い。何故涙が出るのか分からなかった。涙等もう何年も流していない。
切れ長の瞳から留まる事なく流れ落ちる涙。雫が月明かりに煌めいて、綺羅とした星と成って落ちてゆく。涙するシャレールは美しさ其の物だった。
シャレールの歪んだ視界に薄っすらと微笑みが揺らぐ。解き放たれた様な安心感に其の儘泣き続けた。
七種の神が此の世に救いを与えるために遣わせた七人の使徒。誘惑、忍耐、創造、解放、挑戦、破壊
そして静寂。其れ等を司る神と其の分身である使徒。使命を帯び、呪術を使う者達は此の世界に何を見ているのだろうか。多くの謎が未だ明らかにされぬ儘ラプタスは大乱に巻き込まれてゆくのであった。
***
舞踏会から三日が経った頃。年の終わりに如何しても緩みがちな雰囲気。だが其れを一瞬で緊迫したものに変える様な突然の騎士団招集があった。
ヴァイゼン公の元にシャルティネの騎士達が集う。年明けも近いと言うのに不吉な予感を誰もが感じていた。
オルヴァスは例の面々で集い頻りに緊張していた。メルヴァントの表情も何処か硬い。騎士達の流言飛語で落ち着いて居られる様な心境ではなかった。しかしアジィールとシャレールは何時に無く真剣な面持ちで待機していた。
「極度に緊張する事も無い。きっと聖戦の御話だ。大丈夫、何かあれば俺達が支えるから。」
「そうだ。今更緊張しても仕方が無い。落ち着いて神経を集中させるんだ。」
尊敬する先輩からの助言に二人の若人は深く頷き、大きく深呼吸をした。
此の様に落ち着き無いのも仕方が無い。近頃聖戦の戦況が良くないのだ。信憑性の高い話でもないのだが、シャルティネに流れ込んで来るのは、此の頃負傷兵ばかりである。騎士や町の者は皆、暗黙の内に聖戦の戦況が芳しく無いものである事を悟っていた。
「皆、此の様に年の暮れに集まって貰って済まない。私が今日君たちラプタスの騎士を集めた訳は、もう既に察しが付いているだろうが……。他でもない聖戦の事だ。」
慌ただしく屋敷に入って来たヴァイゼン公が開口一番、簡潔に述べた。
此処数年、安定していた戦況が一転し国境付近では隣国との衝突が絶えない。其ればかりか近頃建国された小規模の国家が同盟を結び、連合軍として度々ラプタス周辺を行軍しているのだ。御陰で多くの兵士が命を落とし騎士達も重傷を負う等多大な犠牲を出している。
そもそも七種の神のみが存在する此の世界で何故聖戦が勃発するのか。其れはラプタスと言う何物にも代え難い聖域が大きく関わっている。七種神が此の世界で初めに創造した場所、其れが此処ラプタスと言われている。神が生み出した創世の場所がラプタスなのだ。此処には神が宿り、其の恩恵を受けたタレファルナ山脈やイグリュータ川は何時でもラプタスの者に恵みを齎して来た。
では何故同じく七種神を厚く信仰する者達が、其れ等の神の恵みを受ける事が出来ないのだろうか。
初めは小さな疑問だった。しかし何時の日からかラプタス周辺の国々は皆一様にそう考えるように成ったのである。
可笑しい。国こそ違えど我等とて神々を心から崇める信者である。我等も神の恩恵を受ける権限は有るはずだ。
周辺の国々は一斉に兵を上げた。神の恵みを独占して発展しているラプタスを打ち破り、タレファルナ山脈やイグリュータ川を万人の下に開く為に。大義を抱えた兵士達は死に物狂いで戦った。幾年経ても其の姿は変わらない。七種の神の元に起こった戦いは大陸中の尊い命を奪い、豊かな自然を血塗られた凄惨な光景へと変えてしまったのである。
「……我等には大義がある。神から授かりし、此処ラプタスを戦火から守らねば成らない。だからこそ君たち騎士団には前線で戦って貰いたい。」 ヴァイゼン公は重々しく語った。神の為、郷国の為とは言え、此の国の明日を担う若人たちの活きた命が奪われるのだ。此れ程心苦しいもの等無い。何しろ騎士団の中には自ら育てて来た大切な教え子も居る。
しかし此れは宿命なのだ。神の為に命を投げ出し、生きるか死ぬかの状況で戦い抜く。其れはもう無情にも神に定められた運命の如く。一人の人間が嘆き悲しみ、抗ったところで如何にも出来ないのである。其の運命を受け入れ唯、騎士達の瞬く命を案じる他に乗り越える術など無い。
「三日後の明朝、ラプタス南端ミグルへ出立する。其れ迄に準備を済ませて置く様に。…此度は激戦に成るだろうから家族や恋人、想い人との別れを惜しんで来なさい。」
其の一言が公爵に出来る唯一の気遣いであった。
自分の言葉に純粋な目をした少年達は大きく頷く。其の様子が何とも健気で、若かりし頃の自分を思い出させる。戦の凄惨さや残酷さ、悲しみ、失うもの大きさ等全く知らなかったあの頃、此の少年等の様に勇んで聖戦に出たものだ。当時は唯純粋で何も知らなかった。其れで良かった、其の儘で在りたかった。
「遂に俺達も聖戦に参戦する日が来たな。」
「あぁ、そうだな。」
「気を引き締めて行くか…ってメルヴァントとオルヴァスは未だ緊張気味なのか。全く、若いなぁ。」
言いながらアジィールは二人の背後に回り込み、勢い良く肩に飛び付く。
「はぁ、辛気臭い顔するな。大丈夫だよ、初めは皆緊張する。何か在ったら俺達が助けてやるから、心配するな。」
「アジィールは頼りに成らないが、戦場には多くの騎士が集う。皆、親切だろうから案ずる事は無い。」
シャレールが苦笑いを浮かべつつ、例の如く毒を吐く。
其の軽い冗談にメルヴァントとオルヴァスは、漸く気分が少し落ち着くのであった。
「相変わらず御前は酷い物言いだな。……まぁ先の事を何時まで悩んでも仕方が無い。折角ヴァイゼン公が三日間の猶予を与えて下さったんだ。酒でも飲みに行くか。」
アジィールの楽天さに戸惑いつつも、何時でも知らない世界を見せてくれる彼にメルヴァントとオルヴァスは、心地良さを覚えずには居られなかった。勿論シャレール有ってこそのアジィールではあるが。
此の二人を尊敬して止まないのは、人を惹き付ける何か強い魅力があるからであろうか。
「…否、待てよ。酒よりも先に大切な事がある。」
「其れは一体何ですか?」
メルヴァントが興味津々と言った目で問うた。
「……勿論アズリータ嬢に決まってるだろう。三日間の内に大切な人と別れを惜しむ、公爵は其の為に日取りを合わせて下さったんだ。此の好機を逃してはいけない。…さぁ二人共、行くぞ。」
強引に二人を引き連れて行くアジィールの背後でシャレールは何時に無く大きく溜め息を付いた。
(全く口を開けば、ろくな事を言わないな。)
呆れ果てるのだが、黙って彼の後を追うシャレールはやはり心根の優しい人物なのであろう。
其の後、アジィールの突拍子も無い行動に振り回されるシャレールとメルヴァント、オルヴァスであった。
***
三日間は瞬く間に過ぎて往った。聖戦への緊張と不安を一時でも忘れる事が出来た有意義な日々を過ごす事が出来た。
聖戦前夜ラプタスの夜は少し長い様で、昼下がりからアジィールと出掛けて行ったメルヴァントは未だ宿舎に帰らない。オルヴァスは一人で先に就寝する気にもなれず、夜のシャルティネの町を歩いてみた。
何処からか優雅な音楽と談笑する声が聞こえる。柔らかな部屋の灯が外まで漏れ出て外気を包むと、メルヴァントの居ない事が堪らなく寂しかった。何故か弱気に成って仕舞うのは、明日への不安からだろうか。
行く宛も無く放浪していると、背後から自分を呼び止める声がして衝動的に振り返る。
「オルヴァス様?」
小さな歩幅で駆け寄って来たのは、アズリータであった。
今宵の彼女は又、普段とは違う質素な衣装を身に纏って居た。束ねられていない髪は彼女の動きに合わせて流れる様に靡く。暗闇の中では市井の少女とも見分け難い格好に、彼女が実は幼い顔立ちである事が思いがけず知らされる。
「アズリータさん、此の様な所で一体如何されたのですか。」
驚きを浮かべつつ、彼女を守る様な形で肩を並べて歩く。実に紳士的な行動である。
「明日が出立の日だと伺い、貴方に御渡ししたい物が有って……。宿舎に伺いましたが留守にされている様だったので探して居たのです。」
何の考えも無く外へ出歩いた事がアズリータに余計な手間を懸けさせたのではないか、と若干の心配を覚える。しかし、何の用があって探して居たのかが妙に気に成った。
「父上から聞きました。聖戦は激化している、今回は多くの命が失われるかもしれない、と。……騎士の皆さんには一人も命を落として欲しくは有りませんが、私が咎める事は出来ません。私には此処で案ずる事しか……。」
悔しげに唇を噛み締めながら俯くアズリータ。其の目は薄っすら潤んでいる。
「何も出来ない自分を怨みながら、三日間神に祈って居ました。皆さんを御助け下さる様に、と。…其の祈りを此れに精一杯込めました。」
そう言いながら取り出したのは、煌びやかな首飾りであった。夜空の星を切り取った様な宝石があしらわれ、青い光を放つ其れは正しくアズリータの首に輝くに相応しいものである。
「貴方に此れを託したいのです。私の強い祈りが込められた此の首飾りを私に代わって、戦場に連れて行って貰えないでしょうか。…何時でも貴方と共に私の祈りがある事を、忘れないで欲しいのです。」
「こんな大切なもの、持っては行けませんよ。幾ら身代わりとは言え貴女を危険に晒す様で、堪りません。」
此の儘では折角祈りを込めた首飾りを受け取って貰えそうにないと思い、オルヴァスの骨格の美しい手を取って、首飾りを握らせた。
「そんな…いけません。貴方とも在ろう御人が。」
オルヴァスが慌てて首飾りを返そうとすると、アズリータはあの独特の笑みを浮かべて言った、
「では御守りだと思って下さい。其れは首飾りでも何でもありません。唯の貴方を御守りするものです。……受け取って下さい。」
余りの押しの強さにオルヴァスは諦めて頷いた。其れに此の様な所で騎士の分際が、女性に恥を搔かせては成るまいとも思った。
「分かりました。大切に貰って置く事にします。……有難う。」
オルヴァスの言葉にアズリータの頬は紅潮する。そんな機微に彼は気づく筈も無いのだが、アズリータは終始、彼を真っ直ぐに見られずにいた。
「…御武運を御祈りして居ります。」
***
宿舎に戻るとメルヴァントは既に帰って来ており、待ちくたびれたのか寝台で静かな寝息を立てている。彼を待って外に出ていた事が何だか申し訳なくなる。
(メルヴァント…済まない。)
せめてもの罪滅ぼしにと彼を起こさない様、就寝の装束に着替える。
「……オルヴァス?」
メルヴァントの微かな声がした。
「あっ、済まない。起こして仕舞ったか?」
「いいや。…私の帰りを待ってくれて居たのだろう?有難う。」
やおら起き上ってメルヴァントは話す。今日の昼以来の彼の声に、明日への緊張が解けていく様だった。
「アジィールさんに振り回されてしまったよ。…少し飲み過ぎたかもしれない。オルヴァスは何処に行っていた?」
今一番触れて欲しくない問いであった。
メルヴァントはアズリータを想い慕っている。そんな彼に貴族の出自でも何でもない自分が、今宵特別な夜に彼女に会った事を話したくはなかった。
彼を裏切った様なそんな気持ちが込み上げ、胸が疼く様であった。
「……アズリータ嬢の所か。」
妙な沈黙に頭の良いメルヴァントは悟った。友の気遣いにも痛み入る。彼は彼で無意識に気を遣わせている事が何となく申し訳なかった。
「私に気を遣ってくれたのだな、有難う。でも私と君の仲じゃないか、気遣い等しないでくれ。」
「…済まない。……私はメルヴァントの言う通り、アズリータさんに会った。」
隠している事が耐えられず、オルヴァスは事の顛末をメルヴァントに打ち明けた。
「君の気持ちを知っているからこそ、私は辛かった。秘密にして居られなかった。…悪い、メルヴァント。」
「ううん。気にしていないから顔を上げてくれ、オルヴァス。…其れに私はもう良いんだよ。」
メルヴァントは静かに笑って言った。其の表情は暗がりで良く見えないが、何か吹っ切れた様な透き通った顔だった。
「アズリータ嬢は君に思いを寄せているのだよ。だから、君に首飾りを託した。」
「…そんな事は無い。あの人が私に思いを寄せる等。」
女性の細やかな感情の変化に疎いオルヴァスにはメルヴァントが言わんとする事が理解出来なかった。
「いいや、私も伊達に貴族の三男坊ではないから分かるよ。オルヴァスに対するアズリータ嬢の御厚意は明らかに私やアジィールさん、シャレールさんに対するものとは違う。其れは確かに、女性が想い人に寄せる様な温かさが有る。」
幼少期から貴族社会を渡り歩いて来た彼には分かる。アズリータがオルヴァスに想いを寄せて居ること位は。だからこそ、一言だけ告げて置きたかった。
「聖戦が終わって生きて此処に帰って来られたら、あの方に添い遂げて欲しい。」
友人として一人の男としてオルヴァスに約束して欲しかった。想い人の慕う相手が友人であることは辛い。無論、悔しくない筈が無い。しかし、アズリータの想い人がオルヴァスで良かったと思う。見知らぬ者に華を摘み取られる位ならば、心から通じ合った友人の華に成る方が余程耐えられるのだ。
「……メルヴァントの言ことが事実なら、私はきっと君との約束を果たそう。友の名に誓って。」
オルヴァスはメルヴァントの手を強く握った。
友情は美しいものではあるが、時として残酷である。其れを身以って感じた二人であった。
暫く他愛も無い話をして二人は床に就いた。
「メルヴァント、死んではいけないぞ。」
オルヴァスの一言が胸に染みる。失恋の想いから情けない事を考えていた自分の心情が悟られた様だった。
「……うん。」
***
濃密な夜はラプタスを深みに連れて行く。大乱の足音は直ぐ其処まで迫り来ている。大義とは一体誰に向けられた、何の為のものであろうか。神か人間か、其れとも全く別の、何かの為のものであるかもしれない。
裏切りの神話と抵抗の物語 前編
三章からは「裏切りの神話と抵抗の物語 中編」に続きます。


