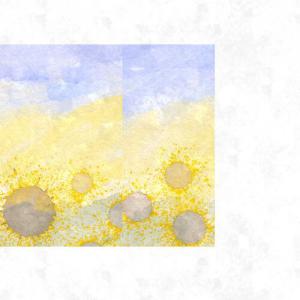砂漠の宮殿
人がまだ「神」だった頃、私と母はとても広いマンションの一室に居た。両足の下にはオオカミのような獣が付いており、移動は全て彼らに任せていた。しかしある日、人は「神」ではなくなり獣たちも失ってしまった。私と母はマンションを探索し台所のような場所に行き着く。そこには裏口があり外階段へと続いている。その階段の下からゆっくりと人が上がって来ている。しかしその人は「まともな人」ではないことが分かる。私は母に自室に戻るように言い裏口のドアを閉め、閂を掛ける。流し台の下のトビラには包丁がしまってあったので、それを五、六丁取り自室に戻る。しかし途中の廊下で迷子になってしまう。遠くから母の私を呼ぶ声がする。その声のする方に行ってみると、そこはデパートの屋上のような場所だった。そこに私、父、母の三人でいる。周りには人もたくさんいる。ボーリングのレーンのような物があり、私たちはそれで「玉転がし」をして遊んでいるのだ。レーンは三つあるのだが、真ん中にあるのは特別なレーンであり、そこには絶対に玉を置いてはいけない。もし置いたら「なにかおぞましいこと」が起るからだ。それは言葉では説明しがたい。呪術的であり想像を絶する呪いなのだ。母がそのレーンを見ながら「アリが逆立ちをして後ろ足で玉を転がしている」と言っている。レーンの先には砂漠が見える。宮殿のような建物もある。(私たちがいる「こちら」と、砂漠がある「あちら」が分けられた感じがある)真ん中のレーンでは「あちら」から玉が転がって来たり、人が走って来たりしている。もしそれが「失敗」してしまったら、おぞましいことが起ると私は知っている。いつの間にか見知らぬ少女が隣にいる。その少女は生まれつきの盲目で、その目は深海魚のように薄皮に覆われている。閉じられた目には、小さな銅の釘がたくさん刺さっている。母は真ん中のレーンに玉を置いてみたい様子だが、父がそれを厳しく戒める。母はそれでも玉を起きたいようで、だんだんと「悪霊に憑かれた」ような状態になり、正常な判断ができなくなってくる。父が悪霊封じのお守りを母に渡している。私は泣きながら母に玉を置かないでくれと懇願する。「お母さん・・・後生ですから、どうか玉を置かないで下さい!」
砂漠の宮殿