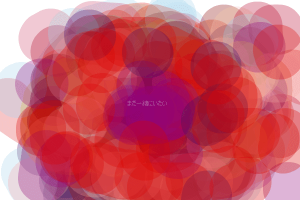ticket -ひとりめの友だち-
低いステージと隙間の空いたフロアであの人はギターをかき鳴らす。それを恍惚の表情で見つめるのはわたし。
あの人はわたしを妹のように大切な存在だと言う。それがどれほど残酷なことか、わたし以外誰も知らない。
あの人と一緒にいるために、わたしは好きでもない「あなた」と夜を重ねていく。
大好きなあの人の横にいるためにわたしは誰と寝ればいい?
空が明るくなっていくのを、ぼんやりと眺めていた。
足は止まっている。もうとっくに電車は動いていて、駅へ向かうサラリーマンがせかせかと歩いて行った。
ついさっき自動販売機で買ったばかりの水はもう半分しか入っていなかった。
二月の朝は、思ったより寒くはない。朝日に目を細めながら、今出てきたばかりの古いマンションを見た。
「ばいばい。」
誰に聞こえるわけでもない言葉は冷たいコンクリートに落ちていった。
携帯のバイブレーションが何度か続けざまに鳴って、目を覚ますとそこは散らかったワンルーム。カーテンのないベランダから薄暗い朝方の空が見えた。
ズキズキと痛む頭をおさえながら体を少し起こした。隣にいるのが誰なのか本当は覚えていた。なんとなく驚いたような素振りをしてみせたのは、本当に望んでいた朝ではないからだろうか。
「起こしてって、言ったのに」
間の抜けた声が布団の中から聞こえてきたが、すぐに寝息に変わる。
肩をゆすると、苦しそうに唸った。起こした体をもう一度沈めたわたしを抱き寄せ、駅までの道を説明してまた寝息を立てた。
細い体を押しのけて、足の踏み場もないベッドの下を見る。そこらじゅうにばら撒かれた衣服から自分のものだけを探してゆっくり身に着けていく。
もう二度とここに来ることのないように、念入りに忘れ物を確認して鞄を背負った。
「泊めてくれてありがと。またあとでね、おやすみ。」
ヒラヒラと手を振りながら小さく返事をした、布団のかたまりをちらりと見て、すぐに玄関に向かった。靴を履いて重いドアを開けた。さっきより少し白くなった空が見えた。
電車に揺られながら思い出していたのは朝のこと。
夜のことはあまり思い出せなかった。頭に浮かぶ情景すべてに白い靄がかかったようで、それはむしろ好都合でもあった。
携帯を見ると、いくつかのメッセージ。どれも返す気にならなかった。
あなたとの夜はつまらなかった。ぽっかり空いた穴は朝になっても埋まっていなかった。
誰かを忘れるために利用したあなたはわたしの心の大穴を広げただけだった。
これほど自分勝手なことはない。それでもわたしはこの生活をやめるつもりはなかった。
あなたに会ったのは、二週間ほど前。気が合うことから、少し仲良くなったのが一週間ほど前。終電を逃したことから、一夜を過ごしたのが、昨日。
もちろん二人に愛はなかった。わたしは大人を試す子どもと同じように、この人と一緒にいることによってわたしの世界がどう変わるのかが知りたかったし、あなたではない大好きなあの人を怒らせてやろうと心のどこかで考えていたのだと思う。
最寄り駅で電車を降りて、とぼとぼと家に向かって歩いて行った。
そこからもほとんど覚えていなくて、次に目覚めたら自分の部屋の布団。時刻はだいたい15時ぐらい。それからわたしは、昨日とほとんど変わらないような服を着て、こってりと化粧をした。
大切なチケットを鞄に入れて、今日も都会に出かけて行く。
愛に綺麗なものなどない。
ticket -ひとりめの友だち-