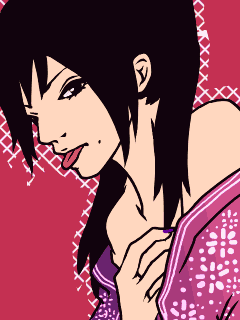不滅恋愛論
永遠の愛という言葉、それはとても綺麗です。
でも、その永遠とは果たして
どこまでを指すのか
いつまでを指すのか
その具体性というものは定かではありません
死ぬまでなのか
死んだあともなのか
人類が滅亡するまでなのか
そうじゃないのか
僕には、 わからないのです。
歯がゆくてたまらないのよ、と彼女は言った。
僕はただ、真っ黒なコーヒーにミルクをたっぷりと注ぎ、
砂糖をここまでやるかという程ためらいもなく入れる細い指先を見つめながら黙っていた。
「だってそう思わない?何この世界?おかしいんじゃないの?」
短気な彼女はいつもそうだ。眉間に皺を寄せている。
そして出来上がった甘ったるそうなミルクコーヒーを口に運ぶ時だけその皺は解除される。
それがちょっと可笑しくて笑ってしまう。
「ちょっと何笑ってるのよ!あたし本気なのよ。」
しかし次には、彼女は怒りと呆れを含んだ声で、
僕の手元にあるチーズケーキに目をやり「ちょっと味見させて。」
と、本日のオススメデザートであるそれを持っていってしまう。
なんというか、感情の移り変わりとか妙に子供っぽい所が愛しいな、なんて思う。
レアチーズケーキにはブルーベリーとラズベリーのソースがかけられている。
それをやはりたっぷりとつけて彼女は口に運ぶ。
あ、ソースがほとんどなくなってしまった。
僕らの周りにいる人たちは「当然」僕らのほうを見てくる。
せっかくデザートを食べて少し機嫌が治ったかなぁ、なんて思っていたのだが。
周りの声に苛立ったように長い髪を掻き分けながら唇を尖らせた。
「ドラマとか映画で、この恋は永遠だとか、騒いでいるじゃない?あたしそれがムカつくのよ。」
おそらく彼女が苛立っているのは毎週水曜21時から放送しているドラマの内容だ。
不治の病と奮闘する少女と、その恋人の悲恋ものである。
タイトルからして彼女の逆鱗に触れるんだろうと思っていたけれど(タイトルは「永遠の僕たち」)
やっぱりそうだった。昨日が放送一回目だったけれど一緒に見ていた彼女はそのドラマを
面白くなさそうに1時間眺めていた。
「ほんっとに不愉快。皆自分の言葉に責任は持たないのかしら。」
「……うーん。」
「あたし達はどうなるの?」
「え?」
「あたし達よ。あたし達は永遠?」
少し間を空けて僕は答える。
「…永遠だと思うよ。」
「ならどうして人々は、あたし達を批判するの!?どうして狂った者を見るような目であたしを見てくるの?あたし達は間違ってはないはずなのよ。」
「ごめんね。」
「どうして謝るの?意味が分からない。」
愛の範囲が分からない。数学より複雑なんだ。
「どうして、あなたは死んじゃったのよ?」
「交通事故じゃん」
ほんとうに、なんで僕はまだこの世界にいるのだろうか。
僕は、今は体を失って骨しか存在しない。臓器も肉も、皮もなにもない。ただの骨。
僕は3ヶ月も前に、トラックにはねられてしまい命を落としたはずだった。
葬儀を終えて、骨も燃やして、骨壷にいれられ、先祖代々の墓に入ったはずだった。
でも、ほの暗い暖かくも寒くもない世界で彼女の泣き声が聞こえて
僕は帰りたい、彼女のもとへ駆けつけてやりたい、そう思った。
そうしたら僕は彼女のもとへ、いた。
ただし、僕は気味の悪い髑髏の姿で、だった。
でもこんな醜い姿でも彼女は一瞬で僕なのだと分かってくれた。
隙間だらけの骨を、彼女は強く抱きしめてくれた。愛してくれる。
僕は骨しかないから涙は出ない。感触もぼやけていて、あまりわからない。
だけど本当に嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんだ。
僕はこの姿を人の目に晒したくなかったが、彼女は違った。
「私たちは普通の恋人同士となんら変わりがないのだから堂々とデートもするべきだ」というのが彼女の主張だ。
今日のデートもそう。一般の人たちと同じように映画のチケットを買い(受付のお姉さんはだいぶ困っていた)
ポップコーンを頬張り(僕はもちろん骨なのでポップコーンは床にそのまま転がっていった)
そして映画を見終わり、ファミレスにやってきたところだった。
はたから見れば変人女が人体骨格標本を連れて街中を歩いているといった感じだ。
それは悪目立ちするのは当たり前すぎるが、彼女はそれに怒っている。
「もし世界に永遠の愛というものが あるんだとしたら
世間は私たちをあんな冷たい目では見ないわよ。」
彼女の言うことは極端すぎるが、僕は生前から彼女のこの負けん気の強さとまっすぐさに惹かれてきた。
喧嘩腰でよく他人と対立してしまうけれど、人一倍他人のことを考え他人のために泣ける優しい人だって分かるからだ。
「永遠の愛とか、そう言うものを簡単に口に出す人は許せない。
そんな事をいうのならあたしみたいに言葉どおり骨のズイまで愛せるのかって聞きたいわ。
その愛する人が骨になろうがゾンビになろうが、あたしなら愛せるもん。」
「はは、骨のズイときたか!」
妙にツボにはいってしまって笑いながら言った僕の言葉に、彼女は何が面白いのよ!
とツッコミそっぽを向いた。
「僕はずっと愛してるよ。たとえそれが人からどう思われようと。」
「あたしだって、ずっと変わらない。」
「他人には分かられなくたっていいよ。僕は君が必要としてくれる、それだけで十分なんだ。」
「悟…。」
「うん。だからチーズケーキ食べたらまた、どこか行こう。」
「じゃあ洋服買いたいから付き合って。」
愛の範囲はとうてい分からない。
だけど例え人々がどう見てこようと僕らの愛はきっと永遠だ。
そう思ってやっていこうと思う。
狂っているとしても僕らにとっては、それだけが全てだから。
不滅恋愛論