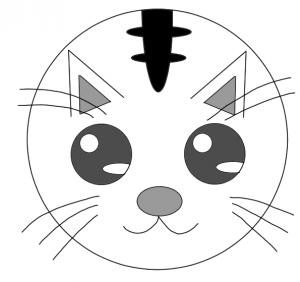sister
1/
男はソコで目を覚ました。
清潔な白いシーツが張られた柔らかなベッドの上。裸電球が一つ吊り下げられた天井には通風孔らしき四角い穴が穿たれている。
部屋の広さは八畳ほどで、床も壁もコンクリートが剥き出し。所々赤錆びた鉄製の扉以外は何もない、殺風景な小部屋。ここでは昼夜の区別もない。
まるで牢獄のような、外界と切り離された閉鎖空間。
男はソコから動けない。
手枷足枷でベッドに固定されている。更には首輪が着けられていて、そこから伸びる鎖によって繋ぎ留められている。古びてはいるが、容易に壊せるものではない。上半身を起こすことくらいはできそうだが、あまり意味はなさそうだ。
ベッドに横たわったまま、ゆっくりと時が過ぎてゆく。その時間の経過すら、ここでは知ることができない。
男は考える。
静かに目を閉じて、今の状態になる前の最後の記憶を呼び起こそうとする。
その時、扉の方から音が聞こえた。カチャリ、と鍵が開けられる音。ギイイ、と鈍い音を立てながら扉がゆっくりと内側へ開け放たれた。
「あら、もう起きちゃったの?」
この異常な状況を感じさせない自然な足取りで、一人の少女が入ってきた。
…
少女は純白のドレスを身に纏い、深い漆黒の長い髪とのコントラストが美しい。
まだあどけなさを残すその顔は上気し、恍惚の表情を浮かべている。幼さと、そして淫靡な雰囲気を醸し出すそのアンバランスな様子は、ひどくみだらだ。
少女は一歩一歩、部屋の中央に置かれたベッドへ近付いてゆく。
男は驚愕の表情を浮かべたまま動かない。なぜなら――
「――夢乃、どうして」
「どうしてって、貴方が悪いのよ、お兄ちゃん?」
夢乃と呼ばれた少女はさもそれが当然だというような口振りで、優雅に髪を揺らす。
しかしその言葉に非難の韻は含まず、むしろ小さな子供を諭すような優しい響きだった。
「でも今となっては感謝をしているほどよ。だって、こうして二人きりになれたのだもの」
そうしてベッドの傍らまで来た夢乃は、自身の兄の頭を優しく撫でる。
慈しむように、いとおしむように。柔らかな笑顔で指先を動かす。
夢乃の指先はそのまま頬を伝い、首筋を通り、胸の上でくるくると踊らせる。
「ふふ、かわいい」
機微な反応を見せる兄の様子を楽しみながら、指は下の方へ移動してゆく。
「おい、夢乃……」
恐れか、または期待からか、言葉はうまく声にならない。この状況下において拒絶の言葉は罪であるかのように、弱々しく霧散してゆく。
ゆっくりと脇腹を撫で、腹筋の形をなぞり、更に下へ。臍のくぼみを跳び越えて下腹部へ到達したところで、夢乃は指を離した。
「続きはまた後でね……もう、そんな目をしないの。椎太はえっちだなぁ」
椎太はもう言葉を忘れてしまったかのように妹である夢乃を見つめる。
その瞳はすでに彼女に囚われていた。
◇
夢乃――今年高校生になったばかりの俺の妹。
兄妹仲は悪くなかったと思う。俺が中学へ上がってからは一緒に遊ぶこともなくなり、お互いの生活を送ってきたからだろう。特に意識することもなく、かといって無視するわけでもなく、普通の家族の距離感を保ってきたと思う。喧嘩だって覚えている限りしたことない。
俺が去年県外の大学へ入学して家を出てからは、たまに連絡をとるくらいになった。
一度、年末に実家へ戻ったとき一緒に出掛けて食事を奢ってあげたら、すごく喜んでくれたのを覚えている。妹は垢抜けたのか、服装とかもお洒落になってかわいらしくなっていた。思春期に一年近く離れているとここまで印象が変わるのか、とその成長の速さに感心してしまったほどだ。
その次に会ったのは春休み。
第一志望の高校に見事合格した妹にお祝いをしようということで、一緒に買い物へ行ったときのことだ。なぜかわざわざこっちへ来て、街案内をしながら一日を過ごした。
しかも夜は俺の下宿先のアパートへ泊まるつもりだという話を聞いて問いつめてみると、次の日の朝早くから好きなアイドルグループの限定イベントが開催されるとのこと。なるほど、それが主目的かと妹の強かさと抜け目のなさに感心したほどだ。
ちなみにお祝いはペンダントを買ってあげた。
その夜は妹に怪しいものがないか部屋を漁られたりパソコンの中身をチェックされたり、ふらりと連絡もなくやってきた彼女と出くわしてしまったりといろいろなことがあったが、楽しいひとときだったと思う。
そう、こんな、おかしなことをする妹ではなかったはずだ。何かの間違いか、冗談なのだろう。
……冗談にしては度が過ぎているが。
何か原因があるはずだと考えを思い巡らせてみたが、それらしい答えに行き着くことはなかった。
(1)
私はなぜか兄のことが好きだった。それが兄妹としての好きではなく、一人の男として好きになってしまったから始末が悪い。だけど、何がきっかけで好きになったのかは思い出すことができないでいる。
これが異常なことであるということは理解しているが、好きになってしまったのだから仕方がない。日々着実に募ってゆく想いは、私の心を侵食していった。
でも誰にも言うことのできない恋慕であるから、密かに想い続けるだけだった。
誰にも気付かせないように、本当の気持ちは胸にしまい込んで。
椎太のことを愛しているけど、その気持ちを口にしてはいけない。
そう考えていた時期も、確かにあったんだ。
苦しくて切なくて、毎日泣いてしまうほど辛い選択だったけど、それが一番いいんだと、それが椎太にとっての一番なんだと、自分に言い聞かせた。
言い聞かせるたび、私の胸に、チクリと痛みが走った。
毎日毎日、チクリチクリ。慣れることのない痛みが毎日繰り返される。
それはなんて苦行だろう。
たとえその痛みが小さな、瑣末なものだったとしても、繰り返されれば無視できないものとなる。
心はカタチがなくて傷を見ることができないから、治すこともできない。
目に見えないものだから、誰にもわからない。誰にも理解されない私の苦しみ。
でもこれは禁忌を犯してしまいそうな私への罰なのだろうと、受け入れることにした。
2/
夢乃が戻ってくると、椎太はゆっくりと顔を向けた。
ジャラリ、と鎖の音が空しく響く。
「夢乃、どうしたのかはわからないが、こんなことはやめよう。冗談にしても度が過ぎるぞ」
「冗談だと、思ってるんだ」
夢乃は椎太の頭を撫でるように後頭部へ手を回し、前屈みになって顔を近づける。
互いの息を感じ取れる距離。相手の瞳には自分の顔が映って見える。この後どうなるのか分かり切っているのに椎太は抵抗できずにいる。
夢乃は静かにまぶたを閉じて、更に顔を近づける。
二人の唇は、ちゅぷ、と瑞々しい音を立てながら交わった。
時が止まってしまったかのように、一瞬が永遠に感じられる。
椎太は夢乃の柔らかい唇を感じながら、夢乃は椎太の熱い吐息を感じながら、二人は融け合う。
重力により夢乃の唾液は椎太の口内へ流れ込み、椎太は自然それを飲み込む。どこか甘い香りが体中に広がった。
夢乃が舌を絡めようとしたところでようやく椎太は正気に戻り、顔を背けて夢乃から離れようとした。
「ん……な、何をするんだ。そんなことは……」
やめろ、と言いかけて椎太は言葉を呑んだ。夢乃の瞳が揺れ動き、とても弱々しく、まるで迷子になった子供のように見えたからだ。しかし、すぐに夢乃は妖しげな表情に戻り、弱々しさは消えてなくなった。
「もっと、深く感じたかったな。でもいいわ。これから時間はたっぷりあるもの」
つう、と指先を椎太の胸に滑らせる。椎太は快感に耐えるように、強くまぶたを閉じた。
その様子を見た夢乃は声もなく笑う。
この空間を支配するのは私なのだと、確信するように。
「椎太……」
夢乃は固く閉じられたまぶたにそっと口付けて、息を荒くしながら肩口に噛み付く。
「――ぐっ」
強く、歯形がくっきりと残るほど歯を立てて、夢乃は口を離した。うっすらと血が滲み、滴る唾液がてらてらと光る。
夢乃の息遣いは更に荒くなってゆく。
「はぁ、はぁ……しいたぁ……」
甘くとろけるような声。夢乃にはもう椎太しか見えていない。いや、焦点の定まらない虚ろな瞳は何も映していない。この空間に酔ってしまった夢乃はただ一つの行為に没頭する。
椎太の浴衣めいた服の前をはだけさせて素肌に舌を這わせる。鎖骨をなぞり、胸に吸い付きながら鳩尾へ。まるで大きなキャンディを目の前にした子供のように、夢乃は椎太の身体を堪能している。
椎太はそんな夢乃を静かに見つめていた。
◇
今の夢乃は、まだ一緒に遊んでいた頃の昔の夢乃に似ている。
元々甘えんぼうだったが、何か嫌なことがあったときはいつも以上に甘えてきた。泣き出しそうな瞳で、けれどそれを感じさせないような明るさで抱きついてきたりしていた。その危うい雰囲気が今も感じられる。
今にも泣き出しそうな、どこか悲しげな笑顔を見せる夢乃に、俺は何と声を掛けて良いのかわからないでいる。
初めはその変わりように戸惑ってしまったけど、そんなことはない。夢乃は昔と何も変わっていない。子供の頃の甘えんぼうな夢乃のままなんだ。
ずっとずっと、寂しかったのかもしれない。でも今の状況は明らかに異常だ。
兄妹のすることではないと解っているのに、強く拒絶することができない。
何が夢乃をここまで追い詰めてしまったのかはわからないが、その責任は俺にあるらしいから。
こういうときは満足するまで大人しくしているか、もしくは話しかけて安心させるしかない。
3/
「な、なあ、夢乃」
椎太は小さなキスマークを残しながらゆっくりと足側へ向かう夢乃に話しかけた。すでに下腹部まで達している夢乃は、全てを舐め取るように臍の窪みへ舌を挿入してから顔を上げた。
「ん、気持ち良くなかった?」
邪気のない瞳が椎太へ向けられる。そんなまっすぐな視線に椎太は言葉を詰まらせて視線を逸らす。
この間も夢乃の右手は椎太の内腿にあり、優しく円を描くように撫で回している。
「いや、そういうことじゃなくて……やめないか? こういうことは」
「――どうして?」
夢乃の表情が強張る。瞳が揺れる。まるで駄々をこねる寸前の子供だ。
この顔が椎太はたまらなく苦手だった。どちらに非があろうとも、一方的にこちらが悪くなってしまう兄の宿命。
「どうして椎太は私を受け入れてくれないの? こんなにも頑張ってるのに……こんなにも、愛しているのに!」
夢乃は叫び、今にも涙が溢れそうな瞳を椎太へ向ける。椎太はまっすぐに感情をぶつけてくる夢乃に対して何も言えず、口を噤んでしまう。
椎太は悪者になる勇気がなかった。ここで妹を拒絶することができなかったのは、彼の最大の失敗だ。
二人は視線を交差させる。夢乃は憤りから、椎太は迷いからお互いに動きを止めた。
静かに時だけが流れる。沈黙だけが支配するこの重苦しい空間では、空気すら凍り付いたように停滞している。
永遠に続くかと思われたこの沈黙もやがて、夢乃の瞳から涙が溢れ出たことによって破られた。
夢乃は頬に伝う涙を拭ってから口を開いた。
「ううん、ごめんなさい。わがままなのは私もわかってる。でも今は、今だけは妹であることを忘れてほしいの」
初めて見せる落ち着いた態度。椎太は毒気を抜かれたように呆然とする。
夢乃はベッドの縁に足を掛け、椎太の下腹部の上に座り込んだ。
「わかってる。コレが男の人の生理現象だってことは。たとえ私を愛していなくても大きくなっちゃうものなんだって。
でも、私は椎太じゃないとダメなの。ねえ、わかるでしょ?
もう……こんなになっちゃってるの」
頬を赤らめながら、夢乃は腰を前後に動かす。ちゅくちゅくといやらしい音が聞こえてくる。
「おい、夢乃――」
「誰にも獲られたくない。私だけのものにして、誰の目にも触れさせたくない。
私だけを見て、私だけを愛してほしい。他の女性は見ないで。
何をしてもいいから。何でもするから――」
夢乃は小さな鍵を取り出し、手枷と足枷を外した。
「――だから、夢乃を選んでください」
そして夢乃は両腕を伸ばした。抱っこをせがむ子供のように、椎太へ精一杯の笑顔を向ける。
そのまなざしはどこまでもまっすぐで、瞳は濁りがなく、透き通るように綺麗で宝石のように美しい。
これが夢乃の本心。
実の兄を愛してしまった一人の女の子の、不安と葛藤が渦巻く、行き過ぎてしまった愛のカタチ。
独占することでしか安心することができなかった、こんな終極的な方法でしか示すことができなかった、儚く悲しい歪んだ愛情。
たとえ間違いであっても、夢乃はこれしか方法がないと信じた。椎太は妹のこの選択を正してやらなければならない。それがどんなに苦しくて、それがどんなに夢乃を傷付けることであっても。
「夢乃」
椎太は上体を起こし、夢乃の背中へ両腕を回した。
微かに夢乃の身体が震える。漏れる吐息は甘く切ない。
夢乃は椎太にしがみつくように胸へ顔を押し付けて、強く目を閉じる。
それに応えるように椎太も両腕に力をこめた。
「夢乃……」
それ以上椎太は何も言わなかった。
夢乃の身体は震えている。むせび泣く夢乃の眼から溢れるのは歓喜の雫。椎太は胸を伝い滴る涙を感じながら、夢乃の背中を優しくさする。
「ありがと……ありがとう、椎太――」
夢乃はそして、椎太を押し倒してすばやす手枷を嵌め直す。椎太は突然のことに何も抵抗することができなかった。
「でもごめんね。私のお兄ちゃんは優しいから、これだけじゃまだ足りないって解るよ。今のだって、私のことを受け入れてくれたんじゃなくて、ただ答えに困っただけなんでしょ? それくらいわかっちゃうんだから。
でも、抱き締めてくれたのは嬉しかったよ。
本当に、このまま死んじゃってもいいくらい幸せな気分だった。
だけど……
私は椎太のことが、もっと欲しいの」
「――夢乃」
椎太は夢乃の本気を理解していなかった。その場しのぎの優しさだけでは変えられない、恋する乙女の心の強さを。
相手のことを深く想うからこそ、心の機微まで読み取れてしまう。口に出さずとも考えは筒抜けとなる。
だから椎太も本気になる必要があった。
たとえ選択が間違っていようとも、考えが全て見抜かれてしまうのなら、その時の本気で応えなければならなかった。
それができなかった心の弱さが、椎太の失敗だった。
今のやり取りも、夢乃の意思を強固なものとするだけであった。こうなっては誰も止められない。
そして夢乃はおもむろにドレスを脱ぎ捨てる。
慎ましやか膨らみの胸。肉付きの少ない体躯。まだ大人になりきれていない少女の身体。
白い肌は淡く朱が差し、汗ばんでしっとりとしている。
「こんな身体じゃ嫌だよね。ごめんね。彼女さんみたいな大きな胸ならもっと喜ばせてあげられたかもしれないのに」
そう言って夢乃は自分の身体を抱く。そして本当に残念そうに、静かに顔を伏せた。
「私の身体じゃ満足できないと思うけど、それでも大丈夫だよね。本当は椎太からされたかったけど、仕方ないか」
夢乃は椎太の下腹部で硬く大きくなっているモノを、両手で優しく包み込む。そのひんやりとした柔らかな感触に椎太は思わず声を上げた。
「う……夢乃、それは」
夢乃は腰を上げて、その先端を自身の秘部へ押し当てる。水っぽい粘膜同士が触れあう音が響く。
緊張からか夢乃の身体は震え、呼吸が荒くなってゆく。
「夢乃、やめろ――」
「は、初めてだけど、頑張るから。私、痛いのも我慢できるからーー」
そして夢乃は少しずつ、力を入れて腰を沈めてゆく。このときの儚げな笑顔は、どこか寂しそうだった。
「ぐ――く、はぁ――」
漏れる嗚咽。まだほとんど進んでいないのに、夢乃の瞳からはぽろぽろと涙がこぼれ落ちる。そして痛みに耐えるように椎太の腕を強く握りしめる。
「い、いたい、痛いよぉ……」
ギチギチと万力のように痛いくらい締め付けられ、椎太は目を閉じて歯を食い縛る。
その痛みは夢乃の悲痛な叫び。今まで溜め込んだ想いの大きさがそれに比例して椎太へ襲いかかる。
「はあ、はあ、はあ……んんっ」
夢乃は呼吸を整え、一気に腰を沈めようとする。二人の結合部にはうっすらと赤色が滲む。
しかし、それでもまだ半分ほどしか進んでいない。
夢乃の顔は苦悶に歪み、涙でぐしゃぐしゃになってゆく。しかしそれ以上に喜びに満ちていた。好きな人と繋がることができた。その幸せを強く感じている。
だから、夢乃は耐えることができる。体が引き裂かれそうな痛みも、その証としての快感に変わってゆく。
夢乃は少しずつ押し進める。
それは止まっているかのように遅いものであったが、やがて最奥へ辿り着き椎太を包み込んだ。
「んん、くう……はあ、はあ、私、頑張ったよ。やっと椎太と繋がれた。
でも、もう少し待ってね。まだ痛くて、動けないから」
夢乃は椎太の胸へ倒れ込み、目を閉じて満足そうに微笑む。
それはまるで、母親に抱かれて安心して眠る子供のような笑みだった。
(2)
私はそして、味気ない毎日を送っていた。
兄は家を出て独り暮らしを始めてしまって、私は愛する人と離れ離れになった。
でもこれは逆にチャンスなのではないか。そう考えた。
だって今は妹としてしか見られていないけど、頑張ってお洒落をしたりすれば私を見る目も変わるのではないか、と。
まずは小さなことから。普段は意識して「お兄ちゃん」とは言わないようにしよう。椎太……椎太だ。ほら、これだけでも少しは意識が変わるじゃない?
好きなタイプの女性は、好きなタレントさんやパソコンの中に隠し持ってたえっちな画像を参考に……しようと思ったけれど、そこには大きな問題があった。
そう、大きなものが必要なのだ。……胸の大きさは努力で手に入るものではない。
それでも私は牛乳を飲んだりマッサージをしたり、いろいろなことをした。その成果は語るまでもない。
とにかく、私は髪型を変えてみたり化粧の仕方を勉強したりファッションの研究をしたり、できるだけ椎太の好みに近付けるように努力した。
そして年末。一年にも満たない急ごしらえの努力だったけれど、椎太は精一杯お洒落をした私を見て「かわいくなったな」と言ってくれた。そこまでは良かった。
なんとその時には彼女ができていたのだ。まさか、高校まで彼女はおろか女友達すらほとんどいなかった人にいきなり彼女ができるなんて、何かの間違いだと思いたかった。
平静を装い写真を見せてもらうと……やっぱり大きな胸だった。
私は途方に暮れた。こんな子供っぽい体付きでは勝ち目がないと。
だから本当に、今度こそは諦めようと、そう思ったんだ。
4/
そして夢乃はゆっくりと体を起こす。
長い黒髪をさらりと揺らし苦しげな笑みを浮かべる夢乃は、一度大きく息を吐いた。
「椎太、おまたせ。そろそろ動いてみるね」
夢乃は椎太の胸に手を置き、少しずつ腰を浮かせる。
粘膜同士が擦れる音。夢乃の嬌声。それらは濃密な甘い空間へ溶け出して拡がり、ベールのように淡く二人を包み込む。
椎太と夢乃は言葉もなく見つめ合う。お互いの存在を感じ、体温を感じ、繋がりを感じ、そして二人はそれぞれの感情を胸に抱く。
椎太は夢乃に対する罪悪感とこの行為に対する背徳感を。
夢乃は椎太に対する愛情とこの行為に対する幸福感を。
「うう、んあ……まだ、痛いよ……」
それでも夢乃は動きを止めない。
「ねえ……椎太は、気持ち、良い?」
夢乃の動きは少しずつ大胆になってゆく。椎太の全てを搾り取るように一心不乱に腰を振る様は、年端もいかない少女らしからぬ淫らな光景を作り出す。
「夢乃……も、もう……」
歯を食い縛り、時折苦しげな声を漏らしながらもなお健気に椎太のために動き続ける夢乃を、どうして否定することができよう。愛する人のための、純粋な好意がそこにある。
椎太はいつの間にか自ら腰を動かしていた。夢乃を下から突き上げるように、音を立てて肌をぶつけ合う。
「ああ、しい、た……あん、はげしい、よぉ」
痛みからかそれとも悦びからか、夢乃はぽろぽろと涙を流す。今日まで実現できなかった、夢に見るしか許されなかった兄への想い。
その想いに、椎太は応えてくれた。
たとえ仮初めのものであろうとも、その事実に夢乃は歓喜する。
やがて――
椎太から迸る奔流が夢乃の中を満たしていった。
◇
そして俺は夢乃の中で果てた。
今は隣で小さな寝息を立てている。その穏やかな顔はさっきまでの夢乃とはまるで別人に思える。
これが悪い夢であれば良かったのに。
しかし二人とも裸で寄り添っている今の姿は、俺に現実をはっきりと意識させる。加えてせがまれた結果とはいえ腕枕までしてしまっている。
まるで本当の恋人のように。そうは成り得ないというのに。
お互いの呼吸を感じ取れる距離で見つめていると、夢乃はぱちりと目を開いた。
「もしかして、ずっと起きてたのか?」
「まあ、ね。まだ何かが入ってるような感じがして、じんじんと痛むの」
「……そうか」
その言葉に対し俺は何と返せばいいのか。今はただ罪悪感だけが胸に込み上げてきて、何も考えられない。
これからどうするのか、どうなってしまうのか。それはわからないけど。
手枷足枷は外してもらえたものの首輪から伸びる鎖でベッドに繋ぎ留められている身としては、逃げることもできないからどうすることもできない。
夢乃はどうするつもりなのか。この長続きするはずのない状況を、どう終わらせるというのだろうか。もちろんこのまま解放されれば公言したりしないし、妹を警察へ突き出したりも絶対にしない。何もなかったかのように日常へ戻れれば、それが一番だ。
でも、と思う。
そんな終わり方はしないだろうということは、なんとなく感じてしまう。
「ねえ椎太、もう一回できる?」
俺の体に指を這わせながら悲しげな笑みを浮かべる夢乃が、これをなかったことにするわけがないと、そう思うんだ。
5/
その日から毎日、何度も何度も、夢乃は椎太を求めた。
初めのうちは抵抗の意を見せていた椎太だったが、回数を重ねるうちにそれもなくなってしまった。きっと諦めてしまったのだろう。どちらにしろ拒否権なんてものは存在しない。
日付どころか昼夜も判別できない小部屋で、二人は身体を重ね合った。
「私、すごく幸せだよ。ねえ、椎太は幸せ?」
「……わからない」
「そう、だよね。ごめんなさい」
「何が『ごめんなさい』なんだ?」
知らず、冷たい声を出してしまった椎太はそんな自分に驚いていた。夢乃は視線を逸らすように天井を仰ぎ見る。
「でも、椎太が悪いんだから。私は諦めようとしたのに、椎太が――」
「俺が何をしたっていうんだ。こんな、夢乃が、こんなことをするのは間違ってる」
椎太には理解できないだろう。どうして夢乃がここまで思い詰めてしまったのか。自覚のない罪が重くのしかかる。
「もう、それ以上は何も言わないで。椎太とは喧嘩したくない。椎太は何も考えなくていいの。ただ私を感じてくれれば、それだけでいいから……」
夢乃の必死の懇願。しかし椎太はそれを認めるわけにはいかない。兄として、いや、男として夢乃にこんなことを続けさせるわけにはいかない。
「夢乃……」
そのためには知らなくてはならない。椎太の罪。夢乃を追いつめてしまった原因を。
「夢乃、教えてくれないか? 俺が夢乃に何をしてしまったのかを」
夢乃は椎太を見る。苦しそうな、泣きそうな、思い詰めた顔で口を開こうとして、静かに首を横に振った。
「椎太がわからないのは当たり前だよ。だからもう気にしないで……」
そこで会話は終わり、夢乃は椎太に背中を向けて横になる。椎太はその寂しげな背中にかける言葉を見つけることができなかった。
…
その日以降、夢乃は極端に言葉が少なくなった。
しかし、作業のように行為は続けられる。
「椎太、ぎゅってして」
「ああ……」
このように求めてくるとき、夢乃が泣いていることに椎太は気がついていた。夢乃は嗚咽を噛み殺していたが、僅かな震えと呼吸の乱れはごまかせない。強く、爪が食い込むほど強くしがみついてくる夢乃に対して、椎太はただ優しく背中をさすった。
椎太の残酷な優しさは夢乃を更に追い詰める。
悦びと、切なさと、悲しさと、寂しさと。
夢乃はわかっていた。椎太を手に入れることができないことを。
だからただ時が過ぎるのを待った。夢乃にはこれしか残されていないのだから。
椎太にとっては終わりの見えない生き地獄。
いつまでも続くと思われた変わらない日々は、唐突に終わりを告げる。
ある日、夢乃は慌てた様子で椎太の下へやってきた。
「ね、ね、椎太。これ見て」
興奮を抑え切れないといった感じで声を弾ませる夢乃。その手には細長い棒のようなものがある。
「これは……」
「うん。私、妊娠したの。もちろん椎太との子だよ」
満面の笑みを浮かべる夢乃であるが、椎太の表情は逆に冷めてゆく。それを見た夢乃は辛そうに顔を曇らせた。
「やっぱり嬉しくない?」
「嬉しいとかそういうことじゃなくて、これからどうするつもりなんだ」
椎太は問う。出産、育児について、父親の問題と金銭面の問題。現実には更に難しい問題がたくさんある。夢乃の表情はどんどん沈んでゆく。
「でも、椎太がいるから」
「俺達は兄妹だぞ。結婚することもできないし。なにより父さん母さんに何て説明すればいいんだ」
「それは……」
夢乃は俯き、強く握り締めた両手を震わせる。そんなことは夢乃にもわかりきっていたことだ。椎太に言われるまでもなく、兄妹であることを悩み続けてきたのは夢乃自身なのだから。
その事実を突き付けられた夢乃は溢れ出す想いが止まらなかった。
椎太を愛する気持ち。誰よりも強く、誰よりも長く想い続けた。けれど報われることは決してない。
誰にも気付かせることなく、胸にしまい込んで、密かに想い続けるだけに留めなければならなかった。
カタチにしてはならなかった。
夢乃に後悔があるとすればそれは、椎太を無理矢理巻き込んでしまったこと。
「ねえ、椎太」
だから夢乃は椎太に最後の問い掛けをする。
「もしも私が妹じゃなかったら、恋人になってくれた?」
でも夢乃は椎太が何と答えるか、初めからわかっている。
「それはわからないな。今まで妹としてしか見てなかったから」
「うん。そうだよね」
夢乃がいかに頑張ったところで、兄妹の壁は高く飛び越えることはできない。
それでも夢乃はこの幸せを終わらせたくなかった。
「夢乃、もうやめよう。今ならまだ間に合う」
「間に合うって何が? 私は嫌なの! このままが一番なの!」
声を震わせて夢乃は叫ぶ。椎太の想いを理解しているからこそ、その先を聞きたくなかった。
「そんなことをしても、何にもならない……!」
椎太のその言葉はどうしようもなく決定的だった。夢乃の身体から力が抜けてゆく。表情が冷めてゆく。
「それくらい、私だってわかってるよ。だから――」
震える右手でナイフを手にする夢乃。それは少し前、林檎を切るために使った小振りな果物ナイフだ。
「お、おい、夢乃」
刃先を向けられて身を引く椎太。しかしそれは自分に向けられたものではないと直感で理解する。
「これをずっと続けるのも無理なんだってこともわかってる。でも、だけど、今更元の生活には戻れないの!」
夢乃の悲痛な叫び。
そう、初めからハッピーエンドはあり得なかった。ひどく悲しい結末しか迎えられない、歪んだラブストーリー。
「だから、椎太にだけは覚えていてほしいな。私のことと、短い間だったけど二人で愛し合ったことを」
最後まで片想いだったけどね、と夢乃は舌を出しながら力なく笑う。
「夢乃、やめろ……」
そのまま夢乃は数歩下がり、自身の首元にナイフを押し当てる。手を伸ばしても届かない椎太は、それを見ていることしかできない。
「本当に私は、椎太のことがずっと好きだったんだよ。もういつからだったのかわからないくらい昔から、椎太のことだけを想ってたんだよ」
ナイフを持つ手はずっと震えている。夢乃の首から一筋、赤い血が細く流れた。
「妹じゃなければよかったのに。赤の他人だったら、もしかしたら」
「夢乃、やめてくれ。それだけは絶対に間違ってる」
椎太の言葉はすでに夢乃には聞こえていない。
夢乃は最期に、笑顔で椎太を見た。椎太の悲痛な表情が夢乃の瞳に映る。
「椎太の赤ちゃん、産みたかったな」
夢乃は片手でお腹をさすりながら静かに呟いた。そしてすぐに両手でナイフを握り直す。
「ありがとう。でもごめんなさい。私はこうするしかないから……」
「――やめろおおお!」
椎太の心からの叫びも届かず、夢乃は泣きそうな笑顔のまま、首元に当てたナイフを一気に引いた。
(3)
椎太との初めてのデートは、私が無事高校受験を終え、志望校の合格が決まった後のことだった。
合格のお祝いをしてくれるということで、私は椎太のところへ遊びに行ってプレゼントを買ってもらうことにした。
狙いはもちろん、椎太の部屋へ行って二人きりになること。男女が一晩同じ屋根の下で過ごせばハプニングの一つや二つは起きてしまうのではないかという淡い期待を抱きつつ、完全に諦める前に少しは良い思いをしておきたいなぁ、なんて下心を持ったまま当日を迎えることとなった。
前日はなかなか寝つけなくてうっかり電車に乗り遅れそうになったけど、予定通り約束の十五分前に待ち合わせ場所である駅前の広場へ到着。だっていうのに椎太はすでに来ていた。どうやら三十分前に着いたらしい。
そんなせっかちな椎太をからかいながら、初めてのデートは始まった。
うららかな春の日差しは今の私の気持ちを表しているようで自然足取りは軽くなる。
私は椎太にしがみつくように腕を組んで歩き出す。兄妹でもこれくらいは許されるだろう。
さあ、どこへ行こうか。
まだ買ってもらいたいものを考えていない私は、椎太を引きずり回すように色々なところを巡った。デパート内の目についた店に入っては商品を見て回り、一通り見たら次の店へ移動する。プレゼントを選ぶよりも椎太とのデートを楽しんでいた私は、それだけで幸せだった。
二つのデパートを征服する頃にはちょうどお昼時となり、食事にしようと右往左往して最終的にファストフードに落ち着いた。
注文した商品を受け取り席につくとようやく一息をつくことができた。
「ふう、午前だけでけっこうたくさん歩いたね」
「そうだな。夢乃にこんなに振り回されるとは思っていなかったよ」
冗談めかした口調で笑いながら文句を言う椎太。嫌な顔一つせず付き合ってくれただけでも私はすごく嬉しい。
「ごめんね。なかなか決められなくて」
「いや、大丈夫だ。こんなに楽しそうな夢乃を見たのは初めてだし、俺も一緒に歩いてて楽しいよ」
「……うん。ありがと」
今の言葉は胸がジーンとした。録音して残しておきたいくらいだ。
ハンバーガーを頬張りながら笑顔で答える椎太と目を合わせるのが恥ずかしくなってしまった私は、俯き加減でストローに口を付けてコーラを吸い込む。シュワシュワと炭酸の強い刺激が私の喉を侵してゆく。
「あれ、そういえば炭酸は嫌いなんじゃなかったっけ?」
涙目になりながらコーラを飲む私を見て椎太は心配そうに覗き込んでくる。
「どうしてコーラにしたんだ。ほら、俺のと交換する?」
「……うん。でも、炭酸は苦手なだけで嫌いなわけじゃないんだよ」
こうして私は椎太が飲んでいたレモンティーを手にする。椎太が口を付けたストローごと容器を受け取り、そのままレモンティーを口に含む。
いつもとは違う甘い香りがするような気がした。
…
食事を終えた私達は、その後も様々な店を見て回り、たくさん歩き回った。そろそろ決めなくちゃと思ってもこれがなかなか決まらない。
だって本当に、一緒に歩くだけで満足だったから。椎太からのプレゼントなら何だって嬉しいのに。だけど欲しいものを問われると、これがなかなか難しい。高いモノでは引かれてしまうし、安いモノでは遠慮したようで失礼になってしまう。
そんな私が最終的に選んだのは、星と月を象ったシルバーネックレスだった。そこまで高くもなく安くもなく、普段身に付けることができて形の残るモノ。思い出としては最高のプレゼントではないか。
そうしてようやく椎太に合格祝いを買ってもらった時には日が沈み始めていた。
世界が朱色から夜の闇へ移り変わってゆく。椎太は自然と私の手を握り、二人で椎太のアパートを目指した。こういう当たり前の優しさが心に染みる。
賑やかできらびやかな繁華街から閑静な住宅街へ。家々から漏れ出す明かりと点在する街灯だけが道を照らす今日は新月でいつもより薄暗い。だけどその分頭上には星空が広がっている。
「ね、星が綺麗だよ」
「おお、ホントだな。星座とかわからないから意識したことないけど、こうして見ると綺麗だな」
二人で星を見上げながら道を歩く。それは本当の恋人のようで。
「……お兄ちゃん」
「ん、どうした?」
立ち止まり、見つめ合う。繋いだ手に力を込めると、それに合わせてきゅっと握り返してきた。
たぶんここで恋人同士ならお互いの顔の距離が縮まってゆくのだろうけど、椎太は疑問を浮かべた顔でこちらを見ているだけだ。当たり前か。
私は軽く首を横に振って答える。
「今日はありがとね。楽しかったよ」
「こちらこそ。夢乃が楽しめたのなら良かった」
「これも、ありがと。ずっと大切にするね」
ネックレスの飾りを指先で弄びながら椎太へ感謝の気持ちを伝える。けれど、私がどれほどの想いでこの言葉を口にしたのかは、椎太にはわからないだろう。
二人で星空の下歩いてゆく。それは寂しいようで、だけどとても温かい時間だった。
…
夜は椎太の手料理を振舞ってもらうことにした。
玄関から途中に浴室の扉と台所がある短い廊下を抜けると、広さ六畳の居間へ辿り着く。部屋の真ん中に置かれた丸テーブルの前に座り、ぼんやりと台所で作業をしている椎太を眺める。
テレビに映っているバラエティ番組の音声は聞き流して、包丁がまな板を叩く音や鍋に張られた水が沸く音を聞いていた。少し本棚とかパソコンを見てみたけど、特に面白い発見はなかった。
小一時間ばかり経って、椎太は出来上がった料理を私の前へ置いた。
「はい、冷めないうちにどうぞ」
カルボナーラスパゲッティとコンソメスープ。途中で寄ったコンビニで買った牛乳とベーコンはこれを作るためだったのか。
椎太は自分の皿も運んできて、私の向かいに腰を下ろした。
「いただきます」
カルボナーラを小さく一口分フォークに巻きつけて口へ運ぶ。滑らかなクリームソースに濃厚なチーズの香り、そしてぴりりとブラックペッパーの刺激が口の中でハーモニーを奏でる。と、評論家っぽく語るとおいしそうに伝わるだろうか。
「どうだ?」
「うん、おいしいよ。お兄ちゃん」
私がそう答えると椎太も笑顔で食べ始めた。クリーム系の料理が好きなことを覚えていてくれたことも、急な手料理のお願いにも応えてくれたことも、とても嬉しい。
そのまま無言で食べ進める。穏やかな空気、緩やかに流れる時間。このまま時が止まってくれれば、私は幸せなままでいられるのに。
だから私は今日のことは忘れない。決して色褪せたりしないよう強く心に刻み込む。
私の最初で最後の恋の相手が、椎太で本当に良かった。
ありがとう、椎太。
「ん、何か言ったか?」
「ううん、何でもない」
コンビニて買ってもらったプリンを食べながら、私は最後の誓いをする。
これで私の恋愛物語は終わりだ。これからはちゃんと妹として生きていくよ、お兄ちゃん。
そうして自己の中に埋没していた私の意識は、突然のチャイムの音によって現実に引き戻された。
「あれ、こんな時間に……まさかアイツか?」
ちょっと待ってろ、と椎太は玄関へ向かっていった。扉を開けると賑やかな笑い声とともに見知った人物が入ってきた。その人物は椎太の横を擦り抜けて居間までやってくると、私を見るなり大声を上げた。
「あー! こんなかわいい子を部屋に連れ込んで、ナニをしようとしてたのかなー?」
「ちょ、大声で人聞きの悪いことを言うな。ほら、写真で見せたことがあるだろ。妹の夢乃だよ」
私に片手を挙げて笑顔で「よろしくー」なんて軽い挨拶をするその女の人は、一度だけ写真で見たことのある、椎太の彼女の……そういえば名前は聞いていない。
「わかってますよー。でもその慌てよう、椎太から滲み出て隠し切れない下心が疑わしいですなー」
「頼むから妹の前でそのテンションはやめてくれ……お前、飲んできただろ」
「わかる? いやー、椎太も大好物なコレが実家から届いちゃったからさー」
その人は椎太に紙袋を手渡してさっきまで椎太が座っていた座布団の上に腰を下ろした。椎太は受け取った紙袋の中身を見て喜びの声を上げている。私は黙って二人のやり取りを聞いている。
「さてと、はじめましてだねー、夢乃ちゃん。あたしは椎太くんの彼女を勤めさせていただいている、籾渡景子です」
そして「よろしくねー」と右手を差し出してきた。
「あの、えと……よろしくお願いします」
急な展開に付いていくことができず困惑したままの私は、勢いに押されるがまま右手を差し出して景子さんと握手をする。にぎにぎと感触を確かめるような握手に私は苦笑いをするしかない。
「よし、若い養分補給完了っと。いやー、若いっていいねー。柔らかいしキメ細かいし、なにより触っていて気持ち良い」
「なに年寄りくさいこと言ってんだ。まだ二十歳にもなってないのに」
ようやく、椎太はグラスを二つ持って戻ってきた。景子さんに場所を奪われた椎太は私の横に腰を下ろす。それがちょっぴり嬉しかった。
「あれあれー、未成年なのにお酒を飲もうとしてる不届き者がいるぞー? ま、あたしもだけどねー」
「夢乃、コイツは悪い見本だ。こうなるとは思わないが、決してマネをするなよ」
「ひどいー。仮にも彼女に対してその言い方はひどいよー」
およよ、と泣きマネをしながら目の前に放置されたプリンを食べる。それは椎太の食べかけだ。
「ま、夢乃には悪いが、俺はこれを楽しませてもらうぞ」
椎太は紙袋から大きな瓶を取り出しテーブルの上に置く。瓶の中は透明の液体が満たされていて、ラベルが貼られていないからその液体が何なのかはわからない。おそらくお酒なのだろう。
「お兄ちゃん、それは何?」
「焼酎だよ。景子の実家が酒蔵を持ってて、たまに送ってくるんだよ」
椎太はとても楽しそうに、二つのグラスに液体を注いでゆく。お酒はあまり詳しくないけど、両親が飲んでいたからそれがビールよりもずっと強いお酒だということはわかる。
なにか、嫌な予感がした。
「今回のは前のよりクセが強いよー。でもまったりと楽しみたいならこっちの方がいいかもだねー」
テーブルの上にはジャーキーやチーズといったおつまみが並べられてゆく。
二人はグラスをかち合わせ、私を差し置いて飲み始めてしまった。
…
二人は良く喋る。酒の講評から始まり、大学での不平不満を口にして、日常の愚痴になったかと思えば政治の話になり、更に国際問題の話へ広がったところで急に将来への不安を語り出す。
繋がっているようで一貫性のない、だけど途切れることなく楽しそうに会話を続ける二人を羨ましく思う。
やっぱり手持ちぶさたになってしまった私は、本棚の奥から見つけたアニメのDVDを手に取る。
「お兄ちゃん、このアニメ観てもいい?」
「おう、勝手に観てもいい――ぞああ! それはダメだ!」
私が手にしたパッケージを見た瞬間、椎太は血相を変えてそれを私から取り上げた。
やっぱり、奥へ隠すように仕舞ってあったのはそれがいかがわしいモノだったからなのか。パッケージだけはまともで、中身は何が入っていたのだろうか。
「まーだそれ持ってたのー? でも夢乃ちゃんに中身を知られたら嫌われちゃうかもねー」
「捨てるのを忘れてただけだ。それに、元々俺のじゃなくて貰い物だからな」
からからと笑う景子さんに目を泳がせる椎太。
それでも椎太は平静を装い、仕切り直すように別の棚を指差して私に言う。
「あっちの棚のやつなら好きに観てもいいぞ」
「じゃあパソコンいじってもいい?」
「……夢乃、他に何を見つけた?」
「別に、胸が大きな女の人が体操服で出てくる動画とかは知らないけどねっ」
私のその言葉で、椎太は項垂れて動きを停止した。少しやり過ぎちゃったかな。
景子さんは今の一連のやり取りを見て、膝を叩いて大笑いしている。
「いやー、夢乃ちゃんにしてやられたね、椎太」
「うう……どうして」
どうして椎太に対してこんなに攻撃的になったのかというと、何というか、寂しいというか悔しいというか、やっぱり嫉妬しているのだと思う。椎太と楽しそうに会話を弾ませる景子さんに対して。
未練がましい私はまだまだ子供だ。
ようやく顔を上げた椎太は、そっぽ向いている私の肩に手を置いた。
「夢乃、ごめん。でも俺だって男だからな、その、わかるだろ?」
「もう知らない」
本当は怒っていないし何とも思っていないけど、わざと冷たい口調で言ってやる。こうなったら意地だ。
そして訪れる静寂。数十秒の沈黙を破ったのは景子さんだった。
「はい、夫婦喧嘩はそこまでにして。夢乃ちゃんも一緒に飲んじゃいなよー」
「お前またややこしくなるようなことを――」
私には挑発にしか聞こえないその言葉。少しイラついていた私は言われた通り椎太の飲みかけのグラスを手に取り、半分ほど残っていた焼酎を一気に飲み干した。
口中に広がるアルコールの香り、喉を焼くような刺激、そして、胸が一気に熱くなってそれは全身に広がってゆく。
椎太が私から空のグラスを取り上げたがもう遅い。
目の前が揺れて、ぼんやりと霞んでゆく。
私の記憶はそこで途絶えてしまった。
…
記憶は途絶えたけれど、眠ってしまったわけではない。覚えてはいないが、その後は三人でわいわいと飲んでいたらしい。もっとも、途中から私に出されていたのは水道水だったようだが。
私がようやく正気に戻ったのは日付が変わる頃、椎太は酔い潰れて寝てしまって景子さんがそろそろ帰ろうと立ち上がったときだった。
玄関で靴を履きながら、景子さんは私に話しかけてきた。
「今日は突然お邪魔しちゃってごめんね。まさか夢乃ちゃんが来てるとは思わなかったからさー。椎太は昼間は用事があるようなことは言ってたけど、詳しいことは何も教えてくれなかったし」
「いえ、そんな……」
「あとは夢乃ちゃんの自由にできるよ。椎太はああなったら朝までぐっすりだから」
私の肩に手を置いてウィンクしてくる景子さんの言葉を、どう受け取ればいいのか。深い意味はないのかもしれないが、それを考えると負けそうなのでやめておいた。
「じゃ、椎太によろしくねー。バーイ」
そして片手をひらひらしながら外へ出ていった。来たときと同じように颯爽と、後腐れなく帰ってゆく。
そんな在り方が私には羨ましかった。
居間へ戻ってきた私は散らかったテーブルと床に寝ている椎太を見る。
座布団を枕にして、横を向いて寝ている。その伸ばされた腕を見て、私はあることを考え付いてしまった。
今しかチャンスはない。それに景子さんも言っていたではないか。椎太は朝までぐっすりであると。
「……失礼します」
私は小さく呟いて椎太の横に腰を下ろす。そして、ゆっくりと、椎太の腕を枕にして横になった。もちろん椎太の方を向いて。
とても顔が近い。鼻がぶつかりそうだし、息が当たる。
当然酒臭かったけど、それが椎太のものだと思うと全く気にならなかった。
そこで突然椎太はもう片方の腕を私の背中に回し、抱き寄せられた私はそのまま抵抗する間もなくキスをされてしまった。
「んんっ――」
唇を食べられてしまいそうな、ねっとりと熱い口付け。侵入してくる舌も拒むことなく私は椎太を受け入れる。
身体を弄る手が下の方へスライドしてゆく。優しくいやらしい手つきで私のまだ誰にも触れられたことのないところを撫で回す。
どのくらいの間そうしていただろう。たぶん一分にも満たない出来事だったと思う。
「んむ、はあ、景子……」
ようやく口を離した椎太が呟いたのは私の名前ではなかった。
私は思わず椎太の胸を押して、ころがるようにして椎太から離れた。
起きる気配がない椎太。私は静かに立ち上がりその場から逃げるように洗面所へ駆け込んだ。
鏡に映る私は、ぼろぼろと涙を流していた。
口の周りは椎太の唾液でべとべと。下着はお漏らしをしたように濡れていて、部屋着のズボンにまで染みている。
「どうして……わたしは……」
どうして私は椎太の妹なんだろう。妹でなければ、一緒になれたかもしれないのに。
「しい、た……」
椎太のことが大好き。愛してる。
だってこんなにも身体が反応しているのだから。
「もう、諦められないよ……忘れられないよ……」
この快感を知ってしまった私は、もう後戻りなんてできそうになかった。
…
朝になり、何事もなかったかのように一日が始まった。
「夢乃は何かのイベントへ行くんだっけ?」
「うん。夕方まであるから、終わったらそのまま帰るよ。だから、またね」
「そうか、わかった。酒を飲んだことは誰にも言うなよ?」
そして私は椎太と別れて外へ出る。駅まで送ろうとしてくれたけどそれは断った。
きっと離れがたくなってしまうから。本当は用事なんて何もないのだから。
私は適当に夕方まで時間を潰して椎太が住む街を離れた。
次に椎太と会うときはもう絶対に離れない。そう誓って。
sister