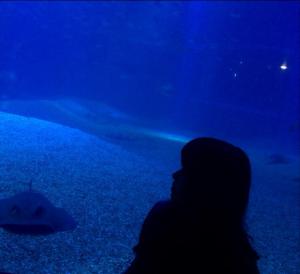空洞の価値
生は不平等だ
「由美が、死んじゃったんだって、」
電話越しの京子の声は震えていて、何を言っているのか理解するのに、私の脳は数秒を要した。死んだの?由美って、中学の?聞き返すと、そう、と京子は答えた。
「なんかね、病気だったんだって。どうしよう、全然、知らなかった。死んじゃったんだって。ねえ、」
明らかに動揺している京子の声は、私の意識を掠めるように、段々と遠くへ聞こえていく。どうやら白血病だったらしいこと、葬儀の日程、それを聞き終えると、私は京子といくつか会話を交わして、電話を切った。次に連絡を回す人は私にはいない。由美とは関わりが殆どなかったからだ。私への連絡は、末端だろう。「死んじゃうなんて、思わなかった」京子は電話越しに泣きながら言った。釣られて私も涙を流した。けれど、京子とは違う気持ちからだった。生は不平等だ。そして、死は誰にでも平等だ。明日私が死ぬことも、明後日京子が死ぬことにも何ら不思議は無い。そして、今朝、由美が死んだことにも。
由美は中学のクラスメイトだった。バスケ部に所属していた彼女は、活発で溌剌としていて、美術部の私とは関わりが薄い。その点、運動部だったという点では、京子の方が親しかったのだろう。由美の顔を思い出すにも、何パターンかの表情しか浮かばない私とは違って、彼女のことを想う誰かは酷く悲しんでいる筈だった。喪服、出しておかなきゃ。冷えた頭の隅の方で、数珠と真珠のピアスの収納場所を思い出す。
葬儀はちょっとした同窓会だった。私のような、殆ど彼女との関わりの無い中学の同級生から、見たことのない高校、大学の関係者、それから職場の人らしき誰かまで。沈鬱な顔を浮かべ、黒い服を着て集まっていた。遺影の中の彼女は、私が知る由美ではなかった。それはそうだ、私が最後に会ったのは中学の卒業式で、それから10年が経過している。死期を知っていて、撮影したのだろう、ウィッグを被って笑っている姿が痛々しかった。お焼香を終え、最後のお別れ、ということで、眠っている彼女の顔を見る列が出来ていた。私はそれに並ばなかった。死に顔を拝んでも良い程、親しくなかったと思ったからだ。
「並ばないの?」
「うん。」
浩太に話しかけられて、少し驚いた。
「浩太は?」
「ん、俺は…。お前、仲良かったの?由美と。」
「ううん。親しかった、とは言えないと思う。私が顔、見ていいとは思えなくて。」
「そっか。まあ、気が向いたら見てやってよ。あいつ、賑やかなの好きだから。」
あいつ、と由美のことを呼んだ浩太の表情を見て、私は幾らか想像を巡らせた。ああ、そっか。目を細めて、浩太を見た。由美の顔は見ないまま、葬儀場の近くで中学の同級生と他愛もない会話をしていると、眠っている由美の柩の前で、立ち尽くしている浩太の姿が見えた。ねえ、浩太って。小さな声で浩太と親しい鈴木に問うと、ああ、そうだよ。と返ってきた。
「大学の頃からかな、付き合い始めて、由美が入院してからはわかんねえけど。かなり本気だったんだと思う。」
そうなんだ。小さく返して、立ち尽くす浩太へと視線を戻した。王子様のキスで、目覚めそうだった。でも由美は目覚めないのだろう。ドライアイスで腐食を止めている痩せ細った屍体は、お姫様では無いのだ。
その後、火葬場へは親族だけということになり、てっきり私は浩太も行くのだと思っていたのだが、浩太は由美の家族へ会釈をすると、こちらの輪へ入ってきた。お清めに行こう、ということになり、ぱらぱら散らばって食事へ向かった。聞いて良いのか分からなかったが、私は恐る恐る、浩太も行くの?と聞いた。俺は…、と、浩太は言い淀んだ。
「ごめん、私、頭痛くなっちゃって。タクシー拾って帰るね」
京子にそう言うと、そっか、そうだよね、と、悲しそうな顔をした。じゃあ、また。みんなに軽く手を振って、私は別の方向へ歩き出した。頭が痛いというのは本当だった。鞄からロキソニンを取り出して、自販機で水を買う。生温い雨が降ってきた。雨だなあ、と思う。雨だ。雨だ。ミネラルウォーターを飲み込みながら、水滴が私の髪を、喪服を濡らしてゆく。そして、雨が、私の右半身だけ止んだ。
「風邪、ひく。」
「ひいてもいいよ」
「変わんねえな、そーゆーとこ。」
黒い折りたたみ傘を半分こちらに差し出して、浩太は右半身を濡らして立っていた。皆と行かなかったの。ああ、気分じゃない。そうなんだ。会話を交わして、由美は今頃焼かれているのだろうか、と考えた。
私と浩太は付き合っていた。高校の時に、1年だけ。中学の卒業式の日に告白されたことを覚えている。教室の隅で絵ばかり書いていた私と、サッカー部で部長をしていた浩太は、釣り合っていたとは思えない。だからこそ快活な由美に、「本気」になったのだろう。私は中学の頃、よく男子から告白をされた。容姿と、大人しそうな雰囲気が、何か女の子らしさを感じさせて、男子の間では人気だったらしい。中学の頃に告白してきた男子のことはことごとく断ってしまったが、浩太と付き合い始めてから、それを聞いた。
「どうして俺はオッケーだったの」
「自分の顔、鏡で見てみれば?」
笑って答えたのを覚えている。浩太は、誰が見ても素晴らしいルックスをしていた。そして、彼はそれを自覚していた。
「どうして私だったの」
「仲間うちで話しててさ、お前に振られたヤツの数とか。お前と付き合ったら、気分が良いだろうと思った」
「じゃあ私が好きなわけじゃないんだね」
「好きだよ。鏡見てくれば?」
容姿の上で、私たちはお似合いだった。言ってみたら、アクセサリー同士だった。隣を連れて歩くのに気分が良い相手。そこに愛があったかは分からない。ただ、私が初めてキスをした相手も、セックスをした相手も浩太だし、閉じられたまぶたのふちから生えた、睫毛の美しさが焼き付いている。
「タクシー拾おうか」
「そうだね。」
私達は相合傘で、大通りまで出ると、通りかかったタクシーをとめた。駅まで、と告げると、こちらが喪服姿なのを見てか、運転手は「雨ですなぁ」と呟いた。「悲しみの雨、ですねえ」そう言った運転手の声に、私も浩太も答えなかった。私は、由美が死んでも悲しく無かった。でも私の隣には、きっと発狂してしまいそうなほど、悲しんでいる男がいる。
駅まではワンメーターだった。私が出すよ。そう言うと、浩太は俺が出すと言い張った。そして、私の手を引いて、タクシーを降りた。手を握って、の方が正しいかもしれない。
「まだ頭痛い?」
「薬飲んだから、さっきよりはましだけど。」
「じゃあ、付き合って。」
浩太は私の手を、今度ははっきりと、握った。その手が震えていたのが分かったので、うん、としか言えなかった。
居酒屋を二軒梯子して、私達は終電を逃した。終電を逃す為に、居酒屋に居たという方が正解だろう。電車、もうないや。ああ、俺も。アルコールの匂いのする息を吐き出して、浩太は言った。私は浩太がお酒に強いことを知らなかった。焼酎が好きなことを知らなかった。由美は知っていたのだろう。そして、浩太も、私がお酒に強いことを知らなかった。それでも私は酔ったフリをして、違う、私達は、酔ったフリをして、「泊まっちゃおうか」とどちらかが言った。「うん」と、もう片方が答えた。
駅から近いラブホテルに2人で入ると、浩太は私をいきなり押し倒した。ねえ、床だよ。ベッド行こうよ。私の言葉に答えずに、浩太は私の首筋に噛み付くようなキスをしていた。それから、はっとしたような表情をして、私を持ち上げた。お姫様だっこ、なんて誰が名付けたのだろう。私は今日、柩で眠るお姫様を見ないようにした。私はベッドの上に落とされ、乱暴に服を脱がされ始めた。ねえ、電気。電気、消して。息を荒げながら言ったけれど、彼の耳には聞こえていなかった。私は観念して、目を瞑る。こうなることを望んでいたのかもしれなかった。ああ、もうだめだ。上を全て脱がされた時、予想通りに、浩太の動きが止まった。私は、目を瞑ったまま首を振った。浩太は私の手首に手を重ね、前戯無しに挿入した。痛い、と声を上げたけれど、その後は、私は単に喘いだ。由美は、骨になっただろうか。骨壷に納められて自宅だろうか。まぶたの裏でその光景を浮かべながら、コータ、と呼んだ。良いよ、中で。そう言うと、何の躊躇もなく、浩太は私の中で射精した。
「それ、なに」
「死に損なったの」
「なんで」
「ばかだったから」
私の手首には、大きな傷が数本ある。2年前に自殺未遂をした時に作ったものだった。それまで、人に見える場所、手首には傷を作らないようにしていたのに、もう死ぬのだからと思って、取り寄せた医療用のメスでサクッといった。鎮痛剤を一箱飲んでいたせいか、痛みはさほど感じなかった。処方されていた睡眠導入剤と安定剤と抗うつ剤と、市販の鎮痛剤、なんだか凄い量を飲み込んで、お酒を飲んだら楽しくなったので、サクサク手首を切りつけていった。次第に気分がとても悪くなり、嘔吐物と手首からの血に塗れた状態で家族に見つかった私は、救急車で搬送された。そして、死に損なったのだった。
「ちがう。なんで死のうとしたの」
「死にたいって思ったから」
「…意味わかんね」
「私もわからない」
ねえコータ、今考えてること当ててあげる。そう言って、私は浩太の鼻先をかじった。
「私が死ねばよかったのに、って、思ったでしょ。由美の代わりに」
衝撃と、痛みが走って、頬をぶたれたことを把握した。そして、私の髪を掴んでいる浩太の暴力的な目がこちらを捉えていた。
「私が死ねばよかったのにね。その方がみんな幸せだったね」
「それ以上言ったら、殺すぞ」
「矛盾してること言ってる自覚、ある?」
私はけらけら笑っていた。笑いながら泣いていた。浩太は私を殴った。そういうところが、好きだった。
「由美のことも殴ったの?」
浩太は無言で私の頭を壁にぶつけた。ぐわん、と視界が揺れるのを感じる。浩太はこういう男だった。私はそれを知っていて、よく浩太をわざと怒らせた。
「もっとやって、いいよ。私は壊れないよ。」言いながら、私は首を絞められていた。げほげほと咳き込む。浩太は泣いていた。愛おしかった。
「ほんとは私、浩太のこと好きだった。だから、他の男子のこと、全部断ってた」
中学の頃、京子との帰り道に、浩太の話が出たことがある。京子は、「由美が浩太くんのこと好きなんだって。お似合いだよね。」そう言った。私は、言い表しようの無い感情に包まれて、京子を振り切って1人で早歩きをして帰ってしまった。その程度には、好きだったのだ。
「体育で、バスケの時間にさ。浩太と同じチームになって、私がパスを受けられないから、どうやってもシュートを外すし、ドリブルも出来ないから、私にボールを回さないようにしてたでしょ。それで、先生に怒られてたでしょ。あの時、私すごく優しい人だなと思った。浩太のこと。」
「…あったな、そんなこと」
「大丈夫。俺に任せろ、って。言ってくれてさ。浩太は、ノロマな私にパスを回さない意地悪なヤツ、みたいに言われてたけど。すごく助けられた」
「そのあと、由美に、ノロマ、って言われたんだろ」
「うそ、知ってたんだ?由美から聞いたの?」
「いや、両方から聞いたよ」
なんだ、私も話したことあったんだね。可笑しくなってしまって、くすくす笑った。由美は凄いんだ。俺が殴ったら、殴り返してくる。股間蹴られたこともあった。だから、好きだったの?馬鹿か、そーゆーわけじゃねえよ。自然とお互いの体にくちびるを這わせ合いながら、ゆるく時間が流れていく。雨音が遠くで聞こえていた。
愛するものが死んだ時には、自殺しなけあなりません——ふとそれが浮かんできて、浩太に問うた。
「コータ、由美に会いたい?」
「会えない。」
「殺してあげようか。今なら、追い付けるかもよ」
それでお前はどうすんの?口元だけで笑われて、私も死ぬよ、と言った。何に興奮したのかは分からないが、浩太は私の乳房を荒々しく揉むと、私達は再び結合した。私は律動に任せながら、浩太に首を絞めてと懇願した。その通りに絞められる首、薄らいで白む意識、由美のタマシイがあるのならば、由美が幽霊になったのならば、今のうちに私の身体を乗っ取るといい。生きたいなら、私の体を使ってくれたらいい。どうして生はこんなにも不平等で、誰かに分け与えることが出来ないのだろう。生きることを放棄した私は、まだ快楽を感じているのに、生きることを望んだ彼女の体は、もうただの骨片でしかない。浩太が呻いて、また私の中に吐精した。同時に首へかかっていた力は緩んで、私は、私でしかないことに絶望した。
「中に出して大丈夫なの」
「今更?大丈夫だよ」
自殺未遂をした2年前から、私の卵巣は排卵をやめた。命をつくる資格を、カミサマに剥奪されたのかもしれない。生理来ないから。そう告げると、浩太は心配そうな表情をした。嘘でしょ、何心配してんの。笑ったら、彼はうにゃうにゃと何かを言った。
「俺は由美が好きだったよ。ノロマな誰かよりも」
「じゃあどうして、卒業式の日、私に告白したの」
「由美が好きだったけど、お前とヤりたかった」
ああ、最低。そう思って、私は浩太の頭を撫でた。汗の匂いのする髪をくしゃくしゃと撫でた。キスをした。伏せられたまぶたのふちから生える長い睫毛に、やっぱり私は、欲情した。
私と浩太が別れたのは当然の流れだった。別々の高校に進学して、別の世界を見るようになり、たまに会って出掛けたりセックスをしたりするだけの関係を、1年以上維持出来る程、私達は大人ではなかった。愛と欲情の区別もついていなかった。たまに会って、私は暴力をふるわれて、その度に痣をひとりで眺めた。これは浩太の痛みだと思った。弱くてノロマな私しか見られない、浩太の弱みなのだと思った。
「泣いていいと思う」
「…」
「でも、ご飯は食べなきゃだめだよ」
お前に言われると思わなかったよ、苦笑いをされて、私もわらった。
2ヶ月後、私は浩太に電話をしていた。
「生理が、きたの」
「…へえ」
電話越しの浩太は、明らかに反応に困っていた。言葉にしてから気が付いたが、確かにこういう場合、生理が来ない、と告げるのが普通なのだろう。妊娠したかもしれない、あなたの子だ、と。それを考えると、私の発した内容は真逆なのだから、相手が困るのは当然だった。しかし、こちらは、そんなことを考える間もなく、レディースクリニックの扉の外で電話をかけてしまったのだ。先日、出血があった。不正出血だと思った。しかし出血は止まることがなく、無排卵月経かもしれないと思いレディースクリニックを受診した。検査の結果、私の卵巣は排卵をしていた。ごく一般的な、妊娠可能な女性に起こる、月経だった。
「よかった、ね?」
「…よかったのかな、わかんない」
「なんで電話してきたんだよ」
「ごめん、わかんない。」
2年間きていなかった生理がきた、のは、2ヶ月前に浩太としたセックスのせいだと直観したから、浩太に電話をかけてしまった。だけど、それを告げてどうになるのだ。私の頭は回っていなかった。…いや、浩太としたセックスのせい、というよりも。あの時、由美のことを考えて、由美に乗っ取られることを考えながら、したことが大きな原因のように思えた。由美の生きたかったという思いは、私の体に何らかの作用をもたらしたのかもしれない。
「まあ、飯、食えよ。」
「うん、浩太も。」
私は、命を宿しても良いのだろうか。その資格を、再び得ることが出来たのだろうか。
「なに、お前、泣いてんの?」
「…ん、」
「俺の子供欲しかったの?」
ばか、と小さな声で返す。見当違いな言葉に、私は更に涙を流した。生は不平等だ。死は、平等に訪れる。命を宿すことが可能になった私は、いつか生命を産み落とすのだろうか。
「コータ」
会いたい。そう零したのは、私ではなく、由美かもしれない。あの時、由美の思いが私の中へ入ってきてしまったのかもしれない。
「なあ」
「ん」
「好きだったよ、あの時。本当は、好きだった。」
あの時、とはいつだろう。中学の時の事だろうか。誰に向けて言っているのだろうか。
「俺も会いたい。」
もう壊さないから。浩太は、そう言った。違うよ、由美は、浩太が壊したわけじゃない。私は壊れないよ。だから、浩太が壊れる前に、壊してもいいんだよ。そう言ったら、電話越しに、鼻を啜るような音が聞こえた。
空洞の価値