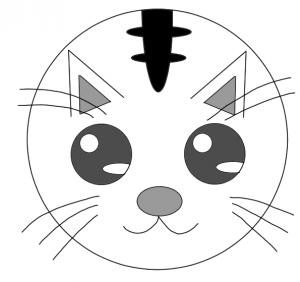思い出のスマイル
三題話
お題
「思わぬ再開」
「○」
「監督」
根倉敦史(ネクラアツシ)はいつものようにパソコンでネットをしていた。
いつも見ているサイトを巡って更新がないかチェックして、その後は適当に匿名掲示板の書き込みを眺めながら時間を潰していた。
/
現在中学生である敦史は、友達から『ヒッキー』と呼ばれている。その友達というのは単にクラスメイトという意で、ほとんど話もしたことがない。それに決して引きこもりではないし、むしろ小学校時代から一度も休んだことがなく皆勤賞だ。
敦史にも本来の意味での友達が全くいないわけではない。ただそれは学校の中だけの付き合いで、外で友達と遊ぶということはほとんどなく、大抵は自宅でパソコンを弄っていた。
根倉という苗字も合わせて、『ヒッキー』という渾名となったのだろう。そんな安直で面白みのない、人を見下した名付けに辟易している。
/
「うわ、こんなのに引っ掛かるヤツはいねぇだろ」
部屋には敦史しかいないから、その言葉は当然誰も聞いていない。
匿名掲示板に立てられた一つのスレッド。そのいかにも怪しげな内容に、敦史は苦笑していた。
「…………」
それはパッと見はアルバイトの募集。
モノを運ぶだけの簡単なお仕事で、報酬は二十万円。その破格な額がいかにも怪しい。
今夜十時、ここからの最寄り駅である、この辺りでは一番大きな総合駅に集合。
現在は午後六時。募集の締切は午後七時まで。
「……ま、まあ、冷やかしだけどな」
敦史はそう呟きながら、一番下に書かれているフリーメールアドレスへ必要事項を明記して送信した。もちろん自分もフリーのメールアドレスを使用して。
…
数分のうちに返信があった。
詳しい集合場所と、メンバーの人数が記されていた。
実際に何を運ぶのかは集合した後で説明されるとのこと。
敦史はいぶかしみながらも、明らかに興味を示していた。
…
両親には適当な言い訳をして外に出て、敦史はアルバイトの集合場所へと向かった。
…
「……あ、あれか?」
午後九時五十分。
指定された場所には既に六人の男女がいた。年齢層はバラバラ。参加人数は七人だから敦史以外のメンバーは揃っているということになる。
「こ、こんばんは」
敦史が声を掛けると、六人は振り返り、各々挨拶を返してきた。
「それじゃあ、行こうか」
金髪で背の高い男がみんなを見渡しながらそう言った。
「あ、あの、貴方がスマイリーさんですか?」
スマイリーというのは今回の主催者……雇用主の名前だ。
当然本名ではなく、ハンドルネームだろう。
「いいや、違う」
その男は敦史の質問に答えながら何かを差し出した。
白の封筒に、一枚の便箋。
封筒にはスマイリーマークが描かれていて、便箋には小さな文字が書かれていた。読んでみると、それは新たな指示書だった。
…
指示された場所へ行くと、そこはもう使われていない三階建てのビルだった。
中へ入り、二階の奥へ行って、ロッカーを開ける。
「な、なんだこれ」
中には大きなボストンバックとビニール袋が六つ。扉の内側にはまたスマイリーマークが描かれている封筒が貼り付けてあった。
敦史が封筒から紙を取り出して広げる。
この荷物をそれぞれ指定された場所へ置いてくること。それについての細かい説明は荷物の中の紙に書いてある。
条件は一人一つの荷物を担当すること。
敦史はビニール袋を一つ取って、さっさとここから出ようとした。
「ちょっと待てよ。こんなのは怪しいだろ。みんなで協力しないか?」
敦史は金髪の男に呼び止められて振り返る。
「怪しいのは初めからだろ。みんな信用できるとは限らないし、俺は指示通り一人でいくぜ」
他の人は黙ってはいたが、敦史の意見を支持したようで、それぞれ荷物を持って外へ出た。
…
七人の男女は、さよならも言わず、ばらばらに散っていった。
…
周りに誰もいなくなってから敦史が袋を開くと、白い靴下が一足と二つ折りの紙が入っていた。
「ふぅん?」
集合場所でもあった総合駅から電車で三駅行ったところの地域掲示板に靴下を貼れ、という意味の分からない指令。
敦史は指示通りの場所へ行き、靴下を取り出して、掲示板にあった画鋲で留めた。よく見ると靴下にはタグが付けらいていて、タナカミカという名前と電話番号が書いてあった。
「……これは」
その名前に見覚えがあったのか、敦史は上を向いた。
「いや、気のせいかな」
紙に書いてあった通り、近くの植込みにスマイリーが描かれている封筒が埋められていて、その中には二十万円が入っていた。
…
次の日の夕方、敦史はテレビであるニュースを耳にした。
隣町の五歳の女の子が昨日の夕方から行方不明になっているというニュースの続報で、バッグに詰められた女の子の遺体と、様々な地区の掲示板で衣類が発見されたという。なんとも不可解な事件。
その女の子の名前は、タナカミカ。
「あ……」
そして女の子の写真を見て敦史は思い出す。中学の授業の一環として訪れた幼稚園で、その子に懐かれていたことを。
◇
何故か俺の側を離れようとしないミカちゃん。笑顔が似合う、とても可愛らしい子だった。
子供は面倒くさいから嫌いだったけれど、こうして笑顔で慕ってくれるのは、嬉しく感じた。
帰るとき、ミカちゃんから一枚のカードをもらった。紙いっぱいに大きなスマイリーマークが描かれていた。感謝の気持ちということらしい。
人から何かをもらうという経験があまりなかったから、とても嬉しかった。
俺はミカちゃんの頭を撫でながら、ばいばい、と言い、学校へ戻った。
その様子を見ていたクラスメイトから「ロリコン」とからかわれたのは嫌な思い出だ……
思い出のスマイル