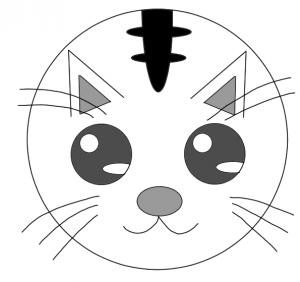切れた糸を、繋ぐ先は
三題話
お題
「野菜」
「アルバム」
「日記」
職場を出る前に妻へメールを送るのが日課だった。
いつもならすぐに労いの言葉と夕食のメニューを送ってくる。だけど、その日に限ってメールは返ってこなかった。職場から自宅までは車で三十分ほど。赤信号で止まる度に携帯電話を確認したが、ついに自宅へ到着するまで妻からのメールを着信することはなかった。
胸騒ぎがした。玄関を前にしてインターホンを鳴らしたが、反応がない。
トイレにでも入っているのだろうか。
そんなことを考えながらカバンから鍵を取り出して扉を開ける。
ただいまぁ、と玄関で大きめの声を出したが家の中は静まり返っていた。
革靴を脱いで上がり框を跨ぎ、居間へと続く廊下を進む。その途中にあるトイレの中には誰もいなかった。
…
居間へ入ると妻が倒れていた。床に散乱した洗濯物の上で眠るように体を丸めていた。
私は取り乱してしまい、そのときのことをよく覚えていない。妻の体を抱きかかえて、そして救急車を呼んで……その後はどうしたのか。
妻はそのまま戻らなかった。死因は心筋梗塞。
あっという間に通夜と葬式が終わり、火葬され、骨となり、墓に入った。
息子夫婦は気遣ってくれたが、私は大丈夫だと言い、同じ家に独りで過ごした。どうせ日中は仕事でいないのだ。ここでは眠るだけ。
◇
朝の柔らかな日差しで目を覚ます。
とても静かな、日曜日の朝。
愛する妻がいなくなって、初めて迎える日曜日。
『妻』という言葉の枕に『愛する』なんて付けたのはこれが初めてだ。思えば、好きだとか愛してるだとか、そういう言葉は長い間使っていない。
――普通に出逢い、恋人となって、結婚して。
――子供が産まれて、成人して、家を出て。
家族として過ごした時間はとても長くて、いつの間にか当たり前になっていたのかもしれない。
――朝は妻の声で起き、既にテーブルの上にある朝食を胃に収めて、見送られながら職場へ向かう。
職場から自宅へ戻ると出迎えてくれて、夕食を共にして、ダブルベッドに並んで眠る。
独りになってしまった私は、ようやく妻の存在の大きさを自覚することが出来たのだ。
一緒にいるときには意識していなくて、独りになってから意識するようになるとは、これが皮肉というものか。
――家事は全て任せっきりで、子育ても妻がほとんど一人でこなしていた。
日曜日だって、基本は家でごろごろしていた。
たまには家族で出掛けることもあっが、妻には苦労をかけてばかりだった。
そんなことにも、今更気が付く。
元から繋がっていたのかわからない妻との糸(キズナ)は、今は完全に切れてしまっていると感じる。
いや、かなり前から切れていたのかもしれない。
きっと私から一方的に断ち切っていたのだ。
…
妻が死に、葬式を行い、最初の休日。目が覚めても布団に潜ったままごろごろしていた。
霊だとか死後の世界だとか、そんなことは信じていない私が、妻にだけそういうものがあればいいなと思うのは都合が良すぎるだろうか。
もちろん死んだらそこで終わりなのだが、もし、妻の魂がまだこちら側に残っているのなら、私は何と言えばいいのだろうか。
独りで静かな家にいる私は、そんなことばかり考えている。何かをしていないと気は沈んでゆくばかりだ。
――ああ、こんなことではいかんな。また明日から仕事だというのに。
外の空気を吸おうと、庭へと続く扉を開けた。
随分と久し振りに開けたように思う。私は玄関から出入りするだけで、庭へは滅多に行かないのだ。
緑の間から漏れ出る光が、きらきらと私に降り注いだ。
――そういえば妻がゴーヤを育てていたな。緑のカーテンとなって室内の暑さが和らぐとか。
数年前からやり始めて、今ではトマトやキュウリも育てていたっけ。
なぜかそこで私は、不思議な感覚に陥った。
――ああ、妻がここに残っている。
どうしてそう思ったのかは分からない。
妻が育てていた植物に、妻の温もりを感じたのだろうか。でも息子からはそんな感覚は得られなかった。
そこに妻の姿を幻視したからだろうか。それなら家の中で感じられないはずがない。
そのとき初めて、妻が亡くなってから初めて、私は涙を流した。
…
私は今まで気にも留めなかった押入れの前に立っている。確か妻がよくここで何かをしていたような記憶があったからだ。押入れなのだから、中に何かを入れていたのだろう。
押入れを開けると、たくさんの段ボール箱があった。
一番手前の箱を出して開いてみると、写真入れとノートが詰められていた。
そういえば妻は写真が好きだったように思う。どこかへ出掛けるときは必ずデジタルカメラをカバンの中へ入れていたし、家の中でもよく写真を撮っていた。
家族の思い出が、切り取られて記録されている。
息子が一人暮らしを始めてからは写真を撮る機会が少なくなったが、妻は事あるごとにカメラで記録していた。
同じような箱は五つあった。どれも一杯に写真入れとノートが詰まっている。
私は時間が過ぎるのも忘れて、写真で家族の思い出を追った。
様々なことがあった。
忘れていたことでも、記憶が蘇って、心が満たされていった。
――ああ、こんなにも、家族だったんだ。
当たり前だったことを、今更自覚して、なんだか気恥ずかしくなってしまう。
――私にもこんなに幸せな日々があったんだ。
忙しく年月は過ぎ去って、いつの間にか分からなくなっていた家族というもの。
妻は、そして息子は、息子の妻だって、かけがえのない家族なのだ。
次にノートを開いた。
それは妻の日記のようであったが、少しおかしな感じがした。
どこを開いても、片側にだけ文字が記してあり、もう片方は空白のページだった。
文字が記してある方のページの上部には妻の名前が、空白のページの上部には私の名前が書いてある。
――この書き方は見覚えがあるぞ。確か付き合い始めの頃にやっていた交換日記と同じだ。
あの時は数回のやり取りで面倒くさくなってしまって、一冊も終わらない内にやめてしまったが。
ぱらぱらと流し読むと、毎日ではないが週に二、三回は書いていたようだ。
一方通行の交換日記。
そこにはたくさんの妻の思い出が詰まっていた。
…
いつの間にか外は暗くなり、夜となっていた。
朝から何も食べていないことを思い出したら、急に空腹感が襲ってきた。
――何か買ってくるか。
私は着替えて、財布だけを持って外に出た。
向かうは近くにあるコンビニ。歩いて五分と掛からない。
適当に弁当とおにぎりを選んで、レジへ持っていく。弁当は温めてもらって、お金を払い、お釣と商品を受け取って、自宅へ戻る。
腹を満たしてから、私は妻の机に向かい、新しいノートを取り出した。
妻が使っていただろうサインペンで、表紙に『交換日記』と記した。これだけでは味気無いから、私と妻の名前も記しておいた。
――この行為が無駄だとは思わない。私と妻の間を繋ぐ、糸となるのだから。
書き慣れない日記に苦労しながらも何とか見開きの半分を埋めて、妻の仏壇にノートを置いた。
◇
もう一方通行とはならない。
私も妻も、ここにいるのだから。
切れた糸を、繋ぐ先は