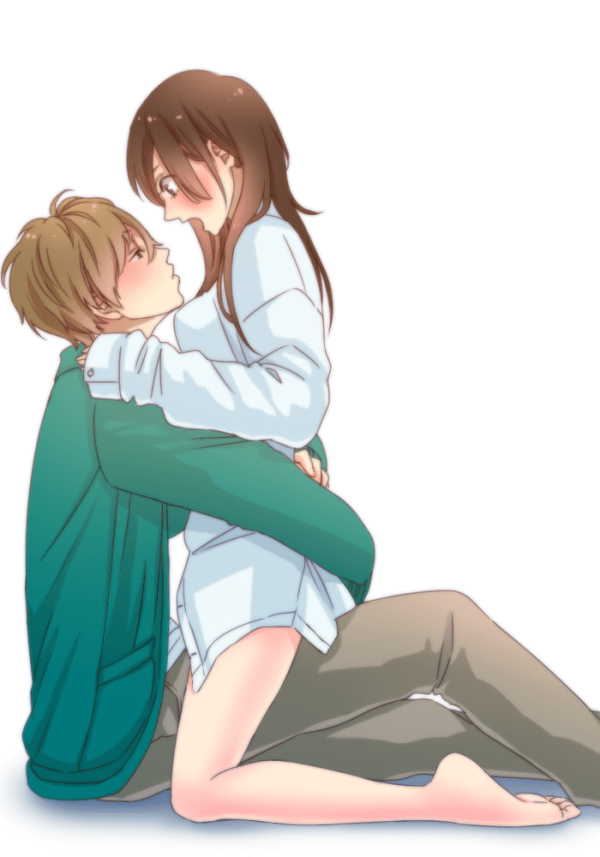
(仮) 彼女
私の仕事は(仮)彼女、一か月限定で誰かの彼女になる
この仕事のルールは
どんな男であっても本当の彼女のように振る舞うこと
途中で逃げ出さないこと
本気で好きにならないこと
この3つさえ守ればあとは自由
ただし、常識圏内で
私はこの仕事に誇りを持っている
自信を持てない男の人たちに少しでも自信を持ってもらえるように全力で
彼女を演じ、幸せになる後押しをする
たった一ヶ月、されど一か月
私と付き合ってみませんか?
目次
1.(仮)彼女になります
1.(仮)彼女になります
私、中村花二十五歳独身女は今日をもって無職となりました。
大学卒業後就活がうまくいかず、派遣社員として勤めることになった中小企業の業績低下により、派遣の私が首を切られた。
三年間働いたが、特に何の思い入れもなかった。
しかし、これからどうすればいいのか未来の自分を想像してみると、どう考えてもお先真っ暗で不安で悲しくて泣けた。
彼氏でもいれば結婚という選択肢が生まれたが、彼氏もいなければ好きな人すらいない。
みんなどこで出会いどんな恋愛をしているのだろうか。
いい出会いを求め、会社の同僚に頼み合コンや街コンに参加したりしたがなかなかいい人に巡り合えなかった。
二十五歳という年齢は”まだ二十五だし、まだ若い大丈夫だ”という気持ちと”四捨五入すれば三十だ、焦る”という気持ちの丁度板挟みになる年齢で、私の場合特に結婚願望はないが、やはり同級生たちが結婚し子供までいるという状況に少しは結婚を意識する。
結婚願望はないにしてもさすがに恋愛はしたい。
彼氏は二年前に別れてからいないし、もちろんセックスだってご無沙汰で女としての魅力がどんどん低下していくのをひしひしと感じる。
女として男の人と触れあいたい、そう思うのは女の本能として当たり前のことだろう。
解雇通知を受け、社内の人たちの憐れむような視線を浴びながら最後の仕事に取り掛かった。
お世話になった上司や同僚に挨拶し、十九時ピッタリにに退社した。
さすがに、誰もいない真っ暗な部屋に帰りたくなかった私は近くの立ち飲み屋に入る。
職場の近くにありながらも、一度も来たことがなかったこの立ち飲み屋は赤い暖簾がかかった昔ながらの雰囲気で、仕事や家庭に疲れたおじさんたちの憩いの場だった。
カウンターの端っこを陣取りお酒を注文する。
「ビールと、味噌きゅうりと、枝豆ください」
注文したお酒とおつまみがカウンターに並ぶと、一人で乾杯して一杯目は疲れか、喉が渇いていたのか、グビッと一気に飲み干した。
おかわりを注文すると、その様子を見ていたおじさんたちに声をかけられ、一緒に飲むことになった。
三杯目に突入したところで今日会社をリストラされたことや、今まで溜まっていた愚痴が一気に溢れ出した。
おじさんたちは何も言わず真剣に私の話を聞き、聞き終えたあとは人生とはなんぞやという話を聞かせてくれた。
お酒はどんどん進み、気付いた時にはもうフラフラになっていた。
さすがにもう帰ろう。
そう思い、会計をして店を出ようと歩き出したが足がおぼつかずよろけてしまった。
倒れる、そう思い目を閉じた瞬間、ふわっとだれかに肩を抱かれた。
「大丈夫ですか?」
その人は低い声で言い、私の顔を覗き込んだ。
わたしはハッとして自分の力で立ち、その人を見る。
酔いで視界が歪み、きちんとは見えなかったが、三十代か四十代くらい、身長はパッと見百八十センチくらいあり、ふわっとしたパーマがかった髪型の男性だった。
「あ、ごめんなさい。すみませんでしたぁ。あの、ありがとうございます~」と言い、軽く頭を下げた。
「いえ、あのほんとに大丈夫ですか?一人で帰れます?」
「あ、はい、大丈夫で~す。ご心配をおかけしましたぁ」と言って店を出てから記憶がない。
タクシーに乗ったような、電車に乗ったような、いや、誰かにおぶられていたような・・・
記憶が曖昧化し、いろんな記憶がぐしゃぐしゃになった。
記憶を辿っても辿っても昨日の帰りの記憶がどこにもなかった。
階段から落ちる夢を見てハッと目を覚ますと、そこには見たことのない部屋が広がっていた。
「ここどこ・・・」
そう呟き辺りを見渡す。
事務所のようなその部屋はまっ白い壁に所々に煉瓦が張り付けられていて洋風な部屋だった。
お洒落な家具に新品同様の家電製品。
ふと壁にかかっている黒板に目をやるがよく見えない。
起き上がり近づいてみると、黒板には女性と男性の名前と日付が記載されていた。
日付は開始日と終了日が記載されていて、一か月や一週間など期間は様々だった。
「なんだろうこれ・・・会社なのかなここ・・・」
そう呟いた瞬間ガチャッという音とともにゆっくりとドアが開いた。
見たことあるような人が入ってきたが誰なのか思い出せない。
脳をフル回転させ記憶を辿る。
あ!思い出した!昨日記憶をなくす前に店で会った男の人だ!
昨日は酔っていたせいで顔をちゃんと見ることができなかったが、その男性は改めてよく見るととても整った顔立ちをしていた。
俗にいうイケメンというやつだ。
イケメンの登場に、驚いた表情を見せる私を見て彼が笑った。
「ビックリしたでしょ。起きたら知らない所にいて」
彼はそう言いながらキッチンへ向かい、コーヒーを入れる。
コーヒー豆のいい匂いが部屋中に広がる。
「コーヒーしかないけど飲める?」
「あ・・・はい・・・ありがとうございます・・・」
私は状況が掴めないまま大きいダイニングテーブルの端に座りコーヒーを飲んだ。
私の前に彼が腰を下ろすと「私こいうものです。」と名刺を机に置いて、
「志摩と言います。この会社のオーナーというか社長をしております。昨日やっぱり心配になって君を追いかけてみたら案の定道で倒れていて僕が拾ったんだ。」そう言い、名刺を私の前にスライドさせた。
名刺には、SHIMAカンパニー
オーナー志摩
住所、電話番号
が記載されていた。
「あ、そうだったんですね・・・ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした・・・それで、このSHIMAカンパニーって何されてる会社なんですか?」
「この会社はまあ、簡単に言うと男の人に彼女を貸し出す会社かな」
志摩さんは笑顔でそう言うと、ハテナがいっぱい浮かんでいる私に詳しく会社の説明をしてくれた。
この会社は志摩さんと、志摩さんの親友杏子さんで2年ほど前に立ち上げた会社だそうで、現在7人の女の子が彼女として所属しているらしい。
システムは、男の人がパソコンやスマートフォンでサイトにアクセスし会員登録を行う。
入会費は無料だが女の子のレンタルは結構高めな値段設定で、一日三万円、一週間で15万円、一ヶ月で30万円らしい。
それに加えオプションで
・手繋 1000円
・ハグ 5000円
・添寝 10000円
・キス 30000円
この四つを追加できる。
このオプションは、一回支払えばその子に対して何度でも行え、この四つ以外ならレンタルした料金で普通にデートを楽しめる。
もちろんセックスは禁止。
プロフィールを見て自分のタイプの女性、開始日、レンタル日数、理由と、自分の個人情報を記入しメールを送ると、次の日にはその女性の連絡先と集合場所、時間が記載されたメールが届き、レンタル開始日を待つだけ。
そして彼女にもルールがあり、
1.どんな男であっても本当の彼女のように振る舞うこと
2.途中で逃げ出さないこと
3.本気で好きにならないこと
この三つさえ守ればあとは自由らしい。
志摩さんは一通り説明を終えると、深く深呼吸をして
「彼女になりませんか」
と言って私に手を差し出した。
「えっと・・・あの・・・なんとなくシステムとしてはわかったんですけど、まだちょっとすぐにはお返事はできないです。すみません」
私はそう言って立ち上がり「介抱していただき感謝しております。本当にありがとうございました。」と深く頭を下げた。
志摩さんは「仕事が見つからなかったらでも、いつでもいいからまた連絡してくれ。いい返事期待してるよ」と言って私の頭にポンッと優しくたたいた。
私はもう一度頭を下げてから部屋を出た。
私は家に帰るとパソコンを開き、”SHIMAカンパニー”と検索した。
検索結果の一番上にホームページが出てきたのでクリックしてみる。
ホームページはしっかりとしていてお洒落だった。
スクロールしながら画面を見る。
「会員登録しないと女の子の顔は見れないのかぁ・・・」
どんな人が彼女として働いているのか興味はあった。
しかし、興味はあると言えども、自分が誰かの偽物の彼女になるなんて想像できなかった。
とりあえず仕事を探して、見つからなかったら少しだけやってみよう。
私は長い髪をまとめ、部屋用の眼鏡をかけると気合を入れて仕事を探し始めた。
求人は沢山あるけど何がしたいという明確な目標がなく、就職活動は難航していた。
就職活動を始めて一週間が過ぎた頃、何社も落とされへこんでいる私に一本の電話がかかってきた。
朝八時、非通知からの着信に「もしもし」と寝ぼけた声で電話に出る。
「ハロー♪」
電話口からは陽気で可愛らしい女の人の声が聞こえた。
その甲高い声で目が覚める。
「あのぅ・・・どちら様でしょうか・・・?」
「あっ、ごめんね~!私、SHIMAカンパニー社長秘書兼(仮)彼女の杏子でーす!突然でびっくりさせちゃったよね、ごめんねっ♪でさ~」
杏子と名乗る女は私に返事をする隙も与えずベラベラと話し続ける。
杏子さんって確か志摩さんの親友で一緒に会社立ち上げた人か・・・
「それでね?って聞いてる?」
「あっ、はい、聞いてます」
「よかった、でね、もし仕事まだ決まってないようだったら一日体験入社してみないかなあって思って。どうかなあ?」
私は少し考え、「一日なら」と体験入社をすることに合意した。
杏子さんは甲高い声で「ほんとー!!?ありがとう!!」と言うと、早速今から会社に来てほしいと告げ、私の有無を聞かず一方的に電話は切れた。
「ああっもう~・・・まあいっか・・・」
と独り言を呟き、私は小さく呆れたような溜息をついて急いで支度をし、SHIMAカンパニーへ向かった。
SHIMAカンパニーは真新しい十階建マンションの十階にある。
エレベーターでボタンを押し、十階を目指す。
順調に上っていくエレベーターは途中七階で止まった。
綺麗な女の人が乗り込み、共に十階で降りた。
ほんのりいい香りがする。
サラサラの髪に、大きな目、そして筋の通った鼻に小さな顔でおまけにスタイルもいい。
どこかのモデルさんだろうか、そう思いながら歩いていると彼女もSHIMAカンパニーのドアの前で立ち止まった。
「あれ?もしかしてあなた噂の新人さん?」
彼女は瞳をキラキラさせて私に近づく。
「あっいや、新人って程のものでは・・」
彼女は私の話なんか聞いていない様子で私の腕を引き、勢いよくドアを開けた。
「志摩さーん!来ましたよ!新人さん!」
彼女は私の腕を掴んだまま、靴を乱暴に脱ぎ部屋にどんどん入っていく。
私はもうついていくのに必死で玄関から部屋までの短い距離なのに疲労困憊していた。
彼女はリビングにつくと、私の腕を離してソファーに座り、携帯をいじり始めた。
「おお、よくきたな。杏子から話は聞いてるよな?」
朝食であろうパンをかじりながら新聞を読む志摩さんが私を見ることなく言った。
「あ、はい・・・まあ粗方・・・」
「それなら話は早いな。今日はこいつのデートに付いて行って欲しい。よろしくな葵」
志摩さんは新聞を畳み、葵にウインクするとコーヒーをグビッと一口飲んだ。
葵はソファーに座ったまま、ラジャーッと言って敬礼し、立ち上がる。
そして、とりあえず自己紹介するね、と言って話し始めた。
年は22歳で私の3つ下、大学四年生で就活の合間にこのバイトをしているらしい。
今回の彼氏は石原浩太、三十三歳。
お堅い公務員で出会いがなく、久しぶりにデートがしたいという理由で彼女をレンタル。
一週間のレンタルで、レンタル二日目の今日は”友達に彼氏を紹介する”という設定だそうだ。
なるほど・・・なんかちゃんとしてるんだなぁ
葵の自己紹介が終わって、私も軽く自己紹介をした。
葵は立ち上がり「よし、じゃあそろそろ行きましょうか花さん。約束の時間だから」と壁にかかった時計を見て黒板の自分の名前の横に、出勤という磁石を貼った。
待ち合わせ場所は恵比寿駅から徒歩5分位にあるお洒落なカフェ。
葵の後ろを金魚のフンのようについて行く。
店内もとてもお洒落で、セレブそうなおば様方が優雅にティータイムをしている。
甲高い笑い声が店内に響き渡る。
葵はそんなことを全くきにしない様子で、店員に「待ち合わせです」と言うとどんどんと店内の奥のほうへ進んでいった。
一番奥の四人掛けの席に座っている男の人の後ろ姿が見える。
葵は座っている男性に近づいて、私と話す時よりもワントーン高い声で話かけた。
「石原さんっ♪」
彼はその声に振り向き、小さく微笑んだ。
そして私たちに座るよう促す。
葵が先に座り、それに続いて私も座った。
石原さんは、想像通り公務員ですと顔に書いてありそうな顔をしていた。
真面目な印象で、休日だというのにスーツできっちりとした格好をしている。
この今日初めて会う二人と、三人でカフェにいるという何ともよくわからない状況に戸惑っていると、
葵が耳元で「女優のつもりで演じればいいんですよ」と小声で言った。
そして石原さんと楽しそうに会話し始める。
女優のつもりって言われてもなあ・・・
まあでも、ごちゃごちゃ頭で考えていても仕方ない!と思い直し、完璧に演じることに決めた。
とりあえずメニューを開き、店員を呼ぶと、ホットミルクティーを二つと葵はモンブランを頼んだ。
「あ、石原さんに紹介しますね。この子私の親友の花。高校の時から仲良いんです。ね?花」
と急に話を振られ動揺し、「あっう、うん!そうそう仲良しなんです」と不自然な笑顔で答えた。
石原さんは「花さん、よろしくお願いします。」と優しく微笑んだ。
その優しい笑顔を見て緊張がほぐれたのか、その後は動揺することも緊張することもなく親友を演じることができた。
注文していたものが届き、二人が会話しているのを聞きながらホットミルクティーを冷ましながら飲む。
心なしか二人は本当のカップルに見えた。
こんなお堅そうな人でもこんな風に笑ったり面白い話をしたりするんだなあ。
これから先普通に生活していたら出会えないような人に出会えて、今まで知らなかったことを知ることができるのがこの仕事なんだとしたら私は少しだけこの仕事に興味がわき、ほんの少しだけやってみようかなという気持ちになった。
葵はケーキを食べ終えると、「この後どうしますか?恵比寿でお買い物とかします?」と言って微笑む。
「買い物行こうか」石原さんはそう言うと立ち上がり伝票をサッと持っていき素早く会計を済ませた。
スマートな会計に驚く。
今まで付き合ってきた彼氏は大体が同い年でいつも割り勘か、たまに気が向いた時だけおごってくれるという感じだった。
石原さんみたいな人と付き合えたら幸せなのかもしれない。
店を出ると、葵は「ごちそうさまでした」といってひょこっと頭を下げた。
かわいい・・・ほんと女の子って感じだなあ。見習わなきゃ。
二人が仲よさそうに歩く後ろをまた金魚のフンのようについていく。
(仮) 彼女

