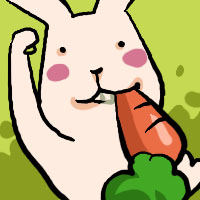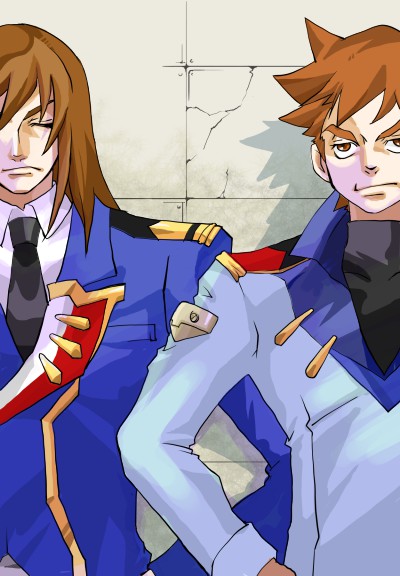
CODE:GLADIO/インターミッション
一日の終わりに
新兵にとって過酷なもの、いやこれは新兵だけに限った事ではないかもしれない。
間違いなくその五本の指に入るであろう訓練、シンクロトライアルオペレーションを東方面軍第8特種重機歩兵部隊が終了したのは、夜も白みかけた明け方の事だった。通称「電脳化」、操縦士をより重機歩兵操作に適した体に作り変える訓練だ。重機歩兵のコクピットに縛り付けられ、大きな金属製の体に意識を溶かし込んだままの長時間は傍から見ているほど楽な物ではない。特に操縦士になって日の浅いマックスにとっては、訓練の度に求められる「あと1パーセントの深度」がとても辛いものだった。例えるならば、もはや息の続かないほど潜った深い海で、さらにあと10メートル潜れと言われるようなものだ。訓練が終わる頃にはまるで脳が水を吸って膨張した海綿体ように狭い頭蓋骨の内で疼き、手足は厚手の布でくるまれたかのように感覚が鈍くなった。その上で戦闘が行われて初めて重機歩兵が兵器となるのだが、今の自分はまだそれどころではない。
彼らが地獄から解放されたのは、それからさらに陽が昇りすっかり辺りが明るくなった頃だった。つかの間の帰舎が許されたマックスは、その前に一息ついておこうと一人休憩室へと向かっていた。頭の痛みはまだ健在で、目の前は霧がかかったままだ。一刻も早く風呂を浴びたい気持ちもあったが、このまま帰れば道中些細な段差につまずいてひっくり返らないとも限らない。同じく訓練を終えた仲間たちは我先にとここを引き上げ、あたりに人気はない。だがすでに言葉を交わす余力のない彼にとってはその方がかえって都合が良かった。
重機歩兵格納庫は修理工場も兼ねていて、中は収納される兵器に合わせて巨大な空洞になっている。おまけにトライアルオペレーション施設も整っており、スクランブルでもない限りマックスは基地での大半の時間をここで過ごす。ここでの主役は重機歩兵で、彼らよりはるかに小さい人間様は、その全長に合わせて周囲の階段を上り下りしなければならなかった。マックスは丁度彼らの胸辺り、建物にすると四階くらいに相当するだろうか、フロア間を結ぶ渡り廊下を歩いていた。堅い靴底が当たる度に金属製の床が甲高い音を発し、広い格納庫内で複雑に木霊する。そんなささいな音すら耳触りに思いながら、マックスは重い両足を引き摺りつきあたりの部屋の前へ辿りついた。そして扉に手をかける。
表面にとりつけられた金属のセンサーはひんやりとして冷たく、触れると鈍い駆動音を立てて扉が横へずれた。部屋の中は殺風景で、ただ四角い部屋に数個の長椅子、中央には大きなテーブルが一つあるだけだ。飾り気のない壁が午前の陽を遮り、まだ薄暗い部屋の中で飲料の自動販売機だけがやけに明るい。マックスのお目当てはそこに並ぶ僅かに砂糖の入ったコーヒーだった。
「ひっ…!」
IDカードを探ろうとポケットに手をかけたところで、マックスは思わず声をあげた。彼の真横には普段はそこに無いはずの長椅子、誰かが入口付近にずらしたのであろう。その上に人影らしき青白いものが横たわっていた。
咄嗟に飛び退いたせいで扉にしたたか左肩をぶつけ、それに靴音が混じってかなりの騒音を立てたが、人影はピクリとも動かない。マックスは扉に押しつけたままの背中に汗が噴き出るのを感じた。
「な、なんだ…キャンベルさんか」
驚きのせいで頭の霞は吹き飛び、視界が一気に冴え渡った。そこに横たわっていたのは、てっきり前に帰ったと思っていたキャンベルだった。青白く見えたのは、彼女がまだ淡い色のトライアル用アンダースーツを着込んだままでいたからだ。マックスは慌てて、しかし今度は音を立てぬよう慎重に今ぶつかった扉を後ろ手に探った。幸い表面の形状に変化はない。おそらく基地のこの一帯の建物は、マックス達の様なアトロフィクシスを収容する為に必要な補強があらかじめなされているのだろう。昔住んでいたボロアパートの扉なら、今の体当たりで風穴があいていても不思議はなかった。
「驚いた、脅かさないでくださいよ」
彼女はそこでぐっすりと眠っているようだった。マックスは小声でそう話しかけつつ、恐る恐る頭のある方から覗き込んだ。元々凹凸の控えめなキャンベルの体は厚手のアンダースーツにがっちり包まれたままで、肩が寝息に合わせて小さく上がったり下がったりしているのがわかる。長椅子の肘掛を枕に、小首をかしげるような格好で眠る彼女の横顔が見えた。
彼女もマックスと同様の新米の重機歩兵操縦士だった。今さっきまで隣に並んで同じ訓練を受けていたのだから、キャンベルもクタクタに疲れているはずだ。ひょっとすると同じような経緯でここへ来て、長椅子の上で力尽きてしまったのかもしれない。
「起きて下さい、こんな所で寝てたら風邪をひきますよ…」
そう声をかけてみはしたものの、相手は身じろぎ一つしない。それからしばらく様子を見た後で、マックスは何か苦い物でもかみつぶしたかのように口をへの字に曲げ、上目遣いに天井を見た。
年齢はキャンベルの方が一つ上だが、軍隊に来た時期はマックスの方がずっと早い。おまけに彼女は少し前まで民間人で、特に何の訓練を経るでもなく重機歩兵に乗る事になったらしい。運が悪い事に彼女がここ第8特種重機歩兵部隊に来た時、マックスは宇宙での合同ブートキャンプのまっ最中で留守にしていた。たったそれだけで彼女からは「後から来た者」扱いを受け、こうして敬語まで強要されている。上下階級に厳格な軍隊組織で何故こんな事になるのかとも思うのだが、彼女をここへ留めておく事が連邦国軍上層部の命令だと言われればどんな理不尽にも素直に従うしかない。どうやらそれはマックスだけに限った事ではなく、隊長達上官にも同じ試練が課せられているように思える。
となれば、触らぬ神に祟りなし。寝ている今は大人しいが目を覚ませばまたどんな難癖をつけられるかわからない。マックスは再び視線を横たわり続ける物体に戻した。幸い部屋には空調も効いているし、スーツの中は適温に保たれているはずだ。彼はこのまま寝ている彼女に気付かなかった事にして立ち去る方を選択しようとした。
その時だった。
マックスが行おうとしている仕打ちを嗅ぎとったのか、キャンベルの目がうっすらと開いた。マックスはまた叫びそうになり、咄嗟に口を手で覆った。
薄暗い室内でその程度の事に何故気付いたのかと疑問に思われるだろうが、キャンベルの翠の瞳は時々発光して見える事がある。特に暗闇ではまるで夜光塗料でも施してあるかのようにはっきりと浮き上がり、時として更に光を増す事があるらしい。今は小さな蛍の灯りほどで、彼女の瞬きに合わせてゆっくりと消えていく。
「ううっ…!?」
マックスはしばらくその様を凝視していた。しかし再び瞼が開かれる事はなく、その間も後も定期的な寝息だけが聞こえて来る。どうやら本当に目を覚ましたわけではなさそうで、マックスはほっと胸をなで下ろした。ふくれっ面のお嬢様というのは教官役ヘレナが彼女に与えた称号で、何でも臆せずやってみるのはいいがとにかく文句が多い。今日のトライアルには最初から最後まで珍しくクラノス隊長が立ちあってくれたのだが、何が気に入らないのか終始ずっと彼に噛みついていた姿が思い出された。連邦軍屈指の操縦技術を持つ隊長からなるべく多くの事を学びたいとマックスは思うのだが、彼らの口論の最中は黙って見ているしかない。ひょっとしたら彼女の疲れの大半はそこにあるのかもしれないとさえ思う。
だというのに結局最後にはマックスと同じだけの数値を叩きだしたのも事実だった。訓練を始めて間もない事を思えばとんでもない成果だ。そもそもキャンベルはただの民間人ではない、彼女の家は元地球最大の武器商で、兄は元連邦軍の天才重機歩兵パイロットだった。連邦国軍の同業者なら知らぬ者はいない…もちろんマックスだって、それほどに優秀な人物だったらしい。だから近いうちに彼女に先を越されてしまうのではないかという不安は、最初からマックスの中にあった。こうして気ままに振舞っていてくれた方がまだ可愛げがあるのかもしれない。
マックスはそっとキャンベルの肩に触れると、静かに揺すった。このまま他に誰も来なければ次の勤務までここで目を覚まさないだろう。今度はポンポンと叩くと、少し赤みがかかった髪が長椅子に擦れてサラサラと音を立てる。少し癖のある毛先が彼女の頬と鼻を刺激し、くしゃみを誘発しようと仕掛ける。マックスは慌てて手を離し、立ち上がると近くの照明スイッチを探った。
その目論見は当たり、部屋が明るくなると同時に、キャンベルは大きなくしゃみを一つして目を覚ました。慌てた様子で上半身を起こし、両足を床に投げ出す。すると踵が床に当たって大きな音を立てた。彼女はブーツもそのままに寝入っていたのだ。
「…ふあ…あれ、マックス?」
彼女の脳はまだスポンジ状から回復していないようで、締りのない口調で声を絞り出した。すっかり室内は明るくなったが、キャンベルの虹彩はまだ縁がくっきりとして見えた。どうやら発光は感情の変化にも連動しているらしい。
「あれ、隊長は?」
「…ハイ?一体どこで寝てたと思ってるんです
隊長がこんな所に居るわけないでしょ」
マックスは両肩を寄せ、大げさに溜め息をついて見せた。訓練の続きでも夢で見ていたのだろうか、彼女はまだ夢と現実の境に居た。二人とも隊長とは勤務報告を終えた後、部屋を出てそれっきりのはずだ。我先にと部屋を飛び出していったのは彼女で、後から続いたマックスは廊下で偶然医療部の人と鉢合わせた。ほんの僅かだが言葉も交わした。彼女は隊長を探していた。
「隊長ならとっくに…」
そう言いかけてマックスは口を噤んだ。
ジェファーソン医長の孫娘、アイロットに会うのは今日が久しぶりだった。医療部に正式採用された証である紅色の制服姿は、普段慎ましやかな彼女を少し凛々しく見せていた。マックスが第8特種重機歩兵部隊へ来た頃には、まだ研修生として出入りしていた彼女がもう一人前になったのだ。嬉しくもあるが、医長の助手から医療部付きになった事で会う機会が減ったのには寂しさもある。別に普通の女性を見る機会がマックスにないわけではないが、アトロフィクスばかり多く集う特種部隊の基地では、彼女の周囲だけ空気が違って見えた。激しく日に焼ける事も怪我を繰り返す事もない彼女の白く抜けるような肌と、金の絹糸のような豊かな髪は嫌でも基地内で男達の目を引いた。上がり症で直ぐに頬を赤らめる姿は、マックスを何度も照れくさいような気恥かしい気持ちにさせたものだ。そんな彼女が隊長の幼馴染だと聞かされた時、マックスはどれだけ落胆しただろう。
「とっくに、ねえ、何?」
そんな彼の気持ちを微塵にも酌む事なく、キャンベルが鼻先をつっこんでくる。だいたい所属部隊の指揮官をまるで自分の使用人の様に思う事自体理解に苦しむのだが、マックスがここで彼女を論破するにはまだまだ彼女に関する知識が足りない。それに隊長の行き先を一番気にしているのは実はマックス自身なのだ。
できれば何も考えたくない。だというのに、あの後談笑する二人の背中を見送った時の、何とも言えない感情が今再び思い起こされて、無性に腹が立ってきた。
「…あのね、俺が隊長の行き先をいちいち知ってるわけないでしょ!?」
まさに言葉どおりだった。隊長の行き先など本当にどうでもいい、あれからアイロットと速やかに別れてくれさえすればいいのだ。無意識の内に飛び出していた下唇を慌てて引っ込めると、マックスはそっぽを向いた。振り向きざまにきょとんとしたキャンベルの顔がちらっと見えた気がするが、もう振りかえらない。マックスは取りだしたカードを強く握りしめ、自動販売機に向かって一直線に歩き出した。
そうだ、今日のコーヒーにもう砂糖はいらない。
CODE:GLADIO/インターミッション