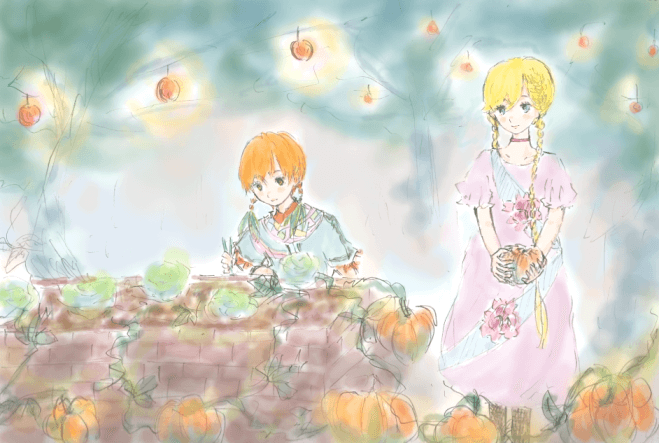
葡萄色のシャンデリア
【いつか、少女は人間にして初めての魔女となるであろう。これは、少女を守った二人の話――】
前編

少女は物心ついた時から、なぜか床に寝ていた。
というよりは、少女が記憶できるようなものなど、こじんまりとした部屋の床と壁、窓のステンドグラス、沢山の彩りに溢れたドレスクローゼット、金糸の刺 繍が施された本の棚、硝子でできた透明の如雨露に、眠りから覚めればいつでもいつのまにか違う花が浮かべられているバスタブ、そして部屋の天井に吊り下げ られた、大きな葡萄の形のシャンデリアしかなかったのだ。彼女は他に何も持たなかった。
床はエメラルドグリーンとシルバーのタイルになっていた。窓にはグリーン、パープル、イエロー、マゼンタ、ペールブルーの硝子の組み合わせで大きな鯨と 小さな鯨が描かれていた。扉のような大きな窓を開くと、バルコニーには小さなターコイズグリーンのキャベツがちんまりと植わっていた。それにはバスタブに 溜められた水を如雨露に汲んで、水やりをしていた。
誰かが言葉を教えてくれたのは確かだった。何故なら少女は、話そうと思えば言葉を話せたのだから。けれど、それが誰だったのかをよく覚えていなかったのだ。濃紺の暗い布に包まれた人。しわがれた声。
少女の単調な日常が終わりを告げたのは、【それ】が言葉を話したからだ。
翠の葡萄と紫の葡萄。それらを模して造られた美しいシャンデリア。葉や蔓は金細工でできている。淡く美しい翠と紫の光を落とす。そのシャンデリアが――しゃべったのだ。
とても可愛らしい女の子のような声で。
「やあ、こんにちは。そろそろその暮らしにも飽きて来たろう?」
シャンデリアは快活な声で、唐突に少女に語りかけたのだ。
「飽きるも何も、飽きない方がおかしいわ」
あまりにも唐突だったので、少女はかえって冷静だった。
「それで……その、それはあなたが喋っているの?」
「うん? それ、とは?」
「だから、シャンデリアさんが喋っているの?」
「あー……うん、まあね。そんなところだよ」
シャンデリアはけろっとしたように言った。
「そんな風に無造作に寝転んでいたら、せっかくの綺麗な金色の髪が台無しじゃないか」
「シャンデリアのくせに見えているの?」
「そう……だね、私は色を捉えているんだよ」
「そう……。だから、なのね」
少女はふう、と小さく息をつく。
「だからこの部屋は、こんなにも色に溢れているのね?」
「まあ、そんなところかな?」
「じゃあ、この部屋は本来あなたのための部屋なのね? そこにわたしが押し込められたという訳ね? 何年も……もうどれくらい長いことここに居るのかさえ分からないわ」
「あなたは賢い女の子だね」
シャンデリアはくすりと笑う。
「私のための部屋ともいえるし、これはあなたのためのお部屋だよ。あなたを閉じ込めるために作られた部屋さ。私はそこに取り付けられた一介の調度品でしかない」
「ねえ、シャンデリアさん」
「なんだい」
「どうして、今更なの」
少女は少し拗ねたような声で言った。
「話せたんじゃないの。どうして、あなたは今までずっとだんまりを決め込んでいたというの? もっと早く話しかけてくれたらよかったじゃない」
「だから、今こうしてお話できているじゃないか」
シャンデリアの声はとても柔らかく、優しい。少女は頬を膨らませてぷいっとそっぽを向いた。
金色の長く艶やかな髪が、無造作に、小川のように床に流れる。
「私がこうして話せるようになったのは、あなたのおかげなんだよ」
シャンデリアは穏やかに応えた。
「あなたの魔力が私に注ぎ込まれた。そうして私はいつしか心を持った。いつか、あなたと話したいと焦がれ続けて、そしてようやく、その願いが叶ったんだ」
少女は困ったように眉をひそめた。
「魔力? わたしに魔力があるというの? 魔法の力が?」
「そうだよ。だからあなたはこの部屋に閉じ込められているのさ。あなたは本来魔力を扱える魔族ではない。けれどあなたの母親が――あなたを身籠っている最 中、魔女のキャベツを食べてしまったんだ。ほら、そこのバルコニーにも生えているでしょう? あれを食べてしまったんだよ。そのおかげで君は、ただの人間 が抱えきれない魔力を持って生まれてきてしまった。あなたの命の源はその魔力なんだ。あなたがいる空間が広ければ広いほど、あなたはその身体から魔力を放 散してしまう。魔力が尽きればあなたは死んでしまう。だから、狭い部屋にあなたは閉じ込められた。いつかあなたが成長して、魔力がコントロールできるよう になるために、ね。けれど、こんなこと、きっと誰も教えてくれなかったでしょう?」
「誰もも何も、わたしに会いに来てくれる人もいなかったから」
「そんなことはないはずだよ」
シャンデリアは優しい声で言う。
「あなたを引き取った魔女のお婆さんが、あなたに言葉も着替え方も食事の仕方も、水やりの仕方も、ちゃあんと教えてくれたはずだ。だからこうしてあなたは そんな可愛らしいドレスを着て、私と話すことができるんだ。けれどあのお婆さんは恥ずかしがり屋だから、あなたに覚えられないようにしていたんだよ。だか らあなたは忘れているんだ」
「そう……なの」
少女は、声を落とす。
「いつか、お礼が言えたらいいのだけど」
「言えるとも」
シャンデリアは笑った。
「私がこうしてあなたと話せるようになったことは、あなたが成長している何よりの証拠さ。もうじきあなたは外へ出られるよ。ここから出て、もっと広い世界を見るといい。時間はたくさんあるからね。お婆さんにお礼も言える」
「そうね」
少女はようやく、ふわりと笑った。
「それじゃあ、それまで寂しいわたしの話し相手になってくれる? シャンデリアさん」
「もちろん」
「わたしの名前はオーロラよ。あなたのお名前は?」
「私の、名前――」
ふと、シャンデリアは声を曇らせた。言いよどむように。戸惑うように。
「あ……そうか、シャンデリアなんだから名前なんてないわね? わたしがつけてもいい?」
「……仰せのままに」
どこか、ほっとしたようにシャンデリアはおどけた声を漏らした。
「ふふっ、何それ。仰々しいわ」
オーロラは微笑んだ。
「じゃあ、そうね……ネフライトのネフラってどう? ほら、あなたの翠に似ているわ。わたしもね、宝石の名前からとったのよ。自分でつけたの。可愛いでしょう」
「……」
「なあに? もしかして、気に入らない?」
「いや――」
シャンデリアは、少しだけ震えたような声を零した。
「そうじゃ、ないよ。うん、綺麗な名前だ。ありがとう。大切にするよ」
「大切にするのはわたしでしょう? その名前を呼んであげるのはわたししかいないんだから」
「ふふ、そうだね。オーロラ。じゃあ私はあなたの名前を大切にしよう」
「ふふ、ありがとう、ネフラ」
オーロラはきらきらと真っ青な瞳を輝かせて、可憐に微笑んだ。
中編
――不思議な魔法のシャンデリア。美しく、儚くて、時々おどける、素敵な素敵なわたしの友達。
けれど、オーロラが再び退屈に沈むのに、そう時間はかからなかった。話し相手ができたと言うだけで、今日も昨日も明日も明後日も変わり映えはしない毎 日。ドレスはいつの間にか眠っている間に新しいものが少しずつ増えていった。けれど、見てくれる相手もいないのに、ドレスを身に着けたって楽しいことは何 にもない。
「どうして? そんなに綺麗なのに」
ネフラが優しい声で言った。オーロラはふわぁ、と小さく欠伸をする。
「そうねえ……そう言ってもらえるのはとても嬉しいのだけれど……でもいまいち嬉しくないのよね……」
「言っていることが矛盾しているよ?」
ネフラは穏やかな声で、まるで小鳥が首を傾げているように笑った。
「わたしは、何が欲しいのかしら?」
「あなたが分からないものを、私が分かるはずがないだろう?」
「そうね、そう、だってあなたはわたしの魔力でしゃべるんですものね。それって、わたしの一部ってことだもの」
オーロラはごろんと床に寝そべったまま緩やかに呟く。
「あなたの一部になれて、嬉しいな」
「ああ……もう、そうじゃないの……そうじゃないのよ、ネフラ」
オーロラは胸に抱きしめていた一冊の本を開いて腕を伸ばし見上げた。
「これよ……そう、物語。物語の囚われのお姫様は誰だって素敵な王子様が迎えに来てくれるじゃない。これなのよ……こういう、そう、どきどきするようなものがほしいの!」
「それは、」
ネフラの声が、どこか無機質な響きを奏でた。
「あなたも、恋がしたいと言うこと?」
こういう時、オーロラはたまらない気持ちになるのだ。彼が――もしかしたら彼女なのかもしれないが、自分とは違うただの【物】であることに、たまらなく胸が苦しくなる。
「そう、そうね……そうかもしれないわ。だってこの部屋にだってあるじゃない、あの素敵な広くて大きなバルコニー! 知っているわ、この部屋は高い塔の上 にあるのよね? 晴れ渡った空の下に見えたのよ。小さな、可愛らしい赤色の屋根たち……。きっとここが雲の上にあるから、誰も気づいてくれないんだわ。こ んなにも待っているのに。ねえ、そうだネフラ。わたしのこの髪を縄みたいに編んで垂らしていたらどうかしら? 誰かが遊びに来てくれないかしら!」
「あまりお勧めはしないよ」
ネフラは少しだけ悲しげに言った。
「でも、そうだね、あなたはそんなに、自分と同じものに出会いたい?」
その声に、オーロラはゆっくりと体を起こして、ネフラを仰ぎ見た。
そうかもしれない。わたしは、会いたいのかもしれない。同じように笑いあえる人に。愛していると伝えてくれる人に。温もりを感じられる人に。手を伸ばせば……届く人に。
「僕じゃ、やっぱり、足りない?」
ネフラの声が震えている気がした。
「そ、んなことは――」
急に胸がきゅっと締め付けられて、オーロラは思わず縋るように呟いた。けれど、ネフラはどこか擦れた、途切れるような音で零した。
「ごめん、ちょっと、考えさ――て」
「ネフラ?」
そうして、ネフラは黙ってしまった。
何度呼びかけても、彼はそれから二度と、オーロラに声をかけてくれることは無かった。
オーロラは、静かな夜を、窓辺に座ってやり過ごすようになった。金色の髪を切って。泣きながら、固く固く編み続けていた。
*
金色の縄を垂らして、どれくらいの時が経ったのかわからない。今日もオーロラは、バルコニーのキャベツの瑞々しい葉を指で撫でながら、ぼんやりと空を眺めていた。
――ああ、なんて退屈なんでしょう。
何度目になるかわからない溜息をつく。ネフラの名前を呼ぶのはやめた。あの部屋で、天井を見つめて寝そべることも、しなくなった。
あの葡萄のシャンデリアを見ているのが辛かった。
ふと、かさり、ぎし、と音がする。
ぼんやりした頭は、その音をなかなか認識することができない。
はっと気が付いた時には、オーロラの顔を覗き込む知らない人の顔が影になっていた。
「きゃっ?」
思わず後ずさる。
栗毛色の髪を一つに縛った誰かが、オーロラをじいっと見つめていた。
「こんにちは」
彼は、やがてふわりと笑った。
「こ、んにちは」
「やあ、こんなところに美しいロープがあったから、なんとなく好奇心に負けて登ってみたのさ。そうしてみたらどうだい、こんなに可憐な美しいお嬢さんがいるなんて」
「か、かれん……」
顔が熱くなる。
「いやあ、すべすべと滑らかなロープだったものだから、とても登り難かったんだよ。けれど、苦労した甲斐があったなあ」
「あ……、ごめんなさい」
「うん? どうして君が謝るのかい?」
そう言って青年は、よっ、と言う声と共にバルコニーの柵を飛び越えた。オーロラはまたびくりと肩を跳ねさせる。
「不思議な部屋だ……なんだろう、この窓も、床も、人の手で作ったにしては繊細すぎる……もしかして君は魔女なのかい?」
そう言って向けられた眼が冷たく感じられて、オーロラは思わず否定するように首を激しく振っていた。
「わた、しは……魔女に、囚われて……」
――ああ、なんてことを言うのだろう。お伽噺の読み過ぎだわ。
オーロラは胸を刺す自責の念に顔を歪めた。魔女はわたしを助けようとしているだけ。だからわたしは囚われているのではない。わたしはこの場所を、嫌いなわけではないのだから。
「そう」
青年は、穏やかに笑う。
「じゃあ、君は可哀相な美女と言うわけだ。ねえ、ここから出たいと思わないの?」
「ここ、から、出る?」
「そうだよ」
出るだなんて、そんなことを考えたこともない。
――出る? この場所を、離れてしまう?
オーロラははっとして天井を見上げた。ネフラは――物言わなくなったネフラは、それでもなお、日の光を反射して、柔らかく輝いている。オーロラの頬に紫と翠の光を零す。
――助けて。助けて、ネフラ。
オーロラは泣きそうな心地で、声すら出すこともできずに震えていた。
助けてくれるわけがない。助けられない。ネフラは手も足もないのだ。動けないのだ。助けられるわけがないのだ。
――怖いの。この人、わたしの話を聞いてくれないの。わたしが話せるようになるまで待ってくれないの。どうして、どうして。
同じ姿の人が来れば、心が通うと思っていた。
「重いわ」
辛うじて、擦れた声でそう言う。青年は、オーロラを床の上に押し倒して、体重をかけるようにして見降ろしている。その顔が影になって、見えなくて、怖い。
恐ろしい。どうしてわたしは動けないのだろう。身動きが取れない。どうすればいいのだろう。どうしたら。何を言えば。
「すぐに慣れるよ? ねえ、お嬢さん。私が貴方をここから連れ出してあげよう。僕の国へ一緒に帰るんだよ」
――帰る? どこへ?
わたしの帰る場所は、この場所以外にどこにもないのよ。
「やめ、て」
声が擦れて、切れる。糸屑のように。青年のざらついた手が、自分の足を、太腿を、撫でる。衣擦れの音。やめて、怖い。やめて。
お腹が、痛い。やめて。
「おや? 月のものが来たのかな?」
ふと、青年が手を止めて、顔をしかめた。お腹が痛い。鈍く痛む。何のことかわからなかった。青年の手にどろりとした赤いものがついている。これは、――血?
「ふうん」
急に、青年は興味を無くしたように冷めた目でオーロラを見つめた。
「ふん、興が覚めてしまった。仕方ない。また来るよ、美しい御嬢さん。お大事に」
お腹が痛くて、気持ち悪い。
吐き気がした。苦しい。痛い。辛い。気持ちが悪い。来ないで。もう、来ないで。
その時、ぴしり、という微かな音が天井から聞こえた。恐らくは、オーロラにしか聞き取れないような微かな音で。
その刹那、悲鳴が聞こえる。オーロラは肩をびくりと跳ねさせた。
青年は、目から血を流して蹲っていた。気が狂ったように叫ぶ。ふらふらと、足がもつれて、彼はバルコニーから真っ逆さまに落ちて行った。
「あ……っ」
顔が青ざめる。死んでしまったのだろうか。死んでしまうのだろうか。それは怖い。
彼を怖いと思ったけれど、死んでほしいと思ったわけじゃない。
「大丈夫だよ」
天井から、擦れた声が聞こえた。
「彼は死なないよ。あれも魔法使いだからね。目が使えなくなったくらいで死んだりはしない。大げさだね……たった、目に硝子の破片が刺さっただけだと言うのに」
「ネ、フラ……」
その声は、記憶にあるよりもずっと擦れて、がらがらとして聞き取り辛かった。
「ネフラ、なのね」
涙が零れる。
「どうして……どうして、ずっとだんまりでいたの……もう、二度と、お話しできないって……」
「泣かないで」
ネフラは優しい声で言った。
「ほら、子供みたいに泣かないで。あなたはもう大人になったのだから」
「大人……? そんなはずないわ。わたしは何も、変わっていない」
「あなたの魔力は確かにようやく変容したよ。だって、あなたは血を流したでしょう」
オーロラは、ドレスを汚していく血を見つめた。
「これが……大人の証だと言うの?」
「そうだよ、オーロラ。あなたはもう、ここから出ることができる。直に迎えが来るだろう。ここから出て、広い世界を見るんだ。願わくば、幸せで、安全な場所で」
「ネフラは……? ネフラは……ついてきてくれるの?」
「私は……」
ネフラは言いよどんだ。
「無理だよ、オーロラ。だって、私はこの部屋のただのシャンデリアだからね。それに、ほら。あなたを守りたくて、破片を飛ばしちゃったから、ひびが入って しまった。ほら、どんどん広がっているだろう? 重みに耐えられないんだ。もっと早くにあなたを守れればよかったのだけれど、私にはこんなことしかできな かった。ごめんね」
ぴしり、と音が連なっていく。
「やめて……ネフラ、やめて……! 割れないで! 壊れてしまわないで! わたしを……一人にしないで……」
「さあ、そこをおどき」
ネフラは少しだけ強い調子で言った。
「最後に君を下敷きにしたくはないからね。さあ、言うことをお聞き!」
ぴしり、と大きな音が裂けた。
崩れていく。紫と翠の破片になって、崩れていく。葡萄なんてなかったみたいに。粉々になって。
オーロラは泣きながらバルコニーへと駆けだした。
その時の音を、忘れることなんてできない。
オーロラは泣きながら散らばった破片へと寄り添った。指が裂ける。血が流れる。赤で染まっていく。やめて。染まらないで。お願い。わたしにあの葡萄の色を返して。
オーロラは声をあげて泣いた。どうすることもできない。ネフラ。ネフラ。わたしはあなたを見捨てたのに、帰ってきてくれた。それなのに、わたしのせい で、壊してしまった。ごめんなさい。ごめんなさい。わたしのせいで。わたしが愚かだったばかりに。あなたは大人になるまでの辛抱だとあれだけ言っていたの に。わたしは囚われていたわけじゃなかった。守られていたのだ。この輝きに。
やがて、濃紺のコートに身を包んだ老婆が影のようにやってきて、オーロラを抱きしめた。
「心配することは無いよ。破片をいくつかかき集めておやり。万華鏡職人の、腕のいいやつを知っているよ。そいつの手を借りて、この破片を芽吹かせておやり」
オーロラは頷いた。血で濡れたドレスを着替える。簡素な水色のエプロンドレスに着替えて、そのエプロンに破片を乗せた。魔女はオーロラの傷を治してくれた。足元へ滴る血の止め方も、教えてくれた。
「さあ、お前はもう自由だよ」
「いいえ、お婆さん」
オーロラはぐすりと鼻を鳴らした。
「もっとずっと、不自由になってしまったわ」
「そうかい」
魔女は笑った。
魔女はオーロラを連れて外へと出る。
黄金色の煉瓦道が、家々の間を縫っていた。
オーロラのいた塔は、歪んだ不思議な建物だった。陽炎のようにゆらゆらと揺らめく。
魔女は右の腕をふわりとあげて、手首をかくりと下に降ろした。
たったそれだけで、それは音もなく崩れて、霞のように消えてしまった。残してきたシャンデリアの破片さえ、跡形もない。オーロラははっとして自分のエプロンを見つめた。そこには、確かに、消えることなく緑と紫の硝子が瞬いていた。
「それはもう消えやしないよ。私の手を離れてしまったからね」
「そうなの?」
オーロラは、まだ鼻の詰まった声で言って、鼻をぐすりと鳴らした。
「お婆さん」
「なんだい」
「わたしを守ってくれてありがとう」
目を擦ると、魔女はその手をそっと握って止めた。
「おやめ。破片が入ってしまったらどうするんだい」
「構わないわ……だって、」
「だってじゃないよ、馬鹿だねえ」
魔女はくすりと笑う。
二人で静かに煉瓦道を歩く。
魔女は、歩く先々で見えるものが何かを優しく説明してくれた。それを聞きながら、ぼんやりとオーロラは尋ねた。
「ねえ、お婆さん。もしかして、お婆さんがネフラだったの?」
「おや」
魔女は目を丸くした。
「これまた。どうしてそんなことを思うんだね?」
「だって……優しいんですもの」
「そうかい」
魔女は微笑んだ。
「いい線いっているよ。けれども不正解だ。答えは自分で見つけておやり」
「え?」
ふと、魔女の儚い声に胸騒ぎがして顔をあげた。
「おばあ、さん……」
「おや、もう限界だねえ」
ぱりぱり、という音がして、魔女の顔はますます皺を増やしていった。固くなって、めくれて――。
「オーロラ。この先をまっすぐお行き。何があってもよそ見はしてはいけないよ。ずっとずっと歩くんだよ。そうしたら、緑の屋根の、黄色い壁の、私の好みそ うな歪んだ家が見える。一つしかないから、間違えやしないよ。そこへと行くんだよ。そこに万華鏡作りの職人がいるからね。たしかに、教えたよ」
魔女の腕は枝分かれして、伸びていく。
「ほら、私の薬指を一本折るんだよ。――早く」
オーロラはまた泣いていた。どうしてこんなにやさしい人が、こんな姿に――大樹の姿になっているのかわからなくて、どうしたら助けられるのかもわからなくて、ただ泣くことしかできなかったのだ。
オーロラは嗚咽を漏らしながら、魔女の左の薬指を――細い枝をぽきりと折った。
「そうだ。いい子だね。それと、そのガラスの破片で万華鏡を作ってもらうんだよ。お前の大事な魔法が守れるからね。さあ、お行き。泣くんじゃないよ。私はね、もう助からない。さあ、早くお行き!」
オーロラは、魔女に触れて、そうして走った。泣きながら。振り返ることなく。震えながら。
「やれやれ」
魔女は一人、静かに呟く。
「随分と、してやられたものだよ。こんなにお膳立てしてやったんだ」
そう言って、一度だけぶるりと身を震わすと、魔女だった木は、風に枝を揺らすだけで、もう二度と言葉を話すことは無かった。
*
息が苦しい。胸が苦しい。
走れば走るほど、胸が張り裂けそうで。
硝子の欠片が零れ落ちてしまいそうで。なくしてしまいそうで。
けれど立ち止まってしまったら、もう動けなくなるのだろうとわかっていた。
オーロラは走り続けた。そうして、閑古鳥が鳴き始める黄昏の中。
ようやく彼女は、その家を見つけた。
「はぁ、はっ……、は……」
息を整える。
零れそうになる涙を、熱を抱える想いをぐっとこらえて、オーロラは木の扉をこんこんと叩いた。
「どうぞ」
どこかで聞いたことのあるような、けれど聞いたことのない、穏やかな、低い声が籠って聞こえた。
オーロラは扉を開ける。扉はぎい、と音を立てて、橙色の光を床に一筋照らした。
「あなたが……っ、万華鏡の職人さんですか……っ」
息を切らしながら、そう叫んだ。
橙ががった金の髪に、太陽のような黄色の目をした少年は、にっこりと笑った。
「はい、僕がそうですよ」
その微笑みを、見たことなんてあるはずがないのに、どこか懐かしいと思った。
「万華鏡を……どうか、作ってください」
オーロラの言葉が最後まで言い終わらないうちに、ふわりと彼女を影が包み込む。
ぱらぱらと、硝子の欠片が床へと零れて散らばる。
目元に優しいキスを落とされていた。
「はじめまして、オーロラ」
少年は、泣きそうな笑顔でそう言った。その柔らかくて低い声に、心が震えた気がした。
また、視界に影が落ちる。唇に柔らかいものが触れる。けれど、嫌ではなかった。
なぜだかとても、泣きたい気持ちになったのだ。次第に深くなっていくキスに、オーロラは縋りつくように彼にしがみついて、瞼を閉じた。涙がまた零れて頬に筋を残す。
涙の中に小さく、彼の左腕に葡萄柄の腕時計がはめられているのが見えた。
後編

その魔女は、キャベツを育てていた。
魔女や魔法使いは、己の眷属を作るため、その眷属の魔力の源となるような植物を育てることが多い。何故植物なのかと言えば、その定かな理由は今や彼らの 誰も知らないのだけれど、植物はかつて薬を作るための材料だったからではないかと考えられている。植物には魔力が宿りやすい。自我と本能を持つ動物より も、ずっと。
何故彼女がキャベツを育てていたのかと言えば、特にたいした理由ではないのだった。魔力が宿りやすそうだからとか、古来より呪術に用いられていた所以の あるものであったからとか、そんなもっともらしいものでは決してなかったのだ。強いて言えば、魔女はキャベツを、まるで翠の薔薇の花のようだと思ったの だ。魔女は本当はお花が大好きだった。けれど彼女は生来酷く恥ずかしがり屋だった。周りの少女達が可愛らしいもの、愛らしいものをこぞって身に付ける中、 自分のように愛らしくもなく、可愛くもない姿には、あんな可愛いものは似合わないと気後れしていたのだ。けれどキャベツは、女性らしくはないかもしれな い、それでも確かにその瑞々しさは美しく、テントウ虫が這うのを見ていると、魔女はたまらない気持ちになったのだ。
――そうだ、私はこの翠のお花を育てよう。
魔女はとにかく恥ずかしがり屋だった。いつだって顔を濃紺のフードで隠した。彼女は眷属を捜すことにも酷く苦労した。鴉、梟、蝙蝠、猫、兎、ヤモリ、魔 力が注ぎやすい動物はいくらでもいた。けれど彼女は、それらの動物が自分が近づくと途端に警戒するのを見る度に、心の枝がぱきりぱきりと小さく少しずつ折 れていってしまったのだ――本来、それらの生き物の警戒心は野生として重宝すべきものでもあるし、だからこそそれらは魔法使いの眷属に向いていたのだが。
結局彼女は、めそめそと泣いていた。やがて彼女の強すぎる魔法は、彼女の悲しみに追いずるようにして、少しずつ彼女のこじんまりとした可愛らしい家を歪 ませていった。輪郭の歪んだ家を見て、不思議と彼女はそれを可愛らしいと思った。他の人々はそれを奇妙だとかへんてこだと言うけれど、彼女はこれはこれで 素敵だと思ったのだ。
――そうだ、誰も使わないものを、眷属にしたらどうだろう。もっと私と仲良くなれそうな、優しい眷属を。
魔女は世界を彷徨った。色々な動物を見て回ったけれど、やはり彼女には向いていなかった。やがて彼女は、植物ならどうだろうと思い始めた。本来、キャベ ツを既に育てているのだから、それを媒介として別の植物を眷属にするだなんて、おかしな話なのだけれど。彼女は、心を持つのにふさわしい植物を探し続け た。
そうしていつしか彼女は、人間の国に迷い込んでしまっていた。魔法を使えず、魔法に怯える人間の国。
魔女はやはりそこでも傷つけられた。人々は心ない言葉を彼女に投げつけた。泣きながら頭を抱えて踞る魔女は、あるとき不思議なものを見たのだ。
小さな子供達が、魔女の姿や骸骨の姿、幽霊を模したのだろうか――白いお化けの姿、そんなお洒落をして、カボチャのランタンを抱えて歌いながら歩いている。
魔女は、生来小柄だった。今なら、あの子供達に紛れ込むことが出来るかもしれない。魔女はそっと彼らに近づいた。
「あの、もし」
「どうしたの? あなたも一緒に行く?」
「あ、あの……これは一体、何をしているんだい?」
聞かれた少女はきょとん、と目を瞬かせた。口が裂けたような化粧をしている。
「ええ? そんな格好をしてるのに知らないの? これはね、お化けの振りをして、大人達から大事なものを奪ってやる子供だけのお祭りなのよ! お菓子をく れなきゃいたずらするぞーって言ったら、大人達が怯えてお菓子をくれるのよ! 一年に一回だけ、子供が一番強く怖くなるの!」
魔女は、あっけにとられながら、少女が抱えているカボチャを見つめた。三角の目、角張ったギザギザの牙のような口――そう見えるように、くりぬいてあるのだ。その空洞が、蝋燭の炎を映し出して金色に輝いている。
「それは、なんだい?」
「これはね! 悪いことばかりして天国にも地獄にも行けなくなった罪人が、せめて道に迷わないように蕪をくりぬいてランタンを作ったって言う話があるのよ。それを真似してるの。私達、今わるーい人なんだから!」
「そ、そうなんだね……でも、そのお話だと蕪なんだろう? どうしてあなたはカボチャを持っているんだい?」
「この国は蕪があまり生えていないの。遠い国のお話なのよ。それで、カボチャになったの。でも素敵でしょう? オレンジの光は悪戯するぞーっ!って感じでわくわくしちゃう」
魔女はカボチャをじっと見つめていた。顔がくりぬいてあるからかもしれない。生命の灯火が与えられているからかもしれない。けれど魔女には、それがこの一時だけだったとしても、心のようなものを持っているように見えたのだった。
*
カボチャの種を抱えて、魔女は帰途についた。
家にたどり着いて真っ先に始めたのは、カボチャを一から作ることだった。魔法のカボチャを作らなければならない。やがて育ったカボチャは中身をくりぬい て、葡萄酒を並々と注いだ。そうして二年間待つのだ。葡萄酒に魔力を注ぎながら。葡萄色の湖面に、契ったキャベツの葉を散らして浮かべながら。
そうして、魔女が初めて作り出した眷属は、カボチャ頭のよく喋る女の子だった――あの日出会った少女の印象が、強かったのかもしれない。
ワインの葡萄色が滲んだ青いカボチャは、まるでゾイサイトの宝石のように輝いて見えた。魔女は彼女にゾイサイトと名付けたけれど、彼女は少しだけその名前の響きを嫌がった。結局、魔女は彼女を「イト」と呼ぶことにした。
けれどゾイサイトは長くは保たなかった。元々生き物でないものに心を保たせるのは非常に難しかったのだ。魔女はその後もカボチャの眷属を作り続けた。頭 だけだったものに、藁や木で案山子のような体を作ってあげた。アレキサンドライト、ペツォッタイト、ストロマトライト、アイオライト、コンドライト、アズ ライト、カイヤナイト、アンモナイト、スギライト、クンツァイト……気が遠くなる程の眷属を作っていった。全ての彼らを「イト」と呼べるように。彼女は途 中から、もう狂いかけていたのかもしれない。
そうして彼女が最後に作ったカボチャは、青いままに葡萄酒を注ぎ込んだというのに、熟したカボチャの橙を明るく輝かせていた。
「こんにちは」
「こんにちは。お前は女の子かね、男の子かね」
「男の子のつもりだよ」
「おや」
魔女は目をぱちくりさせた。
「今までの子供達は、断定するか、どっちでもいいよと言ったものだけれどねえ。お前は変わった答えを持っているのねえ」
「ねえ、魔女のお母さん」
「お母さんという年ではないよ。ほらご覧。もう、こんなにしわくちゃだ。私が作ることの出来る眷属も、お前で仕舞いかねえ」
魔女はしわがれた声で穏やかに笑った。
「わかったよ、じゃあ僕の魔女。あなたはあの子をどうするつもりなの?」
カボチャは言った。魔女はその声の届く先を顧みる。
金色の髪をわずかに逆立てた、まだ小さい赤子が、木で出来たベッドに横になっていた。
「お前はあの子のことをわかっているのかい?」
「もちろんだよ、僕の魔女。僕は生まれた時から、あの子のお父さんが僕のキャベツを捥ぎに来たことも、それをあの子の母親が食べてしまったことも、知っているんだもの。失礼な話だよね。あのキャベツは僕の一部だったのに。おかげで僕は腕が捥がれたような心地がしたよ」
どこかぞわりと身震いするように、小さな声でカボチャは言った。
「もう二度と、僕の魔力をむしゃむしゃ食べられたくないなあ」
「お前の魔力ではなくて、私の魔力だからね、ぼうや。まあ、ほとんど変わらないがね」
魔女は不思議な気持ちでカボチャを眺めた。
「お前は、どうも今までの子と違うみたいだねえ」
「当たり前だよ、僕の魔女。僕の魔力があの赤ん坊とつながってしまったんだ。あの赤ん坊は僕の――あなたの魔力を僕から吸い取る代わりに、僕に人間のもつ 心や本能を与えてしまっているんだよ。おかげで僕は、他の兄弟みたいな強い魔法を使えなさそうだ……不思議だね、まるで、僕が媒介となってあの赤ん坊があ なたの真の眷属になってしまったみたいだもの」
「そんなこともあるものだねえ」
魔女は溜め息をついた。
「あの子は人間だからね、私の魔力があの子の命を蝕んでしまっているのさ。今あの子が生きているのは私の魔力があの子に注がれ続けているからさ。けれどあ の子の体は魔力の扱い方を知らない。人間だからね。このままではあの子は魔力を垂れ流し続けてしまう。留めておくことが出来ないんだよ。私がまだ生きてい られるのならそれでもよかったがね。私はあと数年もしないうちに木になってしまうだろう。だから、あの子が大人になるまで、魔力をせき止めることの出来る 小さな部屋に閉じ込めておくさ。可哀想だがね」
「大人になるには、どうするの?」
カボチャは少女のような可愛らしい声で尋ねた。魔女は少しだけ微笑んだ。
「あの子が女の子だったのが救いだよ。女の子はね、いつか血を流すようになるのさ。その血があの子の救いになるよ。血を流すようになった時が、あの子の体が魔力を扱えるようになったという証拠なのさ」
「ふうん」
カボチャは言った。
「ねえ、僕の魔女。それまであの子を見守っていてもいいかな?」
「そんなに気になるかい?」
「一人はきっと淋しいよ」
「そうだねえ」
魔女は笑った。寂しげに。
「あなたも……だから眷属を作ったんでしょう。作り続けたんでしょう」
「そうかもしれないねえ。今となってはもう、よくわからないねえ。もう少し早く出会っていたらよかったんだがねえ……。私はもうしわくちゃの枯れ木のようで、あの子に見せられるような姿でもないよ」
魔女は静かに自分の腕を撫でた。
「それじゃあ、あの子の暮らす家の灯りを、葡萄の形にしてあげよう。そうすればお前は、お前の空洞を満たすその葡萄酒を通じてあの子を見ていられるよ。た だし、そうなるとお前はその葡萄酒を零すことが出来ない。お前は兄弟のように動くことが出来なくなるんだ。そうやって、水瓶のようにそこにじっとしたまま だよ。それでもいいんだね」
「構わないよ」
カボチャは言った。
「それじゃあ、お前にも名前を付けてあげようかねえ。不思議だねえ、お前は橙色だから、そう言う宝石の名前を付けてあげよう」
「僕の魔女」
カボチャは思い詰めたように言った。
「葡萄酒の色で構わないよ。他の兄弟と同じ色で構わないんだ。だから、僕だけの大切な名前を付けて」
「そうかい」
魔女はにっこりと笑った。
「それじゃあ、キャベツのような色の宝石の名前を付けてあげよう。ネフライト。お前は今日からネフライトだよ。いつか最後の眷属につけてやろうととっておいたのさ」
魔女の声はどこか嬉しそうに、弾んでいる。
「そう……ありがとう、僕の魔女」
ネフライトは柔らかく言った。
「そう……僕のこともやっぱり、【イト】と呼びたいんだね。あなたは、最後まで、そうだったんだね……」
ネフライトは、耳の遠くなった魔女には聞こえないような小さな声で、そう呟いた。
*
オーロラに、思い切って話しかけた日。
彼女は怖がるのではないかと、内心恐ろしかった。
けれど彼女は拍子抜けする程にあっさりとネフライトの声を信じた。
「シャンデリアなんだから名前なんてないわね? わたしがつけてもいい?」
無邪気に笑う声。
僕はその時無性に、彼女に僕だけの名前を付けてもらいたくなった。けれど彼女の呟いた言葉は、ネフライトという、僕そのものの名前だった。
こんなにも、落ち込むという気持ちが自分にあったなんて、知らなかった。やっぱりこの少女は、あの魔女と同じなのだろうかと思ったのだ。魔力の質が同じだから。それはつまり、同じ存在であるということに等しいのだから。
まあ、後で考えれば、あの魔女はオーロラに自分の趣味の宝石の本を沢山置いてやっていたのだから、彼女の好みが似通ってしまうこともさもありなんだったのだけれど。
けれど彼女は、僕のことを【イト】ではなく【ネフラ】と呼んだ。
それだけのことが、僕はどうしようもなく嬉しかった。
泣きたくなるくらいに寂しい気持ちというのを、ようやく僕は知ったのだ。
だから僕は、僕だけがきっと、あの魔女の心を、孤独を理解出来るたった一人の眷属だったのだけれど。
僕はいつしか、あの少女に。
僕の魔法を奪っていった女の子に、恋をしていた。
ただのカボチャだったのに。
*
「僕の魔女、お願いだよ。一生のお願いだよ。僕に、人の体を頂戴。お願いだよ。あなたと同じ姿に、あの子と同じ姿を頂戴」
僕は、擦れた声で、うまく繋がらない声で、魔女に懇願していた。
魔女は、いつものように目をぱちくりさせる。
「そう言えば、そんなことを願ったカボチャは今まで一人もいやしなかったねえ」
「ねえ、悪くない願いでしょう?」
「そうだねえ。そうだねえ……どうしてもっと早くに、思いつかなかったんだろうねえ」
魔女はどこかぼうっとしたような声で言った。
「眷属が人の姿であってはならないなんて、だぁれも言っていなかったのにねえ。私も、まだまだ未熟だったねえ」
「あなたはいつまでも未熟だよ。そしてきっと、可愛らしい女の子だよ」
「まあ、嬉しいねえ」
魔女は笑った。
「いいだろう。私の寿命はちと縮んでしまうけれど、そうしてあげるよ」
僕は、魔女の命を犠牲にした。
*
生き物でないものが、生き物の体を持つ。
それがこんなにも苦しく、痛みに苛まれるものだと知った。
僕は苦しくて苦しくて、ずっとうめき続けていた。だからオーロラと話すことが出来なかった。
そうしているうちにようやく僕の人の体は僕になじんで、僕は楽になったのだけれど、
今更話しかけるタイミングも見失ってしまって、僕はただ毎日静かに、僕の抜け殻――ただのカボチャの器に注がれた葡萄酒の湖面を見つめて、オーロラを、見守った。
やがて僕の声は、まるで老人のようにがらがらと擦れてしわがれた。それは僕にとって恐怖だった。
「僕の魔女……僕の魔女……! 声が……、僕の、声が」
「おや」
けれど魔女は、いつものように目をぱちくりと見開いただけだった。
「お前、それは声変わりをしようとしているんだよ。お前はちゃんと人間になれたんだねえ。よかったねえ」
魔女はそう言って、嬉しそうに笑った。
*
「あの子はなかなか大人にならないねえ。もう、私はもたないかもしれないよ」
ある時、魔女はそう呟いた。
「私が木になってしまった時は、お前があの子を迎えにいっておやり」
魔女は穏やかに微笑んだ。
「大丈夫さ。お前もあの子も魔法使いにはなれないが、万華鏡の作り方を教えてやったろう? それは私の姉が作った魔法だったのさ。私には才能がなかったが ね、お前は私と違って器用なようだから、それで生計を立てるといい。魔法の万華鏡は美しいから、みんながきっと欲しがるよ」
「うん……」
僕は、魔女のつてでいくつか頼まれた万華鏡を作りながら、そう小さく頷くことしか出来なかった。
*
そして僕は、ただ少しの魔法しか使えなかった僕は、とうとう魔法を使えなくなってしまったのだった。
オーロラが身も知らない男に襲われているのを見て、僕はどうしようもない程の怒りに苛まれた。
どうにかして助けたい。助けたい。傷つけてやりたい。めちゃくちゃにしてやりたい。助けなきゃ、助けなきゃ。届かない。届かない。僕の手が、届かない。声が、声を、この擦れた声があの子を怯えさせたらどうしよう。でも。どうしよう。助けなきゃ。離れろ。その子から――。
気がついた時には、僕の抜け殻が――カボチャの器が、弾けて粉々になっていた。
床に零れる葡萄酒に、ノイズが混ざったように、まだかろうじてオーロラが映っている。
僕は、僕の魔法が届いたのだということを理解した。そうして、同時に僕は、僕が魔法を使う媒介を永遠に失ってしまったのだと理解した。
カボチャを失ってしまったら、葡萄酒を浸せない。
魔女の魔力が僕に注がれる路を、永遠につぶしてしまった。
カボチャは他にもあるけれど、それはもう僕ではないのだ。
ああ、僕はもう、用済みだろうか。それともせめて、あの子と同じ人間として生きることくらいは赦されるだろうか。
ああ、でも、僕は、
唯一の特技であった万華鏡さえ、もう作ることが出来ない。
魔法の籠らない万華鏡の作り方なんて、知らないのに。
あの子を、支えてあげることが出来ない。
*
「馬鹿だねえ、お前は」
魔女は怒らなかった。
そして、また新しい眷属を作ろうともしなかった。
それだけで、僕はもう満足だった。
僕は、僕の弟や妹になるかもしれなかった小さなカボチャ達を撫でる。
「私は行くけれど、お前、キャベツとカボチャの世話を忘れないでおくれよ。枯らさないでやっておくれ」
「はい、僕の魔女」
僕は涙をこらえた。
「ごめんなさい、僕のせいで」
「構わないよ」
魔女はくすりと笑った。
年を取っているのに、いつまでも愛らしい魔女。あなたは自分を可愛くないと思っていたけれど、僕はあなたのことをとても可愛らしい人だと思っていた。
「安心おし。お前が魔法を使えなくても、あの子の魔力を使えばお前はまた万華鏡を作ることができるよ。見るものの心を、素敵な夢や思い出へと誘う、魔法の万華鏡をね。お前はまだ生きていけるよ」
そう言って、魔女はふわりと濃紺のコートをはためかせて、扉を閉めて、出て行った。
「さようなら、僕の魔女」
僕は結局涙を堪えることが出来なくて、
キャベツを一つ剥きながら泣いたのだった。
僕の名前をくれた大切な人を、迎えるために。
葡萄色のシャンデリア
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
本編はこのままの形で、変更の予定はありません。ですが、いくつか補足していた方が物語を楽しめるかなと思い、その後の二人について、簡単に解説したい と思います。ネタバレになってしまいますので、余韻をそのままにしておきたい方、二人の未来を自由に想像したい方はご注意ください。
***
あの後、オーロラとネフライトは二人で支え合って生きていきます。しばらくはオーロラの魔力を使ってネフライトが万華鏡を作ることで生計を立てていきま す(オーロラとネフライトは魔力がリンクしているので、ネフライト自身はもう魔法を使えないのですが、オーロラの魔力を使えば可能です)。ネフライトが オーロラを養ってあげる感じですね。
オーロラは、体は大人への一歩を踏み出したとは言えまだまだ子供ですので、オーロラよりは精神的に大人びた、けれど同じようにまだ子供であるネフライト と一緒に成長していきます。ネフライトが自分の稼ぎでオーロラに魔法の先生をつけてあげるので、やがてオーロラは人間としては初めての、魔女となることに なります。
もちろん、魔族でない人間が魔女になるということはそれなりのリスクも障害もあり、二人は色々と苦労することになります(そのため、魔女のお婆さんはお そらくオーロラは魔女にはなれないだろうと思っていたわけなのですが、二人は頑張りました。大好きだった魔女のお婆さんの跡を継ぐために。証を残すため に。)が、オーロラは立派な魔女になり、素敵な女性に成長します。
とはいえ、やはりただの人間の体に魔力を溜め込むのは相当な負担であり、オーロラは人間としては若くして(おそらく四十歳くらいだと思います)静かに亡くなります。もちろん、彼女を看取り、お墓を建ててあげるのもネフライトです。
ネフライト自身の体も、オーロラの死後まもなく動かなくなるでしょう。ネフライトは、魔女のお婆さんから、そして彼女亡き後はオーロラから魔力を注がれることによって生きた作り物の命だったので、魔力の供給が亡くなってしまうともう生きてはいかれないのです。
二人の関係は、人間と、人間の体を持つ人間ではない何かの恋でした。穏やかな恋を育んでいったと思います。
「葡萄色のシャンデリア」。これは、魔女のお婆さんとネフライトの願いが込められています。オーロラの物語と見せかけて、実は彼女を守り支えた二人の影が主人公の物語でした。ずっと書きたかった物語でしたので、こうして書けて嬉しいです。
それでは、ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
P.S. 魔女は恥ずかしがり屋なのでデザインがありません。ご了承ください。


