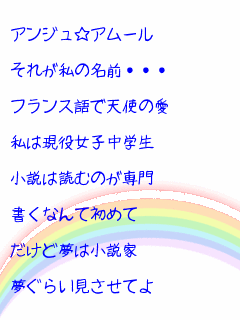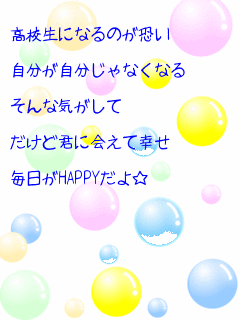
母性本能を失った母親の子
あの日あの朝あの空の下で私達は出会った。
全ての物が美しく見える入学式の日に。
何故か君と私は見つめあっていた・・・
1章
遅れることを承知で家を出発した入学式。
正直、行きたくなんかなかった。
高校生になるのが怖かった・・・
いつまでも中学生のままでいたい。
それが私の本性。
だけど世間はそれを許してはくれない。
親も友達も先生も・・・
わざと寝坊をした今朝。
台所には誰もいない。
きっと、今日が入学式だとは知らないだろう。
だって、言っていないのだから。
いつも通り、テーブルの上にラップのかかった目玉焼きと1000円札が置いてあった。
「10時までには帰ります。」というメモ書きと一緒に。
「バッカみたい。」
誰もいないのにそっと小声で呟いてみた。
誰かが聞いてくれてると思いながら。
でも、子供の噓に気づかない親もおかしいと思う。
私に関心がない証拠だ。
自分たちで調べれば良いのに。
そんなことを何度も思った。
小学校のときも中学校のときも、私の親だけ卒業式に来なかった。
でも、入学式には絶対に来てくれた。
だからかもしれない・・・
今日も心のどこかで親が来てくれる事を願っていたのかもしれない。
「ハァー。」
そう小さなため息をついてから目玉焼きを温めて食べる。
時刻は朝の8時。
入学式は8時30分から始まる。
今から急いだって間に合わない。
「このまま学校に行きたくないなー。」
また独り言。
だけど現実は甘く無い。
8時30分の集合時間を15分くらい過ぎた後、家の電話が鳴った。
見知らぬ番号だった。
「もしもし。」
電話をとってみる。
「あっ、もしもし。森井さんのお宅ですか?」
「そうですけど、どちら様ですか?」
名前を名乗らない相手に対して少しいらつく私。
「申し遅れました。私、桜坂南高校の佐々木と申します。お宅の彩音さんが登校されていないのでお電話させてもらいました。」
「彩音は私ですけど。」
意地悪で答えてみた。
「そうですか?!もう入学式が始まるので早く登校してくださいね。では。」
ふーん。
相手が子供だって分かったらあんなに素っ気ないんだ。
でも、電話がかかった以上登校しなければいけない。
私は異常に短いスカートを履いてゆっくりと身支度を始めた。
2章
桜並木がある坂を上りながら考えてみる。
今から高校生になるのだと。
本当は急いでいくべきかもしれない。
だけど、わざとゆっくりと歩く。
入学式なんかに出る気は全くない。
一体、教師たちは私を入学式に呼んでなにをしたいのだろう。
きっと、たてまえだ。
私が入学早々学校をサボると教師たちの立場が危ういのだ。
私は人を困らせることが大好きだ。
だから遠回りをして学校に行く。
まだ、学校に行くだけでも偉い方だ。
ー森井彩音ー
それが私の名前。
一人っ子で昔から生意気な性格。親友と呼べる友達は一切いない。
それどころか、知人から友達へと発展したことすらない。
もちろん恋愛経験は0で彼氏なんかいない。
今後つくる予定もないし、欲しいとも思わない。
だけど自分の容姿には満足している。
整った瞳と鼻。
ぷっくりと膨らんだ小さな桃色の唇。
グロスなんか必要ないほどだ。
スカウトされた回数は13回。
街を歩くと必ずしも皆振り返る。スカウトマンが目につけない訳が無い。
もちろん全て断っているが。
なんだかんだ言って、学校まであと5分の地点に来た。
だけど足が進まない・・・
なぜなら、その景色が今までに見たこともないほど美しかったから。
桜の花が満開で風で散っている。
傾斜13度ぐらいの坂道。
そこにズラッと並んだ桜並木。
私が入学する桜坂南高校の校名の由来が少し分かったような気がした。
こんな景色が見える高校があと3校もあると思ったら学校生活も悪く無いと思った。
今まで重かった足が少し軽くなった・・・
3章
スキップをしながら桜坂道を登った。
目の前には「入学式」という立て札のかかった正門。
あと一歩で高校の地に足をいれることが出来る。
だけど、その「あと一歩」が私には踏み入れることができなかった。
周りに誰か人がいたら「変な子」と思われたことだろう。
「クック。」
小さな笑い声が聞こえた。
私は気になって後ろに振り返ってみると桜の木にもたれかかった1人の青年がいた。
「なにやってんの?」
笑いながら青年が言った。
「なんだっていいでしょ。」
私は回れ右をして校内に入ろうとした。だれど、やっぱりできなかった。
青年は桜の木から離れようとはしない。
静かに目を閉じて最近発売されたばかりの文庫本を手に持っていた。
私は彼のその美しさに何故か見とれてしまった。。。
長いまつ毛、細い腕、柔らかそうな栗色の髪。
全てが美しかった。
私なんかよりもずっと。。。
さっき私のことをからかった人には見えない。
もしかしたら、さっきの出来事は夢だったのかもしれない。
そう思った時。
「なに、俺にみとれちゃってるの?」
青年の瞳がゆっくりと開き、笑いながら言ってきた。
「見とれてなんかないし。」
私は噓を言った。
顔を赤くしながら。
「あんたこそなにやってるの?そんなところで。」
「同じことを君に聞くよ。」
ムカっとくる返事だった。
「絶対に言わない。」
「ま、言わなくても分かるけど。俺と同じだから。」
「はっ!?」
意味不明な言葉に私は耳を疑った。
「あんたも高校生になるのが恐いの?」
思わず聞き返してしまった。
「ふーん。君は高校生になるのが恐いんだ。」
騙された。
彼の思い通りに私はなってしまったのだ。
「それに俺、君の先輩だけど。」
思いがけない返事だった。
だって、彼が着ている制服は真新しいし制服もブカブカだった。
母性本能を失った母親の子
生まれて初めての小説でしたがいかがでしたか?
文章も滅茶苦茶で読みにくかったことと思います。
本当にここまで読んでいただいてありがとうございました!