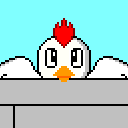
アレが見えるの(その七)
その七 生け贄
日曜日の来るのが怖かった。
御影と敦子のひそひそ話を聞いてしまってからの僕は、心の中で社会的常識と暗愚な慄きとの戦いを繰り返しながら日を送った感がある。
いや、言葉のとおり真に受けて、(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル してたんじゃないぞ。
「生け贄」が言葉のあやだってことはなんとなくわかる。それは察せられる。
いくらなんでも言葉通りであるはずがない。そうだったら僕の身が危ないし。
でも……。
二人のあの口ぶり。「生け贄」という言葉をやり取りするときの、いかにもという感じで声をひそめ聞かれるのをはばかる様子(しっかり聞こえたけど)。
儀式……生け贄の儀式……入団者の生け贄の儀式。
「生け贄」という言葉から連想できるあらゆる事案が懸念された。
『ハムナプトラ』、『アポカリプト』、『インディ・ジョーンズ魔宮の伝説』……それまで見た映画のさまざまな流血場面が脳裏に去来する。
大丈夫だろうな、まさか大丈夫だろうな。
21世紀だし、日本だし、市街地でのことだし、現実だし……。
しかも入団の儀式があるのは昼前だ。小さな子を含む信者の面々が揃ったあの礼拝所で、笑い出すのをこらえて苦しむことはあっても、ホラー映画のようなおぞましい出来事が待ち受けてるわけがない。
よもや我が身がバーベキューの具材になるとかゾンビ化した会衆に囲まれ、生きながら食われるとか、ひそかに案じるような事態がこの身に起こりはしないよな。そういうのって劇画の中だけだろ。
かくたる次第で、日曜日が来るのを人生でこれほど恐れたことはない。
それでも出かけるとは我ながらどうしたもんだろう。
僕は朝十時の礼拝に間に合うよう身支度を整えた。支部長は念入りに身を清めてくるよう言ったっけ。その通りに、朝シャワーを浴びてリフレッシュすると、大人びた感じに髪を撫でつけ、ネクタイを締め、スーツを着込み、自分なりに正装した姿になった。
階下に下りていくと、母が即座に反応した。
「あら、デート?」
「なんでそう言う、お母さん?」
「その服装とおまえの顔。女の子と大事な約束があると見た」
母はなにか誤解してる。でも本当のことは明かせないし、勝手にそう思ってくれるなら好都合だ。しかも違った意味で効能があった。
「お小遣い、足りてる? 臨時のボーナスあげようか?」
いや、くれるというならもらっとくけど。
あれ、一万円も? いいの?
母は楽しんでらっしゃいという感じでウインクしてみせた。
この母親、善良だが、息子の苦悩がわかってない。
表に出ると、いつもの環境があった。
まばゆい光に包まれた日曜朝の住宅地、静けさのうちに喧騒を予兆させる空気に身をさらし、平穏な景色の一部として溶け込んだ自分を感じながら道を行く。
デートに行くのか他の用事なのか、すれ違う女の子たちがみんなお洒落をし、それぞれ魅力的に見える。
「おはよう」と呼びかけると向こうも、「おはよう」と返したり会釈したりで好意的に反応する。それがまた、理不尽な思いをいや増しさせた。
なぜ、あの娘たちのうち一人でも傍らにいないのだろう。それは雑作もない、きわめて自然なことなのに。
なんて気の重さだ。
この素晴らしい日曜日、デートに出かけるのがふさわしい服装でカルト教団の入信の儀式に出席って……。
まったく、やるせない思い。それも、待ち受ける「生け贄の儀式」が何なのかに怯えながら。教団支部に行けば行ったで、御影からそっぽを向いて迎えられるんだ。
ああ、神様。いや、ダラネーナ教の神じゃなくて。
それにしても、黒石御影。
家の中ではよくしゃべった。全然おとなしくない。活発に動き回る。そして我がままなくらい、臆面もなく自分を主張する。
御影の友だちで教団員の志摩敦子から聞いた、狂信に染まった家庭で虐げられる、愛に恵まれない少女というイメージは崩れてしまった。
言ったことと実際とがぜんぜん乖離してるじゃないか。
それでも、敦子の話は根底では正しく、御影のおかれた状況を的確に捉えてるかもしれない。
御影が日頃から、自宅であんな風に性格をあらわにするからといって、彼女がまた学校に行けば、みんなに知られるとおりの寡黙で引っ込み思案な少女のイメージを通し続けるだろう。
これは、自分を偽ったとか別人を演じてるというのとは違う。
三田のおねえさんの心理学講義によれば、厳しい締め付けを課されて育った家の子にはありがちなんだそうだ。
つまり家の中で無意識のうちに感じる圧迫を外側に投影し、本来は自分の家族に対してもつべき認識を世の中に向けることになる。そうすると、巷の人々が自分に悪意を抱いてると感じるのだ。だから自分の家から一歩出れば、敵意と危険が満ちた世界に身をおくような、臆病な態度で警戒的に振る舞うという。
しかもおねえさんによれば、これは特別なものじゃなく、どんな人でも多かれ少なかれ持ってる性向だという。
むずかしいこと書いちゃったかな?
ようするに黒石御影というのは、彼女の家があのままであるかぎり彼女もまたあのままで、家の外で本来の自分をさらし屈託なく振舞うようにはならないってことだ。
さて。
電車に乗り、大野小町の駅から歩く。
妙なもので、この教団支部への往路に関しては妨害を受けそうな気がしないし、現に何も起こらなかった。
日曜日ということもあり、道中で、数え切れないほどの女の子や女の子と一緒に歩く男どもとすれ違い、そのたびに一種独特の胸の痛さと癪な思いを味わいはしたが。
さあ、目的地に着いたぞ。
聖ダラネーナ協会(「教会」じゃない)大野小町一丁目楽園通り支局。
どう見ても、さびれた商店街の店舗が分不相応に背伸び、カルト宗の聖殿を気取っただけの建物だ。通行人の一人として好奇のまなざしを注ぎつつ通り過ぎるのがふさわしい。それがまさか、自分にとって馴染みの場所になるなんて。
チン、コーン。
「守屋護です」
「あ、守屋くんね。どうぞ、入って」
礼拝室には黒石夫妻の他、何人かの信者がすでに来ており、到着した僕を親愛の念をこめて迎えてくれた。仲間として見られるようになったのはあきらかだ。御影の姿は見えないが、志摩敦子がいた。
心なしか、お洒落してきたように感じる。華やいだ色のワンピースに、ポニーテールをリボンで結わえ、可愛く見せようとしてる。
なにより僕への接し方が積極的だ。当たり前のように、僕の隣りに寄ってきて腰かけるし、香水の匂いもこの前と違う。
聞けば、母親より一時間早く来て、礼拝室の掃除やお昼の会食の下準備を手伝ってたという。
「わからないもんね」
敦子は誰に言うともない調子で、ごちた。
「守屋くんが入信だなんて、先週の日曜には思いもしなかった」
そうだろう、そうだろう。僕もだよ。
まったく、この一週間で人生は急転回した。学校では疫病神扱い、そのうえ登校もできない有様だ。ネットでは日本中から叩かれてる感じで、味方がない。そして最愛のおねえさんが食中毒で入院する身なのに見舞いにも行けない。
もとをたどれば、黒石御影という風変わりな同級生のせいで。
その御影は思ったとおり、奥に引っ込んでる様子だ。いよいよ午前の礼拝が始まるまで出てこない気で満々なんだろう。
十時になり、日曜礼拝が始まった。
今度は御影は、時間通りにあらわれた。
その姿に、ハッと息を呑んだ。
盛装している。インドのサリーと神道の巫女の装束を混交させたような、なんとも名状しようがない、しかし美しい長衣。教団の儀式で特別な役割を受け持つ者が身にまとうものらしい。
それでも御影にはよく似合うというか、自分のものとして着こなしていた。髪もそれらしく束ねてるが、まるで違和感がない。女子学生の姿で教室の片隅にいるよりよほどさまになる。
学校などでみせる態度を知ってても、まったく別の美貌の少女として愛しさを感じそうなほどだ。敦子によれば、「御影ちゃんに憧れて入団してくる人が結構いる」らしいのだが、同意したくなる。
だが御影ときたら、例によってこちらの居場所を確認しただけで、あとは見向きもしない。
祈祷のやり方は前とおなじ。ただ、いっそう賑やかだ。平日の夕方礼拝の時よりずっと人が多く、老若男女あわせて五十人くらいいる。ここの教団支部に属するほとんどの信者が揃ったようだ。しかも、ちゃんとした服装で来てる。
カーン、カーン、カーン!
「七難ボジャイ、八苦ダラネーナ!!」
「何とぞ我らから七難八苦を退け、九死に一命を授けたまえ!!」
チーン! ポコッ!
誰もが真剣に祈祷を朗誦する厳粛な熱気の中、吹き出すまいとする努力、その苦しさを理解してくれたのは傍らの敦子だけだった。
絶対に粗相は許されない。ちょっとでも笑ったりしたら信仰の度合いを疑われてしまう。
今日は重大な日。この僕の入団審査の日なのだ。
祈祷が終わり、黒石支部長のボジャイ様や教団支部にまつわる近況報告が続いた。
そして、いよいよ――。
「さあ、皆さん。この時、わたしたちに救いの傘を差し伸べ、加護してくださるボジャイ様への感謝の印に、生け贄を捧げましょう」
生け贄……。
そら、きた。
ついに「生け贄」という言葉が、現実に、支部長の口から、衆目の前で発せられたぞ。
ところが誰も動じない。それどころか人々は黒石氏の音戸に合わせ、教団聖歌のひとつ『生け贄の歌』を唱和し始めたのだ。
あ~あ~あ
大切だから捧げます
失くしたくない 離したくない 別れたくない 奪られたくない
命のように大切なもの
生け贄として捧げます
ボジャイ様、どうぞお召しを
わたしとよりもあなたとあれば、価値も命も永遠(とこしえ)に
あ~あ~あ
僕は不安げな面持ちで(敦子があとで、そう見えたと言った)周囲を見まわしたが、狂信的な熱気や殺気などヤバさはすこしも感じられない。いるのは従順でおとなしく、慎み深い人ばかりだ。
でもみんな、ふところやカバンからあるものを取り出してる。
僕は目を見張った。
人の顔だ。人の顔が見える。誰もが見覚えある、あの人の顔を手にしてる。
福沢諭吉。
ほとんどの人が一万円札を出して握ってるのだ。
人々は手にもった紙幣を、人伝いに回ってきた募金箱のようなものに収めていく。これがつまり、ボジャイ様に「生け贄」を捧げる儀式。
「生け贄」って……何のことはない、教団への献金のことだった。
敦子の話だと、大昔は山羊など家畜をダラネーナ神への貢ぎ物に捧げ、神殿で生け贄として捌いたが、いまでは社会事情にふさわしく現金を供出するようになったのだという。
「生け贄っていうから何事かと思ったけど、教団への献金のことなんだ」
「ふふ……そうよ。何だと思った?」
「いや……祭壇の前で誰かを縛りつけて、心臓くり抜いちゃうとか……」
敦子はしなを作るように笑った。愛らしく見える笑い方を鏡の前で研究し、実践してる感じだ。
「あり得ないでしょ。いくらなんでもね、うふふふ……」
志摩敦子については噂がある。
あいつはもう処女じゃない。火遊びが大好きで、迫れば拒まずやらせてくれる、というのだ。
電車の中でも、わざわざ満員の車輌で痴漢を待ち受けてるとか、嫌がらずに触らせてる場面が何度も目撃されたという。
そうした噂に照らしてみると、いまの敦子の態度はさもありなん、という気にさせられる。純潔とか貞操という観念は、ダラネーナ教の戒律にないのかもしれない。
敦子は僕の傍らで体と体が触れ合っても、平気のようだった。
今も、短めのスカートから伸びた、肉付きよくやわらかそうな光沢の太ももが、どうかすると僕の脚と密着したりするが、そういう状態でも離れようとしない。広からぬ礼拝室に何十人もが詰め込まれた状況とはいえ、脚くらい離そうと思えば離せるのに。
いや。僕のほうでも、ぷりぷりまろまろした感触があまりに快くて、自分から離す気もしなかったけど。こういうのは童貞少年にとっては大変な事件だ。
そんな次第で、厳粛な「生け贄の儀式」の最中なのに、僕の頭は隣りの敦子の太ももの感触で占められ通し、ところが敦子はといえば何事もないという風に前方に固定させた目線を動かさない。頭の中でも別のことを考えてる様子だ。
「実はね、最近、呼び方が変わったの。以前は、生け贄、生け贄って、みんな平気で言ってた。だけどやっぱり、聞こえが悪いから」
そりゃそうだ(太もも……)。聞こえが良いわけがない(太もも……)。
「生け贄、なんて聞いただけで引いちゃって来なくなる人、結構いるのよ。だから誤解されないよう、なるべく教団外の人や入信したばかりの人には生け贄の儀式があるなんて言わないようにしてるのね。守屋くんにも黙ってたわけ」
なるほど(太もも……)、そういうことか(太もも……)。
ああ、太ももばかりで話が進まない。とにかく敦子によれば、信者は給料や年金のうちだいたい十分の一を教団に納めるのが定めらしい。月収二十万の人なら相場は月二万円、生け贄の日は月二回、第二日曜と第四日曜なので、一万円ずつ献上するわけだ。他に、ボーナスが出たときも相応の額を貢ぐ決まりだ。
ちなみに、未成年者や学生は「生け贄」を免除されるという。
そうやって各地の教団支部で集めた「生け贄」のうち半分が支部での取り分として運営や布教のため使われ(実際はほとんど、支部長宅の生活費に化ける)、あと半分は教団本部が徴収する。ざっとした計算でも、年に数千万円がボジャイ様の懐に入る勘定だ。
これじゃ、教祖様はやめられないや!
ボジャイ様ほどでなくても、富裕者の多い地域に展開し信者数も百人を超える別の支局では、支部長一家の暮らしぶりはなかなかのものらしい。
やはり敦子の話だが、若い信者の親睦会で裕福な地区にある支部に行ったとき、建物があんまり立派で、貧乏信者しか集まらないこの大野小町支局とのあまりの違いに呆然としたという。
さて。
僕が敦子の太ももに気をとられるうち、献金箱が敦子の隣りの人から回ってきた。
敦子は、持っていた千円札を折りたたんで中に入れる。
「学生は免除されるんじゃなかった?」
「あたしの場合、自発的に貢いでるの。そうしたほうがボジャイ様のご加護がもっと受けられる気がして。あ、守屋くんはいいよ」
そう言うと敦子は、手に持った献金箱をぼくを抜かすかたちで、僕の隣りの信者に手渡そうとした。なんだか疎外されたと感じる振る舞いだった。
「ちょっと待って」
僕は、手から手へと渡され前を通り過ぎようとする献金箱を自分の手でガシッと受け止め、膝の上に置くと、財布を出した。五百円玉でもあればと思ったが、あいにく小銭ばかり。ポケットを探っても、出がけに母から渡された一万円札があるだけだ。
よし。
僕は一万円札を出して、献金箱に収めた。
やってしまってから、すごく後悔した。
一万円は無職の高校生には大金だ。あれも出来た、これも出来た。どうして貢いでしまったの?
僕が入れた紙幣に福沢諭吉の顔をとっさに読み取った敦子は、伺うように、こっちの顔を覗きこんだ。
「いいの?」
「いいさ」
今更もう取り出せないじゃないか。ところで敦子は、献金箱を回すときに僕のほうに大きく身を寄せた。まるで恋人に寄り添うように、右半身が僕の左半身にべったりとなる格好で。『生け贄の歌』の合唱が終わっても、そのまま姿勢を戻さなかった。
なんだろう、これは。知らない人が見たら、恋人同士と思われるじゃないか。僕は人目が気になりはしたが、迷惑とは感じなかった。
すでに敦子がもっと親密な態度をとるのではと期待するようにさえなってた。
僕はそれとなく周囲を見たが、会衆で気付いた人はいないみたいだ。一瞬こちらにチラッと横目をやり(僕ではなく敦子のほうに)、咎めるような顔をしてから視線を戻した黒石御影を除いては。
敦子のほうでも御影の反応を察したようで、返事のつもりなのか自分の頭をかしげ、僕の肩にのせてきた。まるで見せ付けるみたいに。
それで御影はまた敦子を見やり、怒ったように眉根を寄せ、顔を背ける。
僕と敦子とで馴れ合ってるのがあきらかに気障りな様子だ。
僕のほうは見せ付けたいんじゃなく、ただ隣席女子から示される親愛のアプローチを拒む気になれず快いものとして受け容れるという、いわば敦子のなすがままにされてたわけだが、それでも御影の心を乱したのがわかると、なんとなく一矢報いた気分になった。
しかし、僕にとってのこの幸せな状態は長くは続かない。支部長が僕の名を呼び、みんなの注目がこちらに集まったからだ。
敦子はたちまち姿勢を正し、揃えた膝の上に両手を行儀よくおいた。
「さて。今日は皆さんに、新しい家族を紹介しましょう。なんと、まだ17歳という若々しい年齢の兄弟。稲葉高校二年生の守屋護くんです。同級生の志摩敦子姉妹の導きで体験礼拝に来てくれたのがご縁となり、このたび晴れてボジャイ様の教えを受け容れることになりました。守屋護くん、どうぞ立ち上がってください」
僕はみんなが拍手で迎える中を起立、正面の支部長はじめ各方向に右顧左眄というかたちで何度も礼をした。学校で褒められることをした生徒が満場での拍手喝采を浴びることがあるけど、あれと比べても、よほど熱がこもってて真剣だ。
「守屋くん。どうぞ、こちらへに出て来てくれたまえ」
僕は会衆の見守る中、支部長の前に進み出た。
いよいよ入団の宣誓が始まるのか。
「さて、守屋くん」
進み出た僕に支部長は、一通の封筒を渡した。
「その封筒には紙が入っている。誓いの紙という神聖なものだ。お父さんでもいいし、お母さんでもいいよ。きみには何ものにも代えられないという大事な人がいるだろ? その人の名前を誓いの紙に書いてもらいたい。これから合唱が始まるが、その歌が終わるまでに記入したのを封印し、持ってきてほしい」
僕は仰せに従って、いったん席に戻る。
教団聖歌『あたらしき家』の合唱が始まった。
あ 見える 見えるぞ あそこに見える
あれに見えるは ひとりびと~
え 誰れだ あいつは あいつは誰だ
あいつはひとり ひとりびと~
わ 来るぞ あいつが あるいてくるぞ
あるいてくるは ひとりびと~
お なるぞ 家族に 家族になるぞ
あらたな家族 この家に
いまはみんなが兄弟だ 姉妹もいるぞ この家で
すでに家族だ 信者の絆
われらの家族 あたらしき家
ひとりびと いまは兄弟 みんなの家族
ボジャイ様の傘のもとで 我らはひとつ大家族
我らはすべて 兄弟姉妹
我らはすべて ひとつの家族
「聖歌」が合唱される中、席に戻った僕は、封筒から出した白い紙を前にしばし思案するという風をよそおい、実は必死でこらえていた。唇を噛みしめ、喉元まで出かかった笑いの暴発を。まったく、なんて歌だ。『生け贄の歌』も酷かったけど、この教団にまともな聖歌ってあるんだろうか。
敦子が傍らから、助言するように顔を寄せてきた。書けないのは迷ってるからだと思ったらしい(実際、迷ってた)。
「絶対に失いたくない人の名を書けばいいの。お父さんでもお母さんでも」
そういう人ならいるけど……。
「その人、今ここにいないんだ。本人の承諾もなく勝手に名前を書いちゃって、あとでその人にバレたら困らない?」
「バレないよ。見るのは、入団の質疑をする支部長だけだから」
そうなのか。
「あくまでかたちだけのものなの。自分はこんな大事な人の命に代えても信仰を貫きますと誓約するためだから、そんなこだわらなくていいと思う」
「きみも入団するとき、大事な人の名を書いた?」
「あたしお母さんの名前、書いた。お母さんも入信のときはあたしの名前、書いたって」
何ものにも代えられない大事な人。絶対に失いたくない人。
僕はもはや躊躇せず、それも誇りをもって、おねえさんの氏名を書いた。
三田和美。
そしてすばやく紙を折りたたみ、封筒に入れた。
僕が立とうとすると敦子は、手紙をひったくるように受け取って、囁く。
「いい。あたし、代わりに持ってく。守屋くんは大急ぎでトイレ行く振りして、中で笑ってきちゃいなよ。ここで吹き出したら入信失格になるから」
あ。こいつ、僕の気持ちをよく察してる。
僕は敦子に手紙を託すと席を立ち、奥のほうにあるトイレに向かった。
教団施設というより普通の家庭にある男女共用の御手洗いそのもの。落ち着いた清潔な印象だ。この同じトイレをあの御影が使ってるのかと思うと、なんとも妙な気がする。こんな目的のため利用するのははばかられたが今は仕方ない。水洗の音を大きく出して誤魔化しながら、こらえていた笑いの感情を一気に噴出させた。
しっかし、くだらねえ歌! ひーっひっひっひーっ!
あー、すっきりした。これだけ笑えば、もう大丈夫!
戻ってきたときには、チンケな歌の合唱は終わってた。よかった、救われた。
神妙な顔をよそおった僕はもう一度、支部長の前に進み出る。
衆目の中、僕と黒石氏とは、教卓のような小さな机をはさんで向き合った。台の上には敦子が持っていった封書が置かれてる。いよいよ入団の質疑だ。
「そうだ」
ここで黒石支部長は、よいことを思いついたという顔をして、自分の娘を見た。
「御影」
父親に呼ばれ、御影はビクッとする反応を示す。嫌な役を命じられるのを敏感に察したように。
「おまえ、守屋くんの前に出て、入団式の音戸をとってみなさい。できるだろ?」
「できない」
彼女は父親の仰せに、一呼吸もおかず拒絶の返事で応じた。敦子の話では、御影が衆目の前でこういう態度をとるのはほんとうに珍しいことだという。
「やり方は何十回も見てるから、わかるはずだ」
「いや」
「言われた通りにしろ!」
黒石氏は僕というお気に入りの入信希望者を相手に、その同級生でしかも自慢の娘、信者たちにも評判の良い御影に入団質疑の音戸をとらせることで、いい場面に仕立てられると踏んだのだろう。
しかし実際は、まったく違う状況、予期せぬ修羅場を招いてしまったようだ。とにかく御影はやりたがらない。僕のそばに来るのを必死になって拒んでる。
そんな娘の異常な抵抗を同級の男子の前ではにかんでるからとしか思わず、父親の、支部長としての権限で思い通りにする気なのだ。
こうした黒石氏の、いやがる娘に無理やり若い男の相手をさせようとする強硬な態度のせいで、こっちの立場も微妙になってきた。これじゃ僕まで、御影を虐げる側だ。避けられるだけだったのが今度は、敵意すら持たれかねない。
事実、御影は悲痛なほど嫌そうな顔をして出てくると、僕の前に立った。
政略結婚の犠牲となり望まぬ相手と無理強いで挙式させられる生娘のようだった(実際、まだ処女らしい)。こんなやり方は、僕だって望まない。
御影は、教団の儀式でのしかるべき役目をまかされた者として最低限の神妙さは保ちながら、入団質疑の文句をなんの抑揚もつけず、まったくの棒読みに朗誦する。
「汝、守屋護。ボジャイ様より差しのべられし救いの傘による庇護を受ける代償として、命と持ち物のすべてをボジャイ様に捧げることを誓うか?」
この場の様相が何ともちくはぐに見えるとしたら、理由は御影の台詞よりも顔の向きにあると言っていい。御影は僕を見ないよう、あさっての方向を向いたまま誓いの質疑を読み上げているのだ。
さっそく黒石氏から懲戒が入った。
「御影。ちゃんと相手の顔を見ながら言いなさい。そっぽを向いてるじゃないか」
御影は顔の向きを変えなかった。
「御影!」
父親からドス顔で凄まれた御影はいやいやという感じで、顔をこっちに向けた。目はしっかり瞑っている。
僕は不快な思いとともに、彼女への同情を感じた。いまや、御影に幽霊が見えるというのは嘘ではなかったのだとはっきり悟った。
「汝、守屋護。ボジャイ様より差しのべられし救いの傘による庇護を受ける代償として、命と持ち物のすべてをボジャイ様に捧げることを本心から誓うか?」
「本心から誓います」
僕は本心から嘘を言った。
「汝、守屋護。ボジャイ様より差しのべられし救いの傘による庇護を受ける代償として、命と持ち物のすべてをボジャイ様に捧げることを何度でも繰り返し、誓うか?」
「何度でも繰り返し、誓います」
僕は何度でも繰り返す思いで、嘘を言った。しかし、くどい。
そして御影はダメ押しする。
手探りで、机の上の誓いの紙が入った封筒を取り上げると僕に突きつけた。むろん目をしっかり閉じたまま。
「汝、守屋護。いま述べたボジャイ様への忠誠を、この紙に名を書いた者の命に賭けて、誓うか?」
「………………」
返事が得られないので、御影はさらに繰り返す。
「汝、守屋護。この紙に名を書いた者の命に賭けて、ボジャイ様にすべて捧げると誓うか?」
困ったな……。
おねえさんの命はおねえさんのもので、僕ごときが勝手に、軽々しく誓いの賭け代になんかできるもんじゃない。まず、口先だけで立てた誓いで、ぜんぜん守り通す気がないんだし。
僕から沈黙の応答を受け、御影はさらにさらに、質問を繰り返す。
「汝、守屋護。この紙に名を書いた者の命に代えても、ボジャイ様への信仰を守り通すと誓うか?」
僕が無言でいることに、会衆は不可解そうなざわめきによる反応を示し、支部長は困惑したような顔をする。
そして御影は、CDが壊れた箇所のように同じ文句を延々と繰り返すばかり。
「汝、守屋護。この紙に名を書いた者の命に代えても、ボジャイ様への信仰を守り通すと誓うか?」
本心ではもしかして、僕がついに誓いの拒絶をし、二度とこの場所に来なくなるようにと願ってたかもしれないが。
そう、来られない。
ここで誓いを拒んだら、僕は教団員として認めてもらえない。この支部に二度と来られなくなるだろう。御影に幽霊が見える秘密もわからず仕舞い、人生がオカルトに呑み込まれて果てる。
………………。
とにかくひとつの事実は認めねば。
割り切る以外に選択の途がないってことだ。
よし。
「誓います。その紙に名を書いた者の命に代えて」
我ながらはっきりした調子で、宣誓の言葉を口から出した。
御影はとりあえず、ホッとしたようだ。
これで同じ文句を際限もなく繰り返さずに済む。かくなるうえは、可能なかぎり入団の質疑を早く終わらせて、一刻も早く僕の前から立ち去りたいというのが当座の本音だろう。
会衆も安心したに違いない。仲間が増えたのも嬉しいし、この入団の儀式が済めばバーベキューの会食が待ち受けてるからだ。
いちばん安堵したのは、さっきからの僕と御影とのぎくしゃくしたやり取りに、苛立ちを隠せない様子でいた黒石支部長かもしれない。ようやく儀式の段取りが自分の思う通りに運んだのを知ると、晴れやかな表情を見せた。
さて、御影は詰めを入れてきた。
「守屋護。汝が当教団に命を捧げた者の名を拝見する」
なぜ誓いの紙に書かれた名前を照覧するかといえば。敦子に聞いたところ、時々ふざけてか勘違いでか、芸能人やアニメキャラの名を書くのがいて――そういう人は信者になれない――、ほんとうに入団者の生活圏に存在する人なのか確かめるためだ。
それにしても「当教団に命を捧げた者」とは、なんて言い草だい。何も知らずに病床で臥せってる(命にかかわる容態じゃないらしいが)おねえさんこそいい面の皮だ。
御影は盲人の仕草で封筒を開け、誓いの紙を取り出す。あくまで形式的に目を通すだけ、そこにある名前が守屋護の父か母か、いずれにせよ自分とは関わることのない誰かだろうという距離感をおいた態度で。
しかし目を閉じたまま、どうやって読むんだろう。
僕がそう勘ぐった矢先、彼女は折りたたんだ紙を拡げた。それを両手で捧げ持つ感じで、自分の視界から僕の存在を遮蔽するように顔の前に拡げてしまう。
(あ。この手があったか)
しばらく何事も起こらなかった。
御影は、誓いの紙を顔の前に拡げたまま凍りついたように動かず、言葉も発しない。
こういう態度も儀式の一部なのかと思い、彼女の次の挙措を待ち続けたが、会衆席では御影の様子をいぶかるようなさわめきが生じ、しだいに大きくなってくる。
普段どおりじゃないのだろうか。人々の目にも、御影の様子があきらかにおかしいようだ。
突然、御影に異変があった。
自分の視界を遮っていた誓いの紙をおろし、僕と初めて、まともに向き合ったのだ。不安におののいているが、それは幽霊を怖がっているからには見えなかった。今この瞬間、僕の周囲の幽霊は退散したのだろうか。あるいはすでに意識朦朧として、前にあるものが目に入らないのかもしれない。
彼女はなにか言いたげに口を半開きにし、ついでなにかを求めるように手を伸ばしたかと思うや、白目をむいて放心したような表情になると、こちらのほうによろめくのを立て直すように床に膝を突いたのち、まさかと思ったが、しなやかな身を床の上でスライディングさせるように倒れ伏した。
突っ伏した頭が僕の足に当たりそうなほど迫ってきた。
もともと小柄でほっそりした子なので、床から受ける衝撃は軽かったはずだが、それを見た会衆はみんな、大きな衝撃を受けた。
実のところ、御影が床に倒れるより先に、すばやくダッシュして崩れ落ちる少女の身を受け止めることもできなくはなかったが、とっさの事だし、御影が相手ではどうしてもそうするのを阻むものが僕の心の中にあった。これがおねえさんだったら違ったかもしれない。
いきおい僕は、美しい衣装をまとった姿で気を失った少女を前に、呆然としてたたずむ格好となった。どうすることもできぬまま。
御影のそばには真っ先に母親が、ついで黒石支部長が駆けつけ、抱え起こす。何事かと色めきたった会衆も席を立ち、親子を取り囲んだ。
狭い礼拝室は一定の秩序は保ちながら、人々が口々に取り交わす言葉の喧騒で実際より大きな混乱に陥ったような錯覚をみんなにあたえた。
「大変!」「ああ、ボジャイ様……」「御影ちゃん、大丈夫かしら」「バーベキューは? ねえ、バーベキューは?」
幸い、会衆の中には看護師の女性もいた。
御影に外傷がないこと、呼吸や脈拍も危険な状態でないのを確かめてからどうも貧血らしいという見立てがされ、とりあえず別室に移し、安静な状態で様子見することになった。
黒石氏は御影を抱き上げると、看護師さんの先導で人々が後ずさりしてできた道を通り、奥のほうに運んでいった。御影のお母さんが続く。
さらに敦子や敦子の母など、何人かの黒石家と親しい人々があとを追い、残余の会衆はざわめきの中で礼拝室に残された。
ほとんどの人には気がかりではあるが野次馬ぶって様子を見に行くのがはばかられたからだが、僕もその一人だった。
あんな事が起こって心が騒がなかったかといえば嘘になる。
そのあと長きにわたり、僕は倒れる御影を受け止められなかったのを後悔し続けた。なぜ体が動かなかったのだろう。御影の身をかき抱くあれほどのチャンスは望んでも得られないことなのに。
今の今まで御影が、あの御影が、僕のほうから庇護をあたえられる存在とは思いもしなかった。
それにしても疑問を残す出来事だった。
御影はなぜ失神したのだろう?
あきらかに彼女は、誓いの紙に書かれた名前を見てから様子が変になった。
倒れる直前、僕に助けを求め、すがりついてくるように思えたが、目の錯覚ではないはずだ。
つまり紙に書かれた名前が、幽霊の群れよりよほど恐ろしかったというわけか。
では御影は、三田のおねえさんの名前を見て、あれほどの衝撃を受けたというのか。もしかして彼女、おねえさんを知ってるのだろうか?
まったく、わからない。
この騒ぎの中もはや誰も関心など払わない、御影が手にした誓いの紙が動きまわる野次馬に踏まれたり摺られたりで床をすべるようにして、ぼくのいる付近まで運ばれてきた。
行き交う人々に手を踏まれる危険を冒し、なんとかそれを拾い上げる。誓いなんてどうでもいいが、この紙には大事なおねえさんの名前が書かれてる。紙くずみたいに粗末にされたらたまらない。
しかし拾った紙に目を通した僕は、御影ほどではなかったものの、愕然とした。
それはまぎれもない誓いの紙、御影が封書から出して照覧したものに間違いないが、その前に、僕が三田和美の名を書いたのとは別の紙だった。
僕の筆跡じゃない、ワープロの印字体でおねえさんとは別人の氏名が記されていたからだ。
黒石御影の名が。
その後、ダラネーナ教の奥義がわかってきた頃に、僕はようやく思い知る。
いまのが本当の「生け贄の儀式」だったということに。
( 続く )
アレが見えるの(その七)


