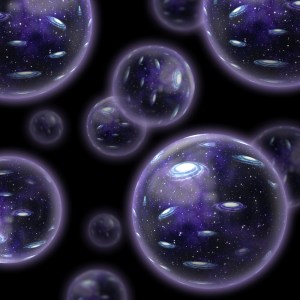終わりなき神話 第1話-17
17
連絡通路を抜けた先に螺旋状に鋼鉄の階段が組まれた縦穴が現れた。チタンで形成されたこの縦穴の先に地上への出入り口があるはず。
ファン・ロッペンを先頭にエリザベス・ガハノフ、マキナ・アナズと階段を踏んだ。
チタンの空間に靴が鋼鉄を鳴らす足音だけが響いた。
と、階段の中間地点にさしかかった時、地下から爆発的な振動が3人を突き上げ、衝撃で女性2人は手すりに身体を預けるほどである。
振動は数秒とたたないうちに静けさをまた取り戻した。
「派手にやってますね」
後方の2人をみやり、粘りのある笑みでファンは言う。皆の前で見せた様子とは、月と泥ほども異なる笑みだ。
「互いに宿命と理解していながら、顔を会わせるのも今が初めて。ましてや能力の詳細はさっぱりなのだから、警戒するのも無理はない」
訝しく、また怪訝に男を睨む女性2人への言葉であった。
エリザベスとは大学時分より知った仲で、運命に糸を引かれていたのを解釈した上での付き合いだったせいもあり、互いをどういった人間なのか理解していた。
「あの娘が居ないと、だんまりなのね」
男の声色を無視するかのように、エリザベスがマキナの丸顔に視線を落とした。
ボアの髪を耳に掛け、少し不機嫌に彼女は口を開いた。
「別にそういう訳じゃ・・・・・・」
瞳は斜線を描いている。
元来、彼女は人見知りだ。他者へ気持ちを話すこともなければ、自ら率先して話題を提供する立場でもなく、誰かの話に頷きを返す程度で、意見を求められても、分からない、というのが精一杯だ。だから人と関わることをしない。大学ではマリアと常に行動を共にし、帰宅はまっすぐにマンションへ直行する。外食は多少するものの、他者との会話、触れ合い極力省きた人間なのだ。
見ただけで彼女の性質を理解したのか、エリザベスは涼やかに言葉を彼女へ放った。
「自分の意見を言えない人間は、これから生き残れないわよ。だんまりで戦えるほど、甘くないんだから、ここからは」
自らの主張を言いたいだけ言うと、前の面長男を押しやり、自分が先頭で階段を上っていった。
この様子を傍観するファンは、眉を引き上げニタニタとにやつき、面白がっていた。
丸い顔をさらに不機嫌に膨らますマキナの顔色は、あまりの不愉快さにリンゴの色となった。
そこから会話が飛び交うはずもなく、無言の上を足音が通り過ぎて行き、最上階へ到達するまで重たい空気は解消されなかった。
チタンの壁にタッチパネルが設置され、チタンの見るからに重厚な扉はロックされていた。暗証番号画面がパネルに投影されているが、番号など3人が承知しているはずはない。
「さてさて、いかがいたしましょうか?」
冗談半分に恭しくエリザベスにファンは視線のベクトルを向けた。彼は彼女が事態を打開する能力を保有している事実を把握したうえで、わざと恭しく言い放ったのだ。
牙をむき出す瞳を男に向けるなり、彼女は長い黒髪を掻き上げると、パネルへ指をゆっくりと這わせた。猫を撫でる指先のように。
すると細く白い指先に細かく、静電気の青白い光が放射された。その直後、分厚い扉のロックが解除去された音が、重たく床を這った。
彼女は弟とその能力を同じくしており、ロックのシステムをショートさせ、システムを初期化、再起動した瞬間にロックが解除された。
繊細な指先をパネルから離し、彼を無上げて軽く笑みをたたえて言い放った。
「これでよろしいかしら?」
やり返す彼女の言葉が心中の心地よい場所に響くらしく、ファンはにたりと笑った。その手で彼は重たい扉を身体を当てるようにして押し開いた。
真夏の生ぬるい熱波が一気に地下のひんやりとした静かな空気に流入した。
皮膚を刺す日差しが薄闇を門を開くように照らした。
宇宙港はバケツをひっくり返した騒ぎと、パニックの坩堝と化していた。避難を求める人、人、人は宇宙港の建物には入りきれずに、チタン製の滑走路まで溢れる始末になっている。
残存する警察が人々の誘導を拡声器で試み、列を作るよう促してはいるものの、オクトパスの現出が招くパニック状態は、警察官の秩序の遙か上を激しく遠くまで飛ぶ。
モスバーグM500ショットガンを常備する警察官たちが威嚇射撃をする銃声が至る所で破裂音となって立ち、群衆を牽制のロープで縛り上げようとするも、群衆の集団パニックの恐ろしさは現在も過去も変わることのない恐怖の一種だ。歴史がバングラディッシュの工場で発生した800人もの集団パニックで照明しているように、異常のない水に異常が発生したとのアナウンス1つが、それだけの人間をパニックに陥れる。
今回は世界規模で原因不明、未知の恐怖、死の接近、異常自然現象などの要因が人類を追い詰め、隣人の命が理不尽に失われる光景など、人類は否応なしに突きつけられた恐怖で、パニックとなった。それが伝染した結果の1つが、3人の前で繰り広げられる、警官を押し倒して命の糸、生からの蜘蛛の糸にしがみつく、無限の亡者の群れだ。
「浅ましいものだな、人間というやつは。おい、見てみろよ。あそこで子供を抱えている母親を。3歳、いや4歳くらいか。きっとあの母親に命を助ける代わりに子供を殺せと言ったら、喜んで首をしめるぜ」
ほくそ笑むファンの顔を、横目で寒気をおびながらマキナは見つめる。
心中に、この化け物と戦う宿命にある自分を慰める言葉が延々と呟かれていた。
民衆の流れは洪水となって警察官を押しやり、決壊した泥を成す。
チタンの滑走路に直立する柱、シャトルは総数が20と少ない。世界的に見るとアメリカのケネディ記念宇宙港は60を越え、中国、フランス、ロシアなど先進国の数は、50を軒並み越える数が揃っている。20という数は、やはり発展途上の都市ならではの数である。
整備倉庫内部にモグラの如く現れた3人の前で、20あまりのシャトルの座席を争い、パニックから一転、つかみ合い、殴り合いの闘争が開始された。
生きることしか考えていない人間の、なんたるおぞましいことか。子供、女性、老人、老婆に差別なく拳は顔を直撃する。
この場限りの事柄ではない。各大陸、各国家、都市、街、村。人が存在するあらゆる所に、恐怖は爪をかけ、人の精神を鷲掴みに、そして握り、壊した。愛するものに見捨てられ、家族は消滅し、兄弟、姉妹は生存を欲して刃を胸に突き立てた。守るべきは自分のみ。肉親の情は泥に沈んでいた。
3人が倉庫から脚をカオスの滑走路へ踏み出した直後、轟音がまるで太鼓となって空気を震わせ、人々を中空へ人形のように弾く光景が眼前で起こった。
紫色の木の根のような血管がむき出しになり脈打ちながら、だらしなく垂れた灰色の脂肪を震わせ、その巨体をもつ人型のデヴィルズチルドレン。それが人を短い腕で叩き、脳髄をぶちまけさせ、体当たりで人間をひき肉とした。
ある種、人間とは異なるのが満足の攻撃にも似た群れの来襲は、もはや人間たちの自我を保っていられるほど、現実的ではなく、悲鳴を上げて逃げる人間の中には、自ら抱く乳飲み子を投げつける母親、突然笑いだし周囲へ暴力を振るう者など、人間らしい何かが切れた。
「これが人間だ、エリザベス。秩序ある生活と国家の保護下にあってこそ、人間は霊長類の頂点に立っていられる。ひとたび皮を剥いて中身を出せば、鼻をつく悪臭にまみれた醜態を表す。獣と同じなんだよ、人って奴は。所詮、動物なよさ」
と口でファンはいうが脳内からは、テレパシーとして思考が彼女の脳へ直接的に会話を試みていた。
【選択の定めにある女。汚物とも形容すべき人の行為を見せられても尚、彼を護ろうと、守護者とならうというのか。それが私的好意で結論づけた結果だと、安易だとしてもか】
【どこかの誰かさんのように、人を諦めちゃいないのよ】
冷静に自己分析してエリザベスは思念を返す。
とその時背後で爆発音が糸を張り、醜い巨体の群衆が倉庫の鉄板を砕き、工具を撒き散らしながら迫ってきた。
「じゃまだぞ、けだもの」
暴走した特急車の如き群れへ、冷酷に縁取られた視線を落としたファンは、腕を腹部から頭上へ斜めに振り向きざまに振り上げた。
刹那、見えない凄まじい力で5メートルを越える巨体が次々と、ボウリングのピンとなって弾け飛ぶ。
肉がチタンに溢れた音にまみれ倒れた化け物の群衆に、更なる追い打ちがかかった。プレス機に潰されたかのように、チタンの地面にクレーターを形成しながら、重力がのしかかり、押しつぶされミンチになった。
生命力が強い。ゴキブリ、雑草など地球上には踏まれても生きる生命体が存在する。クマムシなどは高温、低温に耐え、人間が爪の先で押しつぶすという他者からの害意がなければ生きていける生命体の一種だろう。
デヴィルズチルドレンにも生命体としての強靱さが兼ね備えられていた。その多種多様な種類もさることながら、ファン・ロッペンの重力を指定安易だけ増幅させ、重力による重圧でこのようにミンチになってもなお、肉片からは内蔵や血管のような触手がウネウネとミミズのように這い、獲物と認識した3人へ地べたを這って、未だに接近しようとしていた。
がそれを阻むのは、冷酷に塗られた面相を、虫けらに向けるようる視線と落としたエリザベス・ガハノフの指先から発せられる、青白い一閃。
彼女の細い指から稲妻が落雷となって地上へ落ち、這いつくばる肉片を焦がした。
「わたしは弟ほどのパワーは無いけど、ウジ虫を燃やすくらいはできるのよ」
と、視線をファンの面長な顔に矢のように向けた。
ウジ虫が単純にデヴィルズチルドレンを指しているだけではないと理解しながら、ファンはニタリと不適に粘度の高い笑みを貼り付けた。
棘のあるやりとりをしている間にも、滑走路は血の色に染められる。腹部は弾け内蔵が飛び、頭は水風船のように砕かれ、四肢は曲がらない方向へねじれている。そんな人間ばかりが朽ちて横たわり、まるで落ち葉を踏むように造作もなく、デヴィルズチルドレンは滑走路を闊歩する。
見ていられない光景に顔を背けていたマキナだったが、不意に掌を前へ突き出す。と、掌数センチ先の中空に黒い点が現れ、それが一瞬にビー玉ほどの大きさへ拡大し、静止エネルギーから移動エネルギーへ瞬時に変換されたように、黒点はデヴィルズチルドレンの群れめがけ弾丸となった。
瞬間に中央まで移動した黒点は刹那、人間には想像を絶する吸引の力で瞬く間にデヴィルズチルドレンの群れを吸引し始めたのだ。
もちろん化け物どもは踏ん張る。チタンに肉の塊を乗せて、皮膚を引き裂きかぎ爪を伸ばしてチタンを鷲づかみにして。
だがそれで耐えられるほどの吸引力ではない。この世の自然現象でこれほどの吸引を要する現象は1つしかなく、彼女はそれを生じさせられる。
ブラックホール。
恒星が寿命を迎え内部へ激しい重力で自らがつぶれていく縮体現象の先に発生する、永遠の重力。それをマキナは自在にマイクロブラックホールとして発生させる。
しかも吸引の範囲、シュバルツシルト半径を自在に変化できた。
現にブラックホールが人工島に現出したらすべてが呑み込まれるはずなれど、周囲20メートルのデヴィルズチルドレンと遺体以外、吸引されることはなかった。
踏ん張りを効かせていたデヴィルズチルドレンたちも、自然現象の最高位には太刀打ちできず、中空へ放り投げられると、小さな穴めがけ肉体が吸引力で押しつぶされ、断末魔の悲鳴を発しながら消滅していく。
周囲20メートルを掃除したマイクロブラックホールは、空間の変動を元通りに修正するかのように、消滅したのだった。
人前で能力を発揮すること自体が初めてのマキナは、疲れた様子でボブヘアを掻き上げた。
「重力の操作。わたしと貴女は同じ種類の能力のようですな」
ファンはニタニタとまた、不気味にマキナを見つめるのであった。
物静かなマキナもこれには嫌悪感しか胸になく、珍しくそれをはき出そうと口を開いた。
が、声色は発することができなかった。彼に向ける嫌悪感を打ち消すほどの嫌な、心臓を冷たい指先で捕まれた感覚が彼女に走ったからだ。
視線を感じ、そちらの方向を向く3人の前に、黒い影が、恐ろしく黒い人の形が浮かび上がるのだった。
ENDLESS MYTH 第1話ー18へ続く
終わりなき神話 第1話-17