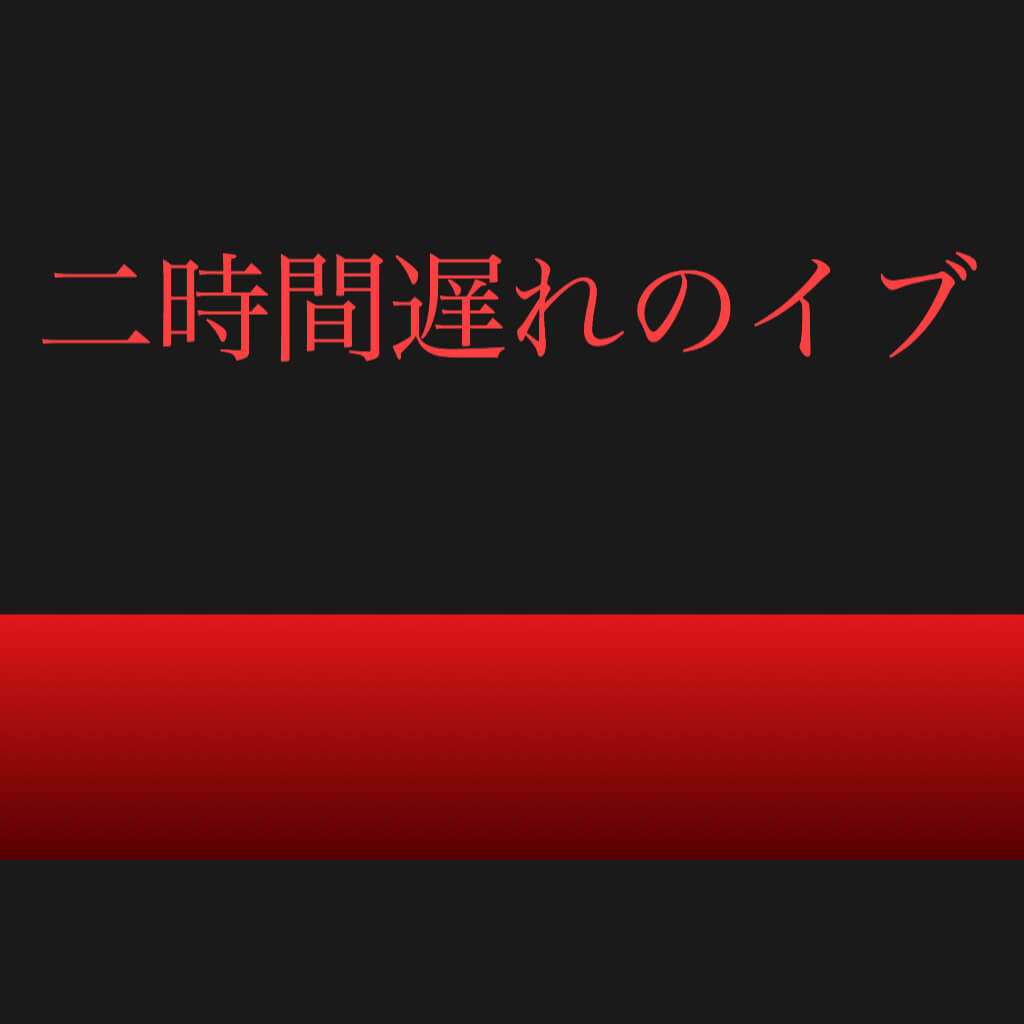
二時間遅れのイブ
ブゥーン……。
物音に目を覚ますと、時刻はすでに午前二時を指していた。
薄暗い部屋の中、一番最初に目に入ったのが時計だった。
起き上がろうとするが、妙な倦怠感がわたしの体を襲った。
だるい……。
どうにか起き上がろうと、ローテーブルの縁に手をかけてゆっくりと体を起こす。まるで全身が鉛になってしまったかのように重くて、上半身を起こすのに数分かかった。
ブゥーン……。
いまなんじだろ……。
ぼんやりとした頭でそんなことを呟いていた。今は午前二時だ。さっき確認したはずのことなのに、すっかり忘れていた。なぜだろう……。
気を抜くと思わずテーブルに突っ伏してしまいそうになるのをこらえながら、現状を確認しようとする。が、なにがあったのかまったく思い出せない。
それよりも喉渇いたなぁ。さっきまで寝ていたせいか、やたら喉が乾燥していて、口の中がカサカサする。倦怠感は残ったままだったが、今は喉を潤したかった。
鉛のような体をなんとか奮い立たせ、ようやく立ち上がることができた。すぐそばに流し台があった。傍らに置いてあったコップに水を満たすと、思い切り飲み干す。冬の寒さで冷たくなった水道水が歯にしみた。
水の冷たさでぼんやりしていた頭が少しだけすっきりした。
改めて部屋の中を見渡す。部屋の中にはローテーブルとソファー。それとベッドが置かれていた。テーブルの上にはきれいにデコレーションされたケーキがあった。
そういえば今日はクリスマスイブだった。日付は変わって今はイブではないけど。
ブゥーン……。
それにしても体がだるい。ついでにいうと頭まで痛い。倦怠感の次は頭痛か。いよいよもしかしたら風邪かもしれない。無理もない。冬の寒い中、布団も被らず床の上で寝ていたんだから。
そんなことを考えていると、少しずつ頭が冴えてきた。もちろん頭痛は残るが。
キリキリと痛むこめかみをおさえながらそっとテーブルのそばに座る。ケーキの上に乗ったサンタと目が合った。メリークリスマス、ミスター。
近くに置いてあったフォークをつかみ、手付かずのケーキを切りわける。一口サイズになったケーキを口のなかに放り込むと、生クリームのほんのりした甘味と、スポンジケーキのしっとりした感触が幸せを感じさせてくれた。ここにターキーなんかもあれば、なおいいだろう。贅沢はいえないか。
切り分けたケーキを食べ終えると、ふと気づいたことがあった。ケーキの傍らにワインボトルが置いてあった。クリスマスといえばシャンパンが定番のはずだ。なのに、置いてあるのは赤ワインのボトル。グラスは二つあった。一方のグラスはワインで満たされていた。もう一方のグラスは空になっていた。これはどういうことだろう……?
ブゥーン……。
不自然なのはテーブルの上だけじゃない。ソファーの上には誰のものかわからない衣服が脱ぎ散らかされていて、ベッドは乱れていた。それがますますこの状況をわからなくさせていた。
頭が痛い。なにか考えようとすると、途端、妙な頭痛に襲われる。まるでなにも考えるなと言われているみたいに。
ブゥーン……。
それよりもさっきからずっと響いているこの音はなんだろう。虫の羽音のような低く重い物音。どこかで聞き覚えのある音のはずなのに、どうしてか思い出せない。
ブゥーン……。
そうか。この音は冷蔵庫のモーター音だ。まだ子供だったころ、わたしはこの音が嫌いだった。夜眠ろうとすると、この音が獣の嘶きのように聞こえて眠れなかったことがあったからだ。もちろん今では気にするようなことではなくなったが、それがどうして今になって……。
ブゥーン……。
……頭が痛い。さっきにもまして頭痛がひどくなってきた気がする。
わたしはそっと冷蔵庫に近づく。冷蔵庫はワンルームにふさわしく、冷凍室と冷蔵室のみのそれほど大きなものではなかった。なのに扉に手を伸ばそうとすると頭痛が激しくなった。
痛い。痛い。痛い。
わたしは頭痛に耐え切れなくなってその場にへたりこんでしまった。
額から汗が滴り落ちる。なぜ……どうして……。
睨みつけるようにして冷蔵庫を見つめる。ブゥーン……とモーター音が重苦しく響いていた。
わたしが彼と出会ったのは今から一年ほど前のことだった。彼を一目見たときわたしは瞬時に恋に落ちた。それまで誰かに心躍らせることなどなかったわたしにとって、彼との出会いは運命だとすら感じたほどだった。
それからの毎日はバラ色と言っても遜色のないものだった。真っ白に見えていた毎日が春に芽吹く花々のように色づいて見えた。
わたしは彼を見ているだけでよかった。彼の優しげな目や声。一見すると華奢に見えて、けれど実は筋肉質な体。それでいて指はごつごつしてなくて白魚のようにしなやかだ。わたしはその一つ一つが好きだった。食べてしまいたいくらいに……。
しばらくしてわたしは彼の家に上がるようになった。部屋での彼はいつも疲れたと言ってすぐに寝てしまっていたが、わたしは彼と一緒にいられるだけでよかった。彼の安らかな寝息をそばで聞いていられるだけで幸せだった。
わたしは彼のことがとにかく好きだった。好きで好きでたまらなくて、頭の中はいつも彼のことでいっぱいだった。
ある日、彼が好きな食べ物の話をしていた。それを聞いたわたしはいてもたってもいられなくて、すぐにそれを作ることにした。スーパーで食材を選び、部屋に戻って作る。その間の一秒さえも彼の喜ぶ顔を思うと幸せに感じていた。
それからもわたしはことあるごとに彼の部屋に行っては料理を作るようになった。なかでもわたしが一番得意としている肉じゃが。彼は喜んで食べてくれるだろうか。
わたしが彼と出会って半年ほどしたころだろうか。彼はあまりわたしと会ってくれなくなった。というより避けられているような気がする。わたしは出会って半年たったからこれが俗にいう倦怠期なのだと思っていた。もちろんわたしの彼に対する愛情は変わらない。いままで通り部屋に上がって料理を作り、時間があれば彼の寝顔を見て過ごす。どんな障害があっても彼とわたしの愛を阻むことはできない。そう。誰にもだ。
ある時を境に、彼は部屋に戻ってこなくなった。仕事が忙しいのだろう。わたしは彼が仕事に熱中するあまり、体を壊さないか心配になった。彼の勤める職場に赴き、彼のようすを見に行くことにした。案の定、彼はやつれているように見えた。やっぱりわたしがちゃんとご飯を作ってあげてないからだ。彼をあんな風にしてしまったことに苛立ちを感じた。彼を支えてあげられるのはわたしだけだ。ほかの誰でもない。わたししか……。
彼が元いたアパートを引き払った。勤めていた会社も辞めてしまったらしい。理由は体調の悪化によるものだと聞いた。やっぱりわたしがしっかりしていなかったせいだ。もっとわたしがちゃんとしていればこんなことにはならなかったはずだ。彼はどこにいるんだろう……。彼に会いたい。
今日は気分がいい。なぜならようやく念願叶って彼を見つけることができたからだ。彼は元いたアパートから結構離れた場所に引越しをしたらしい。本当ならもっと早くに会いに行きたかったけど、居場所を探すのに手間取ってしまった。いなくなってしまったときは悲しかったけど、これでまた彼と一緒にいられる。それからというものわたしは彼のことをずっと見ていることにした。朝、彼が起きてから家について眠るまでずっとだ。そうでもしないとまた彼の体がおかしくなってしまう。それだけは防ぎたい。わたしにできることなんてささいなことかもしれない。だけどわたしは彼の力になってあげたい。
彼が新しいアパートに移ってひと月が過ぎた。彼の体調はまだ良くないらしい。ずっと部屋に引きこもってばかりいた。前の会社の仕事がよっぽど激務だったのだろう。そうか。彼をこんなふうにしてしまったのはあいつらのせいか。だったらそんな場所なんてなくなってしまってもいいよね……?
そこからさらにひと月がたった。彼は少しずつ調子を取り戻してきていたようだった。わずかだが、部屋から出ることもあった。よかった。これもわたしが彼を苦しめたあいつらを消したからに違いない。もっと早めにこうしておくべきだった。これで彼も喜んでくれる。
わたしは彼のことが好きだ。愛している。彼のためならどんなことだってできる。人を殺せと言われれば殺せるし、辱めを受けろと言われれば喜んで体を差し出そう。それでもわたしは彼が好きだ。じゃあ彼はわたしのことをどう思っているだろう……? ついそんなことばかり考えてしまう。わかっている。彼もわたしのことを愛してくれている。彼を信じよう。
ある夜、わたしは夢を見た。本当なら思い出したくもないはずの夢なのに、内容ははっきりと覚えていた。わたしが彼を殺して食べてしまう夢だった。わたしが彼を殺すなんてことはありえない。ましてや食べるなんてことは……。これ以上考えるのはやめよう。
もうすぐクリスマスイブだ。彼と出会ったのもちょうどこのころだった。あれから一年が経とうとしていた。時が経つのは早い。せっかくの記念だ。わたしと彼が出会った記念をしよう。デコレーションされたケーキを用意しよう。ターキーもあればなおいい。飲み物はシャンパンもいいけど、ここは大人らしくワインで乾杯かな。ああ。イブが待ち遠しい。
イブが近づいてきた。街も色とりどりのイルミネーションで飾られて、クリスマスムードでいっぱいだった。彼と過ごすイブを思うと毎日が幸せだ。そのときはちゃんとわたしの思いを伝えよう。そうすればきっと本当の恋人になれるはずだから。
……今日は嫌なことがあった。いつものように彼の家の前で立っていると彼の部屋に知らない女の人が入っていった。いつもわたしだけに向けてくれていたはずの笑顔もその女に向けられていた。どういうことだろう。彼はわたしを愛してくれていたはずじゃなかった……? もしかしたらなにかの見間違えかもしれない。そうだ。きっとそうだ。きっと。きっと。きっと。
彼が裏切った。わたしを愛していたハズの彼はもういない。あの笑顔も嘘だった。もうなにも信じられない。ああ。イブなんてやってこなければいいのに。
あの女を殺した。わたしと彼の邪魔をする奴は誰だってユルサナイ──。どうしてみんなわたしと彼の邪魔をするのだろう。こんなにも彼のことをアイシテイルノニ……。
イブが近づいてきた。
お腹が空いた。
なにを食べても美味しくない。
お腹が空いた。
そうだ彼が欲しい。
彼が欲しい。
彼が欲しい。
欲しい。
欲しい。
ほしい。
おいしい。
オイシイ。
カレハ……オイシイ……?
ブゥーン……という物音で我にかえった。
そうかそうだったんだ。どうしてわたしはこの物音が気になったのか。その理由がはっきりとわかった。
ゆっくりと冷蔵庫の扉を開く。真っ白な庫内には苦悶の表情を浮かべた“彼”がいた。下の段には彼のバラバラに切断された手足もあった。
なんだ。そうだったんだ。
わたしは彼を──食べたんだった。
カレハ……オイシイ……?
ああ。美味しかった。ずっとわたしはそれを望んでいた。わたしが望んでいたのは彼から愛されることでも、愛することでもなかったんだ。
ただ一目見た時から思っていた。
彼を食べたいと思っていた。このイブという特別な夜に。
そっと慈しむように“彼”を取り出す。
「メリークリスマス。あなたはとっても美味しかったよ」
もう頭痛はしない。
ブゥーン……と、いつまでも冷蔵庫のモーター音だけが響いていた。
二時間遅れのイブ


