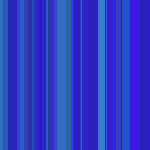血を愛した人
お題サイト「サディスティックアップル」 http://loose.in/sadistichoney/ より
shortお題 「たくさんの人がいたこの星で」
彼女は至って普通の生徒である。勉強はそれなりに出来、性格もそれなりに明るく、人間関係もそこそこ。人当たりはそれなりで、周りに敵を作らない人間だ。俺はそんな彼女の唯一の男友達で、近所に住む昔からの幼馴染だ。俺も至って普通の男子生徒である。
今日も彼女は自転車に乗って、ほどほどの汗をかきながら登校してきた。俺はそれより早く、部活の練習のために登校しており、既に教室で勉強をし始めていた。
「おはよう」
「おはよう」
一言そうかわして、それ以上話すことはない。
彼女には彼女の、俺には俺の人間関係というものがあって、必要最低限の会話しかしない。俺は彼女の方も見ずに勉強を続けた。そしてしばらくして、彼女は教室を離れた。きっと、友達の所にでも遊びに行くのだろう。
「あれ、五百旗頭(いおきべ)はどこ行った」
朝のHRが始まる前に、先生がそういった。
気づけば彼女はまだ帰ってきてなくて、きっとまだ遊んでいるに違いない。俺はそう一人で完結して、単語帳に目を戻した。
「そこ、誰だ、えーと、イオキベか。休みか?」
一時間目が始まって、単語帳に夢中だった俺は、彼女がまだ帰ってきていないことに気付かなかった。授業が始まっているのに、帰ってこないなんておかしい。まして、彼女は、普通のまじめな生徒なのに。かすかな疑問と不安を持ちながら、目前の小テストに挑む。
「イオ、どこに行ったのかな?」
彼女の友達が、集まって話し始めた。朝まではいたのにね、三組の方に向かっていくのを見た、あたしは北校舎に行った時に見たよ、とか、そんな噂。耳をそばだてて聞いてみると、北校舎で見たと言っていた女子は、彼女が突き当たりの廊下を怠惰に歩いていたのを不審に思ったが、そのままにしておいたらしい。俺は、帰ってきた小テストをくしゃりと丸め、北校舎へ走った。そんな俺をちらちらと見るクラスメイトもいたけど、気にせずに行った。
どうせ、彼女を探しに行ったとは思っていないだろう。
北校舎の図書館のある階は、突き当りが壁になっていて、横には非常階段がある。滅多に人は通らないし、図書館に行ったとしても突き当りの方には目もくれない。少し湿っぽくて、暗い一角だった。今、俺は息を切らしながらその場に立ち、非常階段のドアと格闘していた。いつも閉まっているはずのない―閉まっていてはいけない―ドアは外側から固く閉ざされていた。鍵ではなく、何か仕掛けで開かない。しばらくノブを押し引きして駄目だと気づき、携帯を取り出して、二時間目が始まっているのを確認すると扉に体当たりをした。
何度か体当たりをするとつかえが取れ、盛大な音とともに扉が開いた。上に行く階段を数段上がると、少し高い位置に銀色の梯子がある所に出た。光の差さない薄暗い空間に弱く光るそれは結露している。一部、露の付いていないところがある。それは誰かがここを上がったことを示している。俺も颯爽とそれを登る。
彼女は南校舎の屋上にいた。
北校舎と南校舎をつなぐ渡り廊下の上を通っていったらしい。彼女は俺に背を向けて、座っていた。
何をするわけでもなく、縁に。
「イオキベ」
「シシガキ、なんで」
身体をひねらせて、俺を見た。
言葉には驚きが含まれていたが、顔にも声にも感情はなく。逆光で影の差す顔を少し緩めて、苦笑いした。
「二時間目始まってんじゃないの」
「英語さぼった人間が何言ってんだよ」
俺もその隣に胡坐をかいて座って、空を眺めてみた。どこまでも青く、秋晴れの空。山の辺りには灰色がかったスモッグのようなものが立ち込めている。胸のあたりをきゅ、と締め付けられるように空しくなった。
「どうして、こんなとこにいんだよ」
右にいるイオキベの顔を見ると、何処を見つめるわけでもなく、呆けたような表情をしていた。返事を聞くのも忘れて、彼女の横顔を見つめていた。普通の陽ざしに照らされた顔。目鼻立ちもそこそこに整っていて、いわゆる普通の顔、のはずなのに。
どうしてか、美しく見えた。
「私ね、もう、駄目みたい」
「駄目?」
訥々と、言葉を紡ぐ。眼は何処までも光を浴びて、光を失っていた。
「人を、信じられなくなったの」
「俺もか?」
「それは、後で言うわ」
くすりと笑って、話を続けた。
「辛いことや苦しいことに耐えられなくなったみたい。思考もネガティヴだし、なんだか、どうしようもなく死にたいの」
死にたい、という言葉が妙にはっきりと聞こえて、背筋が凍った。勝手に想像する、彼女は此処を、死に場所に選んだんじゃないのかと。
「こんなにも価値のない人間が生きていていいのかしら。嫌われている人間は生きていて意味があるのかしら」
ただの思い込みだなんて言えない。徐々に風は強さを増し、グラウンドの砂埃を微かに連れてくる。
「私は、私が大嫌いなの。自意識過剰で、痛い、私が」
幼馴染から語られる久しぶりの言葉が、まさか遺言のようだなんて、誰が予想しただろうか。
「だから、助けて、この私を。もう、贅沢なんて言ってられないわ」
俺の方を向き直ると、ぎゅっと二の腕を掴まれた。
「私は、この縁に立つ。シシガキはただ、後ろから押してくれればいいの」
貴方は、信じてるから。そう付け加えて、強風の中、彼女は前を見据えて立ち上がった。俺はただ茫然と、立ちあがった彼女を見つめ、そしてぐるぐると思案していた。
従うべきか、従わざるべきか。
長い髪も、セミロングの髪も、スカートも、だらしなく出たシャツも、全て全て、風になびいた。
「本当に、いいのか」
下から見上げ、尋ねてみる。
「後悔も反省もしないわ。今はただ、早く死にたい」
二時間目終了のチャイムが下から聞こえてきた。風の音に混じって。
彼女の声ははっきり聞こえた。風の音からクリアに。
俺は、素直に迷った。
「俺は」
立ち上がって、彼女の背後に立つ。小さな背中だった。
「……」
両手を背中に添える。冷え切っていた。
「俺は――」
ただ鮮血が見たかった。
音も、
感触も、
匂いも。
何も覚えていない。
「ありがとう」
反芻される彼女の言葉。
俺は、何故か犯罪者として捕まることはなかった。どうやら学校側が隠ぺいしたらしい。そっと転校して、何事もなかったように。
彼女がいない毎日は、そして始まる。
血を愛した人
メンヘラ少女は書いていても辛くなりますね。
耐震工事で移転したときに使っていた高校の校舎がとてもときめく構造だったので、それをイメージしながら書きました。