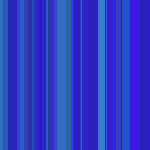光を忘れてしまった人
お題サイト「サディスティックアップル」 http://loose.in/sadistichoney/ より
shortお題 「たくさんの人がいたこの星で」
「仕事ないか?」
「ないわ」
俺は買ってきたクリームパンを頬張りながら、目の前で羽ペンを走らす彼女に聞いた。羽ペンにインクは付いていない。傍にインク壺もない。つまり、何も記されないのだが、彼女はこうして自分の記憶や考えをまとめたりする。彼女独特の記憶法である。最高の頭脳を持つ彼女だからできる技。
「柏木は?」
「見ればわかるでしょ、機密実験の計算を手伝わされてるの」
彼女の持つ頭脳はスーパーコンピューターに匹敵するほどの計算力であり、それを仕事にしている。柏木桔梗(かしわぎ ききょう)と言えば、その世界で知らないものはいない名であり、それ故、仕事は寝ていても幾つも舞い込んでくる。
数学の授業なんて必要ない、科学も物理も沢山触れてるから知っているし、英語も仕事上分からないとやっていけないから授業レベルなんて屁でもないわ。
そう言って、授業中に文字通り内職をしている。しかし、それでも通例のようにテストでは満点をたたき出す。
彼女に出来ないものは、本当にないと思う。
「あんたも早く、仕事探しなさいよ」
「これでも一応、殺生屋なんですけどー……」
俺はといえば、普通の見た目、普通の性格、普通の学力でどれをとっても月並みな生徒である。特殊な点と言えば、殺生屋をやってることぐらいだった。かといって、それがベテランと言うわけでもなく、全く駆け出しの新人だった。だから無名だし、仕事も全然入ってこない。
「そんなことは分かってんのよ。自分で依頼を見つけてくるの」
「まあ、俺に依頼がないってことは世界が平和ってことだよ」
殺生屋というのは、怨恨を買って、復讐を代行する仕事のことだ。殺生、つまり生殺し。殺しはしない。だが、依頼人の怨恨の程度、それと金額によって再起不能にまですることは可能だ。こんな暴力が表世界の仕事でないのは歴然。勿論学校にも親にも友達にも秘密だが、彼女は知っている。
見てしまったのだ、仕事の現場を。
ちょうど梅雨の時期、俺はある詐欺被害者の怨恨を買って、犯人を殺生する予定だった。犯人がパチンコ屋から出てきた後をついて、人通りのない裏路地に入った後、俺は殺生を始めた。声は出させない。気づかれるといけないし、第一、俺自身そんな声、聞きたくもなかった。黒く大きな傘をさし、俺が犯人を殺生するのを見て、詐欺被害者は泣きながら喜んでいた。
ありがとう、ありがとう、と。
詐欺被害者はどこから集めたか大金を支払って、犯人を再起不能にすることを望んでいたので、俺は殺さず生かさず再起不能にした。いつの間にか雨脚は強まり、俺はもらった金を懐にしまって、犯人をそのままに戻ろうとした。
その時、淡く濡れた桃色の傘からのぞく双眼と目が合った。
動けなかった。いつから見ていたのだろう? どうして見られたのだろう?
終わったと思った。
俺の両手は微かに血で赤く染まっていたし、足元にはぐでぐでに伸びた男が転がっている。俺は弁解の余地もなく、終わった。
彼女は少し目を細めて、「面白いわね」と、一言つぶやいた。
それからだ。彼女が学校で執拗に接触を始め、友達にならないとバラすわ、と脅してきた。俺は素直に従い、これにより妙な交際関係がスタートした、というわけである。
「あんた、それじゃいつまでたっても無職同然よ」
「まだ学生だからいいんだよ」
「退学させられないことを祈るばかりね」
小さくため息をついて羽ペンを置き、ノートを閉じた。
「まだ昼休みあるぞ?」
「終わったの、計算が。これから、結果を起こすところ。だからあんたは早く依頼でも見つけに行きなさい」
特別教室から追い出され、俺はすごすごとその辺を散歩することに決めた。
秋と冬の境目は、人を強制的に物悲しい気分にさせる。俺はこの何とも形容しがたい雰囲気が好きだ。少し肌寒くて、体内の熱をゆっくり解いていくような空気。高く晴れ渡った、秋晴れの空とか。屋上はそれを望むのに絶好のポイントだった。元気のいい一年生が屋上を走り回っている。それを見つめながら、露に濡れていないベンチを見つけ腰かけた。
「にぐろめ君?」
「月見里(ヤマナシ)先輩」
後ろから声をかけてきたのは、部活のマネージャーの月見里先輩だった。高い位置で結ばれたロングのポニーテールを揺らしながら、俺のところまで駆けてきた。
「西城先輩は?」
可愛い先輩にはお似合いの彼氏がいる。部活のすらりと格好いい西城先輩だ。
「そのことでお話があるんだけど」
笑顔がちょっと陰って、そのまま俺の隣に腰をおろした。甘いリンゴの香りが少しした。
「どうしたんですか?」
「恭一、後輩に手を出したみたいなの」
「えぇ!?」
思わず大きな声を出してしまった。俺は慌てて口を閉じる。西城先輩は格好いいし、性格もよく、勉強もできる、憧れの先輩だ。
だからファンだって多いし、後輩からも好かれる。でも、マドンナの月見里先輩が彼女だということは周知の事実だ。
ふと先輩を見ると、下唇をかみしめて、今にも泣きそうな顔をしていた。
「せ、先輩、何かの間違いなんじゃないですか? あの西城先輩がまさか……」
「でも、友達が見たって言うし、恭一に聞いたら否定しないし」
なんという証拠。一気に西城先輩に対する信用をなくした。そればかりかマイナスだ。男として、ありえない。
「先輩は、どうするんですか?」
「どうしようもないよ! 気持ちがぐちゃぐちゃで……」
とうとう先輩は泣き崩れてしまった。周りの生徒たちが、俺らに目を向ける。幸いなことにちょうど五分前のチャイムが鳴った。しかし先輩は動かない。放っておくわけにもいかず、俺は先輩が再び話すのを待った。
「にぐろめ君、どうしたらいいかなぁ」
「先輩は、どうしたいんですか?」
先輩は言葉を飲んで、それでも振り絞るように言った。
「あたしを嫌いになったのか、知りたい」
「俺が聞きますよ」
少しでも先輩の力になりたいと思ったし、尊敬している西城先輩がそんなことするはずない、と認められない頭がどこかにあった。俺が胸を張ってそういうと、先輩は泣きやんで笑ってくれた。
「本当に?」
「ええ、先輩のためにも俺が聞きます」
「ありがとう」
泣きはらした目を細めて笑顔で、手を振って去って行った。
「さて、どうするかな」
迷ったら行動だ。別に俺のモットーではないけれども。
テスト週間で悪いとは思ったけど、先輩をメールで部室に呼び出して、早速聞いた。
「そうだよ」
信じられなかった。あっさりと認めたのだ、後輩に手を出したことを。しかも、何人にも手を出したらしかった。西城先輩は悪びれもせずに俺に笑って、携帯をいじり始めた。ふつふつと怒りがわいてくる。はらわたが煮えくりかえる。
「どうしてですか。もう、月見里先輩のことが好きじゃないんですか」
「好きだけど遊びたいし、別に悪いことじゃないだろ。男なら憧れることだ」
聞きたくなかったし、伝えられないし。なんせ、抑えきれなかった。
「先輩、最低」
「へ?」
俺は怒りにまかせて、硬く握った拳で先輩の左胸を貫いていた。先輩は力に逆らわず、そのままの勢いで後ろのコンクリートの壁に衝突した。低い音と、コンクリートの壁がへこんで欠片が散る音。それと、先輩が床に落ちた、鈍い音。
すっと体の芯が冷たくなった。
コンクリートの壁がへこむほど力を入れたつもりはない。
「先輩!」
うつ伏せに倒れる先輩をおこして、顔を覗き込む。完全に気絶していた。俺が貫いた左胸は不自然にへこんでいる。
「先輩!」
一心不乱に体を揺らす。頬を叩く。反応なし。
「先輩!!」
突然先輩は目を見開き、
口から黒い塊を吐き出した。
「うわぁあ!」
一瞬血かと思ったが、違った。その黒い物体はべちゃ、と奇妙な音をたてて床に落ちた。スライムみたいな奇妙な物体で、ぐねぐねともがく様に動いていたがやがて動かなくなった。そして、酸にでも溶かされたように跡形もなく消えていく。俺はその一部始終を、瞬き一つせずに見つめていた。
何秒たっただろうか、我にかえって先輩を見ると、胸の不自然なへこみは元に戻り、規則的な寝息をするにとどまっていた。後頭部や背中を見ても再起不能になるような跡も反応もない。
ひとまず、よかった。
よかった?
何が? 先輩が生きていたこと?
全然よくないじゃないか。状況は別に変っていない。月見里先輩にとっては悪いまま。俺はどうしようもなくなって、先輩を部室に寝かせておいた。
とぼとぼと、帰路につく。結局何もできないままだったし、先輩をけがさせたし、月見里先輩には何と言ったらいいのだろう。ダメな男だ。普通より性質が悪い。
「にぐろめ君!」
その声に俺は息が詰まった。ゆっくり振り返ると、目を疑いたくなる光景。
月見里先輩と、西城先輩だった。
「にぐろめ君、ありがとう! 恭一、元に戻ったよ」
「にぐろめ、何か分からないけど、サンキューな」
じゃあね、本当にありがとう! 先輩は満面の笑みで、俺の前を行った。俺は夢でも見ているのだろうか。
とりあえず、うまく行ったことに違いはない。安堵のため息をついた。
「見てたわよ」
「わ!!」
後ろから突然、気配もなく、空気のよどみもなく、柏木が現れた。
見てた?
「先輩たちのこと、どうこうより、あの黒い物体が何かは気にならないの?」
「……ああ」
すっかり忘れていた。先輩に心血注ぎすぎて、正直どうでもよかった。
「思うに、あれはあの先輩の心にとり憑いて、良心を喰らっていたのよ」
何時になく彼女の眼は輝いていて、見たことのないぐらい嬉しそうだった。
オカルト好き、だったんだ。
「憑きものね、初めて見た」
目を細めて、その場面を思い出すように。
「しかも、もっと面白いのは、あんたにはそれを倒す力があるってこと」
「あんなの、ただの暴力じゃないか」
荒ぶる感情に任せた、力だけの暴力。ただの凶器、ただの狂気。正義でもなんでもなかった。
「そんなのどうでもいいのよ。ただ、あんたには力がある、その事実だけで十分だわ」
一度も見たこともなかった笑顔というものを俺に向けて、(彼女がそんな顔できるとは思ってなかった)
「面白いわね」
そう言って背中を叩いた。
(何が正義で、何が悪か分からない。ただ喜んでもらえればよかった)
光を忘れてしまった人
前作と同じお題で別の作品を書きました。
本当はこっちのほうが先に書き上げたんですがお題が関係ないのとあまりに厨ニ臭かったので、もうひとつ書きました。
しかし勿体無いのでアップロード。