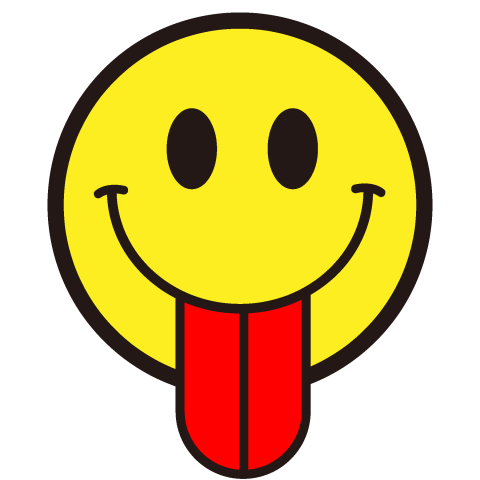
ハイボール
この「ハイボール」という作品は、野良猫が初めて書いた小説です! なので、とうぜんヘタくそです!
もちろん、手直しすれば少しはマシになると思うのですが(たぶん)、こういうテーマの作品は素人である野良猫には
むずかしく、やはり納得のいく結末は書けないだろうと思うのです。ゆえに、あえて手直しは致しません(改稿版を執筆
する予定もありません)。
このような不完全な作品ではありますが、この物語を豪雨災害や震災で命を落とされたすべての犠牲者および遺族の
方々に捧げたいと思います。
野良猫 2019 7/16
***** 金曜ロードショー「ハイボール」 *****
https://www.youtube.com/watch?v=wCDiRGUTfq0
オープニング
https://www.youtube.com/watch?v=mQT1tkgM_ks

ここ数日、雪こそは降らないが、薄暗い曇りの日が続いてた。
そして時折降る俄雨が、日陰に溶け残った雪を道連れに、アスファルトの上をあてもなくただ流れていた。
――2012年3月、東京・墨田区。
朝の通勤時間帯。人通りの少ない裏道を、一台の黒い外車がゆっくりと走っていた。七十七年型ファイヤーバード・トランザム、通称「イーグルマスク」と呼ばれる車。
ハンドルを握っているのは五十代前半の中年の男。片手でハンドルを操作し、上着の胸ポケットからタバコを取りだす。
「あれ? 一本しかねえや」
カラのパッケージを握りつぶすして助手席のシートの上に放り投げると、男は口に銜えた最後の一本に火を点けた。前方のT字路を右に曲がると、ちょうど小さな酒店の前にタバコの自動販売機を見つけた。男が店の前に車を停める。すると、まるで狙いすましたかのようなタイミングで一人のサラリーマンがやって来て、先を越されてしまった。
「あ」
男は苦笑した。今日は朝からついていない。彼はポケットの中の小銭をあさりながら、サラリーマンの後ろに並ぶのであった。
そんな男をよそに、サラリーマンはサイフの中のキャッシュカードや電気店などの会員カードの中に埋もれているであろうタスポを、のんびりと探していた。その様子を後ろに並ぶ例の男がもどかしそうに眺めている。一体いつまで待たせるつもりだ。男は口に含んだ紫煙をいまいましそうに排出しながら、フィルターの部分を親指ではじいて灰を落とした。
そして、ようやくタバコを買い終えたサラリーマンがふと後ろの男を振り返った。
「あっ」
彼は、まるで尻を針でつつかれたように驚いた。
「おっと、遅刻だ」
わざとらしく腕時計を見ると、彼は慌てて逃げるように走り去って行った。
「なんだよ、失礼なヤツだな」
サラリーマンがおどろくのも無理はなかった。黒い上下のスーツに黒いコート、サングラスにオールバック。しかも銜えタバコ。両手をコートのポケットに突っ込んで、不愉快そうに眉間にしわを寄せて立つ姿は、まさにヤクザそのものであった。
男はタバコを足元に落として踏み消すと、走り去るサラリーマンの後姿を見送りながら自販機のボタンを押した。
「あれ? なんだよこれ」こんどは男が目を丸くして驚いた。「ロングピース押したはずなのに……」
取り出し口から出てきたのはマイルドセブン。どうやらサラリーマンに気をとられてボタンを押し間違えたらしい。まあ、しかたがない。買い直そう。これはあとでとり換えてもらえばいいさ。そう胸の中で呟くと、男はポケットから再び百円玉と十円玉を数枚とり出し、コイン投入口へ放り込んだ。ボタンを押し、取り出し口からロングピースをつかみとる。と同時に、いつものクセで、お釣りの返却口にふと目をやる。すると、そこにはさっきのサラリーマンが忘れていったお釣りがあるではないか。とるべきか、とらざるべきか。彼は、辺りをキョロキョロと見回し、誰も見ていないことを確認した。そして、一度わざとらしく咳払いをする。
「あ、お釣り忘れるとこだった」
男はサラリーマンのお釣りをポケット押し込むと、悠長に口笛を吹きながら車に乗り込むのであった。そんな男のなさけなさを憐れむかのように、空から涙のような雨がポタリポタリと、フロントガラスにこぼれ落ちてくるのであった。
「降ってきやがった」
男は鬱陶しそうにワイパーを動かすと、バックミラーにぶら下がる『舌を出したニコちゃんマークのぬいぐるみ』にチラリと目をやった。 ピンポン玉ほどの大きさの小さなぬいぐるみだ。
「オレのことが嫌いか?」
すると、ニコちゃんマークのぬいぐるみは、男をからかうようにユラユラと揺れ始めるのであった。
「フッ」
男は肩で軽く笑い、何度か首を横に振った。そしてゆっくりと車を走らせ、去って行くのであった。
午後になると雨は止み、雲の切れ間から陽の光が射しはじめた。ここは旧中川沿いにある小さな有限会社、泉田自動車整備工場。従業員は社長を含めて四人。そこに、東日本大震災で被災し、津波で家を流され、一人東京で暮らす青年が働いていた。須賀ケンジ。岩手出身の三十一歳の青年である。幸いにも近くに高台があったため、家族は津波から逃れる事ができたのだ。しかし、実家や父親の経営する自動車整備工場は津波で流されてしまった。
ケンジがここへ入社したのは2011年6月。東日本大震災からもうすぐ一年が経とうとしていた。
「ケンジ、そこのトルクレンチ取ってくれ」
彼に声をかけたのは、同じ三十代の青年、吉行オサム。修理中の車のボンネットを開け、エンジンルームを覗き込みながら左手を差し出して催促している。
「これか?」
「おう、サンキュー」
この吉行と言う男は、気さくで明るく、誰とでも仲良くできるタイプだが、お調子者で口が軽いのが玉に瑕であった。
「それにしても、あの人はいつもサボってばかりだな」
工場の右端にある事務所の方を見ながらケンジがグチをこぼした。事務所といってもプレハブ小屋のようなものだが、窓は大きく、作業場からでも事務所の中の様子はよく見えた。そこには社長と一緒にテレビの競馬中継に夢中になっているもう一人の従業員、田崎ジョージの姿があった。齢は四十代半ばのアゴヒゲを生やした無愛想な男で、社長とは競馬仲間である。
その競馬好きの社長の名は泉田テツオ。彼も四十代後半の男で、金髪のオールバックにメガネをかけている。そして事務所にいるときは大抵、赤えんぴつを耳にはさんで競馬新聞をながめていることが多い。
「まあ、ウチはヒマな方だから、オレたち二人だけでも十分なんだけどな。ケンジ、ちょっとそこ押さえといてくれ」
二人が作業をしていると、そこへ例の黒い外車、イーグルマスクがやって来た。この整備工場は外壁も屋根もトタン造りで、外壁のない工場正面側には小さな駐車スペースがあった。そして、そこに駐車してあるケンジの車の後ろに並ぶように、例のイーグルマスクが止まったときのことである。
「あ」吉行が思わず声と上げた。と、同時に「カチャン」という空き缶をふみつぶしたような音が聞こえた。
「ケンジ、またおまえの車だぜ」彼はおかしそうに笑いながらケンジの肩をたたいた。
イーグルマスクに追突されたケンジの車が、軽く震えるように揺れている。そして男はイーグルマスクから降りると、ケンジの車のへこんだリアバンパーを気まずそうに軽く撫でるのであった。
「これで三度目ですよ、浩さん」ケンジが腰に両手を当てて、呆れたように言った。
男の名は若林浩三。ヤクザではないが、堅気でもない。見かけはコワモテだが、どこか憎めないところがある不思議な男だ。
「わりィ」浩さんが照れくさそうに頭をかいた。「どうもブレーキの調子がよくねぇみてえだ」
吉行の車が一回、ケンジの車が二回。たぶんブレーキのせいではないだろう。
「浩さんのウデが悪いんじゃないんですか?」
ケンジは茶化すように言った。
「ほう」と、浩さんが肩で笑いながらタバコに火を点けた。「ケンジ、お前も言うようになってきたじゃねぇか。ええ? それじゃ、ブレーキの修理、たのんだぜ」
彼はタバコをプカプカとふかしながら、事務所の方へ歩いて行った。
「おう、テツ。ポーカーやるぞ」
浩さんは社長を“テツ”と呼ぶのであった。浩さんは週に二、三度はここへ来る。ただポーカーをするためにだ。いつも社長とジョージの三人でポーカーをするのだ。賭ける金額は二千円、浩さんは負けるたびにテツとジョージに二千円づつ払う。逆に浩さんが勝てば二人が二千円づつ払う。ただ、決まって負けるのはいつだって浩さんなのだが。
「どうせ今日も負けだよ」
吉行がイーグルマスクのタイヤを外しながら呟いた。
「懲りない人だな」
ケンジもため息混じりに言った。
「でもよ、競馬とかマージャンはけっこう得意らしいぜ」
「博打だけでよく生活できてるよ」
もう一度軽くため息を漏らすと、ケンジは作業をしながら、事務所でポーカーをする浩さんにチラリと目をやった。
「あれから一年、か……」
ケンジは震災のあった日のことを考えていた。そして、浩さんと初めて会ったときのことを……。
――2011年6月。
ケンジが泉田自動車整備工場に入社して十日目の、ある小雨がパラつく日のこと。彼が吉行と作業をしていると、一台の黒い外車がやって来た。運転席から降りてきたのは中年の男で、齢は五十代前半、黒い上下のスーツ、そしてサングラスにオールバック。誰もが思い浮かべる典型的なヤクザの姿だ。
その男、つまり浩さんはタバコに火を点けると、まっすぐケンジたちの方へ歩いてきた。
「吉行、ちょっと見てくんねえか? この前、代行に頼んだヤツが乱暴な運転しやがってよ、なんだかギアの調子がワリィんだよ。おまけにバンパーまで擦りやがって。とんでもねぇヤローだよ、まったく……」
言い終ると、彼はケンジに気づいた。
「おう、新入りか?」
「ああ」
答えたのは吉行だった。「今月入ったばっかなんだよ」
そして、やや緊張した面持ちでケンジが挨拶をした。
「ど、どうも」
彼はケンジに軽くうなずくと、再び吉行に向き直った。
「そうか。ところで、ユウタはどうした?」
「あいつは社長とケンカして辞めたよ」
つまり、ユウタが辞めて空いたところに、ケンジが来たのだ。ユウタは二十代前半で、性格が真面目すぎたせいか、仕事をサボって社長とジョージが浩さんとポーカーをやったり競馬の話ばかりしてるのが気に入らなかったらしい。
「まあ、いつかはこうなるんじぇねえかと思ってはいたんだがな」彼はケンジをチラリと見て苦笑した。ケンジも口元に作り笑いを浮かべて見せた。そして彼はサングラスを軽く指で押し上げると、再び吉行に顔を向けた。「ジョージは?」
吉行が事務所の方を目で指した。
「じゃ、オレの車、たのんだぜ」
彼は事務所の方へ去って行った。なんとなく不安そうな表情で「その男」の後姿を見送りながら、ケンジは吉行に尋ねた。
「知り合いなのか?」
「ん? ああ、浩さんか?」
「浩さん……て言うのか。何してる人なんだ?」
「え? さ、さあ。自分で聞いてみれば?」
「やだよ。ヤクザだったらどうすんだよ」
もちろんケンジは冗談で言ったのだが、実は半分本気でそう思っていたのだ。
「あの人がヤクザなら警察はいらねーよ?」と、吉行が吹き出しながら言った。「そうだ、今日終わったら飲み行くか? 昼行灯って居酒屋に、いつも来るんだよ。あの人」
東武亀戸線沿いの細い脇道を入ったところの、あまり目立たないところに昼行灯はあった。営業時間は夕方の5時から深夜1時ぐらいまで。あまり早い時間には滅多に客が来ることはないが、9時近くになると、すでに二、三軒はハシゴしてる様子の酔った客が徐々にやって来るのであった。
カウンター席に腰掛けた店主が暇そうに新聞を眺めていると、そこへ仕事帰りのケンジと吉行がやって来た。
「いらっしゃい。おう、吉行か」
「浩さんは?」
吉行が聞くと、店主は外したメガネをカウンターの上に置いて「もうそろそろ来るころだ」と、新聞をたたみながら答えた。
店内はそれほど広くはなく、カウンター席、そして壁際には小さなテーブル席が二つあるだけだ。
それにしても、あの浩さんという男は、一体どういう人なんだろうか? 顔には出さなかったが、ケンジは少し不安だった――ウチには営業で来たのかと思いきや、いきなり社長とポーカーをはじめて、終わるとすぐに帰ってしまった。そもそもサラリーマンやセールスマンがあんな車で来るわけもないし。と、言うことは、やっぱりヤクザだろうか――そんなことを考えながら店の入り口で佇んでいる彼に、店主が目をやった。
「友達か?」
「ああ、今月からウチで働いてんだよ。ケンジってんだ。ケンジ、店主の坂井さんだ」
「どうも」
カウンターの向こう側の店主にケンジが挨拶をした。
「まあ、座んなよ」と、店主は笑顔で言った。「何にするね?」
「そうだな。とりあえず……」
吉行がビール――大ジョッキ――を注文した。ケンジは焼酎のお湯割り。つまみは適当にまかせた。
店主の坂井一郎は六十代前半で、伸びきった坊主頭はほとんどが白髪であった。以前は夫婦で経営していたらしいが、五年前に女房に先立たれてからは一人で店を切り盛りしている。
「今日は遅いな。浩さん」
店主が入り口とは反対側の壁にかかる時計に目をやった。二人が飲み始めて20分が経とうとしていた。吉行はもう4杯目を空けようとしている。ケンジはまだ2杯目に口をつけたところだった。
「どうした、ケンジ。どんどん飲めよ」
吉行はすでに酔い始めていた。
「お前のペースにはついて行けんよ」
ケンジは呆れたような笑みを浮かべた。
と、そこへ客が二人やって来た。浩さんだ。もう一人の男は、どうやら浩さんの連れのようだ。
「いらっしゃい。おう、マサも一緒か」
店主が浩さんと一緒にいる男をマサと呼んだ。齢は四十前後、身長は浩さんより少し高い。そして金髪のモヒカン頭に白いタンクトップ、白のジャージのズボン、素足にサンダル、左のウデには江戸時代の罪人がしていたようなイレズミがある。この人たちは、いったい何者なのか。あまりかかわらない方がいいのではないのか。ケンジはますます不安になった。
浩さんがハイボールを注文しながら吉行の隣に座った。
「おう、吉行。今日はパチンコは休みか?」
「まあね。ケンジが浩さんと話がしたいって言うから」
「ケンジ?」
浩さんがカウンターに身をのり出すようにして、吉行のとなりに座るケンジに目をやった。マサは浩さんのとなりで熱燗とつまみを注文している。
「ああ、テツんトコの新入りの」
「あの、須賀ケンジです。よろしく」
「若林浩三だ」
「カシラ、お知り合いで?」
このマサという男は、なぜか浩さんをカシラと呼ぶ。
「こいつはマサオだ」浩さんが紹介した。「マサって呼べばいい」
「アッシは沢田マサオってェ、焼きそばの屋台をやってるケチな野郎で。なにぶん、よろしく」
と、マサはなぜか江戸っ子口調で話す、変わった男なのであった。
「よ、よろしく」
軽く戸惑いながらケンジも挨拶すると、マサは笑顔でうなずいてみせた。外見や言葉使いからは想像できないような笑顔。このギャップの激しい男は、悪人なのか善人なのか。ケンジにはよく分からなかった。
そして、しばらく飲みながら浩さんと話をするうちに、浩さんは想像していたような人間ではないということが分かった。人間、見かけで判断してはいけないということだ。
「ところで」と、ケンジが訊いた。「浩さんは仕事は何を?」
浩さんに全員の視線が一斉に注がれる。そして静かな店内は、ラジオから流れてくる演歌が独特の雰囲気をつくり出していた。
「……サラリーマン……」
ややうつむきながら、蚊の鳴くような小さな声で答えると、浩さんは気まずそうに顔をしかめてタバコに火を点けた。
「え? なんて言ったんです?」
ケンジが聞き返した。
「サラリーマン……かな?」
浩さんは曖昧に答えると、やはり気まずそうにハイボールを一口飲むのであった。
「へ~。いつヤクザ辞めたんスか?」
吉行が薄ら笑いを浮かべながら茶化すように言うと、思わず浩さんがハイボールを噴き出した。そして店主も吹き出した。マサはお猪口を持つ手を震わせて笑いを堪えている。
「おいおい、人聞き悪ぃこと言うなよ」と、戸惑う浩さん。「まあ、強いて言えば、ポーカーに賭けマージャン、競馬に競輪、たまに“ノミ”もやるが、それがオレの仕事かな?」
「へえ。それで、今の仕事は長いんですか?」
ケンジも茶化すように尋ねると、浩さんは「まさか」と、照れ笑いを浮かべながら、サングラスを指で押し上げるのであった。
「オレだって昔は普通の仕事をしていたさ」
「まあ、人にはそれぞれ事情ってもんがあるってことだよ」と、店主。
「そう言うこと」吉行もうなずいた。「お前も津波で家を流されたりしなかったら、ウチのような会社で働くこともなかったろうにな」
今度は全員の視線がケンジに注がれた。
「吉行」
ケンジは吉行に首を横に振って見せた。このことを知ってるのは吉行だけだった。社長のテツも知らないことだ。と言うのも、テツとの面接時間は1分程度で、ロクに履歴書も見ずに名前だけ聞くと、彼は「明日から来い」の一言で済ませてしまったからだ。もちろんケンジが岩手出身と言うことも知っていたが、テツにとってはそんな事はどうでもよかったらしく、なにも聞かれることはなかった。そして吉行も、それほど詳しくは聞いていないようだった。
「あ、すまん。言っちゃまずかったか?」
別に吉行は悪気があって言ったのではなかった。ただ口が軽いだけなのだ。そして、酒の入った吉行の口はさらに軽くなっていたのだ。
「それじゃ、お前も……」
浩さんはサングラスを外すと、目を細めた。
「お前も?」ケンジは眉をひそめた。
「いや……」
浩さんは慌ててサングラスをかけなおしながら、一度咳払いをして続けた。
「故郷は、岩手か?」
「ええ。陸前高田……。自分の育った街は、もうありませんが……」
分かりきってることだったが、言葉に出してみると、妙に説得力があった。そうだ。もうないのだ。ケンジは心のどこかで否定し続けていた現実を、少しづつ受け入れ始めていた。
「それで、家族は無事だったのか?」
「ええ、なんとか。両親は埼玉の親戚の家に避難してます」
「兄弟は、いねえんですかい?」
マサが言った。
「ええ。一人です」
「そうか……」と、浩さんが軽くうなずいた。「で、お前は、どうして東京に?」
「いろいろ、一人で考えたいこともあって。それで……」
「なるほどな……」
浩さんはケンジの気持ちを理解したかのように、相槌をうった。
「まあ、命が助かっただけでもめっけもんだよ?」店主が焼き鳥を炙る手元を見つめながら言った。「家はまた建てればいいが、死んじまったらそれもできねえ。お前さんはまだ若ぇし、がんばればいずれ家だって建てられる。親孝行しねえとな」
「ええ、そうですね」と、ケンジはしみじみとうなずいた。
ケンジはこのことは他人に話すつもりはなかったのだ。しかし、なんだか少しだけ心が軽くなったような、精神的に楽になったような、とにかく孤独感のようなものがなくなったように感じていた。
「まったく、神様も理不尽なことをしなさる」と、マサが虚しくため息をついた。
「神様、か」浩さんもため息を漏らした。「生きてりゃ楽しいこともあるかも知れねえが、いずれ親兄弟と死に別れ、最後にゃあ自分も死ななきゃならねえ。ようするに、命そのものが理不尽なんだよ」
「ちげぇねえ」と、マサは二、三度深くうなずいた。
ケンジもなんとなくそう思うのであった。浩さんはヤクザのようなことをしているが、それには何かワケがあるに違いない。しかし、それを聞いても浩さんは答えてはくれないだろう。さっきのサングラスをはずした時の浩さんの目。あの哀しみの色に染まった瞳は、一体何を見てきたのだろうか?
ハイボールのおかわりを注文すると、浩さんはケンジに向き直り、静かに語りかけた。
「まあ、そう言うことなら何でも言ってくれ。力になるぜ?」
「浩さん……。ありがとうございます」
ケンジは見かけで浩さんを判断した自分に嫌悪感を覚えていた。そして、心の中で浩さんに謝るのであった。
「じゃあ、一万だけ貸して。月末まで」と、お調子者の吉行。
「なに?」と、あきれたように浩さんが言った。 「誰もテメエの力になるとは言ってねえよ。それによ、知ってんだろ? オレがカネ持ってねえことぐれえよ。こっちも生活苦しいんだよ? それをテメエときたら、いつもいつもパチンコ代せびりに来やがって。挙句の果てに人をヤクザ呼ばわりしやがる。どっちがヤクザだ? ヤクザはテメエの方じゃねえか」
「ちげぇねえ」
マサが深くうなずくと、店内にドッと笑い声が響いた。ケンジはこの日、震災や津波のことを忘れて久しぶりに楽しい酒を飲んだのであった。
――それが浩さんとの出会いだった。
「やれやれ。予備のパーツがあってラッキーだったな」
肩のこりをほぐすように、吉行が首を回した。
「ああ。外車は手間がかかるよ。古いと尚更ね」
ケンジはイーグルマスクのボンネットをポン、と軽く叩いた。
「来たぜ」
吉行が事務所の方をアゴで指した。浩さんがいつものように両手をポケットにつっこみ、銜えタバコで少しうつむきながら歩いてくる。今日も負け。
「相変わらずですか?」
ケンジが皮肉っぽく笑うと、浩さんも皮肉な笑みを口元に浮かべた。
「まあな。じゃ、世話んなったな」
そう言うと、浩さんはイーグルマスクに乗り込み、走り去って行った。

4月。泉田自動車整備工場。
ケンジと吉行が作業をしていると、いつものように浩さんがイーグルマスクでやって来た。
「今日はジョージさん休みっスよ」
事務所へ行こうとする浩さんに、4輪駆動車の下にクリーパー――キャスター付きの寝板――を使って上半身だけもぐり込ませて作業をしている吉行が声をかけた。
「休み? そうか……。二人でポーカーやってもつまんねえしな……」
浩さんは上着の胸ポケットからタバコを取り出しながら言った。その時、胸ポケットから一枚の写真が滑り落ちた。
「何か落ちましたよ?」
ケンジが写真を拾い上げた。そこには、一人の女性、そして小さな男の子と一緒に写る浩さんの姿があった。
「これは……」
「あっ」
浩さんはケンジから写真をひったくると、慌てて上着の内ポケットにしまい込んだ。
「昔のな。別れた女房だよ……」
小さな声でささやくように言うと、浩さんは淋しげな笑みを口元に浮かべた。
「さてと。しゃーねえ。マージャンでもやりにいくべえ」
浩さんはイーグルマスクに乗り込むと、ゆっくりと走り去って行った。
「あれ?」吉行がクリーパーを滑らせて出てきた。「浩さん帰ったの?」彼は立ち上がると、凝りをほぐすように肩や首を回した。
「ああ」
思えば、浩さんは昔の話をほとんどしたことがない。結婚していたことも、いま初めて知ったのだ。どんな仕事をしていたのかも分からない。きっと、今のヤクザな生活をしているのも、なにかよほどの訳があってのことなのだろう。
「なあ、吉行。浩さんて昔、なにやってたんだろうな。仕事」
「さあな」と、吉行は肩をすくめた。「オレがここ来たときには、社長とはもう知り合いだったみたいだからな。はじめからヤクザやってんじゃないの?」
「浩さんがヤクザなら、警察はいらないんじゃなかったのか?」
「まあな」と、吉行は苦笑した。「でもよ、堅気じゃないことだけはたしかだぜ?」
確かに浩さんは、お世辞にも堅気とは言えない。だが、ケンジはなぜか浩さんを放っておくことができなかった。浩さんがサングラスをはずしたときに見せた、あの哀しい眼差しが、ケンジの目に焼き付いて離れなかったのだ。
そして仕事が終わると、ケンジはなんとなく昼行灯へ行ってみるのであった。
店内の客はケンジ一人。
「オヤジさん」と、ケンジが訊いた。「知ってました? 浩さん、むかし結婚してたって……」
まな板の上で野菜を刻む手を止めて、店主がハッとしたように顔を上げた。
「じゃあ、話してくれたのかい? 神戸に住んでた頃の話」
「神戸に住んでたんですか? 浩さん」
店主はやはり浩さんの過去を知っているようだ。ケンジはあの写真のことを店主に話してみた。そして、ぜひ自分にも浩さんの過去を教えてくれと頼んでみた。
「そうだったのかい。実は、浩さんはな……」
言いかけたが、話していいものかどうか、店主は少しためらった。しかし、すぐに決心したように「まあ、お前さんなら話してもいいだろう」と、一度軽くうなずき、ゆっくりと語り始めた。
「この話はマサも吉行もしらねえことなんだが……」
店主の話によれば、浩さんは昔、神戸に住んでいたらしい。当然、仕事もしていた。消防士をしていたのだ。とても今の浩さんからは想像できない姿だ。消防士は二十四時間勤務のところが多く、一日勤務して、一日休む。そして、ちょうど浩さんが当番の日に、阪神大震災が起こったのだ。浩さんの家は火事になり、妻と一人息子は逃げ遅れ、助からなかった。
「いつだったか、競馬で大損して自棄酒を飲んだことがあってな。そのときに、酔った勢いでそんな話をしたことがあったんだ。今の話は、誰にも話さないでくれよ? 浩さんも、あまり知られたくねえみてえだし。あの人は、誰にも心を開いちゃいねえのさ」
店主が言い終わると、そこへ浩さんとマサがやって来た。
「オヤジ、いつもの。それと焼き鳥」
「アッシは熱燗。つまみは天ぷらと煮物を」
二人は注文すると、カウンター席に座った。
「なんだ、具合でも悪ぃのか?」
浩さんはケンジの様子が少しおかしいことに気がついた。
「え? いえ、別に……。今日は少し、飲みすぎたかな」と、ケンジはとぼけてみた。「じゃ、オレはそろそろ失礼します」
「なんだ、もう帰るのか? じゃあ、代行来るまで一杯だけつき合えよ」
ケンジも浩さんも、昼行燈に来るときは、いつも車だった。店の通りを挟んで向かい側にある小さな駐車場に止めているのだ。
「それじゃ、一杯だけ」
グラスの中の焼酎に映し出されたもう一人の自分を見つめながら、ケンジは考えていた。まさか浩さんも自分と同じ被災者だったとは。いや、自分は故郷を失ったが、家族は無事だった。だが、浩さんは家族を亡くし、未来を失い、心に深い傷を負っているのだ。ケンジは、あのとき浩さんが見せた哀しい眼差しの意味を、ようやく理解することができたのだった。
「あ、代行が来たみたいです。それじゃ、オレはこれで」
そして勘定を払い、ケンジは店を出た。
「震災、か」
複雑なため息を漏らし、ふと夜空を見上げる。果てしなく深い海の底のような暗い天に、真珠のような満月が冷たく輝いていた。
5月になって二度目の月曜日。今朝は夕べからの雨が降り続いていた。
ケンジがいつも通り車で出勤する。そしていつもと同じ道をしばらく走っていると、前方の路肩に白い軽自動車がハザードランプを点灯させて止まっていた。運転手はボンネットを開け、傘をさしながらエンジンルームを覗き込んでいる。三十代の若い女性だ。ケンジは一旦彼女の車を追い越し、路肩に車を停めて降りると、女性に声をかけた。
「どうしました?」
エンジンルームを覗き込んでいた女性が、ふと顔を上げた。
「それが、急にエンジンが止まっちゃって……」
彼女は不安げな表情で腕時計に目をやった。午前7時44分。ケンジはエンジンルームを覗いて、一通り軽くチェックしてみた。
「たぶん、燃料ポンプか点火プラグかな……」
「え?」
ケンジがボンネットを閉め、女性に向き直った。
「この先の整備工場に勤めてるんですよ。もし、よろしければウチでみてみますけど……」
「よかった」
彼女はホッと安堵のため息をもらした。そして、ケンジに車を任せることにした。
「今、レッカーを呼びますんで」
ケンジは吉行にレッカーで来るよう、ケータイで連絡した。整備工場からここまでの距離は約七百メートル。数分で来るはずだ。
彼女は一旦車に戻り、ケータイを耳にあてながら腕時計をチラチラと気にしていた。会社に連絡しているのだろう。
しばらく待つと、吉行がレッカーでやって来た。雨はまだ止みそうにないが、だいぶ小降りになっていた。ケンジと吉行が手際よく作業をする。そんな二人の様子を、彼女は傘をさしながら、ただ見守っているのであった。
そして作業が終わると、彼女が思い出したように「あっ」と声を上げた。
「どうかしたんですか?」
ケンジが雨でぬれた上着を手ぬぐいで拭きながら、彼女の方を振り向いた。
「あ、いえ、タクシー呼ぶの忘れちゃって……」
彼女が慌ててショルダーバッグの中をひっかきまわすようにケータイを探し始めた。
「オレが送りますよ」
「え? でも、ご迷惑じゃ……」
「これも仕事ですよ」
ケンジは彼女に微笑むと、両手をポケットに突っ込んで、レッカー車の後輪を退屈そうにつま先で小突いている吉行を振り返った。
「吉行、オレは彼女を送っていくから、社長には少し遅れるって言っておいてくれ」
「わかった。気をつけてな」
そして吉行は彼女に挨拶をすませると、ゆっくりとレッカーを走らせ去って行った。
「それじゃ、行きますか。どうぞ」
ケンジが助手席のドアを開けた。
「でも、本当にご迷惑じゃ……」
「遠慮はいりませんよ」
ケンジが微笑むと、彼女も笑顔でうなずいて応えた。
「どちらにお勤めで?」
ハンドルを握ると、ケンジが彼女に尋ねた。
「銀行に……。明治通り、東向島近くの……」
この若い女性は、ある銀行の支店に勤めているらしい。ケンジは銀行へ向け車を走らせた。
「初日から遅刻、か……」
ため息混じりに彼女が言った。
「初日? 入社したばかりなんですか?」
ケンジが尋ねると、彼女はかすかに笑みを浮かべて首を横に振った。実は、彼女は今日から事務担当役席、つまり窓口や伝票処理、納出などを行う部署の責任者として初出勤する、と言う意味だった。
「そうだったんですか」
管理職は大抵8時までには出勤しなくてはならないらしい。今、午前7時57分。彼女の銀行まではどう急いでも、あと10分近くはかかるだろう。
「オレがもう少し早く作業をしていれば……。本当に、申し訳ないです」
「そんな。私の方こそ、ご迷惑をおかけしたみたいで……。私、いつもこうなんですよ。今日も早起きして準備は万全だったつもりなのに、車が故障して……」
そして彼女が軽くため息を漏らすと、ケンジは少しでも元気づけようと思ったのか、軽く冗談を言って見せた。
「家を留守にしたとたんに宅急便が来たり、席を外した時に限って大事な電話がかかってきたり……。かといって、スムーズに行けば予定変更、計画中止。よくある話です」
「たしかに、そうですよね」と、彼女が可笑しそうに笑った。「やっぱり、どんなことでも、人間の思い通りにはならない、と言うことなのかな……」
「そうですね……。オレも、そう思います……」
ラジオのニュースが終わると、アルトサックスの音色が聞こえてきた。Autumn Leaves(枯葉)。
「枯葉、か」
「知ってるんですか? この曲」
彼女が意外そうな表情でケンジを振り向いた。
「ええ。ジャズとかビパップはよく聴きますから」
「偶然ですね。私もジャズのファンなんですよ」
鈍色の空は相変わらず泣きっぱなしだが、趣味の話に花を咲かせる二人の顔に笑みは絶えなかった。
「あ、ここです」
ケンジが銀行の前に車を停める。午前8時06分。ケンジは可能なかぎり急いだつもりだが、当然、間に合いはしなかった。
「オレが機転をきかせて早めにタクシーを呼んでれば……。申し訳ないです」
「そんな。わたしの方こそ、わざわざ送っていただいて、かえって申し訳ありませんでした」
彼女ドアを開けた。車を降りようとしたとき、ケンジが呼び止めた。
「あ、あの……」
車を降りようとする彼女を、ケンジが呼び止めた。
「え?」
「連絡先を……」
「あ、そうだった」
彼女はショルダーバッグからメモ帳をとりだすと、適当に開いたページの上でボールペンをせわしなく走らせた。
「それじゃ、よろしくお願いします」
彼女がメモしたページを破り取ると、それをケンジに渡した。
「たぶん、一週間ほどかかると思うので、あとで代車を手配しときます。それと、何かありましたら、ここに連絡を」と、ケンジも名詞を渡した。
ケンジが微笑むと、名刺を受け取りながら彼女も微笑んだ。
そして、バックミラーに彼女の姿を映しながら、ケンジはゆっくりと車を走らせるのであった。
数日後。泉田自動車整備工場。昼休み。
「よし、『たんぽぽ』行くか」
オイルで黒く汚れた軍手を脱ぎ捨てながら、吉行がケンジに声をかけた。
「ああ」
たんぽぽ。ケンジと吉行が、ほぼ毎日通う小さな食堂で、工場から歩いて数分のところにあった。
「いらっしゃい!」
店に入ると、店主の松村清二が威勢よく迎えた。歳は浩さんと同じぐらいで五十代前半。さほど太ってはいないが、頭の毛は少し薄かった。
「いらっしゃいませ」
そしてもう一人、そう言って迎えたのは、いつものおばさん、つまり清二の女房ではなかった。清二の一人娘で都内の女子大に通う松村美咲。
「あれ、美咲ちゃん? おばさんはどうしたの?」
吉行が尋ねると、清二がネギを刻みながら答えた。
「あいつは夕べ、階段から転げ落ちてな。ウデ折っちまいやがったのさ。今日はおとなしく二階で寝てるよ」
「そうだったんですか……。後で、改めて見舞いに来ますよ」と、ケンジが心配そうに言った。
「すみません、気を使わせちゃって。でも、ほんとに大丈夫ですから」
美咲が食器を洗いながら言った。
「いつものことだよ」清二がボヤき始めた。「あいつはそそっかしくていけねえ。前にも足折ってんだよ。階段から落ちてな」
「そういや、そんなこともあったな」と、吉行が笑った。
そして二人が席に着くと、清二が「美咲、そこはいいから、早く注文とれ」と、歯痒そうに促した。
「あー、忙しい」と、美咲もボヤきながら注文を取った。
吉行が味噌ラーメン・チャーハン・ギョーザのセット。チャーハンは大盛りだ。ケンジは中華そばのセット。やはりチャーハンは大盛り。そして注文が終わると、ケンジはケータイをいじり始めた。
「最近、よくケータイいじってるな?」吉行がタバコに火を点けながらいった。「誰かとメールでもしてんの?」
「ん? あ、ああ。まあな」
「そういや、この前の銀行に勤めてるっていう彼女、なんていったっけ? たしか、萩野涼子ちゃん、だっけ?」
「鋭いな」と、ケンジがメールを打つ指を止め、呆れたように苦笑した。「どうして分かった?」
実は、あの朝の件がきっかけで、ケンジは彼女、つまり萩野涼子と付き合い始めていたのであった。
「カマをかけただけだよ」と、吉行も苦笑した。「うまく出し抜きやがって。後でオレにも誰か紹介しろよ?」
二人がそんな話をしていると、美咲が料理を運んできた。
「あれ?」
ギョーザが二皿づつある。
「美咲ちゃん、ギョーザ、一皿多いよ?」
吉行が聞くと、それに清二が答えた。
「女房のことで迷惑かけちまったからな。店のおごりだよ」
「さすが。やることシブいね」と、吉行がからかうような口調で言った。
「褒めてくれるのはいいがよ、お前のツケ、だいぶたまってんだよ。それ払い終わるまで、お前は明日から中華そばセット以外は遠慮してもらうぞ。それも、ギョーザ抜きでだ」
中華そばセット。この店で一番安いセットメニューである。
「ひでえ。それでセット料金取るのかよ?」
「だからよ、ギョーザの分でツケを少しずつ払ってもらうってことだよ。ラーメン単品よりはマシだろ? チャーハンは大盛りにしてやってもいいがな」
吉行はいつもパチンコで金欠ぎみなのだ。たんぽぽだけではなく、昼行灯にもだいぶツケがたまってるらしい。
「やれやれ」と、吉行はふてくされた。「当分、ギョーザはお預け、か」
この男も浩さんと同じく、よく生活が出来てるな、と、つくづく思うケンジなのであった。
6月。第二土曜日。泉田自動車整備工場は、第二・第四土曜日は休みである。
ケンジは綿糸公園へと出かけた。涼子とデートの約束をしたのだ。このところ雨の日が続いていたが、幸いにも今日の空は青く澄みきっていた。そして、いくつもの引きちぎった綿のような雲が、消えそうになりながら風に乗って流れていた。
ケンジが待ち合わせの場所に着いたのは、約束の午前10時より15分ほど早い、午前9時43分。涼子はまだ来ていないようだ。噴水の周りでは、小さい子供を連れた親子が楽しそうにはしゃいでいる。
近くのベンチで足を休めると、ケンジはその親子を眺めながら子供の頃を思い出していた。近所の公園で友達と遊んだ事、家族で海で泳いだり、釣りもした。だが、その故郷はもうない。たとえ元通りに復興したとしても、それは自分が育った街ではない。ようするに、レプリカのようなもの。義援金とか、いくら大金を積もうが以前と寸分違わぬ同じ街、そして津波で亡くなった多くの犠牲者は戻っては来ない。ケンジは噴水をジッと睨みつけていた。噴水を津波にダブらせているのだろう。
「ケンジ」
名前を呼ばれ、ケンジはハッと我に返った。声をかけたのは涼子だった。
「ごめん。待ちくたびれた?」
「いや」ケンジはとっさに作り笑いをして見せた。「オレもさっき来たところだ」
手首をまわして腕時計を見る。9時55分。いつの間にか、あれから10分も経っていた。
「ねえ、どこ行こうか」
「そうだな……」
ケンジはゆっくりとベンチから腰を上げると、公園の隅でサッカーをする小学生たちを見ながら言った。
「少し、歩きながら考えよう」
今日は土曜日ということもあり、小さい子供を連れた家族の姿が多く目立った。ケンジは、ふと想像してみた。家族と楽しそうに過ごす浩さんの姿を。
「涼子は、家族は東京に?」
「うん。日野の実家に」
「そうか」
「ケンジは、家族とは一緒に暮らしてないの?」
涼子の問いにケンジは少しとまどった。どう答えようか。できれば涼子には嘘をつきたくはない。それに、別に隠す必要もないだろう。
「親父とおふくろは、埼玉の親戚の家に」
ケンジは正直に答えた。
「親戚の家? 実家には住んでないの?」
「実家は、もう無い」
ケンジは自分が震災で被災したことを涼子に話した。
「そうだったの……。それじゃ、ケンジはいつか岩手に?」
「ああ。帰るつもりさ。最初は、このまま東京で暮らそうかと思っていたんだ。たとえ復興しても、そこはもうオレの育った街じゃないから。でもやっぱり最後は、いずれ死ぬときがきたら、故郷の土に還りたい。いろいろ悩んだけど、そう考えるようになった」
噴水の周りを歩いていると、ケンジの足元にサッカーボールが転がってきた。あの小学生たちのボールだ。
「私、ただ復興すればいいって思ってたけど、そういう心の傷のことまでは考えてなかった……」
「心の傷、か」
ケンジは拾い上げたボールを離して足元に落とすと、軽く蹴って空に上げた。ボールは放物線を描きながら小学生たちの方へ飛んで行く。
「ケンジ……」
ボールは地面に落ちると、小さくバウンドを繰り返しながら小学生たちの方へ転がっていった。
「やめよう」
「え?」
ボールを受け取った小学生たちがあいさつをする。ケンジはそれに笑顔で応えて見せた。
「せっかくのデートだ。震災の話はやめよう」
そう言ったケンジの目は、やはり噴水を睨みつけていた。
――その日の夕刻。
東あずま駅近くにあるマサの屋台に浩さんの姿はあった。
「カシラ、できやしたぜ」
マサができたての焼きそばを浩さんに差し出した。
「マサ」気まずそうに受け取りながら、浩さんが言った。「すまねえが、ツケといてくれねえか? いま持ち合わせが、ちょっとな……」
「カシラ」
彼はフッと笑い、タバコに火を点けた。「お代はいりやせんや。アッシがおごりまさァ」
「そうはいかねえよ。後で、必ず払うよ」
「カシラ」
マサは首を横に振った。
「カシラはあのとき、言ったじゃありやせんか。困ったときはお互い様だ、って」
「あのとき?」
マサがタバコを燻らせ、昔のことを思い出すように遠い目をして語り始めた。
「あれは、忘れもしねえ七年前ぇ。アッシがマージャンで一文無しになって途方に暮れていると、何も言わずにそっとポケットに三万円忍ばせてくれたお方がいる。カシラはそのとき言ったじゃありやせんか。困ったときはお互いさまだ。アッシはそのときの恩を、片時だって忘れたことはねえんですゼ?」
「別に恩を着せたわけじゃねえよ」と、浩さんが照れくさそうに笑った。
「カシラ」
マサは浩さんの目をまっすぐに見た。浩さんもサングラス越しにマサの目を見る。マサの視線は確かに浩さんの目を捉えていた。
「フッ」
浩さんは呆れたように首を振った。
「てめえの気持ちはよく分かった。その心意気に免じて、ここは一つ、ありがたくゴチになろうじゃねえか」
「さすがはカシラ、アッシが見込んだ通りのお方だ」と、マサは感心した。
「よせよ。オレはそんな大した奴じゃねえよ」
そうさ。オレはシャバの人間からは決して褒められるような人間じゃねえ。堅気でもなけりゃあ、ヤクザでもねえ、中途半端な存在。言わば影法師なのさ。浩さんは胸の中で呟いてみた。そして、サイレンを鳴らしながら遠くの方を走って行く消防車を見送った。
空を茜色に染める炭火のように穏やかな夕陽。やがてそれは浩さんの暗い心の中へと沈んでゆくのであった。

一週間後の第三土曜日。泉田自動車整備工場。
「これでよし、と。吉行、そっちはどうだ?」
「もうすぐ終わる」
ケンジと吉行が二人で作業をしていると、そこへ社長に頼まれた用事で出掛けていたジョージが車で戻ってきた。彼は車から降りると、まっすぐ事務所へ向かった。
「まったく」ケンジはため息を漏らした。「社長といい、あの人は何しに会社に来てるんだ?」
テツとジョージは馬券を片手に、仕事では滅多に見せない真剣な表情で、テレビの競馬中継に全神経を傾けていた。テツがジョージに頼んだ用事とは、馬券の購入だったのだ。
「まあ、たまにだけど、一応仕事してるし。そういう意味では浩さんよりはマシかな」と、吉行もため息をついた。
「浩さんの方がマシさ」
ケンジが口の中でく呟いた。
「うん? 何か言ったか?」
「いや。何でもない……」
確かに、ケンジも最初はそう思っていた。浩さんの過去を知るまでは。言葉では表現できない心の傷。たとえ浩さんが、自分が震災で妻と一人息子を失った事を他人に話したとしても、それを聞いた人は“かわいそう”としか思わないだろう。しかし、そうではないのだ。実際に親兄弟を不幸な事故や事件で失った人は、亡くなった家族をただ単に“かわいそう”と思うのではなく、もっと複雑なものを感じているのだ。やり場のない怒り、悲しみ、苦しみ、そして自分の無力さ。
そういうものは、いくら話しを聞いたところで理解できるものではない。だから話しても意味がない。慰めようにも、心の傷は言葉だけでは癒す事は出来ないだろう。浩さんは生き甲斐を失い、幸せを見失ったまま、陽の照たらない裏道を、ただあてもなくさまよい続けているのだ。ケンジにはそんな浩さんの気持ちがよく分かっていた。
「今日は来ないのかな、浩さん……」
「たぶん競馬だろ」
タイヤの取り付け作業をしている吉行がホイールナットを締めながら言った。その日、ケンジはなんとなく浩さんと話がしたくなったので、仕事帰りに昼行灯へ寄ってみた。浩さんは昼行灯には毎日のように通っている。つまり、ここで待っていれば確実に浩さんに会えるのだった。
ケンジが一人、浩さんを待ちながら飲んでいると、マサが一人でやって来た。しかし、いつものマサとは違い、やけに元気がない。
「いらっしゃい。なんだ、マサ。浩さんは一緒じゃねえのか?」
「へえ。それが……」
マサの元気の無い理由は、浩さんの事だった。実は今日、浩さんは競馬の“ノミ行為”の現行犯で逮捕されたらしい。
「浩さんが捕まった!?」
ケンジは思わず椅子から立ち上がった。店主はうなだれてため息をつくと、首を横に振った。
「それで、どうなるんです? 浩さんは」
「まあ、賭け金も大ぇした額じゃありやせんから、たぶん罰金刑で済むんじゃねえかと……」
心配そうに顔をしかめながら、マサはタバコに火を点けた。そして、口に含んだ紫煙を深く、ゆっくりと吸い込んだ。
――三日後。
マサの言った通り、浩さんは一応“初犯”と言う事で罰金刑のみで済んだ。三十万円の罰金。当然、浩さんに払えるような額ではない。安月給のケンジが無理をして十二万、ケンジが涼子に事情を話して借りた十五万、マサがなけなしの三万を出した。おかげで浩さんは労役場送りにならずに済んだと言う訳だ。
――それから更に数日後。
昼行灯。店内にはケンジ、吉行、マサ、そして涼子の姿があった。そして、少し遅れて浩さんもやって来た。
「いらっしゃい」
「おやじ、いつもの」
浩さんはハイボールしか飲まない。それも“炭酸入りオレンジジュース”で割ったものだ。その理由を知っているのは、店主の坂井とケンジだけだ。実は、浩さんは下戸ではないが、酒があまり得意ではないのだ。それでも、オレンジジュースで割って誤魔化せば、少しぐらいは飲めるのだ。そこまでして苦手な酒を飲むようになったのは、やはり“あの時”からのようで、アルコールが入らないとよく眠れないらしい。これは店主がケンジにだけ話してくれた事なので、マサや吉行は知らない事なのだ。
「浩さん、今日はケンジが彼女を連れてきたんだよ」
店主が言った。
「彼女? へえ。ケンジ、おめえも隅におけねえな」
「からかわないでくださいよ」ケンジがとなりに座る涼子を振り向いた。「涼子、浩さんだ」
「あの、萩野涼子です」
「若林だ。若林浩三」
「なんでも、この前のおまえさんの罰金、半分は彼女が立て替えてくれたらしいよ」
店主がハイボールを出しながら言うと、浩さんは声もなく驚いた。そして、サングラスを静かにはずした。
「そうだったのか。いろいろと迷惑をかけちまったようだ。すまなかったな、涼子ちゃん。お金は必ず、少しずつ返すから」
「いえ、私の方こそ、余計な事したみたいで……」
「そうだよ。一度くさいメシ食った方がよかったんだよ」
吉行が言うと、みんなが笑った。
「本当に心配してたんですよ、浩さん」
「いや、すまん、ケンジ」
「借りた三十万、ちゃんと返すんだぜ? 三人に」
店主が言うと、浩さんはマユをひそめてケンジと涼子の顔を見渡した。
「三人?」
店主が続けた。
「マサも出してくれたって言うじゃねえか。三万」
三万。それはマサが七年前に浩さんから借りた金額と同じであった。
「マサ。てめえってヤツは、粋なことしやがるぜ」
そう言うと浩さんは、フッと笑って見せた。
「これで貸し借りなしですゼ? カシラ」と、マサもニヤリと笑って見せた。
「ところで涼子ちゃん。今日はオレがおごるよ。迷惑かけちまったからな」
涼子は遠慮したが、浩さんがどうしてもと言うので、好意に甘える事にした。
「それじゃ、今日はご馳走になります」
「おう、どんどんやってくれ」
「無理すんなよ浩さん」店主が苦笑した。「払えんのかい?」
「てやんでぇ。飲み代ぐれえはあらぁな」
――数日前。浩さんが捕まった翌日の昼休み。
とある喫茶店の店内に、ケンジと涼子の姿はあった。
「まあ、そう言う事で、できれば十五万ほど貸してほしいんだ。急にこんな大金を貸せだなんて、迷惑なのは十分かっている。でも、ほかに頼める人間がいないから……」
ケンジは浩さんの罰金のことで涼子に相談していた。もちろん、事のあらましを聞いた涼子はケンジの頼みを快く承諾してくれた。
「ありがとう、涼子。借りた金はオレが責任を持って、毎月少しずつ返すよ」
「でも、心の傷って、言葉とかそういうものじゃ、癒しようがないし、難しいわね」
「そうだな。でも、これを機に、なんとか堅気になってくれればいいんだが……」
ケンジも同じ被災者だが、家族は無事だった。しかし、浩さんは家族を亡くしてしまった。震災が残した心の傷の深さは、浩さんの方が深かったのだ。たとえば自分が浩さんと同じように家族を失っていたとしたら、その心についた傷を消すことが出来るだろうか。当然、ケンジにその自信はなかった――
「そういや、カシラ。アッシは今日、見ちまったんで」と、マサが思い出したようにお猪口を置いた。
「なんだ、幽霊でも見たか?」
「ちがいまさァ。ほら、例の“ヅラ盗り”でさァ」
「ああ、家他我等巣、か……」
そう言ってうんざりしたようにうなずくと、浩さんはハイボールのグラスを口元で傾けた。
「八咫烏?」
涼子が小首をかしげた。
「暴走族の事でさァ。あの三本足のカラスの事じゃありやせんゼ」と、マサが笑った。
「アイツらまたやったんスか? 例の“ヅラ盗り物語”ってやつ」
吉行がニヤニヤしながら言った。この家他我等巣という暴走族は、人数こそ多くはないが“性質の悪い遊び”をする事で有名なのである。
「ヅラ……トリ……?」
ケンジは微妙な笑みを浮かべながら涼子と顔を見合わせた。
「ヅラ、って、カツラの事?」
涼子が吉行に聞くと、少し吹き出しそうになりながら、彼は何度か無言でうなずいた。
「それで、そのヅラ盗り物語、っていうのは、いったい……」
ケンジが聞くと、浩さんが呆れたようにため息をついた。
「文字通り、サラリーマンのヅラを引っこ抜くんだよ。すれ違いザマにな」
「まさか……」
ケンジが再び信じられない、と言う笑みを浮かべて、涼子と顔を見合わせた。
「そうよ」と、マサがお猪口を傾けた。「まさに”まさかの坂”ってやつでさァ」
果たしてヅラ盗り物語というのは一体どのようなものなのか。マサが丁寧に説明してくれたので、その内容を紹介しておこう。
ヅラ盗り物語。それは、家他我等巣という暴走族グループが始めたサラリーマンのヅラを引っこ抜くという“遊び”で、ヅラであるかどうかを見極めるための優れた観察眼と高い技術が求められるゲームなのである。
ルールは単純そのもので、生え際の怪しいサラリーマンに目星をつける。そして、ヅラの方にいくら、地毛の方にいくら、などと金銭を賭ける。最後に“髪風特攻隊”と呼ばれる総勢三名からなるベテランの隊員の中から一人選ばれた者が、サラリーマンの正面から怪しまれないように、そしてさりげなく殺気を隠しながら近づき、すれ違いザマにヅラを引っこ抜くという、極めて難易度が高く迷惑な遊びなのであった。
ただ、この“髪風特攻隊”の隊員は直接賭けには参加する事はないが、サラリーマンがヅラであれ地毛であれ、一定のギャラが支払われるのであった。ちなみにこの三名の内、出撃した一名にはギャラが二十パーセント多く支払われるとの事。
「ホントですか?それ」と、ケンジは俄かには信じられない、と言ったように苦笑した。
「アッシも、話には聞いてやしたが、直接見るのはこれが初めてだったんでさァ。まさか本当にやりやがるとは……」
「オレも一度見た事があるよ」と、浩さんがしみじみと語り始めた。「ヅラを引っこ抜かれたサラリーマンの姿は、まるで落ち武者よ。そしてヤツらは、敵の首をとった戦国武将のように勝鬨を上げやがる。だれも好きで禿げてる訳じゃねえのにな。それをヤツらときたら、見境なくポンポンポンポン引っこ抜きやがる」
吉行がビールを吹き出して笑っている。店主も焼き鳥を炙りながら肩で笑っている。
「血も涙もねぇとはこの事でさァ」
マサが言うと、浩さんもうなずいた。
「まったく、つける薬のねぇヤツらだよ」
この日は、みんなでくだらない話をしながら飲んで笑った。そして涼子もみんなとすぐに打ち解けていった。
久しぶりの楽しい酒。だが、浩さんの心の痛みを思うと、ケンジはどうしても酔えないのであった。
7月。泉田自動車整備工場。
事務所にはテツ、ジョージ、そして浩さんの姿があった。相変わらず朝からポーカーをやったり、競馬の話に花を咲かせたりと、まるでマフィアのような連中だった。
そして昼休みになっても、浩さんたちは出前のカツ丼を食べながら、飽きもせずマージャンをやっていた。
「やれやれ。ケンジ、たんぽぽ行こうぜ」
「ああ」
――食堂たんぽぽ。
「いらっしゃい!」
「いらっしゃいませ」
清二と一緒に出迎えたのは、おばさんではなく娘の美咲であった。おばさんのケガはだいぶよくはなってきていたが、まだ重いものを持つ事はできなかった。しかし、野菜を刻んだり、注文をとる事ぐらいはできたので、一、二週間前から店には出てくるようになっていたのだ。
「あれ? おばさん、またどっかケガしたの?」
吉行が尋ねると、清二がボヤき始めた。
「まだキズが痛むとか何とか言っちゃってさ。今度は一人で温泉旅行よ。いい気なもんだよ、まったく」
「ケンジさんと吉行さんにも、お土産買ってくるって」美咲は楽しそうである。
「そいつは楽しみだ。なあ、ケンジ」
「え? あ、ああ。そうだな」
今日のケンジはどこかうわの空だった。仕事中にも、普段のケンジからは考えられない細かいミスが多く目立った。
そして二人は適当に空いてる席に腰を下ろした。
「オレは……」
注文をとる美咲に吉行が言いかけると、清二がネギを刻む手を止めて、チラリと吉行を睨みつけた。
「……いつもの……」
軽く目を伏せながら吉行が言うと、店主が無言でうなずいた。相変わらず吉行は中華そばのセット。この店で一番安いセットメニュー。それも“ギョーザ抜き”だ。
ツケを払い終わるまで、ほかのメニューは注文できないのだ。
「チャーハン大盛りで」
吉行が小さくささやくように言うと、美咲が可笑しそうに含み笑いを浮かべた。
そしてケンジは野菜炒め定食を注文すると、ケータイをいじり始めた。しかし、別にメールをするわけでもなく、ただボーッと画面を眺めているだけだった。そんなケンジを横目に見ながら、吉行がタバコに火を点けた。
「今日は、うわの空だな。浩さんの事か?」
相変わらず鋭い吉行に、ケンジは呆れたように苦笑した。
「ああ。浩さんの事だ。あの人は、好きであんな事やってるんじゃないんだよ。だから、なんとか堅気にしてやりたい」
「もう“ノミ”はやめた、なんて言ってたけど、そんなに簡単にやめられるとは思えないけどな」
「たぶんノミはもうやらないよ。浩さんは」
「ケンジ。ギャンブルってのは中毒だ。タバコだってそう簡単に禁煙できるモンじゃないし、酒だって同じだ」
「浩さんは中毒じゃないさ」
今日のケンジには吉行の一言一言が気に障った。いくら考えてもいい知恵が浮かばない、そんな自分の無力さに対する怒り。そして、ケンジの言葉を否定する吉行に苛立った。ケンジの張り詰めた糸は切れそうになっていた。
「オレがパチンコやめらんねぇのと同じだよ。だから浩さんもたぶん――」
「おまえと一緒にすんなよ!」
ふいにケンジが声を荒げた。
その声に驚いて、料理を運んでくる美咲が足を止めた。そしてまな板の上でキャベツを刻む手を止めて、清二がハッとしたように顔を上げる。
「……すみません。大声だして……」
ふと我に返ったケンジは、一度つかれたようにため息を漏らした。
「すまん。吉行」
「別に気にしちゃいないけどさ。少し疲れてんじゃないの? おまえ」
「かもな……」
「どうだ? おまえも、おばさんと一緒に温泉旅行に行くってのは?」
吉行がニヤリと笑った。
「おまえには敵わんよ」
ケンジも歯を見せて弱々しく笑った。笑うしかなかった。自分の無力さを。
「あれ?」
中華そばをすすった吉行が異変に気ずいた。
「おやっさん、いつもより麺が少ないよ?」
その言葉に、清二がフッと笑った。
「なら、早いとこツケを払うんだな。あと一ヶ月以内に、せめて半分払ってもらわなきゃあな」
「もし、払えなかったら?」
「そんときゃあ、おにぎり二個と“ラーメンのスープ”で我慢してもらうしかねえな」
「ひょっとして、それもセットメニューと同じ値段なの?」
「まあな。カップラーメンよりはマシだろ?」
ちなみに中華そばのセットは七五〇円である。
「当分、パチンコはお預けだな」
そう言ってケンジが笑うと、吉行はふてくされながら中華そばをすするのであった。
「浩さんカモにして、ポーカーでもやろうかな」
「おまえ、ポーカーできるのか?」
「社長とジョージさんとなら二、三度やった事はあるよ。当然負けたけどね。でも、浩さんになら勝てるかもな」
「どうして、浩さんになら勝てるんだ?」
「教えてもいいが、条件があるんだ」
「条件?」
吉行の言う条件とは、たんぽぽのツケを半分払う事であった。彼はそういうところだけはしっかりしてるのだ。
「まったく、おまえってやつは」
べつにさっきの償いと言うわけではないが、まあいいだろう、と、ケンジは吉行のツケを半分持つことを約束した。
「さすがケンジ。話せるぜ」
吉行が言う浩さんに勝てる方法。それは、実に単純なものであった。浩さんに勝つ方法、と言うより、浩さんが勝てない理由は、浩さんの“悪いクセ”にあったのだ。手元にあるカードがあまりよくないカード、いわゆる“ブタ”の時が多いが、浩さんはそんな時に決まってあるクセがでる。それは――。
「……って、やつさ。まあ、無意識にやってんだろうが」
「それだけ、なのか?」と、ケンジは拍子抜けしたようだ。
「そうだよ。でもな、そういう些細なクセが、ギャンブルでは命取りになるんだぜ?」
「そんなもんかな?」
ケンジはギャンブルの知識はほとんどないので、いまいちピンとこなかったようだった。しかし、こんな情報でもテツは喜んだそうだ。浩さんのクセに最初に気がついた吉行が、それをテツに教えたのだ。だから、浩さんは何度やってもテツに勝つことができない。そして、浩さんは負ける度にテツとジョージに二千円づつ払うのだ。
「これは社長から浩さんにだけは絶対に言うな、って言われてることなんだ。 頼むから浩さんには内緒な? バレたら給料減らされちまうんだよ」
吉行はお調子者でどこか頼りないが、こういった天性の“鋭さ”を持っている。どんな人間にでも、一つや二つ取り柄がある、と言うことだろうか? 呆れつつも、感心せずにはいられないケンジなのであった。

その日の夕方。昼行灯。
店内にあるのはケンジと涼子の姿だけ。浩さんとマサはまだ来ていない。
「どうだい? 浩さんの様子は?」
店主が焼き鳥を炙りながらケンジに尋ねた。
「相変わらずですよ。朝から社長とポーカーやったり、マージャンやったり」
「それに競馬か」と、店主が呆れたように呟いた。
「ええ。ただ、ノミ行為はもうやらない、って、言ってましたけど」
いい加減バクチはやめてほしいと思っていたが、ケンジはそんな浩さんが嫌いではなかった。誰にでも短所はある。欠点のない人間など居るはずもない。
サイダーは炭酸の刺激があるから旨いのである。気の抜けた、炭酸が飛んでしまったサイダーなど、飲んでも旨いはずがない。水清ければ魚棲まず、と言うことだ。
ケンジがそんな事を考えていると、そこへ浩さんがやってきた。
「おやじ、いつもの。それと焼き鳥」
カウンター席に座ると、浩さんはいつもの“炭酸入りオレンジジュース”で割ったハイボールを注文した。アルコールは控えめだが、酒が弱い浩さんにはちょうどいいのだ。
「おう。涼子ちゃんも一緒か。どうだい、気に入ったかい? この店」
「ええ。お店の雰囲気もいいし、坂井さんもいい人だし」
「おやじ、よかったじゃねえか。褒められてるぜ?」
「おいおい、からかっちゃいけねえ」と、店主が照れ笑いを浮かべた。「よし! 褒めてくれたお礼といっちゃなんだが、今日の勘定は涼子ちゃんだけ半分にまけてやらぁ」
客は少ないが、いつもこんな感じで盛り上がる。涼子も楽しそうに飲んでいる。店は小さく、店内もそれほど広くはないが、ケンジには居心地がよく感じられた。そして、それは浩さんやマサも同じであった。きっと店主のこうしたサッパリした性格が店の雰囲気をつくっているのだろう。そして涼子も昼行灯の常連になりつつあった。
「いや、さすがおやじ、江戸っ子だねぇ。オレが見込んだ通りのお人だ」
浩さんも下心丸出しで褒めてみた。
「悪いが浩さん。いくら褒めてもらっても、あんたにゃあ何もでねえよ」
「おいおい、やさしいのは女にだけか?」
店内が笑い声で明るくなる。浩さんはいつも冗談を言ってみんなを笑わせていた。一人暮らしのケンジには、この雰囲気がとても懐かしく感じられた。震災前は毎日、家で普通に目にしていた光景。また昔のように家族で楽しく過ごせる日が来るのだろうか? そういう不安も、ここでみんなと楽しく飲んでいると、少し和らぐのであった。
そこへ、マサと吉行がやって来た。
「おやっさん、熱いの一本つけてくんな。それと、つまみもテキトーに」
「オレはビールと焼き鳥ね」
注文しながら二人はカウンター席に座った。
「今日はパチンコはどーした?」
上着の胸ポケットからタバコを取り出しながら、浩さんが吉行に尋ねた。
「今日は出そうになかったんでね。すぐにやめましたよ」
さすがの吉行の鋭い勘も、パチンコには役に立たないようだ。まあ、いくら優れているといっても所詮は人間。完璧などありえない。要は、ここぞというときに全力を出しきる事が出来るかどうか、なのだ。ケンジはそう考えるのであった。
「お、涼子ちゃん、久しぶり」
吉行は涼子と軽く挨拶を交わした。
「なあ、ケンジ。オレにも誰か紹介してくれよ。涼子ちゃんの同僚でもいいからさ」
「やめときな涼子ちゃん。どうせこいつは、パチンコ代みつがせるに決まってらぁ」
店主が言うと、ケンジもうなずいた。
「オレもそう思う」
浩さんとマサもうなずく。すると吉行が、ふてくされて一言。
「オレはヒモじゃねえよ」
みんながドッと笑った。そして彼は、ふてくされたままビールを一息に飲み干した。
「そうだ」ケンジが思い出したように言った。「今度の花火大会、オレと涼子で行く事になってるんだけど、浩さんも一緒にどうです?」
「花火大会?」
「隅田川の花火大会だよ」
店主が言った。
「そういや、アッシはその日、東白髭公園の近くに屋台を出す事になってるんでさァ。よかったら、みんなで来るといい。おごりやすぜ?」
「そいつは楽しみだ。ぜひ、よらせてもらいますよ。浩さんも、もちろん行きますよね?」
再びケンジは誘ってみた。だが、浩さんはまだ迷っているらしく、彼は一つ呻って考えた。
「吉行。てめえはどうするんだ?」
浩さんが吉行に言った。
「オレはいいよ。見たいテレビあるから」と、吉行は興味なさそうに、そっけなく断った。
「おやじさんは、行かないんですか?」
ケンジが聞いた。
「オレもいいや。苦手なんだよ、人込み」と、やはり店主も興味なさそうに断るのであった。
「行こうよ、若林さん」
涼子は一番楽しそうにしている。実は涼子も、一緒に行く相手がいないという事もあり――友達はみんな彼氏と二人で行く――毎年部屋の窓から一人淋しく眺めていたのであった。しかし、今年は淋しい花火ではない。涼子は心の中で、子供のようにはしゃいでいたのであった。
「まあ、涼子ちゃんの頼みとあっちゃあ断るわけにもいくめえ。よし、じゃあ三人で行ってみるか」
こうしてケンジ、涼子、浩さんの三人で花火大会に行く事になった。
それから数日後。
泉田自動車整備工場。作業をしているのはケンジと吉行。ジョージは社長のテツと、相変わらず事務所で競馬新聞を真剣な眼差しで眺めている。
「まったく。いいご身分だよ」
ボンネットを閉めると、吉行は事務所の方をチラリと一睨みした。
「ウチだからいいようなものの、当然ほかでは通用しないさ」
ケンジもため息を漏らした。
「そりゃそうだ。ウチが倒産したら、浩さんみたいになるんだろうな? あの人」
吉行はジョージのことが気に入らなかった。かといって、険悪な仲でもなかった。ただ、あまり口をきかないだけだ。はっきり言って、吉行はジョージのことを相手にしていないのだ。ジョージがやる気があるときは頼むし、やる気がないときは頼まない。テキトーにあしらってる感じだ。
「浩さん、か……。今日は来ないのかな……」
はたして、どうしたら浩さんを立ち直らせることができるのか? もちろん、決まり文句のような慰めの言葉をかけても、なんの効果もないのは分かっている。言葉では無理なのか? ケンジが浩さんの過去を知っていることは、浩さんはまだ知らない。どのタイミングで話そうか。自分のこれからの人生、そして浩さんの人生。ケンジは一人で二人分の悩みを抱えていたのだ。
花火大会当日。午後5時過ぎ。
涼子のアパートの前の駐車場に一台の車がやってきて停まった。ケンジである。一階と二階、各五部屋の二階建てのアパートで、駐車スペースは外階段側から反対側までの5つしかなく、三番目まで住人の車が止まっていたので、ケンジは外階段側から四番目に車を停めた。
2階にある涼子の部屋へ向かおうとアパートの角を曲がると、外階段の脇に浴衣姿の女性が一人、携帯電話を片手で操作しながら佇んでいた。黒地に薄紅や藍白のアサガオが咲き乱れる浴衣。涼子だろうか? 後ろを向いているので顔は見えない。かと言って、急に声をかけて人違いだったらちょっと恥ずかしい。そんなことを思いながら階段を登ろうとしたとき、彼女がケンジを振り向くのであった。
「あ、ケンジ」
その瞬間、ケンジはホッとした。と同時に、自分が意外と気が小さいことに気づき、苦笑した。
「……どうかしたの?」
「い、いや、そういう格好だから……涼子だったのか。気がつかなかったよ」
「浴衣着たの、久しぶりだから……。やっぱり、似合わないかしら?」
「そんなことないよ。とてもキレイだよ」
涼子は少し恥ずかしそうに微笑んだ。自分も浴衣を着てくるべきだったか。ケンジは今更ながら後悔していた。助手席に涼子を乗せると、ケンジはゆっくりと車を走らせた。
「それにしても、今日はさすがに多いな。浴衣姿が」
街中が浴衣姿で埋め尽くされていた。ケンジにはそれが、まるで街中に花が咲き誇ってるように見えていた。
「これはどうかすると、花火よりもキレイかもしれないな」
今年は2年ぶりに大船渡の花火大会が復活する、と言う話がある。大船渡はケンジの住む陸前高田から近かったので、毎年家族で花火を見に行っていたようだ。
「花火大会、か」
いつか、また家族で見に行きたい。涼子にも見せてやりたい。ケンジは改めて故郷に帰ることを誓うのであった。
しばらく走ると、浩さんとの待ち合わせ場所にしてある駐車場に到着した。二人が車から降りて、辺りを見回す。どうやら浩さんはまだ来ていないようだ。
「浩さんは、まだ来ていないみたいだな……」
そのとき、遠くの方から一台の外車が近づいてきた。浩さんのイーグルマスクだ。しかもルパン音頭を大音量で流しながら。道を行く通行人たちも、すれ違うたびにその“怪しい車”を振り返るのであった。そして、その怪しい車は軽くドリフトをしながら駐車場に入ってくると、駐車スペースに若干ナナメに車を止めた。
「よう、待ったか?」
車から降りると、キーを差し込んでドアをロックしながら浩さんは言った。
「い、いえ。オレたちも今きたトコですよ。それにしても、ずいぶんと賑やかでしたね……」
「ああ、今のか? この前ラジオ聴いてたらよ、偶然流れてきてな。気に入っちまったんだよ」
ケンジは不思議でならなかった。よくあの大音量で耳が平気でいられるものだ、と。しかも、若干小さめの声で話しているケンジの声も、普通に聞こえているらしかった。
「そうっスか」と、呆れたようにケンジがため息を漏らした。「どうでもいいけど、もう少しボリューム下げた方がいいんじゃないんですか?」
「うるさかったか?」
そう聞きながら、浩さんは徐にタバコを取り出した。
「まあ、少し」と、小首をかしげながらケンジが苦笑した。
「そうか。うるさかったか」
と、いまひとつ納得できない感じで小首をかしげると、浩さんは少しうつむきながらタバコに火を点けた。
そして、ふと顔を上げたときである。
「おいおい、ひょっとして涼子ちゃんか?」
今更だが、浩さんが浴衣姿の涼子に気がついた。
「なんだか、ちょっと恥ずかしいな。私だけ浴衣」と、涼子は面映ゆそうに言った。
「オレも浴衣着てくりゃよかったぜ」と、浩さん。
「はは。浩が浴衣なんて着た日にゃあ、ただの風呂上りのオッサンにしか見えませんよ」
ケンジが皮肉っぽく冗談を言って見せると、涼子が右手で口元を覆いながら、くすくすと可笑しそうに笑った。
「確かにな。ちげぇねぇや」と、浩さんがポッコリと出た自分の腹を撫でると、三人はドッと声を上げて笑うのであった。
「それじゃあ、ぼちぼち行くか。たしか、東白髭公園だったな? マサの屋台は」
そして三人は、とりあえずマサの屋台のある東白髭公園まで歩いて行く事にした。
「浩さん」
ケンジが前を歩く浩さんに声をかけた。
「なんだ?」
歩きながら、浩さんは肩越しに軽く振り向いた。
「嫌いなんですか? 花火」
「いいや。なんでそう思う?」
浩さんは前を向いたまま、後ろを歩くケンジに言った。
「いえ、あまり乗り気じゃなかったから……」
浩さんが燻らすタバコの紫煙が、ケンジに向かって流れてくる。タバコを吸わないケンジは、それを鬱陶しそうにパタパタと手で払った。
「オレには浴衣は似合わねえからな」浩さんは首を振って笑った。「それに、花火もな」
そう言うと、彼は指でタバコを弾き飛ばした。そして2メートルほど先に落ちたその吸い殻の火を、ケンジが通り過ぎるついでにさりげなく踏み消した。
「ちゃんと消さないと火事になりますよ、浩さん」
ケンジが何気なく言った一言に、涼子が反応した。彼女はケンジの腕をそっとつかむと、首を横に振って見せた。ケンジは「しまった」と思い、かすかに顔をしかめた。二人が前を歩く浩さんをそっと見る。
「大げさなやつだ」
浩さんは肩を小さく上下に動かして笑っていた。しかし、浩さんがどんな顔をして笑っているのか。彼の後ろを歩く二人には分からなかった。
そのとき、数メートルほど先のスーパーマーケットで、ある事件が発生した。突然、店の中から十代後半の若い男たち三人が、まだ“会計の済んでいない商品”を山積みにしたカートを押しながら、ものすごい勢いで飛び出してきたのである。
「あいつら、家他我等巣の連中だな」
浩さんが言った。
「家他我等巣、って、あの暴走族の?」
ケンジの問いに、浩さんは無言でうなずいた。
「そしてこれがウワサに聞く“地獄の暴走特急”か……」
「地獄の……? なんです、それ……」
「三人が縦に一列に並んで、一定の間隔を保ったまま猛スピードで走り去るところから、そう呼ばれてるのさ」
三人組が商品を山積みにしたカートを押しながら、ものすごい勢いで歩道を駆け抜けていく。それはまるで特急列車のように見えた。それを少し肥満気味の中年の店員が必死になって追って行く。頭の毛が薄い男で、メガネをかけている。その姿から察するに、おそらく店長であろう。
通行人達も慌てて歩道の端に避ける。その様子はまるでモーゼの十戒の海が割れていくシーンそのものであった。そして、足の遅い太った店長らしき男と三人組の距離は見る見る開いていった。やがて三人組は、一定の間隔とスピードを保ったまま、遠く地平線の彼方へと消えて行くのであった。とうとう太った店長らしき中年の男は、追うのをあきらめて、へたり込んでしまった。
「つける薬のねぇ奴等よ」
浩さんは呟いた。ケンジと涼子は、ただ呆然と立ち尽くしている。
「信じられない……」
涼子が言った。
「これが“まさかの坂”ってやつさ」浩さんが皮肉な笑みを浮かべながら言った。「世の中、信じられねえ事ほど起きちまう。この前の震災だってそうだろ? ケンジ」
「確かに、そうかもしれませんね……」
浩さんの言った「この前の震災」。それは、東日本大震、そして災阪神大震災、この二つの震災の事を言っているのだ。ケンジにはそう聞こえていた。
パトカーのサイレンが聞こえてくると、三人はゆっくりとその場を後にした。
――東白髭公園近くまで来ると、さまざまな屋台が並んでいた。そして、そこは多くの人で賑わっていた。
「おう、ここだ。マサの屋台は……と。おお、あそこだ」
浩さんが指差した。
マサの屋台を見つけるのは、それほど難しい事ではなかった。あのモヒカン頭は結構目立つので、すぐに見つける事ができたのであった。
「よう、マサ。景気はどうだ?」
「カシラ。こりゃあ、皆さんお揃いで。今、ちょうどできたとこでさァ」
マサができたての焼きそばとペットボトルのお茶を三人に差し出した。
「どうも。ゴチになります」
「わぁー。おいしそー。ありがとうございます」
「おう、すまねえな。ところでマサ。さっき、見ちまったんだよ。例の“特急列車”をよ」
「カシラも見なすったか?」と、マサが可笑しそうに笑い始めた。「まったく、あいつらの足の速さときたら、それこそオリンピック選手顔負けでさァ。ああいうのを才能の無駄使い、って言うんでやすかねぇ」
「まったくな」と、浩さんは呆れたようにため息を漏らした。「天は二物を与えず、とはよく言ったもんだ。じゃ、しっかり稼ぎな」
そしてマサの屋台を後にすると、三人は近くのベンチで足を休めた。
「まだ上がんねえのかな?」
腕時計を見ながら浩さんが呟いた。
「マサさんの焼きそば、おいしいね」
「ああ。浩さんも、食べたらどうです? まだ、時間もあるし……」
「ん、そうだな……。おっと、忘れるトコだったぜ」
浩さんが思い出したように、上着の内ポケットから茶封筒を二つ取り出すと、ケンジと涼子に渡した。
「この前借りた二十七万、確かに返したぜ」
「どうしたんです? このお金……」
ケンジが封筒を受け取りながら、疑いのまなざしを向けると、浩さんはフッと笑った。
「ノミじゃねえよ。心配すんなって。この前競馬でよ、大穴当てたんだよ。五十万だぜ? 五十万」
と、浩さんはうれしそうに興奮しながら言うのであった。
「でも、若林さん。これ、一万円多いですよ?」
ケンジも封筒を確認すると、やはり一万円多く入っていた。
「いいんだよ。迷惑料ってやつさ。とっといてくれ」
「本当に、ノミじゃないんですね?」
ケンジはまだ疑っていた。すると、浩さんはサングラスを外しながらまっすぐにケンジの目を見ると、無言でうなずいて見せた。そしてケンジも、納得したようにうなずいた。
「でも、浩さん。ノミだけじゃなく、もうバクチそのものから足を洗った方がいいんじゃないんですか?」
「そいつは無理な相談だ。オレには、ほかの生き方なんてできねえよ」
浩さんはサングラスをかけなおして、軽くため息を漏らした。やはり、このままでは浩さんは変わらない。変われない。ケンジは涼子の顔をちらりと見た。そしてケンジの目を見た彼女は、彼がなにを考えているのかすぐに分かった。彼女も同じことを考えていたのだ。涼子は同意するように、ケンジにうなずいて答えた。
「――あのことを、今でも?」
「あのこと?」
浩さんには、ケンジが何の話をしているのか分からないようだ。もちろん、ケンジの言う「あのこと」とは、阪神大震災のことだ。
「聞いたんですよ。おやじさんに」
ようやくケンジの話を理解した浩さんは、面食らいつつも「ああ、そのことか」と、苦笑しながらひとつ小さくため息をついた。「あのたぬきジジィ、余計なこと言いやがって……」浩さんは困り顔でタバコに火を点けた。「でもまあ、お前にはいつか話そうかと思ってたんだよ。お前がくじけそうになったとき、オレのようにならないように……」
「浩さん……」
「これから話す事は、マサや吉行には言わないでくれよ? テツやジョージにもだ」
「ええ。誰にも言いませんよ」
ケンジが約束すると、涼子もうなずいた。
「オレが昔、神戸に住んでたってのは、もう聞いたな?」
「ええ」
浩さんが初めて語る自分の過去。ケンジには興味深かったが、あまり聞きたい話しでもなかった。浩さんがこれから語ろうとしているのは、くだらないウワサ話でもなく、ジョークでもない。自分が経験した震災の話だ。楽しいはずもなかった。
そして徐にタバコを取り出し火を点けると、浩さんはゆっくりと、自分の生い立ちから話し始めた。
「オレのおやじは、オレが六つの時に病気で死んじまってな。兄弟もなく友達もろくにいなかったオレは、学校でよくいじめられていたんだよ。泣きながら家に帰ると、おふくろに『そのぐらいの事でめそめそするんじゃない』ってよ、いつも怒られてたもんだ。そんなおふくろも、オレが高校を卒業すると今までの苦労が祟ったせいか、病気でな。死んじまった……」
そして浩さんは、口に含んだタバコの煙を深く吸い込むと、再び語り始めた。
「それから消防士になって、すぐに結婚したんだよ。おやじのいない家庭で育ったオレは、人並みの家庭を持つことが夢だったんだ。子供も一人生まれた。やっと手に入れた家族。そして幸せ。だが、それも長くは続かなかったさ……」
「阪神……大震災、ですね」
ケンジが言うと、浩さんは無言でうなずいた。
「消防士ってのは、一日おきに休みでな。運の悪いことに“あの日”はちょうど当番だったんだ。仮眠中のところを地震で起こされてよ。書類棚も倒れるし、デスクの引き出しも飛び出してな。床は足の踏み場もねえありさまよ」
そして、浩さんはもう一度タバコの煙を深く吸い込み、続けた。
「これはただ事じゃねえ。妙な胸騒ぎがしやがるんで、急いで家に電話をかけたんだ。だが、通じやしねえ。オレは不安でたまらなかった。あいつらは無事なのか? 家まで様子を見に戻るべきか。そんなことを考えていると、街中のいたるところで火の手が上がり始めやがった……」
浩さんの話を、ケンジはただ黙って聞いていた。涼子も、ただ黙って、静かに耳を傾けていた。
「そしてオレは、家族より仕事を選んだ。もちろん本音を言えば、仕事なんてほっぽり出して、すぐにでも家に帰りたかったさ。だが、それはみんな同じだった。みんな家族が心配だったんだ。それでも、仕事を優先するしかなかったのさ。より多くの命を……救うためにな……」
浩さんの言っていることは、よく分かった。同じような状況になったとき、はたして自分には出来るかどうか。ケンジには自信が無かった。そして、ケンジはそんな浩さんを尊敬するのであった。
「オレ達はすぐに現場へ向かった」浩さんが続ける。「そして、いざ街に出てみると、崩れた家の外壁、放置された車が道を塞いじまっててな。運よく現場に辿りつけたはいいが、消火栓がイカレちまっててよ、ロクに放水も出来やしねぇ。そんな時、また火災発生の無線が飛び込んできやがった……」
一度深くため息をつくと、浩さんは忌々しそうに、吐き捨てるように言った。
「現場はオレの家さ」
タバコを足元に落とすと、踏み消しながら浩さんが続けた。
「宝くじは当たらねえが、嫌な予感だけはハズレる事はねえ。オレは命令を無視して消防車に飛び乗ると、一人で“現場”へ向かった。ところがどっこい、もう消防車一台でどうにかなる状況じゃなかった。女房と一人息子は……まだ家の中にいたんだ……。倒れた家具や柱に挟まれて……オレが駆けつけた時は……まだ、生きていたんだよ……」
言葉に詰まりながら、浩さんは話し続けた。
「消化をあきらめて助けようとしたんだが、火の勢いが強くてな……。それに、ガレキが邪魔して、思うように進めやしねえ……。普段なら十秒かからずに進める距離が、だ……」
天を仰ぐ浩さんのサングラスが、月明かりで白く光った。
「もう少し早く、せめてあと三十分早く駆けつけてりゃあ……あいつらは……」
浩さんが後悔するように歯噛みをした。
「オレが殺したも同じさ……。九歳になったばかりの一人息子……そして女房は……二人目を、妊娠していたんだ……」
「そんな……」
ケンジには言葉が見つからなかった。涼子も涙ぐんでうつむいている。
「……でも、今の浩さんを見たら、亡くなった奥さんや息子さん、きっとがっかりするんじゃないかな……」
「かもな……」
浩さんは上着の内ポケットから家族の写真を取り出して眺めた。
「署のデスクに飾っておいたものだ……。みんな焼けちまったが、こいつだけは……難を逃れたのさ……」
そして言い終わると、浩さんは写真を上着の内ポケットにゆっくりと戻した。
「あの震災の後、オレはシャバの人間と関わるのが嫌になってな。消防士を辞めて、死のうと思ったんだけどよ……死ねなかったよ。そんな度胸はオレにはなかったのさ」
「浩さん……」
「オレは影なのさ。死ぬことも、生きることも出来ねえ影法師。それでいいんだよ。どうせ誰にも必要とされてねぇしな……」
「そんな事ないよ」涼子は思わず立ち上がった。「若林さんは消防士として、少なくとも震災が起きるまでは、多くの命を救ってきたはずよ? その人たちにとっては、若林さんは必要な存在だったのよ」
涼子が言うと、ケンジもうなずいた。
「そうだよ、浩さん。今からでもやり直せるさ」
「お前らの気持ちはうれしいよ。だがな、オレにはもう生きがいってやつがねえんだよ。オレは今のままでいいんだよ。今のままで……」
浩さんが上着の胸ポケットから取り出したタバコを一本銜えた。そして一度軽いため息をつき、火を点ける。同時に、一発目の花火が上がった。2発目、3発目が後に続く。夜空に咲く無数の花。
「……あいつらにも見せてやりたかったぜ……」
花火に照らし出された浩さんの頬が涙で光った。
「浩さん……」
夜空に、一瞬だけ咲いて散っていく花。浩さんの砂漠のように乾いた心にも花を咲かせてやりたい。しかし、どんな種を植えればいいのか。それはケンジ、そして涼子にも分からなかった。

8月15日。
泉田自動車整備工場の近くを流れる旧中川。毎年この日は、東京大空襲による犠牲者を慰霊するための灯篭流しが行われる。ケンジも仕事が終わると、涼子と一緒に灯篭を流した。
「恐ろしいな……」
黒い川の上に浮かぶ無数の小さな灯が、ケンジに震災を思い出させた。夜空を照らし、気仙沼の町を焼き尽くす炎の海。テレビのニュース番組で、何度も目にした映像。まるで空襲だった。
「この灯篭の数だけ、いや、ちょっとした町一つ分の人命が、一度に、一瞬にして失われる……」
「戦争は、人間の意志で止めることが出来るはずなのにね」と、涼子は虚しくため息を漏らした。
「そうだな……。震災のような自然災害だけは、どうにもならないけどな」
「そうね……」
死は何の前触れもなく訪れる。だが、どんな物にも裏と表があるように、生と死も表裏一体。生まれてきたからには死は避けて通ることはできない。そして、その死は多くの人の心に悲しみを残す。命とは何なのか。いつか浩さんの言った“神様が理不尽なのではなく命そのものが理不尽”と言う言葉。ケンジは改めてその意味を考えさせられた。
数日後。泉田自動車整備工場。
昼休みが終わり、ケンジと吉行が作業を始めようとしたとき、ふいに遠くの方からルパン音頭が聞こえてきた。けっこうな大音量だ。
「誰かさんのおでましだ」
吉行が言った。
「相変わらず騒がしい人だ」
ケンジもため息を漏らした。
ほどなくして浩さんのイーグルマスクがやって来た。カーステレオから激しく轟くルパン音頭。あまりの大音量に、事務所のテツとジョージも苦笑しながら首を振っている。
「よう、お二人さん。元気でやってるか?」
車から降りると、彼はなにくわぬ顔でケンジと吉行に挨拶をするのであった。
「浩さん。もう少しボリューム下げた方がいいんじゃないんスか? そのうちパトカーに止められますよ?」
吉行が呆れながら言うと、浩さんは冗談っぽく笑いながら言った。
「うるさかったか? ワリィ。気をつけるよ」
ケンジは思った。この会話はこれから何度か繰り返すことになるだろう。そして、浩さんはいつものようにテツ、ジョージの三人でポーカーを始めるのであった。
「懲りない人だよ、まったく」
吉行は呆れながら故障車のボンネットを開けて作業を始めた。ケンジも吉行を手伝いながら、事務所でポーカーをする浩さんを見守った。吉行から聞いた浩さんのクセ。ケンジはそれを自分の目で確かめたかったのだ。
「ケンジ、そこ押さえといてくれ」
「ああ」
ケンジはうわの空ではなかったが、視線はつねに事務所の方へ向けられていた。そして、ゲームを始めて3分ほどが経ったとき、浩さんが“肩の凝りをほぐすように首を軽く回した”のである。
「あっ」
と、ケンジが思わず声を上げた。肩の凝りをほぐすように首を軽く回す。それが浩さんのクセであったのだ。そして、それを見たテツとジョージは、互いに目を見合わせると、かすかに口元に薄ら笑いを浮かべるのであった。
「な? 言ったとおりだろ?」
吉行が言った。
これは“ブタ”の時によくやるクセで、浩さんにはほかにもいくつかこういったクセがあるらしかった。当然、それは浩さんが無意識にやっていることで、本人はまったく気づいてはいないのである。結局、この日も浩さんが勝つことはなかった。
仕事が終わると、ケンジは昼行灯で浩さんを待つことにした。店内にはケンジのほかに二人ほど客が居る。そして、ケンジが焼酎を一杯飲み終えようとしたとき、浩さんとマサがやって来た。
「おやじ、いつもの。それと、串カツ」
「アッシも、いつもの熱燗。それと鯖の味噌煮を」
二人は注文すると、ケンジの隣に座った。
「相変わらず負けっぱなしですね、ポーカー」
ケンジが言うと、浩さんはタバコに火を点けながらぼやき始めた。
「マージャンでは負けねえんだぜ? 競馬だって自信はある。でもよ、どうもポーカーだけは、な……。ひょっとして、あいつらグルになってイカサマでもやってんのかな?」
「オレはポーカーのルールはよく知らないんですが、相手のクセを見抜いたり、逆に見抜かれないように気を使ったりして、なんだか”肩が凝る”ゲームですよね?」
ケンジがさりげなく浩さんのクセを指摘した。
「別にそれほど肩は凝らねぇけどな」
浩さんは気がつかない。しかたがないので、ケンジはわざとらしく繰り返した。
「だって浩さん、首を回して肩の凝りをほぐしながらやってたから……。あれは別に肩が凝ってた訳じゃなかったんですね?」
ケンジが言うと、浩さんはハッとしてマユをひそめた。そしてタバコを燻らせながら、なにかを考え込むようにジッとハイボールのグラスを凝視した。
「フッ……」
軽く鼻で笑うと、浩さんはケンジに向き直った。
「それだよ、ケンジ。そういうことだったんだよ」
口元に笑みを浮かべながらケンジがうなずくと、浩さんもニヤリと笑った。マサと店主は、二人が何の話をしているのか分からなかった。そして、要領を得ないといった表情で顔を見合わせた。
翌日。泉田自動車整備工場。
横に積み重ねたタイヤを椅子代わりに腰掛けながら、ケンジと吉行は事務所でポーカーをする例の三人を眺めていた。事務所の窓は大きいので、作業場からでも中の様子がよく見えるのだ。
「どうかしてるぜ? あの人」
吉行が呆れながら言った。
「でも、今日の浩さんは、いつもと違うような気がする」
実は、今日のポーカーのルールは、いつもとは少し違うのだ。
――10分ほど前のこと。
いつものように浩さんがイーグルマスクでやって来た。そして事務所へ行くと、浩さんは上着の内ポケットから茶封筒を取り出し、テーブルの上に置いた。封筒の中には十万円入っていた。浩さんは、その金をポーカーに賭けるというのだ。浩さんの言うルールは、次のようなものであった。
浩さんが勝った場合、次のイーグルマスクの車検はタダでテツが請け負うこと。そして、浩さんが負けた場合は、この十万円を車検料にプラスして払う、というものだった。
それを聞いたテツは、二つ返事で喜んで承知したのであった――
「負けるに決まってるさ。もし浩さんが勝ったらオレはパチンコやめてもいいぜ?」
吉行が自信ありげに言い切った。
「その言葉、忘れるなよ?」
念を押すように言うと、ケンジはニヤリと笑った。と、そのとき、浩さんが“あのクセ”をやってしまった。浩さんがこのクセをやるときは大抵ブタ、つまりハイカードか、あるいはワンペアのときなのだ。テツとジョージがニヤリと笑う。
「終わったな」
吉行がタバコに火を点けると、ケンジが冷静に言った。
「いや、まだ分からないさ」
テツとジョージがテーブルの上にカードを見えるように置いた。テツのカードはストレート。ジョージはツーペア。そして浩さんは……。
ゆっくりとカードをテーブルの上に置くと、浩さんはタバコに火を点けた。テツとジョージが浩さんのカードを覗き込む。そして、そのまま固まった二人をよそに、浩さんはテーブルの上に置いた十万円の入った封筒を上着の内ポケットに戻した。
「まさか……」
吉行が思わず立ち上がった。テツとジョージも、信じられない、と言った表情で、顔を見合わせた。浩さんのカードはフラッシュであった。なんとかギリギリ勝てた、と言ったところだ。
浩さんが得意げな表情で事務所から戻ってきた。
「やりましたね、浩さん」
ケンジが言うと、浩さんはすがすがしそうに笑った。
「いやー、ちょっと危なかったけどな。何とか勝てたよ」
「ケンジ。お前、まさかあのことを浩さんに……」、
吉行がケンジに疑いの眼差しを向けた。しかし、ケンジは浩さんに“直接”教えたわけではなく、さりげなく“気づかせた”だけなのだ。だから、ケンジは吉行との約束を破ったわけではなかったのだ。事務所の中から二人が、窓越しに不機嫌そうな表情で吉行を睨みつけている。彼は、あくまで知らない、言っていないとシラをきったが、結局一万円の減給と言う結果になってしまった。
この日は仕事が終わると、吉行は昼行灯で自棄酒を食らった。ケンジも少し気の毒なことをしたと思ったので、今日はケンジがおごることにしたのだ。そして二人で飲んでいるところへ浩さんとマサもやって来た。
「よう、ケンジ。今日はお前のおかげで、あいつらに一杯食わせる事ができたぜ」
「ケンジ。お前、やっぱり……」
吉行はケンジをジロリと睨んだ。
「まあ、聞けよ」と、ケンジは吉行に事のあらましを説明した。
「……とまあ、そう言うワケなんだよ」
浩さんも続けて言った。
「そう。ケンジは直接教えたわけじゃねえんだよ。ただ“肩が凝るゲームだな”って、言っただけなんだよ」
「どうだ? お前との約束は破ってなかったろう?」
吉行は「やれやれ」と、首を振った。
「お前のトンチにはかなわねえよ。分かったよ。オレの負けだよ。そのかわり、今日はしこたま飲むからな。ちゃんとおごれよ?」
「ああ。好きなだけ飲めよ」
「おやっさん! ビールおかわり!」
翌日、調子に乗り過ぎた吉行は、二日酔いで仕事を休んだと言う……。
それから二ヶ月後の10月。泉田自動車整備工場。
今日はイーグルマスクの車検日だ。もちろん車検料は会社が負担するのだ。テツは浩さんの勝負を受けたことを今更のように後悔していた。
「いやあ、なんだかワリーな。タダでやってもらって」
と言いつつ、浩さんは得意げな笑みを浮かべていた。
「自業自得ですよ。社長とジョージさんには、いい薬になんじゃないんですかね。これ、代車のキーです」
ケンジがキーを渡すと、浩さんは事務所の前に駐車してある代車をチラリと見た。
「なあ、ケンジ。やっぱりあの代車はオレには似合わねえよ。お前の車、貸してくれ」
ケンジも代車をチラリと見た。年式の古い、白い軽自動車。あちこちベコベコにへこんでいる。それも黄色いホイールのスペアタイヤを履いたやつだ。まあ、二、三日だけ我慢すればいい事だ。ケンジは自分の車を浩さんに貸す事にした。
「いや、ムリ言っちまってワリィな、ケンジ。じゃ、まかせたぜ」
そして浩さんはケンジの車に乗り込むと、いつものようにルパン音頭を大音量で流しながら走り去って行った。ケンジと吉行は、さっそくイーグルマスクの点検を始めた。吉行がボンネットを開けてエンジンのチェックを、ケンジは運転席に乗り込み、ペダルなどをチェックした。
「ん?」
ふとバックミラーを見ると、例の「舌を出したニコちゃんマークのぬいぐるみ」が、ゆらゆらと揺れながらぶら下がっていた。「こいつ“あっかんベー”してやがる」
おそらく、浩さんは自分自身の運命に対する皮肉のつもりでこんなものをぶら下げているのだろう。ケンジはしばらく運転席に座ったまま、この舌を出したニコちゃんマークのぬいぐるみをボーッと眺めていた。
「ケンジ」
運転席側のドアウィンドウを吉行がノックすると、ケンジはハッと我に返った。
「どうした? ボーッとして。どっか具合でも悪いのか?」
「いや、なんでもない。ちょっと考え事をしていただけだ」
そして、しばらく点検していると、エンジンルームを覗き込んでいた吉行が厄介な問題を発見したのであった。
「ケンジ、ちょっと見てくれよ、これ。この部品はもう交換しないとダメだね。しかも、外車の部品となると、なかなか日本では手に入らないからな。アメリカから取り寄せるしかないよ」
「そんな……」
ケンジは途方に暮れた。それじゃあ、オレは一体いつまであの廃車同然のスクラップに乗ってなきゃあならないんだ。しかし、ケンジの心配は杞憂に終わった。運よくテツの知り合いの経営する修理工場の裏に、浩さんのと同じ年式のイーグルマスクのスクラップが一台転がっていたのだ。処分するにも費用がかかるので、何年もの間、野ざらしのまま放置されていたのだ。
さっそく問題の部品が使用可能かどうかチェックすると、野ざらしになっていたわりには意外と保存状態は悪くなかったようだ。まるっきりの野ざらしではなく、下屋のかかったところにあったのが良かったのであろう。とにかく、ほかにも使えそうな部品が結構あったので、それを全て外して、予備としてストックすることにした。車体は、工場の裏にブルーシートを被せて放置した。
――それから三日後。
「どうだ? おわったか?」
「ええ。もう済んでますよ」
ケンジからキーを受け取ると、浩さんはイーグルマスクのエンジンをかけた。
「お? 前より調子よくなったじゃねえか」
「そりゃあ、けっこう苦労したからね」と、吉行が苦笑しながら言った。
「いや、ホントにいいウデだよ、おまえら。“こいつ”にかわって礼を言うぜ」
「でも、浩さん」ケンジが言った。「そろそろ国産の中古に買い換えた方がいいんじゃないんですか? あちこちガタがきてるみたいだし。それに、年式が古い上に外車となると、パーツの規格が違うんで整備の問題もあるし……」
「ケンジ。オレは“あれから”ずっとこいつと生きてきたんだよ。言わば兄弟みてえなもんさ。だからオレは、こいつ以外には乗るつもりはねえんだよ」
「浩さん……」
「じゃ、世話んなったな。また来らぁ」
浩さんは生まれ変わったイーグルマスクに乗り込むと、タイヤを鳴らしながら走り去って行った。が、すぐにものすごいスピードでバックしながら戻ってきた。
「CD忘れた」
そして、改めてルパン音頭を大音量で流しながらイーグルマスクは走り去って行った。

11月になって三度目の週末。
昼行灯。店内には仕事帰りのケンジ、涼子、そして浩さんの姿があった。
「吉行とマサはパチンコかい?」
焼き鳥を炙りながら、別に誰に聞くわけでもない、と言った感じで店主が言うと、浩さんが「ああ」と、気の抜けたような返事とともに、鼻や口から紫煙を排出しながらタバコを消した。
そしてケンジも、その排出された紫煙を鬱陶しそうに右手でパタパタと払いながら「ええ」と返事をした。「でも、終わったら来るかもしれない、って言ってましたよ。」
「懲りねえやつらだ」
そう言ってグラスの底に一口分ほど残ったハイボールを一息に飲み干すと、まあ、オレも人のことは言えないか、と、浩さんは苦笑した。
「お、地震か?」と、店主が天井を見上げた。
店内が軽く揺れ始める。しかし、揺れはすぐに収まった。おそらく震度1、もしくは2ぐらいであろう。
「最近、多いな。地震……」
そういうと、浩さんはハイボールのおかわりを注文した。
「今でも、あのときのことを思い出すんですよ」ケンジが独り言のように呟いた。「地震があるたびに、あの日を思い出してしまう……。この記憶は、一生消えないんでしょうか? 浩さん……」まるでグラスの中の焼酎に映しだされた、もう一人の自分に語りかけるように、彼は言うのであった。
「そうさなぁ」浩さんは軽くため息を漏らした。「オレも夜中に消防車のサイレンが聞こえてくると、飛び起きることがある。だが、それはオレたちだけじゃねえ。事件や事故で親兄弟を亡くしたやつだって、きっと同じようなトラウマを抱えてるのさ」そう言うと、彼はタバコに火を点けながら続けた。
「身寄りがあるやつはまだいい方さ。心の拠り所があるやつはな。だが、オレのように天涯孤独のやつは……」
浩だんはサングラスをはずし、哀しいが力強い眼差しでケンジを見つめた。
「ケンジ。お前には両親がいる。そして涼子ちゃんもいる。一人じゃねえんだよ。だからよ、負けるんじゃねえぜ? オレのように……」
「浩さん……」
ケンジの瞳がかすかに涙で潤んだ。
「そうだぜ?」店主も口元で微笑んだ。「困った事があったらなんでも言えよ、ケンジ」
「おやじさん……」
「ケンジ……」
涼子が寂しげに微笑むと、ケンジも可能な限りの笑顔でうなずいて見せた。
「どうだ? みんなでやるか?」
浩さんがポケットからトランプを取り出すと、ケンジが困ったような笑みを浮かべた。
「浩さん。オレたちポーカーはちょっと……」
「ババ抜きだよ。ババ抜き」
そう言って浩さんはニヤリと笑った。そしてケンジ、涼子、浩さんの三人はカウンター席からテーブル席に移動した。浩さんがカードを配り終えると、三人はペアのカードをテーブルの上に捨てた。そして、まずケンジが浩さんのカードを引いた。
「お前、いつか故郷へ帰るって言ってたな? 帰ったら、どうすんだ? また今と同じ仕事でもすんのか?」
手元のカードを眺めながら、浩さんが言った。
「ええ、できれば……。震災前は親父の整備工場を継ぐつもりでいましたから……」
涼子がケンジのカードを引いた。
「はやく元通りになるといいね。ケンジの街……」
ペアのカードをテーブルの上に捨てると、彼女は寂しそうに言った。
「そうさなぁ」浩さんが涼子のカードを引きながらため息を漏らした。「だが、たとえ街が元通りになっても、死んでいった人間はもう戻っちゃ来ないのさ。つまり、被災した人間の家庭生活までは元に戻すことは出来ないってことよ」
言い終ると、ペアのカードをテーブルの上に捨てた。そして、ケンジが浩さんのカードを引いた。
「浩さんは、帰らないんですか? 神戸に……」
そう尋ねると、ケンジはペアのカードをテーブルの上に捨てた。
「今は、帰りたくねぇな。年に一度、墓参りに戻るんだが、あの街にいると、あのときのことばかり思い出しちまう……。もう、戻れねえだろうなあ……」
そして涼子がケンジのカードを引きながら言った。
「復興も大事だけど、被災者の支援も、それ以上に大事と言うことかしら……」
「そうかもな」浩さんが涼子のカードを引きながら言った。「津波で家や家族を失ったやつ。原発事故で避難生活をしてるやつ。そして仮設で暮らすやつは、オレのように、いや、ひょっとしたらオレ以上に苦しんでいるのかもしれねえし、いくらカウンセリングを受けたからといって、つらい記憶が消えるわけでもねえ」
「……そうかもしれませんね……」
浩さんからジョーカーを引きながら、ケンジは呟いた。そして涼子がケンジのカードを引くと、徐にタバコを取り出しながら浩さんが言った。
「世の中、泣くほど悲しいことはあっても、泣くほどうれしいことなんて滅多にあるもんじゃねえさ」
そして言い終わると、眉間にしわを寄せながらタバコに火を点けた。
すると、涼子がカードをテーブルの上に置いて、ハンドバッグの中から小さな包みを取り出した。赤いリボンのついた小さな包みだ。
「はい、若林さん」
彼女はその小さな包みを浩さんに差し出すと、微笑んで見せた。
「涼子ちゃん、これは……?」
灰皿にタバコを置いて、事情がよく呑み込めないまま、浩さんは包みを受け取った。
「浩さん。今日が何の日か、忘れたんですか?」
ケンジの言葉に浩さんがハッと気がついた。そうだった。オレの誕生日だった。
「誕生日、おめでとうございます。浩さん」
「おめでとう、若林さん」
二人の言葉に、浩さんは忘れかけていたぬくもりを思い出した。
「おまえら……」浩さんが思わず涙ぐむ。「あけて見ても、いいかい?」
込み上げる思いに声を詰まらせながら言うと、涼子は笑顔でうなずいて見せた。そして浩さんが包みを開けると、中から現れたのは赤いチェックのマフラーであった。
「……涼子ちゃん……」
肩を震わせながらゆっくりとサングラスを外すと、浩さんの目から大粒の涙が零れ落ちた。
「あったじゃねえか。泣くほどうれしいことがよ」と、店主も焼き鳥を炙りながら、鼻をすすった。
「そうさ。浩さんは独りじゃないんだ。決して孤独なんかじゃないんだよ」と、ケンジが手元のジョーカーを見つめながら呟いた。
「涼子ちゃん……ケンジ……ありがとう……。オレ、もう一度生きてみるよ」
「浩さん」
「若林さん」
ケンジと涼子も気が緩んだのであろう。二人とも頬が涙で濡れていた。
「チクショー!」
ふいに吉行がいきり立ちながら入って来た。「今日は自棄酒だ! おやっさん、ビール! 大ジョッキで」
「アッシも日本酒を! 一升瓶で!」と、マサもいきり立っている。
どうせパチンコで大損したのだろう。やけくそになりながら注文すると、二人はみんなの様子がおかしいことに気がついた。浩さんが慌ててサングラスをかける。ケンジも右手の親指で左の目を拭った。涼子もうつむきながら、ハンカチで目頭を押さえるように涙を拭った。店主は目をしばたたかせながら焼き鳥を炙っている。そして、マサと吉行は要領を得ない様子で顔を見合わせた。
「ひょっとして、みなさん、泣き上戸ですかい?」
マサが言うと、みんながドッと笑い始めた。そして、マサと吉行は再び要領を得ない様子で顔を見合わせた。
「よし! 今日は店のおごりだ! マサ、暖簾を引っ込めろ、貸し切りだ! さあ、飲むなり食うなり勝手にしやがれ!」
そして浩さんも、いつもの調子にもどるのであった。
「さすがオヤジ、話せるぜ! よし! 今日は朝まで飲むぞ!」
店の灯りが消えたのは、空がうっすらと明るくなり始めた頃だった。しかし、もともと酒が弱い浩さんは、当然二日酔いで寝込むはめになったのであった。
それからちょうど一ヶ月後の12月18日。八広駅近くの路地裏に、ある一軒の喫茶店がオープンしようとしていた。
そして、その看板を上げたばかりの店の前に、浩さんのイーグルマスクが止まった。浩さん、それに助手席からマサも降りてくると、二人で店の前に立つのであった。
「見ろよ、マサ。オレの店だ。年内は無理だが、準備が整い次第、オープンするつもりさ」
やや緊張した面持ちで、そして、うれしさで興奮しながら浩さんが言った。
「まさか、カシラが堅気になるとはねえ」マサがしみじみと言った。「これが本当の“まさかの坂”ってやつかも知れやせんねえ」
「なに言ってやがる」と、浩さんが苦笑した。「だがよ、お前の言う通りかもな。そして、これもみんなケンジと涼子ちゃんのおかげさ」
そう言って浩さんは、首元を覆い包む赤いチェックのマフラーにやさしく触れるのであった。そう。涼子に貰った誕生日プレゼントの赤いチェックのマフラーだ。浩さんの黒いコートにはよく似合っていた。
「涼子ちゃんの銀行から融資を受ける事ができてな。この店は中華料理店だったらしいんだが、中も改装したんだ。なかなかいい店になったろ?」
「なかなかおしゃれな佇まいで。アッシも知り合いに宣伝しときやしょう」
「おう。頼むぜ」
「それにしても」と、マサが店の看板を見上げて言った。「カシラ。この“ストック”ってぇ店の名前、こりゃあ、いってえどういう意味なんで?」
「ああ、それはよ……」
浩さんがマサに説明した。このストックと言うのは花の名前なのだ。アブラナ科の多年草。花の色は、赤、ピンク、黄、オレンジ、青、紫赤、白。そして、花言葉は見つめる未来、思いやり、など。
「なるほどねぇ。ところでカシラ。ここ、トイレは使えやすかね?」
「今か?」
マサがモジモジしながらうなずいた。
「たぶん使えるはずだ。もう電気も水道も通ってるはずだからな。小便か?」
「それが、大の方なんで」
マサが恥ずかしそうに答えると、浩さんは声を上げて笑った。
「早く済ましてこい」浩さんが店の入り口の鍵を開けた。「まっすぐ行って、突き当りを右だ」
「それじゃ、ごめんなすって」
浩さんは肩で笑いながらタバコに火を点けた。
「やれやれ。とんだ先客だ」
そして左手をコートのポケットに突っ込み、イーグルマスクに寄りかかった。ちょうどそのとき、三メートルほど離れたところに、黒い怪しい車が停まった。運転席と助手席のドアが開き、中からヤクザ風の男が二人降りてくる。一人は四十代前半の黒い上下のスーツにサングラス姿。もう一人は三十代半ばぐらいのベージュのロングコートを着ている男。そして、彼等はまっすぐ浩さんの方へと歩いてくるのであった。
「おいおい、困るなぁ。こんなトコで勝手に商売されちゃよォ。これ、オッサンの店か?」
黒いスーツの男が店を見上げながら、浩さんに尋ねた。どうやらこの男たちは、たまたま通りかかった地元のヤクザらしい。
「まあな。ところで、何が困るんだ?」
まあ、こういった連中とは遅かれ早かれ、いずれ関わることにはなっていただろう。相変わらず嫌な予感だけは外れることがねえ。浩さんは忌々しく思った。
「ちょっと目を離すとコレだ。野良犬みてえにフラフラっとやって来ては勝手にマーキングしていきやがる」
ロングコートの男が、まるでつまらないテレビ番組でも見ているかのような表情で、見下ろすように浩さんを睨みつけながら言った。
「オレが野良犬なら、テメエは発情してイライラしてるサカリのついたオス犬、ってとこか?」
浩さんがせせら笑った。
「テメェ……余裕こいてるフリしてんじゃねえぞ」
ロングコートの男が逆上した。しかし、浩さんは決して余裕をこいてる“フリ”などしていなかった。競馬のノミなどで、この手のチンピラとはよく関わっていたので、浩さんは慣れていたのだ。
「なあ、オッサン。この手の仕事は下っ端に任せてあるんだがよ、見ちまったからには素通りするワケにはいかねえんだよ」
「で? どうしようってんだ?」
「オレたちと“契約”してもらわなくちゃならない」
黒いスーツの男が言う契約。つまり、みかじめ料のことを言っているのだ。もちろん、浩さんもこの男が言ってる意味はよく分かっていた。
「契約? ああ、あんたらセールスマンか? もうすぐクリスマスだしな。今が書き入れ時ってワケだ」
浩さんがとぼけて見せると、さすがに黒いスーツの男もイライラし始めた。
「オッサン、オレたちを知らねえのか? この辺じゃちょっとばかり有名なんだぜ? 聞いたことあんだろ、景山組」
すると浩さんはタバコを足元に落とし、踏み消しながら言った。
「景山組だかハゲ山組だか知らねえが、テメエらごときポン引き風情に払うゼニなんざあ、持ち合わせちゃいねえんだよ」
「テメェ……」
いきり立つロングコートの男の左肩を、黒いスーツの男が右手で掴み「まあ、待て」と制した。
「なあ、オッサン。月々一万でいいからよ、どうだい? この辺で契約しちまった方が身のためだぜ?」
「あんたらが毎月、オレの店でコーヒー飲んで二万円使ってくれるんなら考えてやってもいいぜ?」
浩さんが皮肉な笑みを浮かべながら、サングラスを指で押し上げた。
「オッサン。この上オレたちにケンカまで売るつもりか?」黒いスーツの男の顔が引きつり始めた。
「先に仕掛けたのはそっちだぜ?」
黒いスーツの男はロングコートの男と顔を見合わせると、深くため息をついた。
「やれやれ」
スーツの男は怪しい車の方を振り向いた。よく見ると、車の中にはもう一人、リーダー格の男が乗っていたのだ。その男は、白い上下のスーツにサングラスをかけており、後部座席の真ん中で両手をズボンのポケットに突っ込み、足を組んで座っている。
黒いスーツの男は彼に首を横に振って見せた。すると、白いスーツの男は、それに右手の中指でサングラスを押し上げて応えるのであった。
それを見て軽くうなずくと、黒いスーツの男はロングコートの男に向き直り、やはりうなずいて見せるのだった。するとロングコートの男は、不敵な笑みを浮かべながらコートの内ポケットから拳銃を取り出した。白いスーツの男がとった行動。それは、拳銃の使用を許可する合図であったのだ。
「オッサン。ファイナルアンサーだ。オレたちと契約するか、店をたたむか。どっちか選べや」
ロングコートの男が、浩さんに銃口を向けた。
「たのむよ、オッサン。オレたちゃあ忙しいんだよ。いつまでもチンタラ遊んでるヒマはねえんだよ」
黒いスーツの男がタバコに火を点けながら言った。
「契約もしねえし、店もたたまねぇ。そしてテメエはオレを撃つこともできねえ」
まあ、いつものことさ。思えばオレの人生、何一つスムーズにいったためしがなかった。ケンジや涼子ちゃんには悪いが、ここで死ぬのも悪くない話だ。やっぱオレは神様に嫌われてんのかな。
「ハッタリだとでも思ってんのか?」
ロングコートの男が再びイライラし始める。
「なら、弾けよ」
浩さんがマフラーを脱ぎ、イーグルマスクのボンネットの上に置くと、ロングコートの男を睨みつけた。
「さっさとハジィてみろや!」
ふいに浩さんがロングコートの男に掴みかかる――タイヤがパンクしたような乾いた音が二つ――ほんの一瞬、時間が止まったように静かになった。
「おいおい、マジで撃つんじゃねえよ」
黒いスーツの男が苦笑した。しかし、ロングコートの男は興奮した様子で銃を握りしめる手を小刻みに震わせていた。
「おい!」
黒いスーツの男がウデを掴むと、ロングコートの男はハッと我に返った。
「ズラかるぞ」
そしてヤクザたちは車に乗り込むと、タイヤを鳴らしながら走り去って行った。
「ようやく……死神が、迎えに来たようだ……」
そう呟いた浩さんの目には、青空に白く輝く太陽が映っていた。
「もう……許して、くれるよな……?」
浩さんは上着の内ポケットから、持てる力を振り絞って、家族の写真を取り出した。
「カシラ、なんです? 今の音は。また家他我等巣の連中がバクチクかなんかを――」
トイレから戻ったマサの目に飛び込んできたのは、胸から血を流して仰向けに倒れている浩さんの姿であった。
「カシラ! どうしなすった!? 一体ぇ、誰がこんなマネを……しっかりしておくんなせぇ! カシラ!!――」
――泉田自動車整備工場。ケンジが外したタイヤを転がしながら運んでいると、ふいにケータイのベルが鳴った。
「マサさんだ。なんだろう?」
ケンジがケータイに出る。
「どうしたんです? マサさん……え!?」
タイヤの取り付け作業をしていた吉行が、ホイールナットを閉める手を止めてケンジを見上げた。ケンジの声の調子から、なにかただならぬことが起きたのだろうと思ったのだ。
「それで、浩さんは……分かりました、とにかくすぐ行きます!」
「どうした? ケンジ」
ケンジは吉行を無視して車に飛び乗った。
「おい、ケンジ!」
そして、とてもいつものケンジからは考えられないような乱暴な運転で走り去って行った。
「浩さんが、そんな……」
ハンドルを握る手が震える――信号もロクに目に入らない――どこをどう走ってきたのか分からないが、気がつくとすでにストックの近くまで来ていたのであった。
ほどなく前方にストックが見えてきた。救急車も今、到着したばかりのようだ。車内からフロントガラス越しにケンジが叫ぶ。
「浩さん!」
ケンジは車から降りると、担架に乗せられて運ばれようとしている浩さんに駆け寄った。浩さんは意識が無いまま、担架で運ばれて行く。
「浩さん!」
浩さんの手から、一枚の写真が滑り落ちた――浩さんが家族と写っている写真――ケンジはそれを拾い上げた。
「浩さん……」
ケンジはイーグルマスクに、背中から倒れこむように寄りかかった。そして彼は、そのまま座り込んでしまった。
「ケンジ」
マサがゆっくりと歩いてくる。
「すまねえ、ケンジ……」彼は浩さんのマフラーをケンジに渡した。「アッシがついていながら、こんなことに……」こぶしを固く握りしめ、しかめた顔でつま先を見つめながら彼は言った。
「マサさん……」
「すまねえ……ケンジ……」マサは繰り返し詫びた。
「マサさんのせいじゃないですよ……」
ケンジは口元にかすかに笑みを浮かべて、マサに首を横に振って見せた。
浩さんを乗せた救急車が走り出す。
マサもケンジのとなりでイーグルマスクに寄りかかった。車体が軽く揺れる。バックミラーには、「舌を出したニコちゃんマークのぬいぐるみ」がぶら下がっている。どんな悲劇も冗談にしてくれそうな無邪気な笑みをたたえながら、ゆらゆらと揺れている。それは、手を振りながら浩さんを乗せた救急車を見送ってるようにも見えた。
――あれから三日が経った。浩さんはなんとか一命をとりとめたのだが、意識不明の状態が続いていた。そして、それから更に数日後の、ちょうどクリスマスの日の朝。もう意識は戻らないかもしれないと担当の医師たちが諦めかけたとき、浩さんの意識は戻った。
その日、仕事が終わると、ケンジは涼子、そしてマサと一緒に病院へ向かった。しかし、まだ意識が戻ったばかりと言うこともあって、やはり面会することは出来なかった。もちろん、それは予想していたことだった。
だが、医師の発した予想外の言葉に三人は面食らった――記憶喪失――彼は、自分が誰なのか、今まで何をしていたのか、そして家族やケンジたちのことも、何もかも分からないようであった。
そして、これが心因性のものなのか外傷性のものなのか、今のところ医師にも原因が分からないとのことだった。
「カシラ……」
マサは浩さんの病室の前にあるベンチに腰を下ろすと、膝の上で手を組んで、うなだれてしまった。
「マサさん……」
ケンジが静かに声をかける。
「アッシは、もう少しここに……」
「……オレたち、先に行ってますよ」
マサは返事をしなかった。いや、したのかもしれない。きっと、胸の底からわき上がる様々な思いが、彼のノドを詰まらせたのであろう。そっとしておこう。二人は静かに、その場を立ち去った。
「ちょっと、夜景でも見ていくか」
涼子は無言でうなずいた。もう、浩さんに会うことはないだろう。ケンジはなんとなくそう思った。そして屋上へ出るまで、彼は一言も言葉を発しなかった。涼子もそんなケンジの背中を見ながら、ただ黙ってついて行くのであった。
屋上へ上がると、二人は手すりの前に立った。そこから見える夜景は、まるで湖面に映し出された星空のようであった。
「これで、良かったのかもな……」
ケンジが呟いた。
「え?」
「これで浩さんは、やっとつらい記憶から解放されたんだよ。そして、やっと幸せになれるんだよ」
「そうね……。でも、なんか淋しいね」
そう。ケンジたちの知る若林浩三は、もういないのだ。泣くほど悲しいしいことと、泣くほどうれしいことが、同時に訪れてしまったのであった。
「ああ。今日はクリスマスだ。きっと天国の、浩さんの家族からのクリスマスプレゼントだったんだよ」
そう言うと、ケンジはコートの内ポケットから浩さんの家族の写真を取り出して眺めた。
「ありがた迷惑なクリスマスプレゼント、か……」
ケンジが静かに呟いた。
「え? なんて言ったの?」
「いや、なんでもないさ」
コートの内ポケットに写真を戻したとき、ケンジのケータイのベルが鳴った。
「……おふくろだ」
ケンジがケータイに出る。
「ああ、オレだよ。……ああ、こっちは大丈夫だよ。親父は? ……そうか、よかった。……ああ、そのうち行ってみるよ。来年の正月にでも。……ああ、分かってるよ。それじゃ」
「お母さん?」
「ああ。たまには顔見せろってさ」
思えば、もう一年以上、両親の顔を見ていなかった。ふと震災前の記憶がよみがえる。家族と過ごした、平凡だが幸せだった日々の思い出が。あの震災への憎しみとともによみがえる。
だが、あの震災がなかったら、自分は浩さん、そして涼子には会えなかったのだ。果たして、この事実をどう理解すればよいのか。ケンジの気持ちは複雑だった。
「あ、雪……」
涼子の肩に、綿毛のような雪が一粒とまった。
暗い空から、まるで桜の花びらのようにヒラヒラと雪が舞い降りてくる。
「さてと。そろそろ帰ろう」
今日は昼行灯で、雪見酒でも飲もう。浩さんのハイボールで……。
ケンジは心の中で呟いた。そして、夜の街を照らすかのように、真っ白な大粒の雪が降り注ぐ。しかしそれは、淋しさで凍ったケンジのうれし涙だったのかもしれない。
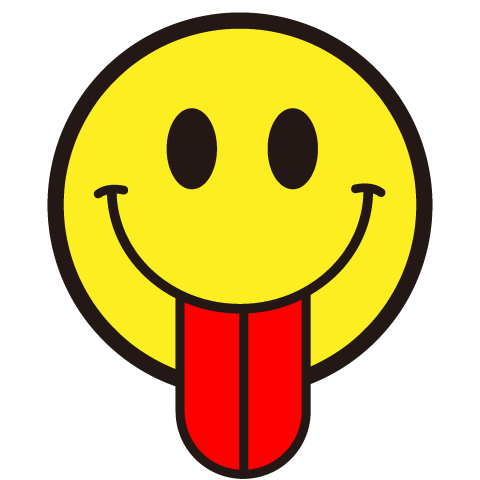
―― おわり ――
ハイボール
エンディング
https://www.youtube.com/watch?v=VBr05wvpR1k
【挿入歌】
*チャプター3の「たんぽぽ」の店内に流れるBGM(ラジオ)
https://www.youtube.com/watch?v=9BLjOalsk8Y
*チャプター6終盤の屋上のシーン
https://www.youtube.com/watch?v=am7-K9deHss
ひとつ追加しました! 2019 8/8
*** 野良猫監督、地震雲を目撃?! ***
みなさん、こんにちは! このたびは野良猫の初監督作品「ハイボール」をご覧いただき、ありがとうございました!
まあ、ヘタクソですよね(笑)。これを書いた当時、野良猫は小説の書きかたなんてぜんぜん知らなかったんですから、当たりまえといえば当りまえの話ですよね(いまもよくわかってないんですが)。
さて、あいさつはこれぐらいにして、さっそく本題に入りたいと思います。
あれは、ちょうど東日本大震災が発生する2週間まえのことだったと記憶しています。そう、たしか2011年の2月26日(27日?)の夕方、午後3~4時ぐらいかな。ふと部屋の窓から空を見ると、なにか黒い竜巻状のものが雲の下に浮かんでいるのが見えたんです。50メートル先の電柱とおなじぐらいの太さだったかな。地上から空に向かって、すこし斜めに傾いた状態(時計の針で例えるなら7時5分の角度)で浮かんでるんです。うっすらと茜色に染まりかけた空の裂け目からのぞく夜の闇のような、不気味な黒い雲。いや、そもそも雲なのかどうかもわからない、得体のしれない物体。それは風にも流されず、煙のように揺らめくこともなく、まるでジャックと豆の木の如く天に向かってそびえているのです。そのとき、野良猫は「はっ」としました。もしや、これが世に言う「地震雲」というやつなのではないだろうか、と。しかし、野良猫は元来、そういった都市伝説や迷信の類はいっさい信じないタイプなので、すぐにあたまの中から「地震雲」を追い出しました(笑)。
ばかばかしい。野良猫は窓に背を向けると、ソファにケツを沈めてテレビのリモコンに手を伸ばしました。そして2、3度チャンネルをいじってから、ふと窓をふり返ると、もう雲の下に地震雲の姿はありませんでした。ちなみに野良猫は福島県の県南地区に在住なのですが(白河寄りの地域)、地震雲が見えたのは南の空でしたね(埼玉か群馬の方角)。
地震雲を見たのは、あれが最初で最後でしたね。じつに不思議な現象でした。野良猫は基本的に迷信とかは信じないのですが、自分の目で見た事実まで否定することはありません。それがたとえ非現実的な現象だとしても、まぎれもない事実として目のまえに存在しているからです。この世には、人間の理解を越えた不思議なものが、たしかに存在している。野良猫は、なんとなくそう思うのでした。
それから、これもたぶん震災となにか関係があったのかな、と思うことがもうひとつ。震災の半年まえ、2010年の夏を襲った、あの超ゲリラ豪雨のことです(もしあれが局地的なものだとしたら知らない方もいるかも)。あの夏の雨は、すさまじいものがありましたね。空からというより真横から、まるで氾濫した川のように窓から雨がなだれ込んできましたからね。音もすごいし、量(勢い)も尋常じゃない。まるで洗車機で洗車中の車の中にいる気分でしたよ(笑)。あんな雨は、いままでいちども経験したことがなかったですね(現にあの夏以前と震災後にあのような雨はいちども降っていない……と思う)。
まあ、現実主義者の野良猫が言うのもなんですが、地震雲やゲリラ豪雨(狂った雨)など、何らかの形で地震の前兆は現れるのかもしれませんね。もちろん信じる信じないは個人の自由ですが、たとえ「まさか」と思っても、用心し過ぎてし過ぎたということはないと思います(常に最悪の事態を想定して準備しておくこと)。むろん、ここで野良猫が述べたことはすべて事実です。あれだけ大勢の犠牲者を出した震災の話でウソは言えませんから。
と、いうわけです。
最後に、この「ハイボール」を読んでいただいた読者の皆様に感謝を申し上げるとともに、豪雨災害や震災で命を落とされたすべての犠牲者のご冥福を祈りつつ、お別れしたいと思います。
野良猫 2019 7/25


