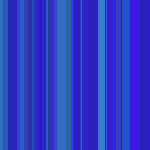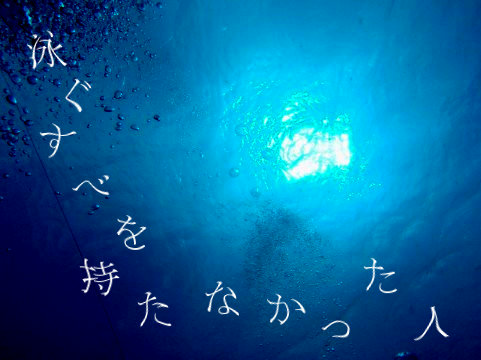
泳ぐすべを持たなかった人
お題サイト「サディスティックアップル」 http://loose.in/sadistichoney/ より
shortお題 「たくさんの人がいたこの星で」
高く、うねり、押し寄せ、飲み込む
もがき、苦しみ、ばたつき、溺れる
そんな海を越えるもの
「就活なんてめんどくせー」
「うん」
押し分け、進み、割いて、上る
散って、消えて、凪いで、止む
そんな海を越えたもの
「いっそ、ニートになっちまうか?」
「それもいいかもね」
泳ぐ術を持たなかった人
現在俺らは25歳。金もなく、風呂なしトイレ共同(ボロ)アパートに二人で住んでいる。家賃と食費を、日雇いバイトで稼いでは、その食費を削り、就活に当てている。大学を卒業してまもなく、俺らはフリーターになった。
正直、地獄だ。
こんな生活から早く抜け出したいのは山々なのだが、今時、無名の大学で、大学院まで行かずに卒業した俺らを雇ってくれるほど余裕のある会社なんて一社もなかった。大体は書類審査で落ち、書類審査で面接までこじつけても学歴に触れられるとアウトで、何かと文句をつけられるのが落ちだった。それでも俺らは諦めず、就活に向かう。
「いってくるな」
「うん、行ってらっしゃい」
羊(よう)がいつも通り小さい元気のない声で、俺を見送った。今日は、羊が就活に行くらしい。二着目千円のスーツを着まわし、就活セットで手に入れた安物のネクタイを締めて、髪の毛も丁寧にムースで撫でつけて。見た目だけは立派だ。そんな羊の姿を俺は横目に見てから、ドアを閉める。軋む木製の床を、履き潰したスニーカーで踏みしめ、アパートの前を掃除する大家さんに挨拶してから、そこらへんに立て掛けてあった自転車に飛び乗り、バイトへ向かった。
「こんにちは」
「おお、坊主、早いな」
現場の仲間(だいたい皆年上)が既に錆びついたドラム缶に火を焚いてそれを囲んでいた。
「若いのに、いい心がけだなーおめーは」
現場の監督が、低くドスのきいた声で言って、俺の肩を叩いた。早く着替えちまえよ、とも言って、火にあたりに行った。俺は簡素なプレハブに入って、急いで着替えて(プレハブ小屋は寒くて、長くいると凍えちまうから)ドラム缶の周りに行った。俺と同じぐらいの年の人や、俺よりちょっと年上ぐらいの人が後からどんどん来て(たぶん、派遣)もたもたと着替えていた。俺らが仕事をやり始めるあたりに、どうしたらいいか分からずにもじもじ、キョドっていて監督に怒られてた。
「派遣なんて、そんなもんだ」
「わけぇもんのくせに、うじうじしてんじゃねぇ」
おじさんたちが悪態をついて、派遣を一瞥してからいってしまった。俺は、へこんでいる派遣の肩を叩き、気にすんなよ、と言ってから後についていった。日雇いのくせに古株な俺は気に入られているから(自分で言うのもなんだけど)気負いせずに仕事ができた。
こんな生活でもいいかと思ってしまう、原因でもある。
「はぁ……」
僕は、緊張を一気に解放して、肩を落とした。道行く人は、そんな俺に見向きもせず通り過ぎていく。
木枯らしが、俺をかすめた。
喜ぶべきなのか、戸惑うべきなのか。どうしよう。いや、あいつなら、きっと喜んでくれるに違いないし。
僕は、二流会社に合格してしまった。
「ただいまー」
「おかえり、お疲れさま」
遅かったね、と一言つぶやいて、極めて質素な食事を見やる。当分、見ていなかったので、その姿が何であるかを思い出すのに時間がかかる、
「酒?」
発泡酒の缶。
俺は眉をひそめて羊を見た。
「無駄遣いしたのか?」
「いや、違うよ。めでたいことがあってね?」
良い予感と、それにともなう、自分の黒い感情。
「僕、二流だけど、合格したんだ」
気まずそうに、それでも笑顔で言う羊。
ワイシャツ姿に、寒さを和らげるためだろうか、着たままのスーツの上に毛布を羽織って。質素な食事をもう一度つつき始めた。
「そう、か」
ぎこちなく笑って、よかったな、と言うとそれが本心でないのが丸わかりなぐらい言葉尻が荒っぽかった。
汗を流すために行こうと思ってた銭湯も、腹が減っていてどうしようもなかった腹も、何もかもどうでもいいかのように、ぐるぐると頭の中を感情が渦巻いている。
喜ぶべき? 悔しむべき。
悔しむべき? 喜ぶべき。
どうしたらいい?
何を悩んでる?
どうしたらいい?
「給料もいいところだから、いい生活ができるよ」
もやしを咀嚼する音が、テレビの無い室内に空しく響いた。
「二人共就職できるまで、がんばろうね」
俺が踏みしめる畳の音が、やけにリアルに聞こえた。
「がんばれよ」
俺から出たのはその言葉だけだった。
「よろしくお願いします」
僕より年下の人間に囲まれ、新人研修を受ける。皆が皆、全身からインテリオーラを出しているわけではなくて、ここが二流だと体感する。適当に資料を渡され、それをふるえる手で読んでいると、隣の人が話しかけてきた。
「ねぇ、あなた、誰かに嫌われてない?」
妙なことを言うと思った。
明朗快活そうな顔をした女性は、僕の返事も聞かずに続けた。
「あたし、見えるのよ。黒い、羽が貴方の肩にのってるわ」
もちろん、おろしたての僕のスーツの肩には何ものっていないし、女性の目は本気ではなさそうに見えるし、僕は「そうですかぁ」と適当に返事をした。
嫌われてる、なんて言葉に引っかかってないとは、言わない。
「ただいま」
一人空しく、薄っぺらいドアを開ける。暗い部屋にあいつはまだ帰ってなくて、きっとまだ仕事してるんだ。僕は、適当にあるもので食事を作りあいつの帰りを待った。
「これがあれば、なんでも上手くいくって? そんなうまい話、あるわけないじゃねぇか」
「でも、千次 羊に負けたくないんでしょう? 抜かされて、嫌なんでしょう? 彼が嫌いになったんでしょう?」
「嫌いになんか――」
「なってないって言えますか? 自分よりできる、千次 羊が羨ましくて、憎らしくて堪らないのでしょう?」
「――」
「自分の方が、社交的で明るくて、出来る人間なのに、周りが認めてくれない」
「そう、か」
「これがあれば、認めてもらえますよ? 欲しくなったでしょう?」
「いくらだ?」
「お金はいりません。ただ、あなたに幸せになってほしいんです」
「嘘くせぇけど、くれ」
「幸せになりますね、」
黒服の男は、俺の背中を叩いた。
「私が」
ドアが開く音がして、あいつが返ってきたんだと安心する。
「おかえり、夕飯さめちゃったよ」
靴を脱ぐ音が聞こえる。もう一度、履きなおす音も。返事はない。
「どうしたの――」
目の錯覚だと思った。
それでも疑えなかったのは、あの女性の話か。
「それ、」
「俺、もう人間止めるわ」
涙が出てきた。歪んで、滲んだけど、確かに見えた。
あいつの背中から生える、双翼の黒い羽根。
「どうして?」
「人間でいるのが、嫌になった」
禍々しい色を孕んだ其れは紛れもない心の闇。
「これからは、僕が働いて、苦しくなくなるんだよ?」
「俺が認められないなんておかしいだろ。この世界にお別れすんだよ」
あいつの欲、あいつの悲しみ、あいつの妬みとか、すべて。黒い羽根は狭いこの部屋に似つかわしくない、絶対的な圧迫感をもった異質。それを生やす、あいつも異質。
「じゃあな」
「待ってよ!」
あいつは、僕の言葉も聞かずに窓にまっすぐ向かい、片足をサッシにかけた。
「どうして、来てくれたんだよ!」
「――」
無言で、飛び去って行った。
割いて、かいて、進んで
泳ぐ術を知る者
もがいて、溺れて、沈んで
泳ぐ術を知らぬ者
人の波にもまれ、
それを切り抜ける術を知らなかった者
彼は、陸路を選んだ。
それは、途方もなく遠く寂しい道であったが、波にもまれ、溺れるよりも遥かに楽であった。
その道が、どこに続いてるとも知らずに、陸路を。
泳ぐすべを持たなかった人
普段っぽい生活にビターというか厨ニ要素を加えてしまう癖が抜けません。
まとまりが欲しいですね。