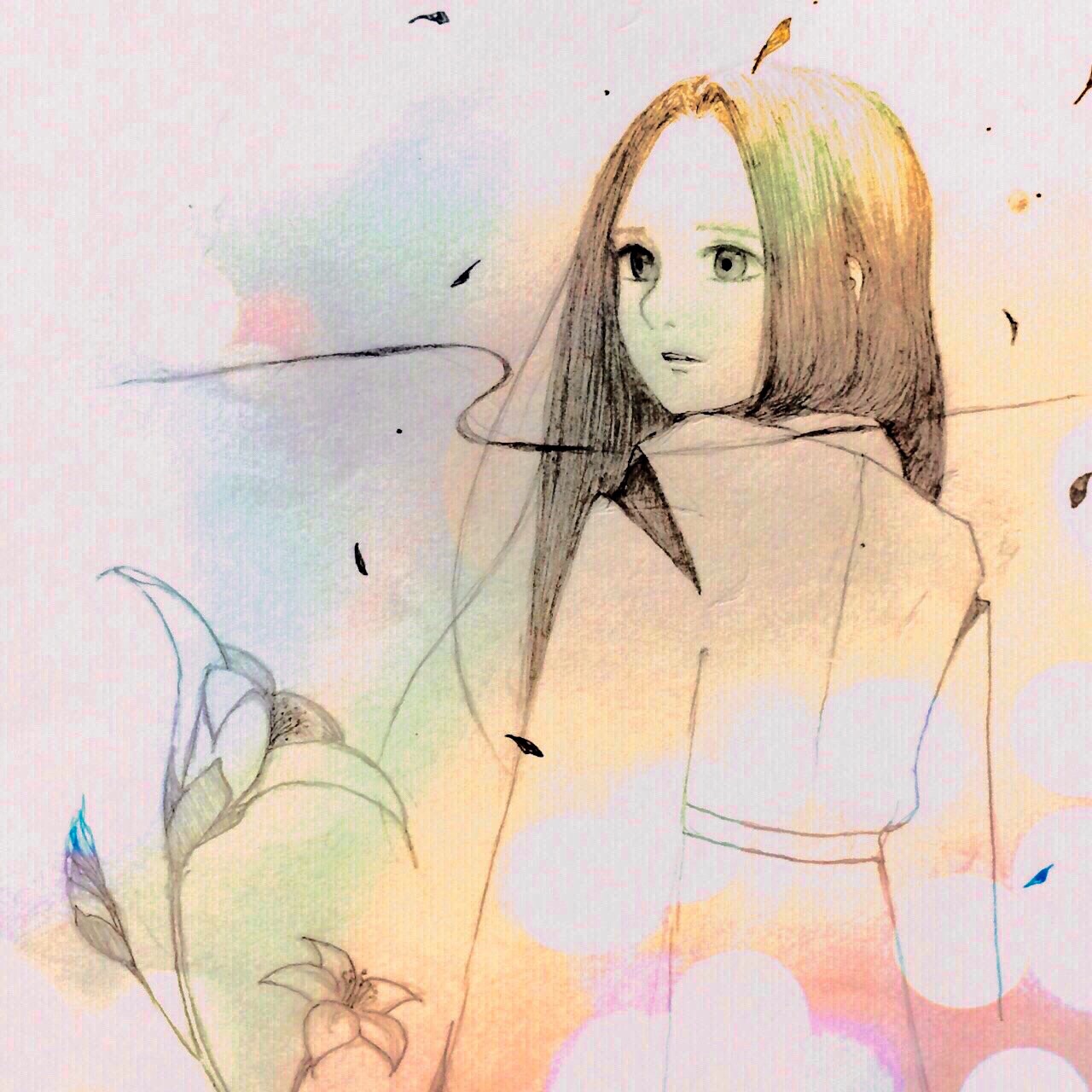
咲夜の物語
稚拙な文章ですが、自分で楽しむ目的で書いてみようと思います。ゆっくりゆっくり書きます。
夜明けの夢
何度も見る夢の中で、私の手を引く声。
遠い記憶のどこかで、すべてを今でも覚えている。
けれど、もう思い出すことは出来ないのだろう。
いつかもう一度、あなたに巡り会えるその日までは。
咲夜は突然、目を覚ました。薄暗い部屋に、自分の荒い呼吸がやけに大きく響く。身体中にじんわりと汗が滲んでいた。長い髪は寝床いっぱいに広がり、すっかり乱れてしまっている。ふと、無意識に指に触れた頬が、熱く濡れているのに気づいた咲夜は、何度目か分からない溜息を吐いた。枕元には、一週間後の誕生日にはじめて着ることになっている、美しい緋色の裳が掛かっている。咲夜は随分前からそれを楽しみにして、目覚めると毎日のように、うっとりとその裳を眺めてきたというのに、今は何故か、その喜びも思い出せないほど疲れ切っていた。
初めてその夢を見てから、もうすぐひと月がたつ。最初はごくたまに見るだけだったのに、最近ではほぼ毎日その夢を見るようになった。日を重ねるごとに、夢の内容は鮮明になる。そしてその度に、咲夜は泣いて目を覚ますのだ。
咲夜は涙をそっと拭って、寝返りをうった。どうして自分は、何度もこの夢を見るのか、いくら考えても答えは一向に出ない。
真っ暗闇の中で、咲夜の名を呼んで、その手を引く一人の人物。顔はよく見えず、誰なのか分からない。けれど夢の中で咲夜は、その人をずっと昔から知っているような、不思議な感覚にとらわれていた。握られた手は、驚く程温かかった。
咲夜は気持ちを落ち付けようと、布団を引き寄せて包まってみた。けれど、どうしても眠ることが出来ず、もぞもぞと布団から這い出た。
冬の残り香が漂う早朝は、まだ随分寒かったが、咲夜は寝間着のまま、ふらりと部屋の外に出た。
庭に出ると、夜明け前のやけに静かな空気が辺りを支配していた。咲夜は縁に腰掛けて真上の空を見上げると、薄くなった藍色の中に、小さな星たちが煌めいていた。咲夜はなぜか、胸の奥がきゅっと切なく締め付けられ、涙が出そうになるのを感じた。
視線を東の方角に向けると、空は白み始めていた。目に見えない何かが、咲夜の肌にぴりぴりと刺さる。空気は静まり返り、迫り来るその時をじっと待っていた。周りの生き物と同じように、咲夜も静かに息を潜める。とうとう、風の音も、虫の声も、ぱったりと聞こえなくなった。
不意に東の山際から、一本の光の矢が空に突き刺さった。その傷口からは、じわり、じわりと、血が滲んでいく。追い打ちをかけるかのように、矢は次々と放たれ、あっという間に空はその明るさに飲み込まれた。
空気が一層澄んだ瞬間、遠い山際から、黄金色がゆっくりと滲み出した。その光は大きな波となって、地上に押し寄せた。辺りの空気は一変し、何処かに隠されていた音という音が、一斉に鳴り出す。空は見る間にその色を変え、藍と橙とが複雑に混ざり合っていった。
しかし、その光景を目にした咲夜は、胸に微かな痛みを覚えた。誰もが感嘆の声を漏らすような、美しい払暁を繰り広げる空。それが、咲夜の目には、恐ろしく燃え盛る豪炎のように写った。みるみるうちに燃やされていく名も無い星たち。気づけば咲夜の目は、東の曙ではなく、頭上の静かな殺戮に奪われていた。日が沈めば、また星屑の夜は巡り来るのに、その光景は咲夜に強く"死"の匂いを感じさせた。
夜明けの空気を胸いっぱいに満たし、咲夜はすっと立ち上がった。溜息を吐いてばかりではいられないのだ。そして、刻一刻とその輝きを増す太陽を見つめ、小さく呟いた。
「負けないわ。」
咲夜は太陽にくるりと背を向け、一人部屋に戻っていった。西の空に残った最後の星が、きらりと瞬いて消えた。
白百合の護り
咲夜は部屋に戻ると、しばらく座ったままじっとしていた。頭の中には、先程の空模様と、あの夢が、交互に浮かんでは消えていった。ついに、いてもたってもなくなった咲夜は、卓に向かい、筆をとった。何故か、これ以上何も考えてはいけないような気がして、思いついたことをただひたすら木簡に書いた。そんなとき、自分でも何を書いているか分からず、後で見返してみても、よく分からないことばかり書いている。その癖に意味はなくても、咲夜はそうすることで、いつも無心になれた。木簡が真っ黒になっては削り、また繰り返し書いた。どれくらいの間そうして書き殴っただろうか。没頭していた咲夜は、随分時間が経ち、いつも起き出す時間になったことにも気づかなかった。
「咲夜様」
突然聞こえた声に驚いた咲夜は、飛び上がって小さな悲鳴をあげた。ぱっと振り向くと、女が困惑した表情を浮かべて、開けっ放しだった戸の近くに立っている。彼女の普段と変わりない、品のある立ち姿に、咲夜はふっと緊張を解いた。
「鹿野」
「随分お早いですね」
鹿野は心配そうな顔で咲夜のすぐ隣に来て座った。鹿野は、美しい女性だった。長い艶やかな黒髪は、簡素ながらも上品な形に結い上げられ、雪のような肌が映えていた。黒々として大きな瞳には、内に秘めた芯の強さが滲んでいる。身につけているのは、質素な柳色の普段着であるのに、その姿はまるで、一輪の白百合のように凛としていた。
咲夜は彼女と二人で、人里離れた森の中の小さな宮に住んでいた。鹿野は、咲夜に読み書きや料理を教えるなど、咲夜の日常の様々な手伝いをしている。鹿野の他に家族というものを持たない咲夜だったが、毎日のように森の様々な生きものと戯れながら、寂しさを感じることもなく、穏やかに日々を過ごしていた。
咲夜は、鹿野の問いかけに答えようとして、慌てて口を噤んだ。夢を見て泣いてしまったなど、恥ずかしくて言えたものではない。
「何でもないの。ちょっと目が覚めてしまって、一度起きたら眠れなくなっただけ」
咲夜はいつも通りの笑顔を見せたつもりだったが、上手くいっているかどうかは、自分にもわからなかった。鹿野は、そういった隠し事やごまかしにはとても聡い。内心恐る恐る彼女を窺うと、鹿野は案の定、険しい顔になって、咲夜をじっと見つめた。
「どうされたのか、仰って下さい」
さっきよりも力のこもった声に、咲夜は一瞬たじろいだ。鹿野はいつも咲夜を側で支え、見守ってくれる。彼女には、咲夜の考えていることなど、筒抜けなのだ。不意に白く細い手がすっと伸びてきて、咲夜の手を優しく握った。
「咲夜様のお顔がいつもと違うことくらい、私には分かります。ここ最近、何か様子がおかしいのも知っています。遠慮なさらないで、私に仰って下さい」
鹿野は口調を和らげ、心配そうな顔で言った。咲夜が眠れない日々が続いているのを、鹿野は知っていた。咲夜は本当の訳を言ってもいいと思ったが、鹿野に言ったところで何も変わらない。咲夜は内心溜め息を吐いた。仕方ない。
「私、裳着が楽しみで眠れないのよ。あの裳を見ると目が覚めてしまうの」
咲夜は夢見るようにうっとりと言った。実際、裳着が楽しみなのは本当のことだ。咲夜はまたこっそり鹿野を窺う。それを聞くと鹿野は、安心した顔で微笑んだ。今度はうまくいったようだ。
「咲夜様が大人になるのももうすぐですよ。でも、お身体に障りますから、しっかり眠ってくださいね」
鹿野の優しい言葉に、咲夜は心の中でほっと胸を撫で下ろした。いつも何から何まで、助けて貰ってばかりの鹿野に、余計な心配をさせる訳にはいかないのだ。
「さて、着替えなくちゃならないわね」
そうして、咲夜の長い長い一日が始まった。
続きのはじまり
やってきたのは、清々しい朝だった。
生まれたての風がそよぎ、若い緑の葉が音を立てた。木々の間に川が流れ、飛沫は木漏れ日に反射して煌めいている。
咲夜は森の中を歩き回って、春が、宮のまわりに満ちているのを身体中で感じた。新しい風、新しい地面、新しい生命。この世のありとあらゆるものが、喜びの声をあげているように思えた。
咲夜の暮らす宮は、森の中の丸く開けた場所に建っている。そのまわりに村や集落はない。一年中、人の往来は殆どないが、咲夜にとっては、豊かな自然こそが友であり、師であり、家族だった。咲夜は毎日のように自然と戯れ、慎ましく幸せに暮らしていた。
咲夜は、土手を降りたところにある河原の大きな丸い石の上に座って川を眺めた。轟々と音を立てて、雪解けの水が流れてゆく。その音には何の迷いも、穢れもなかった。
咲夜は一週間後に待っている、「裳着」と言う儀式に思いを巡らせた。裳着とはいったい、どんなものなのだろう。鹿野が言うには、大人の女性になるための大切な日らしい。けれど咲夜は、それがどんなものあれ、あの緋色の裳を身につけることが楽しみで仕方なかった。
清らかな音を胸に満たした咲夜が、その場から立ち去ろうと腰を上げた瞬間だった。絶え間ない水の音の間に、ほんの一瞬だけ、それを乱す奇妙な歪みを感じた。
はっとした咲夜は、川の真ん中あたりを小さな生きものが流れて来るのを見つけた。よく見るとそれは、まだ生まれたばかりの小さな子鹿だった。子鹿は必死にもがきながら、川をどんどん流れて来る。咲夜は咄嗟に川岸に駆け寄ったが、全く手が届かず、子鹿は瞬く間に目の前を流れ過ぎて行った。
あのままでは溺れて死んでしまう…!
気がつくと、咲夜は地面を蹴って走り出していた。子鹿はどんどん流されて行く。咲夜はそれを夢中で追いかけた。しかし、足場の悪い川岸をどんなに全速力で駆けても、徐々に咲夜と子鹿の距離は離れていってしまう。
そのときだった。突然、咲夜の目の前の景色が大きく揺らいだかと思うと、何かが弾けるような音と共に、鋭い閃光が走った。咲夜は足を縺れさせ、その場に倒れてしまった。身体中がびりびりと痺れて、動くことが出来ない。遠くで子鹿が鳴くのが微かに聞こえた。咲夜は声のする方を見やったが、子鹿はもう追いつけない距離に見えた。
もう助けることは出来ないと咲夜が諦め俯いたとき、川下で大きな飛沫があがった。咲夜ははっとして顔を上げ、目を凝らしてよく見ると、人が川の真ん中に立っているのである。その人は両腕を左右に大きく広げ、流れてくるものを待ち構えていた。子鹿は必死にもがきながら、ついにその人のところまで流れ着いた。その人は子鹿をその腕に捕まえると、ばたつく足をやっと抑えて、川の端まで泳いでいった。それを目にして、心底ほっとした咲夜は、動こうとするのも止め、しばらくその場に倒れたまま、全速力で走ったせいで、信じられないほど速くなった自分の鼓動を感じた。しかし、次第に気分が朦朧とし始め、何も考えられなくなっていった。咲夜がついに意識を手放そうとした瞬間、頭の上から貫くような鋭い声がした。
「助けられもしないのに、軽はずみに追いかけようとしてはいけません」
気がつくと、黒々とした体格のいい馬が、咲夜の側に立っていた。その上から、男が此方を見て厳しい表情をしているのが見える。男は簡素ではあるが、それなりにきちんとした身なりをしているようだった。馬はその毛の色と同じ、黒の鞍を付けていて、すましたように静かにしていた。
咲夜は言われた言葉に言い返そうとしたが、声にならず、ただ男を睨みつけた。しかし、咲夜はその姿をもう一度見て、はっとした。男の衣や髪ははぐっしょりと濡れて、雫が滴り落ちている。この人が子鹿を助けるために、雪解けの冷たく凍える川に飛び込んで、子鹿を捕まえてやったのだ。咲夜は慌ててお礼を言おうとした。しかし、やはり言葉にすることができない。男は厳しい表情のまま、あたりを素早く見回し、何か言おうとしている咲夜を制止した。
「声を出さないで」
男は辺りを警戒しながら、更に強い口調で急いで馬に乗るように言った。咲夜は事態が飲み込めず、惚けたように男を見つめていたが、男のただならぬ様子に、慌てて立ち上がろうとした。しかし、どうしても身体に力が入らない。すぐにそれに気づいた男は素早く馬を降りると、ぐったりとする咲夜をひょいと抱き上げ、瞬く間に馬上に乗せた。馬は男が乗るやいなや、物凄い速さで駆け始めた。咲夜は、得体の知れない脱力感が、身体が力強い馬の背に触れている面から徐々に消えて、力が戻ってくるのを感じた。何も考えられなかった頭も少しづつはっきりし始める。気が付いた時には、自分の置かれている怪しげな状況に焦ったが、どうやら馬は、咲夜が元来た道をそのまま走っていくようだ。馬は風のように森を駆け抜け、あっという間に咲夜の暮らす宮へたどり着いた。まだぽかんとしている咲夜を、男が今度は引きずるようにして馬から下ろし、何も言わずに咲夜の腕をひっつかんで、どんどん宮に入った。咲夜は男に引っ張られながら、なんとか歩けるようになっていた。そして、男はある部屋の前に立つと、戸をぴしゃりと開け、中に座っていた美しい女性に向かって切迫した声で叫んだ。
「この子は外に出た。もうここは危ない」
鹿野は部屋の中で正座をして、男が来るのを待ちかまえていた。ただでさえ白い肌は、今や血の気を失い蒼白になって、まるで病人のようになっている。鹿野は、咲夜が今まで見た事もない程に緊張した面持ちで、男の言っていることを何もかも悟っているようだった。張り詰めた空気の中で、咲夜だけが何も分からないまま、男に腕を取られ、呆然としていた。鹿野は男に向かって頷いた。
「こうなったからには仕方のないことです。ここのことは私に任せて、あなたは咲夜様を峰河様のところへ急いでお連れしなさい」
男は掴んでいた咲夜の腕を離すと、咲夜に向かって静かに言った。
「できるだけ早く、ここを離れなくてはなりません」
それだけ言うと男は部屋から出ていった。
鹿野は立ち上がって咲夜の側に寄ると、優しくも焦った口調でこう告げた。
「咲夜様、申し訳ありませんが、説明しているいとまがございません。急いでここを離れる支度をしてください」
咲夜には訳がわからなかった。何もかもが唐突過ぎて、何がなんだか理解が追いつかない。しかし、彼らの間にのっぴきならない事態が起こっていること、それが自分と深く関係しているということだけは理解できた。しかし。
「どこに行くというの。私たちはいつ帰ってくるの」
「咲夜様はもう、ここへは戻りません。行先は遠い場所です」
咲夜はこの場所が大好きで、林や川や、そこに生きる全ての生きものを愛していた。それなのに、こんなに突然降って湧いたような分からない理由で、ここを離れるというのだ。鹿野は表情を変えず、淡々と告げた。
「もうここにはいられないのです」
そして咲夜は、鹿野に促されるままに着物や食料を用意し、馬に括り付けた。咲夜はまたしても男に引っ張り上げられ、馬に乗せられた。そして、鹿野を振り返った。
「鹿野」
鹿野は緊迫した面持ちで咲夜を見つめている。
「あなたはどうするの」
「私は遅れて行きます。咲夜様は先にその者とここを出てください。」
「また会えるのよね」
咲夜の懇願するような表情に、鹿野はその唇にいつもの柔らかな笑みを浮かべ、答えた。
「ええ、かならず」
鹿野は努めて落ち着いた声音で話していたが、やはり声の端々に緊張と焦りが感じられた。いつも穏やかな彼女が、こんなにも焦っているところを咲夜は初めて目にした。しかし、ここには馬はもういない。鹿野がすぐにはこの宮を離れることができないのは、咲夜にも分かった。彼女がここに残って無事でいられるのか、尋ねようとしたが、次の瞬間、馬はまた風のように走り出してしまった。この一連の出来事があまりに突然であることへの驚きと、戻ってこれない悲しみが一気に咲夜を襲った。そして次には、説明も何もないまま、見知らぬ男に連れられて、親しんだ場所を離れさせられた怒りが込み上げてきた。咲夜は前に座る男に向かって、つっけんどんに叫んだ。
「あなた誰なの」
男の背中は馬の走りと共に規則的に揺れている。しばらくの間があって、声が聞こえた。
「…緋梢といいます」
静かな低い声だったが、激しい馬の足音に掻き消されることなく、咲夜の耳まですんなりと届いた。
「何が起こっているの」
再び咲夜は男に向かって大声で叫んだ。男はそれを聞くと、小さくため息をついたようだった。
「鹿野から何も聞かされていないのでしたね」
緋梢は、誰に言うでもなくそう呟いた。言葉に微かに息が混じっている。咲夜が黙っていると、緋梢は言った。
「鹿です」
「…鹿?」
まったく訳が分からない咲夜は、ぽかんとして聞き返した。
「鹿は罠だったのです。あなたをおびき寄せるための」
それでも訳が分からない咲夜は、今度は黙って考え込んだ。
咲夜が何も言わないのを見て取ると、またため息交じりに緋梢は言った。
「あなたは子鹿を追って川を下ったでしょう。鹿野からよく言い聞かされているはずの目印を忘れて。」
その瞬間、咲夜ははっとした。そうだ、目印--。
「あなたは超えてはならない境界線を超えた。鹿野があなたを守るために張り巡らせていた結界を破ってしまったのです」
緋梢はただ淡々と事実だけを述べた。それを聞いた咲夜には、思い出したことがあった。
いつも優しい鹿野が、たったひとつだけ、小さな頃から咲夜に厳しく言いつけていたことがあったのだった。
"林の中にある夕顔。そこより先へ行ってしまうと、鬼に見つかってしまう。"
小さい頃はそれを心から信じて、林の中の一定の距離に必ずある夕顔に出会っては、恐ろしくなって宮に引き返したものだった。しかし、今となっては幼い咲夜があまり遠くに行かないためのただの脅しだと思っていた。
「本当に、鬼が…。」
口にした途端に、周りの空気が真冬のように冷たくなって、ぞわぞわと気味の悪い悪寒がした。緋梢は淡々と馬を駆った。
「鬼、ですか。」
緋梢は少し考え込むようにゆっくりと呟いた。
「確かに、そうとも言えるかもしれません。彼らはずっと昔から、あなたのことを狙っているのですから。」
「私がいったい何をしたというの。」
咲夜はますます混乱して、半ば喚くように言った。あまりの恐ろしさに涙が滲んで、緋梢にしがみつく手に力がこもった。一拍ののち、緋梢の淡々とした声がゆっくりと告げた。
「あなたは器の巫女だ。天照大御神をその身体に宿す、この世で最も恐れられる能力の持ち主なのです。」
黒馬の主人
規則的な揺れに身を任せ、いつのまにか、やり場のない激しい怒りも落ち着いた。ただ、どうやったって分からないはずなのに、ぐるぐると頭の中であれこれ考え続ける。
咲夜は今まで、これほど遠くに来たことは一度も無かった。どれくらい走っただろうか。太陽はもう西に傾き、夜の気配が少しづつ辺りを蝕もうとしている。
緋梢は馬を止めると、咲夜を手伝って地面に下りた。この辺りもまだ、同じ森が途切れることなく続いている。馬は東へ駆けてきたので、咲夜のいた宮は西の方に随分遠くなってしまったのだろう。
「焚き木と食べ物を探して来ますから、しばらくここで待っていてください」
緋梢は無感情な声でそれだけ言って、何処かへ行ってしまった。残された咲夜は、辺りを見回しながら、森の雰囲気が暮らしていた辺りと少しづつ違っているような気がした。しかし、生えている木や植物には大きな違いは無く、咲夜は少しづつ気持ちが落ち着いた。自分にとっては、本当になにもかも初めてなのだ。これから一体どうなってしまうのか、想像することさえもできない。言いようのない不安と恐怖が胸の奥から滲み出してくるのが分かった。
ふと横を向くと、乗ってきた黒馬が静かに立っている。咲夜は黒馬にゆっくりと近づいてその瞳を覗き込んだ。毛色より一層黒々とした、賢そうな目をしている。馬に乗ることも、触ることも、今日が初めての咲夜は、馬がどんな生きものなのか、全く知らなかった。しかし、先ほどの不思議な癒しの力を持つこの黒馬に、強い興味を惹かれた。咲夜が恐る恐る手を伸ばして、鼻面を撫でてやると、馬は気持ちよさそうに鼻を鳴らした。それを見た咲夜は、背伸びをしたり、横に回ったりして、頭や背中の美しい毛並みを撫でた。指で触れると、漆黒の毛がさらさらと柔らかな音を立てる。
「あなたのおかげで、力が湧いてきたのよ。本当にありがとう。」
咲夜は呟くように言った。結界を破って力が入らなかった咲夜は、この馬に乗らなければ歩くこともできなかっただろう。心からの親愛の情を持って、咲夜は馬を撫でた。すると、降って湧いたような声がした。
「まどか。」
咲夜ははっとして馬を見た。驚異的な癒しの力を持つ馬。人の言葉を操ることも、それほど不思議ではないように思えた。外の世界には、こんな生きものまでいるというのか。心底驚いて馬を見つめたまま、口を開けたり閉じたりしていると、背後からまた声が聞こえた。
「私ですよ」
振り返ると、焚き木と2匹のうさぎを抱えた緋梢が立って、少し不思議そうな顔で咲夜を見ていた。咲夜はびっくりして、馬と緋梢を交互に見ては、あまりの恥ずかしさに燃えるような心地がした。何も言えずそのまま黙っていると、せっせと焚き木を組みながら、緋梢が言った。
「その馬の名前は円です。賢いけれど、自尊心も強い。他人が触れるのを許すのは稀なことです」
咲夜はもう一度振り返って円を見た。円は、緋梢の言葉に満足げに首をもたげている。咲夜はそれを聞いて嬉しくなり、そっと円に微笑みかけた。
「あなたの馬なの」
「ええ」
緋梢は黙々と焚き木を組んで、すぐに火をおこし始めた。咲夜はじっとしている訳にもいかず、しばらくそわそわと周りをうろついていたが、何も出来ることがないと分かると、邪魔にならないところで待つことにした。
焚き火が完成すると、緋梢はうさぎの皮を手際よく剥いで、短刀で裁き、枝に刺して火にくべた。そうしてひと段落すると、緋梢は咲夜の向かい側に座って、2人で焚き木を囲んだ。
咲夜は向かい側に座る緋梢を見つめた。咲夜は、その話し方や、振る舞いのせいで、緋梢のことを随分大人だと思っていた。しかし、その顔をよく見ると、緋梢は顔立ちの中にまだ微かにあどけなさの残る、若く精悍な青年だった。咲夜よりも、幾つか年上であるだけのようだ。
「…何か」
不意に聞こえた声に、咲夜ははっと我に返り、慌てて言った。
「いえ、あの、すみません…」
どうやら、あまりにじっと見つめていたらしい。咲夜は恥ずかしくなって、また黙り込んでしまった。しかし、緋梢に聞かなければいけないことは山ほどある。咲夜がやっと口を開きかけたとき、先に沈黙を裂いたのは緋梢の方だった。
「大切な人から貰った馬です」
咲夜ははじめ、緋梢が円のことについて言ったと気付くまでに少し時間がかかった。緋梢は続けた。
「その人は、私に円の他にも沢山のものをくれました。私の一生の恩人です」
緋梢は火を見つめながら、言葉を噛みしめるように言った。焚き火がばちぱちと音を立てて、その顔を照らし出している。咲夜には、緋梢がまるで泣いているように悲しげに見えた。
「その人は、なぜ死んでしまったの?」
緋梢は顔を上げて咲夜を見た。驚きと共に、微かな疑いのようなものが混じった複雑な表情をしていた。
「死んだとは言いませんでしたが」
「分かるの」
咲夜は穏やかに言った。痛みを堪えるような緋梢を見ていたら、訳を聞かずにはいられなかった。緋梢はまた俯いて火を見つめた。
「分かりません。ただ、その人は最後の最後まで、与える人でした」
咲夜には、ただ無表情に火を見つめる緋梢が、その人を思って涙を流しているように見えた。気づけば、頬を伝って流れ落ちたのは、咲夜の涙だった。それに気づいた緋梢は微かに目を丸くし、考え込むように黙った。
それから、二人は焼けたうさぎで空腹を満たし、川から汲んで来た水を飲んだ。そしていよいよ、咲夜は円に乗って来た間に緋梢が言いかけていたこと、自分の本当の正体について、尋ねることにした。
咲夜の物語

