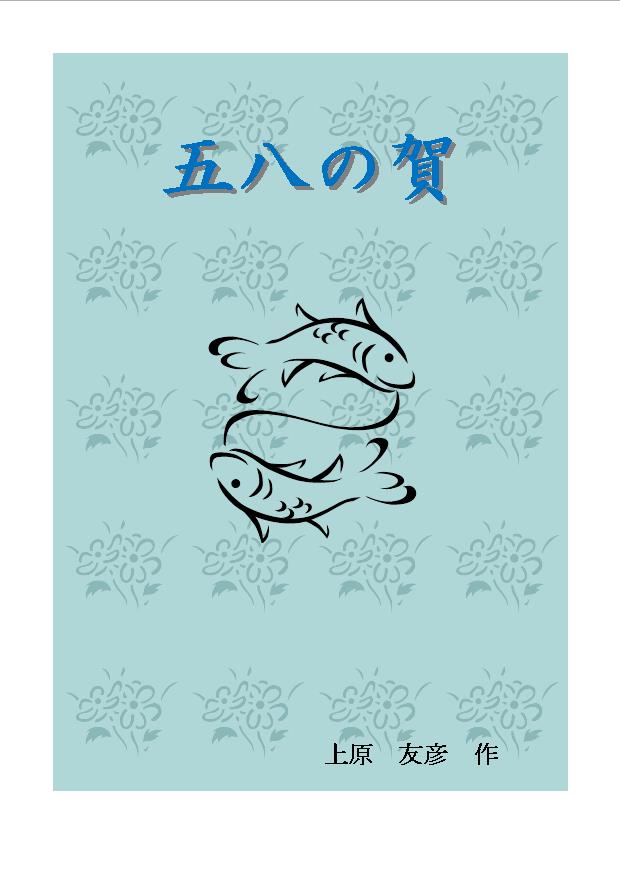
五八の賀
官能小説に挑戦しました。
18禁でお願いします。
自分の意思とは関係なく、次々と女性が現れ、関係を持ってしまう。
それはある物の力であった。
性に溺れて、人生を誤ってしまうか?
フィクションです。登場する人物は、現存いたしません。同姓、同名の団体名はすべて架空の物です。
ご指導頂ければ、ありがたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
序章
春と言うにはまだ肌寒い日が続いている頃、いつものように仕事をしていると、
社内メールが突然に来た。
「前からあなたの事が好きでした。時間のある時に会って頂けないでしょうか?」
女性からのメールである。
彼女は25歳だったと思う。経理部で事務をしている子だ。
名前は確か「高橋順子」だったと記憶している。
ボクは、営業部に属し企画担当を行っている。
一応、課長補佐である。
仕事中に何を考えているのだ?と、嬉しい事は事実だが、私は妻子ある身。
放置する事に決め込んだ。
一
何事もなく2週間が過ぎようとしていた水曜日、そろそろ就業ベルが鳴る頃であった。
「今日は、そちらまで行って最上階の講堂まで行きます。
舞台袖で待っています。来るまで待っていますから」とメールが入った。
興味半分、メールで断るのもこれからの仕事上での付き合いもあるので、できなかった。
午後6時前に、講堂の舞台袖まで行ってみた。
「来てくれたんですね」
「ああ、でも何であんなメールくれたの?」今思えば大変失礼な質問であった。
「前から、気になっていて」
「それは、ありがとう。しかし、何でボクなんかを?」
「素敵だからです」
「………」無言状態が続いた。
息苦しくなり、「ボクの事好きなら、キスしてもいいかな?」
彼女は無言であった。
そうなるべくしてそうなったのか?
彼女の愛くるしい顔を見ているうちに、自然と彼女を抱きしめていた。
「嬉しい」
「ボクもこんなに可愛い子から、告白されてすごく嬉しいよ」
髪の毛を撫で、その手を彼女の顎の下に移動させ、顔を上向きにさせた。
彼女は、少し荒い息遣いで目を閉じていた。
ピンク色にきれいに塗られたルージュが輝いている。
初めは、触れるか触れないかくらいの口づけをした。
背中に回していた手を前に持ってきて、彼女の胸の膨らみを確かめるかのように撫でていた。
彼女の息遣いが次第に荒くなって来た。
それに刺激され、軽く合わせた唇を割って舌を挿入させた。甘酸っぱい香りがボクの口の中でいっぱいになった。
下着をつけている上から、胸の突起物を探り当て、親指の腹で円を描くように愛撫を加えながら、更に舌を奥へと挿入させていく。
それを待ち構えていたかのように、彼女の舌が絡み付いてくる。
お互いの唾液で、口の周りはベトベトになっていた。
かなり長い時間、ディープキスをしていたと思う。堪えきれずに、
「ああ……」と微かな喘ぎ声と共に身もだえしながら唇を話していった。
「あなたが欲しい」と彼女が言いだした。
「ここで?」彼女はコクッと頷いた。
「分かった」しかし、舞台袖から降りた部屋には、実験に使用する台が2つ並べて置かれているだけである。
舞台袖から彼女の手を取り、数段の階段を下り、今度は初めから激しく唇を奪った。
彼女もボクの肩に手を回し、体全体を押しつ得てくる。
キスをしながら、彼女のブラウスのボタンを外していった。そこからはピンク色の花柄で上部に刺繍が施されている上品な下着が現れた。
ブラウスを肩から脱がせて、台の上に置いた。彼女の首筋から肩、脇の下まで舌を這わせる。甘ったるい汗の匂いがした。
嫌がる様子もないので、ブラのフォックに手を回し、外すと豊満な乳房が現れた。薄桃色の小さめの乳暈に尖った乳首に吸い付いた。
「うっ!」舐め回していくと、
「ああ~、感じる」
彼女の口からは、甘酸っぱい吐息が吐きだされた。
乳房を揉みながら、その尖った乳首の周りをゆっくりと舌を這わせていく。
彼女は首を仰け反らせて、白い喉が丸見えだ。
肋骨付近にも舌を這わせながら、髪の毛を優しく撫でていく。
外は寒いくらいなのに、二人ともジッとりと汗ばんでいた。
上半身に舌を這わせていても、その汗の匂いがする。微かな香水と混ざり、何とも卑猥な香りだ。
彼女も身悶えしながら、ボクの股間ですっかり大きくなり、ズボンがきつくなっているものを、着衣の上から撫でている。
「ジ・・・」と、ズボンのジッパが下されていった。そこからは、押し込められていた物が解放されトランクス型の下着をこんもりと持ち上げていた。
巧みに彼女の指は、下着の間から脈打つくらいに大きくなったものを捉え、外へと導き出した。
先には我慢していた為液体でヌルヌル状態であった。その液体を塗すように、大きくなった物の先を優しく撫でまわしてくれた。
そのあまりの気持ち良さに、声が出そうになった。
しばらく撫でまわした後、胴体を掴み根本から先に向かってやさしく撫でまわしていく。
彼女はにっこり笑いながら、跪いてボクの大きくなったものを、パクッと咥えた。
舌で万遍なく、先の方を舐め回す。
上目づかいで、ボクの反応を確かめながら。
鈴口を入念に舌で遊ばせ、今度は下から裏筋を舐め上げて行く。
「なんて、気持ちがいいんだ」心の中で叫んだ。
顔を前後に徐々に激しく動かせ、両手で優しく玉を持ち上げるように揉んでいる。
「もういいよ」と言うと、スポっと口から引き抜いた。
今度は、彼女を抱き上げて立たせ、再びキスをする。
上半身は、裸である。キスをしながら、タイトスカートのフォックに指を掛け、外しファスナーも下していく。
ストンとスカートは落ち、肌色のパンティストッキングだけとなった。
「寒くないか?」
「ええ、大丈夫。抱いてくれているから暑いくらい」実際、彼女の肌はジッとりと汗をかいていた。
再び乳首を人差し指と中指で挟みながら、豊満な乳房を揉む。白い肌に青い血管が透けて見えている。
彼女は腰をくねらせながら、喘いでいる「ああ~」
次第に周りに濃密な香りが漂ってきた。
そのまま、ストッキングをずらせ、机にもたれさせながら、片足ずつストッキングを巻き取っていった。
下着は、ブラとセットになっていて、薄いピンク色で縁に刺繍が施されていた。
机の上に座らせて、脚をM字型に広げた。
そこだけ二重になっている部分を人差し指で下から上になぞってみる。
「はぁ、はぁ」彼女の息が早くなってきた。
その部分に鼻を近づけると、酸味のある濃密な香りが漂っている。
下着に指をかけると、彼女から腰を上げて脱がせやすくしてくれた。一気にパンティをずり下げる。
そこには、プッくらした丘の上に細やかな恥毛が芝生のように生い茂っている。
膣口は真っ直ぐな線を描くように、閉じられていたが、その隙間から白濁した液体が滲みだしていた。
「きれいだ」
「恥ずかしい」
彼女は脚をくねらせ、その部分を隠そうとする。
すかさず、内腿を5本の指で撫でさすると、自然と脚は開いてきた。
秘めた部分に顔を近づけ、花弁を指で広げるとそこは、鮮やかなピンク色の肉襞があった。
舌で膣口から尿道口を辿り、皮を被っているクリトリスを露出した。
真珠のようにキラキラと光沢を放っている。皮を被せたり、剥いたりを繰り返し、舌でも突起物を舐め上げる。
「うっ!」
「あ~~、はぁ~」声を抑えきれないようだ。
手の甲を口にして、声を出さないようにしている仕草が可愛らしい。
クチュクチュと音がするくらい舐めると、秘めた部分から白い液がどんどん滲み出て来る。
酸味かかった淫臭がボクの鼻孔を満たしていく。
「お願い入れて。我慢できない」
「わかった、ゆっくり入れるね」
こんなに元気だったのか?と驚くくらいボクの分身は、下腹に当たるくらいまで持ち上がっていた。
それを持ち、彼女に覆いかぶさるように、狙いを定めて、静かに埋め込んでいった。
「うっ!あっあ~」
暫く、入口付近で送出を繰り返していると、
「奥まで!奥まで入れて」
言われるまま、ズンと奥まで突き抜けるくらいの勢いで、挿入した。
「いや~~、感じる。奥に届いている。ズンズンするのが感じる、あ~」
もうここまでくると、フルピッチで送出を繰り返した。
「うっ!」こっちが今度は快楽の波が押し寄せできた。
「出る~」
「出して、内に出して!」
その言葉が終わらない内に、勢いついた樹液が放出された。ドクっ、ドクっと。
その放出に合わせるかのように、体をガクガクと痙攣させ、彼女の中は収縮を繰り返し、出たものを全て飲み込むように絞り出されていく。
最後の1滴まで、吸い取られたようだ。
まだ、分身はそのままにして、激しい愛欲の余韻を味わっていた。
「好き」彼女はそう言うと、貪りつくように唇を合わせてきた。
グッタリしているところに、顔中を舐められるように、キスをされ舌で舐めまわされると、
さっき出したばかりなのに、ボクの分身はまた大きくなってきた。
「すごい、また大きくなっている」
「君が余りにも素敵だから、またしたくなってきたのかな?」
「私何度か逝っちゃったけど、大丈夫だよ。しても」
「本当?でも、中がベトベトになっちゃっているよ」
「このまま、して」
汚れないように、彼女のブラウスや下着を横に寄せて、彼女を俯せにさせ、腰を持ち上げた。
ひんやりした、小ぶりの小さなお尻を突き出している格好だ。
ボクの残液なのか、彼女の愛液なのかボタボタと、机の上に滴っている。
お尻の割れ目を、手で少し広げるとそこには淡いピンクの蕾があった。
そっとその蕾に舌を這わせ、少し舌先を内部にいれると、微かに微香がした。
「イヤ、恥ずかしい。そこは止めて」
「あまりにきれいなので」と、舐めるのを一時中断して、さらに奥深く舌先をいれて中でクチュクチュ動かしていくと。
「何か変。そんな所が感じるなんで初めて」
ボクは黙ったまま、微かな微香がする蕾の中を堪能した。
机には、先ほどより多くの愛液が滴り、水溜りのようになっている。
「本当に変になりそう」
「また、いっちゃいそう」と言うなり、ガクガクと体を痙攣させ、そのまま俯せてしまった。
「私はもう堪忍して。十分。その代わりこの大きくなったものを大人しくさせないとね」
と言うなり、ボクの分身を咥えた。
たっぷり自分の唾液を先端に万遍なく塗し、右手で幹を擦り上げる。
口と手を駆使して一生懸命分身を扱きあげている。
可愛らしい眼を上に向け、ボクの表情を読み取っているようだ。
だんだん気持ち良くなって行き、自分でも恥ずかしいくらい感じて仰け反ってしまった。
次の瞬間、樹液を思いっきり彼女の口の中に放出していた。
放出が終わっても、幹を絞り上げるようにし、最後の最後まで絞り出すように、口でも吸いあげ体中の体液が呑み込まれたような錯覚を覚えるくらいであった。
ボクもその場に座り込んでしまい、彼女はその横にしゃがみ込み、口づけを交わした。
二
後日、彼女の職場へ用事で行ったが、何もなかったかのように、完全に無視している。
女性って怖いなと、つくづくそう思っていると、
「上原さん、忘れ物です」
「えっ?」
「精算がおわっていますので、これ渡しておきますね」と封筒をわたされた。
もちろん、精算する物などないのだが………。
自席に戻り、封筒を開封したら中にメモが入っていた。
「来週の金曜日、お会いできますか?できれば一緒に食事したいと思っています。
OKならこのメモにOKと書いて、そのままこの封筒ごと私に返してもらえますか?」
OKありきのメモであったが、もちろんボクはそのつもりで「OK」と書き、封筒に戻した。
当日は、仕事がかなり重なり、結局約束の時間には行けなかった。しかし、彼女は約束の場所で待っていてくれた。
「ごめん、仕事がなかなか終わらなくて」
「いいえ、構いませんよ。仕事を一生懸命されている方が私は大好きです」
「会社の人に会わなかった?」
「多分大丈夫と思います。この辺までは、会社の人も来ないとおもいますので」
「何が食べたい?」
「何でもいいです、居酒屋みたいな所に行ってみたいです」
「じゃ、そうしよう」
イタリアンとか、フレンチなどと言われても行きつけの店などなく、堅苦しいだけで可愛い人と二人きりでは、味わっている余裕もないだろうな。
と思っていた所に、居酒屋と言われで内心ホッとしていた。
「チェーン店だけど、そこに居酒屋があるからそこでいいかな?」
「ええ」
ボクが先に入り、彼女は後から入ってきた。
「いらっしゃいませ」店員の元気のいい声がした。
「お二人様ですね。こちらの席でよろしいでしょうか?煙草吸われますか?」
ボクは愛煙家だったので、「喫煙できる席でお願いします」
「分かりました、こちらが喫煙席になります」
昔は、居酒屋ではどの席でも煙草は吸う事ができた。今は、煙草を吸う習慣のある人の方が少ないからであろう。
「お飲物からご注文頂きます」
「じゃ、生ビールもらえる?」「私も」
「かしこまりました。お食事のメニューはこちらになりますので、お決まりになりましたら呼んでください」
「はい」店員は、さっさと厨房の方へ消えた。
「遅れて本当にごめんね」
「いえ、わたしこそ、我儘いってすみませんでした。でも、OKの文字見て嬉しくて飛び上がりそうになりました」
「いや~、こんなおっちゃんと一緒に飲んでもらえるだけでも光栄だよ」
「おっちゃんって、言わないでください。私にとっては、掛替えのない人なのですから」
「どこが?って、聞く方が野暮だよね。ボクもこんなに若くて綺麗な人から想われるだけで若返ると言うか、それまで毎日仕事・仕事で、家に帰るのも夜遅くだろ、また朝早く起きて会社に行く毎日が嫌になっていた所」
「それで、私と付き合うと言われるのですか?」
「いや、そんな事ないよ。君が素敵でボクも君がすきだからだよ」正直、心にもない事を平気で言えるものだなと、自分が怖くなった。
今日で終わりにしよう。
自分には家庭があるのだから。
と、勝手に相手の気持ちも考えず、ましてや家で待っている妻や子供の事をさしおいて、こうして若い女性を会っている事自体許されない事とわかりつつ。
「お刺身もいいよね。後、串焼きやサラダなんかどうかな?」
「わたし、お刺身大好きです。お任せしますから頼んでください」
「じゃ、すみませ~~ん」と店員を呼び、食事用の品を注文した。
「お代わり頼もうかな?君は?」
「私もお願いします」
「焼酎でいい?明くる日に残らないので最近こればっかり飲んでいる」
「わたしも同じ物をお願いします」
「じゃ、焼酎の水割りにするね」
初めは、ギクシャクしていたが、お酒が回るに従い、会話は弾んでいた。
気が付くと、10時近くになっていた。
「もう帰らないといけないんじゃない?」
「私は大丈夫ですが、大原さんは帰らないといけませんか?」
「ボクもまだまだ大丈夫だよ」
「じゃ、もう一軒付き合って頂けますか?」
「いいよ」と、言いながらかなり酔っているとは言え、帰ってからの言い訳を考えていた。
次の店は、彼女の知っているショットバーであった。
「ここによく来るの?」
「たまにね。一人で飲みたくなった時に来るわ」
「ゲスな話だけど、女性が一人で飲んでいると、いろんな誘惑はない?」
「ない。と言えばウソになるわ。若い人が一緒に飲まないか?と何度かさそわれたけど、若い人と飲んでいても楽しくないの。
話題が薄いと言うか、経験がないからかも知れないけど、上面の話ばかりで、下心が見え見えなのが嫌なの」
「だから上原さんのような人生経験を積んだ方だと、話題も豊富だし何より頼りがいがある感じがいいの」
「ボクはそんなに人生経験豊富じゃないよ。毎日ヒイヒイ言って仕事しているだけ」
「それが大事だと思うの。仕事には必ず壁ができるでしょ。それを何度も乗り越えて来られていると思うの。それには人への配慮、やり抜く気力、リーダーシップ的な人を惹きつける人望が必要だと思うの」
そう言われれば、もうダメかと思った事は何度かあった。
しかし、皆の協力のお蔭で何とか順風満杯とは言えないが、何とかしてきた自信はある。
「そのとおりだね。失礼だけど見ていないようで、しっかり周りを見ている君こそすごいじゃない?」
「女性はほとんどそうよ。仕事では男の人には敵わない。女性がリーダーシップ発揮しても、それを裏付ける実力、またはバックがいないと、誰も言う事を聞いてくれない。悔しいけど、それが事実ね」
冷静に且つ論理的に見て、それをしっかり自分の考えとして持っている。この年齢で。
ある恐ろしさを感じた。
また若い子に誘われ、鼻の下を伸ばして、ここまで来ている自分が恥ずかしくなった。
「いろいろこっちが勉強になったわ。ありがとう。自宅の近くまで送るよ。あまり遅くなると親御さんが心配されるし」
「ありがとうございます。今日はかなり酔って、余計な事をしゃべりすぎ申し訳ございませんでした。お楽しみは次回と言う事で、お言葉にあまえていいですか?」
「もちろん、ボクも楽しかったし、失礼な言い方だが、こんな素敵な女性がわが社にいる事を非常に嬉しい気持ちになった。社長じゃないけどね」
二人とも大笑いした。
それをきっかけに、店を出てタクシーを止めた。
ここからタクシーで彼女の自宅までは30分くらいで着くだろう。ボクの家まではそこから3,40分で着く。
今日は、何となく清々しい気分で帰れそうだ。
ボクが先に乗り、後から彼女が乗ってきた。
運転手が「どちらまで?」
「谷町筋の○○交差点までお願いします」
「わかりました」というと、静かにタクシーは走りだした。
何を話せばいいか?と迷っている間もなく、彼女が手を伸ばし、ボクの手を握ってきた。
ひんやり汗ばんでいる。
ボクも彼女の手を握り返した。
ボクの手を広げ、反対の手の人差し指で「好き」となぞってきた。
運転手が見ているであろうが、我慢できずに彼女の唇を捉えてしまった。
微かにお酒の香りに混じり、甘酸っぱい香りがボクの鼻孔を満たしてくれた。
店を出る前に、化粧直しをしたのであろう、彼女は、微かに喘ぎながらその行為にしっかり応えてくれ、唇が離れるとハンカチでボクの口を拭ってくれた。
そこには、真紅のルージュが付いていた。
「ここら辺でよろしいでしょか?」運転手の声で我に還った。
「ああ、ありがとう。ここで一人降ります」
「今日は、ごちそうさまでした。また、ご一緒出来る日を楽しみにしています。おやすみなさい」
一人残されたタクシーの中で、疲れているが目を瞑ると、愛くるしい彼女の顔が浮かんでくる。
また、さきほどの口づけの余韻も残っているので、眠気はおこらなかった。
「次もあるのだろうか?」今日で止めようと決めたばかりなのに、彼女に惹かれていく自分の気持ちを抑える事はできなかった。
三
半月くらい経った頃である。
ボクをメインとしていたプロジェクトの営業本部会議でのプレゼンも無事終わり、結果待ちと言う状態であった。
「やりましたね。大原課長補佐。そのプロジェクトが採用されれば、飛躍的に売り上げ増は間違いないですよね」
一人の部下が、感情を抑えきれないように興奮しながらボクに伝えてきた。
確かに、3ヵ月も練りに練った自分で言うのも可笑しいが、画期的な企画の自信作であった。
「皆のお蔭だよ。役員の受けも良さそうだったしね。今夜は皆で前祝でもしようか?」
「いいですね~。皆に伝えておきます。スタッフ全員が今興奮状態ですから、盛り上がりますよ」
「ははは、それはいい」
そんな時、携帯のバイブが震えた。
「おめでとうございます。上原様のグループの企画が素晴らしいかった事、すでに会社中の噂となっています。
ご苦労さまでした」彼女からのメールであった。
部下達に分からないよう、トイレに立ちそっとメールを返した。
「ありがとう。君から褒めてもらえると一番嬉しいよ。所詮組織人だけど、組織にいる為に出来る事があるよね。
大きなお金が動くけど、それ以上の回収が見込めるからね」
終業ベルが鳴ったと同時に、部下が近づいてきて「すすき屋に予約いれておきましたから、お仕事が終わられましたら来てください」
「ああ、ありがとう。一緒に行けばいいんだが、最後の仕上げをしてからそっちに行かせてもらうわ」
「申し訳ないですが、我々先に行ってもう始めちゃっていいですか?」
「もちろん、片苦しい事は抜きで大いに楽しもう」
チラッと、課長の方を伺ってみると、別のチームと難しい顔をして話をしておられた為、また今夜の事も事前に了承を得ているので、君のチームだけで行いなさいと言われていた。
一通り仕事をした後、課長へ「それでは、お先に失礼いたします。明日も仕事ですので、羽目を外さない程度にいたします」
「ああ、今日はよく頑張ってくれた。私も行きたい所だか他の案件もあるので失礼する事を皆に伝えて欲しい」
「かしこまりました。では、お先に失礼いたします」同じ言葉を繰り返してしまった。
店に着くと、2階の座敷に通された。宴会はもう始まっていて、結構出来上がっている者もいた。
「課長補佐、こっちに席を用意しています。今日は最高にウマイ酒が飲めますね」
「みなさん!課長補佐が今来られました、改めて乾杯いたしましょう」
どの組織にもこういう宴会屋がいるものである。
仕事は、ソコソコできるのであるが、皆で騒ぐのが大好きな者。
「では、今日の我がチームの企画採用前祝いで、乾杯~~」
「乾杯!」あちこちでグラスを合わせる音がした。
そこに部下である、名前は田川洋子、年齢は30歳にならないくらいの美形社員が近づいてきた。
「今日の課長補佐のプレゼン最高でした。簡潔に分かりやすく、私たちが纏めた資料を見事に印象つけて頂きました。役員も皆様頷いておられたのを見て、私涙が出そうになりました」
「ボクの力じゃないよ。皆が協力して最高の企画を出してくれたので、それをそのまま会議にかけただけだよ」
「そんな事ないです。どんなすごい企画でもプレゼン一つで印象が全然違います。企画した私たちですら感動したくらいですから」
「そう言っていただけると、男冥利に尽きるね」
更に近づいてきて、ボクの耳元でささやくように
「課長補佐は、素晴らしい男性です。今までもお慕いしていましたが、今日の課長補佐姿を見て私の体に電流が流れ、我慢していたものが堰を切ったように溢れ出してきました」
「????どう受け取ったらいいのかな?」
「いじわるですね。女の私から言わせたいのですか?」
「いや~、分からないものはわからないよ」
薄々感じる事であるが、ここは迂闊に受け入れちゃダメだと自制が働いた。
「今日の課長補佐を見て、今まで我慢していたことを告白しますよ。今日課長補佐のような素敵な男性に抱かれたいと思っています」
「エエッ!」
思わず、周りを見渡した。
皆、お互いの話に夢中になり、こちらの事に気付いている者がいない事を確認し、内心ホッとした。
「この会が終わりましたら、少しお付き合い頂けますか?」
ドギマギしながら
「別の店で別にお祝いするって事ならいいよ」
「また、本当に意地悪ですね。今日の仕事のお祝いはこの席で終わりです。二人きりになりたいのです」
「二人きりに?君さえよければ、ボクは一向に構わないが」なんて奴だ!また軽々しく女性の誘いに乗ろうとしている自分が情けない。
「宴たけなわですが、そろそろお時間となりましたので、ここで課長補佐の音頭で会を閉めたいと思います。課長補佐どうぞ」
「本日は、大成功と言っていいくらいの仕事だった。皆のお蔭だと感謝している。それでは僭越ながら、一丁締めをします。よ~っ、パン!」皆の拍手でお開きとなった。
「課長補佐、お帰りですか?我々は二次会に行こうと思っているのですが、ご一緒にいかがでしょうか?」
「申し訳ない、明日もあることなので今日はこれで帰るよ。少ないけどこれカンパ」一万円札を渡した。
「ありがとうございます。では、お気をつけてお帰りください。ここで失礼いたします」
「ああ、お疲れ様。明日からも頑張ろう」
「はい」
部下達と別れ、田川が言っていた駅前の公園へと足を向けた。
「お待たせ」
「すみません。我儘言って」
「いいよ。今日は仕事うまくいったので、気持ちよく飲めたね。少し酔いさましに歩こうか?」
「ええ」ボクの後から付いてきていたが、公園の奥に入っていくと、いきなり腕を絡めてきた。胸の膨らみが、腕に当たっている。
「ずっと憧れていた人とこうしてデートできるなんて、夢のようです」
「また~。田川さんならいくらでも彼氏は出来るだろうし、今もいているのでは?」
「本当に課長補佐は意地悪ですね。彼氏なんていません。私はずっと課長補佐が好きでした」
「ありがとう」
「そこのベンチに座りませんか?」
当たりを見渡しても、人がいる気配はない。
「そうしよう」
外国であれば、ハンカチをひいて女性をエスコートするのであろうが、日本人のボクにはそういう洒落た事が出来ない性質である。
さっさと自分が先に座り、彼女に座るように促しただけであった。
「今日はお疲れ様。さっきのお店ですっかり酔ってしまった。君はあまり飲んでなかったようだね」
「洋子と呼んでください」
「よ、ようこ?って、いきなりは難しいな」
と、言い終わったとたん、いきなり彼女からボクに覆い被さってきて、キスをしてきた。
それもすぐに舌を入れてきて、ボクの舌に絡ませてくる。甘酸っぱい口臭がボクの口いっぱいになった。
しばらく貪るように、ボクの舌を吸い鼻息がかなり荒くなってきている。ボクもキスに応えるうちに、自分の分身がムクムクと大きくなってきていた。
彼女は、ボクの手を取り、自分のブラウスの下から自分の乳房へと導いた。いつの間に?いや最初からだったようだが、胸に下着は着けていなかった。
手を宛がうと、ボクの手より遥かに大きな乳房を感じる事ができた。
「ああ~っ」
優しく彼女の豊満な乳房を揉みながたもう片方の腕を腰に回していた。
口は繋がったままである。
外での行為なので、これ以上はダメだと自制心が働くが、彼女の手がボクのズボンのチャックを探し当てると一気に引き下ろした。
「えっ?」心の中で叫んでしまった。
解放された分身が自由を得た魚のように、飛び出していた。
「うれしいわ。こんなに感じてくれている」と彼女は分身を引きずり出し、亀頭のヌメリを広げるように全体を捏ね回してきた。
「もう、これくらいにしよ。外だし、誰かが来るかもしれないから」
「会社では堂々とされているのに、意外に気にするんですね」
そのまま、彼女は前屈をする格好で、ボクの分身を咥えてしまった。
ズルズルと卑猥な音を立てながら、頭を上下に激しく振っている。我慢できなくなってきた。
「ああ」女性のような声を立ててしまった。
彼女の動きは更に激しくなり、手も添えてしごき上げてくる。
「うっ!」急激な刺激で一気に頂点まで達してしまった。
ボクが出してしまった物を、彼女はゴクリと飲んでくれた。
「どう?よかった?」
「うん。すごく気持ちよかった」
「嬉しい、喜んでもらって」
「呑み込んで、気持ち悪くなかった?」
「全然そんな事ないわ。大好きな人の物だもの、美味しかったわ」
最後の一滴まで、ストローで吸うように飲んでくれたお蔭で、分身は唾液だけとなっていたので、自分でズボンの中に仕舞い込んだ。
「また、会ってくれますか?今度はちゃんと私の中に入って欲しいから」
「うん。約束するよ」また、いい加減な返答をしてしまった事を後悔している自分がいる。
「かなり遅い時間になっちゃったね」
「お家まで送ろうか?」
「いえ、大丈夫です。駅はそこですし、電車の方が早いですから」
「分かった。じゃ、気をつけてね」
「今日は急に我儘を言って申し訳ございませんでした。是非次に会える日待っています」
「ボクこそ、楽しみにしているよ。ありがとう」
彼女とはそこで別れた。
「何で急にモテだしたのだろう?今まで、誰も見向きもしなかった。それは自分が妻帯者であるからと思っていたのにな~」と独り言を言って、ボクも足早に駅に向かった。
四
数週間仕事に追われていたと言うのもあって、何度か経理部の高橋さんからメールをもらっていたが、忙しい事を理由に会う事を断っていた。
部下の田川さんの目もあったからかも知れない。
ついに最終通告のようなメールが来た。
「会って頂けないなら、私自分の命を絶ってしまうかも知れません」
「ええ!そんな事言いだすなよ」と内心かなり動揺しながら、返信した。
「申し訳ない。本当に仕事が深夜までかかり、会いたくないのではなくて、会えない状態なんだ。
しかし、後2,3日もすれば時間取れそうなので、こちらから連絡しますので、要らぬ考えを起こさないで下さい」
「分かりました。ご連絡をお待ちしております」
もうこうなったら、開き直るしかない。と、自分に言い聞かせその日から3日後の金曜日に会う事にした。
前に行った居酒屋で会う事を、18時半で約束をした。
約束の時間より、10分早く店に入った。
少しでも、誠意をみせようと考えたからである。
定刻となり、程なくすると彼女が店に入ってきた。事前に店の人に伝えていたため、
「お連れ様が来られました」と、私の席の向かい側へ案内された。
「お久ぶりです。また我儘言って申し訳ございません。今、会えてホッとしています。このまま捨てられちゃうんじゃないか?と何度も泣いてしまいました」
「申し訳ない。捨てるなんてとんでもないよ。本当に仕事に追われ、ボクも会いたかったけど出来なかった。ごめん」
「いいえ、もういいですよ。こうして実際に会えたので、すごく嬉しいのですから」
「まず、何を飲む?」店員が待っていた。
「私も、同じビールで」
「では、同じビールもう一つお願いします。
それと、すぐにできるもの、冷奴と串カツの盛り合わせをお願いします」
「承知しました」店員は厨房へと消えた。
「本当に久しぶりだね。元気にしていた?」
場違いな質問をしている事にも気づいていない。
「元気だったわけないでしょ。ずっとあなたの事を考えて夜も寝られませんでした」
「そうだったね。申し訳ない」
「今日は、ゆっくりできますよね。ひと時でいいから私の人になってください」
「もちろん。ゆっくりできるし、高橋さんのお相手させてもらうよ」
ビールと食べ物が運ばれて来た。
「まず、再会に乾杯しよう」
「ええ」
「乾杯!」グラスを合わせた。彼女は必ず自分のグラスを下に下げて、合わせてくる。
心遣いのできる子だ。
「仕事相変わらずお忙しいですか?」
「一時は本当に忙しくて、深夜に帰っていたけど、今は少し楽になったよ。サラリーマンは辛いよ、かな?」
「無理されないでくださいね。今日は私がお疲れの体を癒させて頂きますから」
「癒してくれるの?うれしいな」
暫く会話を楽しみ、お酒も少々飲み酔いが回ってきた。
「場所変える?」
「ええ、できれば二人きりになりたい」
「わかった。すみません、お勘定お願いします」支払を済ませ、店の外に出ると心地よい風が頬を撫でてくれて気持ち良かった。
タクシーを止め、二人で乗り込んだ。
「どちらまで?」運転手に聞かれ、目的地をほぼ決めていたが、そこでいいのか?彼女に確認していなかった事に気付いた。
もう、遅いので「○○町までお願いします」
彼女は知っているのか?そこはホテル街である。
チラッと彼女の方を見ると、酔っているのかシートに体を埋めて薄く目を閉じていた。
しばらく走ると、目的地に着いた。
「ありがとう」と料金を払い、タクシーから降りた。
周りは、簡素な住宅街の用に見えるが、そこの角を曲がればホテル街である。
歩きだすと、彼女の足元がふら付いて倒れそうになったので、慌てて彼女の体を支えるように受け止めた。
「すみません。ちょっと飲みすぎたようです」
「大丈夫、ちょうどこの近くで横になれる所があるので、そこでしばらく休む?」
「そうなのですか、はい少し横になりたいです」
「わかった。ここでお姫様抱っこはできないから、ボクの肩に手を回して」
「こうですか?」
「そうそう。歩ける?」
「大丈夫です」
けが人を介抱しているように、彼女を抱えてホテル街へと行き、派手〃しい店を避け、ひっそりとした店に入って行った。
入ると、パネルで部屋の様子が分かるようになっており、好みの部屋番号を押すと鍵が下の受け口から出てきた。
鍵を取り、エレベータに乗った。彼女を抱えたままである。
5Fの503号室のドアに鍵を差し込み、回すとロックが解除した音がした。
ドアを開け中に入ると、壁はピンクで赤色のライトで部屋が照らされ、中央に大き目のベッドがあった。何故かベッドの上には大きな鏡が付けられている。
「大丈夫?もうすぐ横になれるからね」
「すみません」
ベッドの掛け布団を取り去り、彼女をベッドへ寝かせた。
「水でも飲む?」
「ええ、頂きます。出来ればあなたの口から欲しい」
「分かった」
冷蔵庫から、ミネラルウォータを取りだしたコップに注いで一口含み、彼女の口に近づいていった。吐息が微かにお酒の匂いに混じり白粉粉の香がした。
ゆっくりと、口移しで水を彼女の口へ流し込んでいった。
「ゴクッ」と彼女は喉を鳴らして呑み込んだ。
「美味しい。かなり気分も落ち着いてきました。ありがとうございます」
「こんな場所で、申し訳なかったね。ちゃんとしたホテルがあれば良かったんだが」
「いいえ、私もこういう所は初めてですが、興味はありましたので、ラブホテルってこんな風になっているのですね」
「ボクも初めてだよ。内装がケバいね。時間は大丈夫かな?」
「ええ、まだ大丈夫です」
「そう、じゃせっかくなので、汗も掻いたしシャワーでも浴びてくるわ。ゆっくり休んでいて」
「はい」
脱衣場で全て脱ぎ去り、浴槽に入ってまた驚いた。エアーマットのようなものが洗い場に敷かれている。
「返って邪魔だな」と独り言のように愚痴りシャワーを浴びていると、驚いた事に彼女が頭をタオルで巻いた状態で入って来た。もちろん全裸である。
「お背中流しましょうか?」
「ああ、頼むわ」
スポンジを泡立てて、背中を洗ってくれている。その手が後ろから前に周ってきて、ボクの胸も洗い出した。次第に下腹部に降りてきて、すっかり元気になっている物を泡まみれにしていく。スポンジを落とし、素手で一物を握りしめ、先端を手のひらで円を描くように撫でまわしてきた。快感が背筋を走った。
次に、ボクの前に周り込んできた。
自然に彼女の肩を抱き、口づけをした。舌を入れきれいに揃っている前歯を舐めているうち、彼女も舌を出してボクの舌を迎えるように絡めてきた。
吐息が熱く感じられる。さらに彼女の乳房を優しく揉み乳首を指で挟んで持ち上げるようにし、先端を指で捏ねるようにしていると
口を離し、仰け反るように頭を後ろに倒し、
「ああ~~、気持ちいい。もっと強く」
首筋から鎖骨付近まで舌で舐め下していく。
石鹸の匂いが強い。彼女の手は、ボクの一物を握り、上下に激しく刺激してくる。
「マットがあるね。ここで遊んでみようか?」
「………」
黙って彼女は、マットの上に仰向けに寝転んだ。
上から覆いかぶさり、髪の毛が濡れないよう気をつけながら、再び淡いピンクの乳首に吸い付く、シャワーで流したのでもう石鹸の匂いはしない。
身を捩りながら、彼女は喘いでいる。
胸から徐々に下に舐め降りていく。
鳩尾から縦長のおへそを辿り、こんもり茂っている草むらは、ヌラヌラとしたもので濡れ光っている。
そこをあえて触らずに、内腿、脹脛、足の指を親指から順番に嘗め回すと、
「まだ、洗ってないから汚いわ」
「大好きな人の体で、汚いところなどないよ」
指の間からは、微かに汗の香が残っていた。
甘噛みしながら、指をしゃぶっているだけで
「うっ!ああ~~」すごく感じているようだ。
局部が丸見えだ。縦に筋を描くようにきれいに合わさった、女性器からは白い液体が溢れていた。
今度は逆に下から上に舐め上げていく。
指で熱く息づいているおまんじゅうのようにぷっくりした割れ目を広げると、そこには鮮やかなピンク色をした襞が伺えた。鼻を近づけると酸味かかった香がする。ヌラヌラと光る液体を啜るように舐め上げ、尿道口を通りその先に可愛く尖ったクリトリスが皮から飛び出している。そこも啜るように舐め回す。
「いや~~、あ~~」と喘ぎながら、体をビクンビクンと跳ね上げる。一通り舐め続けていると、
「もう、もうダメ。早く欲しい。ここに入れて」
「わかった。いくよ」
彼女は眼を瞑った。
先を割れ目に合わせ、そろそろと挿入していく。十分潤っているので、スムーズに奥まで入った。
「ああ~~、いい~~」彼女の方から腰を突き上げてくる。
それに合わすように、初めはゆっくり、次第に早く送出を繰り返した。
「奥まで届いている~~~」
彼女の乳房を鷲掴みし、激しく一気に登り詰めてしまい、樹液を放出した。
「熱いのが、奥にいっぱい感じる!イク~」
ガクガクと彼女の体も大きく痙攣し、後グッタリした。しかし名残惜しげに彼女の中はヒクヒクと痙攣しているので、快感が永遠に続いているように感じられる。
お互いに体の洗い合いを行い、そのままベッドへと移動した。
彼女を腕枕で抱いた形で、
「すごくよかったわ」
「ボクも、すごく良かった」空いている手で彼女の乳首を弄ぶ。
「ああん!私、そこ一番弱いの」
確かに言う通り、すっかり乳首は立っていた。
「またしたくなっちゃうわ」
「ボクも、もうほら!こんなに元気になっているよ」
「本当、すごい」
言っている彼女の口を塞ぐように、口づけをした。いきなり舌を入れていく。
彼女も応えるように、舌を絡めてくる。
そして、ボクの一物をしっかり握り、擦り始めた。
「ほしくなってきた?」
「ええ、欲しいわ。これが、私の中に」
「じゃ、今度は君が上になってしてくれる?」
無言のまま彼女は、上体を起こし、一物を握り自分の膣口にあてがい、そのままズブズブと腰を沈めてきた。
「ああ~~」仰け反る彼女ののど元が白い。
両手をついて、腰を上下に振ってきた。その動きに合わすように、ボクも腰を振る。恥骨同士があたり、少々痛いが快感の方が大きい。
ふと上を見ると、二人のそのままの姿が、天井の鏡に映しだされていた。
その光景を見ているだけで、すごく興奮してしまい、一気に絶頂まで駆け上がってしまった。
「出る!」ドクドクドクとさっき出したばかりなのに、まだ残っていたのか?と思うくらいの量が出た感じがした。
「熱い、熱いわ。私もいく~」
ガクガクと彼女も体を震わせオルガスムスを迎えたようだった。
そのまま倒れ込むように、ボクの体に体重を乗せて、喘いでいる。
「なんて、可愛いんだ」と、心の中でつぶやいていた。
つながったまま口づけをし、ボクの顔全体を舐めまわしてくる。
「ああ~」思わず声が出てしまった。
隠微な香りが顔中に広がっている。
「好き。大好き」
「ボクも、だよ」と答えながら、彼女の体を強く抱きしめた。
また、天井を見ると、彼女の背中・お尻が写っていた。細い体の割に、お尻が大きく見えた。
ベッドのシーツの上は、愛液なのか、ボクの出した物なのか?ベットリ濡れていた。
五
久しぶりの日曜日で、何もすることがない。
散歩でもしようかと、電車で一駅行くと河原に行ける場所があるので、休みに定期を使うのも久しぶりだな~と、
考えながら駅で普通電車が来るのを待っていた。
「あら、山川さんじゃない?」
初めは誰なのか思い出せず怪訝な顔をしていると、
「忘れたの?私!山本恵子。ほら、高校三年生の時、同級生だった……」
やっと思い出した、年を取ったからであろうか?
「ああ!あまりに美しくなられたので、気がつかなかったわ」
「へぇ~、昔はむっつり助平のうようだったのに、社会に出ると口もお上手になるのね」
「本心からそう思って言っているんだよ」
「まぁいいわ。褒めて頂いてありがとう。ところで、どこかにお出かけ?」
「久しぶりに一人になったんで、隣町まで行って散歩でもしようかな?と考えていたところ」
「ひとりとは寂しいわね。ねぇ、ここで会ったのも何かの縁なので、うちに遊びに来ない?」
「えっ?結婚して、旦那さんも子供さんもいる、じゃなかったっけ?」
「ええ、もちろん既婚で、子供もいるわ。今日はたまたま、旦那の実家へ呼ばれて旦那と子供はそっちに行っているわ。私は、仕事があったので、行けなかったの。で、今仕事帰りなの」
「会社、この近く?」
「いいえ、市内よ。買い物したくてこの駅で降りたの」
「そうだったんだ。じゃ、本当に寄寓だね」
「私も、違うかな??と思いつつ、近づいて確信したんで、声をかけたの」
「しかし、懐かしいよね。卒業してもう20年以上経つよね。ボクはすっかり、おっちゃんになったけど」
「そうかな?」少しボクから離れしげしげと見つめてくる。
「行けていると思うけど。モテモテじゃない?」
「そんな事ないよ。毎日会社と家の往復だけ。山本さんこそ、当時はマドンナ的な存在で、モテていたよね。確か~~、商社のバリバリサラリーマンと結婚したって、友達に聞いた事ある」
「うん。そうだけど、海外出張ばかり。結婚したのに、ほとんど一緒にいる時間は少ないわ。そうそう、上原君にも憧れてら女子結構いたの、知っていた?」
「えっ?全然気が付かなかった。モテないと思い込んでいたわ」
「女子はね、自分から言わないの・サインを出して、気づいてくれるのを待っているのよ。
それすら、気づかないようじゃダメだな」
「そうだったんだ、惜しい事したな」
「まぁ、そんな話もうちに来てゆっくりお話ししましょう」
「いいのか?」
「誘っているから、いいに決まっているじゃない。何言っているの?相変わらずね」
「お家はどこ?」
「次の駅を降りて、快速に乗り換えて一駅で○○駅」
「すごい!高級住宅街じゃないか」
「まぁ、世間ではそう呼ばれているのかな?」
決して嫌味ではなく、さらっと言われたので、気分よくついていく事にした。
着いた家は、想像以上に立派な建物であった。駅からタクシーで10分くらい坂を上った所で、周りを見渡しても、自分ではとても住めそうもない、豪華な家が建ち並んでいた。
門があり、玄関まで大理石であろうか?表面を磨いてなくそのままの形できれいに敷き詰められていた。通路の両脇には常緑樹が植えられ外から中は見えないようになっていた。
門に、監視カメラがあったのもしっかり確認していた。
玄関のドアを開け、家の中を覗くと更に驚いた。広い玄関に靴を何処に入れるのだろう?普通の下駄箱がない。スリッパが並べられている室内の床も大理石なのか?キラキラ高貴な輝きを見せていた。
いやに明るいと思って、上を見ると二階までの吹き抜けとなっており、天窓から採光されているのが分かった。
「すっ、スゴイ家だね」
「初め来たとき、掃除どうするんだろ?と悩んだわ。しかし、お手伝いさんが週に4日来てくれて、掃除、洗濯してくれているから助かるわ」
「同じ高校出ても、歩む人生全然違うんだね」
「短い人生、何がいつ起こるかわからないわよ。明日、突然に私がホームレスになっているかも?知れないわ」
「それは、極論だな」
「さぁ、もっと中に入って。今、お茶淹れるから」
「ありがとう」と、言ってもどこに座ればいいのか?迷うような応接セットであった。
「お待たせ~。何突っ立っているの?好きな場所に座って。気を遣う事ないでしょ」
「ありがとう」と言って、座ったが体が沈み込むようなソファーだった。
「うまく行っているの、夫婦中?」
「一応はね」
「私は、さっきも言ったように旦那がほとんど家にいなくて、ずっと寂しい思いしているの。慰めてくれる?」
「慰めるって?」
「相変わらず、知って惚けているのか?本当に女心が理解できない大馬鹿者か?どっちかね」
「………」
「ねぇ、キスして」
ボクも立ち上がり、彼女の髪を撫でながら、すでに目をつむりやや上を向いている唇にボクの唇を合わせた。
「んんん~」もう感じているのか?
舌を差し入れていくと、待っていたかのように彼女の舌が絡みついてきた。
手を後ろにまわし、ワンピースのファスナーを下していった。最後までは、手が届かず下せなかった。
肩から肌を手で舐めるようにワンピースを外していく。
彼女も、ボクのいきり立った一物の形を確認するように、ズボンの上から撫でさすってきた。
「クッ!」思わず声が出そうになるくらい巧みな指の動きだ。
キスを外し、中腰になってワンピースのファスナーを一気に下まで下すと、「ストン」と、ワンピースは床に落ちていった。
下着だけの姿となった彼女を見ると、見るからに高級な下着で、なんと下はガーターベルトであった、真紅の。
「ああ~、そんなに見ないで恥ずかしいから」
また、彼女を抱きしめ、ブラジヤーのフロントホックを外すと、たわわに実った大き目の果実のように、プルンと飛び出した。
中腰になり、両方の乳房を揉みながら、交互に乳首を舌でねっとり、舐めていくと、
「ダメ、立っていられない。ベッドに行きましょう」
「分かった」と言い、彼女を抱き上げた。
「キャ!」小さな悲鳴を上げたが、顔は微笑んでいた。
ベッドに移り、髪を撫でながら優しく耳を噛む、
「ああ~~、いい!感じるわ」
首筋から徐々に下に向かって、舌を這わせていく。彼女は声を出さないよう堪えて、眉をハの字にし、息だけで喘いでいる。
脇の下に鼻を近づけると、僅かな絨毛があり汗の匂いがした。そこも丹念に舐め、脇腹を通り、きれいな縦長のおへそを通過させると、そこには意外に多めの絨毛が茂っていた。
敢えてそこは、触れずに内腿を舐め足の指にしゃぶりついた。
「そこはダメ、汚れているから」
「あなたの体で、汚いと感じる場所はないよ」
「くっ!」感じているようだ。
親指から小指まで丁寧に舐め、指の間を舐めるとそこも汗の独特な匂いがした。両方の指を全部舐め終わり、さっきとは逆に舐め上げていった。
目を局部にやると、女陰から白いねっとりした液体が、滲み出ていた。
女陰に近づくと、酸味かかった匂いがきつくなってきた。会陰から女陰の外だけを舐め、その上にある、やや大き目の蕾はすっかり皮から顔を出していた。
それに、吸い付くように口づけをし、転がすように舌を這わすと、
「いい~、イキそうになる」腰をくねらせながら、荒い息で喘ぎだした。
何度も下から上への往復で、我慢の限界がきたのか、
「ああ~~、このままイキたいけれど、欲しい。あなたの大きな物が欲しい。ここに入れて欲しい」
「わかった、お望み通りに」
ボクの一物を女陰に手であてがい、ゆっくりと沈めていく、
「ああ~~、ああ~~、うっ!」
奥まで届いた感触が伝わってきた。
ゆっくりと、ピストン運動を始めた。
「き、気持ちいい!すごく感じる。奥、奥まで届いているわ」
ピストン運動のピッチを上げていく。
苦痛に似た表情で、両手でボクの腕をつかんできた。
「あん、あん、あん」動きに合わせて、声を発してくる。
フルピッチで攻め上げると、
「イク~~、いっちゃう~」
「ボクもイクよ」
「だ、出して」
「うむ!」一気に背筋に快感が走り、樹液をドク、ドク、ドクッと放出した。
「熱い!熱いのが、私の奥に来ている。いく~~~」
激しく、ガクッ、ガクッ、ガクッと体を痙攣させ、ボクの体にしがみ付いてきた。
「はぁ、はぁ、はぁ」荒い息をさせながら、口づけを求めてきたので、応えると生くさいそれも嫌な臭いではなく、淫靡な香りであった。
くちづけをしながら、彼女の体をゆっくりと、ベッドに寝かせた。
「よかったわ。こんなに感じた事初めてかも?」
「ボクも良かったよ。こんな素敵な方と交わる事ができて」
「ねぇ、しばらくこのままでいていい?」
「もちろん」
ボクの一物はまだ彼女の中にあった。
彼女の中は、快感の余韻か、まだヒクヒクと蠢いている。
さすがに、もう一回は無理なのに、ボクの一物はムクムクと、意思とは反対に反応し始めていた。「大きくなってきている!」
「いや~、さすがにもう無理だ」
「私も、もう無理です」そっと、彼女の中から抜き、彼女を抱きしめた。華奢な体に似合わず、豊満な乳房が胸に当たってくる。
お互い汗だくになっているが、お尻に手をやって火照った体を抱きしめても、そこだけは異常に冷たかった。キスをした。いきなり舌を絡めてくる。
しばらく、余韻を楽しむように、お互いを貪りついた。
「こんなに良かったの、始めてだわ」
「ボクも、昔のマドンナとこうなるなんて、天にも昇る気持ちだったよ」
「今日は、もう少しゆっくりできる?」
「そうしたいところだが、散歩と言って家を出てきているので、そろそろ帰らないと……」
「優しい奥様が待っているのね、ちょっと嫉妬しちゃうわ」
「ごめん」
「ううん、我儘言っているのが、分かっているから、また会えるかしら?」
「もちろん、こちらからもお願いしたい所だよ」
お互いの、メールアドレスを交換した。
「じゃ、次に会えるのを楽しみにしているよ」
「私も」
六
月曜日が始まった。
また一週間、働き蜂のように働かないといけないのか~。ため息が出た。
そんな時電話が鳴った。
「高橋です。お仕事中すみません。あなたの部下の三浦さんの精算について、ご相談したい事がございまして、電話させて頂きました」
「三浦?あいつが、何かしたのか?」
「ええ、不明瞭な領収書の請求が出ております」
「それは、イカンな。手間をかけて申し訳ない。そちらに伺った方がいいかな?」
「いいえ、こちらからそちらに向かいます。出来ましたら、第一応接室を押さえておきましたので、今からでもよろしいでしょうか?」
「そうだな、ここではそういう話はできないな。心遣いありがとう。今からボクも応接室に向かうよ」
「では、後程」何をしでかしたのだ??確かあいつが出した清算書、ちゃんと内容も確認せずに上長印を押したのがマズかったかな?
第一応接室へノックし、ドアを開け中に入ると、すでに彼女は来てソファーに座っていた。
「三浦の件、経理で問題になっているの?」
「いいえ、まだ誰にも申しておりません」
「それは、ありがとう。ボクもちゃんと確認せずに、承認印押しちゃったからね。責任はボクにあるよ」
「そんな、たいした事ではないですから、ご安心を」
「どこが、疑わしいの?」彼女が手に持っている、請求願の伝票を覗きこんだ。
「この請求書に、印紙が抜けているんです」
「本当だ。さすがに経理課だね。ボク達営業は、なかなかそこまで気が付かないわ」
「まだまだですね。課長代行さん」
「5万円までは、非課税なのですよ」
「じゃ、この領収書には問題がないのでは?」
「はい。問題ございません」
「では、何故私を呼びつけたのかな?」
「分かっているくせに!」
「ああ、そういう事ね。二人きりになりたかった。って、事?」
「意地悪!」彼女は、黙って立って応接室の鍵をカチャと掛けた。
「ごめん。ごめん」と言いながら、彼女の唇にボクの唇を重ねた。
「うう……」綺麗に揃った前歯を舐めると、向こうから舌を出して、迎えてくれた。
舌と舌をお互い出し、絡め合う。自然とボクの手は、彼女の胸の膨らみを捉えていた。柔らかい!指が沈んでいくようで、また押し返す弾力性があった。
彼女をソファーに座らせた。
「あっ、ああ~~~」手を口にやり、声が出ないように、堪えている姿が愛らしい。社内なので、時間を気にしていた。
早急に、責めるのもいいかな?と考え、いきなりスカートを捲りあげ、ストッキングの隙間に手を入れパンティを通過し、秘所へ手を入れていった。
そこは、もう既にグチュグチュになっていた。
「いいわ~、激しいのもたまには…ウッ!」
指をすでに膣内に挿入していた。彼女はしがみ付くように、ボクの腕をつかんでくる。指を折り曲げ、奥の上で窪んでいる箇所を攻めた。
「いい、イク~~」なんと、とろんとした目で、喘いでいるので、少し涎が唇の端から垂れている。更に激しく、窪みを攻め、もっと奥にある少し硬めの子宮口を突く。
「ダメ~~、ああ~~、ほ、本当にいっちゃう」ガクガクっと、何度か体を痙攣させ、絶頂と迎えたようだ。
「魔術師のような指ね。指だけでイッちゃったのは初めて。悪い指!」と言いながら、自分の愛液塗れでベトベトになっているボクの指をしゃぶりだした。
「きれいにしておかないとね」と言いながら。
時間が気になるが、彼女が絶頂を迎えた姿を見て、ボクの一物は痛いくらい大きくなっていた。それを見て、
「今度は、私がしてあげる」と、言うなり、いきなりズボンのファスナーを引き下ろした。
次に、ベルトを緩め、ズボンのフォックも外し、下着の間からボクの一物を引き出した。
プルンと、解放を待っていたかのように、それは、テカテカと光り、先からは透明な液体が滲み出ていた。その液を愛おしむように、舌でペロリと舐め、先の部分だけを口に含んだ。
「ウッ!」思わず、声が出てしまった。
先を舌で円を描くように舐めまわし、しばらく同じ動きをした後、分身全部を呑み込むように含んできた。「うぐぐ……」そんなに奥まで入るのか?と思うくらい入っている。
これが「ディープ。スロート」なのか?自分の喉まで入れ、根本を指で固定させ、激しく頭を振っている。髪の毛がその度に、大きく揺れている。
「で、出る~」限界がすぐにきた。構わず彼女は、激しい動作を繰り返している。
「クッ!」「あ~」ドクドクと勢いよく樹液を彼女の喉の奥に放出した。
「ゴクリ」と、出したものを呑み込み、ゆっくりと、幹に沿って先に戻っていき、最後は先に吸い付き、最後の液を吸い取るように吸引し、スポンと一物から口を離した。
「あなたのは、すごくおいしいわ。少し苦いけど」
幸い誰も応接室に近づいてくる気配はなかった。
「ねぇ、またここでしましょう」
「ここで?落ち着かなくない?」
「少しでも、あなたと一緒にいたいの」
「分かった、会社の連中にバレないようにしないとね」
「ええ、その辺は女の私に任せておいて」
「お願いします」と場違いな返事をしてしまった。
「では、私はこれで失礼します。しばらく、窓を開けておいてください。証拠をのこしたくないので」
「ああ、分かった」窓を全開とした。
10分くらい、その場にいたであろうか?
七
応接室を後にし、自分の席に戻ると、部下の田川洋子が近づいてきて、「何処に行っていらしたのですか?行先も告げずに!」と言って、少し屈んで、ボクの太ももを抓ってきた。
「ごめん、ごめん。資料が要るのを急に思い出して、資料室に行っていたんだ」
「本当かしら??まぁ、いいわ後でたっぷり悪い子に、お仕置きをするから。フフフ」不敵な笑いと共に去って行った。背筋に寒気が走った。
午前中に経理の高橋と交わった為、一日気怠かった。しかし、仕事上では何も問題となるような事がなかったのが、ボクにとっては嬉しかった。
終業ベルが鳴った。今日も一日終わりかぁ~。部下達も、「お先に失礼します」と、次々に帰っていった。一人一人に「お疲れ様~」と声を掛け、
自分も帰る支度としていた時に、背後から近づいてくる気配を感じ、振り向くと、田川洋子が微笑みながら立っていた。
「まだ帰らないのか?」
「ええ、帰りませんよ。今日言ったように、課長補佐は悪い子ですので、お仕置きをするために、待っておりました」
「ほ、本気で言っていたのか?」
「もちろんですよ。女の勘は鋭いですからね。課長補佐が資料室?で、何をされて来たのかは、匂いでわかりましたので」
「に、匂いで?」(高橋と交わった後も、トイレに行って、局部をきれいに洗ったのに)
「微かに、いやらしい匂いがしていました」
「いやらしい匂いって?何もしてないよ」
「まだ、白を切るおつもりですか?」
「そんなつもりはないけど、ここは会社だよ。誰が会社でいやらしい匂いのする事をする?」
「私も驚きましたが、課長補佐のズボンのシミで確信しました」
「え?どこにシミがある?」
「今は、乾いて見えなくなっていますが、その時はそこ!が濡れていましたからね」
思わず、周りを見渡したが、誰も居ていなかった事に安堵した。
「あ~、お漏らししたかな?」
「また~、そんな事では誤魔化されません。白状しろ!とは申しておりません。あなただけと、誰かがいい思いしている事に嫉妬しちゃった」
「と、言うことは~」
「と、言うことは~」彼女は顔を近づけ、ボクの鼻を、人差し指でツンツンした。
「あははは、負けたよ。晩飯でも食べに行くか?」
「ええ、それだけでは済みませんけど」
「おお~、怖い」
会社を出て、タクシーを拾った。
中に入ると、いきなり彼女はボクの腕に、しがみ付いてきた。
「梅田に出て、考えようか?」
「ええ、お・ま・か・せ」
「運転手さん、梅田…新地近くで下してください」
「かしこまりました」
車内は、彼女のパヒュームで満たされていた。しがみ付いている腕に頻りに、豊満な乳房を押し付けてくる。そして、ボクの腕を取り、ブラウスのボタンを外し、中へと導いていく。
されるままにしていると、あるべき下着が無かった。ノーブラであった。いきなり柔らかな感触を味わったのにいささか驚いたが、その柔らかさを堪能した。「何て柔らかいんだ!」
耳元で「運転手さんが見ているから、優しくね」
「ああ、分かった。すごく触っていて気持ちいいよ」
「私も。でも、やっぱりお腹空いちゃった」
「はは、若いね。正直でいい」
まもなく目的地に着き、適当に安そうな焼肉屋に入った。
「課長補佐、私がお肉大好きなのを知っていて?」
「そういう訳じゃないけど、ボクも肉が食べたいと思ったから」
「精をつける為?」
「まぁ、それもあるかな?」
「じゃ、今日はいっぱい楽しませてね」
「ん?ああ」何て答えれば良いのか?思い浮かばなかった。
早々にコースを頼んだので、肉の盛り合わせが運ばれて来た。飲み物は、ボクがビールで彼女は、赤ワインだ。
「焼肉は任せてください」
「ああ、頼むよ」
ボクは、ビールを流し込み、焼きあがる肉が取り皿に盛られてのを食べるだけで良かった。彼女も、しっかり肉を食べている。
「気を遣ってくれていないので、こっちも気楽に食べる事を楽しめてるな」と、心の中でつぶやいていた。
一通り、出てきた野菜・肉もなくなりかけてきたので、「飲み物、お代わりする?」
「お腹一杯なので、もういらないわ」
「では、次行きましょうか?お嬢様」
「何を言っているんですか、課長補佐!洋子と呼んでください」
「じゃ、洋子、次に行こう!」
「はい」彼女の頬は微かにピンク色となって、満面の笑みで答えてくれた。
外はすっかり夜となり、結構な人が歩いていた。「ここでは、会社の人とも出会わなだろう」しかし、用心するに越した事はない。
彼女とは少し距離を置き、歩きだした。彼女も心得ているようで、数歩後ろから付いてくる。次に行く場所は、もうあそこしかない。
ホテル街に向かって行った。その周辺までくると、景色が一転する。人通りもかなり少なくなり、周りはアベックが数組腕を組んで歩いているだけだ。
後ろを振り返ると、彼女がいない!何処へ行った?ホテルに行くのが嫌だったのか?キョロキョロしていると、いきなり後ろから誰かに抱きつかれた。
「ビックリした?」
「ああ、驚いたよ。次でホテルに来たんで気を悪くして、帰ったのか?と思ってしまった」
「そんな事ないですよ。私も、早くあなたに抱いて欲しいですから。でも、今日のお仕置きの一つです」
「そういう事か、嫌われたと思ったわ」
彼女は、今度はギュッとボクの腕にしがみ付き、頭を肩に乗せてきた。
そこそこ、立派に見える建物へと、二人で入っていった。こういう場所は今まであまり来た事がないので、仕組みは以前入ったホテルとよく似ていたので、安心した。
パネルがあり、好みの部屋を選びボタンを押す。なるべく普通の部屋を選んだ。
先に進むと、エレベータがある、部屋番号のある階を押した。エレベータ内は鏡貼りであった。「私たちがいっぱいいるみたいですね」
「ああ、確かに面白い作りだね」
部下である田川は高橋と違い、エレベータ内での前戯は要らないらしい。
部屋の上部に付けられている、ランプが点滅している。この部屋ってすぐに分かるようになっているようだ。部屋に入ると、パネルの通り、普通のシティホテルの作りとなっていたので、安心した。
「シャワー浴びたいのですが」
「いいよ、お先にどうぞ」
「では、お先に失礼します」彼女は、バスルームに向かって行った。ボクはテレビを付け、ベッドの上に横になった。ふと、横を見るとバスルームが丸見えになっている。
彼女が、シャワーを浴びている姿がそのまま見る事が出来た。彼女がこちらを見て、ビクッとしたが、何の変化も見せない。マジックミラーとなっているのか?
それも、湯気で曇らない仕様になっているようだ。しなやかな裸体に、ボディソープを付け、丁寧に洗っている。髪の毛も濡れていいのか?そのままだ。
局部を覗きこむように、丁寧に洗っている姿を見て思わず笑ってしまった。「まだ、子供なのかな?」
彼女は何も気づかないまま、バスルームから出てきて「サッパリしました。課長補佐もどうぞ」
「ああ、ソファーにシャンパンがあったので出しておいたよ。それでも飲みながら待っていてくれる?」ベッドまで行き、バスルームが丸見えで、ボクが洗っている所を見られたくない為、反対側のソファーを示した。
「ごゆっくり、遠慮なく飲ませてもらいます」
ボクもシャワーを浴び、汗を流してきれいにして、早々に出た。
「早いですね。男の人は、お風呂に入るのが早いのでしょうか?」
「さぁ?他の人は知らないけれど、ボクは長湯に入るのは嫌いなんだ」
「シャンパン美味しくて、半分以上飲んでしまいました。ごめんなさい」
「いいんだよ。好きなだけ飲むといいよ」
しばらく二人で飲む事にした。すると、彼女は立ち上がり、バスローブの紐を外してそのまま、ストンとバスローブを床に落とした。
下は、何もつけていない。「キスして」「……」黙って、彼女の肩を抱き寄せ、口づけをした。
「うう……」と声を上げながら、舌を出してきたので、その舌を吸った。
更に、舌を絡めてお互いの唾液で、口の周りがベトベトになるまで、口づけを続けた。
「抱いて」彼女を抱きかかえて、ベッドまで移動し、優しく彼女をベッドの上に寝かせた。
横になっても、豊満な乳房は、やや変形しただけで、その原型を留めている。下に目をやると、少し多めの茂みがあった。目を瞑ったままである。
静かに彼女の横に寄り添い、髪の毛を撫でながら、耳たぶを舐め始めた。
「ああ~~、感じる!」
たっぷりと耳を攻めた後、首筋に舌を這わせ、鎖骨に沿って舌で触れるか触れない程度で愛撫していく。首を仰け反らせて「ああ~、ああ~」と喘ぎ続けている。
乳房を両手で揉みながら、乳首に吸い付きその先っぽを舌で転がしていく。
ゆっくりと、時間をかけて、決して力を入れないように優しく……。「もう、もうダメ。欲しい」
「まだ、ダメだよ。もっと気持ちよくなってから、ご褒美を上げるよ」
「じらさないで、もう我慢できない!」
無視をして、おへそから局部は通過して、内腿を舐め、足の裏・指を一本ずつ念入りに舐めていく。
「くすぐたいわ。でも変な感じ」
たっぷり足の指を舐めた後、両足を持ち、上に持ち上げた。V字型に広げられた奥には、膣口があり、白濁した液体がトロリと滴っていた。
それを舐め上げて、その奥に小さな蕾があった。
黒色を少しだけ混ぜたピンク色をしている。その蕾に舌を差し入れた。
微かに微香がする。「やめて!そこは汚れているわ」舌でクチュクチュとしていると、キュッと締めてくる。
「ああ~、なんだか変な感じ…」
それに応えるように、膣口からはさらに愛液が溢れ出してきた。
そっと舌を抜き去り、持ち上げていた脚を下におろして、股の間に顔を進めていき、キラキラ溢れた愛液で光っている絨毛をかき分け、指で局部を広げた。
鮮やかなピンク色をした襞がそこにあった。膣口を舐め、尿道口も舐め上げるとその先には、真珠のように輝く、クリトリスがあった。
しっかり立っているが、小さ目だ。半分皮を被っている。その皮を剥いたり、覆ったりすると、「本当に勘弁して、入れて欲しい!お願い」潤んだ目で、訴えてくる。
「わかったよ、いくよ」
「ああ、来てくれるの!早くぅ~」
自分の物を持ち、場所を確認して一気に刺しいれた。
「ああ、いい~~、感じるわ」
ふと、ベッドの上部に目をやると、「振動」と書かれたボタンがあった。弱・中・強を選べるようになっていた。
「なんだろ?」と心の中でつぶやき、弱のボタンを押してみた。
すると、ちょうど今結合した部分の下あたりのベッドが上下運動を開始しだした。
「おお!」思わず叫んでしまった。
彼女もビックリしたようだったが、意外にリズムよく動いてくれているので、ボクも動かないでも、ゆっくりピストン運動ができている。
「いや~、ああ~~、ああ~~」彼女は手を上に上げ、イヤイヤをするように、顔を振りながら大きな声で、喘ぎだした。
「これはすごい!ウッ!」ボクも上り詰めそうになったが、何とか堪えた。
ボタンを強に変えてみる。
「うぁ~~、おお~~」獣の声に変わり、一気に、ガクガクと痙攣しだした。
「と、止めて!あ~~、感じすぎる!」
まだ、痙攣は止まらない。ボクも刺激が強すぎて一気に上り詰めてしまった。
「出る!出るよ!」ドクンドクンと樹液を放出してしまった。ベッドの上下運動は続いている。
「と、止めて!!お願い」慌てて、ボタンを切った。
「はぁ~、本当に、あの世まで逝ってしまうんじゃないか?と言うくらい、感じすぎたわ」
「確かに、若い頃ならまだしも、この年齢になると、あんな激しい動作はできないわ」
まだ彼女の中に、ボクの物は入ったままだ。
激しすぎる刺激で、彼女の中はまだ収縮を繰り返している。
その刺激に、また反応してしまっていた。
「マヒしちゃっているけど、分かるわ。大きくなっている」
「余りに、洋子が可愛いからだな」
「本当?嬉しいわ」
「でも、もうダメ。これ以上したら、歩けなくなっちゃう」
「凄かったものね」
「そうだ、お仕置きを忘れていたわ」
「お仕置きを、本当にするのか?」何をするんだろ?と、正直期待感があった。「俺ってMなのかな?」と心の内で囁く。
「当たり前でしょ、会社の事もあり、また今のように、私を快楽死寸前まで行かせたのだから」
「……」
「さあ、そのまま仰向けに寝てください」
「こうか?」
「ええ、悲鳴を上げても止めないから、覚悟していてね」心臓が高鳴っているのを感じる。
まず、ボクの乳首に吸い付いて、舐めまわしてきた。男なので、そんなに感じはしない。
次に、歯を立てて噛んできた。流石にこういうのが、慣れているのか?快感が走った。
しばらく同じ動作を繰り返した後、「今度は俯せに寝てください」なんだか、マッサージを受けている気持ちとなっている。
肩でも揉んでくれるのか?と思った瞬間、お尻を広げそこにある穴に舌を滑り込ませてきた。
「うっ!」さすがに、そんな所までと思って無防備でいたので、かなり驚いたのと、そこを刺激されると、ムクムクと一物が大きくなってきた。
かなり奥まで、舌を挿入されたと思う。確かに気持ちよかった。
舌で攻めながら、手は睾丸を柔らかく揉んでいる。シーツは先ほどの行為で、ビッショリ濡れていたので、ボクの一物の先から滴る液は、バレズにシーツに吸い込まれていた。
「どうですか?気持ちいいですか?これからですよ」
「すごい技を持っているね」
彼女は、黙ったままボクを仰向けにヒックリ返し、睾丸を口に含み、片方ずつ口の中で転がしている。
更に、お尻の穴に指を入れながら、竿をすっぽり含んで来た。いきなり急ピッチで竿を出しいれし出した。
髪の毛が、すごく揺れている。
喉や口のあちこちに竿の向きを変え、しゃぶっている。そろそろこっちも限界に近づいてきた。
「出そうだ!」と言う声を聞くと、何と彼女は、ボクの一物の根本を指できつく縛ってきた。
出そうなのに、出せない!
刺激はどんどん強くなり、縛りを緩めたかと思うと、またキツク締め付けてくる。
「これは、拷問だ!」
「なぁ、頼むから、出せてくれ!」
「私に隠れて、悪い事すると、お仕置きよ。わかったわ。今日はこれくらいに、しておいてあげる」と、言うと、指の縛りが解放された。その途端に、樹液は迸り出た。
「よかった?」
「いいわけないだろ!出したいのに出せないのはキツイ」本心は、出た瞬間の快感は今までと比べ物にならなかった。すごい女性だなと、変に関心した。
結婚してから、今までモテた事がなかったのに、最近は立て続けに女性が寄ってくるな~。何故だろう?と、自席で書類に目を通しながら、余計な事を考えていた。
八
いろいろ考えていると、確か家族旅行で立山に行った時に、お土産屋さんでその店の横にみすぼらしい御婆さんから呼ばれて、
「この石をお主に渡そうと思っている」と言われ、見るからに、黒々と輝いていて形は、女性のそれをイメージする形をしていた。
大きさは、碁石に使う石を一回り大きくしたくらいである。
「頂けるのですか?」
「ワシが見込んだ男なので、渡したいのだがワシも飯を食っていかねばならないので、少々の出費をお願いする」
「いくらでしょうか?」
「値段が付けられないくらい、貴重な物だがお主に、こやつが付いて行こうとしておる。一万円でどうじゃ?」
少し高いが、念力を信じていたボクにとっては、魅力的な物であった。
「分かりました。では、一万円で譲ってください」
「おお、すまないのぉ。これは、ワシの亭主が持っておったもので、どんな力を秘めておりのか?女のワシには分からん。
そこで、この石が持ち主を探しているようだったので、半年前からこの店の亭主に頼んで、軒先を借りて、その者が現れるのをずっと待っておった」
一万円を払い、現物を手に持っても特に何もなかった。
「あなた、何しているの?先に行くわよ」と、嫁さんに促されて、後を追いかけて、振り返ると、御婆さんが居た場所は、何もなかったかのように、跡形も無く消えていた。
あの時の、ポケットの中から石を取り出すと更に黒味を増しているように見えた。
「この石のお蔭か?まさか、いくら念力を信じるボクでも、この石にそんな力があるとは思ってもいなかった。ん、な訳ないよな。と独り言を言い、ポケットに石を戻した。
石の存在も忘れるくらい、仕事が次々と舞い込んできて、気が付けば終業時間はとっくに過ぎていた。
そう言えば、部下達が挨拶しながら帰って行ったようで、生返事をした記憶があるが、片づけなければいけない仕事に没頭していた為、周りを見渡しても、誰もいなかった。
ポツンと一人残されていた。
時計に目をやると、7時を少し過ぎていた。
「今日は久しぶりに、どこにも寄らずに家に帰るとするか」と自分に言い、帰路に着いた。
「あら、今日は早いのね。いつも残業お疲れ様」嫁さんは、ボクが外でしている事に気付いていないようで、内心ほっとしていた。
「明弘はもう寝たのか?」
「ええ、学校で遊びすぎたみたい。あなたも毎日帰ってくるのが、遅いし今日は特別早く寝たわ」
「そうか、元気が一番だな」
「お風呂入る?それとも、お食事?」
「シャワーを浴びてから、飯を食うわ」
「分かったわ」久しぶりに早く帰ったのが嬉しいのか、嫁さんはどこかウキウキしていた。
バスルームに向かい、石の事を思い出し、一緒に風呂に入った。
湯船に浸かりながら、石を丁寧に洗っていると、女性器に似た石の間から、白い液体が溢れてきた。
「なんだ!どうなっているんだ?」まじまじと石を見るが、特に変化はなく、ただ後から後から甘酸っぱい匂いのする液体が溢れているだけである。
と、その時バスルームの扉が空き、嫁さんが全裸で入ってきた。
「どうしたんだ?先に済ませたのではないのか?」
「ええ、お先にお風呂は頂きました。でも、変な感じなの。あそこが疼くの」
「疼くって??」もう、一年以上も交わっていない。
「一緒に入っていい?」
「どうぞ」
「何持っているの?」
「いや、普通の石だよ。握っていると、ツボを押して肩こりに効くと書いてあったので買ったわ」
「そう、でも久しぶりね。こうして一緒にお風呂に入るなんて」
「ああ、そうだな。仕事、仕事で、家の事は任せっぱなしで、申し訳ない」
「いいのよ、いつも遅くまでお仕事ご苦労さまです」背筋に寒気が走るような、嫁さんの言葉だ。普段はほとんど会話らしい、会話をしたことがなかった。
「どうしたんだ?」心の中でつぶやく。嫁さんがすり寄ってくる。
ここは、応えてあげないとダメだろう。息子も寝ていると言うし。
肩を抱き、キスをする。
久しぶりであったが、慣れ親しんだ感触だ。
軽く舌を絡めで、小さ目の乳房を揉むと、喘ぎ始めた。「ああ~~、あなた、久しぶりよね」
「仕事ばかりだったからね」乳房を揉みながら片方ずつ乳首に吸い付く。すっかり乳首は立っている。指で秘所を弄っていると、「ベッドへ行きましょう」
「ああ、そうしよう」二人で、軽く拭いて、ガウンを羽織った。そのまま、寝室へ行く。
寝室は、ツインベッドであるので、ボクのベッドへと誘った。
その通りに嫁さんは、ベッドにもぐりこんできた。結婚当初は、毎日のように交わっていたが、子供が生まれ、
子育てに忙しくなるにつれ、誘っても断られる事が多くなり、そのうちになくなっていた。
普段と変わらない手順で、嫁さんと交わる。失礼だが、胸躍る興奮はない。
一頻り、秘所を舐めた後、挿入しピストン運動を繰り返した。
それだけで、嫁さんは絶頂を迎えていた。
「ああ~、イク~~」ガクガクと体を震わせ、それに合わせたように、樹液を中に放出する。
「久しぶりに、あなたの熱いものが私の中に入っていくわ」
「よかったよ」腕枕をして、髪の毛を撫でる。
「しばらくこのままでもいい?ご飯まだだけど」
「うん。いいよ。君がそうしたいなら」
「ありがとう」と言って、ボクの胸に顔を埋めてきた。10~15分くらいそのままでいたであろうか?
「お腹空いているよね。ご飯出来ていて、温めるだけだから、少し待っていてね」
「ありがとう、ここで待っているわ」
「は~い」イヤに機嫌がいい。
そのまま、夕食を採り、眠りに就いていた。
九
やはりこの石の効果なのだろうか?それ以外、ボクが他の女性からモテる理由が見当たらない。
これを持っている限りは、色んな女性と交わる事ができる。
しばらくは持っておこうか?誰かに渡すか、捨てるか、悩んでいた。
昼休みになり、一人になりたくて、空いていそうなレストランに入った。
「いらっしゃいませ~」ウエイトレスを見て、思わず二度見てしまった。可愛い!スタイルもいい。このような子とも?など、余計な事を考えながら、誘導されるまま席に着いた。
「何を召し上がりますか?」
「オムライスお願いします」
「承知致しました」と、言いニコッと笑ったように見えた。気のせいだな。
「お待たせしました、この近くの会社の方ですよね。以前お見かけした事があります。浅川奈緒と言います」ネームプレートを指さし名前まで教えてくれた。
「ここに来た事、ありました?」
「ええ、ちゃんと私は覚えています」
「ごめんね。歳の所為か覚えられなくて」
「歳だなんて、素敵なお兄様って感じです」
「あ、ありがとう」
「ごめんなさい、お客様に話しかけちゃって。食事できませんよね」
「いいよ、君のような美しい女性なら大歓迎だよ」
「嬉しい!これ、私のスマホの番号とアドレスです。良かったら、連絡ください。6時には、仕事終わりますから」
「ありがとう」と言って、渡されたメモを慌てて上着のポケットにしまった。
昼食も早々に終わらせ、午後の仕事に集中した。そんな中、経理の高橋からメールが入る。「今日、会えませんか?」
「申し訳ない、大事なお客さんと商談があるんだ。このお詫びは必ずするから」と返信した。
「残念です」との返信があった。
さて、早速今日会った、レストランの浅川って子に連絡してみようと、自前のスマホから、彼女のスマホに電話した。
「もしもし、山川と申します。突然の電話をお許しください」
「山川様?」
「申し遅れました、今日、そちらのレストランでお会いした者です。早々に連絡させてもらいました。今、お時間大丈夫でしょうか?」
「ええ、大丈夫…あ!今日来て頂いた、お客さまですね。ちょうど、仕事が終わって帰ろうとしていた所です」
「早速で申し訳ないですが、今から会う事は可能でしょうか?」
「ええ、是非!こんなに早く、ご連絡頂けると思っておりませんでした。正直、嬉しいです」
「ありがとう。では、駅前の売店の傍で。今からでしたら、15分後に行けると思います」
「その時間でしたら、私も行けますので、よろしくお願いしま~す」…、駅前はマズかったかな?
と、電話してしまったので仕方がない。一人でいるように振る舞えば良いのだ。
と、勝手なものである。
駅に着くと、すでに彼女は待っていた。軽く手を挙げ、シーとするジェスチャーをした。彼女も心得たもので、OKサインを出す。
ボクが駅の改札口とは違う方向に歩き出し、後ろをチラッと見れば、彼女は少し距離を置いて付いて来てくれている。
以心伝心なのか?彼女が聡明なのか?こちらの意図する事を瞬時に読み取ってくれていた。
わざわざ、高架下を抜け、駅の反対側に周ると、急に人通りが少なくなっていた。
そこに幸い一台のタクシーが止まっていたので、乗り込み、運転手がドアを閉めようとしたのを制して、
「暫く、待ってもらえませんか?」
「????」運転手もどうしたものか?と、悩んでいた所に、彼女が慌てず、タクシーに乗り込んできた。
運転手も納得したようで、ドアを締め、「どちらまで?」
「京橋の方まで行っていただけますか?」
「かしこまりました」タクシーは走りだした。
「さっきは、ごめんね。会社の連中に見られたて、良からぬ噂たてられたくなかったんだ」
「すぐに、わかりましたわ。見知らぬ女性と一緒だと、誰もが噂します。人の事を言う事を、楽しく思っている人多いですからね」
「失礼だが、若いのにすごく人生経験があるって感じだな」
「家が貧しかったものですから、学生時代からアルバイトしながら、長く生活していたからでしょうか?」
「偉いね。うちに入ってくる新入社員は、世間知らずが多いから、今まで何を学んできたんだ?って、言うのが普通になっている。言葉使いから教えないといけない」
「私は、たいした事ございませんわ」
「お腹空いているでしょ。食事に行こうと思っているのだが、何か希望はある?」
「京橋って仰いましたよね。前にも行ったのですが、お好み焼き屋さんに行ってみたいです」
「ハッキリ言ってもらう方が、こっちとしては楽だな」と、心の中でつぶやき、
「運転手さん、京橋駅の傍で、止めやすい所までお願いします」
「かしこまりました」昔は、ブッキラ棒な運転手が多かったが、最近の運転手さんは礼儀正しい。
しばらく走ると、目的地に到着した。「ありがとう」と運転手さんにお礼を言い、下車した。
「行きつけの、お好み焼き屋は決まっているの?」
「はい、いつも行く店はこっちです」と、彼女が先導してくれて、店に着くと数名が並んでいた。
「人気のある店なんだね」
「ええ、ここのお好み焼き、ふっくらしていて美味しいです」
「それは、楽しみだ」
暫く待つと中に入る事が出来た。客席が少な目の店だなと感じた。
もっと大きくすれば、もっと儲かるのにな~と、余計な事を考えながら、彼女が注文した物と同じ物を注文した。
確かに、美味しいと感じた。大阪生まれの大阪育ちなのに、こんなにおいしいお好み焼きは、初めてであった。
「結構お腹一杯になるね。時間あるなら、飲みに行く?」
「私もお腹一杯。是非お供させてください」
「嬉しいね。こんな美人と飲みに行けるなんて」
「美人じゃないですよ」
「この辺は、土地勘がないので、適当なお店でいい?」
「私、美味しい刺身が食べられる店知っています。お値段もリーズナブルですから」
「いいね。安月給者にはありがたい」
「じゃ、そこに行きましょう」
二人で、しばらく歩いた所にある居酒屋に入った。
「いらっしゃい!」威勢のいい掛け声が聞こえた。
「ここも人気の店みたいだね。もう、いっぱいになっているよ」
「ええ、新鮮なお魚が食べられるので、有名です」
ビール中ジョッキで3,4杯飲んだ。彼女も同じ量を飲んでいた。
「結構、お酒いけるんだね」
「父が、お酒大好きでしたから、遺伝かな?」
「酔い覚ましに、ここを出て、少し歩こうか?」
「ええ、お供させてもらいます」ほんのり、頬を酒のせいか、赤くなっている所がまた、可愛い。見れば見る程、美人(ボク好みの)である。
「そんなに、見ないでください。恥ずかしいです」
「何度も言うけど、美人だな~と、思って」
「そこに公園があるね。少し休んで行く?」
「はい」
公園を歩いているうち、茂みに隠れたベンチを見つけた。
「ここにしよう」彼女を促し、横にハンカチを広げる。(以前はこのようなことはできない男であったのに)
「紳士ですね。安心します。男の人はすぐに、変な事をする方が多くて」
「ボクはそんなつもりはないよ」
「さっきの内容は、一般論を言わせてもらっただけで、山川さんでしたよね。山川さんは、別!キスして欲しいの」
「ここで?」と、自分でも呆れるような、返事をしてしまった事を後悔した。
しばらく沈黙があった後、思い切って彼女の肩を両手でつかみ、こちらを向かせた。
一切抵抗しない。
そのまま、きれいな形をした唇に自分の口を合わせていき、きれいに生えそろった前歯を舌で舐めた。
彼女も舌を出してきて、絡めてくる。吐息はお酒の匂いに混じり、白粉の香りがした。自然と、ボクの右手は、彼女の乳房を弄っていた。
「ああ~、気持ちいい」声は小さ目にしているようだ。
更に大胆になり、ブラウスのボタンを外し、手を中に入れ、ブラの中の実物に触れた。
大きくもなく、小さくもなく、ちょうどボクの手に収まる大きさの乳房がそこにあった。
指で、乳首をつまむ、クリクリ捏ね回しているだけで、体を震わせ感じているようだ。彼女の手もボクの肩を掴んでいる。
しばらく口づけを続けていた。息苦しくなったのか?彼女から口を離し、ハァハァと荒い息遣いをしていた。
すると彼女は、いきなりボクのズボンのファスナーを下し、イキリ立っている物を掴み出し、口でしゃぶってきた。
「おお!」なんて柔らかな舌なのだ!
彼女の頭を押さえ、必死に絶頂を迎えるのを抑える。咥えたまま、舌で巧みに先端全体を舐めまわしてくる。
指で、幹を上下に擦りながら……。
「出る~~」と言った途端、樹液が彼女の口中に放たれた。
チュゥと吸い上げてくるので、いくらでも出てきそうな感触となった。
「美味しかった。まだ、お若いですね。一杯出ましたよ」ニコッと笑い、ハンカチで口を拭っていた。
また、ボクの一物もティッシュできれいに拭き取り、ズボンの中に納め、上から「ポンポン」と叩いてきた。
その仕草がまた、可愛さを増していた。
「ボクはいったけど、まだ君をイカしていないね」
「今度会った時に、一杯可愛がってください。私、山川さんの事益々好きになってしまったわ。どうしよう?」
「嬉しいね。また、会いたいね」
「私も、次はすごく期待していますから」
「家まで送るわ」
「いえ、駅はすぐそこですので、電車の方が早いかも?」
「そう、じゃ、今度会える日を楽しみにしているね」
「ありがとうございました。そしてごちそうさまでした。またね」手を振り、彼女は消えていった。
また一人の女性と知り合った。交わりはなかったが、それに近い所までいった。
やはりこの石の力かな?とポケットから石を取り出した。相変わらず、黒々と怪しく輝いている。じっくり見ると、やはり女性器の形に似ていると言えば、似ているな~。
魔法のランプのように擦れば、女性が寄ってくるのかな?
しかし、石に気付くまで、あえて擦った事はない。何故かな?と、仕事中にも関わらず、余計な事を考えていた。
試しに、擦ってみると、中心部分から、例の液体が滲み出てきた。
「わ!」思わず、声を出してしまい、部下達の視線が、一斉にこちらに向けられた。
「何でもないよ。驚かせて済まない。仕事続けて」
しかし、何も起こらない。この石を持っているだけで、そうなるのか?
そんな時、部下の美川好美が近づいてきた。
来たか!と、期待しながら待っていると、
「課長補佐、ちょっと相談事があるのですが、お時間いただけないでしょうか?」お~、やはり。と期待に胸ふくらませていた。
「ここでは、話できない事?」
「はい、できれば、二人きりで、ご報告したい事がございます」
二人きりは、期待感が高まるが、「報告」の言葉に引っ掛かりを感じた。
電話で第二応接を押さえた。
「第二応接室を取ったので、そちらで話聞こうか?時間かかるかな?」
「いえ、そんなにお時間は頂戴いたしません」
「わかった。先に行っててくれないか?後で、すぐに行くよ」最敬礼して、「お願い致します」と席を離れて行った。
なんだろうな?話を聞かないと、どうしようもないよな。と独り言のように呟き、近くの部下に、
「第二応接で、来客があるから、行ってくる。急用があれば、応接室に電話してくれ」と伝え、応接室へと向かった。
第二応接室の札を確認し、ノックした後、中に入った。もうそこには、彼女は居て座っていたが、ボクが入るなり立ち上がり、最敬礼した。
「お忙しい所、申し訳ございません」
「大事な部下の報告は、しっかり聞かないとね」
「ありがとうございます。実は、私の隣に座っている、佐伯君の事なのですが」
「彼が、どうした?」期待感が一気に消えていった。
「同期入社なのですが、付き合って欲しいとしつこく言ってくるので、困っています。
仕事中でも構わずメールしてきますし、帰りもストーカ並みに付きまとってきます。正直迷惑しているので、彼に直接断りましたが、いう事を聞いてくれません。
課長補佐なら、彼は上司を尊敬しておりますので、いう事を聞いてくれるか?と思いまして」
「ん~、まず、彼が好意を寄せている事が君には迷惑なのだね。ハッキリと断って一切付きまとわないで欲しい。が、言いたい事だね」
「はい。その通りです。お願いできますでしょうか?仕事ではなく私事で、課長補佐に相談すべきか?
かなり悩みましたが、これしか解決策がございませんと、自分で確信しましたので。ご迷惑なのは重々承知しておりますが、お願いできますでしょうか?」
「ん~、君のような優秀な部下が困っていると聞くと、対応しないと上司じゃないな。わかった。何とかしてみるよ」
「ありがとうございます」と、また最敬礼している。
「話は、それだけ?」
「はい、お願いして良かったです」涙目になっていた。余程、辛かったのであろう。
先に応接室を出た。席に戻ると、暫くして美川が戻って来た。化粧も直していたようだ。
早々に対応したい所だが、ちょうどその佐伯は、営業で外に出ている。
一所懸命仕事している中で、この手の話はしない方がいいな。と、決め後日彼と会おうと、心に決めた。
翌日、美川から連絡があり、早々のご対応ありがとうございます。
と、メモ書きが机上にあった。
「あれ?ぼくは、何もしていないぞ」と思っていると、頭を掻きながら、佐伯がやってきて、
「昨日、課長補佐から叱られる夢を見てしまいました。それを、ご存じと思いますが、彼女に伝えると、
課長補佐に相談したと聞きまして。ご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした。二度と、彼女には、近づきません」
「ああ、そうか。そうしてやってくれ。辛い君の気持ちも分かるが、お互い求め合って愛が生まれるんじゃないかな?」
「その通りですね。反省しています」
彼は自席に戻って行った。ふと、美川に視線を向けると、ウインクで答えてくれた。
ポケットの石を触りながら、これで一件落着かな?と、安堵して仕事に戻った。
数日何も起こらなかった。気になっていた石の事は、忘れかけていた時に電話が鳴った。
「わしじゃ!覚えておるか?立山の土産物屋にいた、婆じゃ。
石の効果は、あったであろう。その石が、他の者の所へ行きたいと、ワシに言ってきておる。
そこで、せっかく選ばれし者であったが、その資格がなくなってしもうた。
悪いが、その石、ワシに戻してくれないか?」
「やはり、この石のお蔭でいろんな事があったんですか。しかし、はいそうですかと、お渡しする訳には行きません。お断りします」
「石が申しておるのじゃ、おぬしの意思ではどうしようもない事じゃ。
おぬしに、断る選択はできぬ。と、言っても、その石の効力を知ってしまえば、溺れてしまうのは分かっておる。
ワシは今、おぬしの会社の前の喫茶店に来ておる。相談じゃが、売値は1万円であったが、500万円で引き取るのはどうじゃ?」
「御婆さん、食べるのも困っていると言っていたじゃないですか。500万円なんて、大金お持ちなのですか?」
「売る気はあるのか?聞いておるのじゃ。どうかな?」
「考えさせて頂く訳にはいきませんか?」
「ダメじゃ。今すぐ答えが欲しい」
ん~、手放すのは惜しい。しかし、500万円はかなり魅力だ。
結構楽しい思いをさせてくれたし、これ以上溺れてしまうと、自分の家庭を壊してしまうかも?知れない。
「わかりました。お返しします」
「その方が、ええ。その石はおぬしには、もう何の価値もない物となっておるんでな。石の意思で、効力は、発揮するのじゃ」
「そうなんですか。では、今からそちらに向かいます」
「待っておるぞ」
早々に上着を着て、今からお客様の所に行く事、急用があればスマホに連絡するよう、部下に伝え、向かいの喫茶店を目指した。
「おお、待っておったぞ。あの頃と変わっておらぬな。で、石はどこじゃ?」
「ここにあります」と、御婆さんの前に石を置いた。それを奪い取るように、老人とは思えない素早さで、取り去っていた。
「約束の金じゃ。それでは、縁があればまた会おう」と、老婆は出て行った。
残されたのは、大きな封筒に入っている、帯付の札束だけであった。
精算し慌てて、連絡先でもと思い、飛び出したが、そこには老婆の姿はどこにもなかった。
「不思議な事もあるんだな」と、独り言のように呟き、会社に戻り、封筒をカバンに丁寧に詰め込んだ。
これで、終わりだな。と、残念な気持ちと溺れなくて良かったと言う安堵感もあった。
また、もう一度チャンスがあれば、あの石を買うか?と、自分に問うてみたが、もういらないと言うのが自分の答えであった。
今年は男の前厄だったな。厄払いでも行こうかと、窓の外を見ると鮮やかな夕焼けであった。
不思議な経験をしたが、人生にこんな事もあっていいんじゃないか!毎日、あくせく仕事に追われ、クタクタになって帰る毎日に戻るだけだ。
夕焼けの空に、各々の女性の顔が現れて、ゆっくりと消えていった。
各々の顔は、皆、笑顔であった。
五八の賀
自分でも経験した事がない事を想像の世界で書きました。
オリジナルですが、すでに出版されております作風と似通っている部分があれば、お許しください。
「五八の賀」とは、40歳を表す言葉となっております。
主人公は、40歳である事を想定して、書き上げました。
文章を作り上げる(生みの難しさを)痛感しております。
まだまだ、半人前にもなっておりませんが、堪能して頂ければ幸いです。
最後まで、読んで頂いた事に感謝いたします。


