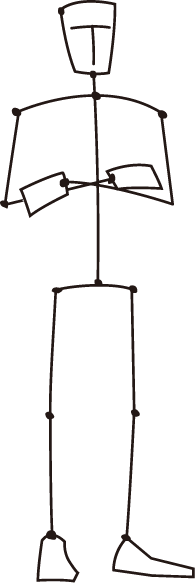嘆きとそれらの夜
その人が消えても悲しみは消えるものだろうか
鈍重な鉄と炭が噛み合うたび、車輪は回転を速めて次の街に向かう。
蒸気機関車の黒いモヤも無ければ遠吠えも無い。
澤宮市ノ助はあてもない旅によって生まれる何かを求めていた。
一ヶ月ほど経ってから得るモノが何かという期待に飢えなくなった。
一年経つと欲しいモノが遠ざかる気が強くなり、大分焦って世界を周ったものの、
目標から無意味に距離を空けた気がしてならなかった。
彼は時空列車に他の人と同じように流行にかぶれた理由で選ばなかった上、
特殊に強い興奮を抱いたわけでもない。
世界一周旅行の進化としての実質的な
期待の分が大きいために応募にハガキを送った。
停車場でちょっとでも整備を手伝えば安く上がり、想った以上に大きな寝具も借りられた。
何時の何処の場も後学の為に観て回れるからこれを逃す手はないと、父親の免許を拝借した。
見まねで覚えた技術で大まかに済まし、細かい技術は聞きながら試し試しで過ごした。
金は貰えないけれど、列車を使う間は食事と風呂と洗面の用の心配はなく、物質的な困窮がなかった。
ふと、目の前の黒い海が不自然な波のしぶきを上げて、月の光で輝く様が変容した気がした。
「どうにもできない事を、どうにかしようとする。
それは無謀の身滅ぼしと一つだよ」
後ろで常連客の一人、川山修司がからかいの笑みを口元に浮かべていた。
「君はそうやって波が変わることに、人生の特別な分岐があると思うか?」
川山は軽く厚い羽毛の外套を長い二本の指でさすって、大きく欠伸をしつつ腕を伸ばしのけ反る。
のけ反っても後ろが窓ガラスだから体を動かすには不十分そうだ。
後ろ頭の重みをガラスにあずけている。
「川山さん。俺が海を見ても海は変わりゃあしません。
でも俺と多くの人の気持ちは変わります」
川山は一瞬呆けたようだが、身の丈に合わない大きな口で豪快に笑った。
童顔で体もそう大きくないので、無暗な高慢な口が人から嫌われ高い評価の高値の絵を描いて生活していた。
自身の孤立を鼻と手のしぐさで笑い、周りを苛立たせるので誰も相手にしなかった。
「市ノ助くんはたまにこういう返答があるから侮れない」
「苛立ってしまいまして、つい」
川山に対して幾分も気の乗る返事をするつもりはないでいたが、しつこさに折れ、
声の調子やら反逆性の態度やらが気に入られ、澤宮はいつも気の利いた皮肉を周到にめぐらす癖が身についていた。
列車が変わり映えしない月光の海を進み、停車場にたどり着き、車内の客らは外に出た。
ホームでは駅員が日常で出しそうもない調子の響く声で
「悲海駅ー。悲海駅ー」と放送している。
「市ノ助くん、市ノ助君。
そう汚い服で観覧に行くのも笑いの種だから、服を借りた。着たまえ」
「俺、ちょっと休んでから行こうと思います」
「君、そう言うな。こういうのは我先に出ないのは野暮なんだ」
澤宮は面白くなさそうにし、
顔を濡れタオルで拭いてから炭や油で汚れた作業服からジャケットに着替えた。
市ノ助という男は何も知らない男の割に気苦労の激しい青年だった。
何も知らないフリをしているまま人生を過ごそうとしているのに、友人が多い青年だった。
川山はその対に居て、人生を謳歌している男だった。
目の前は暗闇と月の対照した海の広がりで、青も群青も漆黒も在った。
あとは白い鉄柱の明かりが軽妙に点り、暗く重い海に跳ね返る安易さは、
澤宮に多大に衝撃的な光景を見せている実感があった。
一秒の間の波のうごめきや、月と雲の影の瞬きの劇場が奏す揺れの巡りが、
観覧者たちには想像できない巨大な動きがあることを思い知らせていた。
澤宮と川山はホームの端と波の届きそうな切れ間に立ち、その動きに見とれている。
川山はじっとしていた。澤宮は黙って月を見ていた。
観覧者たちは一人も音を出せない脅威の美貌に釘付けにされている。
市ノ助は、なにも考えられず、耳と目と心の奥だけに自然な清い流れが向かうことに気づかずに、
しばらく、風景と一体したような悲しい錯覚に陥った。
随分落ち着きがない海だと思った。
荒れてはいないけど、懐かしいほど遠くに葬ってきた彼女の歴史があると思う。
愛すべきものを食らうような残酷さもある。
彼らの方に長身で細身、
茶色のジャケットと渋い抹茶色のスラックスを着た女性が歩み寄ってきた。
新見 静子(43)の名札を首から下げた案内人だ。
澤宮は175センチだから彼女はそれと大体同じになる。
彼女は問いに答えるだけで、過大過小の表現をせず、
また、必要以上も以下も語らないが、無愛想でもなかった。
細長く低い鼻で、とても頭が良い印象がある。
美人ではあるけれど、可愛さと愛嬌は足りない風に感じさせる。
それら平凡な評価より、彼女は教養から離れた哲学を背負っているようで、
強情や哀願する女性より強く感じさせた。
なんらかの境地に至りつつも自分と人間の本質を見失っていない素晴らしさがある上に、若く見える。
市ノ助は黒い空を見上げ、ふうっと息を放った。
白い息は闇にぼんやり消えた。闇へ溶けて沈むような錯覚があった。
市ノ助の錯覚には自然と一体になる空想があった。
市ノ助は、一旦静かになってみたいと思った。
こういった侘しい世界に消え入りたいと思った。
乾いた夜の胸の中で眠りたい気持ちが腹の内で湧いて、それができずに笑った。
川山は苦笑していた。
どうも苦手だと言って、そしてまた口を元の薄ら笑いに戻した。
静けさの中でぼんやり煙草の煙を吐き、海の方に投げる動作を止め、潰してポケットの中に入れた。
ぼうっとして、新見がじっと見つめているのを気配で感じ、
新見の方とは逆を向いた。
二人と彼女は悲海の方へ再度気を寄せ、心の中に気を向けて、また眺めだした。
「随分、静かね」
市ノ助も修司も何も言わない。
ただ静かで強くこわばった気の張りに、どこか過去の弱さを感じ、
ぞっと身震いしそうな緑の山を見て、パクリと潤いの音を立てて口を開けた。
ほぼ無感動な表情のまま、三人は心臓の脈絡に障りが出たのでは無いかと思った。
緑の山はじっと海を見下ろしていた。風のすすり泣く音が山から下りて、見下ろしていた。
「……あの海は人を呑み込んだ。山は毎日嘆きに朝日と共にくる」
天国は地獄に密接しているものだろうか?
遠くで鳥が鳴いていた。
日が出て静かな夜明けだが、この世界で太陽は十数分で隠れる。
死者が浮かびあがってくる想いが起こるような夜明けに、
市ノ助はしん、と体の髄の震えが一気に止まり、
体へ加わる重圧と気圧が強まるように感じた。
夜から朝になってすぐの著しい変容は観覧者たちの体を縛るようだった。
市ノ助は遠くでギチギチと唸る音を聞いたと思った。
風の方角が変わって木々の枝葉が擦れる音だった。
「海は毎日泣いている。夜になるといつも思い出す。
彼ら彼女らを殺した日の事、彼ら彼女らと過ごした日々の事。それでも神は許さない」
新見は唇の滑らかな光を結ぶようにしてすぐ、
「太陽と森と月は一緒に泣いてくれる。神が許さなくても、毎夜毎夜、共に泣く」
震えが治まって、市ノ助は信じがたい存在が夜には有ると理解した。
人間の存在しなくなった世界の感情や意義のなにもかもが剥がれ落ちて、
理屈や生活の根本すらも無くなるから想像もしなかった。
時空列車が到着する世界のうちには、倫理上、介入して可い部分もある。
市ノ助にとって規定は在っても無くても同じ事で、
世界を観て回れるだけで充分ではあった。
彼は世界を回遊し、つかみどころの無いカタチを、
天や地平線を見つめるような憧れとして抱き続けている。
手に入れもしていないカタチに満足してすぐ淋しくなるときに、
世界史上最高の宝石を手に入れる喜びと、
自分の物にしても物足りない絶望を思い描き、
世界を旅する事を諦めようと思うことがある。
彼はそういう時、夜の空を眺めることにしている。
自分の人生の大きな流れを忘れ、能書きも忘れ、命を持っている事も忘れだす。
彼はそれを見つめている時に、なんらかの巨大な波を感じた。
人生という途方もない旅を、非常に長い間忘れた。
自分の人生は一体、なんの形を得て、どういった形で終わり、
全体の感覚や感慨として狂った熱を持てるのか。
人生の山場を迎えるとき、どういう存在を胸に抱いて終えるのかを、理解したがる。
自分という小さな存在を流れの一員としても見ていたし、
大きい不自然な何かに交わることも出来ると考えることがあった。
列車はイギリスの箱庭に着いた。
庭は高名な男爵の城の中庭だが、限りなく空虚な美意識で作った風に見えて、
人生の終末を退屈に迎えているように思えた。
聞いたところによると男爵はまだ四十前だそうで、
野望や名声によった俗な事柄を、欲しいがままにしたそうだ。
川山は空中に浮く列車から城の中庭の花畑を写生し、
ふんふん鼻を呻らせて目を輝かせていた。
皿洗いを手伝いつつ、澤宮はその様子をちらちら見て、彼が絵に没頭するのを嬉しく思った。
澤宮は川山を毛嫌いしてはいるけれど満足そうな顔を見るのを大体は好んでいる。
澤宮自身への嫌味な行動や言動を嫌っているだけである。
あまり感情だけにとらわれない所を皆が好いていて、もどかしくもある。
絵が半ば出来上がってきた頃にアナウンスが降りるよう促した。
アナウンスは半ば手抜きみたいな間の抜けた声だ。
川山はパタパタと絵道具を折り畳んで真っ先に中庭に入り、
添乗員に「ここの介入はある程度できるらしいな」と確認し、
足早に向かって城の前に居る男爵の執事に声をかけた。
川山は小さな脚で、どすどす草を踏みつけて歩き、落ち着いた調子で、
「モントランス卿に挨拶したいんだが」 と、言った。
列車近くなら勝手に言語が翻訳される。
白い髭を伸ばした執事は随分長く間をおき、ぼそぼそと「こちらでございます」と呟いて、
トンネル状になった城門へ短い歩幅でゆっくり入った。
門をくぐればすぐ庭がひろがっていた。
鳥の声は胸を弾ますほどだったので喜びが体から溢れだした。
白のテッポウユリ、青のバラ、造園の脇にはタンポポが力強く伸び、
髪の毛先が揺れるほどの心地よい風で、
入ってきた観光客は一度に表情を緩めだす。
庭の草花は少しも儚さを感じさせなかった。
淡い色こそそこらにあるものの、
力強く、美しく存る事の幸福さがあった。
太陽の薄い光が雲の加減で揺れている。
市ノ助は、こういう所で一日中誰かしらと、
どうでも可い話をして笑い合いたいと思った。
その楽しみを永く続けたいと思った。
その場で笑い合って、耳の後ろを風で撫でられたいと思う。
川山はどんどん奥に行き、
城の中でおーいおーいと声をあげている。
他の執事や小間使いは
なんの厳かさもなく市ノ助の後方の客たちを誘導し、
和気あいあいとして彼ら彼女らを庭の整備士などに紹介していた。
市ノ助は庭を観覧している一団の輪に入り、
やかましい川山をニヤニヤと一瞥した後、
普段回った世界でも見たこともない植物、
見たことのある名も知らぬ草花、蜂や蝶を
胸がすっと爽やかになる心地で眺めて歩き、
そのうち庭の中に池を見つけた。すこぶる綺麗な池だった。
池の底で綺麗な水草が漂っている。
喉元がぐっと澄んだ心地がした。
彼は自然的な美の喜びにめっぽう弱く、
錯覚とも本能とも断ぜられない不覚の快感に陶酔した。
「ここは良いところだろう」
男の声がした。
横でベンチに座ったスーツ姿の男が脚を組み、
梢の影日に目を細めて市ノ助を見据えていた。
黄金の瞳に見えた。
男がベンチの隣を掌でぽんと叩き、
市ノ助はそろそろ近づいて、
「なんでしょう」と問いにもならない事を聞いた。
「お客さんだろう。座るといい」
「はあ」
男はげっそり痩せていて長身、スーツは質の良い品らしいが、
アイロンをかけていないのかシワだらけだった。
急激に痩せたためかスーツの横幅がほとんど合っていない。
「貴方はこの庭をどう思う?」
急な問いだった。
男は聞いておいて済ましている。
市ノ助は何か答えないと
可けないのは分かっていたが何も言わなかった。
そしたら男はよろよろ立ち上がって、
木に生えている赤い花に目を近づけて香りを嗅いだ。
市ノ助は高く長い鼻筋に見とれ、ぼうっとし、
数秒のその間に周りの草花の甘い香りを喉の奥に感じた。
ツバを飲んだら苦かった。
市ノ助は男の視線に羞恥らしきものを感じて
目を逸らし、足元を見た。
足の脇でミツバチがコスモスに三匹たむろしている。
彼は異質な喜びを受け止めようか悩んだ。
ミツバチが一匹小さな羽音を立てて眼前を通り、池の水面に脚を着けている。
きっと水を飲むのだろう。
市ノ助は男を気にかけつつスッと立ち上がり、
ミツバチの様子を窺うため池に近づいた。
池は西洋風でなく和風である。
それでもこの庭の雰囲気になじんで融和している。
市ノ助はあえて和風の池にした着眼点の鋭さに感激して、
男にあれこれと細かいを事を聞こうとした。
けれど、男はまだ赤い花の香りを嗅いでいたので、
池や庭の風情などを話すには振るった事も話せそうじゃないから、少し待った。
市ノ助は男のその仕草を自然愛好家の主張と考え、
その真似をしようか逡巡していた。
花の香りを胸いっぱいに吸い込み、
まるで窪みに挟まった動かない岩のような瞳を、
上方に向け感動して声もなく息を吐いて微笑む。
市ノ助はその一連の行動を度が過ぎていて不愉快に思い、
顔をしかめ、ジロジロと胡乱な目をした。
下卑ていても崇高な考えでも、周りに合わない過剰な行動は見ていて煙たい。
「それじゃあ失礼いたします」と声を小さくしてさっき居た一団の方へ向かった。
男は角ばった不自然な目で彼を見据えてお辞儀し、それからベンチに近づいた。
男は足元のコスモスを眺め、タバコを吸いだした。
川山修司がまだ人間を信じていた頃、とても純粋だった頃に、戦争があった。
修司は母と妹と共に疎開し、都会と比べて生活水準の低さに驚き、
それでも活発な生活をしていた。
村の暮らしは困窮してはいなかったが、
一時しのぎで生活するにしても少々不満の感があるといえた。
ベニヤ板を張ったあばら小屋の中で生活し、三人はどこに行っても歓迎された。
父の思惑通りだった。父には賢さを成すことのできる伝手が多くあり、
誰もがそういう側面に対して作り笑顔して黙っていたのだ。
父は、皆に笑顔の仮面を渡して、それを被れと命令したのと同じだった。
修司はそれを知らなかったが薄々感づいてはいた。
村の人間たちにイタズラを沢山しかけ、いつ怒られるだろうと考えた。
誰かがきっと怒ってくれる。いつか誰かが怒ってくれる。
叱ってくれない事にいつも不満を抱いていた。
修司が九才になる頃、父があばら小屋にやってきた。
父は母に金を貸してくれるよう催促しているようだった。
修司はなにやら怪しい雰囲気だぞと思い、
走り回ってカラカラになった喉をこりこり細い指でなぞった。
「どうしてそのような口をきく? 俺がここまでお前らを連れてやったんだぞ」
ドスの効いた静かな響きが、修司の胸を一気に重くした。
「なにもそんな風に云う事ないじゃないですか」
母は手の平で顔を覆っている。
「騙されたんだからしょうがないだろう!」
父はぎりぎりと歯を食いしばり、母の肩を揺すり、宥めだした。
修司は何も言わないでいた。
見てしまった事を打ち明けたらどうなるだろうと
いつも考え込んで五日過ごしていた。
彼は五日の間、家から一歩も出ず、誰ともろくに話をしなかった。
頭の中にただ蝉の鳴き声がしているのを覚えている。
ビビビビ……ジィーン……ビビビ、
鳴き続けてくたばる蝉をうらやましく思った。
彼は四六時中、ほとんど水も口にしなかったたため高熱を出した。
近くの診療所に連れて行ってもらった。診療所は閉まっていた。
村に一つだけの診療所の中にはお医者様が居た。
薄暗い部屋で誰かと話をしており、
先生はソファに座って床をじっと見つめている。
アルコールや薬の棚、瓶がカタカタと鳴っているような輝きを放っていた。
先生のソファの右側からの夕日は
綺麗に部屋に差し込んでいるらしかった。
母は入り口のガラス戸を叩き割りそうな勢いで、先生を呼んだ。
先生はチラとこちらを見たけど、すぐ下の方に目を向けてしまった。
修司の高熱は腸チフスによるもので、近所の女の子が診療に来たら
治療を受けさせてくれたが、それからは村から疎外される扱いとなった。
修司は、何事においても父と母を恨むようになった。
自分が産まれた環境や境遇そのものを忌々しく思った。
誰も彼もが憎くてたまらなかった。
実質では、本人が一番分かっていた。誰も憎いのではない。
自分自身が一番憎いのだ、と。
川山が城で叫んでいるのを執事が止めた時に正面の階段を回って、
モントランス男爵が一階の方に下りてくる。
川山は小休止の息を吐き、すぐブスッと幼子のような顔をした。
男爵は、苦しみすら無いほど疲れたような足取りで歩いてくる。
どことなく争いに疲れた兵士のように見える。
「なんの御用ですか?」
モントランス男爵は、疲れている様子だが愛想笑いは見せた。
ボロボロのスーツを着ている。
川山はワイシャツに絵の具が付いた部分を親指と人差し指で擦り合わせながら、
不気味な顔でブツブツと唱えるように独り言を云っている。
モントランス男爵は先ほど逢った青年が、
川山と接点が有ることに気づいてはいた。
けれども、接する点に生じている感情が何かを探ろうとは思わなくなった。
目の前にいる男がいかに気が狂っており、
どれほど危害を加えかねないかを懸念している。
川山はある頃から自分が陥れられる生き物だと知っていた。
苛立つほど不愉快な運命の車輪が、
彼を蹴り飛ばそうと邪魔をしているのをある頃から理解していた。
「お茶でもいかがですか?」
モントランス男爵はやせ細った顔に刻んだような濃いシワを入れて微笑む。
川山は心地よい安堵が、不図、胸にわいてきて頭にまで届くような気がし、
思わずニコリと微笑み返そうとさえした。
どうしたら良いのか分からなくなっていた。
ただ自分を胸の中で抱いてくれる母が頭に浮かんだ。
しかし、そういった母すら存在しないことを、彼は悔やみだした。
ああ、僕は憎しみを殺す誘惑に敗北したのだ。川山はそう思った。
川山は自身の真実をそう理解した。苦しみと憎しみがある中ではそれを直感していた。
昔、ある約束をした事がある。ある世界では憎悪も悲しみも癒され、誰も彼もが幸福に生きられる場所があるのだ、と。
それを天国というのだと、川山は教わった。
事実、彼はそれを実感していたからこそこの世界に入ったときに、心のどこかで満足しだした。
男爵自身が中庭の白塗りのテーブルに紅茶を用意した。
備え付けらしい白い椅子と、赤白青のしま模様のパラソルもあった。
このセットだけで十分幸福そうに見え、花と木々の葉が足元によく凪いで、川山のふくらはぎにフ、と撫でた。
川山はそれでも無言のまま男爵をチラチラ顔色を窺うように睨んだ。
男爵はテーブル上の花瓶の中でしなるように入った青い花を眺めていた。
男爵はツと立ち上がり、川山の後ろに手を振った。新見が通りかかったところだった。
新見がこちらに来た。
「お久しぶりでございます」男爵は笑った。
「本当ね」新見は恥ずかしそうに笑う。
川山は、とても憎かった。全てが憎かった。信じられないくらい全てが憎かった。
この世の中の全てが信じられなかった。だからこそ悪い事をあえて言ってきた。
誰も彼もを侮辱したいと思った。でも、それも出来ないくらい、今ここの天国は心地よかった。
市ノ助は、静かな庭園をうろうろ迷い歩き、
立派な家屋の前で止まっていた。ログハウスと云うのだろう。
静けさと活力を持った建物でかなり大きい。屋根に大きな枝と葉が被さって、
屋根の青色が群青になっていた。
市ノ助は胸の中に木の枝の影が落ちたような心地がした。
それでいて梢の間から日も落ちたような感じがした。その影は涼しく気持ちが良いものであった。
後ろから彼を呼びかけた声があった。
「お客さんだね? 良い家だろう」
背の高い声はどこにも他人行儀や無作法の怯えがなかった。
『お客さん』というのは彼らにとってみれば家族という扱いに当たるのであろう。
「ええ。面白い家ですね」
市ノ助は気持ちが良いので随分と大げさな微笑みを浮かべたと思った。
そして面白い家という言葉を穿たれなければ良いと思う。
「そうでしょう」
男も大いに笑った。
少しの間、市ノ助と体格ががっしりした男は、ニコニコと家を眺めた。
ざわざわ凪ぐ風が気持ちよく、静かな城に何故これほどの家があるのかと聞くかを忘れた。
がっちりした男はふっとした隙に挨拶して行ってしまった。
市ノ助は、不図、川山のことを思い出した。嫌な気持ちになった。
自然、彼からされた嫌な事が思い浮かんだ。少し様子を見に向かおうと思う。
市ノ助は城の中に入り、ごめんくださいと声をかけ、
しぃんと響きが伝わる様子を不気味に思いつつ、もう一度声をかけた。
薄暗く、石の渡りが大きくつながってる城だった。壁にまで通っている。
市ノ助が強く一歩を出すと大きな響きが出た。
市ノ助は引き返そうか迷い、逡巡していると先ほどのスーツの男が出てきた。
「お友達をお探しでしょうか?」
市ノ助は思う暇なく、はい、と答えた。
「お友達はお休みですよ。汽車の中で休むそうだ」
「ああ、そうですか。もっと早く言えばいいのに」
「貴方はあの男の辛みをどう思いますか。分かっておられるでしょうに?」
市ノ助は、鋭い問いにはっとした。
「貴方は、人の痛みが鋭いほどに分かるのでしょう?
それが貴方の素晴らしい直感性というものでしょう」
市ノ助は何も答えなかった。じっと黙って男を睨むような目をしていた。
外に出ると庭は寒気がしていた。まるで冬になったみたいに、薄暗い空になっていた。
「ここの天気は変わりやすいですよ」
市ノ助は服をまくって体を覆いながら汽車に向かった。
市ノ助は街を見ていた。機関車が故障して停留中だった。
静かな暗闇にぽとんとゴムボールでも落ちて奇怪な薄ら寒さがしそうな街だった。
市ノ助は胸に花を抱いている。
この前の世界で去り際に男からもらった淋しさのある青い花だ。
空しい風でも吹いたら散ってしまいそうな花だった。
川山はあれから毎日考えながら絵を描いているようだ。
市ノ助はそれを見ていて胸騒ぎがしていた。
胸元に石を詰まらせているようだった。
新見は放っておきなさいとよく言った。新見はまるで母親のようだった。
汽車が鳥の国に着いたとき、新見は高原の空気に思わず咳をしそうになった。
新見は寒い場所が苦手で、寒い所では分厚いコートを着る。
分厚いコートに肩と腕を隠すと、高原に居る鳥の名を川山が聞いた。
「ジュゼンベクルマドリっていうのよ」
「ふうん。初めて聞く名前だ」
ジュゼンベクルマドリはふさふさの毛をしていて飛ぶことができない。
足も速くない。ただ仲間が多いため毛づくろいや巣作りを非常に器用に行う鳥だ。
「あれが巣か?」
川山が指した方向には植物で紡がれた丸い籠があった。
鳥が繕った物で、大勢の人がくちばしで細かい事ができるのが分かり、
感嘆の声をあげると新見は知っている。
新見は眼差しを空の方へ向けた。
空にはバラバラに欠けてしまった月がおぼろに白く見えた。
この世界ではそうなのだと新見は知っている。
家の中に居ただけの昔とは全く違う。
今はしっかりとした知識もあり長旅もしてきた。
悲しい事も沢山あったが、それだけではない経験もあった。
師との出会いやその家族との親愛が重なって、
それこそが世界で最も大切にするべき事柄なのだと分かった。
「新見さん」
他の観光客が新見を呼んだ。
川山は考えながら巣の中の鳥の絵を描き、背景を欠けた月にするべくしゃがんだ。
新見はこの世界のエピソードを語った。
「月の鳥」という話で、これもまた大きな感嘆が上がった。
新見は、悲しみに暮れる月に憑りつかれた鳥の話を始めた。
月がまだ裂けていない頃、まだジュゼンベクルマドリは空を飛ぶことが出来た。
ジュゼンベクルマドリは籠を作るのも上手くなかったし、
子供もそれほど作らない性質のようだった。
ある日一匹のクルマドリが声高に叫んだ途端月が八つに割れたという。
とてつもない轟音がし、月の隕石がいくつも鳥の国に落ちて何万羽もの鳥が死に、
住むところは狭くなってしまったそうだ。
それで空中にぶら下がって居住のスペースを確保したというのだが。
「------それで、ジュゼンベクルマドリ達はその叫んだ同胞の鳥のことを責め、
追放したらしいの。その鳥は自分がやっていないと月に証拠を探しにいくのよ」
新見は真摯な顔で眉間にシワを寄せ、唇を強く結んだ。
月へ飛んだその鳥は巨大な氷山を見つけ、
居心地が良いのでそこに移り住むことにした。
月にある氷山はあまりにも美しいところで、独り占めできると知り、
彼女(メスの鳥だと伝説では云われている)はそこで孤独に地上を見下ろすことにした。
月からみる地球はあまりにも小さく、なにもかも無駄なことだと考えるようになり、
地上でうごめく彼らを蔑視し、彼女は世界最高の鳥と自分自身を崇め、
毛づくろいから何から全て丹念にするようにした。
しかし、エサはあまり取れず、冷たさのあまり風邪を引いてしまった。
刻一刻と症状は悪化し、肺炎となり、彼女は助けを求めた。
「でも------誰も彼女のことを覚えておらず、
助けるどころか様子を見に来る者さえいなかったというのよ」
川山は話を聞いて、ふうん、とその伝説にあまり興味無さげに答えた。
彼はこういった話に興味を持つのが常だったが、
最近になってそういう趣向に飽きたのか、黙ってしまった。
「川山さん。つまらなかったかしら?」
「いや、今絵を描いているから」
川山は月を見上げた。
「だが、結局月が割れた原因はなんだったんだ。月が寿命で爆発したのか?」
「それは分からないそうよ。結局そういう話だったんじゃないかっていう説もある」
彼らはいつしか緊張で呼吸が荒くなっているのを感じている。
新見は彼の絵をじっと見つめて、練達した絵の上手さを誉め、市ノ介の方へ歩み寄った。
「どう? この国は?」
市ノ助は何も答えず笑った。青いバラを手に取り、空に向かって投げた。
バラは空宙を舞い、花弁が散り散りになって天高く飛んで行った。
川山はそれを眺め、すばやく描きこんだ。
「月の鳥の弔いをした。…………良いところだよ。
空を舞う存在しかここには居ない。天国にだっていますぐ行けるよ」
新見は微笑み、彼の肩を叩き、川山の方に連れて行った。
川山は絵を描いていた。青いバラが月と鳥と一緒に描かれていた。
「いいじゃないか。月の鳥、青いバラによって弔われる。……うーん、ゴージャス」
「……川山さん、貴方はこういう洒落たことをするんですね」
新見と市ノ助は笑った。
奥の空には真っ黒な積乱雲が集まり、遠くからやってきていた。
高原を下ると海が見える。
耳の奥から体の芯にまで届きそうな海鳴りが聞こえて、
市ノ助は、それに呼ばれたような気がした。
胸で、心臓の音がとくとくと鳴っているのも聞こえる。
丘から海を見下ろした。
丘から見下ろしやすい所には、ひざ下にまで届く岩があった。
彼は岩の隣に立ち、胸にこみ上げさせる音の鳴る、
小さなあぶくの白波を起こす海と、 高々とした黒い空とを眺めた。
積乱雲は雷を遠くで起こして、大海の奥の孤島に落ちた。
家屋ほども高さがある白い街灯が、彼をぼんやりと白く照らしていた。
彼は体が強い風で圧されているのを感じて、耳の奥でばたばたとした音を聞いた。
耳が赤くぽっと染まって、耳たぶを親指と人差し指で擦り掻いた。
下の奥の方にも街灯が見える。白波に漂っているように思えた。
そうしていると汽笛の音を聞いた。
汽笛は観光客らを呼ぶためにあるため、
他の用で鳴らしていい勝手はないのだけれど、
奇妙な事にそれは海の方から聞こえた。
さきほどまで休憩時間と云って眠っていた皆はどこに行ったのだろう。
暗闇だから気づかなかっただけだろうか。やはり戻った方がよいだろうか。そう考えた。
しかし海の方から聞こえるのは確かなのだ、だから僕は降りて行った方がよいのだろう。
彼は海岸へ下って行った。暗い中で頼りになるのは街灯だけである。
下る最中にある小石混じりの砂の質は貝だと分かる。
ちゃりちゃりと心地いい音が耳の中でこそばい。
その音の感触は本当に奇妙だと思った。
星のかけらでも踏んでいる気がし、肺の気道が落ち着いてかすれもしない。
全ての感覚が感じたことのないほど整然と成される。
市ノ助は驚きより強く心地よさを感じた。
市ノ助は、胸の奥であの男爵の云ったことを思い出した。
あなたは痛みが誰よりも分かるのでしょう。彼はそう言った。
腹の内に沈むような言葉だった。
どこかに慈愛もあるようで、市ノ助はそれが濡れた着物のように重い気がして、
苛立つ羽目になった。
爽やかな潮風が吹いた。バタバタと耳元で音が鳴る。
足元の砂をキュイキュイ鳴らして彼は浜に足を着けた。
ここの砂もさきほどと同質のように思えた。
後ろの方で街灯のジリジリした電子音が耳に障る。
彼は海岸の方へ駆けてった。汽笛はやや奥の方で響いている。
「行くな」
市ノ助は誰かが彼を呼び止めたのを右目の視界の端で見つけた。
黒いコートを羽織ったモントランス男爵が居た。
市ノ助は驚いて何も言えずに細い唇を歪め、ただ男爵の方を見つめた。
男爵の後ろにはピアノがあった。
市ノ助は何かを口に出そうとしたけれど、それは強めの風に持っていかれて、
なんの音色もない、唇の震えにしかならなかった。
「僕はときどきこうやって現れるよ。君の夢の中でね」
背の高い彼がまっすぐに立つと、なかなか威圧感があり、彼は少なからず気劣った。
それとも、この夢の美しさと感覚の素晴らしさに怯えているのか。
「僕はここではモントランス男爵ではないよ。ただの男爵。僕を男爵と呼ぶといいよ。
それがここのルールの一部だからね」
男爵は薄く笑った。彫の深い笑みには強い影があるけども、とても優しい笑みに見えた。
「その……そのピアノはなんですか」
市ノ助はおずおずと聞く。
「これもこの世界のルールのうちの一つだ。弾いた感情によって道が開かれる」
そう言って男爵はピアノの前に座り、鍵盤の上に手の平を置いて奏でだした。
温かみのある、ショパンの夜想曲第二番だった。この曲は市ノ助も大好きだった。
目の前が光りだして、汽笛の音が大きくなった。
市ノ助が目覚めると鳥の国の草原を枕にして夕日に顔を当てていた。
観光客の皆が眠っている。
ぼうっとしていると鉄道員が燃料を燃やすよう大きな声でドヤした。
昼寝をし、かなり目が覚めたから足腰と腕の筋肉も活発に働き、
いつもより早く燃料の薪を運べた。
燃料が薪というのが安っぽくて好きだった。
燃料と燃焼の合理が合わないから初めは妙だと疑ったが、
最初から時空列車は水晶燃料をおもに使い、薪はあてがいらしい。
シャベルを持って腕を動かし水晶を火の燃ゆるかまどに入れ込むと、
市ノ助は産まれた騒がしい町を思い出す。
いつもそういう事を思い出して仕事するのが癖だった。活発に体が動く今日は尚そうだった。
既述して臭わせたけども彼の出身は鉄道の通う町だ。
それもけっこう大きなターミナルがあった。
鉄の窓枠すら大きい天井ガラスがあった。大きなガラスだから天井も高かった。
地面から三十メートルほど高い天井には鳥の糞がべっとり付くため、
高場で仕事する清掃員はいつもボヤいていた。
空気はいつも薄い煙がたちこめて鼻をつまむ人が多くいたように思う。
といっても、煙を入れずに出すような仕掛けもされているから、
人為的工夫のおかげで乗客たちはさほど苦痛ではないようだった。
彼の祖父と親父、それと伯父も汽車のかまど焚きだったため、
彼自身もそういう仕事に就くのだろうと自然に思い込んでいた。
彼が鉄道の仕事に関係することで最も好んだのは乗客と他愛ない話や
土産話を聞くことであった。
幼いころから鉄道仕事に身を置き、
真実らしい話や言葉は乗客らの経験の伝説めいたストーリーだった。
彼らの話はどれもこれも情熱にたぎり、強く美しいものだった。
市ノ助は自然とそれらに魅せられた。
彼にとってみればターミナルは輝く集まる巨大宝物庫だった。
これ以上に美しさが集う場所などあり得ないとさえ思った。
彼はそのうち自分で宝石の実体をつかみたいと願うようになった。
幼い少年は奇跡の集合体の一つ一つを耳にできる場で、
自分をその身に置きたいと望み、
安定した足場が待っている世襲の鉄道仕事よりも、
自分の脚を強くできる危険な旅の道を選びたいと考えた。
かまどを炊く仕事を終えて、川山と新見が起きてきた。
なにやら楽しそうな雰囲気である。
新見は楽しげな顔つきにもどことなく戸惑いを浮かべていたが、
川山はうれしそうに絵を描き始めた。
「どうしたんですか。何かうれしい事でもあったんですか?」
市ノ助は二人の興奮具合から感化気味に興奮し、聞き出す。
「私と川山君で同じ夢を見たのよ。とてもきれいな海の夢を」
市ノ助は心に思い当るところがあり、目を丸くして驚き、静かに唇から、ふ、と息を出した。
驚きの息は二人の反応を引きだして、俄かに大きな感動を与えた。
「やはりお前もか! なんなんだろうねこれは。とてつもなく巨大な運命の歯車がかみ合って、
僕たちをどこかに運び出そうとしているみたいだ!」
川山はにこやかに、かつ豪快に歯を見せて笑い出して、それでも筆を止めずにキャンパスに
絵を描いている。
「どういうことなんだろう。夢の紡ぎだす新しい世界だろうか」
嘆きとそれらの夜