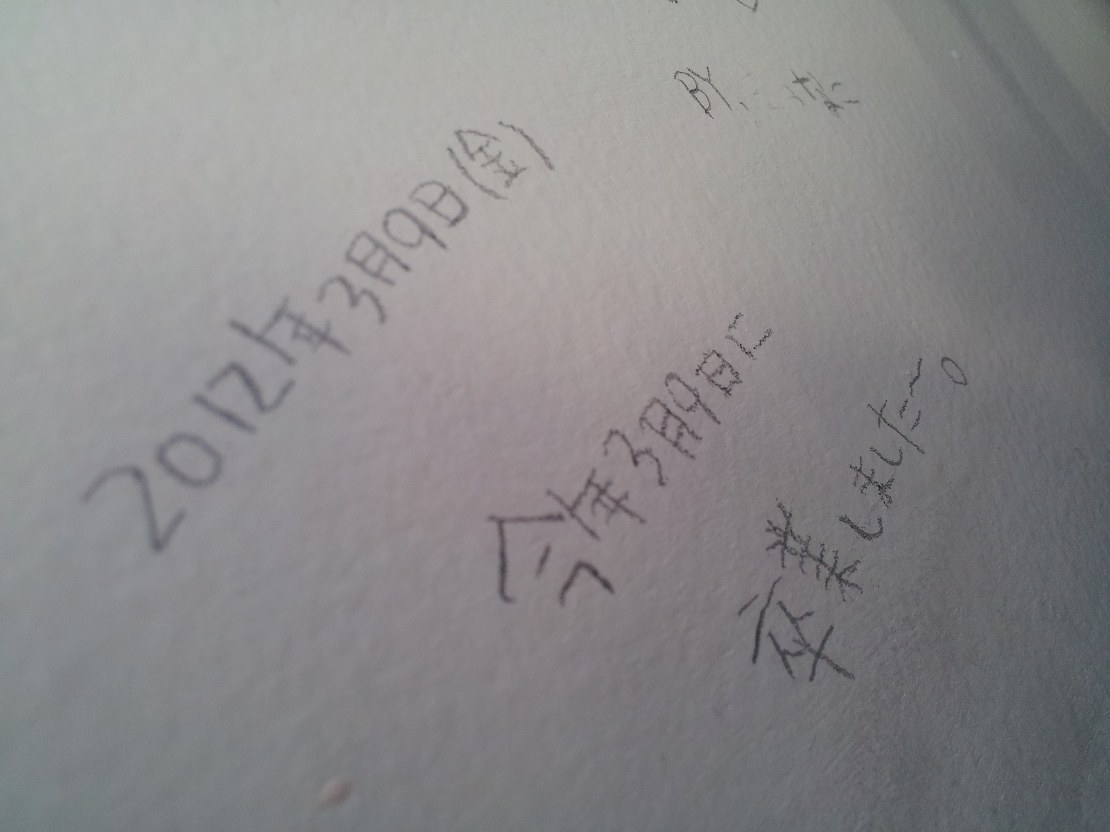
卒業 ~続 真実はどこに~
1 公平な判断
しとしと、雨が降っている。しかし、これまでのような冷たい雨ではない。久しぶりにマフラーと手袋がなくても、支障なく歩ける。2月末。着実に、春の訪れを感じる朝だった。
それにしても、ここ数日は、憂鬱だ。「モンスターペアレンツ」への対応といってしまえば、それまでだ。しかし、それですべてを片付けてしまうのも、ちがうような気がする。そもそも学校だって、古臭いルールに縛られ、融通のきかない「モンスター」ということもできる。どちらがモンスターか、いい勝負だ。
そう自分に言い聞かせたとしても、やはり、憂鬱なのである。足取りが重い。このまま、無事、卒業式を迎えられるのだろうか。ビルの窓ガラスに映った自分は、予想以上に猫背だった。肩甲骨を意識し、ぐいっと胸を張ってみる。でも、体の真ん中あたりに感じるモヤモヤは晴れるはずもなかった。
小野寺は、あれこれ考えながら歩いていた。すると左後ろから、気配を感じた。急ブレーキの音が聞こえた。
「おい、危ないやろ!」
窓を開け、中年男性が罵声を浴びせてきた。
「す、すみません」
謝るしかなかった。目の前の歩行者信号の色は「赤」。小野寺は、横断歩道のど真ん中に突っ立っていた。
その父親が訴えに来たのは、昨日の放課後だった。
「どういうことですか。おかしいでしょ」
校長室のソファから、身を乗り出す。目の前のテーブルを何度も叩く。威圧しているつもりだろうが、そんな親を何人も見てきた小野寺にとって、別段、目新しい経験でもなかった。
父親の主張はこうだ。1年生からずっといじめにあっていたことが、ここ最近、やっとわかった。学校はこれまで何をしてきたのか。うちの子はそんなハンデを背負いながら、勉強をやってきた。内申点を公平に判断してほしい。
要は、内申点を上げろ、というわけだ。
内申点というのは、高校入試の際に本人があらかじめ持っている「持ち点」だ。それに、入試の点数を合計して、勝負する。内申点は、通知表の1~5の評価の合計と一緒だと考えていい。
白髪交じりの髪をかきあげながら、目を真っ赤にして、興奮気味に続けた。
「内申点を上げろなんて、一言も言ってないでしょ。公平な判断をしてくれ、と話をしているんですよ」
何が「内申点を上げろなんて、言ってない」だ?聞いてあきれる。
校長が、静かな口調で話す。
「お父さんね。内申点というのは、それぞれの教科で評価してますんで、この時期にはどうしようもないです」
「はぁ?それじゃあ、学校は何もしてくれないって言うんですかぁ」
怒声が響いた瞬間、いつも通り騒がしかった隣の職員室が、しーんと静まり返った。おそらく、父親の声が届いたのだろう。
「もう卒業までちょっとしかないから、何事もなかったかのように卒業していけ。そういうことですかぁ。学校ってそんなに冷たいところなんですかぁ」
さらに、ヒートアップする。
「過去を振り返るな。そういうことですか。校長先生」
「まぁ、過去を変えることはできませんからねぇ」
「うちの子はねぇ、その過去にいまだ振り回されているんですよっ!」
父親の目からは、涙がポロポロとこぼれだした。同情する気にはなれなかった。
小野寺は話した。
「お父さんのおっしゃる通り、卒業まであと10日ちょっとしかありません。ぼくたちにできることは限られています。まずは、カズヤくんからお話を聞かせてください。事実を確認させてください。ただ、お父さんに話をするのにも、それだけの年月がかかったんですから、ぼくたちに腹割って、話をしてくれるかわかりません。無理やり聞き出すこともできません。でも、その中で、具体的な名前が挙がれば、状況を確認して、間違ったことをしている生徒がいたら、それを指導する。ぼくたちにできることは、そこからです。過去をかえることはできませんが、振り返ることはできますよ」
「あの子は人間不信なんです。多分、先生たちにも、話さないでしょう」
「そうかもしれませんね。でもね、お父さん。あの子、社会科は結構好きじゃないですか。ぼくは授業終わって、あまり生徒たちが話しかけてくるようなことはないですけど、カズヤ君は結構寄ってきてくれましたよ」
そう話しているうち、少しずつ、父親の表情は和らいでいく。
「いずれにしても、明日の1番に、カズヤくんから話を聞かせてもらいます。よろしいでしょうか」
担任の石本の言葉に、父親は黙り込む。
「でも、あの子は根掘り葉掘り聞かれるのは、嫌がるだろうから、そっとしてやってくださいませんか」
「わかりました」
次の日。石本は、カズヤを指導室に入れた。もちろん、詳しく問いただすことは、なかった。
「しんどくなったら、お父さんか、私に言いや。爆発する前に、やで」
「はい」
カズヤは比較的、おだやかな表情に見えた。しかし、昼食時間のことだった。
「カズヤがいません。4時間目から」
授業の空いている教師で、校内を探す。見当たらない。小野寺は昼休み、校舎の上から、あちこちの窓を開け、下をのぞきこんだ。「最悪の事態」が脳裏をよぎったからだ。
幸いなことに、カズヤは職員室と、生け垣の間にある、狭いスペースに隠れ込んでいた。小野寺が発見し、声をかけた。
「おう、カズヤ、大丈夫か?」
声をかけると、カズヤは震えながら。顔を上げた。「大丈夫です」
顔は青ざめていた。しかし、声はしっかりしていた。
「カズヤな。逃げることはいつでもできる。これからも嫌なこと、山ほどあるぞ。おれだって嫌なこと、あるわ。そん時、どうするかや。おれは、悔しい時はな、その気持ちを次のことにぶつける。『なにくそからの一歩』や。今すぐ、そうなれとは言わん。これからの、課題やな」
「はい」
「クラスメイトが探してるわ。石本先生には、こっぴどく怒られるぞ。めっちゃ心配してはったからな。覚悟、あるか?」
「はい」
「よっしゃ、出よう」
職員室に、向かう。ちょうど、石本が出てきた。
「カズヤ、どこ行っとんたん?心配してたんやでぇ」
石本は、やさしい声をカズヤにかけた。小野寺は、隣のカズヤに言った。
「あれ。予想がはずれたな」
カズヤは、にっこり笑っていた。
2 謝る、ということ
翌週のことだった。「三寒四温」とはよくいったもので、暖かい日が続いたと思えば、また寒さが戻る。その日は、日差しもあり、暖かな日だった。
3学期の期末テスト初日。3教科を終え、いそいそと家路につく生徒たち。テストがどっさり戻ってきた教師は、採点を始める時だった。職員室の電話が鳴る。生徒が帰宅している、このタイミング。職員室にいる誰もが、いやな予感を感じざるを得なかった。苦情だ。
「はい。はい。はい」
そう繰り返す教頭。受話器を置くと、
「通報でーす。南側のマンションで、中学生がたばこを吸ってるって」
「はぁ」
ため息が漏れる。1度開いた答案用紙を折りたたみ、席を立つ。だれ1人、文句も言わず、職員室を出る。
いち早く出た友田が、マンションの駐車場で、男子2人を見つけた。3年のケンイチとヒロだった。ケンイチの手には、火のついたタバコがあった。
「こら」
友田が言うと、タバコを地面に捨て、足で火を消した。ヒロはタバコを持っていなかった。この前、アリサとともに、たばこの指導を受けたばかりだ。
ケンイチは、学校に連れて来られ、放送室の小部屋に入れられた。昨年末に、校内喫煙が発覚し、ペナルティとして「個別指導」を5日間受けた。それでも、同じことを繰り返す。担任の杉本が、怒りをぶつける。
「お前なぁ、この前のコベツで『もう懲りた』ってゆうたんちゃうんか」
「うん」
悪びれもせず、ケンイチは足を組む。杉本が、登下校中の喫煙発覚について「3日間の個別指導」と伝えると、ケンイチの表情が一変し、しかめっ面になった。
「どうしたん?納得がいかんのか」
杉本が聞くと、ケンイチは「うん」とだけ、答えた。
「何が、不満なん?」
途中から入った小野寺が尋ねる。すると、ケンイチは声を荒げた。
「アリサが1日で終わったんやろ。なんでなん。なんであいつが1日で、おれが3日もせなあかんの」
小野寺は、これまで通りの、落ち着いた口調で説明する。
「アリサは、タバコのケースを持っていただけやろ。しかも中身は入っていない。それでも、あかんということで、1日個別指導をした。お前は、タバコを吸っているのを、友田先生に見られて、お前も認めている。状況がまったくちがう」
ケンイチは反論する。
「でも、前に杉本先生に聞いたら、『タバコのケースを持っているだけで、3日』と聞いた」
杉本は
「そんなやりとりをした覚えはない」
ときっぱり否定した。
小野寺は言う。
「これまで、タバコのケースを持っていて、3日間の個別指導をしたことはある。それは中身が入っていたからや。今回は中身が入っていない。空のケースは『ヒロから預かった』と説明している。アリサと比べること自体がおかしい」
「でも、あいつが吸っていたのをおれは見た」
初耳だった。
「そんなんは、今初めて聞いたぞ。ヒロも言ってなかった」
「近くにいた。アリサは吸ってた」
「ヒロは?」
「吸ってへん」
「ただなぁ、生徒の証言だけでは追及しきれへんのや。もし、お前のように、教師が見ていれば、徹底的に追及する。アリサが吸っているのを見たお前にとって、アリサが1日、自分が3日のコベツは納得がいかんのは、重々わかる。けど、確認できた事実をもとにしか、指導できひん。これが現実や」
「もうええから、おかん呼んでや」
ケンイチは、吐き捨てるように言った。
杉本が母親に連絡し、すぐに来校してもらった。小野寺が、母親に事情を説明した。母親のボルテージは、いきなり頂点に達していた。
「わたしもアリサのことは聞いてた。なんで、あの子が吸ってるのに、あの子が1日で、うちの子だけが3日もせなあかんの。こんな卒業式間際で。息子が怒るのも無理ないわ」
少しの期待は、見事に裏切られた。母親のスタンスは、ケンイチのと、まったく一緒だった。
小野寺は、うんざりしながらも、冷静に応じた。
「アリサについては、まわりの証言から問いただしましたが、本人が認めませんでした。教師の目撃では徹底的に追及できるが、生徒、地域住民の証言だけでは、追及しきれない面があります」
母親は、ここぞとばかりに息巻く。
「そんなんおかしいんちゃうの。正直に言ったうちの子が3日で、隠し通したアリサが1日なんて。学校はどうなってんの。卒業式前で、わたしはちゃんと学校行けって言ってんねん。んで、学校はこれか。たばこ1本ぐらいで、しょうもないわ。校長と話さして」
このままでは、らちがあかない。小野寺は、校長に事情を説明し、ケンイチ親子を校長室に通した。
校長は、切り出した。
「ケンイチくんよ。これはなぁ、何日別室とはではないんよ。君が1日の個別指導でタバコをやめられるんだったら、1日でもいいよ。どうや?」
「それは無理」
「無理って、君は15歳だろう。1日どのぐらい吸ってる?」
「1日1箱ぐらい」
「お小遣いは?」
「1か月2500円」
「たばこ買うには足らんやろ。どうしてる?親の財布から盗んでいるのか?」
「それはしてへん」
「たばこを勝手に取ってるとか。お母さん、どうですか」
「カートンで買ってるので、たまにごっそりなくなっていることがありましたけど」
「お母ちゃんも息子がたばこ吸っていること知っているんでしょ。しっかりしてもらわんと、お母ちゃんに別の指導をせなあかんことになる。大人として、ね」
「息子には言ってるんですけど。前よりは減ってきてます」
母親は、さっきとは別人だった。
校長は提案した。
「明日、明後日のテストは2時間ずつしかないけど、しっかり別室で受けて、月曜日をまる1日がんばれ。午後からは校長先生がみる。これで3日間クリアしたことにする。しっかりできるか」
母親はケンイチに向かって、ささやいた。
「それで3日なら、いいんちゃうの」
ケンイチは渋々、了承した。
その夜。いつものように、2歳2か月になる娘をお風呂に入れていた。言葉をどんどん覚え、今は「パパイヤー」が口癖だ。それでも、お風呂だけは、毎日機嫌良く、一緒に入ってくれている。
視界に入った物は、なんでもおもちゃになる。
「これで遊ぶの-」
この日も、風呂おけを頭に乗せ「ぼうし!」と言って、遊び始めた。そこまでは、微笑ましかった。しかし、だ。その風呂おけを振り回し、小野寺の肩に、コツンと当たった。
「痛い」
きつく言うと、娘の動きは止まった。バツの悪そうな表情をしている。
「なんて言うの?」
このごろ「ごめんね」が言えるようになった。迷惑をかけた時は、ちゃんと謝れる人になってほしい。妻も同じ思いだった。
娘は、固まったままだった。
「ごめんねは?」
「・・・」
「言わないの?」
「言わないの」
「言わなあかんやろ!」
娘に初めて、大きな声を上げた。娘はびっくりして、お風呂の中で、腰を抜かしてしまった。すぐに抱き上げたが、湯を少し飲んでしまったのか、むせながら大泣きしている。
「わー」
その声を聞きつけた妻が、のぞく。
「大丈夫?」
「うん。『ごめんね』が言えなかったから」
「さきちゃん。『ごめんね』言えてたでしょう」
「ごぅ、めん、ね」
嗚咽しながら、なんとか言えた。
「よし。言えたな」
お風呂の中で、娘をぎゅっと抱きしめた。その瞬間だった。小野寺の脳裏には、昼間のできごとがよぎった。ケンイチと母親の姿が、よみがえった。
「あかんことしたら、『ごめんね』やな」
「ごぅ、めん、ね」
小野寺は娘に言ったが、もっと伝えたかったのは、ケンイチの親子だった。
個別指導の最終日。放送室の奥にある、指導室。小野寺は、パソコンをたたきながら、黙々と漢字練習を繰り返すケンイチの姿に、少しの希望を感じていた。ケンイチに聞いてみた。
「ケンイチよ。どうや。アリサみたいにうそついて、つきまくって生きていきたいか。それとも、悪いことしたら、正直に言って、反省してやり直せる人間になりたいか」
ケンイチは即座に答えた。
「アリサみたいには、なりたくないわ」
「そうか。おれも、お前にそうはなってほしくない。そうやって生きていくやつには、いつかバチが当たると思う。というか、『バチが当たれ』と思ってるわ。ほんまに」
ケンイチは、いやっと笑う。
「先生、そんなこと言うていいん?」
「アリサには、言うなよ」
「言うわけないやん」
そう言って、ケンイチは、また黙々と漢字を書き始めた。
3 信じる、ということ
冷え切った校長室。午後9時を回っていた。彼女の右足は、小刻みに揺れ続けている。貧乏ゆすりだ。
「だから、謝ってってゆってんねん。お前のせいで、コベツになんねんで」
3年のレナコは怒りをぶつける。矛先は、1年の教師、山室だ。
「だから、わたしはあなたがこうやってプハーって白い煙を吹き出したのを見たの。それを『お前のせいで』、って言われても・・・」
生活指導の全体をとりまとめる坂下が諭すように、続けた。
「けどなぁ、先生が見てないもんを見たとはいわんで。卒業式の間際になって、お前をおとしめようなんて、だれも思ってないしな」
「でも、こいつはうそゆうてんねんで!」
珍しい。いつもは感情をあまり表に出さないレナコが、声を荒げた。
前日のことだった。早退をするということで、昼前に学校を出たレナコとフミ。2人がたばこを持ちながら、歩いているところを、校門の近くにいた山室が見つけたのだ。
「たばこ吸ってる!」
山室はそう叫んだが、2人は走って逃げ、どちらかの「吸ってへんわ-」という声だけが聞こえたという。
そして今日。小野寺は5時間目、レナコから事情を聞いた。レナコの担任を務める崎山は、小野寺にこう引きついだ。
「おれとは話したくないらしいわ」
小野寺は。冷え切った指導室に入った。レナコはソファの上にあぐらをかいて、両手で顔を覆っていた。
小野寺は、いきなり本を取り出した。「新聞で学力を伸ばそう」(佐藤孝著)をおもむろに読み始めた。その間、レナコの姿勢は変わらなかった。しばらくして、口を開いた。
「なんか、言いたいことあるか」
小野寺は1年の時、レナコの担任をした。そのころは、まだ前向きな姿勢を持っていた。授業で手をあげることもあった。しかし、2年の時、身内に不幸があってから、そのような姿は一切見られなくなった。休む日も、急激に増えた。まるで、がけから転落するようだった。それでも、小野寺は、レナコと、少しは話ができる関係を保っている。
レナコは首を横に振った。
「ムダや。どうせ、聞いてくれへんねやろ」
「話したくないんやったら、ええわ。その代わり、おれが話したいこと。話させてや」
小野寺は、ふさぎこんだままのレナコに語りかける。
「これまで何回も、たばこの指導をしてきた。お前が吸ったかどうかは、知らん、おれは見てないからな。でもな。これから、うそを突き通して生きていく人間になるのか。それとも、正直に話をして、反省できる人間になるのか。お前は大きな分かれ道に立ってる。今、すぐに分かれ、とは言わん。ゆうてもまだ、中学生や。でも、何年後か先に、『あぁ、あんとき間違えたなぁ』とか『あぁ、正直に言っておいて良かったなぁ』って振り返ってくれたらいい。教師っていう仕事は、すぐに答えが出るような仕事じゃないからな」
いつからか、レナコは顔を上げて、小野寺の目をじっと見つめていた。
「あぁ、すっきりした。言いたいこと全部言えたわ」
小野寺の頭の中には、「正直な人間になりたい」と言って、必死に勉強する姿を見せたケンイチ。うそを突き通したアリサ。2人の姿が浮かんでいた。レナコはどちらの道を選ぶのだろうか。残りあと数日で卒業だ。でも、最後に見せてほしい。うそでもいいから、正直な道を選ぶ。そう言ってほしい。
そんな気持ちを持ちながら、最後に聞いた。
「1回しか、聞かん。ほんまはどうやったんや」
レナコは視線をはずさず、言った。「ほんまのこと言うとな。フミは吸っててん。でも、私はほんまに吸ってない」
「ほう」
「その話は、フミと、ママも電話でしてる」
「ママって、レナコの?」
「うん」
ここまで、話をして、じっとこちらを向いて、うそをつけるとは思えない。しかも、友人の喫煙を『チクッた』ことになる。レナコとフミの力関係はない。とすると、山室先生の見間違いという可能性も、ゼロではなくなってきた。
「信じるわ。このことは聞いてなかったことにするわ」
小野寺はそう言って、指導室を出た。
その夜。レナコは母親と学校を訪れ、校長室にいた。貧乏ゆすりは、まだ止まらない。
母親が口を開いた。
「レナコ、ちゃんと聞いてや。わたしはあんたを信じている。あんたが、そこまで言うんやったら、吸ってないと思うわ。でもな、学校の先生は『見た』と言ってる。はっきり言ってグレーゾーンや。どうしようもない。問題は、あんたがこれからどうするかや。悔しかったら、完璧に『コベツ』をクリアしたら、ええやん。3日間やりきって、意地を見せんかい。ほんで、わたしは吸ってないって、言い切ったらいいんや。なぁ」
レナコは母親の顔をじっと見つめたまま、聞き続ける。
「先生方も、こんなに遅くまで付き合っていただいて、ありがとうございました。この子がどう感じているかは、わかりませんが、さっきよりは落ちついていると思います。貧乏ゆすりも、なくなってますんで。あとは、本人に考えさせます。ほな、行くで」
母親はすっと、立ち上がり、レナコを連れて、校長室を出た。教師陣は頭を下げるしか、なかった。
校舎を出ると、真っ暗だった。敷地内に、街灯はない。小野寺は、帰ろうとする母親を呼び止めた。
「お母さん、ありがとうございました」
「いえいえ、とんでもないです」
「あそこまで、学校の立場を理解していただくなんて」
「これまで、さんざんご迷惑をかけてきたんで。レナコも、小野寺先生は、話を聞いてくれた。『信じる』って言ってくれたって」
「言ったんですけどね。ぼくも学校の人間なんでねぇ」
「わかりますよ」
「成人式ぐらいに、もう1回聞きますわ。5年後ですね。ほんまはどうやったん?って。真相はそんときでいいです。そうお伝えください」
「先生。それ、本人に言ってやってくださいよ」
そう言われ、小野寺は校門を出ようとしていた、レナコを呼び止めた。
「おれがどこの学校にいるか、突き止めて、ほんまのこと言ったら、焼肉おごったるわ」
「ほんまにぃ」
レナコの目に月明かりが反射し、きれいに輝いて見えた。卒業、おめでとう。5年後の再会を楽しみにしているよ。
レナコは、3日間の個別指導をなんとかクリアし、卒業式に出席した。フミは結局、クリアできず、卒業式には出席できなかった。
フミは個別指導の初日、「病院に行く」と言って、早退した。それっきり、学校には顔を見せなくなった。
4 因果応報
職員室の朝は、いつも慌ただしい。電話が連続して鳴る。欠席の連絡だ。冬場は、インフルエンザが流行し、電話の鳴る回数は増える。この日も例外ではなかった。その中で、電話を受けた石本の応対に、まわりは違和感を覚えた。
「火事?やけど?ケロイド?」
いつもは、冷静な石本の声が震えているように聞こえた。受話器を置き、言葉少なに報告した。
「リョウコが火事で、大やけど。入院しているらしい」
リョウコは、3年生の女子では、最も指導に従わない、非行傾向の生徒の「トップ」だ。2年の途中から、ほかの学校の生徒とつるみ出し、ほぼ登校していない。3年になってからは、気に入らない同級生を公園に呼び出し、暴行。傷害容疑で逮捕されたが、少年審判では「保護観察処分」となった。教師の間では「あんなやつを野放しにしたら、何が起こるかわからん。裁判官はわかってへんな」と、司法に対する不満の声も聞かれた。
そして、今回の事件。詳細の情報が入ってくると、あまりのおぞましい光景に、寒気がした。中高生5人ほどが、マンションの一室にこもり、ガスの缶を吸っていたというのだ。しかも、その横で、タバコを吸い始めたことから、爆発。キョウコはその中でも、重症だという。
そのキョウコと、最も仲が良かったのが、フミだった。どういうルートで情報が入ったのか分からないが、おそらく、キョウコの見舞いに行くのだろう。
その夕方。石本もキョウコの見舞いに行き、学校に戻ってきた。いつになく、青ざめた表情だった。
「もう、あかんわ」
やけどの度合いでいけば最悪の「3」に近い状態。髪の毛を全部剃り、顔、腕、足に大やけどを負い、目を開けることすら、できなかったらしい。「キョウコ!」と耳の近くで叫んでも、「う」としか、反応がない。そんな状態だった。
その日の夕刊の社会面には、そのマンション火災がでかでかと掲載されていた。火災発生から30分後の写真が載っていた。窓の奥には、大きな火が上がっていた。あの中に、キョウコはいたのか。小野寺は想像し、ゾッとした。
5 自暴自棄
卒業式の3日前。雨が上がり、湿気が残っているせいか、空気がもやっとしている。
「先生の胸の内に、しまっといてもらえませんかねぇ」
ケンイチの母親は、しかめっ面で猫なで声を出した。小野寺は、即答した。
「それはできません。その場に居合わせた教師に、話をしましたので」
「はぁ」
母親は、深いため息をしたまま、だまりこんだ。
「通報でーす」
いつもの、教頭の声が、職員室に響く。「うちの学年じゃなければ、いいのに」
だれもがそう思いながら、職員室を出る。1時間目。1、2年生は通常の授業だが、3年生は卒業式前のため、午前中だけの授業予定だ。
小野寺は自転車に乗り、通報のあった近くの神社に向かった。「中学生が制服を着て、たむろしている」という通報内容だった。まだ登校していない生徒の顔が浮かぶ。「できればほかの学年で」という思いだった。
赤い鳥居の近くに自転車を止める。境内に男子2人、女子1人の姿。うち1人の男子が、タバコを持っているのが見えた。小野寺の姿に気づいたのか、とっさに後ろ向きとなり、ポイっとタバコを捨てたが、あとの祭りだ。
「見たぞ。おれは見たからな。あとからごちゃごちゃ言ってもあかんぞっ」
小野寺は、境内に届く声で叫んだ。これまで、さんざん認めずに、ごねられたケースがある。それだけは、避けたかった。
振り向いたのは、ケンイチだった。
まさか。つい先日、喫煙による個別指導をやっと終え、卒業式の練習にも参加していたのに。自分の目を疑った。
ケンイチは、バツの悪そうな表情を見せた。
もう1人の男子は、ヒロだった。甲子園常連の私立高校にすでに進学を決めている。最近、距離を縮めているミサと一緒だった。念のため、この2人の持ち物検査もした。
「おれたちは大丈夫だから」
ひょうひょうと話すヒロ。小野寺が一喝した。
「止めたらんかい」
ヒロは自分が「無実」であることから、余裕綽々だ。そこに、担任の城山が駆けつけた。
「ヒロ、何してんねん!」
ほかの教師も続々と駆けつけた。2人を任せ、小野寺は自転車を押して、ケンイチと学校に向かった。
「ほんま、わからんわ」
小野寺は、ケンイチをにらみつける。ケンイチは、にやりとする。
「1年のときは、サッカー部で面倒見て、2年の途中でやめて、最後はタバコの指導か・・・。お前、卒業式、3日後やねんぞ」
信号待ちをしながら、ケンイチの方を見ずに話を続ける。
「まぁ、反省する気持ちは持っとかなあかんけど、こればっかりはおれ1人の気持ちでは決められん。コベツを3日間やってたら、卒業式、終わってまうからな」
「出られへんのかなぁ」
「おれの個人的な意見は、出してやりたいよ。でも、この前は校長先生にまで話をしてもらって、コベツにも入ってもらってやで。で、これか。やめられへんのか?」
「いやでも、減らしてんねんで」
「でも、外で吸わんでもいいやろ」
都合が悪くなると、ケンイチはにやりとする。
信号を渡ると、ちょうどケンイチのマンションの前だった。
「お母さん、いてはるか」
「おると思う」
「寄ろか」
「うん」
すたすたと階段を上がるケンイチの後ろをついていく。かぎのかかっていない玄関のドアを開け、部屋に入る。中で、かばんをポーンと放り投げた。
なにやら会話をしているが、幹線道路沿いのため、聞きづらい。しばらくして、母親がグレーのスウェット姿で、現れた。そして、いきなり放った言葉が、「胸の内にしまっておいてくれ」だった。まぁ、想定内だ。最悪の事態として考えていた「逆ギレ」だけは、免れそうだ。
「じゃあ、この子は卒業できない、ということですか」
「卒業はできます。しかし、卒業式に出られない可能性が出てきました」
「はぁ。あんた、何してんのよう」
「もう、2部でも3部でもいいわ」
全体で行う卒業式とは別に、不登校の生徒を対象とした第2部、第3部でもいいというのだ。
小野寺は言った。
「でもそれは、こっちがやり切れんよ。せっかく先週もしっかり練習に参加して、あと少しというところで・・・」
母親は、ブスっとした顔のままだ。
「お母さん。毎度ですけど、また学校に来てもらわないといけません。いつもいつもで、申し訳ありませんが」
「ちょっと体調も悪いんでねぇ。行けませんわ」
本当かどうかは、分からない。でも、そういわれたら、それまでだ。
「では、学校での今後の指導を、担任から電話で連絡します。『卒業式に出席できない』という最悪の事態も、覚悟しておいてください」
「はぁ」
声は小さかったが、かろうじて学校側のの結論を受け入れてもらう意志だけは確認した。まぁ、こんなことがひっくり返ることは、珍しいことではないが。
意見は割れた。きびしい立場は、石本だ。「そんなやつ、卒業式に出す必要ないやろ」
ごもっともな話だ。再三の指導に従っていない。チャンスは何回もあったはずだ。
小野寺は、校長の意見を聞いた。
「というわけなんです」
事情を説明すると、校長は言った。
「卒業式は出してやったら。火、水、木曜の3日間で、金曜日の本番。どうや?」
「学年で検討します」
その意見を、石本に報告したら。眉間にしわを寄せるだけで、ノーコメントだった。担任の杉本にも聞いてみた。
「担任としての意向はどうなん?」
「担任としては出してやりたいですけど、まわりの子らへの影響を考えるときびしいですよねぇ」
小野寺は、煮え切らない杉本の返答に、もどかしさを感じた。
「んで、意向は?」
「出してやりたいんですけどねぇ。きびしいですよねぇ」
「結論を聞かせてや」
「きびしいですよねぇ」
小野寺は、それ以上は突っ込まなかった。小野寺はこの3月で、転勤が決まっている。生活指導の後任は、杉本だ。責任を負う立場の人間は、決断をしなければならない。4月から、杉本にそれができるか、一抹の不安を覚えた。
ケンイチを指導室に入れ、小野寺は自分のクラスに入った。2時間目は英語と数学のプリント学習だった。静まりかえった2階の教室に、小野寺はパソコンを持ち込み、早速、ケンイチの報告書を作っていた。その時だった。ノックの音が聞こえた。
副担任の藤堂だった。
「ケンイチが、下で暴れています」
一瞬、耳を疑った。神社から学校に帰ってくるときには、穏やかな表情さえ見せていたケンイチが、暴れている?
1階にかけ降りる。すると、指導室から、逃げようとするケンイチの姿が見えた。ケンイチは、校門を飛び越えて、全速力で走り出した。
「待て」
担任の杉本が、追いかける。杉本はプロ野球の入団テストを受けるほどの運動能力を持ち主。しかし2年前、体育の授業中に、ひざの靱帯を傷め、3か月間、休職を余儀なくされた。杉本は、そのけがをかばうことなく、全力でケンイチを追った。
小野寺が校門を開けると、遠くのほうで、190センチ超の巨体が、ケンイチを取り押さえているのが、見えた。ケンイチは杉本の腕を振り払い、再び、逃げ始めた。
やっと、小野寺が追いついた時には、ケンイチは走るのをやめ、自宅の方向に歩いていた。小野寺は、ケンイチの横についた。
「さっきも言ったけどな。おれは出させてやりたい。でも、学校の判断がどうなるかはわからん。それはわかってるな」
反応はない。
「お前はどうしたいんや」
「もう、どうでもいい」
「卒業式は?」
「もういい」
「お前がその気持ちなら、いい。その代わり、ほかのやつの邪魔だけはするな」
「うん」
ケンイチは、表情を変えなかった。さっきとは、別人だった。
ケンイチの後ろ姿。小野寺と杉本は、それを見送り、学校に戻った。
「まぁ、しゃあないやろ。本人があれなら」
小野寺は言った。杉本は、いつになく硬い表情だった。担任として、ケンイチを卒業式に出させたかった。杉本の目は、そんな思いにあふれているように見えた。
卒業式まで、あと3日。無事、迎えられるのだろうか。小野寺はとてつもなく、3日間が長く感じられた。
6 不安
明日が卒業式。最後の練習。200人全員が体育館に集まり、ひな壇を組んだ舞台に上がる。本番で歌う、「仰げば尊し」を練習していた。
「まだまだ、出るよー」
石本の威勢のいい声が体育館に響く。それに乗せられ、全体のボリュームがぐんと大きくなる。
「いまーこそー、わかーれめー」
アリサは、歌っているかどうかもわからないぐらい、口が動いていない。
レナコは、最初は「しんどい」と訴え、舞台に上がっていなかったが、途中から参加した。マスクをしているため、歌っているかどうかは、わからない。
カズヤは大きな口を開けて、歌っている。校内で行方不明になって以来、前向きに学校生活を送れたのだろう。表情にあらわれている。ヒロも、口こそ開いていなかったが、歌おうとする姿は、見られた。
ケンイチの姿は、舞台にはなかった。
フミも来ていない。キョウコの看病をしているようだ。校長がお見舞いに行った時、出くわしたそうだ。「卒業式に出なくてええんか」と聞くと、「もう出られへんねん」と笑って答えたという。キョウコの母親は「とても助かってますわ」と言って、娘をフミに任せて、夜の仕事に出かけたらしい。
7 感謝
卒業式の当日は、雨だった。第1部は、大きなトラブルもなく終わった。
毎年、舞台の上で行われる「悪しき慣習」があった。卒業証書を受け取ったあと、さんざん指導に従わなかった連中が「お世話になりました。ありがとうございました」と言って、パフォーマンスをするのだ。今年はなかった。それだけが、救いだった。
午後からは、不登校の生徒を対象とした第2部。小野寺は、それにも出られなかった不登校の生徒の自宅を訪問していた。
セイコの家の前に来た。彼女は2年の1学期から、1度も登校していない。小野寺は担任になってから、1度も顔を見たことがなかった。通信制の高校への進学が決まっている。
「今日も会えないだろう」
そう、たかをくくっていた。チャイムを押す。母親が出てきた。
「最後の最後まで、お手数かけました。すみません」
深々と頭を下げる母親に、小野寺は言った。
「いえ。こちらこそ、何の力にもなれませんでした。謝るのは、こっちのほうです」
大きなバインダーに挟んだ卒業証書を、手渡した。すると、母親は、玄関の奥にある階段のほうを向いて、声をかけた。
「セイコ、降りてらっしゃい。先生来てくれてるわよ」
すると、2階から降りてくる人影が見えた。スウェット姿の彼女は、笑顔だった。予想していなかった。
「おう。久しぶりやな。元気そうで」
セイコは穏やかな笑顔のままだ。会うのは、ほぼ2年ぶり。担任としては、初めてだった。
「卒業証書を持ってきてくれたのよ。お礼を言いなさい」
母親にそう言われ、セイコは軽く会釈をした。
「びっくりしました。いい顔色してて」
「やっと最近良くなってきたんですよ。ここまで時間がかかりました」
母親の顔も、これまでにない清々しい表情だった。
セイコの家から、学校に戻った。これで、やっと一段落。今年は、早く家に帰れるかも知れない。と、淡い期待をする間もなく、電話が鳴った。
「通報でーす」
最後の最後まで、この声を聞かなければならないのか。もう1度気持ちを奮い立たせて、重い腰を上げた。
河川敷の橋の下に、刺繍の入った学ランを着ている生徒が多数集まっている、という通報内容だった。どこの中学生かは、分からない。ただ、校区内のため、うちの生徒の可能性が高い。
車に乗り込み、現場に向かった。橋の下にいるのは、やはり、うちの男子生徒だった。30人ほどが、何をするわけでもなく、談笑していた。
ヒロは、紫の刺繍ラン。小野寺が担任したマサトは赤。ほかにも、白、黒、ピンクと色とりどりだった。そこに他校生だろう。見知らぬ女子生徒が、取り囲んでいる。
刺繍ランを着ていない生徒もいた。ケンイチは黒のジャケットをまとっていた。いち早く、小野寺のところに寄ってきた。
「おれの返事、良かったやろ」
ケンイチは結局、「どうでもいい」とやけくそになった日の翌日、「反省したい」と朝から登校し、個別指導を2日間、やり遂げた。式への出席は、校長が特別に認めた。
小野寺はハッとした。出席が決まったあと、ケンイチに話した内容を、思い出した。
「担任の杉本先生は止めてくれたわな。おれが担任やったら止めへんぞ。去る者は追わん。でも、杉本先生は追ってくれた。お前がその気持ちに応えるのは、卒業式での返事しかない。楽しみにしているわ」
そう声をかけたのを、すっかり忘れていた。正確にいえば、卒業証書を受け取り、席に戻ってきたケンイチを見て、思い出した。
実は、ケンイチが舞台に上がっている最中、隣の生徒にコソコソ話しかけているマサトの姿が、視界に入った。小野寺は、マサトをにらみつけた。少しの間があって、マサトはおとなしくなった。その間に、ケンイチの返事は済んでしまっていたのだ。
「ごめんな」
小野寺は、正直に話した。
「でも、席に戻ったときの顔がすっきりしてたから、安心したわ」
そう言うと、ケンイチは「やろ」と、いつもの屈託のない笑顔を見せた。
そうだ。こんなところで、話している場合ではない。早く帰りたい。帰るには、この集まりを解散させなければ、ならない。
小野寺は、マサトを呼んだ。
「暗くなって寒くなってきてるから、解散せえよ。カラオケでも行ったら」
「えーわ。こんな格好でカラオケ行ったら、恥ずかしいやん」
それなら着るなよ。と小野寺は思ったが、口には出さなかった。迷惑をかけないよう伝え、教師陣はその場を離れようとした。その時だった。
「アリサや」
黒い刺繍ラン姿のアリサが、土手の階段を降りてくるのが見えた。同じような風貌の女子2人を引き連れているが、顔は見たことがない。アリサは同じ学校の男子とつるむわけでもなく、現物に来ている他校生の女子と話し始めた。
小野寺は、アリサに視線を送った。アリサはスッと、友達の影に隠れた。小野寺は、アリサのそばに近寄っていった。
「派手な格好してぇ。高校の先生が心配してたぞ。迷惑かけんようにな」
アリサの進学先は、正確にいうと「高等専修学校」といって、高校の卒業資格がとれる学校だ。実際に、その学校の教師がやって来て、アリサの情報収集をしていった。もちろん、うわさレベルの話をすることは、なかったが。
アリサの表情は、マスクに隠れて見えなかった。その時だった。
「ありがとうございました」
アリサが、ペコリと頭を下げた。想定外だった。彼女から、そんな言葉を聞くとは。小野寺は内心、たじろいだ。表情には出さないように、取り繕う。
「まぁ、がんばりや」
そういって、きびすを返した。
いつも、無表情で感情をおもてに出さなかったアリサ。最後に口にした、感謝の言葉。
小野寺はふと、思い出した。彼女が入学してきたころの姿を。素直に話ができる、人なつっこい性格だった。ただ、話題といえば、先輩のことばかりだった。
いつからだろう。表情に影がかかったのは。彼女には、タバコのみならず、盗み、クスリの噂が絶えない。その裏には、彼女なりの大きなストレスが、あったのだろう。
ヒロといたときのタバコの話。真実はどうだったのだろうか。
今、振り向けば、聞くことができる。でも、もうよそう。確かめる必要はない。すべては終わったのだから。
小野寺は学校に戻り、急いで帰宅した。
後日。卒業式に関する「評価」の情報が流れてきた。
「あんなだらしない卒業式は、ここ最近ではめずらしいな」
そう酷評したのは、来賓として出席した前校長の橋渡だった。男子の髪が長くだらしなかった、とのことだった。
小野寺は、舞台の上でのパフォーマンスがなかったことに、一定の達成感を覚えていた。それだけに、少しショックだった。確かに、髪型の指導まで、行き届いていなかったのは、事実だ。
小野寺は、崎山に報告した。予想通りの答えだった。
「気にするな」
その言葉を聞いて、小野寺は、またがんばろう、と思った。
卒業 ~続 真実はどこに~


