
スペースソルジャーズ〈7〉
原案 田頭満春
兵器考証協力 岡村智教
ページの途中に複雑な科学式が展開されるようなハードSFではありません。そもそもそんなもの書けません。スペースオペラです。大宇宙を駆け回る宇宙船と、武器を手に走り回るヒーローヒロインが、己の肉体のみを頼りに活躍する、純然たるスペオペです。
『スターウルフ』シリーズや、『ノースウェスト・スミス』シリーズなどを思い浮かべて頂ければわかりやすいかも知れません。
宇宙船や超兵器も登場しますが、あくまで主役は人間です。笑い、泣き、怒り、叫ぶ主人公たちの活躍を読んで頂けたらと思っています。ジャンルはSF冒険アクション、ですが、もう1つ付け加えることが許されるなら、「青春」小説にもなり得ているという自負もあります。
故・野田昌宏氏にこの作品を読んで頂きたかったと、心から思っています。
魔王への挑戦 その4
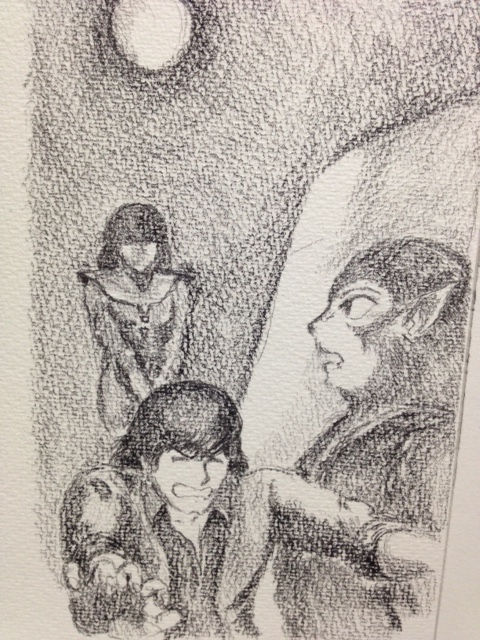
(4)
ブレイザークロス第1惑星にして主星であるラドン。その首都タキアスが夜を迎えようとしていた。
3つある月――衛星の軌道、探査網とレーダーの死角に当たる宙域で、隕石塊を装ったスプリッツァとレスサットⅣとが停止した。ジンリッキー、グレイハウンド、ライトニング装甲車が、情報に基づきコイケが弾き出した経路に添ってタキアスに降下を開始する。
周辺電磁波微弱。惑星自体の液体核が小さいからだと思われた。地震なども少ないらしい。厚く綺麗なオゾン層を越えると、タキアス郊外に出た。2機と1台はエンジン消音装置を作動させた。
夜の首都の広いこと。半径3000キロにも及ぶその広大な面積は、一瞬この星の全表面が都市であるかのような錯覚さえもたらす。そして真夜中である筈なのに、その明るさ。惑星表面や都市建造物の色が全て白っぽい上に、3つの月に照らされているからだ。
「…こりゃあ、相当低空を飛ばねえと、見つかっちまうんじゃねえか?」ライトニング操縦席を見下ろすクエンサーが呟いた。
「経路を外れたが最後、探査網に引っ掛かる」ナビシートのルストが首を振った。「今だってコースの外はビームの網だ。ただでさえ周りに電磁波が少ないんだ。引っ掛かると誤魔化しようがない」
「心配するな。眼下には人っ子1人いない」とマルカム。「しかし外出禁止令が徹底されてるとは言え、クルマの1台も通らないとはな」
ルストが頷いた。「チューブカーも通ってない」
「それに、緑も少ないな。いや、ないと言ってもいい」
ルスト、それにクエンサーも頷いた。広大な都市がどことなく冷たいものに見えるのは、壁の色のためばかりではなさそうだ。ジンリッキーからマキタが言った。“酸素は27パーセントある。”
「こんな不毛とも言える大地でか。海だって狭いぞこの星は」
“作ってるんじゃないか?”
「酸素をかよ」
2機と1台は、ソールと打ち合わせてあった郊外の合流地点に近づいていた。
白い砂漠にも見える、広い空き地である。
1本の道、通る車の1台もなく、だだっ広い荒野に動くものの気配1つ感じられなかった。3つの――もうすぐ2つになろうとしていたが――月の光に白く浮かび上がる地面はあちこちに土の地肌を剥き出してはいたが、草の芽すら吹いていなかった。いかなる自然物・人工物も動かなかった。動こうとしなかった。
“動物? ああ、この辺じゃ見ないみたいね。でも、いるって話よ。”
マキタに訊かれ、縁起でもないは言った。ラドンには数千種に及ぶ動植物がきちんと生息している。但しそれらは全て、政府の管理下にある。開拓時代の濫獲に教訓を得ての措置らしい。稀少種だろうが食用だろうが、はたまた害虫だろうが、ラドンの各地に置かれた環境管理センターという建物で飼育されていると言う。それを指導・徹底したのは誰あろう、閉鎖星系総統、ブレハム・グランザーその人なのだそうだ。
“何だか調子狂うよなあ。”とマキタ。“グランザーってのは民を虐げる悪逆非道の帝王ってのをイメージしてたんだが。”
“尊敬されてるわよ。”エレナは素っ気なく言った。“あたしたち以外からは、ね。”
「しかしホントに、この静けさは何だ?」ルストが呟いた。「人口4000万の都だろう…」
クエンサーが鼻を鳴らす。「まさかこれも罠、ってか?」
「止めろ縁起でもない。ソールが既に捕まってるとでも…」
「これまでの経緯と敵さんのやり口を考えてみろよ。今この地面の下から数千人の兵士がうわーっと現れても、俺は驚かねえぞ」
「着陸するぜ」モートレイの合図に、全員が思わず首を竦め…。
2機と1台はそのまま着陸した。
センサーで大気の安全と、周囲の無人とを確認し、まずマキタがジンリッキーの操縦席より飛び降りた。同時にカラバがライトニングから降りる。彼の五感にも異常は感じられないらしい。
2人のオーケイの合図に、ルストたちもライトニングから降りてきた。ジャスとベーリックがその車体に、探査波遮断シートを掛けた。ライトニングにもステルス機能はついているのだが、カモフラージュ徹底のためだ。表面が感応色素繊維で編まれたシートはたちまち、白っぽい地面の色と同化する。
人工惑星ギーンにて、キャメロン・ボウイの店から仕入れたシートである。
こちらに向けられる探査波がないことをモートレイが確認後、ルストの合図で、降り立った全員が武器を携え、待機の姿勢を取った。
マキタは大きく息をついた。僅かに粉っぽいが、海の香りにも似た金属臭を含む大気を胸一杯に吸い込む。地面が足裏を吸いつける感触が筋肉に心地いい。久しぶりに本物の地面に立ったせいだろう。いかに宇宙が最高とは言え、人間それだけでは生きていけないということか。
その横に、マルカムが立った。「お前の言う通り、調子が狂うぜ」
マルカムはマキタより遥かにヴェテランの傭兵だ。銃弾飛び交う激戦地にも、腐敗し切った傀儡政権の牛耳る荒れ果てた首都にも、幾度となく降り立った。
そのマルカムが感じていた。ここはそれらのどれとも違う、と。危険でもなければ荒れ果ててもいない。開放機構基地での戦闘、自分たちを追い回した数十隻の戦闘艦の記憶はまだ生々しいと言うのに、それとはまるで無関係にも見える平穏、無事、静謐…。
「街も随分、綺麗に見える」マルカムは遠目に見えるタキアスを顎で指した。「月の光のせいだけとは思えん」
マキタは小さく頷いた。綺麗なだけではない。緑がない分、冷たい感じは与えるが、街も星も豊かにさえ見えた。これが噂に次ぐ噂を聞き続け、畏れ半ばでやってきたあの閉鎖星系の首都なのか。開放機構をあんな手段で壊滅に追い込んだ保安省の潜む場所なのか。
これじゃあ…、マルカムがエレナを気にして、小声で言った。「俺たちの方が悪人だぜ」
「平和な星の治安を混乱させにきた、か?」マキタも小声で笑った。
ルストが手を挙げた。時間が来た。
マルカム、マキタたちは思い思いの姿勢で待機を続けながら、周囲に注意を配っていた。ライトニング装甲車内ではモートレイとクエンサーがレーダーと探査波センサーを睨んでいた。エレナはいつでもグレイハウンドを飛び立たせられる態勢にあった。いざ上空から敵が来た際には、最も頼りになるのはエレナだと傭われ軍団の皆も認めているからだ。しかし皆の視線は、ついついカラバに注がれる。視力、聴覚ともにライトニングのセンサーさえ凌ぐ彼だ。しかも臭いと気配という、レーダーでも捕捉不可能なものまで捕まえる。変化が起これば必ずキャッチしてくれるという信頼があった。
だが…、
カラバが気づいた時には、そいつは既に、シートに覆われたライトニングの横に立っていた。
もちろん他の面々が気づくのはもっと遅れた。体毛を膨らませたカラバが警戒の唸りを上げた瞬間、マキタはハンディキャノンを引き抜いていた。身を翻し、倒れ込むまでのコンマ3秒の間に、ようやく目がそいつの姿を捉えた。
月の1つを背にしたそいつは、背の高い女だった。
肩まである髪が、微かな風に揺れた。肉づきの良いその胸とマキタの目との間にハンディキャノンの照準が割り込んだその時、
女は言った。
「待てよ」意外なダミ声だった。「俺だ」
第1印象の与える影響は大きい。その『俺』が知った声、聞き慣れた声であったにも関わらず、識別には彼らにしては大層な時間を食った。カラバなどは嗅覚が味方したのが却って徒となり、視覚とのギャップに大混乱を起こしかけていた。
「遅かったじゃないかよ」
そいつは言った。ハンディキャノンを構えたまま立ち上がったマキタの目に、もう1つの月が照らしたそいつの全身が見えた。薄茶色の髪、ふくよかな体つき、人目を惹くというわけでもないが、魅力的と呼べなくもない容貌。
その口から発せられるダミ声さえ聞かなければ。
「全滅したかと心配してたぜ」月光の下、その表情が情けなく歪んだように見えた。「昔馴染みのソールさんを放ったらかしにして、な」
マキタたちは声もなく、変わり果てたソールの姿を見つめた…。
細胞変化による変身能力、催眠による幻覚効果、アーカム・ソールはそのどちらも使わない。そもそもそんな能力など彼にはないからだ。ラテックスとビニルレザー混合液による原始的な変装が、技術さえ傑出していれば今でも通用するということを、ソールは証明している。肌の荒れや汗の臭いまで真似られるか、或いは近いものを錯覚させられるくらいに、彼の技術は飛び抜けているのだ。
顔を覆うだけである筈のマスクが、表情を作るかに見えるのだ。眉間の皺、頬の引き攣りまでも。彼の演技力と絶妙の呼吸とが、そう見せてしまうのである。連邦軍の将軍に化けて、バレないわけである。
「いやん」突如、マキタを見つめ返すその目に含羞みが宿り、艶っぽい細声が漏れた。マスクの顔が赤く染まったかに思えた。「あまり見つめないで」
マキタの全身に鳥肌が立った。
ソールはニヤリと笑って見せる。「堂に入ったもんだろう」
「入り過ぎだ」マキタは後退りながら言った。「お前、そういう趣味の持ち主だったのか」
「馬鹿言っちゃいけないわ」
「ええい、寄るな」
変装を解かないままのソールを乗せ、2機と1台は再び音もなく、夜の闇に舞い上がった。
首都上空までの移動の短い間に、ここに辿り着くまでの経緯をルストが簡単に要約し、開放機構の生き残りたちを紹介した。ソールは頷いた。
「開放機構壊滅の騒ぎは知ってた。情報は豊富に入ってきてたんでね」外見とそぐわぬダミ声が、ジャスたちを震え上がらせる。
銀河で最も高価なブラニガン&ハーディ社製の狙撃銃をチェックしながら、クエンサーが訊いた。「情報が豊富? おめえ、一体何に化けたんだ?」
「内務省のオペレーター」
「おい、待てよ。俺たちが今から向かうのは、その内務省職員の宿舎ビルとか言ってなかったか?」マルカムがその碧眼を剥いた。「お前、最初からそれを見越して…」
「まさか。いくら俺でもそこまでの先読みは出来なかったさ」
今度はソールが、潜入から今までの経緯を話す番だった。「とにかく墜落したメルヴィル号の情報を得なきゃならん。そのためには軍か警察機構に潜り込みたかったんだが、流石に軍にはつけ込む隙がなかったよ。誰かに化けるどころか、脱出だけで手一杯だった。で、街に潜んで情報収集した結果、この星での警察機構を内務省と保安省が行使してることがわかった」
だが、保安省には軍以上に近づけなかった…、ソールは呟いた。街で拾う噂のことごとくが、あの役所の恐ろしさを伝えていた。その不吉さは建物の雰囲気にすら現れていた。「陽の下であの建物を見ればわかると思うぜ。背筋にゾワゾワっと…」
「日が昇るまで長居できるかい」クエンサーが鼻を鳴らした。
もう1つの役所、内務省を窺っている時に、ソールは1人の女を見つけた。
彼女に成り代わってみて驚いた。内務省にお目当てのアリーゼ・サロイがいたんだからな。
女に化けて内務省の仕事をこなしているうちに気づいたのだが、ここタキアスは、主要な設備のほとんどを機械任せにしていなかった。女が市街の管制担当員だったことも幸いしたが、内務省内部にいる者誰もが、ほとんどあらゆる施設に近づけるのだ。技術が遅れているというわけではない。現に生活居住区はほぼ全自動化され、市民は皆、快適な生活を送っている。そのチェックに携わる人間が、他の星より格段に多いのだ。「この星では最終的に、機械より人間を信用しているんだ」
無論、街の各システムが全自動化されているということはどこかにそれを制御するどでかいコンピューターがある筈だった。然り。中央管制コンピューターは軍の1部、内務省、保安省が共用していた。機密事項への接触はもちろん不可能だったし、軍や保安省と違って入手できる情報も限られていた。しかし市街を覆う探査網の情報は、何と最高レベルの機密ではなかった。
そして墜落した異星船からの収容者に関しての情報は、もっとオープンだった。
「クロムから受け取っただろうからわかるとは思うが、艦隊だとか、船の等級とか装備とか、防衛関係の情報には手が出せなかった。俺の変装した女は管制コンピューターにアクセスできる立場だったが、それでも駄目だった。まあ、他の誰に化けてても、手に入った情報に大差はなかっただろうな」
「まあ、開放機構からの情報もあるから」と、ルスト。
「特に防衛システムの位置特定なんてのは、ソールからの情報だけじゃ弱かったからな」とマルカム。「開放機構のお陰で、訓練も出来たわけだし」
「ああ、その辺の情報が薄かったのは悪かった。探査網の調査に加えて、もう1つ追われてたもんでな」
「しかしやっぱりおめえ、キモチワルイぜ」と、クエンサー。「なまじ外見がそこそこイケてるだけに、おぞましさも倍だ。化けるなら男にしろよな」
「まあ、男女どちらでも良かったんだけどな。時間もなかったし、それにこの女は、ちょうどいい条件を満たしていたんだ」
「何だよその条件ってのは。カラダか?」
“おい、下で動いてるのは、ありゃ何だ?”
通信機から飛び出したマキタの声が、皆を慌てさせた。街中に入って10キロ、雲1つない空から降り注ぐ月の明かりが建物を白く浮かび上がらせる。その壁が不意に、別の光に照らし上げられた。
10基のサーチライトを光らせた路上車が出現した。人っ子1人いない路上を、這うような速度で進んでいる。
「心配ない。ありゃあ無人清掃車だ」
皆の緊張した顔を見渡し、ソールが肩を竦めた。「対人センサーもついてるけどな。引っ掛かったら即座に内務省パトロールが登場する。場合によってはもっと怖い連中の出現もあり得る」
こちらにセンサーが向く心配はまず、ないがな…、カメラスクリーンを見下ろすソールは頬に掛かった髪を掻き上げた。夜間の一定時間は市民全員外出禁止。人が全くいないのはそのためだ。命令は保安省の管轄、もちろん反対する者はいなかった。
あの暗殺部隊を指揮下に置く保安省の命令だ。徹底されないわけがない…、皆が頷いた。「あの清掃車も元々は内務省のものなんだが、センサーだけは保安省が受け持ってる」
この外出禁止令の中、宿舎を抜け出すのも大変だったんだ…、ソールがボヤき始めた。始まったぞ…、マルカムの目の呟きに、ルストが笑い出しそうになる中、
“条件って?”通信機向こうからエレナがソールを促した。“途中だったでしょ?”
「ああ、そうだった」
…人は誰しも、自分こそが主役であると自惚れるか、或いはそうありたいという願望を抱く。が、大抵の場合、それは願望のまま終わる。皆の自惚れが具現化するようなら、スターを輩出するショウビジネスなど、存在理由すらなくなってしまう。人は人が思う程、他人の挙動になど注意を払っていないものだ。
中には存在にすら注意を払って貰えない者もいる。同窓会パーティに出席していなくとも、気づいて貰えない者である。ソールは呟いた。「俺が私が、ってみんなが出しゃばりたがる時代に、それは一種の美徳にさえ思えるがね」
とにかく、控え目な、おっとりした、穏やかな、儚げな…、等々。そんな在り来りな言葉でしか面影を再現できない、それでいて実はどこにでもいそうな存在が、今回の狙い目であった。
“見つけた相手がちょうど女の人だったわけね?”
「そう。男でもよかったんだが、今回は人選も急拵えだったからな。選ぶ間もなく最初の1人に飛びついた。エレナだっけ、君、鋭いなあ」
風俗、習慣の差異を瞬時に見抜き、見分ける。その瞬間的判断の素早さは訓練の賜物でもあったが、ソールに与えられた天分でもあった。彼によれば全銀河は140余の風俗地図に色分けされ、細部の差こそあれ、当てはまらない区域はないのだそうだ。
もちろんその細部の細かい差が失敗を生むこともある。そんな時、慌てずに、あ、ちょっとボケてた、程度に相手に思わせるのは呼吸1つだと言う。そこで女が普段目立たぬ存在であることが効力を発揮する。
「まあ、この女を通じて、内務省からいろんなデータを頂こうってとこまでは予定通りだった。ところがだ、捕まった他星者を収容する施設が、内務省職員の宿舎の1つにあったと来たじゃないか」
「何だと?」
マルカムがその美しい碧眼を剥き、他の面々も唖然とした顔をソールに向けた。
何でも、捕らえられた外惑星からの侵入者は、抵抗、危険度、その可能性の有無によって収容場所が振り分けられるのだと言う。危険だと見做されれば郊外の収容所か保安省施設に、さして危険がないと見做された場合には、首都内にある各種施設が充てがわれるらしい。
仕事の隙に探査網死角を割り出しつつ、収容者の行方も探っていたソールは、すぐにアリーゼ・サロイの名前を見つけた。
若干の抵抗はしたかも知れないが、危険分子とは見られなかったのだろう。従者も同じだったらしい。各宿舎は内務省パトロール部隊がそれぞれ警備に当たっているが、施設の警備体制やら防衛装置やらは、保安省に比べれば段違いにユルい…。
「偶然にしたって出来過ぎだ…」ルストが首を振った。「神懸かってるよ」
「だろ? 普段からの行いが真っ当だと、こういう幸運も舞い降りてくるってわけだ」
「ほざけ」
保安省と軍とが開放機構制圧の仕上げに乗り出し、首都も騒然とし始めた。収容される侵入者たちももう1度チェックを受け、幾人かが別の宿舎へと移送された。まさに渡りに船。ソールはオペレーターの立場を最大限に利用した。
飛び交う命令に、アリーゼと従者とを、自分の寝泊まりする宿舎に移すという項目を、こっそりと追加したのだ。
ここでソールは突然、声色を変えた。「私が幸運の女神に見えてきたでしょ」
“頼むからその声は止めてくれッ!”
「この場で射殺したくなってきたぜ」
ちなみにボディガードたちは移せなかった。銃を携帯していた彼らは、郊外の収容所に送られたのだ。それでも保安省に送られるよりはマシだと思う。尋問にも、アリーゼのことは一切白状していないらしい。護衛官の鑑だ。
「女か? C102で仮死状態にしてある。大丈夫、殺しちゃいない。コイケにくどい程念を押されたからな。後、半時限もすりゃあ目覚めるだろう。その頃にはとっくにおさらばさ」
“出来たらボディガードたちも引き揚げたいな…。”
「無理だな。その時間はない。まあ、心配は要らないと思うぜ。病気の母親のために、どうしてもジュドー星に帰らなくちゃならない、なんて奴がいない限りは」
どういうことだ、とマルカムが訊こうとした時、ライトニングが停止した。モートレイがもそっと言った。「着いたぜ」
30階建の6角形ビルディングが装甲車の2キロ前方に、もう1つのビルと並ぶ形で立っていた。
「あの、奥の方のビルが、俺の寝泊まりしてる内務省宿舎ビルだ」
全員がソールの指示に従って、屋上を見た。探査波照射も出来る自動追尾サーチライトが3基、地上に向けられていた。今は点灯していない。ライト1基の横に、警備の兵士用駐屯所があった。ズームアップすると、中で人影が動いていた。
まずはあそこを黙らせてくれ、という要請で、クエンサーが狙撃銃を抱えた。「ここからじゃ狙えねえ。もう少し近づけねえかよ」
「無理だな。ここからビルに近づくと、俺たちが死角から外れる」モートレイが盾にしたもう1つのビルを指し、「それにこの明るさだ。ここから前に出れば、駐屯所の中からでも見つかる」
「心配するな」ソールがブレスレットの時計を見た。「纏めておびき出してやる」
クエンサーは狙撃銃を構え、毒づいた。
「アリーゼ・サロイ本人には会えなかった」時計を気にしながら、ソールは言った。「但し、側近の何とかいう奴…」
「アントラン?」
「そうそう。そいつとはコンタクトできた」
ここは監視も緩いため、一定の時間には収容者同士の接触も可能なのだ。軟禁中、アントランも何度かアリーゼと会えたと言う。彼女は無事は無事だが、消耗もしているとのことだった。
「命に関わるような状態でもないらしいが…」髪を掻き上げ、ソールは頷いた。「よし、2分前。準備だクエンサー」
“1匹の蝿の力を見せてやろうじゃないか。”
「何だマキタ、俺たちは蝿か」マルカムが笑う。
“出てくる前にコイケさんが言ったんだ。昨夜私は千匹の蝿を叩き殺した。そして今朝、1匹の蝿に眠りを覚まされた…。”
「成程な、“私”ってのが政府軍、俺たちは蝿の最後の1匹ってわけだ」
「ガクのある奴の話はわからねえ」クエンサーが鼻を鳴らした。「ハッチ開けろ」
「1分前」
ルストが言った。「頼むぞ」
クエンサーは目を逸らし、ボソッと呟いた。
「上手く行くように祈っててくんな」
ライトニングの天井が開き、金属臭を含む猛烈な風が吹き込んできた。ルストが顔を背け、マルカムが目を細める中、クエンサーの座席が上昇し、狙撃銃を抱える彼の上半身だけが車外に出た。
全重量11キロの、ブラニガン&ハーディ社製狙撃銃が強風を浴びて揺れた。エネルギーカートリッジをチェンバーに挿し込み、麻痺ビームモードが選択されていることを確認、コンプ&ブッシュネル社製の巨大な多目的光学スコープのピープサイトを覗き込む。探査波や追尾レーザー照射システムまでついた最新鋭の狙撃用スコープなのだが、逆探知の可能性を考えれば使えない。この時間帯、この明るさで、標的が鮮明さを保つギリギリの倍率が50倍だった。2キロ先、50倍の標的は、銃身がコンマ1ミリずれただけで、視界から姿を消す。
何度も2脚を据え直したクエンサーは、遂に座席に片膝を立て、中腰になった。どうやっておびき出そうって言うんだよ…。
スコープ視界に駐屯所の窓の1つが映っていた。中にいる警備の兵士2人がカップ片手に談笑していた。ソールの話ではあと4人いる筈だ。ビル屋上は意外なくらい狭かった。6人が一斉に出てきたとしても、瞬時に撃ち倒さなければアウトだ。誰か1人が駐屯所に逃げ込み、下に連絡を送ればジ・エンド、なのだ。全員を、2秒以内。クエンサーの額に汗が滲み、冷えながら筋を作った。それが額から目尻に流れ込み、涙と混じって頬に落ちる。畜生め、痛えぜ。
「早く出てきやがれこん畜生…」
と、駐屯所の中で動きがあった。何か連絡が入ったらしい。兵士たちがバラバラと屋上に飛び出してきた。並んでビルの下を見下ろす。6人いる!
クエンサーは1秒半で、1発の無駄撃ちもなく、その6人を撃ち倒した。
特大の溜息とともに、クエンサーの両足が座席からぶら下がった。カラバがそのクエンサーと入れ替わりに、天井から顔を出す。他の面々の目は操縦席のディスプレイを覗き込む。
「よし、やった」ソールは皆に溜息をつく間を与えない。「急いでライトニングを屋上に降ろせ」
モートレイが操縦桿を引いた。ライトニングは盾にしたビルから月光を避けるように移動、宿舎ビル真上にて一旦停止した。ルスト、マルカムが屋上に飛び降り、麻痺ビームで意識を失った6人をタングステン合金のワイヤーで、手際よく縛り上げた。ソールが駐屯所に駆け込む。
“見事だったな。”
通信機からのマキタの声に、クエンサーは玉汗の浮いた鼻を再度鳴らした。「俺だってプロの端くれだぜ」
“大したもんだ。しかし、あの6人、よくもまあ都合よく雁首を並べたもんだ。”
「それだ。ソールの野郎、一体どんな魔法を使いやがったんだ?」
カラバとジャス、ベーリックも手伝い、6人の兵士を駐屯所に運び入れた後、ライトニングは屋上に降りた。降りたはいいが、駐屯所のあるせいで狭い屋上は、装甲車1台だけで一杯になってしまった。
「マキタたちには裏手の空き地に降りて貰う。俺の指示するコースから1ミリたりともズレるなよ」ソールはジンリッキーとグレイハウンドに数値を指示した。「ついでに俺も下ろしてくれ。魔法? ああ、そのタネは後で明かすよ」
…宿舎ビル内部の全管理、及び収容者の監視は、7階の警備室で行われている。各廊下には不可視光線の網が張られ、それを遮断した侵入者或いは脱走者は、常駐する内務省の警備兵10名に追われる。警備兵の手に余る相手だと、内務省治安パトロールのお出まし。彼らにも手に負えない相手だと、今度は保安省に連絡が飛ぶ。
「この星には下らん縄張り意識とか、縦割り行政の弊害とか言ったものがない」ソールは言った。事件が大きくなると内務省は保安省に処置やら捜査やらを平気で頼むし、保安省は開放機構やら帝国やらが絡んでいそうな事件以外は内務省に完全に任せてる…。「それでいて責任の所在は常に明確だ。縄張り争いは大袈裟にやるくせに、責任だけは押しつけ合うどこかの星の政府とは大違いだね」
ジンリッキーとグレイハウンドはソールのくれた数値と1センチも違えずに、空き地の指示地点に降りた。
「俺たちはその警備室を押さえる必要があるんだな?」エレナとともにシートをジンリッキーとグレイハウンド機体に被せ終えたマキタが訊いた。「しかし今聞いた話じゃ、そんなに危険な警備は…」
「ああ、基本的に人に危害を与えるシステムは、この星じゃ採用されない。但し、相手がこの星この街の市民である限りにおいて、だ」
エレナの顔が月明かりの下、瞬時険しくなった。
「だが、警備室を押さえないでは各部屋の警報が解除できない。警報が鳴り響いたらこの建物だけじゃない、内務省、保安省にも連絡が行く。
まあ、もっとも、どちらが出動するかは侵入者の規模、危険度を見て決めるみたいだが…」
それに保安省とて、首都内部で市街戦を仕掛けてくるわけにはいかないだろうがね…、ソールは言った。
マキタは頷かなかった。開放機構基地での保安省暗殺部隊の暴れっぷりを見ていたからだ。
と、マキタの目が、ソールの襟元につけられたバッジを見た。
「ああ、気がついたか。これは住民識別票だ」ソールは爪までしっかり手入れされた綺麗な指でバッジを摘んだ。「内務省職員の身分証でもある。街のあちこちに仕掛けられた監視システムがこれを読み取り、住民か否かを識別する。こいつがなければ、不可視光線を浴びた瞬間に警報が鳴る。他の役所? もちろん皆持ってるさ。このバッジは市民全員が持たされてる。
ナノマシンでの攻撃? そんなことがあったのか。ああ、確かにこのバッジをつけてれば、ナノマシンも読み取って、攻撃対象から外すかもな。成程、そんな手も考えてやがったのか」
“もし保安省が出張ってきたら、それこそあのナノマシンだって使いかねねえだろ?”その威力を目撃しているクエンサーも、こればかりは真剣な口調で訊いた。
「いや、そこまではやらんだろう」とソール。「この星の盾とも言える保安省だが、実は政府の中での評判は微妙に悪いんだ。やり方が残虐すぎると、保守派の高官たちに、いつも槍玉に上げられてる。それもあるから、このタキアス内では滅多なことは出来ないと思う」
バッジはその他に、体温・脈拍等を測定、使用者の心理・肉体的な異変をも監視システムに伝えるのだと言う。マルカムが訊いた。“つまり何か? 脅迫なんぞされていても、バレる、と。”
「そう、いろんな場所に筒抜けだ」だからさっきの6人のバッジを使えばいいというものでもないのだ。「あくまで本人が持たなきゃならない」
“おめえは使ってるじゃねえか。”
「当たり前だ。まあ、俺は今は、バッジに仕掛けを施して、監視システムを謂わば騙しているわけだけどな。でも、その作業だけで、一晩潰れたよ」
“とすりゃあ、俺たちは動けねえ。おめえに行って貰うしか…。”
「馬鹿吐かせ。どうして一介の住人でしかない俺が、警備室に赴かにゃならんのだ。それこそ変な疑いを招くわ。あんたらが上から侵入しろ」
ソールは不可視光線網の死角を数値で伝えた。もっともそれは監視カメラの死角ではないと言う。どうするんだ、との声に肩を竦め、「手は打ってあるから心配するな。まあ、仕上げにはちょっとした手伝いを頼むことになるが」
と、マキタに意味ありげな目配せを送ってくる。マキタの背中に鳥肌が立つ。嫌な予感…。
「警備室を占拠したら、俺が指示を出すまで手を触れるな。下手にキーを打ち間違えたりしたら、中央管制コンピューターに記憶されるんだ。2度目の間違いで、これまた警報が鳴る」
やっと終わる…、ソールは小さくボヤいた。これを全部お膳立てするのに、完全に胃がおかしくなった。今はクスリで誤魔化しちゃいるが、帰れたらすぐさま入院かも知れない程だった。
その分の超過報酬もコイケと交渉しなくちゃならんかな…。
魔王への挑戦 その5

(5)
内務省宿舎ビルの正面玄関ドアがそっと開いた。
2台の監視カメラが角度を変え、身を滑り込ませてきた女の姿を捉えた。顔のズームアップとともに、センサーが襟の識別票を確認する。ルアンナ・シイ。市街管制室オペレーター。
心拍数に変化あり。動揺。
何か囁いていた。カメラ接続の集音マイクが聞き耳を立てる。つまりは警備室内の10人の兵士たちが。
「ついて来ないでって言ってるでしょ」明らかな外出禁止令違反。しかも…、「お願いだから帰って」
カメラレンズが焦点を変え、入り口外に立つ長身の男を捉えた。女の手首を掴んでいる。マイクがその声を拾う。
「なあ、頼むよ。入れてくれ」情けない声。ドアフレームの陰になっていてよく確認できないが、表情も同様だろう。「もう少しだけでいい。俺と一緒にいてくれ。こんなままじゃ帰っても眠れない」
「駄目よ。帰って」喘ぐような声。溜息混じり。そして一層の動揺。「お願いだから私を困らせないで。ただでさえ外出禁止違反を犯してるのよ。これ以上…」
言いつつも、声の端々が震えている。後ろ髪を引かれている。
「中に入ってもいいだろ?」
「駄目だったら。ここの住人じゃないあなたが1歩でも入って御覧なさい。警備装置に…」
「警備装置が何だ。警備兵が何人来たところで…」
「違うわ。対人レーザーがあるのよ」
聞いている兵士たちは苦笑する。どうして女という連中は、平気でこんな大嘘をつけるのだろう。ここの警備にそんなものは配備していない。寝坊してバッジを忘れて飛び出した職員をレーザーが撃とうものなら、それこそ大事になってしまう。
外の男も流石に動揺した。しかしいきなり、握っていた女に手首に力を込め、「出よう」
「え…?」
「ここが駄目なら俺の部屋に行こう、な?」強引に手首を引っ張る。
「止めて。放して」女は抵抗する。しかしそれも素振りに過ぎないのだろう。ドアの外に向かって引きずられるままだ。「放してったら…」
明らかに、男の力が強いからだけではなかった。
…内務省職員の住居はこのビルの6階まで。7階から上は、侵入してきた他星者を収監する簡易監獄の役割を負わされている。
その7階の、警備室のドアが開いた。モニターの音声と笑い声とに送られ、3人の兵士が出てきた。
腰に銃を吊ってはいるが、それ以上の装備は身につけていない。相好を崩した若い彼らは、内務省勤務の警備兵とは言え、これまで大きなトラブルに遭遇したことがない。治安の安定は好ましいことなのだが、反面彼らにとっては退屈でもある。上空では今、厳戒態勢が敷かれているらしいが、それも彼らにとっては遠い世界での話だった。
身持ちが固い上に勤勉で名高い市街管制オペレーターの外出禁止令違反。しかも原因は色恋沙汰。相手の男を連れての真夜中過ぎの帰宅と、正面玄関前での一悶着。ちょうどドアの死角になっているため、警備室から男のバッジは読み取れなかったが、それもすぐに判明するだろう。シルエットだけでは判断もつきづらかったが、内務省の職員ではなさそうだった。華々しい手柄などとは程遠い仕事だが、話題だけは鬱屈垂れ込めた暇を慰めてはくれそうだった。
恐らくそんな期待を抱き、警備室を出た3人の頭上で、緑色の何かが動いた。
ずっと玄関先を映すモニターばかり見入っていた3人と、中の7人は、廊下の天井を這ってきた影2つに気づかなかったのだ。
「………!」
麻痺銃の力線を浴びた3人は、声を上げる間もなく崩れ落ちた。
7階廊下を見渡せるモニター内の異変に、残った兵士たちはざわめいた。何事だ、あいつらどうした…?
「ちょっと見てこい」1人の声が命じた。「ここは俺が見ている」
その声に6人の兵士が警備室を飛び出した。そして飛び出した瞬間、2方向からの力線を浴び、全員がその場に倒れ伏した。
ドア越しに折り重なるように倒れた兵士たちの上を、張り巡らされた不可視光線網に触れることなく、マルカムが警備室に飛び込んだ。唯一残っていた、顔に火傷の痘痕の残る兵士に、変形した左腕をかざす。
その兵士も即座に意識を失い、床に伸びた。
マルカムの金属製の右腕、掌と肘の裏側に、真空吸引盤が露出していた。膝のパットの下にも。これらを天井のタイルに吸いつかせ、不可視光線の死角をヤモリのように這ってきたのである。右腕を振ると吸引盤は折り畳まれ、義手の内部に収納された。膝の吸引盤もだ。
マルカムが声を掛け、ドアからカラバが逆さ向きに顔を出した。彼も肘と膝に吸引盤――但しベルト装着式――をつけていた。巨体に似合わぬ身軽さで警備室内にふわりと飛び込んでくる。携帯麻痺銃を腰に戻す。ルストの代役は充分に務められた。自分が先頭に立つと言ったルストを後陣に残したのはマルカムだった。
「妻子持ちに先鋒を任せられるか」と言って。
マルカムの左腕には銃身を切り詰め、パラボラを開いた光線銃が装着されていた。ハーフナー社製のSPAWN――多用途万能火器は破壊光線モードで撃てば、重戦車とも渡り合える代物だ。左上腕に内蔵された原子力電池がエネルギープール。現在のモードは麻痺銃。取り外された本来の左腕は、彼の腰のベルトを掴んでぶら下がっていた。
その左腕を右手で掴んだマルカムは、ブレスレットの通信機に呼び掛けた。
「済んだぞ、上がって来い」
玄関ドアにて痴話騒ぎを起こしかけた女――ソールが、識別票を使って堂々と上がってきた。床に転がる兵士たちを跨ぎ越え、異常のないことを確認し、コントロールパネルの1つをいじる。その際、床に伸びる痘痕顔の兵士をちらりと一瞥し、鼻で笑ったように見えた。7階から10階までの監視カメラと不可視光線網とが切れた。そして各部屋に仕掛けられた警報装置と室内監視カメラも。壁を覆い尽くす4階分の全モニターが消える。しかし次の一操作で、画像は全て回復した。そのソールの合図でカラバが廊下に出た。不可視光線網も切れており、監視カメラにも彼の姿は映らない。
廊下の窓からカラバが垂らしたワイヤーを、エレナと、さっきまでの色男マキタとがよじ登ってきた。「どうして俺とエレナだけ…」
「まあ言うな」出迎えたソールが言った。中央管制コンピューターに勘づかれないうちに画像をダミー映像に切り替える細工、不可視光線網を切りセンサーを眠らせる細工に、思ったより時間を取られた。7階から上の4層分しか仕上がらなかったのだ。「お前さんたちには外から侵入して貰うしかなかったのさ」
その代わり、7階から10階までは自由に動き回れる。眠らされたセンサーは架空の認識票情報を与えられており、マキタたちの動きが中央管制コンピューターに伝わることはない。
「ワイヤーを登るくらい何だ。俺とカラバは爬虫類の真似だぞ」廊下と警備室内の10人の兵士を手際よく縛り上げながら、マルカムが言った。マキタの顔を正視できないでいる。見ると笑ってしまうのだ。「随分な熱演だったぜ」
通信機で下での遣り取りを聞いていたのだ。カラバまでもが肩を震わせていた。上ではクエンサーたちが口も利けないくらいに笑い転げているらしい。
マキタは子供のように膨れっ面を作った。「何をいい気に…」
「さあ、急ぐぞ」ソールは言った。ダミー映像で中央管制コンピューターを騙せるのにも限界があった。精々1時間だ。「アリーゼ・サロイは10階だ」
マルカムを先頭に、5人はエレベーターを使わず、階段を上り始めた。深夜、各階には動くものの気配すらない。各フロアに備えられたカメラ、マイクも眠っている。それでも5人は靴音1つ立てず、風のように移動する。
視線を感じたマキタは振り返った。
エレナのニヤニヤ笑いが彼を見返した。「いつもあんな感じで女を口説いてるんだ」
「な…!」
物凄く嬉しそうな意地悪声だった。「サビア・サロイって人も、ああやってモノにしたわけね?」
「ちょっと待て。それは誤…」
「確かにあれは上手かった」前を行くソールが唐突に言った。「迫真の演技を超えてた。俺が女だったら、間違いなく許してたな」
マキタは腹立ちを忘れ、エレナに自分の前を走って貰うことにした。ソールから1センチでも遠ざかるために。
10階に駆け上がったマルカムが通信機に合図を出した。カラバが窓を開けた。屋上から別のワイヤーが垂らされる。SPAWNを構えたマルカムが周りを見張る中、ソール、マキタ、エレナがドアの1つに近寄った。
「カードロックね」エレナが腰の銃に手を遣った。「ぶち破る?」
「1発でバレる」ソールはエレナをどかせ、“豊かな”胸の谷間から、1枚のクリスタル製カードを抜いた。その仕草の艶っぽさに、エレナは内心ムッとした。あたしより女らしい…。
カードは手製の偽造品だった。それを1本の針とともに、差込口に挿入する。パネルの表示が赤から青に変わる。ロック解除。
「完了だ」
ドアロック解除だけではない。警報解除、ダミー映像への切り替え、全てだ。
「これで俺の仕事は終了だ。ひとまずお前さん方にバトンを渡すわ。大丈夫だ。さっきも言ったが、作戦が終わるまでは中央管制コンピューターに悟られる心配はない」
「あんたは掛け値なしの天才だ」マキタは心の底から言った。ギーンのホテルに潜入するだけで、ボウイの力を借り、それでも大騒ぎにしてしまった自分とは何たる違い。
エレナも頷くしかなかった。開放機構の精鋭数ダースが命と引き換えにしても遂行できなかったタキアス施設への、そして警備システムへの潜入を、いともやすやすと…。
「コイケさんの言った通りだ。今回の仕事はあんた抜きでは成り立たなかったよ」
「嬉しいがな、その台詞はきちんと脱出できた後に頼むわ」
と口では言いながらも、ソールのラテックスのマスクに、安堵の色が浮かんだ。杞憂で、済んだか…。
…差込口から針をそっと引き抜くと同時に、ドアが開いた。
中は明るかった。しかも広い。窓は開閉不可能なようだったが空気は新鮮で、温度湿度ともに快適な状態に保たれていた。ロッカー、机、テレビまで置かれており、棚には銀河共通語で書かれた――今の時代では珍しい――書物が収まっていた。コイケがここにいたら狂喜したかも知れない。
「点けてみろよ」ソールがテレビに顎をしゃくった。「この時間でもまだ映る筈だ。いい番組もあるぜ。音楽とか、ドラマとか」
「嘘よ。ここでは総統のプロパガンダ番組しかないって教わってきたわ」
ソールは首を振る。「ここに居座って4時限近く経つが、そんな政治的な番組は観たこともない。ここは随分と文化程度は高いよ」
ベッドルームは別室になっている。浴室、トイレもだ。部屋中央のテーブルには、手のついていない食事が置かれていた。冷めても尚、香ばしさを放つ肉のソテー、緑色野菜をたっぷり使ったサラダ、切り分けられたパン、澄んだ水の入ったクリスタルの水差しと熱湯を沸かすポット…。そして皿の横には、薬とおぼしきタブレットが3種。憔悴したアリーゼのために医者が出した精神安定剤だとのことだ。
これが囚人を閉じ込める部屋だろうか。環境と言い待遇と言い――エレナが側にいるから口には出せなかったが――、客人として扱われた開放機構での時間が霞んで見えた。遅れて入ってきたマルカムとカラバも、ただただ感心していた。
「いい場所だよ、ここは」ソールは言った。この街には4000人を超える他星者が住んでる。幽閉されているわけじゃない。洗脳された形跡もない。ちゃんとした市民として、然るべき保護の下で暮らしているんだ。中には連邦軍の潜入工作員だった奴…、「つまりは俺の、かつての同僚までいるってのには驚いた。まあ、面識がある奴じゃなかったけどな」
「ホントかよ…」
「ただ、帝国の潜入工作員にだけは目を光らせてる」
「当然だろう。この星系の月までぶっ壊した連中だ。用心もするだろうさ」
「それ以降も帝国は度々ここに工作員を送り込んでたようだがな」
「へえ…」
「お前さんたち、ガリア第1惑星産業振興同盟、って肩書に聞き覚えはないか?」ソールは皆を見回した。「帝国軍特殊工作班の面々がカモフラージュに使ってる組織の1つだ」
「たまに聞くな、その名前。ベルフォスタムの奴らが所持してた身分証がそんな組織だった」と、マルカム。
「それを内務省のデータバンクから見つけた時は驚いたよ」ソールはほくそ笑んだ。「どういうことかわかるか? 元ガリア第1産業振興同盟の構成員だったそいつは、既にこの星で、市民の暮らしを享受してるってわけだ。
まだ帝国の潜入工作員として息を潜めてる? いや、それはない。理由は後で話す。
お前さん方もさっき見てると思うが、警備室の中にいた兵士の1人だよ」
マルカムがああ、と頷いた。火傷の痘痕の、あの兵士のことらしい。
「俺はこっちの正体を明かさぬまま、あいつに連絡を入れてみた。あんたが実は、この星が未だ用心している帝国の工作員だと知ったら、保安省はどう動くかな、ってね。奴さん、慌てたねえ。何でも言うことを聞くから、それだけは内密にしてくれ、と泣きついてきた」
ソールはそいつの弱みにつけ込み、警備室と中央管制コンピューターとを遮断し、ここにいる皆の姿を隠してくれるダミー映像を組み込んだシステム回路をコントロールパネルに繋がせた。楽な作業ではなかった筈なのだが、流石はベルフォスタムの元メンバー、見事な手際でやってのけた。「鮮やかなもんだった。その分、こちらも時間が節約できたよ」
それだけではない。屋上の監視施設に虚偽の警戒連絡を送り、一斉にクエンサーの銃口の前に並ばせ、マルカムとカラバが天井を這っている最中に同僚の目を騒ぎの映るモニターに誘導し、その同僚たちを纏めて部屋から誘い出す真似までやってくれたのだ。今回の仕事での最大の収穫は変装でもなければコンピューターへの目眩ましの成功でもない。
ソールは言った。「元ベルフォスタムのあの男を利用できたことだ」
マキタたちは半ば唖然と、その話に聞き入っていた。
「さっきの話の続きになるが、面白いことがあってな」ソールは笑った。「俺はこちらの正体を明かさずに接触したんだが、奴さん、俺が帝国の関係者じゃないことをやたらめったら確認したがった。正体を明かされて保安省に捕まるのも怖いが、実はそれより、かつての古巣の方をもっと恐れてた」
「何だよそれは?」
「何回か連絡を取り合っててわかったんだ。あいつはな、昔のお仲間に救出に来られたくなかったんだよ。しつこいくらいだった。ベルフォスタムにだけは俺の生存を伝えないでくれ、ってな。
あいつにとっては、ここでの生活を失うことの方が怖かったんだ」
だから俺の脅しにも簡単に屈した…、ソールは誰にともなく頷いて見せた。わかる気がする。ここはいい場所だ。威張らない軍人、責任感の強い役人、ここでは人間が大事にされてる。ベルフォスタムに縛られて、いつかは使い捨てにされてどことも知れない宇宙で野垂れ死ぬことがわかってて、それでもそこから抜け出せなかったあいつが、やっとのことで手に入れた人としての生活なんだ。思うんだがな…、ソールは言った。「皆がここを“1度入ったら出られない場所”って言ってるが、“1度入ったら出たくなくなる場所”の間違いじゃないのかな、ってな」
「しかしだな、俺たちは現に、数百隻の艦隊に…」
「追いかけられたわけだよな。もちろんここが恐ろしい場所だってことは否定しない」そう、あの視線…。「だがそれは一面的な味方だって気もしてる。お前さん方があのまま来なかったら、俺は内務省に自首して出る積もりだったよ。助け出せないボディガードたちも、今は収容施設にいるが、いずれは市民としての認可が降りて、終生安楽に暮らせると思うぜ。ジュドー星に新婚の嫁さんと生まれたばかりの赤ん坊でも置いてきてない限りはな」
マキタもマルカムも首を振り、溜息をつくしかない。
エレナなどは複雑な心境をそのまま表情に出すしかなかった…。
…隣室の窓際、寝心地良さそうな広いベッドに、白いナイトドレスを着た女が沈んでいた。ほどいた長い髪が黄金の扇のように広がっていた。青白く、透き通る程の肌、浅い呼吸、血の気を失った唇。
似てるな…、ベッドの脇に立ったマキタは思った。
幾らか丸顔で、おっとりした感じを与えはするが、やはり似ている。どこがどのように、という具体的な説明はつけづらい。それでもマキタには直感できた。彼女を見た瞬間、以前スプリッツァで見せられた顔写真よりも先に、目に涙を溜めて彼を見上げるサビアの顔が浮かんだのだ。
そのマキタの背中を押す者がいた。カラバだ。どうしたんだ、と訊くマキタの声など聞こえていない様子で、整った顔と理知的な目をすっかり弛緩させ切っていた。
アリーゼ・サロイに見とれているらしい。
マキタは笑いを堪えてカラバの脇腹を肘で小突いた。
我に返ったカラバがあたふたする横で、アリーゼの両肩に手を掛ける。細く尖った感触。心労、憔悴の気配。
そうだろう。憔悴するのが当然だ…。
「おい、本物だろうな」マルカムが訊いた。もっともである。これまでの経緯が経緯だけに、疑わない方がおかしい。「偽物とか影武者とか、クローンってことはないんだろうな?」
「クローンがこの短期間で作れるかよ。第一、どうして彼女の偽物やら影武者やらを用意せにゃならんのだ」ソールが肩を竦めた。
マキタはアリーゼの肩を優しく揺さぶってみた。小さな呻きは返ってくるが、目は覚まさない。ソールがマキタを制した。「開放機構の裏切り者だっけ。彼女のことを保安省にも漏らさなかったみたいなんだ」
マキタとマルカム、エレナは顔を見合わせた。「ホントか、それ?」
「だからこそマークも甘かったんだ。危険度・重要度の低い他星者ってことで、内務省の宿舎入り。宿舎の移動が簡単だったのもそのためさ」さっきも言ったが、銃を所持していたボディガードたちは、郊外の、ここよりきつい場所で寝泊まりさせられてる。それでも帝国の強制収容所に比べれば天国みたいなものだけどな…、ソールは髪、いや、鬘から、1本の針を引き抜いた。アリーゼの顎と首筋の境目をほっそりした指先で探り、そこに針をそっと打った。
アリーゼの瞼がピクンと震えた。カラバが呻く。なんてひどい真似を…。
ソールが呆れ顔でカラバを見た。「どうしたんだお前?」
な、何でもない。
同時にアリーゼの意識が戻った。
経絡に注がれた薬で強引に呼び戻された覚醒だけに、寝惚けた状態やらボーッとした状態やらはあり得なかった。開かれた目がマキタを見据え、深い緑色を湛えた瞳がそれを見知らぬ顔だと判断するまで1秒掛からなかった。
悲鳴を発しかけたその口を、マキタの厚い掌が塞いだ。
「静かに」アリーゼの瞳を覗き込んだマキタは言った。「俺たちはサビアに頼まれてここに来た」
抵抗を試みようとした彼女は、その1言で大人しくなった。もっとも抵抗したところで、大した力は出せなかっただろうが。
マキタは掌をどけた。アリーゼはマキタの顔を見上げていた。マキタの眼を凝視していた。
じっと見つめられるマキタの方がそわそわしてきた。「サビアに頼まれて、あんたをここから引き揚げに来たんだ。立てるかい? 急いでここを脱出しなくちゃならんのだ」
急かされるままに立ち上がったアリーゼだったが、今の弱った身体では自力で立つのも苦痛だったようだ。よろめいたその肩を慌てて抱き止めたマキタは、再度その眼をアリーゼに覗かれることとなった。
そこでアリーゼは、初めて口を開いた。
「…綺麗な目」
「………!」
ソールの姿が消えた、と思いきや、2人の男女を伴ってすぐに戻ってきた。女はエレナ以上に若く見えた。と言うよりまだ少女だ。サビアの侍女のエルダといい勝負だ。
髭面の男はどこか軋みそうなくらい痩せこけていた。素顔のソール以上だ。風貌はマキタが以前故郷で見た、救世主とやらの肖像画にそっくりだった。
「メリサとアントランだ」ソールが紹介する。アリーゼに直接接近できなかった彼が、連絡を取り合っていたという側近たちだ。
頭を下げつつマキタたちを観察していたアントランは、消耗し切った主人の姿に驚いた。ソールの顔と声の落差に半ば怯えるメリサと2人で、マキタからアリーゼを受け取る。
「アリーゼ様、御無事で」
「あなたたちも」
細い小声ながらもしっかりとした口調で応え、アリーゼは微笑んで見せた。メリサが泣き出しそうな顔になる。安堵の溜息がマキタの口からも漏れた。
エレナがマキタを見ていた。何とかまともになったみたいね、と目で話し掛けてくる。さっきの第一声がエレナには全く意味不明だったからだ。頷きはしたが、マキタにはわかっていた。あれは寝惚けて発した言葉ではない。
マキタはその言葉を前にも聞いていた。それも彼女と血の繋がった妹の口から…。
連絡を取り合っていたアントランに口添えさせ、ソールがアリーゼに事情を説明していた。
アリーゼの呑み込みは早かった。「わかりました。お任せします。すぐに出発して下さい」
「10階から上は警報が生きてる」ソールが言った。「誰かにアリーゼさんを担いで上って貰わにゃならんのだが」
「またワイヤーかい。まあ、俺かマルカムしかいないだろう」
マキタの言葉にカラバが不満の声を上げる。僕もいるぞ。
「後はそこの侍女のお嬢さんもだな。ルスト聞こえるか。ワイヤーを垂らしてくれ」
“了解だ。”
「待てよ、それよりシーエメラルドは無事なんだろうな?」マルカムが訊いた。「俺たちの目的はあんたと宝石の両方であって…」
「大丈夫です」アリーゼは微笑んだ。悪戯っぽい表情が浮かんだ。完全にまともに戻ったようだ。
表情を取り戻すと、アリーゼはサビアとは随分印象が違って見えた。かけ離れていると言ってもよかった。先程どうして直感できたのかわからないくらいだった。微笑みが子供っぽいせいもあろう。笑顔だけで接したら彼女の方が姉だなどとは、説明されても信じなかったかも知れない。「ちゃんと隠してありますから」
「隠して…?」
マルカムは側近2人を見た。メリサもアントランも首を振るだけだ。知らないらしい。それを見てアリーゼはまた笑う。邪気のない笑顔が周囲を和ませる。不思議な笑顔だ、マキタは思った。彼女が外交官もやっているのだとしたら、この笑顔も一種の武装かも知れないと思う。寝顔、寝起きの顔、今の笑顔…。
本当の彼女はどこにいるのだろう。サビア以上に掴めなかった。
「身体検査とかされなかったのか?」
「されましたわ。厳重に。でも大丈夫です。信じてませんね?」
「またここに逆戻りってのは嫌だからな」
“おい!”
通信機からルストの声が割り込んできた。響きの緊迫に、その場の空気が凝固したかに思えた。
“何か近づいてきてるぞ!”
マキタは答を期待するでもなく、自然にエレナと顔を見合わせていた。
“おい、聞こえてるのか?”
「聞こえてる」マキタが応えた。「アリーゼ・サロイは無事に確保した」
“そうか。”
「近づいてくるって、清掃車じゃないの?」
“いや、違う。サーチライトだらけってのは同じだが、清掃車とは違う。兵員輸送車っぽい。”
同時にカラバが全身の毛を膨らませた。低く唸る。彼の感知力に何かが引っ掛かった。それは恐らく、迫ってくる危険。
接近してくるのは間違いなく敵だ。
“7台だ。全てこのビルを目指してる。”
ルストの声の背後から、いや8台だ、と怒鳴るクエンサーの声も聞こえる。
「行きましょう」怯え始め、質問さえ発せないメリサとアントランを横目に、決然と言ってのけたのはアリーゼ本人だった。「一刻も早く、私を連れ出して下さい」
その目から今は、意志と決意とが迸っていた。
マキタは改めて思った。やはり姉妹だ。
「行くかソール」
返事はない。「ソール?」
ソールの肩が震えていた。畜生、と呟く声が聞こえた。やっぱり、だ…。
「やっぱり、って、何がだ?」
「錯覚じゃなかった…」人工の皮膚の下で、物凄い歯軋りの音が聞こえた。「俺は、最初から、見つかっていたんだ…」
「ちょっと待て。それは一体…」
“何をしてる! 早く上がって来い!”
ルストの声を爆発音が掻き消しそうになった。砲撃だかミサイルだかを受けたのだ。罵声とともにシューッ、という鋭い高音の銃声がした。クエンサーが高精度狙撃銃での反撃に出たようだ。叫んでいる。あの装備、保安省だ! お馴染みの暗殺部隊さんのお出ましだぞ…!
“ビルに入っていく。聞いての通り、保安省の暗殺部隊と…、”ルストの声。“何だあれは…?”
「暗殺部隊と、何だ?」
“わからん。装甲車輌にも見えたが、今建物に入って…、”再度の爆発音にクエンサーたちの喚き声が聞こえなくなり、ルストの声も瞬時途切れた。
「大丈夫か!」
“今のところ直撃はない! だが時間の問題だ! これ以上ミサイルを食らうと、建物が保たん!”
マキタは歯噛みした。まさか住民もいる建物に向けてミサイルを撃ってくるとは!
“応援を送る。早く上がって来い!”
「要らん! そっちはライトニングを守れ!」
廊下に出たマルカムが叫ぶ。「エレベーターが降りた!」
ハンディキャノンを引き抜いたマキタは、カラバにアリーゼ護衛を一任した。表情を輝かせたカラバは、半ば喜々としてアリーゼを抱え上げた。メリサとアントランにはマルカムの前を走るように指示する。「外に敵か。これでワイヤーは使えなくなったな」
「階段しかない。見ろ」マルカムが顎をしゃくった。エレベーターの表示が1階で停止した。「纏まって来るぞ」
「行くか」マキタはアリーゼを窺った。アリーゼが小さく微笑む。怯えた素振りさえ見せない。マキタも笑顔を返した。「いいかカラバ、何が何でも階段を駆け上がれ。俺たちのことは気にするな」
「マキタ」エレナが近づいた。「あたし、外に出ようか? グレイハウンドで下の奴らを…」
「待て。今はここを守ってカラバを上に行かせる方が先だ」エレベーターが上り始めた。「ソール…」
ソールは尚も壁を睨みつけ、唸っていた。マキタがその肩を揺すった。いきなり腕を掴まれる。
マキタを見上げるその目には、これ以上はない憤怒があった。「こんな屈辱は初めてだぞ…」
「何…?」
「俺の潜入を最初から見抜いてた奴がいるんだ!」
これにはマキタも目を見開いた。
最後の最後まで俺を泳がせておいて、今になって悠々と行動を起こしやがった…、ソールは長い人工の髪を掻き毟った。
「ずっと感じてはいたんだ。俺の背中を見てる、視線を。錯覚だと思ってた。錯覚であって欲しいと思ってた…!」
「何、だと?」
保安省の暗殺部隊は、ソールのこの変装を、行動を、全て見抜いていたと言うのか。そんなとんでもない監視システムが、この星にはあると…、マキタは慄然とした。
ソールの受けた衝撃もわかる。どこの誰に化けようと、決して見破られたことのないという彼だ。作戦の初期段階ならまだしも、敵は今の今までその彼を泳がせておいて、最後の最後で引導を突きつけたのだ。まさにソールにとっては、屈辱以外の何物でもなかったことだろう。
それに、さっきソールの奴、視線とか言わなかったか…?
俺も感じていた。この星系に来て以来、ずっと…。
だが、今は…。マキタはソールの横っ面を張り飛ばした。「しっかりしろ!」
「来たぞ!」
叫んだマルカムが、左腕のSPAWNを破壊光線モードに切り替えた。マキタもハンディキャノンを構え…、
エレベーターが停まり、扉が開いた。マキタ、マルカム、エレナがその前に飛び出した。
「………!」
広いエレベーターの箱の中は無人だった。代わりに入っていた者が、そろりそろりと身を乗り出してきた。脚が伸びた。それも8本。立ち上がると、その全身が廊下一杯に膨れ上がったようにも見える。縦に並んだ赤と青の眼に光が灯った。
「〈クランゲージョ〉!」
マキタとエレナの上げた声をセンサーが、3人の姿を赤い眼が捉えた。突き出された大口径機関砲が火を噴いた。重低音の遠吠えとともに、機関砲弾が壁と天井にミシン目を穿っていく。照明が打ち砕かれ、壁の破片が降ってくる。
3人は間一髪、部屋に飛び込んだ。マキタとマルカムが1発ずつ応射するというオマケつきで。
ハンディキャノンの生む数トンの衝撃を食らい、〈クランゲージョ〉の前進が止まった。脚1本にSPAWNの破壊光線が命中、胴体から音を立てて外れ落ちた。バランスを崩し壁に激突、その轟音で、他室の収容者たちが騒ぎ始めた。
もう1発撃ち込もうと廊下を窺ったマルカムを、マキタとエレナが引き戻した。
クランゲージョは体勢を崩しながらもその砲座を回転させていた。しかも青い眼の横に、もう1つ別の突起が。
機関砲弾の合間を縫うように、レーザーが廊下のタイルを切り裂いた。マルカムが圧し殺した悲鳴を漏らす。引き戻されていなかったら、生身の頭を輪切りにされていたところだ。
2発目のレーザーが壁を貫通、伏せたマキタたちの頭上をかすめ、熱風を起こす。マキタたちは平べったくなったまま動けない。メリサの悲鳴が続いている。機関砲は執拗に火を噴き、ドア入り口の周囲を砕き、幅を広げ始める。もうすぐクランゲージョが入ってこられるまでに拡張されそうだ。マルカムが叫んだ。
「あれがクランゲージョか!」
「そうよ」エレナも叫び返した。「保安省の殺戮兵器!」
他室の騒ぎはますます大きくなってきた。機関砲の轟音がそれを煽っている。マルカムが思わず顔を上げる。その数ミリ真上を3発目のレーザーが通過していく。
しかし構わずマルカムは言った。「あいつ、他の部屋にも、弾を…」
「ああ、そうだ」開放機構基地にて1度遭遇済みのマキタは、クランゲージョの恐ろしさが身に沁みていた。「あいつは生きてる者の反応を察知したら、完全に破壊されるまで撃ち続ける!」
考えてみるとルストもクランゲージョの脅威に直には出くわしていなかったのだから、知らなかったのも当然か。
恐らくセンサーが例の認識票を読み取るのではあろうが、下手をすれば流れ弾に巻き込まれる。現に室内にいるソールも体を起こせないでいる。味方にさえ危険な殺人機械を、まさか首都内で平気で使ってこようとは。どんな犠牲を払っても侵入者を生かして出さない積もりのようだ。ソールの読みは外れた。
やはり閉鎖星系は、いかなる侵入者をも逃さない場所なのだ。
クランゲージョはレーザーだけはマキタたちの部屋に狙いを定めつつも、機関砲は当たり構わず乱射を続け、前進を再開した。
5発目のレーザーで、遂に部屋の壁が半壊した。野郎…、歯軋りしたマルカムがさっと立ち上がった。次いでマキタも。
崩れかけた壁越しに撃った4発のハンディキャノン銃弾とSPAWNの破壊光線は、クランゲージョの赤い眼を貫き、脚2本をへし折った。それでも止まらない。乱射が一層凶暴になっただけだ。
呻いたマルカムを、再度マキタが引っ張った。僅かに体温の残る床を、レーザーが抉り取った。壁際に固まれ、とマキタが叫ぶ。カラバがアリーゼを抱えて壁に張りついた。他の2名をエレナが押しやる。ソールが立ち上がった瞬間、足元に機関砲弾が降り注いだ。床が穴だらけになる。
「糞っ、もう少し早く上に行ってりゃ…」マキタが言った。責めたわけではないのだが、ソールは黙って項垂れた。
壁際に釘づけとなったカラバが顔を上げた。次いでマキタも。「………?」
靴音…?
「マキタ! マルカム!」ルストの声だ。応援など要らんと言っておいたのに…! マキタは入り口に転がりざま、叫んだ。
「来るな!」
遅かった。廊下に飛び出したのはベーリックだ。飛び出した姿勢のまま体を凍りつかせる。彼も遭遇自体は初めてだが、基地にてクランゲージョの恐ろしさは叩き込まれていた。勢い込んだ闘志は消し飛んだ。動けない。
「馬鹿野郎! 早く逃げ…」
機関砲の1吠えと同時に、ベーリックの上半身が消失した。
「ベーリック!」側に来ていたエレナが、マキタの顔の横で呻いた。
ルストが怒鳴る。「マキタ、まさかあれが…!」
「ああ、クランゲージョだ。そこから出るなよ!」
叫びながらマキタはハンディキャノンを撃った。火花を散らしてたじろぎはするものの、クランゲージョの装甲は堅牢過ぎた。必死に思い出そうとする。俺は前に、ヤツの足の付根を撃って黙らせた。その前に俺は、どうやってヤツを引っ繰り返したんだっけ。
7発目のレーザーが背後の壁を貫通し、隣室にまで達した。収容者たちの悲鳴が聞こえた。
無関係の人間を…!
頭に血が上ったマキタは考えるのを止めた。刺し違えてでも黙らせてやる! エレナがその決意に気づいた。マキタのジャケットの裾を引っ張り、彼を制する。しかしマキタはエレナを引き摺りかねない勢いで廊下に出ようとした。
その時。
階段の前まで進んだクランゲージョの胴体が、爆発したかのような火花を上げた。階段の踊り場から立て続けに伸びた光線が、その装甲に突き刺さる。クランゲージョは階段と反対の壁に押しつけられ、めり込んだ。残った5本の脚のうち、4本が次々に千切れ、床に転がる。
そして遂に、クランゲージョは横転した。光線は尚も、その胴体に突き刺さる。ハンディキャノン銃弾をも弾き返した外殻に亀裂が走った。そこから大量の煙とピンク色の液体が溢れ出す。
ガクン、とへたり込んだクランゲージョの前に、モートレイが飛び出した。構えられたのはハーデス・ビームランチャー。センサーが捕捉した敵を記憶、作動停止装置を働かせない限り、その敵に熱戦を吐き続ける代物だ。どこかクランゲージョに似ていなくもない武器だとも言えた。
「一丁上がりだ!」
ビームランチャーが最後の光線を撃ち込んだ。爆ぜるような音が響き、クランゲージョはビクン、ビクンと生き物のように痙攣した。モートレイはマルカムに向かって歓喜の雄叫びを上げ、鼻息も荒くクランゲージョに近づいた。マルカムが「待てモートレイ!」と叫び、マキタも立ち上がろうとし…、
2人をエレナが床に引き倒した。
モートレイの顔が消失していた。
煙を上げるクランゲージョが動き出した。
1本しかない脚が壁を、そして床を蹴った。まだ立ち上がろうとしている。装甲に入った亀裂が床や壁と擦れ、悲鳴のような音がする。機関砲は破壊できたようだが、レーザーは健在だった。気の狂ったような乱射が始まった。しかも出力ノンセーブだ。天井を貫通し、床をぶち抜いた光線は、他の階にまで被害を出し始めた。
「畜生、モートレイ!」マルカムが喚いた。「何てバケモノだ、こいつは!」
マキタがハンディキャノン弾倉を替え、構えた。エレナが即座に援護できる態勢で背後につく。レーザーがすぐ側で炸裂、一旦頭を伏せた2人だったが、すぐさま立ち上がり、マキタはハンディキャノン1弾倉分を撃ち尽くした。
ようやく静寂が訪れた。
マキタはハンディキャノン弾倉を替えた。今度こそ動かなくなったクランゲージョに近づいていく。SPAWNを構えたマルカム、そしてエレナも続いた。階段からルストも出てきた。
「恐ろしい奴だ」初めてクランゲージョに遭遇したマルカムはまだ恐怖冷めやらぬ顔で言った。「こんなのが何台もウロウロしたやがるのか」
「おい」ルストがマキタに言った。「大丈夫なのか?」
クランゲージョはピンポイント射撃に、脚の付根を撃ち抜かれていた。炸裂徹甲弾に穿たれた穴の内部に、電子頭脳の残骸…。
「モートレイのお陰だ」マキタは沈痛に言った。彼がクランゲージョを引っ繰り返していてくれなければ、この急場でマキタはその方法を思い出せずに終わっていただろう。マルカムの碧い目が曇った。モートレイは長いつき合いの傭兵仲間だった。今回は大変な仕事だとマルカムが釘を刺したにも関わらず、二つ返事で引き受けてくれた男だった…。
「行こう。長居は出来ない」ルストが呟いた。マキタが声を掛け、アリーゼを抱いたカラバが立ち上がった。流石に青い顔をしているアリーゼに何か囁き、階段に向かう。メリサは失禁していた。卒倒寸前の顔をしたアントランは膝をがくがくさせながら、そのメリサを引き摺るようにカラバに続く。マルカムがモートレイを、エレナがベーリックの四散した体を痛ましげに一瞥し、皆に続いた。
階段を上り始めた時だった。
カラバが低く唸った。
もう1台、来る!
同時に全員の耳にも、階下から響く歯車の軋むような音が届いた。クランゲージョが、もう1台! メリサがかすれてしまった喉から悲鳴を上げた。マキタが叫んだ。
「ルスト、マルカム、先に行ってくれ!」
機関砲が咆哮した。砲弾の雨が階段を突き上げた。躊躇したルストだったが、そうするしかなかった。「よし、ここは任せたぞマキタ!」
マキタに頷きを送ったマルカムが、先頭を切って階段を駆け上っていった。ルストがカラバたちを率いて続く。それを見送ったマキタは、まだ項垂れているソールに、いつまで気に病んでんだ、と笑い掛けようとした。
その耳元で、声がした。
「マキタ、やっぱりあたし、下に降りる」
「何…?」
「囮になるわ。上手く逃げてね」
そう言ったエレナは、既にエレベーターの方に向かっていた。
「お、おい、待て。お前1人で…」
階段がいきなり赤熱化し、膨れ上がった。マキタは横っ飛びにソールを突き飛ばし、廊下に転がり出た。膨れに膨れた階段の金属の床は風船のように弾け、灼け爛れた鉄塊を周囲に降り注いだ。大穴の空いた階段の底の方から、クランゲージョの8本の脚が、ガリッ、ガリッと壁を噛む音が聞こえてくる。
「うおっ!」
穴から下を覗き込んだマキタに、機関砲弾が浴びせられた。暗い穴底から、赤と青の眼がこちらを睨んでいた。瓦礫が数個、落ちてくる。「あんたも早く上がれソール、来るぞ」
「マキタ!」
振り返ると、エレベーター前でエレナが叫んでいた。「箱が…、エレベーターが上に昇ってる!」
一瞬マキタには何のことだかわからない。それが、何だと…。
気づいて愕然とする。エレベーターは1台目のクランゲージョを運んでこの階に来た。この階に停まっている筈だった。
「ルスト、マルカム、気をつけろ!」マキタは通信機に怒鳴った。「待ち伏せられて…」
階上で爆発音。遅かった。
やはり自分も行くべきだったか…、マキタは壁を殴りつけた。マルカムが一緒である以上、逃げ果せてくれるとは思うが。
再度、穴底から機関砲が吠えた。階段を跳弾が飛び回る。壁を引っ掻く音。狭い階段をクランゲージョが無理矢理上がってこようとしているのだ。温かい人体を嗅ぎつける限り、こいつは何が何でも止まらないのだ。
「マキタ!」
エレナの声。何だこんな時に。
エレベーターの扉が開いていた。エレナがこちらを振り返っていた。微笑みを浮かべて。
その微笑みの意味するところを、マキタは一瞬、掴みかねた。
エレナは言った。「有難う…」
「………?」
「さよなら」
見つめ合ったのはほんの数十分の1秒。しかしそれだけで充分だった。無言の裡に、想いの全てが伝わった。エレナは満足気に、もう1度微笑んだ。
マキタはそうは行かなかった。待てと叫んで立ち上がろうとした時、穴底から迸ったレーザーに足元を掬われた。伏せた頭上を光線と熱風とが吹き抜けていく。2台目のクランゲージョはすぐ下にまで迫ってきていた。
エレベーターの扉が閉まった。
マキタは皆の駆け去った階段を見上げ、クランゲージョの迫る階下を見下ろし、エレベーターを見遣った。
ソールが言った。「彼女を追えよ」
マキタはソールを見た。ソールはモートレイの死体の横に置き去られたビームランチャーを拾い上げ、エネルギー残量を調べた。「上がっていった連中にはマルカムとルストがついてる。こっちは何とかしてみるさ」
「しかし…」
「早く行け。あの娘は包囲の真ん中に出る気だぞ。エレベーターは駄目だ。屋上からのワイヤーが垂らしたままだろ。今見たら1本は無事だ。それを使って降りろ」
マキタはガラスの割れた窓を振り返った。確かにワイヤーが風に揺れていた。「わかった。無理はするな」
「お前さんこそな」
頷いたマキタは窓に走った。外は屋上に向けて伸びるサーチライトで明るかった。建物の周囲には兵員輸送車、そして黒スーツの保安省暗殺部隊が屋上を見上げていた。ただ、この窓に向けられるライトも視線もなく、真下の建物中庭にも人の気配はなかった。
誰もこっちを見るんじゃないぜ。
マキタは屋上から垂らされたワイヤーを掴み、まずは7階を目指した。その窓に、最初に垂らしたワイヤーがある。
見送ったソールは豊かな胸にランチャーを抱え、クランゲージョを待った。
カラバが大きくよろめき、14階の壁に肩からぶち当たった。
脇腹に穴が空き、鮮やかな緑青色の体液が溢れ出した。しかしカラバはものともせず、アリーゼ・サロイを胸に庇い続けた。アリーゼが何か叫ぶが、耳を貸さない。
マルカムとルスト、侍女メリサとアントランも壁にぶつかるように身を寄せた。
階段を出て真っ直ぐのところにある、広い十字路からの攻撃は、小型ミサイルによるものだった。カラバの腹に食い込んだのは爆発の破片だ。6人の背後は瓦礫の山と化し、周囲には既に10人以上の暗殺部隊兵士が転がっていた。マルカムのSPAWNとカラバの腕力、ルストの投技がこしらえた死人たちだ。
ルストの身ごなしにはマルカムも恐れ入った。小柄な体をフルに使っての豪快な投技は、師匠レイバーの技のキレにも匹敵すると思われた。
そのルストが訊いた。「大丈夫かカラバ?」
アリーゼが同じことを訊いた。気遣わしげな優しい声に、止血バンドで腹を縛ったカラバは死に物狂いの笑顔で応じた。
下からクランゲージョで追い立て、上で待ち伏せ。まさに常套手段だった。そんな手など歴戦の戦士マルカムたちにはとっくにお見通しだった。待ち受けていた第1陣をたちどころにして片づけた彼らを見て、暗殺部隊も攻撃を変えた。十字路の両角に隠れての、小型ミサイルに切り替えたのだ。
「この辺は一般住人の住居だろう。ここでミサイルを使うとは…」
「ああ、さっき室内から悲鳴が聞こえた。コイケが知ったら、怒るぜ」ルストの言葉に、マルカムは頷いた。「マキタもだ」
「あいつ無事かな。通信が途中で途切れたが」
「あいつが銀河のあちこちに女の子たちを残したまま、死ぬわけがない」マルカムは通信機に囁いた。「おい、そっちは無事か?」
“ヒデえよ。”周囲からの攻撃は相変わらず屋上を削り続けているらしい。轟音と雑音の間から、クエンサーの声がする。“早く戻れ。さもねえと2度と飛べなくなるぜ。”
「すぐにでも飛び立てる準備をしといてくれ」
通信を切ったマルカムは、そっと角から顔を出した。即座に熱線銃が壁の角を削り取った。
「20人はいる」危うく顔半分を削られるところだったマルカムが首を振った。「また突っ込んでくる気だな」
「マズいな。カラバがこの調子じゃ、お付きの2人を護れない」
アリーゼたち3人を連れ階段を屋上まで駆け上がるのは無理そうだった。メリサはともかく、アントランなどは普段の運動不足が祟り、4階を上がっただけだと言うのに顔色が蒼白を通り越していた。クランゲージョがエレナの言う通り、味方にまで脅威を与えかねない代物なら、2台以上が建物に入ってくることはあるまい、マルカムとルストはそう踏んだ。
だから6人はエレベーターを奪うことにした。
ここ14階はエレベーターの連絡フロアでもあった。下から来るエレベーターはここで終点。その向かいに、ここから屋上真下まで上がれるエレベーターがあった。階段の出口からエレベーターのフロアまでは約50メートル。しかしフロアの手前すぐにある十字路を突っ切れないでいた。角の向こうには暗殺部隊兵士たちがひしめいているのだ。そこからの集中砲火だけではない。箱が来るまで暗殺部隊を食い止めていなければならないのだ。その間に下からのエレベーターが増援を運んできたら、それこそ最悪である。
シュッ、という音。マルカムが叫んだ。「伏せろ!」
爆発が瓦礫の山を増やした。メリサに加えアントランまでが悲鳴を上げた。ルストがメリサの上に覆い被さった。カラバは伏せなかった。アリーゼの盾になり、灼けた破片を背中全体に受け止める。
畜生…、マルカムが歯軋りした。容赦がない。マズいことに、連中にとってはアリーゼはVIPでも何でもないのである。仕方ないか…。「オーケイ」
ルストが顔を上げた。頬から血を流していた。そのルストに笑い掛け、マルカムは言った。「俺が突っ込む。奴らを食い止めてる間に、エレベーターの前に行け」
「ちょっと待て。その仕事は俺が…」
「新婚同様の妻子持ちにこんなこと任せられるか」
レイバーになら遠慮なく任せたがな…、マルカムは笑った。言葉に詰まったルストに追い打ちを掛ける。「それにな、俺のほうが生き延びる可能性は高いんだ」
確かに、頭部以外はほとんど機械であるマルカムなら…、ルストはその言葉の正しさを認めざるを得ない。「…死ぬなよ」
「箱が来るまで俺を待っててくれよ」
凄みのある笑顔でマルカムは言った。
カラバが歯を食い縛り、呻きを堪えていた。止血バンドの下から尚も溢れる血が緑の体毛をより色濃くし、アリーゼの白いドレスを緑青色に染めていた。立っているのもやっとのくせに、降ろして、私は大丈夫、走れます、と訴えるアリーゼの声には耳も貸さない。
「カラバ、もうすぐだからな」と声を掛け、ルストは左手に愛用のアレスター光線銃、右手に敵から奪った熱線銃を構えた。マルカムに頷く。
頷き返したマルカムが階段出口から飛び出した。右腕で顔を庇い、左腕のSPAWNを構え、走り出す。
ブオンブオンブオン…!
出力無制限のSPAWNが、廊下の壁を、床を、天井を震わせた。
今のミサイルで侵入者たちの抵抗を封じ込めたと思っていた暗殺部隊は不意を衝かれた。不用意に角から出ていた1人は胴を真っ二つにされた。直撃を食らった壁には数メートルの大穴が穿たれ、1面に亀裂を走らせた。顔を覗かせた兵士は頭を破裂させられた。角の背後に脳漿が飛び散った。
1秒で3人を失った暗殺部隊は、十字路の角の左右に散った。残った1人が小型ミサイルランチャーを構えた。マルカムは躊躇なくその本体にSPAWNを向けた。ランチャー毎爆発したミサイルは、角に散った兵士まで巻き添えにした。
部隊に動揺が走った。しかし恐慌を来す腰抜けはいない。開放機構相手の実戦で培った筋金が彼らを支えている。敵の武器の強力さを悟り、十字路から左右に一旦下がる。
その間に十字路を突っ切り、エレベーター側に隠れたマルカムは、左右に向けてSPAWNを乱射した。暗殺部隊兵士たちはドアや柱の陰に身を寄せ、直撃を避けた。
その隙を縫うように、両手に銃を構え、メリサを追い立てたルスト、アリーゼを抱えたカラバ、アントランとが駆け抜けていった。
暗殺部隊兵士たちも侵入者の意図を悟った。増援を呼ぶ通信が走り、マルカムへの反撃が開始された。ドアの陰、柱の陰から光線が走る。2人を吹っ飛ばしたマルカムだが、光線の多さに一旦角に身を潜めるしかなかった。早速腹に2つ、穴を空けられた。煙を上げる鋼の胴体を見下ろし、苦く笑う。轟音にちらりと視線を走らせると、ルストが下に通じるエレベーターに2丁の銃を撃ちまくっていた。箱の方はまだ上ってきていなかったが、それを吊り上げる重力ケーブルを切断するためだ。
上に通じるエレベーターの表示も動き始めていた。
エレベーター前に座り込み、震えながら泣いているメリサ。銃を撃ちながら、それを宥めるルスト。不貞腐れた顔をし、それでいてオロオロするしか出来ないアントラン。壁に寄り掛かり、喘ぎながらも、守護者の気魄に満ち、アリーゼに笑顔を向けるカラバ…。
角の向こうに気配が来た。それも左右同時に。考えることは同じだ。反撃覚悟で突っ込んできたのだ。しかも人数の利は向こうの方にある。
マルカムは角から飛び出しざま、斥候役らしい若い兵士の首筋に右拳の錐刀を突き立てた。即死した兵士の体を盾に、SPAWNを左右に撃ちまくる。
暗殺部隊も今度は慎重だ。乱射の前に立ち尽くす真似はしない。それに彼らには容赦がない。味方でも殺られたとわかれば平気で撃ってくる。斥候役兵士の死体には次々と穴が空き、マルカムの身体を縫う。死体の頭を貫いた熱線は眼球と脳漿を降らせ、頭蓋骨の破片を頬に突き立てた。光線の1本が耳を半分千切っていく。しかも攻撃は左右から来る。つまり死体を盾に防ぐ反対側からも。幸運にも後頭部にこそ食らわずに済んだが、背中にもどんどん損傷が増えていく。
急げ。長くは保たないぞ。SPAWNを左右に振りながら、マルカムはエレベーターを見遣った。降りてくる表示の遅く感じられること。
大型ライフルを持って飛び出してきた兵士が視界に入った。対峙。双方は同時に互いへの狙いを定めていた。発射!
ライフルを構えた兵士の上半身、そして盾にしていた死体が四散した。マルカム自身も全身に衝撃を食らって、仰向けに引っ繰り返った。生身の後頭部をしたたかに打ったが、構わず跳ね起き、左腕を構え…、
愕然とした。
SPAWNが左腕もろとも消え失せていた。
右腕で顔を庇うと同時に、10本を超える光線が胴を、胸を、脚を、肩を、次々に貫いた。
傷口から派手な火花が散り、穴だらけの身体から煙が上がる。マルカムはまたしても仰向けに倒れた。
マルカムが動かなくなったのを確かめ、暗殺部隊兵士たちがドアや柱の陰から現れた。後方から増援も加わった。30人はいる。エレベーター前にいる。用心しろ…。3人が銃を手に十字路に近づいてきた。1人がマルカムを蹴りどけようとした。
転がるマルカムがニヤニヤと笑っていた。
3人は15万ボルトの放電を全身に受け、悶絶した。
マルカムの持ち上げた右拳から突き出た錐刀の周囲を、白い放電がのたうっていた。どうにか上体だけ起こしたマルカムが、その右拳を前にかざす。
錐刀から迸った放電は廊下中を疾走った。たちまち6人を弾き飛ばす。同時に柔らかなブザー音が聞こえた。
エレベーターがようやく到着したのだ。
暗殺部隊兵士たちもそれに気づいた。しかし未だ放電が廊下の床から天井を走り回っており、迂闊に近づけない。動きを重視する暗殺部隊はコスチュームも軽装で、顔や首なども露出している。そこに電撃を受ければ一撃で倒される。
その彼らを見ながら、マルカムが立ち上がった。
颯爽と跳ね起きる、というわけには、流石に行かなかった。穴だらけにされた身体が言うことを聞かないのだ。それでも放電を続ける右拳をかざし、十字路の真ん中に立ちはだかって見せる。
だがマルカムの原子力電池にも限界はある。放電が次第に弱まってきた。遠巻きにする暗殺部隊兵士たちが、それに勘づかないわけがなかった。銃口が一斉にマルカムを狙う。
その瞬間、撃たれていたマルカムの膝の部分が捻れた。大きく体勢を崩す。
「頼むルスト!」
エレベーター側に向けて倒れたマルカムは、倒れ切る寸前、身体から頭部を射出した。
彼の生身の頭部は、頸から直径20センチのカプセルに繋がれ、カプセル内には主要臓器やその代役の人工臓器、脊髄組織とが収まっている。撃ち出された頭部とカプセルはエレベーター前にて待つルストに向かって飛んだ。謂わば大砲から撃ち出された頭突きみたいなものだったが、ぐううっ、と息を絞り上げられながらも、剛直に鍛え上げられたルストの腹筋は見事にそれを受け止めた。ルストが箱に飛び込むと同時に、カラバに抱えられるアリーゼが、扉の開閉ボタンに掌を叩きつけた。
エレベーターの扉が閉まるブザー音が鳴った。マルカムの体はその場に完全にへたり込んだ。
何が起きたのか咄嗟には理解できなかった暗殺部隊兵士たちは、エレベーターを撃つのも追うのも忘れ、マルカムの“脱け殻”を気味悪そうに見下ろした。仕掛けに気づいた1人が腹立たしげに、脱け殻を蹴飛ばした時。
高性能爆薬を仕込まれていた脱け殻は大爆発を起こした。
ビームランチャーを構えたまま、体をくの字に折り曲げたソールは大きく咳き込み、黒い血の塊を吐き出した。
折しも階上のどこかで大爆発が起きたところだった。腹と胸からは鮮血が噴き出し、左肩から顔までの変装は焼けて剥げ落ち、骨ばった素顔が覗いていた。鬘の毛は燃え、自毛は皮膚もろとも抜け落ち、左耳はなくなっていた。
クランゲージョはまだ生きていた。赤と青の眼がソールの動きを捉えていた。機関砲とレーザー、6本の脚までは潰したが、まだ攻撃の意欲は満々だ。ソールが油断して近づくのを待っているだけだ。
誰が近づくものか。よくぞまあ、お前のような悪意と執念にまみれた自動機械を造り上げたもんだと思うぜ。保安省の長官はある種の偏執狂だという噂を聞いたが、本当だったらしいな。
しかしそんな恐ろしい殺人機械に、正面から立ち向かった俺も、なかなかどうして、大したもんじゃないか。
まあ、マキタやマルカムのように鮮やかに、とは行かなかったが。所詮、下調べ専門の潜入工作員に過ぎない俺だ。当然と言えば当然なのだが。それでもこいつにトドメを刺すくらいは出来るだろう。
これで失態の埋め合わせになればと思う。
悔しいのは潜入以来、ずっと俺の背中を見ていたあの視線の正体を確かめられないまま死ぬことだ。自他共に認めてきた己の技術・技倆への自信を根底から引っ繰り返されたままなのだから。
やはり恐ろしい星だった、ここは。あの視線が機械的監視によるものなのか、それとも有機的な生命によるものなのかは曖昧なままだったが、要はそれがこのクランゲージョとかいう殺人機械と一体だったと思うと、その執拗さはただならぬものだった。伝説の傭兵にさえ汚点をつけたというこの星の真価が、今はわかる。
この星にはやはり恐ろしい奴がいる。
成功してくれよ、みんな。
ソールは内ポケットに仕舞った自決用の高性能爆薬の起爆装置をONにし、立ち上がった。奴に鼻があったら、それを絶対明かして見せてくれ。俺の誇りと実績とを打ち砕いた奴に、必ず一矢報いてくれ。
ソールの接近を見て取ったクランゲージョが、思いがけない敏捷さで身を起こし、脚の1本を振り上げた。ソールもビームランチャー砲口を、その脚の付根に向けていた。覗いた素顔には苦笑があった。
「しまらねえよな、こんな格好でくたばるなんてよ…」
しかしこの格好で同性たちの視線を集めるのに、何やら不思議な快感があったなどと白状したら、マキタの奴なんて俺に2度と近寄らなくなるだろうな…。
…2つ目の大爆発は建物を揺るがした。階段でおこったそれは、エレベーターを壊され、侵入者たちを足で追うしかなかった暗殺部隊の行く手を、完全に塞いだのであった。
魔王への挑戦 その6
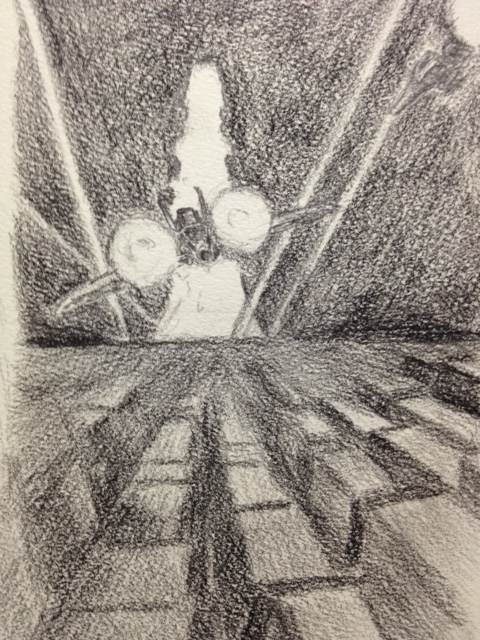
(6)
宿舎の住人――内務省の職員――たちが殺到したため、エレベーターは各階で停まった。押し合いながら入ってこようとする住人たちを、エレナは銃で脅して足止めしなければならなかった。こんな様子では1階フロアもパニックになっているに違いない。それ以上に、保安省暗殺部隊と鉢合わせする可能性も高かった。
エレベーターを2階で停め、雪崩れ込んでくる住人たちの頭上を飛び越えたエレナは廊下に飛び出した。人混みを掻き分け走る。何人かが見慣れぬ服装に気づき、「侵入者だ」の声を上げたが、ほとんどの住人に耳を貸す余裕はなかった。
窓に駆け寄ったエレナはガラスを叩き割った。下の通りでは、保安省の追跡装甲車3台がサーチライトの光線を屋上に突き上げていた。ライトばかりではない。視線も、光線も、銃弾も、全てが屋上に向いていた。
エレナは躊躇うことなく、窓から飛び降りた。
全身筋肉のバネであるエレナに4メートルの高さなど衝撃にもならない。ほとんど音もなく地に降り立ち、走り出す。サーチライトの光芒の生む闇の深さに紛れ、裏通りに入る。
その向こう、ビルとビルとに挟まれた空き地には、ソールが言った通り、誰もいなかった。近づいてもきていなかった。
――どういうわけか、ここには誰も来ない。理由はわからないな。墓地? そうかもなあ…。
エレナは空き地に走りこむや否や、今は土色に染まったシートを撥ね上げ、グレイハウンドの円蓋を外部操作で開け、コクピットに飛び込み、エンジンを掛け…、以上を一挙動で済ませてしまう。
3次元ジャイロコンパスが点映、エンジンが低い唸りとともに回転を上げ始めた。全武装チェック。エドランド・ビームマシンガン〈エネルギー充填済み〉、無薬莢自動追尾ミサイル〈残弾なし〉、重イオン粒子砲〈出力68パーセント〉。
充分とはとても言えそうにない。だが、構うものか。エレナは回転を上げるエンジンに合わせ、スロットルを開いた。
V-TOLが唸り、グレイハウンドはふわりと宙に浮いた。
表通りにいた保安省兵士たちが気づいた。光芒が右へ左へと動き回り、光線・銃弾が屋上から逸れた。彼らにしてみればグレイハウンドの離陸は幽霊の出現かとも思えただろう。まさに音も気配もなく。
慌てつつも追跡装甲車は動き出した。砲座が回る。
エレナは容赦なく、引き金を絞った。
1分間4000発を発射するエドランド・ビームマシンガンが、そのエネルギーを吐き出し始めた。
咆哮2秒で、車輌3台の装甲は紙のように貫かれ、燃えたプラスチックのように捲れ、縮み、赤熱化した。高熱は即座にエンジンと火器を誘爆させる。爆発は鉄塊の雨を降らせ、周りの兵士を薙ぎ倒す。
充分だ。エレナは頷いた。充分に戦える。
操縦桿を引いた。グレイハウンドは新しい獲物を求め、ゆっくりと大通りの方に動き始める。
…通信機がソールの起こした大爆発を中継し、自分が飛び出した窓が炎を噴き出した時、マキタの眼下、2階の窓からエレナが飛び出した。装甲車3台と兵士たちの前で呼び止めるわけにも行かないうちに、エレナは闇の中に消えた。と思いきや、グレイハウンドが動き出し、立ちどころに装甲車と兵士とを全滅させてしまった。四散した装甲車の鉄塊がいくつも体をかすめ、宿舎ビルの壁に食い込んだ。
グレイハウンドが消えたと同時に、マキタは地上に飛び降りた。エレナのように軽やかにとは行かなかったが、それでも豹のような俊敏さでジンリッキーへと走る。表の大通りから銃声、砲声、甲高いビームマシンガンの咆哮と爆発音とが立て続けにに聞こえ、すぐに止んだ。
マキタはジンリッキーのコクピットに体半分を収め、耳を欹てた。聞こえるのはグレイハウンドの低いエンジン音のみ。
それが突然、つんざく轟音に変わった。たちまち遠ざかっていく。
思った通りだ。
マキタはコクピットに体を沈め、エンジンを作動させた。
冷たい真空中ではないだけに、エンジンはすぐに回転を上げた。マキタは操縦桿を一杯に引き上げる。反重力ホーバー作動。
ジンリッキーは一気に、内務省宿舎ビルの上に上昇した。屋上のライトニング装甲車を見下ろす形になる。4方から撃たれすぎた屋上は今や崩落寸前という状態、装甲車は破片や瓦礫に埋め尽くされそうになっていた。装甲車の上に立つのはクエンサーだ。高精度狙撃銃を抱えたまま、呆けたように市街を見つめていた。
グレイハウンドは、その視界の彼方に去ったのだ。
そしてその遥か遠く、地平線の上に、青白い照明に浮かび上がる塔が見えた。一体ここから何キロ離れており、何キロの高さがあるのだろう。あれが…、
総統庁…。
マキタは通信機に叫んだ。「マルカム、ルスト、無事か!」
“マキタか。今どこだ?”
「建物の外だ」
“ソールがやられたらしい。”
「知ってる。だが、そのお陰でクランゲージョもくたばったみたいだ。それに、包囲もひとまず解かれた」表裏の通りにはやってきた8台の装甲車の残骸が散らばっていた。「エレナが…」
“こっちも一応無事だ。”ルストの声。“アリーゼ・サロイには傷1つついてない。”
そうか…、マキタは腹の底から息を吐きだした。これで仕事は完了する。ならば、後は…、
「エレナが包囲網をぶち破った。今、総統庁に向かってる」マキタはスロットルを開いた。見上げるクエンサーの姿がたちまち遠ざかる。「あいつ、囮になる積もりだ。先に脱出してくれ。チャンスは今しかない」加速とともに、宇宙空間とは比べ物にならない重力の抵抗。大した速度を出していないうちから、体がシートにめり込んだ。「俺はエレナを追う」
“ちょっと待てマキタ!”
「俺はエレナを見捨てるわけには行かない」
マルカムが息を呑む気配がした。ルストが叫ぶ。“止めろマキタ、俺がマードックに怒られる!”
「またな!」
内務省宿舎ビルは既に後方に遠い。引き返す積もりもない。目に映るのは地平線の総統庁の塔のみ。
行ってやろうじゃないか。
眼前に点った各種照明が、闇を駆逐するかのように広がっていった。光の列は、油の上を走る火のようにたちどころに地平線の彼方――あの塔の下まで辿り着いた。
真夜中の首都タキアスが目覚めた。
2機の侵入者が、眠っていた首都防衛網を目覚めさせたのだ。
…広い道路の左右を照明が走る。それを追いかけるように、グレイハウンドが疾風の如く驀進する。
路上には人っ子1人いない。グレイハウンド、その爆風の巻き起こす風、吹き飛ばされる塵芥、そして街頭に設置された、グレイハウンドの動きを追う数百台の監視カメラが動くのみ。
視界の遥か彼方に、青白く輝く光の塔が聳え立っている。総統庁を実際に目にするのは初めてだ。ここに同志たちと一緒にこうやって、乗り込んでくるのがエレナの夢だった。
今、エレナは1人だった。
総統庁の手前で動くものが見えた。防衛システム発動だ。塔周囲のあちこちに、対空粒子砲砲台がせり上がってきた。塔上空に羽虫のように群がってきたのは、首都防衛部隊の戦闘機隊らしい。砲塔が、戦闘機が、臨戦態勢でエレナを待ち構えている。目のいい彼女にはディスプレイを使わずとも、戦闘機やカメラの1台1台までが見て取れた。
戦闘機は例のシーザンス戦闘艇を大気圏内活動用に小型化したものだ。見える限りで70機はいる。連中の相手をしながら総統庁に突入するのは至難の業だろう。だが、当たって砕けてやるだけだ。
開放機構最後のパイロットの戦いっぷりを存分に披露してやる。
エレナの全身に、久々にたぎるものが溢れた。
唯一の心配は、マキタたちが上手く脱出できるかどうか。多分大丈夫だろうとは思う。彼らは並外れたプロなのだから。宿舎ビルの周囲の敵は片づけた。デビアスへの無謀な突撃によって作った借りは、あれで返せたと思う。
やっとのことで、マキタにもお礼が言えた。
素直じゃないんだ、あたしは。有難う、の1言を伝えるのに、どれだけの時間を要したことか。
思えば今やろうとしている特攻も、マキタの独白を聞かなければ実行を思いつきもしなかったかも知れない。漠然と、首都に殴り込むんだなどと夢見てはいた。しかし仲間のほとんどを失った今、そんなことは最早夢想以上の何物でもなくなったと思っていた。
そんな時に聞いた、マキタの言葉。全てを失った今、自分に出来る残されたことは他にないと思い切る引き金ともなった。
マキタ…。
子供みたいな笑顔を浮かべる人。
マイスコルとはまるで違ったタイプに見えて、やっぱりどこかで繋がっていた人。あのひたむきな眼差し…。
「………!」
眼前を覆った閃光とつんざくような轟音が、エレナを現実に引き戻した。全身を使って操縦桿を倒す。主翼すれすれを粒子砲光線が通過していった。機体が衝撃波と熱風に煽られる。
眼下は住宅街だと思われた。その高層ビル屋上や路上、窓際などからも、対空砲座が顔を覗かせ、グレイハウンドの行く手に砲口を向けていた。
粒子砲砲座が動く。レーザー砲座も。一斉に撃ち出されたミサイルが尾を曳いて滑空する。全てがグレイハウンドに迫る。
エレナは慌てもしなかった。それどころか両眼が吊り上がる。この程度の防衛網であたしの足を引っ張れるとでも…。
嘗めるな。あたしを何だと思っている!
狙いをつけた筈の光線は全て外れ、上空に消えた。宇宙・地上兼用の広い翼がスピンとともに突風を巻き起こす。我が目と計器を疑う砲術士たちの頭上を、稲妻の疾風が通過して去る。
大気圏内の重力の大きさは、戦闘に足枷を嵌める。どうしても加速が限られてしまうのだ。その分、無駄な動きは抑えられる。
今のエレナにとってラドンの重力は足枷どころか、最高の舞台装置にさえ思える。全身に受ける重力の、なんと均等なこと。翼の切れのよさ。数区画20キロにも及ぶ防衛網からの粒子砲全光線を、グレイハウンドはことごとく回避した。
砲座の回頭はとても追いつけない。しかしミサイルだけは執拗に追ってくる。頭に血の上るエレナはそれらを引きつけるだけ引きつけて、防衛システムを擁するビルの1つに全弾叩き込んでやろうかとも考えた。同時に手足はそれを実行に移していた。
が…、
それは止めろ!
その声に慌てて機首の向きを変えたエレナは後部を映すディスプレイに目を走らせた。機体が失速し、光線に捉えられそうになる。
“建物だけは傷つけるな! この辺は住宅だ。中に逃げ遅れた奴らがいたらどうする!”
マキタの、声…!
“非戦闘員だけは絶対に巻き込むな!”
はるか後方から光線が伸びた。エレナは機を垂直に反転、上昇させた。光線はグレイハウンドの尻に迫っていたミサイルの1発に命中、他を次々に誘爆させた。
爆発の炎を貫いて、ジンリッキーが出現した。
流石、同じパイロット。マキタはあたしの行動を読んでいた…、などと感心すると同時に、腹が立ってきた。せっかく逃げ道を作ってあげたのに…、
あの『有難う』、あれは最後だから言えたのに。それを口にするのに、どれだけの苦労があったと…。「このわからず屋!」
“何だよいきなり。”
ジンリッキーはグレイハウンドの代わりに、目前のビル街防衛網に突っ込んだ。唸りを上げる小口径原子砲の光弾は、粒子砲とレーザーの砲座だけを過たずに吹っ飛ばす。
上昇していたグレイハウンドが戻ってきた。2機が並んだ。
比翼の鳥のように。
「どうして逃げなかったのよ!」
“ここまで来て、逃げろはないだろ?”
「冗談じゃないわよ! あたしが一体何のために飛び出したと…」
“囮が1機である必要はないだろが。”
エレナは言葉に詰まった。マキタの声の快活なこと。“それになあ、前にも言わなかったか? スペースサルベイジャーズは仲間を決して見捨てないんだ。”
仲間…。
エレナは口の中で呟いた。唇が緩んだ。憤りが消えた。
「…あなたって、正真正銘の馬鹿よね」
“マジメな口調でその台詞を言うな。”
「だって他に言い様がないもん。あたしにつき合って、命を捨てる気?」
このまま帰れば、名声も大金も思いのままだろうに。
どうしても夢にこだわるのね?
「サビア・サロイが泣くわよ」
“うるさいな。”マキタの声が苛立った。“人を散々バカ扱いしてくれたな。帰ったら1度じっくり話をしようぜ。”
エレナは笑い出した。やっぱりあなたって優しいんだ…、鼻と喉を妙にくすぐる温かいものに、胸の奥が満たされる。仲間。こんな当たり前の言葉が重く、かけがえなく胸に沁み込む…。
エレナはそれを隠すように、威勢よく言った。「遅れるんじゃないわよ、お馬鹿さん!」
“そっちこそな! どっちが先にブレハム・グランザーと対面するか、競争と行くか!”
総統庁の周囲を覆っていた戦闘機隊が集結し、隊列を組み直すのがわかった。もちろんこちらに向かってくる気だ。
「マキタ…」
“…ん?”
「生きて帰れたら、殴られた時のお礼を一発食らわしてやるからね」
“何じゃあそりゃあ!!!”
「嘘よ」マキタの反応が思った通り過ぎて笑ってしまう。「もし、生きて帰れたら…」
エレナは次の言葉を呟くと同時に、スロットルを全開にした。
「帰ったら、何だって?」
訊くと同時にマキタはジンリッキーを横に倒した。
前方の戦闘機隊に気を取られ過ぎていた。2機は新たな防衛網区画に入っていた。粒子砲の光線が本数の数だけ機体を揺さぶった。マキタの胃袋は縮み上がった。それに対してグレイハウンドの動きの鮮やかなこと。光線が何本何十本走ろうが、全てを悠々と、且つ的確に避け続ける。
流石、エレナ。
グレイハウンドが先行した。戦闘機を迎撃する積もりだ。マキタは下方に視線を走らせる。戦闘機隊とグレイハウンドが遭遇するであろう空域の真下にて、防衛システムの火砲群が動き始めていた。戦闘機隊とぶつかっている最中に狙い撃つ気だ。
マキタはジンリッキーを降下させ、防衛網の目の前に突っ込ませた。
原子砲が唸る度に、ミサイルを除く砲座の1つ1つが吹き飛ばされていく。スコープが数十分の1秒捉える標的に、指だけが正確に反応する。文字通りの一瞬に、決して遅れを取らない。睡眠不足が呼び込んでいた身体と心の淀みも既にない。心身の切れは絶好調だった。
吹っ切れたからだ。
もう何の悩みも迷いもなかった。今からブレハム・グランザーと対決しに行くのだ。この銀河でたった1人、親父を打ち負かした男に戦いを挑む時がやってきた。
ずっと夢見てきた。引き摺るコンプレックスは重かった。何をやっても勝てた試しのない、あまりに巨大な親父の影を、いつも自分の背中に、他人の視線の中に感じていた。いつの日にか必ず追い越す、その誓いがあったからこそ生じた疑念。親父のやらなかったことではなく、出来なかったことに挑まなければ…。
その時が遂にやってきたのだ。
悪いな、コイケさん。命令に背いて。でも、アリーゼ・サロイも救出できたことだし、後は上手くやってくれ。
生きて帰れたら…、マキタはそう言ったし、エレナもだ。しかし実は、今のマキタに、帰ってからのことなど考えもつかなかった。諦めたわけではない。充実に満ちた全身に、そんな思いなど入り込む余地がなかっただけの話。解放感などという生易しいものではない。まさに今の彼は撃ち出された銃弾だ。引き返すなどあり得ない。
標的にぶち当たるまでは。
遥か上空ではグレイハウンドが、先行してきた20機相手に戦闘を開始していた。マキタはニヤリと笑い、ジンリッキーを僅かに減速させる。それを隙と見た防衛網が、無傷のミサイルポッドからミサイルを一斉に射出した。
マキタはそれを待っていた。
ジンリッキーが急上昇する。ミサイルを引き離さず追いつかせずの距離を保ったまま、ほとんど垂直に上昇、次第にスピードを上げる。久しぶりに感じる大気圏内飛行の重力が身体に心地よい。ミサイルも速度を上げるが、もちろんジンリッキーの方が速い。
20機の後方からもう20機が加わった。グレイハウンドに接近しようとしている。エレナがそれを許す筈もない。猛然たるダッシュ。電光のような曲折。既に7機を戦闘不能に陥らせている。撃墜も出来ただろうが、墜落する敵機がこの市街地を巻き添えにするのを避けたのだ。マキタにはそれが嬉しくて仕方がない。
それにしてもエレナはまさに不死身であった。今の彼女には体力の続く限り、敵はいまいと思われた。マキタの知るどんなパイロットをも足元に近づけないテクニック。銀河最強を名乗っても遜色はあるまい。
もしかするとこの瞬間、噂に聞いた親父のテクニックをも、彼女は凌いでいるやも知れないとさえ思えた。
「エレナ、塔に向かえ!」
返事の時間すら惜しみ、グレイハウンドはビームマシンガンを撃ちまくりながら反転した。総統庁に機首を向ける。
戦闘機隊もすぐに反応する。しかし差が開いた。戦闘機がなまじ高性能だったのが災いした。重力過負荷制御機能が彼らの転針速度を邪魔したのだ。それに無理な加速も。距離は開く一方だ。
グレイハウンドに追いつけないまま、必死に機を駆る彼らが市街地上空を抜けたと同時に、ジンリッキーが背後から割り込んできた。強引に間を擦り抜け、前方のグレイハウンドと並ぶ。
2機が並んでも戦闘機隊は攻撃できない。外せば光線は総統庁に飛び込むからだ。
その2機がいきなり機首を反転させた。
戦闘機隊は思わず逆噴射で速度を落とした。その尻に、ジンリッキーを追ってきたミサイル群が咬みついた。
戦闘機隊が市街地外――官庁街の外れらしい――に墜ちていくのを確認したマキタは雄叫びを上げた。エレナもグレイハウンド円蓋から、腕を振り上げてそれに応じる。
2機はそのまま再度転針、総統庁に進路を向けた。対空砲火の勢いが増し、光線の数、密度も段違いに濃くなった。新たな戦闘機隊が前方に待ち受けていた。
しかし、2機を阻止するには至らない。
ほとんど速度を緩めることなく、神業に近い転針を繰り返し、2機は総統庁に向かって飛ぶ。
その塔の巨大さと言ったら…。
ライトに照らされていなければ、風雨に削られた細い岩山にも見えただろう。1000メートル近い高さがある筈だ。青白く、且つ決して派手に飾り立ててはいない、天を衝く城塞。
機体が僅かに振動した。幾層にも張られた対エネルギー兵器防御シールドの最初の1層を越えたのだ。遂に絶対防衛圏の中に入った。俺は、ここまで…。
粒子砲光線の雨を避け、エレナを真似た螺旋飛行でミサイル、戦闘機隊のレーザーを掻い潜り、ジンリッキーは飛ぶ。目前に戦闘機隊第3波が迫る。エレナの豪快な喚き声とともに、グレイハウンドが突っ込んでいく。マキタも遅れじと操縦桿を引き絞る。
俺は遂にここまでやってきたのだ。
親父、見ているか!
初めて、そしてとうとう…、
俺はあんたと同じ土俵に立った!
総統庁周囲30キロは、道路と芝しかない、だだっ広い空き地でしかない。
その広大な敷地は、総統庁の権威の象徴に見えなくはない。しかしこの星の総統は、見栄や権力誇示のために土地を徴用したりはしない。総統庁への攻撃が為され、対エネルギー兵器防御シールドは役に立たなかった際、市街地と市民に被害を出さないため…、というこの総統命令は、市民には伏せられている。
蜘蛛の巣状に伸びる道路と芝の各所に、対空粒子砲の砲座が点在していた。
もちろん数も多い。空き地の外から総統庁正面までの直線上だけでも、50基以上の砲座がその砲身を天に向けている。今、その全砲座が内務省首都警備隊の指示に従い、狙いを一点に定めていた。
標的は2機の侵入者。
砲術士たちは手と額に汗して、固唾を呑んで待ち受ける。
つい今し方、2機が首都防衛戦闘機隊第2、第3波と交戦、これらを突破したとの報告があった。市街・官庁街の砲座群は侵入機の驀進に追いつけなかったとも。
ここで食い止めるしかないのだ。
砲術士たちは緊張の中、待った。侵入機の動き、速度はレーダーが逐一捕捉している。経路も割り出している。突入してきた瞬間に全砲門が弾幕を張る。その中心に突っ込めば、2機も終わりだ。自分たちがコンピューターの指示に遅れさえしなければ…、
必ず阻止できる。
光線が疾走った。粒子ビームが交錯した。何十本ものエネルギーが飛び交い、多くは虚空に消えた。そして閃光が走った。
やった!
だがそれは、交錯したエネルギー衝突が引き起こした閃光に過ぎなかった。砲術士の幾人かがそれに気づいた時には…、
2機の侵入機はほとんどの砲座の背後、総統庁正面にて逆噴射を掛けていた。
馬鹿な! 砲術士たちは我が目を疑った。速度、方向、全て指示通りではなかったか。
しかし、外した。答は1つしかなかった。2機が戦闘時以上に速度を上げて突入してきたのだ。並の人間の耐え得る加速を平気で超えてしまう2機を、コンピューターさえ侮ったのだった。
2機のうち、細長い戦闘機――ジンリッキーが、機首の原子砲を撃ちまくった。
最初、芝の空き地に数本の火柱を上げた原子砲光弾が、総統庁の壁に命中し始めた。4発、5発、6発…。3重層合金の壁材も、ピンポイント射撃の前に屈した。轟音とともに大穴が空く。
そのすぐ後ろで旋回したグレイハウンドの、ビームマシンガンが唸りを上げ始めた。我に返った砲術士たちが慌てて向きを変えようとする対空砲座の隔壁に、ビームマシンガンは面白いように穴を穿っていく。
グレイハウンドが1回転し終えた時には、2機を狙っていた付近の対空砲座47基は全て沈黙させられていた。
それを尻目にグレイハウンドは、ジンリッキーが滑り込んだ壁の大穴に、ゆっくりと入っていった。同時に大爆発が空き地を揺るがした。47本の火柱が噴き上がる…。
明らかに開放機構基地の格納ドックより広い大ホールに入ったグレイハウンドは、そこでエンジンを停め、V-TOLでのホバリングを始めた。こう言った小技が実は苦手なエレナだが、今は随分簡単にやってのけられた。肩の力が丸っきり抜けているからだ。全身には力が漲っていると言うのに、心は信じ難いくらい落ち着いていた。これは、安心感?
たった独りでの特攻の積もりが、側に仲間がいてくれたから…?
そう、仲間。全幅の信頼を丸ごと受け止めてくれそうな響き。自分のすべてをかなぐり捨てても何とかしてやりたいと思える存在。これまで自分にそんな仲間がいただろうか。そう考えると、何となく項垂れそうになる。
厳しい訓練に耐え、ともに戦いを挑み、生死の境の彷徨をも分かち合ってきた開放機構の同志たち。だが彼らとは信条の上、組織の1員としてしか結びついていなかったのではないかという思いが、今はある。
それが証拠に、エレナには心から信じ合い、支え合えた同性の友人は1人もいなかった。強くならねば…、ただそれだけを目指し、父と母の人生を踏襲しようとするエレナに、同性の同志たちは驚嘆し、また呆れてもいた。
“あんた真面目すぎるよ。もっと気楽に行ったら?”
冗談ではない。父と母は戦士だった。自分も戦士として生き、そして死ぬ。そのために強くなりたいと願い、己の非力に憤り、焦りもした。安易な恋に落ち、いとも簡単に初志を放り出す連中に侮蔑さえ覚えたこともあった。
あたしは違うぞ。
あたしは女である前に戦士なのだ。
その思いが間違っていたとは思わない。変える積もりもない。だがその結果、同志たちと信条以外の繋がりを育めずに終わったのも確かだった。
でも、今は…、
エレナはグレイハウンドをジンリッキーの横に着陸させようと下を見た。
下では既にマキタがジンリッキーを砦に、内務省の警備隊と撃ち合っていた。いや、正確には警備隊からの一方的な攻撃だった。兵士たちの手前には、逃げ遅れた総統庁の職員――非戦闘員数名が蹲って震えていた。夜遅くまで真面目に仕事をしていたせいで災難に巻き込まれたのだろう。警備兵たちは彼らを盾にでもするかのように、その背後からジンリッキーに攻撃を仕掛けていた。
エレナの頭に血が上った。マキタが非戦闘員を撃たないことに気づいたのだろうが、それをいいことに…!
グレイハウンドはホバリングしたまま、機首を警備隊に向けた。
気づいたマキタが何かを叫んでくる。もちろん聞こえない。でも、言いたいことは…。
大丈夫、わかってるわ! エレナは躊躇なく引き金を絞った。
エドランド・ビームマシンガンは吠えた。
灼け爛れた壁材の破片が降り注ぐ。警備隊の大半はそれを背後から食らってぶっ倒れた。残った連中はマキタが射殺する。手前の非戦闘員たちが無事なのを確認し、エレナはグレイハウンドを下ろした。
シートの背後から、古めかしい重火器を引き摺り出す。これまたエドランド社製車輌搭載火器ミニ・コマンド機関砲の銃身を切り詰め、クッション付き銃床を取りつけて、持ち運べるようにしてある。もっとも重量は18キロにも及ぶ。マキタかエレナの筋力なしにはとても扱い切れないだろう代物だ。
50発装填の筒型弾倉25個を収めた弾帯2本を無造作に両肩に引っ掛け、機関砲を担ぎ、エレナはマキタの前に飛び降りた。
「馬鹿野郎、ヒヤヒヤさせる…」額の汗を拭いながらマキタは言った。「もし手前の連中に当たったらどうする気だったんだ」
「そんなドジ、踏まないもん」エレナは事も無げに言ってのける。「あたしの腕を信じてないな?」
「それとこれとは話が別だ」
「あなたはゲリラにはなれそうにないねえ」
「ゲリラとテロリストには、いつから境界線がなくなったんだよ」
笑っているマキタの精悍な横顔を、エレナは見つめた。そうだ、今あたしにはこの人がいる。「さあ、行こうよ!」
その楽しげにも聞こえるエレナの声に、マキタの方が呆れた。ピクニックにでも行く時のような声だ。エレナの抱える機関砲に目を遣り、眉を顰める。エレナはそれに応えるかのように、機関砲を左手だけで軽々と持ち上げて見せる。それにはマキタも笑い出した。
「行くとしますか!」
未だ震え、命乞いする非戦闘員たちを一顧だにせず、2人は走り出した。マキタは走りながらハンディキャノンをホルスターに収め、警備兵の落としたビームライフルを足先で掬い上げた。作動を確認し、エネルギーパックも奪い、エレナに頷いて見せる。
エレナも頷き返した。何の曇りもない笑顔で。
政府軍陸上部隊正規兵、内務省首都警備隊、保安省特殊部隊。総統庁に駆けつけられる距離にいた、武器を持つ兵士という兵士が、侵入者2名を排除するために駆り出された。総数は300人に達した。上手く行けば完璧な包囲網も完成していただろう。
しかし包囲網は完成しなかった。内務省の警備兵と政府軍の正規兵たちは、からっきし役に立たなかったからだ。銃声と跳弾の音を聞いた瞬間に、大半が浮足立ってしまったのだ。
訓練は怠りなくやっている。だが、永年の首都の平和は訓練そのものを形骸化し、政府軍の陸上部隊や警備隊兵士たちを生死を賭けた緊張から遠ざけ、銃声1発でパニックに陥るような木偶に変えてしまっていた。
総統庁の各通廊は、上下左右の幅が恐らく20メートル以上あった。通廊と言うよりは長大なトンネルだ。長引く銀河大戦で計画の頓挫している銀河超特急のプラットホームにもなりそうだった。
その中央に仁王立ちになったエレナが、弾帯から引き抜いた筒型弾倉を機関砲に叩き込んだ。遊底を引きざま掃射を開始する。
腹に響く重低音の銃声が切れ目なく続く。その合間を縫うように、床に落ちる空薬莢がカチンカチンカチン…、と涼しく乾いた音で拍子を刻む。弾丸は小さいが高速、しかも弾頭にノーザン・テクタイトの芯が埋め込まれた徹甲弾だ。壁を削り、亀裂を走らせる。兵士の戦闘スーツに易々と穴を空け、胴体を千切る。
1弾倉50発を撃ち尽くす前に、通廊に押し寄せていた兵士たちの大半は足元を見失い、右往左往逃げ惑う始末となった。
役立ったのはやはり、政府軍の中でも開放機構相手に実戦を経験してきた艦隊勤務の部隊、そして保安省兵士たち。数人毎に隊列を組み、右往左往するだけの内務省兵士が撃たれる度にその間隙を衝いて、僅かずつ接近する。もちろん犠牲も出たが、謂わば波状攻撃を繰り返すことで何組かの隊が、反動で銃身が跳ね上がりがちになる機関砲弾幕の内側に潜り込めた。
それを見届けたエレナは猛ダッシュで通廊隅の柱の陰に飛び込んだ。代わりに飛び出したのはマキタだ。接近組に向けてビームライフルを掃射する。そのマキタが引っ込んだ時には、せっかく接近できていた兵士たちも全滅していた。また最初からやり直しだ。
その前にマキタとエレナは広い通廊を、奥へと走り出していた。
政府軍・保安省の連合部隊もすかさず後を追う。背後からの攻撃を恐れて蛇行する2人に比べ、追う側の足は当然速い。たちまちにして40人ばかりが2人のすぐ背後に殺到する。中には軽量装甲に身を固めた歩兵も混じっている。攻撃が始まる。
マキタとエレナは再び、通廊角とドアの陰とに飛び込んだ。
エレナがドア陰で立ち上がる。軽量装甲など機関砲の徹甲弾の前には紙も同然だ。通廊に兵士たちの屍が積み上げられる。しかし1弾倉が空になる頃に、接近してくる連中が出る。それを入れ替わったマキタがライフルで片づける。息をもつかせぬ交替、半瞬の狂いもない呼吸の一致。打ち合わせも何もない。あるのはただ、一体感だけ。
3度の交替でまたも接近組を殲滅した2人は、腕を振り上げ歓声を交わし、走り出す。それだけで充分だった。次に何をすべきかも、その1声だけで通じ合った。
慌てたのは政府軍・保安省の連合部隊だ。2人と思って高をくくっていたところがとんでもない。侵入者2名は研ぎ澄まされた突撃歩兵1個大隊に匹敵した。
既に60人を片づけ、2人は2階に進もうとしている。いや、もう階段を上り始めている。
連合部隊は完全に後れを取った。エレベーターを止め、ロビー大ホールを始め、閉められるあらゆるシャッターを下ろした。しかし階段は緊急脱出避難路も兼ねており、シャッターは下ろせない。侵入者対策に各通廊に窓をつけなかったことも裏目に出た。エレベーターで先回りしたところで、20人だか30人だかの部隊で果たして2人を止められるかどうか。もちろん総統閣下のいるこの中に、クランゲージョなど持ち込めない。殺人ナノマシンを総統庁に流し込もうかという提案も出たが、認識バッジも持たずに逃げ出した総統庁職員がいたりしたら、それこそ彼らを巻き添えにしてしまう。与えられた権限は大きい代わりに、失態には政府内から特に厳しい目を向けられる保安省だ。迂闊な真似は出来なかった。
仕方ない。長官に連絡しろ。こうなったら…、
…2階でも死闘は続いた。2人は敵を引っ掻き回すだけ引っ掻き回し、3階へと駆け上がった。マキタが叫ぶ。「長いなあ!」
「まだ3階だよ! 総統執務室は最上階なんだからね!」
「このタワー、何階建てだ?」
「121階!」
「なあ、エレベーター使わないか?」
「さっき見たでしょ? 止められてる。さあ、頑張って走れ!」
「うえ~」
2人は同時に振り返った。そして同時に、通廊の左右に跳ぶ。
2人のいた床を、太いビーム砲光線が切り裂いた。
立ち上がったマキタは一瞬目を疑った。エレナもだ。広大な通廊の彼方に、首都防衛部隊の戦闘機が出現したのだ。逆噴射とホバリングで機を巧みに操り、緩慢な速度で近づいてくる。2人は顔を見合わせた。兵士では追いつけず、装甲車輌を運び込むわけにも行かなかった総統庁内部に、誰かが詰腹を切る覚悟でもして、戦闘機を呼び入れたのだ。
しかしそんなことになるくらいなら、最初から各通廊に防衛システムを仕掛けておけばいいだろうに。ソールの言葉が耳に蘇る。これも総統閣下のお触れってわけか…?
戦闘機が目前にまで迫った。ビーム砲が撃ち出される。ホーバーの突風がエレナを壁に吹き飛ばし、マキタを床に叩きつける。鏡のように磨き上げられた床材がビーム光線に溶かされ、灼ける。飛び散った灼熱の金属塊が風圧に飛ばされ、2人の皮膚に突き刺さる。
天井すれすれを通過していった戦闘機は、通廊同士が交差するフロアでビーム砲を撃ちながら回頭した。狂暴さでは譲るが、火器の威力はクランゲージョ以上だ。マキタは壁の凹みに転がり込み、エレナは柱の陰に身を潜めた。そこで機関砲を構え、戦闘機を狙う。
ガインガインガイン…!
火花が床に降り注ぐ。しかし軽量装甲を紙のように貫いた機関砲弾も、大気圏突破まで出来る戦闘機装甲を貫通するまでには至らない。頭上すれすれを通過する戦闘機の轟音に、エレナの罵声が混じる。
マキタが走り出した。
戦闘機の進む方向とは逆に向かって。
「どこに行く気?」
「そこにいろ!」
「1人でどうする気よ!」
「任しとけ!」
何か言いかけたエレナの背後で、戦闘機が2度目の回頭を行った。慌てて振り返り、機関砲を構え、撃つ。戦闘機もビーム砲を照射した。徹甲弾は出鱈目に飛び交い、ビーム砲光線はエレナをかすめて壁を切断した。物凄い熱風に髪の毛の一部が焦がされた。
仰向けに引っ繰り返ったエレナは、自分に向かってくる光線を転がりながら避けた。機関砲を撃ち返す暇もない。
マキタは既に通廊の直線を走り抜け、エレナと300メートル近い距離を隔てていた。ライフルを床に置き、ハンディキャノンを両手で構え、戦闘機と向かい合う。
再度エレナの頭上を通り過ぎた戦闘機が、ビーム砲の砲口をマキタに向けた。
ハンディキャノン1弾倉分を撃ち尽くしたマキタがさっと横に跳んだ。それを追い切れずに、途切れがちなビーム砲光線が床を刻み…、
戦闘機はビーム砲根本から火を噴いた。
超音速の炸裂弾は機体とビーム砲の継ぎ目の薄い装甲を貫通し、機関部にまで達したのだろう。火は即、エンジンにも回った。ホーバー噴射口が炎を吐き、1度天井に激突してから、戦闘機は通廊床に激突した。黒煙を上げながら、床を掻き毟り、惰性でマキタに向かっていく。エレナが叫ぶ。
「マキタ!」
その細長い身体が、縦にもっと長く伸びた。と思いきや、マキタは突っ込んできた戦闘機を飛び越えていた。
黒スーツ姿のパイロット――保安省暗殺部隊の隊員だ――もコクピットから這い出し、その直後に戦闘機は爆発した。
マキタは床に降り立つと同時に爆風に吹き飛ばされた。伏せようとしたエレナも同じ爆風に煽られ、仰向け大の字にぶっ倒れた。その鼻先をぞっとする大きさの、戦闘機の灼けた破片群が通過していった。
だが、倒れる寸前、エレナは見た。
爆風に舞うマキタが空中でハンディキャノンの弾倉を替え、身を捻りざま、撃ったのを。
マキタはエレナの側にまで飛ばされてきた。床に転がり、ノビてしまう。エレナは膝でマキタににじり寄った。と、視線が燃え上がる戦闘機の手前に吸い寄せられた。
黒スーツのパイロットが血溜まりに沈んでいた。その頭部が消失していた。ハンディキャノンの弾丸1発で。
その手が握り締めていたものが、彼女の視界にクローズアップされた。
あの、殺人ナノマシン発射銃!
マキタはあの一瞬に、パイロットの持つものに気づいた。だから容赦なく撃った。あの体勢から…。エレナはマキタを見た。神業だ。神業に近い。
やはり〈あの男〉の息子なのだ、この人は。
マキタが呻いた。防弾繊維のジャケットもあちこちが破れ、血だらけになっていた。爆風に混じった破片を全身に浴びたのだ。それでも致命傷にもなりかねない、大きな破片を食らわなかったのは僥倖と言えた。
エレナはズタボロのジャケットに注意しながら、マキタの背中を抱き上げた。マキタはエレナの腕の中で、うっすらと目を開けた。
エレナは微笑んだ。マキタの額に流れる血を拭い、「大丈夫?」
「痛えよ」マキタは弱々しく呻いて見せた。
エレナは笑いながら、マキタの鼻の頭を指で弾いた。「甘えるな」
それでも優しい手つきでマキタの背を支えたまま手を取り、「立てる?」
「大丈夫、だ」
マキタは呻きつつ立ち上がり、壁に頭をぶつけた。
「お見事」エレナが言った。
マキタが応えた。「いいえ」
エレナが機関砲を、マキタがビームライフルを拾い上げ、2人は走り出した。もちろんマキタのペースは格段に落ちたが。
ぎくしゃくと走るマキタが、エレナの横顔を見つめていた。
エレナはすぐに気づいた。整った鼻梁に流れる汗を拭い、「どうかした?」
「うん、あのな…」マキタは口ごもった。「何でもない」
「何よお、はっきり言いなさいよ」
「後で言う」
多分、言わないだろう。傷のせいに違いない。それとも頭を打ったか。
さっき薄目を開けた時に見上げた、自分を抱き支えるエレナの、
美しかったこと…。
錯覚だ錯覚。それに今そんなことを言ってみろ。悪い冗談と決めつけられるに決まっている。下手をすればまた殴られる。
だが、そんなマキタの目に、汗を浮かべるエレナの横顔は未だ一層輝いて映っていた。
スペースソルジャーズ〈7〉


