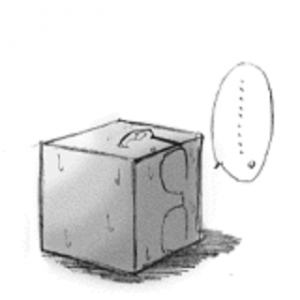降ってわいた休日
午前五時半。
私はいつものように目を覚ました。正確には、目ざまし時計が鳴る数分前には目が覚めて、布団の中でまどろんでいるのだ。
隣に妻の寝息を聞きながらじっとしていると、目ざましがけたたましい音で私を呼ぶ。
素早くベッドを出て目覚ましを止め、すぐ脇に置いてある眼鏡をかける。
まずは顔を洗い、玄関で新聞を取るとリビングのテーブルに置き、そのまま今度は台所に向かう。
朝食を作るのが、私の一日の最初の仕事。
ここに家を買ったときから、一番早く起きなければならない私が朝食を用意することになった。もう何年も続けているから、少しも苦にならない。
慣れた手つきで卵を割り、手早くかき混ぜる。毎日のことだから、たまご焼きだけは妻よりも上手に作れる自信がある。
朝食は一部取り分けて自分の弁当箱に詰める。弁当男子? そんな大層なものじゃない、これも節約の一環。ローンはまだたっぷり三十年残っている。
朝食を取りながら朝刊にざっと目を通す。一面から斜め読み。ゆっくりしている暇はない。
ひげを剃ってから改めて顔を洗い、髪を整えたらワイシャツに袖を通してネクタイを締める。
起きてからきっちり一時間半、私はいつものように家を出た。私はこれから約一時間の長旅、妻や子どもが起き出すのは私が家を出た三〇分後だ。
最寄り駅までは歩いて十分ほど。今日は木曜日だから、出がけに燃えるゴミも忘れずに出した。
毎日同じ風景を見ながら駅までの道を歩く。都心に通勤する人たちが、同じように駅に集まってくる。いつも同じ時間に家を出るから、見かける人もだいたい同じだ。
毎朝犬の散歩をしているリタイアした男性とすれ違う。三十年後に家のローンが終わった頃には、私もあんな風になっているだろうか。いつもすれ違うので顔だけは知っているが、あいさつを交わしたことはない。ほかの通勤者も同じようなものだ。みな顔をうつむき加減に、黙々と歩く。
私はいつものように改札に向かった。出来るだけ背筋を伸ばして颯爽と、少し大股気味に。毎年のメタボ検診で引っ掛からないように、歩き方にはちょっと工夫をしている。
背広の内ポケットから素早くパスケースを取り出し、改札にかざす。毎日のことだから動作には一切の無駄がない。
が、私は抜けようとした改札に阻まれ、したたかに腰をぶつけた。声にならない呻きと同時に、アラームが鳴る。私の後ろを抜けようとしていた若い男が軽く舌打ちをするのが聞こえた。私のいる入口を避けるように人の流れが瞬時に出来上がる。私はその流れの中に取り残された。
パスケースの中の定期券を見ると、有効期限が昨日で切れていた。迂闊だった。ここに越してきてから今まで、こんなことは一度もなかったのに。
人の流れに逆らって券売機までたどり着く。硬貨で切符を買うなんて久しぶりだ。
五分のロスだ。出社時刻には十分余裕があるが、朝の五分は痛い。
結局いつもより五分遅れて会社に着いた私は、いつものように階段で七階のオフィスに向かった。メタボ検診も怖いが、去年初めて脂肪肝の疑いを指摘されたから、できるだけ身体を動かすようにしている。七階に上がる頃には額にうっすらと汗がにじむ。
フロアで軽く息を整え、私はオフィスのドアを開けた。
「おはよう」
あいさつは自分から、大きな声で。新入社員の頃に教えられたことを私はいまだに忠実にやっている。それは立場が変わろうが関係ない。今や私が教える側だ。教えるにはまず自分が実践する。私の部署ではいつもそうしている。
しかし、様子が変だ。いつもなら即座に返ってくるはずのあいさつが、誰からも返ってこない。それどころか、既に来ていた社員数人が、怪訝な顔で私のことを見ている。
「あの……、ご用の方は受付を通してからお願いいたします」
「は?」
あまりのことに私は思わず間の抜けた声を出してしまった。部下からこんなことを言われるとは心外だ。
「おいおい、お前上司の顔も忘れたか?」
私は部下に怒気を込めた声で伝えたが、彼はあくまで真面目だ。
「課長は、本日体調不良のため休みとなっておりますが」
一瞬新手のリストラだろうかと思った。ここで毅然とした態度を取らなければ、上司としての威厳が保てない。叱りつけてやろうとしたところで、私は言葉を失った。
部下の名前がどうしても出てこない。今オフィスにいる、彼の、彼女の、顔はわかるのに名前がどうしても思い出せない。名前を呼ぼうとしてあんぐりと開けた口は、そのまま言葉を発することなくぱくぱくと動いただけだった。
結局、私は自分のオフィスから丁重に追い返されてしまった。自分のIDカードでオフィスに入ったんだから絶対間違いないのに、なんだか居場所がない。やっぱり新手のリストラかもしれない。まだ三十年払わなければならない家のローンのことが頭をかすめる。
とりあえず家に電話をかけようと携帯を探したが、ついてないことは重なるものだ、家に忘れてしまったらしい。おかしい、いつものところに置いていたはずなのに、なんで今日に限って忘れるんだ。
慌てて公衆電話を探すが、最近は公衆電話も減ってしまってなかなか見つからない。結局駅まで戻るはめになってしまった。十円玉を入れ家の番号を押そうとして、指が止まる。
家の番号が思いだせない。なんでだ、若年性のアルツハイマーか。その割にはすいぶん意識がクリアだぞ、と私はとりとめのないことを考える。
鞄の中を探し回って、やっと手帳に書いておいた個人データ欄から自宅の電話番号を探し出して受話器を取った。
五回……十回……十五回。呼び出し音は鳴るが誰も出ない。時間を見て納得した、妻は子どもを保育園に送って、パートに出かけた時間帯だ。
こういうことはちゃんと覚えている。なのに、なんで電話番号や部下の名前は出てこないのだろう。妻の携帯に電話をかけようにも思い出せないし、番号はどこにも書き取っていない。参った、打つ手がない。
その時になって、私はもっと大事なことに気がついた。
妻の名前、子どもの名前も思い出せないということに。
時計はいつの間にか十時を回っている。
私は公園のベンチに腰掛けてぼんやりしていた。今日は春の暖かい日差しが降り注ぐ穏やかな日だ。
普段連絡は全部携帯に頼っているから、手帳に書いてあった電話番号に片っ端から電話をかけようとしたが、繋がらなかったり出なかったり、繋がってもすぐに切られたり。一見で飛び込んだ営業先とかだから、元々関係の薄い相手ばかりだ。誰も私のことなど相手にしない。
不思議なことに、部下の名前は思い出せなくても今日の仕事の予定はちゃんと覚えている。得意先を数件回らなければならなかったはずだが、先方は私がすっぽかしたことで腹を立てはしないだろうか。心配だが、私にはどうしようもない。
孤独だ。
この世の中で私を覚えていてくれる人は一人もいなくなってしまったのだろうか? ひどく不安な気持ちになる。
こんなことは今まで考えたこともなかった。一体、私はどうすればいいのだろう?
私は近くのコンビニで買ったコーヒーを飲みながら、足元をうろついている鳩を眺めるでもなく眺めていた。
コンビニはいい。私が誰であろうと、お金さえ出せば必要なものを売ってくれる。なんとなくそんなことを考える。
私が誰であろうと。
鳩が何かに驚いていっせいに飛び立った。
ところで、私は一体、誰だったろう?
「あのう……」
若い女性の声がしたので私は顔を上げた。目の前にはどこかの事務員風の制服に身を包んだ小柄な女性が立っている。肩に掛かる明るい色の長い髪に丸顔、くりっとした目で私のことを見つめている。
「私に何か?」
知っている人の名前はおろか、今や自分の名前すらあやふやになっている私が言うのも変だが、初めて見る人だ。
「えっと、……今、お困りなんじゃありませんか?」
奇妙な質問だ。
ただベンチに座っているだけの見ず知らずの人に対して、普通はこんな質問はしないだろう。
しかし、現に私が困っているのもまた事実だ。
「え、ええ……まあ」
困惑しながら私がそう返すと、彼女はいきなり勢いよく頭を下げた。
「ごめんなさい、それ、わたしのせいなんですっ」
いきなり頭を下げられて、私は面食らった。
なんなんだ、この子は。
「……と、以上が今回の顛末なのですが、お分かりいただけましたでしょうか?」
私の隣に座った彼女は一通り話し終えると、不安そうな顔で私に尋ねた。
「いや、なんとも……」
私はそう答えるほかない。業務の報告としては過不足のない説明だと思うが、問題はその内容だ。
彼女の話はこうだった。
彼女は「知能局存在部存在同定課第二八九六係」に所属する新任の天使で、私を含む数千人のアイデンティティを司っているのだという。
天使といえば恋を司る「キューピッド」が有名だが、実は男女の縁結びというのはこの存在同定課の仕事の一部に過ぎない。彼女たち天使は、私たちの人間関係一切を取り仕切っているのだと彼女は言った。
「実はわたし、先日仕事で失敗したんです」
彼女は申し訳なさそうに言葉を継いだ。
彼女が言うには、前任者との引き継ぎの際に誤って空白期間ができてしまい、今の状態は私と直接の人間関係のある人が私を私として認識できない、ということらしい。その影響として、私の記憶野にも一部障害が起きて、その人の顔は認識できても名前などの固有の情報をうまく取り出せなくなっているのだという。
「あ、でも空白は一時的なものですから、すぐに終わります。たったの半日だけですから!」
彼女は取り繕うように明るくそう言った。
しかし、かえって気まずい空気が流れる。
彼女が焦っているのが、私には手に取るようにわかる。
「えと、出来るだけ、支障が出ないようには、してますので」
会社には今日は急病のため休む、と彼女が連絡したらしい。
「しかし、会社に若い女性から電話があったとなると、どうも面倒だな」
「だいじょうぶですよ、あなたの声で電話しましたから」
後半は確かに私の声だ。自分の目の前で自分の声でしゃべられるというのはなんだか気味が悪い。
しかし、彼女が私の人間関係の一切を取り仕切っているなどという話は、どう考えても嘘くさい。私の声を模した特殊技能だって、それが直ちに彼女が天使だという証拠にはならないし。
「君ね……」
私は彼女に言った。
「人をからかうもんじゃないよ」
「からかってなんかいません!」
彼女はムキになって反論する。が、すぐに目を逸らして下を向いてしまった。
「あ……、すみません、わたしが悪いのに……」
なんだか気の毒なほどに落ち込んでいる。
にわかには信じ難い話だが、あながち嘘ではないのかもしれない。実際、今私は関係のある誰ともコンタクトできなくなっているわけだし。
私は彼女に問いかけた。
「君が天使だっていう証拠って、無いのかな?」
「職員証ならありますよ」
「いや、そういうのじゃなくって、なんていうのかな、人間とは違うっていう証拠」
彼女はちょっと考えていたようだったが、すっと立ち上がってこう言った。
「じゃあ、それを見せたらわたしの話を信用してくれますか?」
「ああ、信用しよう」
私はうなずいた。
その言葉を聞くと、彼女はベンチから数歩前に出た。
「ちゃんと見ててくださいよー」
彼女はちょっと前かがみになって私にいたずらっぽく微笑みかけると、その場でくるりと一回転して見せた。
「……!」
私は思わず息を呑んだ。
一瞬にして彼女の背中から、白く大きな翼が出現した。翼の作る影が、ぽかんと口を開けて眺める私の顔を覆う。
「どうです?」
彼女が微笑みながら言う。
「驚いた」
私はそれだけ言うのが精一杯だった。
「これでわたしの話、信用していただけますよね?」
「ああ、信用しよう」
その言葉に、彼女は背中の翼を大きく広げた。
「──それにしても、天使って本当にいるんだなぁ」
私は両手を頭の後ろに置いて空を仰ぎながらつぶやいた。青々とした桜の梢の向こうで、白い雲がゆっくりと青空を横切っていく。
彼女は翼をしまって私の隣に座っている。
「普段は誰にも見えないんです。でも、いつでもすぐそばにいるんですよ」
「ふぅん……ところで、天使ってみんなそんな格好なのかい?」
「あ、これですか?」
彼女は左右の腕を広げてどこかのOL風の自分の制服を眺めた。
「いえ、こうやってやむを得ず人の前に『出現』するときは、その人の生活環境に近い姿で現れるよう、服務規定で決まってるんです。言葉も、それに合わせたものを使います。わたしたちって身体のない精神で、本当は性別もないから、形だけなら何にでもなれるんですけど」
「じゃ、男の姿にもなれるってことか」
「男のほうがよかったですか?」
彼女はくすくすと笑う。笑顔が実に綺麗だ。
「いや、こっちでよかった」
私も思わず笑みを返した。
「そう言えば、仕事って言ったよね?」
「はい?」
「仕事。君の仕事だよ」
私は彼女のほうを向いて言った。
「今日は、君の仕事はどうしたんだい?」
彼女は膝の上に両手を乗せてちょっと黙っていた。
「今日は、お休み、なんです」
声が沈んでいる。
「わたし、仕事で失敗したって、言いましたよね?」
彼女はそう続けた。
「ああ。確か、引継ぎに失敗したとか……」
「それで、上司に叱られちゃったんです。責任感が足りない、一時的にせよ存在を疎外される人の身になってみろって怒鳴られちゃって……」
私は黙って彼女の話を聞いていた。このあいだ若い部下に同じような叱り方をしたばかりだ。
「ちゃんと謝ってくるように言われました」
「それで、今ここにいるってわけか」
彼女は小さくうなずいた。
「天使でも、その辺は同じなんだな」
私は空を仰いだまま彼女に言った。鳥が一羽、私の上空を横切っていく。
「何かミスがあると相手に迷惑がかかる。それは、これまで築き上げてきた信用を、一瞬で失う行為だ」
彼女は黙ったまま下を向いて私の言葉を聞いている。
私は伸ばしていた背を戻して彼女に向き直ると、わざと調子を変えて続けた。
「でも、ま、いいさ」
彼女がびっくりしてこちらを見る。
「休みが一日、降ってわいたと思えばいいんだ」
そう言って私は彼女にウインクを送った。
彼女は、泣きそうな顔で無理やり笑ったようだった。
日がだいぶ傾いてきた。
彼女と街を歩くと、いつもは見えなかったものが色々と見えて面白かった。いや、普段は気に留めていなかっただけなのだろう。
街路樹の脇で精いっぱい根を張っているタンポポや、店の軒先で巣づくりするツバメ、電線の上で遊ぶカラスなど、この街では人だけが生活しているわけではなかった。
虫には虫の、鳥には鳥の担当の天使がいるんですよ、と彼女は言った。わたしたちは生きるお手伝いをしているだけなんです、と。
私たちは、たくさんの生き物と、たくさんの目に見えないものに囲まれている。
「あと五分で元に戻ります」
彼女が時計を見て言った。
「元に戻ったらどうします?」
「そうだな、……まっすぐ家に帰るか」
「奥さん、きっと待ってますよ」
「ああ、そしたら今日のことを話してやろう」
彼女は私の目をじっと見つめた。
「それは、出来ません」
努めて静かな口調で彼女は告げた。
「え──」
「残念ですが、元に戻ったらわたしに会ったことは忘れてしまいます」
そんな。
今日のことを忘れてしまうのはとても惜しいような気がした。もちろん、彼女のことを忘れてしまうのも。
「規則なんです。天使の存在は、やっぱり不可視でないといけないんです」
「しかし──」
私は何か言おうとしたが、言葉にはならなかった。
「あの、ありがとうございました」
彼女は不意に私に向かって頭を下げた。
「わたし、落ち込んでたんです。やっぱりわたしには天使なんて出来ないって」
「……」
「でも、もうちょっと頑張ってみます」
そう言った彼女の目には、自信が見えた。私は少しほっとした。
「そうか。じゃ、頑張って」
私は右手を差し出した。
「はい」
彼女は、しっかりと私の右手を握り返した。
「あなたが忘れても、わたしは今日のことを忘れませんから」
私はうなずいた。
時間が来た。
「あ、そうそう。定期券、買い忘れないでくださいね」
彼女は最後にそう言った。
それから、彼女の姿はふっと空気に溶けるように消えてしまった。
午前五時半。
私はいつものように目を覚ます。正確には、目ざまし時計が鳴る数分前には目が覚めて、布団の中でまどろんでいるのだ。
隣に妻の寝息を聞きながらじっとしていると、目ざましがけたたましい音で私を呼ぶ。
素早くベッドを出て目覚ましを止め、すぐ脇に置いてある眼鏡をかける。
まずは顔を洗い、玄関で新聞を取るとリビングのテーブルに置き、そのまま今度は台所に向かう。
朝食を作るのが、私の一日の最初の仕事。もう何年も続けているから、少しも苦にならない。
慣れた手つきで卵を割り、手早くかき混ぜる。毎日のことだから、たまご焼きだけは妻よりも上手に作れる自信がある。
朝食は一部取り分けて自分の弁当箱に詰める。弁当男子? ふふ、そう言われるのも悪くないかもしれない。ただ、男子と言われるにはいささか歳を食ったかな?
朝食を取りながら朝刊にさっと目を通す。一面から斜め読み。政治も経済も社会も、世の中では色々なことが起きるが、私には私の世界がある。
ひげを剃って改めて顔を洗い、髪を整えたらワイシャツに袖を通してネクタイを締める。身支度を整えると気合が入る。今日も一日真剣勝負だ。
起きてからきっちり一時間半、私はいつものように家を出た。
最寄り駅までは歩いて十分ほど。今日は金曜日だから、出がけに燃えないゴミも忘れずに出した。
毎日変わり映えのない風景だと思っていた街が、なぜだか今日は妙に鮮やかに見える。
いつも同じところですれ違う犬の散歩をしている男性に出会う。「おはようございます」とあいさつをすると、彼も笑顔であいさつを返してくれた。
私はひとつ深呼吸をしてから、買ったばかりの定期券を通して改札を抜けた。
電車がもう来ているらしい、ホームのほうからチャイムが聞こえる。私は階段を一段飛ばしで駆け上がる。よし、来年は脂肪肝返上だ。
途中、上から降りてきた制服姿の若い女性とすれ違った。
(ん?)
私はちょっと立ち止まって振り返った。
(今の人、どこかで会ったことのあるような……)
しかし、振り返った私の視線の先に、女性はなかった。
(気のせい、か)
そう思い直すと、私はまた、階段を駆け上がっていった。
了
降ってわいた休日