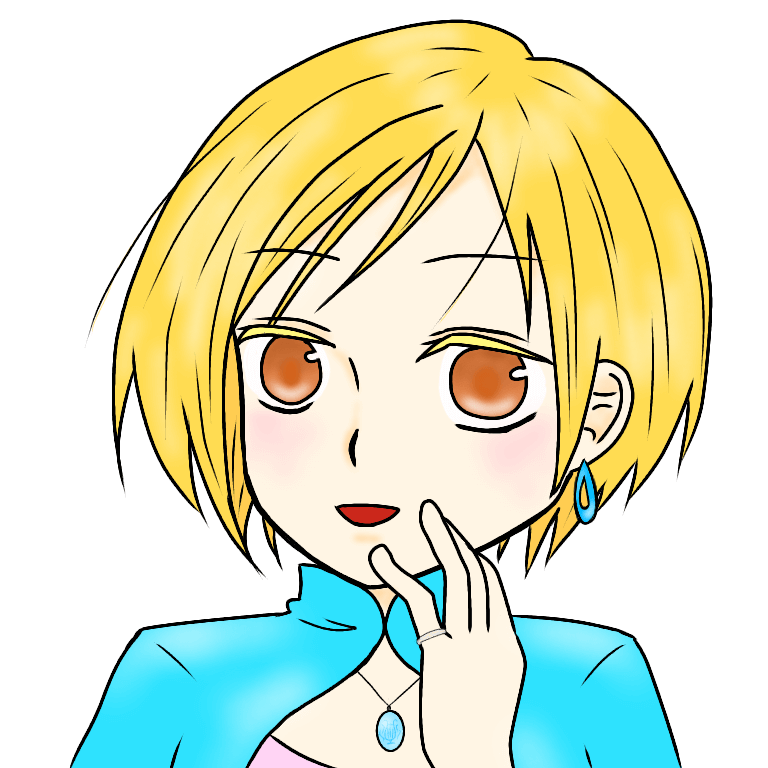
水上の天使
ジェイドがロリコンと言われても否定できない世界観だけど、オールドラントの1年間の日数は地球のほぼ2倍なので許してください…!そしてルークに会うまでが長い!
マルクト皇室
マルクト帝国には、エミリーという名の姫がいた。
(やっぱりグランコクマは綺麗な街…)
水に反射した陽を受けて輝く、キャラメル色の瞳は母親譲り。
父親と同じバターブロンドの髪はスッキリと短く、左耳には雫をモチーフにした海色のピアスをしている。
「あー…仕事なんてなくなればいいのになぁエミリー」
マルクト皇帝である父・ピオニーは、よく仕事をサボってはペットであるブウサギ達と戯れてばかり。
「ピオニー、娘の前でなんてことを言うの…」
母・ネフリーは、ややきつい印象を与える、眼鏡の似合う美女だ。
二人の馴れ初めは、幼馴染みだったというシンプルかつ庶民的なものである。
「エミリーはもう11歳なんだぞ?俺の発言が本気かどうかなんてわかるさ」
「…そうね、この子は私に似て利発だから。――ただ、皇帝とは思えない発言だったけれど」
「ジェイドみたいなこと言うなよなぁ」
ネフリーの兄・ジェイドは、ピオニーから絶大な信頼を得ており、“皇帝の懐刀”として恐れられている。
彼はマルクト軍の第三師団師団長を務め、階級こそ大佐だが実力はそれ以上だと聞く。
「父上は、私が今から軍本部に行くのが心配なんでしょう?」
出かける前の挨拶のため、両親の私室に立ち寄ったのだが、予想以上に引き留められている。
「問題は行き先じゃない!護衛も付けずに一人で城の外に行くとか言うから心配なんだろうが!」
「ほぼ敷地内じゃない。しかも自分は一人で頻繁に通ってるよね…?」
「安心しろ、俺は体術には自信がある。それに抜け道を使ってるから安全なんだ。あっ、だがエミリーは抜け道なんか緊急時以外使っちゃダメだぞ?」
「まるでお手本にならない父親ね。そもそも、仕事を放って脱走することを気にしてほしいわ」
「俺にも休息は必要なんだっ!」
母と娘が揃って小さくため息をついた。
「私だって護身術は身につけたよ。ただジェイドに書類を届けたいだけなんだけどなぁ」
「なら、兵を遣わせばいいだろう。もしくはジェイドを呼べ」
「その言葉、そっくりそのまま貴方に返すわ」
「ネフリー!俺はだな、息抜きがてらジェイドの様子をネフリーに報告するために…」
「じゃあ今日は私が代わりに行ってくるねっ」
武器となる傘を手に取り、ひらりとドレスを翻す。
「おい!?ちょっ待てエミリー!」
「いいじゃない、“もう11歳”なのよ?――お兄さんによろしくね」
「はーい♪」
*
彼女がマルクト軍本部に入ると、兵士達は驚きながらも最敬礼をした。
(確か、ジェイドの執務室はこの廊下の奥だったはず…)
コンコン、とノックをすると、深呼吸をしている間にそのドアは開いた。
「これはこれはエミリー殿下。廊下が騒がしいと思ったら…」
「大臣の遣いで来たの。…中へ入っても?」
「あぁ、失礼。どうぞ」
小さな姫に、恭しくお辞儀してみせる。ドアを閉めると彼は首を傾げた。
「…護衛がいないようですが?お一人でいらっしゃるのは珍しいですね」
「家族と会うのに護衛が必要?」
おや、とジェイドは微笑んだ。
「ですが軍本部だからといって安心しすぎるのも…。いえ、本来は安心していただきたい場所なのですが…」
「父上や皇室に不満を持つ者もいるのはわかってる」
危機感を持つように母から言い聞かせられているのだ。
「それで緊張したような面持ちだったのですね。――何か飲まれますか?お掛けになってお待ちください」
「気を遣わなくていいよ」
ソファに腰を下ろし、少し寂しそうに笑った。
「…来客には飲み物を出すものです。それが上司であっても身内であっても」
「あ、そうだったね。じゃあ、コーヒーを…」
ジェイドはテーブルに二人分の飲み物を置き、向かいのソファに腰かける。
「どうぞ。お口に合うかわかりませんが」
(あ…ミルク多めに入ってる)
カップを見つめるエミリー、ジェイドは何か思い当たったように手を叩いた。
「あぁ、失礼。毒味をしなくては…」
「ふふっ、大丈夫。ありがとう」
エミリーはジェイドのことを昔からよく知っているというわけではないが、父との信頼関係を信じている。
「ところで、ご両親のお許しはちゃんと得て外出されているのでしょうね?」
「もちろん。でも、父上はあまり良く思ってないみたい」
「お父上は心配しておられるのですよ。――それで、その書類は…」
ここに来た目的を思い出し、書類の入った封筒を手渡す。
「そうそう。大臣から預かったんだった」
「皇女殿下を遣いにするとは、失礼な大臣がいたものですね…。呼んでいただければ私が城へ伺いますよ?」
「…口実だってわかってるくせに。わざとらしく皇女殿下なんて呼ばないでよ。あんまりしつこいと伯父上って呼ぶから」
「すみません。それは勘弁してください」
本当に困ったような顔をするものだから、エミリーは声を出して笑った。
「城を出るための口実、ですか。お父上の真似をしてはいけませんよ」
「それもあるけど、ジェイドと二人きりになりたかったの。迷惑だった?」
「はは…素直なお姫様ですね。迷惑だなんて、とんでもない」
ジェイドの本心を探るように、眼鏡の奥の赤い瞳をじっと見つめた。
「それならいいけど」
ふいと顔をそらしたのは照れたから、ではなさそうだった。
「もちろん皇女という仕えるべき立場ではなくても、ですよ」
「…何も言ってないけど」
「疑った顔をしていましたよ」
「そう?じゃあ、私の不安を取り除いてくれない?」
はらりと顔にかかった髪を耳にかけ、エミリーはスッと目を細めた。
「困りましたねぇ」
「私が困らせているの?」
「ははは。なにせ二人きりですから、貴女しかいませんねぇ」
「あははっ、そうだった」
エミリーは伏せ目がちに、言葉を発しようとして飲み込んだ。
「…殿下?何か──あぁ、謁見の間で話すべき内容ですか?」
「ううん、そうじゃなくて…正式発表の前に話しておきたいなと思うことがあって」
「はい。何でしょう?」
「キムラスカとの和平条約…に関する話なんだけど」
「そろそろですか?」
小さく頷いて応えた。ジェイドは変わらず微笑みをたたえていた。
「心配なのですか?邪魔が入るのではないかと」
「邪魔が入るのを見越して、親書は信頼できる人に託すつもり」
「…なるほど。つまり私が和平の使者として、キムラスカへ行くお役目を仰せつかるのですね」
「和平の使者、って貴方に似合わない響きだけど…そういうこと」
「確か、親書の内容としては…」
以前、謁見の間でピオニーが話していたことを思い返す。
「和平条約の締結と、アクゼリュスの救援要請…かな」
「ということはまさか、殿下がご心配なのはこの私ですか?アクゼリュスの瘴気は、確かに酷いと聞いていますが」
「うん、だって…。でも、これは確実に成功させなきゃいけないから。だから私も、第三師団に行ってほしいと思ってる」
「信頼にお応えできるよう、老体に鞭打って頑張りますよ」
ジェイドの言葉は、茶化しているのか本気なのかよくわからない。
「…私、矛盾してるね。いつもこうやって悩んで、理屈を並べて自分を納得させてる」
「立派な皇女になられましたね」
「そんなことない。軍人とはいえ大切な国民なのに…犠牲を強いることもあるのがつらいよ」
「我々は、国や大切な人を護るために戦っています。貴女が胸を痛める必要などありませんよ」
「…私は常に護られていて、貴方は常に命懸けなんだね」
「皇室も国民を護っているではありませんか。命を狙われることもありますし、ね?」
「最後の一言は余計でしょ!…でも、納得した。ジェイドには敵わないなぁ」
「年の功ですよ」
「見かけによらず35歳だもんね?ふふ…」
口元に添えたエミリーの左手をジェイドの目が追う。
「おや?私と会うときに、その指輪をつけるとは流石ですねぇ」
「毎日つけているのに、それはあんまりじゃない?」
「これは失敬♪謁見の間でお会いする際は、いつも手袋をしておいででしたので」
「そうだね。でもホントだよ?もう…傷ついた」
ジェイドは不意に立ち上がったかと思えば、エミリーの斜め前に跪いた。
「申し訳ありません、殿下。その寛大な御心でお許しください」
スッと左手を取り、小指にはめられた小さな指輪に口付けた。
「…キザだけど、絵になるのが悔しいな」
「お褒めにあずかり光栄です」
そのピンキーリングはシンプルかつ上品なデザインで、11歳の少女には年不相応にも見える。
〜回想〜
「──ハァ…ありがとう。お城から連れ出してくれて」
そこは宮殿の庭とはいえ、一部は民間人にも解放しているため色んな人が歩いていた。
「慣れないことの連続で疲れたでしょう。それに、エミリーはまだ街をゆっくり見ていないのではないかと」
「うん、ちゃんと見るのは初めて。でも、変装する必要ある?」
エミリーは帽子で髪の色を隠し、銀縁の眼鏡をかけている。
「念の為です。新しい皇室に国民は興味津々ですからね」
「ふぅん?」
宮殿の敷地を出て、広場の噴水に歩み寄った。
「わぁっ、すごい…!ケテルブルクの雪も好きだけど、水に囲まれた街も綺麗だね」
「ここを好きになれそうですか?」
「うん!――急にグランコクマに呼び出されて、即位式とか習い事とか…環境の変化についていけないけど」
「無理もないですね」
「でも、こうして伯父上と会えたし、悪いことばっかりじゃないよね」
ジェイドの赤い眼が驚きで見開かれ、そして穏やかに細められた。
「おや…どこで覚えたんです、そんな口説き文句。しかし、その呼び方はやめてくださいと言ったでしょう」
「えー?事実なのに」
「いいから名前で呼びなさい。──あぁ、そこの店にエミリーを連れてきたかったんです」
「キラキラした宝石がいっぱい!よく来るの?」
エミリーは店頭のディスプレイ棚に釘づけになった。
「私が?まさか。渡す相手も…いるとすればネフリーかエミリーでしょう」
「じゃあ今日は母上へのプレゼントを選ぶんだね?」
「いえ、貴女にですよ。失礼ながら、質の良い宝飾品はまだ持っていないでしょうから」
実際にエミリーは、比較的安価な宝石や、皇女として相応しいとは言えない――どちらかと言うと子供向けの――アクセサリーしか持っていなかった。
宮殿にはドレスや高価なアクセサリーがたくさん遺されているが。
「わ、私にはまだ早すぎると思うけど…」
「再会の記念に贈らせてください。女性は買い物でストレス発散をする、とピオニー陛下も仰っていましたし」
「うん…?」
「こうして二人だけで出歩くことも、気安くエミリーと呼ぶこともできなくなりますから」
「どうして?私がジェイドさんの姪であることは変わらないでしょう?」
「私は軍人ですし、私自身が今の立場を望むからです。──さて、店に入りましょう」
少しムッとしたエミリーは、ふといいことを思いつき、ジェイドに倣って店に入った。
「ネックレスやイヤリング、髪飾りもいいですね」
「あのね、せっかくならお揃いがいいな」
上品な店員や着飾った客たちが、入店した二人に注目したのは明らかだった。
ジェイドは色々な意味で有名であり、もし知らなかったとしても軍服は目立つ。さらに、場違いな少女を連れていることも要因だろう。
「…ペアアクセサリーは、主に愛し合う男女がするもの、と認識していますが?」
「私まだ子供だからわかんないや。ふふっ♪――あっ!指輪なら、手袋に隠せるね」
「聞こえませんでしたか?」
「聞こえてるけど、記念にって言ったから。…あ、小指だったらいいかな?」
彼女の目線を辿ると、そこは小さな宝石があしらわれた細い指輪――ピンキーリングの並ぶ棚だった。
「そもそも指輪に抵抗がありますよ。どれどれ…ふむ、もっときらびやかで派手なものを選ぶのかと思いましたが」
「派手なのは嫌でしょ?でも例えばこれとか、曲線を重ねたデザインが可愛いね!あっ、こっちも…」
「…強いて言えば、凝ったデザインは戦っているうちに壊してしまいそうですね」
ジェイドはもう諦めたらしく、小さくため息をついた。
エミリーはその態度が気に食わなかったが、自分の我儘で困らせているのはわかっていた。
「じゃあこっちの、模様が綺麗な色違いの指輪は?宝石がないから壊れにくそうだよ」
「そういう問題ではありませんよ。…ペアリングなどおそれ多いですし、万が一私との関係を誤解されるようなことがあっては不利でしょう。今はまだ不安定なお立場ですから」
「それでも…私の、最初の命令として、聞いて?」
それは皇女の“命令”と言うより、可愛い姪の“お願い”だった。
店員や客たちにチラチラと見られながらヒソヒソ話をされているこの状況から、ジェイドは早く逃げ出したかった。
「…御意」
その後、グランコクマでは様々な噂――死霊使いに隠し子がいる、小さな恋人がいるなど――が飛び交った。
噂は時間差で皇帝の耳にも届き、ジェイドはしばらく問い詰められることになったとか。
〜現在〜
「──ところで、素朴な疑問なんだけどさぁ」
「感傷に浸っていたかと思えば…何ですか」
「マルクトとキムラスカの関係は、言うまでもなく緊張状態でしょ?マルクト軍でも、和平の使者ならキムラスカへ入れるの?」
「旅券があれば入れることには入れるでしょうが…穏やかで楽しい旅というわけにはいかないでしょうねぇ」
「そっか。中立の立場にあるローレライ教団ならまだしも、どうするんだろうって思って」
「おや!なるほど〜」
ジェイドはわざとらしく感心したような声を出した。
「な、何?急に子供扱い?」
「気のせいですよ、私の敬愛するエミリー殿下。ローレライ教団に同行してもらえないか、早速陛下に進言してみます」
「えっ?あ、でも!貴方はまだ知らないことになってるから…せめて謁見の間で話すのはやめてね?」
「もちろんです。さぁ、宮殿へお送りしますよ」
*
「おかえり、エミリー!って、ジェイド、送ってくれたのか。ご苦労だった」
宮殿に入ると、正面にある階段の上からピオニーの声が降ってきた。
「陛下、丁度良かった。ご相談があるのですが…」
「ん?謁見希望か?」
彼は、今しがた出てきた重厚な扉をクイッと親指で指した。
「いえ、もしお時間が許すのであれば、他の落ち着く所で話したいですね」
「父上の私室がいいんじゃない?」
ピオニーは階段を下りながら、エミリーとジェイドを交互に見やった。
「なんだ?お前も同席するのか?」
「殿下の柔軟さのおかげで見えたことがありますので」
「そうか?ま、いいだろう」
謁見の間の下、宮殿に入って真正面にある部屋がピオニーとネフリーの私室である。
扉をくぐると書物が並んだ書斎があり、その奥にはゆったりとした寝室が広がっている。
ピオニーのペットである五匹のブウサギ達が迎えてくれた。
「ハァ…相変わらず、汚い部屋ですねぇ。貴方もネフリーも、よくこんな所で眠れますね」
別に部屋を設けたエミリーは、母はよく我慢できるものだと感心している。
「いきなり嫌味か。つーか、お前らが揃って私室で相談とは何事だ?」
「ええ…。ネフリーは公務ですか?」
「ん?謁見の間にいる。新しくドレスを仕立てさせるらしくてな」
ピオニーが少しふてくされ気味に答えた。
「ドレス屋さんが来てるの?」
「ああ、デザインはある程度考えていたみたいだが、レースはどれにするかだの生地の質感だの…俺は疲れたから抜けてきたんだ」
「いいなぁ、楽しそう」
ネフリーの所在を確認され、これから聞かされる話を想像したピオニーはハッとした。
「まさか…婚約したいとか言い出さないよなぁ?!」
「その発想には驚かされますよ」
「あのなぁ!俺が即位してすぐの頃、お前達のペアリング事件が耳に入ったときはこっちが驚かされたんだぞ?!」
「それはそれは、ご心配をおかけしました」
「あー…父上、ごめんね?」
ピオニーはため息をつき、ブウサギの寝ているベッドに腰かける。
「おかげで仕事が手につかなかったよなぁ?可愛い方のジェイド〜♪」
「……」
ジェイドは何か言いたそうな顔をしたが、無言でエミリーのために椅子を引いた。
「ありがとう。ジェイドも座ったら?」
「では、お言葉に甘えて」
ピオニーは心の中では、2人の仲睦まじい様子を嬉しく思っていた。
(他人と変に距離を置きたがるジェイドと、急な環境の変化に戸惑いや不安を抱えていたエミリー。そんな二人が親しくなれたのは良いことだとは思うんだがなぁ…)
「…ま、お前が指輪を買い求めたとき、一緒にいたのがエミリーだと気付いた者はいないようだし、それが不幸中の幸か」
「あの頃の私は、あんな騒ぎになるとは思ってなくて…改めてごめんなさい」
「殿下、私のことはどうかお気になさらず。私も軽率だったと反省していますよ」
困った表情をするジェイドに、ピオニーは呆れたような声を出す。
「ジェイドは女っ気がないから、その程度で騒がれるんだ」
「私は身も心も、マルクト皇室に捧げておりますので♪」
「よく言う…。とにかく!男女でお揃いのものを持つってことはだなぁ…特に――ピンキーリングだかアタックリングだか知らんが――指輪っていうのは特別な意味が…!」
始まった説教を遮るようにエミリーは、はいはい、と手を叩く。
「わかってるってば。私かジェイドの預言に婚姻のことが詠まれたら、約束通りこの指輪は外すから」
左手小指に視線を落とした娘に、ピオニーは胸を痛めた。
「あぁ、可哀想になぁ〜!でもエミリーにはパパがいるぞ♡」
「早く本題に入ろうよ。ジェイドは忙しいんだから」
「ジェイド“は”?パパだってちゃんと仕事してたんだぞぉ?!」
無視された上にぞんざいな扱いをされて、ピオニーは盛大なため息をついた。
「…じゃ、いい加減本題に入るか。お前達の婚約話でなければ、一体何の話だ?」
ジェイドは眼鏡のブリッジを押し上げ、ゆっくりと口を開く。
「…和平条約の件なのですが」
「ん?…なるほど。それで私室に来たわけか」
「ごめんなさい」
「怒っちゃいない。俺もこいつには先に話すべきだと思っていたからな」
父の言葉に、エミリーは少しだけホッと胸を撫で下ろした。
「陛下の名代として“誰か”がキムラスカへ向かうわけですが、もし中立の立場にあるローレライ教団がこの旅に同行してくれれば心強いと思うのです」
「そりゃそうだが…邪魔が入るのを見越して、少数精鋭で向かわせるつもりだったんだが。――というか、お前も同じ考えだと思っていたんだが?」
「もちろん私も同感ですが、殿下がその“誰か”の身を案じているので。同行していただければ手を出しにくいのでは、と」
ピオニーは視線を落として唸った。
「…それだと、キムラスカの前にダアトを説得する必要があるな。それに、同行してもらうなら影響力のある人物でないと意味がないだろう?」
「影響力で言えば最高権力者である導師イオンでしょうか。マルクトとキムラスカの関係は少なからずダアトにも影響しますから、どちらにせよ説得しなくてはなりません」
「ローレライ教団は今、派閥抗争で大変なんだろう?導師も、正直あまり良い噂を聞かんな」
「導師派と大詠師派の対立が激しくなっているようですね。実権を握っているのは大詠師モースだとか」
考え込む二人の思考を遮るように口を開く。
「大詠師モースって…あの何か企んでそうな人だよね?導師と仲が悪いの?」
「殿下、発言には気をつけてください」
とはいえ、エミリーのモースに対する印象は、ジェイドもピオニーも否定できずにいた。
「改革的な導師派と保守的な大詠師派…考え方が違うから分かり合えないんだ」
「うーん…考えが違うのは他人だから当然なのにね。それに、導師の方が偉いなら、それに従うのかと思った」
「そうですねぇ。ですが、どんな組織でも内部抗争は起こりうるのです」
「エミリーは良く言えば確かに柔軟で視野が広いが、悪く言えばまだまだ世間知らずだな」
エミリーはムッとして父を睨んだ。
「…いつもサボってる人には言われたくないな」
「おっと、怒るなよ。お前を責めたわけじゃない。ケテルブルクとグランコクマしか知らないんだから世間知らずなのは当然だろう?」
「じゃあ父上も世間知らずってことだね」
「そうなるなぁ。だが、俺はこれでも皇帝だ。歴史は本を読んで勉強したし、今の国民の声はなるべく国民から直接聞くようにしている」
「だから謁見希望もなるべく受けるようにしているんでしょ?」
謁見希望者はとても多いが、貴族や急ぎの者が優先されるため、一般庶民はなかなか順番が回ってこないんだとか。
「そうだ。あとは、たまーに城を抜け出して、庭園にいる民に声をかけたりしてだな…」
「陛下…。今後は供の者をつけてください」
「お前が構ってくれないからだろう」
「それは理由にはなりませんよ」
ピオニーはブウサギから視線を上げ、パァッと顔を輝かせた。
「――というわけで!エミリー、お前も旅に同行しろ」
「…えっ??」
「“というわけ”とはどういうわけですか」
ジェイドが呆れつつ怒っているようにも見える。
「もっと多くの街を見て、もっと多くの人と話してこい。お前にとってはいい勉強になるだろう」
「でも、父上…いつも私が出歩くのを咎めるのに」
「危険です。社会勉強のために命懸けで旅をする必要などありません」
「うるさいな…もう決めた!今回はお前がいるから安心して送り出せるんだ。それに、皇族は常に命を狙われているという覚悟くらいあるさ」
ジェイドは複雑そうな顔でため息をついた。
「…仕方ありませんねぇ。私が必ずお護りいたします」
「おう、頼んだぞ。――にしても意外だな、エミリー。ジェイドと一緒に行きたいって言うと思ったんだが」
「それはそうだけど…足手まといになりたくない」
「殿下、そんな弱気になって貴女らしくない。ピオニー陛下譲りの自信と強引さはどこに行ったんです?」
「ジェイド…」
二人が見つめ合っていると、ピオニーがわざとらしく咳払いをした。
「あー、そうと決まれば、旅に着ていく動きやすいドレスでも新調したらどうだ?」
「えっ、いいの?じゃあ私、謁見の間に行ってくる!」
ドレスの裾を踏まないように気をつけながら、嬉々として立ち上がる。
「殿下、お供しましょうか?」
ジェイドも立ち上がり、先回りしてドアを開けた。
「ありがとう。でも、まだ父上とお話があるでしょ?あ、城まで送ってくれてありがとう」
そう言うエミリーを見送って静かにドアを閉めると、ピオニーが鼻で笑った。
「エミリーにフラレてやんの」
「何を仰っているのですか」
「お?フラレるわけがないってか?ずいぶん自信があるんだなぁ」
「ですから一体何を…。違います。殿下は、忙しい私を気遣ってくださったのです」
ため息をつくジェイドに対し、ピオニーは自信満々で余裕の表情だ。
「そんなことはわかってる。俺は父親だからな」
「そうですね。さすが賢帝」
「…嫌味か?だが、あの子は賢いぞ」
「ええ、ネフリーに似て利発ですね」
デジャヴだなと思いながら懐刀を睨む。
「…やっぱり兄妹だな。同じこと言いやがって」
「おや…そんなに喜ばれると照れますね」
「誰も喜んでねーし、キモいぞ」
「お褒めにあずかり光栄です」
「褒めてない!!」
漫才のようなやりとりをして、一気に疲れたピオニーはベッドに寝転がった。
「…本当によろしいのですか」
「ん?何がだ」
「大切なご息女を危険な旅に行かせて」
「…“可愛い子には旅をさせよ”ってな」
その言葉は本心なのだろうが、少し強がっているように思えた。
「皇族としての自覚を持ち、立派に成長してほしいという気持ちはよくわかりますが…殿下はまだ11歳ですよ」
「そうだなぁ。まだ早い気もするな」
「…幼い頃の陛下は、よく屋敷から抜け出して遊んでいましたね」
「外の世界を知ることが大事なんだ。エミリーも、城の中で甘やかされて育ったって……」
天井を見つめる真剣な表情に、ジェイドもそれ以上の反論は飲み込んだ。
「…私は教育係ではありませんよ」
「ん?じゃあエミリーの騎士様か?」
「ハァ…殿下をお護りすること自体は構いませんが、できれば危険な場所にお連れしたくはないですね」
「お前なぁ…そういうことをサラッと言うから、娘をその気にさせるんじゃないのか?」
おや、とジェイドは首を傾げる。
「私は何か間違ったことでも?」
「いいや?ただ――」
上半身を起こし、真っ直ぐとジェイドを見据える。
「お前は意外と過保護だなって話さ。しっかり護ってくれよ?お前にしか頼めないからな」
「…御意」
スッと立ち上がり、右手を胸に当てて腰を折る。
ネフリーと同じ赤みがかったブロンドの髪が、はらりと肩から滑り落ちた。
旅のはじまり
正式発表の後は作戦会議や準備であっという間だった。
エミリーは、体力づくりを兼ねて戦闘訓練に励んだ。
ジェイド率いる第三師団の訓練は、いつも以上に厳しいものだったと聞いているが、出発の前日であるこの日は体を休め、装備の手入れや備品の確認をしている。
(…落ち着かない…)
エミリーの私室は宮殿の一階、入って左手すぐの部屋である。
ちなみに上の部屋と二階右手は客室、一階右手は資料室になっていて、その他にも長い廊下や部屋は覚えきれないほどある。
資料室での調べものを終え、ぼんやりと自室へ歩いていると、階段から下りてくる人影が視界の端に映った。
「――エミリー皇女殿下」
凛とした声に振り向くと、ビシッと背筋を伸ばしたアスラン・フリングス少将がいた。
「フリングス将軍。ふふ、そんなに威勢よく呼ばれると、何事かと身構えちゃうよ」
彼は、しまった、という風に僅かに表情を崩した。
「…申し訳ありません。カーティス大佐のように物腰柔らかく接するよう心がけます」
「真面目だね。――って、ジェイドのようになる必要はないけどさっ」
エミリーは少し動揺し、ハッとしてフリングスを見上げた。
「…何を笑っているの」
「いえ、笑ってなど…。先程は心ここにあらずといったご様子でしたが、私の杞憂だったようで安心しました」
「心配させちゃったんだね…。あ、そうだ。このあと忙しい?大事なお仕事があったりする?」
質問の意図がわからないなどと文句も言わず、彼は真面目に答える。
「ピオニー陛下とのお話は終わりましたが…?外出されるのでしたらお供します」
「だったら、ちょっとお茶しない?」
「は…?」
話が噛み合わず、思わず唖然としてしまった。
「っ、失礼しました。しかし、私ごときが殿下とお茶など…」
「“私ごとき”って言うけど、じゃあ誰なら相応しいの?言っておくけど、貴族院は嫌だからね」
抵抗できるはずもなく、腕を引かれるままエミリーの私室に入った。
城には使用人がたくさんおり、エミリーの専属メイドというのも存在するのだが、私室には誰もいなかった。
「ドアは開けたままにしておくから。あ…それとも嫌だった?困らせてごめんね?」
「そんなことは…!ただ、もう少しご自身のお立場をですね…」
ジェイドであればハッキリ言うであろう場面でも、忠実で優しいフリングスは言葉を濁す。
「お話に付き合ってくれたら、もっと元気になれそうなんだけどなぁ」
「うっ…」
こういう言い方をすれば、彼は確実に断れないとわかっている。
(でも気持ちを押し付けないようにしないと…)
「父上は私に、もっと多くの人と言葉を交わすようにと言ったから。貴方と話すのも、いつも勉強になってるよ」
「…お役に立てて光栄です」
「だったら座って。あ、コーヒーでいい?」
ケテルブルクの屋敷では使用人が少なく、ネフリーやエミリーは簡単な家事を手伝っていたのだ。
「私がお淹れします。火傷をしては…」
「私の部屋の物に触れたら怒られちゃうよ?それに、周りに甘えてばかりではいけないと思うし、わざわざメイドを呼ぶのもどうかと思うしね」
無理矢理ソファに座らせて、自分用と来客用のカップを取り出す。
エミリーでも届くようにと、この部屋の調度品は低いものが使われている。
「…知っていると思うけど、明日の朝には城を発つんだ。だからみんな忙しそう」
「そう、ですね」
「それに城内の空気がピリピリしてるから、私も何かしていないと落ち着かないよ。…やり残したこととか、私がやるべきこととか…」
最後は独り言のように呟いた。
「任務遂行中は更にピリピリと…慌ただしくなるかもしれません。今のうちにゆっくり湯浴みでも…」
「ここ数日は、稽古のあとお風呂に入るのが習慣になってたから、もう十分かな」
「皇女自ら、戦闘訓練…ですか」
「街の外には魔物がいるでしょ?今回の旅では、ジェイドは私の護衛じゃないもの。なるべく自分でなんとかしたいから」
テーブルに二人分のカップを置き、向かい合ったソファに座った。
「ありがとうございます。――そこまでお考えとは…ご立派ですね」
「もー、本当に思ってる?言いたいことがあるなら言わないとわからないし、ストレス溜まって良くないよ?」
そう言って、ミルクたっぷりのカフェオレを一口流し込む。
「――では私から申し上げましょう」
すうっと吹いた風が、エミリーの好きな声を乗せてきた。
「ジェイド!」
「カーティス大佐…」
開け放たれた部屋の入口にもたれるように、彼は立っていた。
「今回の旅、確かに私は殿下の護衛としてお供するわけではありません。ですが、貴女をお護りするのは私の役目です。失礼ながら、私としては黙って護られていてほしいのですが」
「…すっごく嬉しいけど、素直に頷けない」
「やれやれ。護れと言ったり構うなと言ったり、困った親子ですね」
彼は呆れた声を出したが、顔は嬉しそうにも見えた。
「…ところで、何かあったの?ノックもなしに珍しいね」
「おや、失礼。これでは私もピオニー陛下に言えませんね」
「まぁ、私がドアを開けていたから構わないけど。――船の点検は?作戦会議は?」
「ご安心を。私のやるべきことは済ませました。あとは力仕事ですので、若い部下達に任せてきましたよ」
「…そっか」
ジェイドは入口のドアをパタンと後ろ手に閉めて、エミリーの側に片膝をついた。
「殿下のことが気になって来てみたのですが、やはり少しお元気がないようですね」
「元気だよ?ただ、落ち着かないだけ」
失礼、とジェイドはエミリーの手をとった。
「な、何?」
するりと手袋を外され、何事かと動揺する。
「――あぁ、思った通りですね」
「エミリー皇女!こんなに…」
「あ…マメができて潰れたアトのこと?」
エミリーの手は、彼女の努力を物語っていた。
「全く…皮がめくれたところから細菌が入ったらどうするんですか」
「自分で消毒はしたし、治癒してもらうほどじゃなかったから。それに、もっと鍛えないと…。私に何かあったらジェイドが責められちゃうし」
「お気持ちだけでも十分ですよ」
フリングスまで心配そうに頷いている。
「護られるだけのお姫様にはなりたくないから…」
「…もし戦うことになっても、貴女には譜術があります。離れた所からサポートしていただければとても助かるのですが」
「ジェイドみたいな強い譜術は使えないのに…。はいはい、わかったよもう」
眼鏡越しの眼力に負け、お手上げのポーズをしてみせた。
「ご理解いただき感謝しますよ、姫様♪」
「気持ち悪いからやめてね」
「おや、心外ですねぇ」
そう言って立ち上がり、フリングスの横に腰を下ろした。
「そうやって戯けてみせても、私の緊張はほぐれそうにないからさ、今後の確認をしようよ」
「はっはっはー。そうですか?では…」
ノックされたドアから現れたエミリー専属のメイド――ベルが、主の手を見て青ざめた。
「お客様に気付かず申し訳――お嬢様?!なんてこと…失礼します!」
ベルが両手をかざすと、傷はたちまち治っていった。
そう、彼女は第七音譜術士なのだ。
「えへへ…ありがとう」
「ありがとうではありません、お嬢様!ケガをしたらすぐに仰ってくださいといつも…」
「私からもお礼を言いますよ。完璧な私でも、第七音素だけはどうにもなりませんから♪」
説教を遮ったジェイドに、ベルはハッと落ち着きを取り戻した。そして手早く淹れたコーヒーをジェイドの前に置いた。
「…失礼いたしました」
「ありがとうございます」
邪魔をしないように気を遣ったのか、彼女は速やかに部屋を出て行った。
「…助かったよ、ありがとう。ベルってばお説教が始まると長いんだから。あ、それで…」
「――明日、ダアトに向けて出発します」
✽
翌日、エミリーに新しいドレス――裾は短く、動きやすく仕立ててある――を着せてくれた使用人のベルは、旅に同行させてほしいと直前まで訴えていた。
第七音譜術士でもある専属メイドがいてくれたら、もちろんエミリーとて心強いが、危険な旅だからと全力で反対した。
「――ま、私が反対しなくたって、父上が許可しないだろうけど」
「第三師団にも第七音譜術士はいますからねぇ」
「だね。しばらくの間、ベルには暇を与えるように手配したの。ベルはケテルブルクのお屋敷時代から、私のことを優先してくれたから…」
「殿下はお優しいですね」
そんな他愛のない会話をしながら、エミリーとジェイドは謁見の間にやってきた。
大きな扉の側に控えていた兵士が、二人の顔を確認して仰々しく開け放った。
玉座で待つ両親を見据え、コルセットベルトから伸びた腰布の裾をあおるように歩く。ジェイドは彼女の斜め後ろに控えている。
「――いよいよ出発だな」
ピオニーは珍しく険しい表情をしている。
「アスラン、例のものを」
「はっ」
玉座の側に控えていたフリングスが、ジェイドに巻物を手渡す。
「導師イオン宛の親書です」
「確かに」
ジェイドは親書を懐にしまった。
「厳しい旅になることは重々承知している。が、あえて言おう。…俺の国を頼む」
「はっ」
片膝をついたジェイドを見下ろし、ピオニーはすっくと立ち上がった。
しかし、皇帝として相応しくない言動を遮るように、ネフリーも立ち上がり、キビキビと娘に歩み寄る。
「――エミリー、これを」
母が差し出したのは、マルクト帝国の紋章が刻まれたクリスタルペンダントだった。
「…これは?」
「マルクト皇族だけが持つことを許されたペンダントよ。きっと貴女を守ってくれるわ」
「そんな大事なもの…受け取れないよ。これは母上が持っていて」
「いいえ、貴女が持っていくのよ。身分を証明するためにも必要になるかもしれない」
幼い娘に合わせて調整されたチェーンのネックレスが、優しい手つきで首にかけられた。
「…ありがとう」
デコルテを飾るペンダントをそっと撫でた。
「では、そろそろ行きましょう」
すっと立ち上がったジェイドを、ピオニーが呼び止める。
「エミリーだけじゃなく、お前も無事に帰ってくるんだぞ」
ネフリーは娘を強く抱きしめ、名残惜しそうにそっと離した。
「…気をつけてね。お兄さん、エミリー」
「行ってきます!父上、母上」
✽
「…しばらくグランコクマにも帰れませんよ」
「うん…。でも代わりに、知らない街を見れるね」
「そういう前向きなところ、殿下らしくて救われます」
エミリーはマントのフードをぐいっと深く被り直した。
「こうやって二人で街を歩くのって、あのとき以来だね」
あのとき――ペアリングを購入した日を指している――と違うのは、エミリーの知名度だろうか。
警護を敢えてジェイドのみにしたため、こうして目立たずに移動できているのだ。
「…あれが最後になると思ったのですがね」
港に到着すると、そこには第三師団旗下の高速艇が停泊している。
「作戦通り、タルタロスは先に出発し陸路を移動中です。…殿下、お忘れ物はありませんか?」
「うん…行こう」
傘をきゅっと握りしめ、高速艇に乗り込んだ。
ジェイドに倣ってブリッジに行くと、ジェイドの部下達が最敬礼で迎えてくれた。
「あ…楽にしてください。あの、長旅になりますし、私のことは気にせずいつも通りでお願いします」
「そうですね。――重要な任務だからこそ、いつも通り、しっかり切り替えて自己管理するように。以上!」
「「はっ!」」
ジェイドの合図で高速艇はついに出港した。
「…殿下もですよ」
胡散臭い笑顔に戻ったジェイドを見上げ、首を傾げた。
「いつも通りで構いませんし、休めるときに休んでください」
「うん、ありがとう」
「しばらく私の出番はなさそうなので、部屋までご案内しましょう」
二人はブリッジを離れ、廊下を突き進む。
「軍艦って、どれも似たような造りをしてるよね」
「客船のような装飾や遊び心はありませんし、連絡船ともまた違いますからねぇ。――あぁ、ここです」
たくさん並んだ扉の一つ――ドアノブに青いリボンが結びつけてある――を指し示した。
部屋を間違わないように、だが、わかりやすすぎると敵襲があった際に狙われてしまう。そんな葛藤が感じ取れた。
部屋に入るとジェイドは一通りの設備を説明した。
ベッドの手前に衝立があったり寝具が新品だったりと、室内も少しだけ配慮されていた。
「ふふっ、ありがとう」
「すみませんねぇ。なにせ男所帯なものですから、必要なものがあれば何なりとお申し付けください」
「わかった。とりあえず、甲板まで散歩してきてもいい?」
「退屈でしょうからね。お供しますよ」
ジェイドのエスコートで廊下を抜け、階段を上った。
「風が強いので、少しだけですよ」
甲板に出ると、エミリーは思わずスカートを押さえた。
「わぁ…水平線が見えるよ!」
「おや、海は見飽きているものと思っていましたが?」
ジェイドは鬱陶しそうに長い髪を押さえていた。
「城からは滝ばっかりで意外と海は見えないから…。あっ、向こうは真っ白だよ!」
「あれはシルバーナ大陸ですね」
「そっか。ケテルブルク、見えるかな〜」
楽しそうに水平線を見ていたエミリーが、少しだけ俯いたのにジェイドは目ざとく気付いた。
「寒いですか?」
「ううん、大丈夫。…このあとのことだけど」
「導師を連れ出すことですか?」
連れ出すと言うのはやや語弊があるが。
「やっぱり、私も一緒にダアトに行って説得したい」
「…どういう流れになるか、私にもわかりませんよ。正直、導師はあまりいい噂を聞きませんし」
ジェイドが心配していることはわかっている。
「それはもう聞いた。でも、親書だけじゃなくて、皇族がいた方がいいでしょう?」
「親書だけでも十分だと思いますし、危険ですから殿下はこの船でお待ちください」
「ジェイドと一緒にいる方が安全だと思ってたんだけど」
違う?と見上げてくるエミリーに、ジェイドは一瞬言葉を失った。
「…沖に停泊している船が理由なく襲われることはないと思いますが。ハァ…わかりました、私の負けです」
「ありがとう!…ワガママ言ってごめんね?でも、黙って待つのは苦手だもの」
「まぁ、構いませんよ。私が護ればいいだけの話ですから」
今度はエミリーが言葉を失う番だった。
「殿下?顔が赤いようですが…」
「そろそろ中に入ろっか!」
顔を見られないように早歩きで船内に戻ると、背後でフッと笑う気配を感じた。
「ジェイド、何を笑っているの…」
「これは失礼。ピオニー陛下に言われたことを思い出したのですよ」
「父上に?」
《そういうことをサラッと言うから、娘をその気にさせるんじゃないのか?》
ジェイドは少し困ったように笑った。
「大したことではありませんよ。陛下に呆れられてしまったという話です」
「ジェイドが父上に呆れられるなんて、どんな…」
「――さて、私は仕事に戻ります。殿下も、部屋でお休みください」
「…じゃあ、本でも読もうかな」
エミリーの部屋の前で別れ、ブリッジに向かうジェイドの背中を見送った。
✽
高速艇は予定通り待機ポイントに到着し、ジェイドとエミリーは譜業モーターの小型ボートに乗り換えた。
マルクト帝国軍の船では、これ以上パダミヤ大陸に近付けないのだ。色んな意味で、とジェイドは説明していた。
「…ジェイド、その荷物は?」
「いざというときの備えですよ♪さぁ、私の側に」
「あ、うん」
ジェイドの操縦でモーターボートはダアト港を目指した。
「こんな船に乗ったの初めて!」
「楽しそうで何よりです。船酔いも心配なさそうですね」
「うん。――ダアトに行くのも、導師とお会いするのも楽しみだよ」
ローレライ教団の総本山に行くのは少し緊張するが、ジェイドが一緒であれば怖くない。
「導師…。協力的な方だといいのですがね」
「父上の即位式でお見かけしたけど、すごく若くてびっくりした記憶はあるよ」
「若いというより幼いというべきでしょうね。大詠師が実権を握っているというのは、年齢的な理由もあるのでしょう。――入港します」
港に着くとマントを羽織り、石碑のある丘を登った。
「巡礼者が多いですね。――ダアトが見えてきましたよ」
「わぁ…あれがダアト!なんていうか、質素な街だね」
「確かに、華やかさに欠けますね」
「私そこまで失礼なこと言ってないけど…」
心の中では、どうしてもケテルブルクやグランコクマと比べてしまうのだが。
丘を越えて街に入ると、エミリーは違和感を口に出さずにはいられなかった。
「ここのみんなの服装って…ローレライ教団の?」
「街全体が独特の法衣を着ていますね。ここには神託の盾騎士団もいますし」
「知ってたことだけど、実際に見ると圧倒されちゃうね。マルクトでもキムラスカでもないっていうのも変な感じ」
「グランコクマでは馴染む殿下のドレス姿も、ここでは浮いてしまいますから、しっかり隠してくださいね」
公務なのに隠れるという矛盾に、思わずため息をついた。
「だからってマント着てフードかぶってるのも目立つと思うけどなぁ…」
✽
「――カーティス大佐とおっしゃられましたね。ご意向は確かに承知いたしました」
大聖堂にて、導師イオンは丁寧に親書を読んで頷いた。
大詠師モースとツインテールの少女――こう見えて付き人だろうか――がイオンをはさんで両隣に控えている。
「それに、エミリー皇女が同行されているとは驚きました」
「…親書の内容こそが父・ピオニー九世の嘘偽りない本心です。私も、自国のためにできることをしたいのです」
「ピオニー陛下もエミリー皇女も、心より和平を望んでいらっしゃるのですね」
はい、と片膝をついているジェイドが応える。
「それも何より国民を愛するが故に…。素晴らしいことだと思います」
(すごく理解ある導師に見えるけど…これは表の顔なのかなぁ?)
しかし、ジェイドも少し驚いたような顔をしていた。
「どうかされましたか?」
そんな二人の反応に、イオンは不思議そうな顔をしていた。
「…いえ、これは失礼を」
ジェイドは眼鏡のブリッジを中指で押し上げ、イオンに柔らかな笑みを向けた。
「想い深きお言葉に胸を撫で下ろす思いでおります。…噂とはあてにならぬものと」
(ジェイドってば一言余計なんだから…)
エミリーが睨むと同時に、モースがイオンを隠すように進み出た。
「カーティス大佐!この場は親書をお預かりしましょうぞ。正式な返答は改めて後日!」
即答できないのは当然だろうが、数回謁見したことのあるこのモースという男にエミリーは不快感を抱いていた。
「承知いたしました。港にてお待ちしております」
ジェイドはスッと立ち上がり、踵を返す。
「…どうか前向きなご検討を」
何か言いたげなモースを無視して、エミリーも大聖堂をあとにした。
✽
「――そういうわけで、ご協力できかねるというのが導師のご結論です。恐縮ですが…」
エミリーがぶらりと港を一周し船着き場に戻ると、導師という単語が耳に入った。
「そうですか…。それは大変残念です」
話していた相手はやはりジェイドだった。
エミリーは法衣を着た人物とすれ違い、何やら考え込むジェイドに声をかけた。
「導師に呼ばれたんじゃないの?…まさかダメだったの…?」
「おや、お買い物はもうよろしいのですか?」
「あ、買い物したかったわけじゃなくて、見たかっただけだから――って、それはどうでもいいの!」
「どうでもいいなどとは、とても言えませんねぇ。殿下にとっては社会勉強の旅ですから♪」
そのわざとらしい言い回しに、エミリーは思わずムッとした。
「――導師は突然のご病気とのことで、直接ご回答いただけなかったのですよ」
「えっ、ご病気?それは心配だね」
ジェイドは少し呆れたようにため息をついた。
「殿下、少しは疑った方がよろしいかと」
「…国民を信じなくて何が皇女だ、って思わない?」
「それで臣民に騙されたらどうするんだ、と思いますよ♪」
二人は丘を越え、街に行ってみることにした。
「――巡礼者のみなさーん☆」
可愛らしいよく通る声に視線を向けると、見覚えのあるツインテールの少女がいた。
「彼女は確か…導師イオンの?」
「導師守護役ですね。これはちょうどいい」
ジェイドはそう言うと、人の悪い笑みを浮かべて少女に近付いた。
「石碑巡りにガイドはいかがですかぁ?美少女ガイド、アニスちゃんが格安でご案内しちゃいますよー♡」
「お願いできますか?お嬢さん」
「はぁい!喜んで――」
アニスという少女は元気いっぱいに振り向いたが、相手を確認すると固まってしまった。
「いやぁ、私の可愛い姪が勉強熱心でして、ぜひ石碑巡りをしたいと…」
「えっ?あ、うん!えっと、五大石碑でお願いします」
急に話を振られて動揺したが、一応嘘はついていない。
「は、は〜い…。では、初心者向けコースにレッツゴー…」
やりづらそうではあるが、割り切って石碑巡りをするようだ。
「楽しみだね、伯父上」
「そうですね、エミリー様」
今更身分を隠さなくても、とアニスは内心思っていたが、さっさと終わらせて逃げたいというのが一番だった。
「姪に様付けはおかしいよ、ジェイド…」
「しかし血縁関係は事実ですから♪」
「あっ、それを今言うの?ずるい…」
港から始まった五大石碑巡りも、アニスの進行であっという間に終わりを迎えようとしている。
「――ところで、導師は公式行事にも出ず、臥せっておられるそうですね。突然のご病気で」
ジェイドが意地の悪い“世間話”を振り、アニスはスルーして石碑の説明を続ける。
そんな攻防戦の最後はダアト教会前の石碑のようだ。
「こちらが第1石碑になりまぁす☆」
「我々が訪ねた直後に突然倒れられ…。しかも、ピオニー陛下宛てのご返答を人づてになさるほどのご病状!」
「え〜、あとは預言を守って静かに生きていきましょうと書かれてあります!以上っ!」
説明に感心していたエミリーも、そろそろジェイドを止めるべきかと考え始めた。
「真意をお伺いしたいとご伝言願えませんか。ご病気の導師に」
「ただいま副業中につき!そーゆーご依頼は受け付けておりませんっ!」
「まぁまぁ、そう仰らず。伝えるだけでも」
ジェイドがにこやかにガイド料を払うと、アニスは逃げ帰ってしまった。
「…大丈夫なの?」
「禁止されているはずの副業を見逃し、金銭を支払ったことですか?」
「えっ?禁止されている…?」
「ええ。ですから、我々のことも報告できないと思いますよ」
唖然とするエミリーにジェイドは手を差し出した。
「今日はこのくらいにしましょう」
慣れた素振りで手を重ね、二人はゆっくりと港へ戻る。
「でも、明日も動きがなかったら?」
「そうですねぇ…六神将が戻る前に決着をつけなくては」
六神将とは神託の盾騎士団の中でも卓越した戦闘能力を持ち、他国にも名を馳せている六人のことだ。
「私、サフィールに会ってみたいのに〜」
「あんな鼻垂れ、会う価値などありませんよ」
サフィールは、エミリーの両親とジェイドの幼馴染みであり、現在は六神将の死神ディストと名乗っているらしい。
「でも、そんなふうに言ってるのはジェイドだけだよ?」
「陛下もネフリーも、実に寛大な御心をお持ちですね」
「もーっ、昔の話になるとすぐはぐらかすんだから…」
話したくなるのを待つと決めているが、気になるものは気になるのだった。
✽
「殿下、本日のお召し物です」
翌日、そう言ってジェイドが差し出したのはシンプルで動きやすそうなパンツスタイルの服だった。
受け取った服を広げたエミリーは、少し神託の盾の服装に似ていると思った。
「これって…変装?というか、その口調は何…」
「たまには執事のように接してみようかな、と思いまして♪」
「…服装は執事っていうより一般兵だけどね。いつもより薄着だし」
先に着替えていたジェイドも、ダアトに溶け込みそうなシンプルな服装をしている。
「おや。降格してしまいましたねぇ」
「モーターボートに積んだ荷物って、これだったんだ…。でも眼鏡と長髪でジェイドだってわかるよ」
「眼鏡は外すのですが…ふむ。では髪型も変えるとしましょう」
「あ、じゃあここに座って?ほら、すぐ終わるから」
ジェイドは促されるまま、エミリーに背を向けて腰かけた。
「…。これから私は少しだけお側を離れますが、すぐに戻りますので教会の裏手でお待ちください」
小さな手の感触に意識を向け、手短に作戦を伝えた。
「えっ、どこに行くの?無理はしないでね…」
「信者の力を借りるだけですよ。ただ、そんな中に殿下をお連れするわけにはいきませんからね」
エミリーはなんだか恐ろしそうだと思い、ここは大人しく言うことを聞こうと頷いた。
「…わかった。――はい、できたよ」
「ポニーテールですか。手慣れたものですね。ありがとうございます」
「よく母上の髪を触らせてもらってるからね。髪質が似てるから結びやすかったよ」
いつもと違う格好で眼鏡を外す仕草に、エミリーは見惚れてしまった。
「では、のちほど教会の裏手…警備が手薄な所で。きっとそこに導師イオンも現れるはずです」
「?!う、うん…わかった」
ダアトの街に紛れるジェイドを見送り、エミリーは緩んだ頬を叩いた。
✽
着替えを済ませたエミリーが街に出ると、信者達が教会に向かって叫んでいた。
「導師を解放せよ!!」
「我らの導師に自由をー!!」
どうやらジェイドが民を扇動しているようだ。
「信者の力を借りるって、そういうこと…?確かに、この中には行きたくないけど」
教会前には続々と人が集まり、その対応に兵も増えていく。
「教会の横暴を許すな!!」
(あ、早く裏手に回らないと…人の波に飲み込まれちゃう)
この様子だと兵は正面に集中しているだろう。
裏手に回ると、見覚えのあるモーターボートを発見した。
「つまり、ジェイドはこの辺りを想定して…」
「――イオン様、もう少しです!」
声のした方に近付くと、教会の上の方から垂らされた一本のロープ。そして下りてくるのは――。
「えっと、アニス?と…導師!」
「ん…?はぅあっ!もしかして、マルクトのお姫様…?!」
アニスはストンと着地して、大げさに驚きのポーズをとった。
(ドレスじゃなかったら、意外と気付かれないのかも…?)
「えっ、皇女…?――あっ?!」
「きゃっ?!」
エミリーと目が合った瞬間、イオンは足を滑らせてアニスの上に落ちてしまった。
「だ、大丈夫ですか?!ごめんなさい…私が声をかけたから…」
「いえ…!アニス、すみません…」
「あはは〜…地面で良かったです…」
「あっ…では、こちらへ!」
二人が立ち上がるのを確認し、モーターボートに誘導する。
「あの、カーティス大佐は…?」
「ここですよ、導師」
三人が乗り込むと同時に、変装したジェイド――眼鏡は既にかけている――が現れた。
「お待たせしました、殿下」
「うん。早く行こう!」
御意、と微笑ったジェイドの操縦でダアトを離れる。
モーターボートとはこんなにもスピードが出るのか、とエミリーは思わずジェイドの服を掴んだ。
「――我ながらとんでもないことしちゃった…!!クビになったらどうしよおおお!!」
「すみません、アニス。僕の権限で、そんなことにはならないようにしますから」
「ホントですねっ?!」
そんな二人を横目に、エミリーはホッとしていた。
(無理矢理連れ出すことにならなくて良かった…)
「この河を下って、港を使わずに海に出ましょう。沖に私の船を待たせてあります」
ジェイドの髪を纏めていた紐が風圧で解けた。
「六神将が任務遂行中で良かったですよぅ。でなきゃ教会から抜け出すこともできたか…」
「でしょうね」
さらりと言ってのけるジェイドに、イオンが首を傾げる。
「彼らの留守をご存知だったんですか?」
「情報収集は基本です。様々な状況を想定していました。…お嬢さんの協力が得られない場合のこともね」
「うーん…複雑ですけど感心しました…」
本当に複雑そうなアニスに対し、それはどうも、とジェイドは面白がって返した。
「ジェイド、むやみに敵を増やさないでよね…」
「これは失礼♪――さぁ、海はもうすぐですよ」
海に出た途端、小型のモーターボートが並走する。
「教団の船…!モース様の追手です!」
一体何隻いるのかと後方を振り返るが、最後尾は確認できなかった。
(え…結局、誘拐したと思われてる?)
「導師イオン、私の側へ。殿下も、そのまま離れないでくださいね」
ジェイドは左手でイオンとエミリーを抱き寄せた。
「振り切りますよ!」
エミリーは咄嗟に目を瞑ってしまったが、遠心力と水しぶきで無茶な操縦が想像できた。
「――ほぅ、譜術ですか。これは心強い」
音素の高まりとジェイドの呟きに、エミリーはそろりと目を開けた。
「う〜ん…手加減がムズいなぁ。大怪我させるわけにもいかないし…」
(二人にとっては、同じ教団の仲間だよね…)
エミリーは心の中で、自分を納得させる理屈を探した。
「――大佐、ダンスのご経験は?」
そんなアニスの問いに、ジェイドはフッと笑みを浮かべる。
「…たしなむ程度には。しかしダンスは床の上でするものと思っていましたが?お嬢さん」
「アニス。アニス・タトリンです、大佐。これでも私、導師守護役です。しかも最年少エリートの♡」
「ふむ、これは失礼。ではアニス殿、お手並み拝見といきましょうか」
アニスは勢いよく飛び出し、背負っていたぬいぐるみを巨大化させた。
「アニス?!なんて危険なことを…!」
その行動に驚き声を上げたイオンとは別の意味でエミリーは目を瞬かせた。
アニスが乗った巨大なぬいぐるみは教団のモーターボートを一隻、二隻と沈めていった。
「貴方を護るためですよ、導師。いい部下をお持ちですね」
「…!はい!」
しかし敵も馬鹿ではないらしく、アニスから逃げるようにモーターボートが散ってしまった。
「あっ、ジェイド!」
「おっと…」
降ってきたアニスをぬいぐるみごとギリギリのところで受け止める。
「お見事!大佐!」
「貴女もね、アニス」
二人が仲良くなってずるい、などと考えている間に周囲には教団のモーターボート。
「あちゃー…結局囲まれちゃいましたねぇ…。すみません…」
「アニスはよくやったと思う。謝る必要はないよ」
「はわわっ、恐縮ですぅ」
小さく拍手を贈るエミリーを見て、ジェイドがわざとらしく唸った。
「ふーむ…海のど真ん中で、困りましたねぇ。そういえば、第四音素は殿下の得意分野だったかと思うのですが」
「え?そうだけど…私が攻撃したら国際問題に…」
「何のための変装ですか。もっとも、船まで追いつかれれば仰る通りになりますが」
「もうっ…やってみるけど、波に飲まれないでよね!」
言うや否や、エミリーの足元には大きな譜陣が出現した。
そして四人が乗るモーターボートを中心に、大きな水柱が花弁のように広がっていった。
「はぅあ!まるで海を操ってるみたい…」
「マルクトは譜術に長けていると聞きますが、あの年齢でここまでとは…」
十隻近くの小型ボートが大きな波に飲まれていった。
「流石は水上の天使ですね♪」
「…転覆させただけだから、すぐに追ってくるよ」
「では、今のうちに参りましょう」
部下の待つ高速艇を目指し、不自然なほど凪いだ海を走らせた。
聖なる焔の光
高速艇に合流した四人は、ひとまずハッチ近くの船室でひと息つくことにした。
「追手はとりあえず撒けたみたいだね…?」
船窓から確認し、エミリーは安堵した。
「いやぁ、殿下のおかげで助かりました♪――導師、お怪我はありませんか?」
「はい、ありがとうございます。僕は何もできませんでしたが…」
「そんなこと…!教会から抜け出すだけでも、大きな決断と勇気が必要だったと思います」
思わず口を挟んだエミリーだったが、イオンの肩書きを思い出して青ざめた。
「って、私ってば偉そうなこと…」
「ふふ、僕は構いませんよ。お互い、楽にしましょう」
「あ、ありがとうございます…。アニスも、よければ堅苦しいのはやめてね?」
反応に困るアニスを尻目に、ジェイドが便乗して口を開く。
「あ、私も堅苦しいのは苦手です♪ファミリーネームに慣れていないもので、是非ジェイドとお呼びください」
(“慣れていない”って…養子に入って何年経つの)
エミリーはジト目で伯父を見上げた。
「ふっ…あははっ!」
突然笑い出したイオンに、三人はポカンとしてしまった。
「なんだか、急に安心してしまって…。僕、こんなにドキドキしたのは生まれて初めてです!」
「あ、私も!城の外って怖いけど、ワクワクしますね」
「…お二人にとっては恐ろしい逃走劇だったでしょうね」
少し申し訳なさそうにするジェイドを手で制して、エミリーはイオンに向き直った。
「――イオン様。危険を冒してまで我がマルクト帝国の使者を引き受けてくださったこと、心から感謝します」
「…僕も、和平に協力したいんです。導師である僕が、ただの"和平の象徴"ではなく、お役に立てるのなら嬉しいです」
笑顔で握手を交わす導師とマルクト皇女。
ジェイドはそれを微笑ましく見守っていたが、思い出したかのように口を開いた。
「導師。今後、戦いは我々に任せてください」
「…任せる?」
イオンは僅かに顔を強張らせたが、ジェイドは気にせずに続ける。
「そうです。体を張って戦うのは貴方の役目ではない」
エミリーは他人事とは思えず耳が痛かった。
「貴方はその御心で民を戦争から守ってください。…イオン様」
「…!はい!」
嬉しそうに頷くイオンを見て、アニスも顔を綻ばせた。
「きゃっ…?!」
突如、船がグラリと大きく揺れ、少女達は驚いて短く悲鳴をあげる。
ブリッジの方が騒がしくなり、ジェイドの部下が船室に駆け込んできた。
「師団長!」
「今のは何だ?」
ジェイドはエミリーを背後に庇いながら尋ねた。
「強力な第七音素反応です!キムラスカ方面からマルクト領土へ収束を確認!正体は不明!」
「…調べる必要がありますね」
「キムラスカからの第七音素…?何が起こったの?」
端的に報告された情報を、エミリーは不安そうに反芻した。
ふーむ、と顎に手をやるジェイドの横で、アニスが思い出したかのように主を振り向いた。
「…イオン様、お疲れじゃないですか?」
「僕は平気ですよ、アニス」
「いえ、休めるときに休んでください」
「――ご案内します」
報告を終えた兵は、イオンとアニスを連れて部屋を後にした。
「さて。変装も良い社会勉強になったかもしれませんが、そろそろ着替えましょうか」
「好きで着てるわけじゃないんだけど」
「これは失礼♪」
ジェイドは片膝をつき、ドレスの入った袋を手渡した。
「…収束地点に行くなんて言い出さないよね?」
「まさか。部下に調べさせますので、ご安心を」
「それならいいけど」
エミリーの目を覗き込んだジェイドは、ふむ、と顎に手を当てた。
「疑ってますね?確かに興味はありますが…。ま、他の師団が向かうでしょう」
「そうだよ。みんな気付いただろうし、全部ジェイドがやらなくていいんだからね?」
「おや、ありがとうございます。私の仕事を増やしているのは、貴女のお父上なのですがね」
それは、とエミリーは父の気持ちを慮った。
「…仕方ないよ、皇帝の懐刀だもん。だから、他の仕事を減らした方がいいと思う」
「はっはっはー。やはり貴女は賢いですね」
スッと立ち上がった彼は、ドアを開けて側に控えた。
「食事を届けさせますので、先にお部屋でお待ちください」
「みんなで一緒に食べないの?私、食堂に行くよ?」
「いえ、殿下のお食事は別に用意させますから。――あぁ、大したものはお出しできませんよ?殿下のお口に合えばいいのですが」
はぐらかしたジェイドに、エミリーは口を尖らせた。
「…ま、いいよ。ジェイドも忙しいんだろうし、一人で食べるよ」
「ご理解いただき感謝します」
「ただし、私のお願いを聞いてくれるなら♪」
ジェイドはドアをパタンと後ろ手に閉めた。
「…嫌な予感しかしませんが、とりあえず聞きましょう」
「今夜、添い寝してくれる?」
ジェイドは僅かに驚いたような顔を見せた。
「…確か、とっくの昔に添い寝は卒業されたと伺いましたが」
「だから何?…あ、もしかして迷惑だった?」
「ハァ…殿下。断れないとわかっていて尋ねるのは、貴女の悪い癖ですねぇ」
「あははっ、ジェイドは断ろうと思えば断れるでしょう?」
ジェイドはわざとらしく何度目かのため息をつき、再びドアを開けてエミリーを促した。
*
食事は普段と比べれば慎ましいものだったが、トレイを下げに来てくれた兵の食事はきっと更に質素なのだろうと思った。
(なんだか、申し訳ないな…。精をつけなきゃいけないのはみんなの方なのに)
あてがわれた船室の窓からぼんやりと外を眺めた。
いつの間にか日は沈み、月光に煌めく海しか見えないが。
(イオン様とアニスは今頃何してるのかなぁ…)
部屋を訪ねてみようかと思ったとき、ドアを叩く音が聞こえた。
「?どうぞ」
失礼します、と言って姿を見せたのは、音叉を模した杖を持つ少年でもツインテールの少女でもなく、眼鏡をかけた長身の男だった。
「あ、ジェイド。ちゃんとご飯食べた?」
「ええ、一応」
そこは心配させまいと嘘をつくところではないのか、とエミリーは肩を竦めた。
「お医者様に痩せすぎだって言われたんでしょう?知ってるんだからね」
「おやおや、よくご存知で♪――明朝、タルタロスに合流できそうです。朝早いので、そろそろ休みましょう」
「えっ、もう?」
「お子様は寝る時間ですよ。それに、私の時間が空いたのでお願いを叶えに来たのですが」
そう言ってジェイドはおもむろに軍服のボタンを外しだした。
「は…?え?あ、ありがとう…」
添い寝なんてしてくれないのだと思っていたエミリーは、戸惑いつつコルセットベルトを外す。
手袋を外すジェイドを横目に、エミリーはジャケットも脱いでワンピース姿になった。
「まだ眠くないのに…」
エミリーがベッドの奥に入ったのを確認し、ブーツを脱いだジェイドが続いた。
「ハァ…誰かと同じベッドに入るのも久しぶりですよ」
「もしかして、他人がいたら眠れないタイプ?」
「どんな状況であろうと休息はとれるようにしています」
向き合うように横向きになると、顔にかかった髪をジェイドが優しく払いのけた。
「狭いでしょう?なぜ添い寝しろなどと言ったのですか」
「だって…ジェイド、休んでいないんじゃないかと思って」
「必要なときは休んでいますよ。軍人ですから、ご心配なく」
(またそうやって距離を置こうとする…)
こんなに近くにいても、心を閉ざされては意味がないのだとエミリーは思い知った。
「軍人である前に人間でしょう?――それに、いつもと違う環境で私が不安だったから…」
「殿下…。ご自分のことで精一杯でしょう。どうか、私のことはお気になさらず」
エミリーは返す言葉が見つからず、ジェイドの胸元に顔を埋めた。
「私が寝たらすぐ仕事に戻ろうって思ってるでしょ?これだけくっついていれば気付くんだからね!」
「…これでは寝返りもできませんねぇ」
ジェイドは呆れたように呟いたが、そのまま彼女を包み込むようにして瞼を閉じた。
(ジェイドの鼓動…?安心する…)
「…おやすみ、エミリー」
名前を呼ばれた気がしたが、確認する間もなく意識を手放した。
✽
(――薄ら明るい…。もう朝?確か、早朝にタルタロスと合流するって…。あれっ、ジェイドは…?)
半分眠った状態のエミリーが手探りでジェイドを探す。
(抜け出したの全然気付かなかったな…)
小さく息を吐いた彼女のそばで、フッと微笑うような気配がした。
「殿下、私はここですよ」
エミリーの好きな声が降ってきた。
「ジェイド…。おはよう」
エミリーの左手にそっと重ねられた手に、ひんやりとした硬い感触があった。
「ん…?えっ、指輪つけてくれてるの?」
「おや?ずっとつけていたというのに、それはあんまりじゃないですか?」
ジェイドは、意地悪な笑みの横に左手を掲げてみせた。
「だ、だって……!」
(手袋の下ならわからないからって言ったのは私だった…!昨夜は何ともなかったのに、急に恥ずかしい…!)
エミリーは口をパクつかせて赤面した。
既に身支度を済ませていたジェイドは、手袋を身に着けながら窓の外を一瞥した。
「殿下、着替えてブリッジに来てください」
「わ、わかった…」
*
エミリーが着替えてブリッジに行くと、慌ただしく乗り換えの準備が進められていた。
「エミリー皇女。おはようございます」
イオンとアニスは既にブリッジに揃っていた。
「おはようございます。イオン様、よく眠れました?」
「ええ、まぁ。…実を言うと、興奮して眠りが浅かった気がします」
「ふふっ。タルタロスでゆっくり休みましょう」
エミリーの言葉に、アニスもうんうんと頷いた。
「そうですねぇ。親書が届くまではエンゲーブ付近に滞在しますから、殿下もイオン様もゆっくり休んでください」
ジェイドに釘を刺されても、エミリーは大人しく待つ気など更々なかった。
やがて合流地点に着岸し、一行の乗り換えはスムーズに完了した。
「――陸上装甲艦タルタロスへようこそ」
それぞれの部屋へ案内する前に、ジェイドは三人を作戦会議用の大部屋に集めた。
「ねぇ、ジェイド。まず指示とかしてこなくていいの?」
「タルタロスのことは艦長に任せていますし、今のところトラブルもないので私の出る幕はないんですよ」
ジェイドは緊張感のない笑みを浮かべて、机に世界地図を広げた。
地図の右半分に描かれた大陸、そのまた上半分を彼の長い指がスーッと横断する。
「現在地がこの辺り。そして、このエンゲーブで親書を受け取る予定です」
「インゴベルト陛下宛の親書が…」
エミリーは正直、親書の重要さを理解できていないような気がした。単なる父の手紙、とは思っていなかったが。
「食糧の調達も兼ねていますが。私はまず村の代表者に挨拶してきますので、皆さんは待機していてください」
「村を見て回っても構いませんか?」
「あっ、もちろん私も!」
イオンにつられるようにして、エミリーは勢いよく挙手した。
「…まぁ、いいでしょう。ただし、危険ですので単独行動は控えてください」
「はーい」
満足げなエミリーを一瞥して、ジェイドはアニスに向き直った。
「親書は使者であるイオン様にお渡ししますが、狙われる可能性もあるのでアニスが預かってもいいでしょう」
「お願いしますね、アニス」
はい、とアニスは元気に応えた。
「あとは…いざというときに落ち合う場所を共有しておきましょうか」
「いざというとき…」
呟いたエミリーに、ジェイドは表情を和らげてみせた。
「殿下も、襲われる可能性を危惧していたではありませんか。だから第三師団に行ってほしいのだと」
「そうだけど…」
「念のためですよ。ダアトで派手に立ち回りましたからね」
ジェイドは、あらゆる可能性から考えられた数パターンの合流地点を説明した。
今もし何かあったら、マルクト軍の基地があるセントビナーで待ち合わせるのだと、エミリーもしっかり頭に入れた。
「退屈でしょうから、軍事機密に関わる部分以外は自由に見学して構いませんよ」
「イオン様。せっかくだし、少し休んだら見て回りませんか?」
「そうですね」
エミリーは記憶をたどるように、人差し指を口元に当てた。
「確か、ブリッジとか機関室は立入禁止区域だったはず」
「よく覚えていましたねぇ。もっとも、殿下には立入禁止区域など存在しませんが」
たとえ立入禁止だったとしても、あの自由気ままな皇帝の血を引く皇女が、果たしてその決まりを守るかどうか定かではないが。
「危ないところはダメだって父上に言われてるから、入るとしてもブリッジくらいかな」
「危ない旅に送り出した人間の言葉とは思えませんねぇ」
「本当だよね」
ここにはいない皇帝に対し、二人は呆れ顔をした。
「大佐…そういう態度で大丈夫なんですかぁ?」
「陛下に対してですか?ええ、本人の前でもこういう態度ですから♪」
「はぅあ!さすがというか何というか…」
驚くアニスに、ふふっ、とエミリーは小さく笑った。
「父上とジェイドは、幼馴染みで親友だから」
「ほぇ?そうなんですかぁ。だからエミリー皇女とも仲良しなんですね」
「「仲良し?」」
ほぼ同時に聞き返したエミリーとジェイドは、思わず顔を見合わせた。
「ふふ。息ぴったりですね」
「ですよね~」
イオンとアニスも楽しげに顔を見合わせている。
「はあ…恐れ多い話です」
「私からしてみれば、イオン様とアニスだって仲良しだと思ったんだけど」
「え?」
きょとんとするイオンの隣で、アニスがギョッとしたように顔を引きつらせた。
「そ、それこそ恐れ多いですよぅ!」
「おやおや。では似た者同士ということで。部屋にご案内しますよ」
話を無理矢理切り上げたジェイドの案内で、三人は割り当てられた船室に向かった。
高速艇同様、エミリーの部屋は青いリボンが目印となっていた。
ベッドに腰かけて景色を眺めても、眠気はすっかり吹き飛んでいた。
(ジェイドは仕事に戻ったし、イオン様は休むって言っていたから、アニスは警護中だろうし…)
休憩室や簡易食堂に顔を出すと、兵士達の気が休まらないであろうとエミリーは推測した。
(音機関には興味ないし、一人で甲板に行くと心配されるし…やっぱりブリッジにいるのが一番勉強になるよね)
そう言い聞かせて、エミリーはすっくと立ち上がった。
廊下を進むと、突き当たりのドアがシュッと自動で開いた。
「おや。早速ブリッジに来ましたね?」
ニヤニヤしているジェイドを、エミリーは強い気持ちで見上げた。
「勉強のためなんだけど…邪魔だった?」
わかっていて尋ねる悪い癖も、社会勉強の旅だと揶揄されることも、開き直ったような言い草だった。
「とんでもない♪艦内は見られましたか?」
「…なんだか気を遣わせるから、あまり身動きとれなくて」
貴方の部下は悪くない、と言外に含ませたが伝わっているだろうか。
「城にいたときは、よくお一人で動き回っていたと思いましたが?広い城内を捜すのは大変そうですねぇ」
「でも…ここにいる人達はメイドじゃないから、私のことで手を煩わせたくないんだよ」
ジェイドは感心したように目を瞬かせた。
「――お話し中失礼します!師団長…」
艦長が顔だけ振り向き、外の様子が映し出された大きなモニターを指し示した。
「おっと…あれは漆黒の翼ですね」
黒い馬車が走っている。客車には何やら赤い模様が見えた。
「漆黒の翼…?聞いたことあるような」
「男女三人組の盗賊ですよ。――殿下、掴まってください」
言われたとおり近くに掴まると、轟音とともに振動が伝わってきた。
タルタロスが、漆黒の翼が乗っているという黒い馬車を砲撃したのだ。
何の躊躇いもなく、立て続けに爆音が響く。
(ギリギリのところで避けてるけど…当たったら死んじゃうよね?)
あの馬車とタルタロスでは、大きさが犬小屋と宮殿ほど違うのだから。
「前方に民間の馬車を確認!」
部下の報告を聞くや否や、ジェイドは手元の音機関に向かって口を開いた。
「――そこの辻馬車!道をあけなさい!巻き込まれますよ!」
彼の声はタルタロスの外に拡声されたらしく、民間の馬車は急な方向転換をしたことで巻き込まれずに済んだ。
「…辻馬車は無事みたいだね」
ええ、とジェイドが短く相槌を打つ。
一方、黒い馬車は大きな橋に差しかかった途端、カランカランと“何か”を落としていった。
(タルタロスの進行を妨害…できるほどの大きさじゃないけど、軽くして速度を上げるつもり?)
「――フォンスロット確認!敵は第五音素による譜術を発動!」
「おやおや…橋を壊して逃げる気ですね」
エミリーは耳を疑った。この大きな橋を、壊す?盗賊が?
「タルタロス、停止せよ!譜術障壁、起動!」
「了解!タルタロス、停止!譜術障壁、起動!」
ジェイドの指示を艦長が繰り返す。
橋の手前で速度を落としたタルタロスを爆風が襲うも、譜術障壁のおかげで衝撃はなかった。
やがて煙が晴れたとき、ジェイドの判断が大げさなものではなかったと知る。
「嘘でしょ?!橋が…完全に落ちてる」
それは損傷という規模ではなく、間違いなく破壊されていた。
「ハァ…あの橋はローテルロー橋といって、とても重要な橋なのですがね」
「あれがローテルロー橋…?!それを、自分達が逃げるためだけに?なんてことを…!」
エミリーの中で、漆黒の翼が“ただの盗賊”ではなくなった瞬間だった。
「…どうするの?」
「どうもしませんよ、我々はあくまで目的が優先です。エンゲーブに向かいましょう」
冷静沈着なジェイドの様子に、エミリーはハッとした。
「…親書がいつ届くかわからないから、こっちが早く着いておきたいものね」
「ええ。それに、余計なことで殿下を危険な目に遭わせたくありませんからね」
「余計なこと…かどうかはわからないけど、イオン様もいるしね」
「そういうことです。いやぁ、賢くて助かります♪」
デコルテのネックレスを握り締め、ふぅ、とため息にも似た深呼吸をした。
*
「さて。タルタロスはここに置いて、エンゲーブへ向かいましょう」
タルタロスや備品の点検を始めた部下達を見渡し、ジェイドはブリッジに背を向けた。
「村の入口に停めないの?食糧の調達をするんじゃ…」
エミリーは後に続きながら、疑問に思ったことを口にした。
「巨大な軍艦が村の前にあっては通行の邪魔です。それに、住民を不安にさせてしまいますからね」
「そっか…。よし、じゃあ村の代表者に挨拶に行こ!」
「イオン様と一緒に村を見学しなくてよろしいのですか?」
「村の様子はあとで見るけど…イオン様を案内できるほどの知識はないもの。それならジェイドに同行したほうが勉強になりそうじゃない?」
確かに、皇女として導師をもてなすべきなのではないかと、頭をよぎったが。
「なるほど。では参りましょうか」
村に入ると、まず感じたのは家畜臭。
「ブウサギさん、こんにちは。たくさんいるんだね」
ブウサギに挨拶するエミリーは、ドレスのせいか村人達の注目の的だ。
「殿下、ブウサギはペットではなく家畜です。肉になって食べられる運命ですよ」
「そのくらい知ってるよ。…父上はペットにしてるけど」
エミリーは家畜臭など慣れたものだったが、気になったのは辺りの民家だ。
(グランコクマは首都だし、ケテルブルクは貴族の別荘が多いから、比べちゃいけないか…)
「――安いよ安いよ!」
客を呼び込む元気な店主に、エミリーは「綺麗なリンゴですね」と声をかけた。
「き、貴族の客人とは珍しい…」
店主は動揺を隠せず、貴族然とした少女と傍らの軍人を交互に見やった。
「グランコクマで召し上がっているほとんどの食料はエンゲーブ産です。食料調達には適した地ですのでご安心を」
それを聞いて、店主は少し納得したような顔を見せた。
「そうだね。お邪魔しました」
エミリーは笑顔で店の前を過ぎ去り、ジェイドをちらりと見上げた。
「…迷子の観光客だと思われているようでしたので」
「そういうこと?声をかけたのは軽率だったね。ごめんなさい」
「いえいえ、社会勉強ですからね♪先ほどの会話で、軍事演習か慰問だと思われたでしょう」
エミリーは村の様子を観察しながら、考え事をしているようだった。
「…着きましたよ。村の代表者のお宅です」
「あ、うん。私は身分を明かしてもいいの?」
「そうですねぇ。流石に家族旅行だと誤魔化すのは無理がありますから」
*
「――まさか皇族の方まで、こんな田舎にいらっしゃるなんて…何のおもてなしもできなくてすみませんねぇ」
そう謝罪する村の代表者ローズに、いいえ、とエミリーは首を横に振った。
「むしろ普段の様子が知れて良かった」
「普段…でしたら、もっとご馳走をご用意できたはずなんですけど…」
エミリーとジェイドは目を見合わせた。
「ふむ…不作なのですか?」
「魔物に畑を荒らされたとか?」
「実は…」とローズがため息まじりに口を開いた次の瞬間、玄関のドアが荒々しく開け放たれた。
驚いてティーカップを取り落としそうになったエミリーを、庇うようにジェイドが立ち上がった。
「ローズさん!」
「何なんだい、今お客さんが…」
慌てるローズの前に、村人達に押されて一人の男が倒れ込んだ。
「いってぇ!何すんだよ!」と叫ぶ口調に反して、身なりは上流階級のそれだった。
(私もこの人も、エンゲーブでは浮いてるな)
エミリーよりも五つは年上に見えるが、落ち着きのない言動のせいで幼い印象を受けた。
「店のリンゴを勝手に食べたんだ!こいつ、漆黒の翼かもしれねぇ!」
「最近続いてる食料泥棒もこいつなんじゃないか?!」
そうだそうだ、と玄関の外からも男達の怒号が届く。
「だから違ぇって言ってんだろ!食いもんに困るような生活は送ってねーからな!」
彼は村人達を振り払い、怒りを隠さず立ち上がった。
変わったデザインの白い服からは見事な腹筋が覗き、夕日のような髪は腰まで伸びている。
「おやおや、威勢のいい坊やだねえ…」
困惑するローズを見かねて、ジェイドが口を開く。
「皆さん、落ち着いてください」
「大佐…。すみませんねぇ、大事なお話の途中で…」
申し訳なさそうなローズと目が合ったエミリーは、安心させるように微笑んでみせた。
「食料はこの村の命でしょう?それも大事な話だよ」
「ご理解いただけて助かります」
そう言って頭を下げるローズの前に、ジェイドが進み出た。
「…なんだよ、あんた」
赤髪の少年は腕を組み、ジェイドを睨むように見上げた。
「私はマルクト帝国軍第三師団所属ジェイド・カーティス大佐です。あなたは?」
「ルークだ!ルーク・フォン――」
「ルーク!!」
突如、玄関に集まる野次馬の中から、少女が飛び出し、ルークと名乗った少年の口をふさぐ。
戦闘訓練を受けた者の動きのように素早かった。
(…?貴族のお忍び旅とか?)
彼女は腰まで伸びたマロンペーストの髪で片目が隠れており、チョコレート色の衣装が落ち着いた雰囲気を醸し出している。
「どうかしましたか?」
ジェイドが声をかけると、彼女はルークを庇うように一歩前に出た。
「失礼しました、大佐。彼はルーク、私はティア。ケセドニアへ行く途中でしたが、辻馬車を乗り間違えてここまで来ました」
ティアと名乗った少女は堂々としていて、ルークより少しだけ年上のように感じた。
「おや。ではあなたも、漆黒の翼だと疑われている彼の仲間ですか?」
「私達は漆黒の翼ではありません」
ぴしゃりと否定したティアは、小さくため息をついたように見えた。
「本物の漆黒の翼は、マルクト軍がローテルロー橋の向こうへ追い詰めていたはずですが」
「ああ…なるほど。先ほどの辻馬車に、あなた達も乗っていたんですね」
笑みを深めたジェイドに、ローズが首をかしげた。
水上の天使

