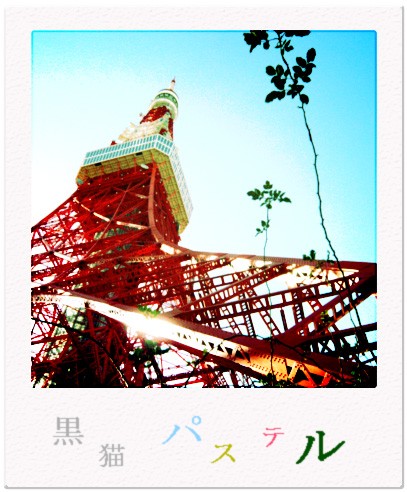
黒猫パステル
綿あめ(作者)が何だか憧れてしまうような物語を書いています。完全に自己満みたいですが、それでも読んで下さる方がいれば幸いです。ちなみに完全フィクションです。…どうでもいいか。
ともかく、一話一話オムニバス形式で芽衣と春を動かしていきますのでよろしくお願いします。
いつものバス停。
いつもの夜。
誰もいない路に、月明かりだけが綺麗に見える。
私は、いつものように彼を待つ。
ヒュー…
時折吹く風が冷たい。紅葉の季節はすっかり終わってしまい
草木は春に向けての準備期間、冬に入った。
私の手は風の強さに反射するように冷たくなっていく。
両手をポケットに忍ばせて、また空をみる。
満天の星空。
…あれは多分オリオン座だ。
あそこにあるのは確かカシオペヤ座で…あれは…えっと…
「…芽衣」
「…!」
突然の声に一瞬驚く。
声のした方を向くと、いつものように彼がいた。
「ごめん、ちょっと遅かったね」
「全然! 仕事大変だもん、仕方ないよ」
私達はバス停の椅子に腰かける。
風はまだ強かったが、彼が来た事でそんな事は忘れていた。
如月芽衣 -キサラギ メイ-
なんだか胡散臭い名前みたいだけど、これが本名だ。
今年高校3年生になる。
「最近はどうなの?」
「…? どうって?」
「仕事とかー、色々。会えなかったから聞きたい事ありすぎだよ」
「はは、ごめんごめん。もうすぐ曲が出来る」
「あ、本当に?今回は早いんだね」
「うん」
「あ、そうだ。皆は元気?」
「元気だよ。むしろ元気すぎるくらい。」
「そっか、よかった」
何気ない会話。その中にも幸せは嫌というほど転がってくる。
それを一つ一つ拾いながら、私は今日も何気なく星空を眺めてみたりする。
「今回も曲出来たら、まずメンバーに聴かせるけど」
「うん」
「その後すぐにギター持ってお前んとこ行くから」
「はは、ありがとう。待ってるね」
今度は同じタイミングで空をみる。
「あ、牡牛座」
彼が不意に呟いた。
「牡牛座は確か、オリオン座の近くにあるんだったよね」
「そう、よく覚えてるじゃん」
「だって、覚えなかったら次の唄聴かせてくれないんでしょ?」
「え。そんな事言ったかな」
彼は少し恥ずかしそうに笑う。
笑う時、口に手を当てるのは彼の癖だ。恐らく本人は気付いてないだろうけど。
「言いましたよ、この前ー」
「そっか、だから覚えてくれたんだ」
「それに」
「…? うん」
「星は好きだから」
「そっか」
気が付けば、手を繋いでいた。
★:
原子番号Ⅰ
ある日のこと。
突然彼からの電話。
彼はあまり電話をしない。本人曰く、恥ずかしいとのこと。
だから今鳴っているベルが彼だと気付いた時、私はすぐに通話ボタンを押した。
「もしもし?」
「……あ、芽衣。俺。」
彼の、やはり心地のいい声が私の耳を柔らかく包んだ。
「うん。どうしたの?電話なんて珍しい」
「そうそう。珍しいでしょ。…実はね」
彼は少し間をおいて、静かに言った。
「曲聴いてほしいなと思ってさ」
・・・。
・・・・・・・。
「…え? そんだけ?」
「そんだけってお前…冷たい」
「だって、いつもはメールとか直接とかだから、なんか違和感」
「・・・」
「ごめん。でもなんでわざわざ電話してきてくれたの?」
「うーんとね」
「うん」
彼はまた少し間をおく。
結論を言う前、こうして間を置くのはまた、彼の癖。
これは多分私やバンドのメンバーにしか分からないものだと思う。
ライブをしている時の彼は、まるで別人みたいにすらすらと言葉を口にする。不思議だ。
よっぽどファンの人たちを大切にしてるんだなって、いつも思ったりする。
「…実は今回の曲さ、芽衣に宛てた曲みたいになっちゃったんだよね」
「ほお! それは嬉しい」
「でもさ、それってどうなの?音楽家としてそういうのっていいのかな」
「いや、私に言われてもー…」
「えーお前に宛てた曲になっちゃったのに無責任だぞー」
…えー。私責任ないし。
「メンバーの人にも言ってないの?」
「うーん、ナオにだけ話した。」
※ "ナオ"というのはバンドのベース担当・吉田直義の愛称である。
「で、ナオさんはなんて?」
「別にいいんじゃん? って、本当いつものノリで」
「はは。ナオさんらしーっ!」
「笑い事じゃないよ。俺結構深刻だよ今。」
「ああ、ごめんごめん。なんか春が深刻だと逆に笑えてきちゃうの」
「反作用ってやつだね」
彼は彼なりに苦労してる。
彼の苦労が世の中の人にとってどんなモノになってるかは知らないけれど
彼は彼の限界をいつも持って、それをいつも超える。
私はいつだって、そんな彼の背中を見てきた。
無愛想でも無責任でも、ちゃんと背中だけは見てきた。
それから長々と電話をした。
曲の話から話題は逸れ、日常会話をした。
好きな食べ物はなんだっけだの、水族館はデートに最適だの
女子高生同士でするような、そんな会話。
彼がするから、可愛くなる
「…あ。芽衣、話題逸れ過ぎ」
「あちゃー忘れちゃってたわ!」
「でも俺、なんか分かった気がする、」
「え、何が分かったの?」
彼の突然見つかる答えにはいつも、私の心を揺り動かす何かが潜んでいる。
それが暖かくても冷たくても、私への作用は変わらない。
「こうやって電話で話せたのって、まぁお前が初めてなのね」
「…? うん」
「なんか、芽衣とする事にはいつも『初めて』って言葉が似合ってて、」
「…うん」
「新しいのに、初めて見たはずなのに、懐かしいって事よくあるでしょ?」
「あー、ある。」
「その感覚に似てるかな。俺が曲書いてた時、そんな気持ちだった」
「…つまり?」
「つまり…」
これからもよろしく。
彼は、受話器越しに照れながらそう言った。
★:
原子番号Ⅱ
とあるスタジオにて。
「あ、芽衣ちゃんじゃん! 久しぶり~!」
「ナオさん! ご無沙汰してます。」
私は今日、春の収録現場に来ている。
一番に声をかけてくれたのは、やはりナオさんだ。
「へー!何年ぶりだっけ俺ら?」
「何年って…つい3ヶ月くらい前に会ったじゃないですか」
「冗談冗談(笑)」
私とナオさんが話をしていると、それに続きギターの横井さん、ドラムの山田さんが顔を出した。
「あ、ハルの彼女さんだ」
「ほんとだー」
「こんにちは」
私が頭を下げると、二人もその後に続きお辞儀をした。
「なんか堅いぞ君たち!」
その後絶妙のタイミングでナオさんが空気の読めないつっこみをする。春のメンバーに会うと、いつもこういう感じだ。
冷めてるのに、あったかい感じ。
「何話してんのー?」
声の主は春だった。
「あ、春」
私が声をあげる。
「おっ!待望の春さん登場!」
「…待望ねぇ…。 ナオさ、そのネタ俺らが付き合い始めた当時からだよな。いい加減飽きないの?」
「ぜんっぜん!むしろ年を重ねるたび楽しくなるわ」
「えー…」
げっそりとする春と、その隣で苦笑いの私。
いつも通りの景色に、胸が少し綻んだ。今日もちゃんと『当たり前』がある。
「なんか、変わらないね」
横井さんが笑いながらそう言った。
「それに、春と芽衣ちゃんだんだん似てきたよ」
『えっ』
二人は顔を見合わせた。
私と春は…似てるのか?
「いやいや、顔とかじゃなくて。なんか雰囲気?俺芽衣ちゃんに会うたびに思うよ」
「本当ですか?」
「うん」
横井さんはなんだかよく分かってるんだなー…。
「でも、確かに言われてみれば。なんか春の彼女が芽衣ちゃんって納得だ」
山田さんがさらに声をあげる。
「いやあ…へへへ」
私は少し照れくさくなった。
好きな人と雰囲気が似てくるって、結構嬉しいもんなんだね。
★:
黒猫パステル

